【中小企業向け】休職とは?制度の基本・主な理由・手当の条件・注意点をわかりやすく解説

しかし、中小企業では休職・欠勤・休業の違いが曖昧なまま運用されているケースも多く、「給与はどうなるのか」「社会保険料は払う必要があるのか」など、実務上の疑問が多く生じやすい領域であることは間違いありません。
本記事では、休職の基本的な定義から、主な理由、休職期間の設定方法、給与・手当の扱い、手続きや診断書対応、復職・退職に関する実務ポイントまで、中小企業が押さえておくべき内容を体系的に整理して解説します。
また、以下の記事では休職制度と同じくらい重要な退職給付金制度について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
「休職」とは?欠勤・休業との違いをまず整理
休職とは、従業員が病気やケガ、メンタル不調、家庭の事情などにより一定期間働けなくなった際に、会社との雇用関係を維持したまま労務提供を免除する制度です。
労働基準法に明確な規定はなく、企業が就業規則で内容を定める「任意制度」として運用されています。ただし、実務上は多くの企業で制度として整備されている制度です。従業員が安心して働き続けられる環境づくりの一環とされています。
そのため、休職期間の長さ、休職中の給与扱い、復職基準などは会社ごとに異なり、事前に就業規則で明確にしておくことが重要です。特に中小企業では「法律で決まっている」と誤解が生じやすいため、制度の目的と位置づけを社内で共有しておくことがトラブル防止につながります。
休職の定義と就業規則上の位置づけ
休職は、従業員が私傷病・メンタル不調・家庭事情・公職就任などで長期の労務が難しい場合に利用する救済制度として定められています。
就業規則では、次のような内容を定めるのが一般的です。
- 休職を認める事由(私傷病、メンタル不調、公職就任など)
- 休職期間の上限(例:6か月、1年など)
- 休職中の給与・社会保険料の扱い
- 復職可否の判断基準(医師の意見、業務遂行能力など)
- 期間満了後に復職できない場合の取り扱い
法的義務ではないものの、就業規則での明文化が不十分だと、判断が属人的になりやすく、不公平感や労務トラブルが起きやすくなります。
欠勤や休業とどう違うのか?混同しやすい用語を整理
休職は長期間働けなくなる場合に用いられる制度です。しかし、日常の労務管理では「欠勤」「休業」と混同されやすく、給与の扱いや手続きでトラブルになるケースが多くあります。
まずは、休職との違いを正しく整理し、社内で共通認識を持つことが重要です。以下の表で、それぞれの違いを比較しました。
| 用語 | 意味・定義 | 主な原因 | 給与の扱い | 判断基準のポイント |
| 欠勤 | 出勤すべき日に働いていない状態(短期) | 私用・体調不良など | 無給が一般的 | 長期化する場合は休職への切り替えを検討 |
| 休業 | 会社都合で働けない状態 | 経営悪化・災害・業務停止など | 休業手当の支払い義務あり(原則60%) | “個人都合”ではなく“会社都合”がポイント |
| 休職 | 個人の事情で長期の労務が難しい状態 | 私傷病・メンタル不調・家庭の事情など | 原則無給(就業規則による) | 就業規則の基準に基づき判断する |
休職はあくまで「個人の事情による長期の労務不能」に該当する場合に用いられ、欠勤や休業とは原因も給与扱いも異なります。制度ごとの違いを明確にし、社内で統一した運用を行いましょう。
休職の主な理由とパターンとは?
休職は「病気やケガによる長期の療養」をイメージされることが多いですが、実際には企業の就業規則によって幅広い理由が認められる場合があります。中小企業では、私傷病休職のほか、家庭事情や留学、公職就任など、さまざまなケースが対象です。
正しく理解しておくことで、従業員への説明や判断基準の明確化につながり、労務トラブルの防止に役立ちます。
最も多いのは「私傷病休職(うつ病・適応障害など)」
休職理由として最も多いのが私傷病休職で、病気・ケガ・メンタル不調など、従業員本人の健康上の問題による長期療養を目的としています。
特に近年は、うつ病・適応障害・不安障害など、メンタルヘルス起因の休職が急増しており、中小企業でも対応が避けられない状況です。
私傷病休職では、一般的に以下のような状態が該当します。
- うつ病・適応障害・パニック障害などのメンタル不調
- 手術・重い病気による長期入院や治療
- 重大なケガや交通事故
- 慢性疾患の悪化による長期休養
医師の診断書をもとに休職可否を判断するケースが多く、復職時も医師の意見が重要な判断材料です。
自己都合・留学・公職就任・起訴休職などの例
私傷病休職が最も一般的ですが、企業の就業規則によっては、本人の事情やキャリア、法的な理由など、さまざまな休職理由が認められる場合があります。
中小企業では対象範囲を広くすると運用負担が大きくなるため、表のように「どの理由を認めるのか」を明確に整理しておくことが重要です。
以下に代表的な休職パターンを表にまとめました。
| 休職の種類 | 主な内容 | 注意点・運用ポイント |
| 自己都合休職 | 家庭の事情、介護、育児など業務外の個人的理由 | “どの程度の事情で認めるか”の基準を就業規則に明記するとトラブル防止に有効 |
| 留学休職 | 本人のキャリア形成を目的とした留学のための休職 | 業務への影響が大きい場合が多く、期間・復帰条件の定義が重要 |
| 公職就任休職 | 選挙当選、公職への就任に伴う職務専念義務が発生する場合 | 法律で業務との兼務が制限されるため、会社として制度を準備しておく必要がある |
| 起訴休職 | 従業員が刑事事件で起訴された際の休職 | 有罪確定前に解雇は原則認められず、慎重な対応が求められるため、顧問弁護士など専門家への相談を推奨 |
これらの休職理由は、法定制度ではなく「会社の任意制度」のため、どこまで認めるかは就業規則次第といえます。特に中小企業では制度を広げすぎると対応が煩雑になりやすく、対象範囲・期間・復職条件を明確にすることで運用の安定性を確保することが可能です。
業務起因の場合は労災休職になることも
従業員のケガや病気が業務に起因する場合、一般的な「私傷病休職」ではなく、労災休職として扱う必要があります。
休職後の給与補償・保険手続き・会社の責任範囲も大きく変わるため、原因の判断は慎重に行いましょう。まず、業務起因となりやすい主なケースを表にまとめました。
| 区分 | 内容 | 企業側の対応ポイント |
| 業務災害 | 業務中の事故・作業中の負傷・機械トラブルによるケガ | 労災申請のサポート、事故状況の記録、再発防止策が必須 |
| 業務起因の疾病 | 長時間労働・強いストレスなどによる心身の不調 | 労災認定の可能性が高いため、労働時間記録・業務内容の整理が重要 |
| 通勤災害 | 通勤中の事故やケガ | 労災保険の対象となるため、会社は通勤経路の確認と申請の案内を行う |
| メンタルヘルス起因の労災 | 仕事由来のプレッシャー・ハラスメントなどでのうつ病・適応障害 | 記録・証拠管理が必須。私傷病扱いにしてしまうとトラブルに発展しやすい |
労災休職になると、給与の代わりに労災保険から休業補償給付(給付基礎日額の60%)が支給されるため、会社が給与を払う必要はありません。
一方で、企業には労災発生時の報告義務や安全配慮義務が伴うため、休職扱いの判断は慎重かつ記録を残しながら進めることが重要です。
休職期間に関するルール|最長期間や延長はどうなる?
休職期間は法律で一律に決められているわけではなく、企業が就業規則で自由に定められる任意制度です。そのため、期間の長さ・延長の可否・休職満了時の取り扱いも会社ごとに異なります。
中小企業では、運用方法によって復職判断や退職手続きに影響が及びやすいため、事前の明文化と公正な運用が重要です。
就業規則で定めるケースが一般的
休職期間は法令で一律に定められているわけではなく、企業が就業規則で内容を明記することで運用する任意制度です。
そのため、「何か月まで休職できるのか」「延長はあるのか」「復職の判断基準はどうするのか」といった内容は会社ごとに異なります。
中小企業では、判断が属人的になりやすいため、事前に就業規則で基準を明確にしておくことで、従業員への説明や復職対応がスムーズになり、トラブル防止にもつながります。
参考記事:就業規則とは?記載内容や中小企業が注意すべき点をわかりやすく解説
「最大〇か月」の上限設定と運用上の注意点
休職期間には「最大3か月」「最大6か月」といった上限を定めるのが一般的です。ただし、上限の設定方法や延長の可否によっては、運用が曖昧になりやすく、中小企業ではトラブルにつながることもあります。
以下に、上限設定と運用上の注意点をまとめました。
| 項目 | 内容 |
| 上限設定の考え方 | 私傷病休職は3〜12か月など、会社規模・代替要員確保の難易度で設定する |
| 延長の判断基準 | 医師の意見、業務遂行可能性、改善状況などを基準化する |
| 長期化のリスク | 他社員の負担増、職場の生産性低下、復帰後のミスマッチ発生など |
| 運用時の注意点 | 連絡方法、定期報告の頻度、復職判断のプロセスを文書化すること |
上限期間は“従業員の回復に必要な期間”と“企業の業務が維持できる範囲”のバランスで決めることがポイントです。
また、延長可否の判断を個別に行うと不公平感が生じやすいため、「医師の意見書」「勤務可能なレベルの明確化」「就業規則上の基準」などを組み合わせ、判断プロセスを固定化しておきましょう。
休職後に復職できない場合の取り扱いとは
休職期間が満了しても従業員が職場に復帰できない場合、就業規則の内容に基づいて「休職満了による退職(自然退職)」とする運用が多くの企業で採用されています。
ただし、復職判断は非常に慎重に行う必要があり、判断基準を明確化しておかないと労務トラブルにつながります。
| 判断ポイント | 内容 |
| 医師の意見 | “働ける状態かどうか”を診断書や医師意見書で確認する |
| 業務遂行能力 | 会社が求める業務に支障なく従事できるかを会社側で判断する |
| 配置転換の検討 | 軽作業や別部署など「配慮可能な職務」があるかを検討する |
| 退職扱い | それでも復帰が難しい場合は「休職満了による退職」とする |
復職判断は、単に“働けるかどうか”だけではなく、「従来の職務に支障なく従事可能か」「配置転換で解決できるか」まで含めて総合的に判断する必要があります。
個別事情によっては退職扱いが妥当でないケースもあるため、最終判断の前には、医師の意見や本人・上司との面談内容を十分に踏まえたうえで慎重に検討することが重要です。
休職中の給与・手当・社会保険料の取り扱い
休職期間中の「給与」「傷病手当金」「社会保険料」の扱いは、企業と従業員双方にとって誤解が生じやすいポイントです。就業規則・健康保険制度・税法が絡むため、制度を正しく理解しておくことで、休職時のトラブルを未然に防ぐことができます。
休職中の給与は「原則無給」だが例外もある
多くの企業では、休職期間中は原則として無給です。これは、従業員が労務を提供していないため、会社に賃金支払い義務が発生しないためです。
ただし、次のような例外があります。
- 就業規則で「一定期間は給与の一部を補償する」と定めている場合
- 労災による休職で、労災保険の休業補償給付が支給される場合
- 福利厚生として、企業が独自に手当を支給する場合
中小企業では、完全無給とするケースが大半ですが、「最初の〇日間のみ有給扱い」「会社独自の見舞金制度を設ける」など、企業によって運用が異なります。
傷病手当金の支給条件と計算方法
休職中の生活を支える代表的な制度が 健康保険の「傷病手当金」 です。私傷病(業務外)による休職の場合、給与に代わる生活補填として利用できます。
支給されるための主な条件は以下の3点です。
- 業務外のケガ・病気で働けない状態である
- 連続する3日間の待期期間(欠勤)がある
- 4日目以降も働けない状態が続いている
傷病手当金は「給与の3分の2」が目安で、健康保険組合から支給されます。
なお、同一傷病による支給は通算で「1年6か月」が上限となります。
計算式(概要)は次の通りです。
| 支給額=1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 × 支給日数 |
休職中の給与がゼロの場合でも、傷病手当金が支給されるケースが一般的です。ただし、休職中に給与の一部が支払われる場合、差額調整が行われる点に注意しましょう。
参考記事:傷病手当金をスムーズに受け取るには? 条件・計算・申請方法を完全ガイド
社会保険料・住民税の支払い義務は継続する?
休職中であっても、社会保険料や住民税の支払い義務は原則として消滅しません。
雇用契約が継続している限り、加入している保険制度は維持されるため、無給であっても保険料の支払いが必要になります。誤解されやすいポイントでもあるため、休職開始時に従業員へ丁寧に説明しておくことが重要です。
以下に、社会保険料と住民税の取り扱いを整理しました。
| 区分 | 支払い義務 | 休職中の扱い | 企業側の対応ポイント |
| 社会保険料(健康保険・厚生年金) | 継続(免除されない) | 無給でも保険料は発生。従業員から立替徴収が必要な場合あり | 事前の説明と徴収方法の確認を行う |
| 雇用保険料 | 継続 | 給与がゼロの場合は発生しない(給与比例のため) | 給与の有無に応じて自動計算される |
| 住民税 | 継続(前年所得に基づき課税) | 特別徴収から普通徴収へ切替になるケースが多い | 切替手続きと納付方法の案内が必要 |
休職中に給与が出ない場合でも、健康保険・厚生年金の保険料は従業員・企業ともに負担する必要があります。給与から天引きできない場合は、従業員からの直接徴収や立替処理が必要となり、未納が発生すると保険資格に影響が出る可能性もあるため、注意しましょう。
休職時の手続きと診断書の扱い
休職を開始する際には、診断書の確認、申請手続き、社内外との連携など、企業側で対応すべき項目が多くあります。特に中小企業では、担当者が兼務しているケースが多く、曖昧な運用がそのまま労務トラブルに発展しやすいため、手順を標準化しておくことが重要です。
診断書の提出は必要か?ない場合の対応は?
休職の判断には、従業員が本当に業務遂行困難な状態なのかを確認する必要があります。診断書の提出を求めるのが一般的です。
診断書が提出できないケース(通院前、緊急時など)では、一時的に欠勤扱いとして対応し、後日提出を求める運用が一般的です。
ただし、「本人が診断書を拒む」「運用があいまい」などの状態のまま休職を認めてしまうと、復職判断・休職延長・自然退職の判断が困難になり、のちのトラブルにつながります。
診断書は、あくまで「休職判断の根拠」として扱うものであり、医師の意見だけではなく会社としての就業可能性判断と合わせて総合的に判断することが重要です。
休職開始時の労務担当者の対応フロー
休職をスムーズに開始するためには、「何を・いつ・誰が対応するか」を明確化しておくことが不可欠です。
対応が属人的になると、本人との意思疎通のズレや傷病手当金の手続き遅れにつながりやすく、企業側のリスクも高まります。
以下の表で、実際の中小企業でも使いやすい形で、休職開始時の基本フローを整理しました。
| ステップ | 内容 | ポイント |
| ① 本人からの申し出を受ける | 症状や困りごとをヒアリングし、勤務継続が可能か確認 | 感情的な詰問は避け、事実を淡々と聞く姿勢が重要 |
| ② 診断書の提出を依頼 | 提出可能か確認し、難しい場合は後日提出を案内 | 診断書なしで休職決定をすると後で復職判断が困難になる |
| ③ 休職可否を判断 | 就業規則に基づき、休職事由・期間・条件を整理 | 医師の意見と会社の判断(業務遂行可能性)の両方を確認 |
| ④ 休職開始日の決定と通知 | 書面やメールで「休職期間・条件・社会保険の扱い」を伝える | 曖昧な通知は後で紛争の火種になるため文書化は必須 |
| ⑤ 傷病手当金の案内 | 健康保険組合への申請書類の流れを説明 | 特に中小企業では申請漏れや遅れが発生しやすいポイント |
| ⑥ 定期連絡の方法を合意 | 月1回の連絡・面談の頻度・提出物のルールを決定 | 「連絡が取れない問題」を防ぐためルール決めが重要 |
休職開始時は、本人・会社双方が精神的に不安定になりやすいタイミングです。そのため、企業側は「手続きの標準化」を徹底し、落ち着いて対応できる仕組みを整えておくことが重要といえます。
本人・上司・産業医との連携における留意点
休職対応では、本人・上司・労務担当・産業医(または主治医)が関わるため、情報の扱いやコミュニケーションのルールを整理しておくことが重要です。
以下の表に、連携時の主なポイントを整理します。
| 相手 | 留意点 | 具体的に気をつけること |
| 本人 | 連絡窓口を一本化し、混乱を防ぐ | 労務担当を窓口とし、上司・同僚が個別に連絡しないよう周知する |
| 上司 | 情報共有は必要最小限にとどめる | 病名は共有しない。「就業不可」「業務調整が必要」などに限定 |
| 産業医・主治医 | 復職判断には医師の意見書が極めて重要 | 「仕事内容に対する就業可能性」まで具体的に確認する |
| 社内(労務・人事) | 復職に向けた支援策を事前に検討しておく | 時短勤務・業務量調整・段階的復帰プランを準備する |
休職対応では、まず本人とのコミュニケーションの一本化が極めて重要です。
上司や同僚が善意で個別に連絡してしまい、本人の負担が増えたり、情報の食い違いが起きるケースは中小企業で特に多くあります。そのため、休職中の連絡窓口は「労務担当者」に固定し、他部署からの接触は控えるよう社内で統一することが必要です。
休職者と中小企業の対応|復職・転職・解雇の扱い
休職者への対応は、復職判断・転職可否・退職取り扱いなど、企業として慎重に進めるべきテーマが多く含まれます。特に中小企業では、制度や人員の余裕が限られるため、正しいルールと適切な運用が労務トラブルの予防に直結するポイントです。
復職の可否判断と医師の意見の重要性
復職判断は、休職対応の中でもっとも慎重に行うべき領域といえます。医師の意見は重要な判断材料になりますが、企業側にも独自の判断責任があり、両者をどう照らし合わせるかが実務上のポイントです。
以下に、復職判断における主要な観点を整理します。
| 判断項目 | 内容 | 実務でのポイント |
| 医師の意見(就業可能性) | 勤務可能・制限の有無・必要な配慮などを確認 | 「就業可能=即復職OK」ではない点に注意 |
| 業務遂行能力 | 従来の業務に無理なく従事できるかを会社が判断 | ミスマッチがある場合は業務調整や配置転換を検討 |
| 職場環境との適合性 | 職場ストレス・業務負荷に耐えられるか | 人間関係や業務量調整が必要な場合も |
| 段階的復帰の可否 | 時短勤務・業務限定復帰などが可能か | 再休職リスクの低減に効果的 |
| 安全配慮義務 | 再発防止・職場の安全を確保する責任 | 無理な復職判断は企業側のリスクにもなる |
復職判断では、まず医師の意見書が重要な判断材料です。ただし、医師は企業側の具体的な業務内容を必ずしも把握していないため、「就業可能」とされている場合でも、そのまま復職できない場合もあります。
また企業には「安全配慮義務」があり、職場復帰によって従業員や職場に過剰な負担が生じる場合、無理に復職させてはいけません。
医師の意見と社内判断を組み合わせ、文書化したうえで慎重に判断することが、後々の労務トラブル回避にも繋がります。
休職中に転職活動を拒否してもいい?
休職中の転職活動は、本人の自由に委ねられる領域であり、企業が強制したり、逆に禁止したりする権限はありません。この点を誤解すると、本人への不当な圧力や労務トラブルにつながるため、企業側として正しく理解しておく必要があります。
| 観点 | 内容 | 実務上のポイント |
| 本人の自由 | 休職中の転職活動は「しても・しなくても自由」 | 私生活への介入はNG。強制・禁止のいずれも不可 |
| 拒否しても不利益なし | 転職活動をしないことで評価・復職判断が不利になることはない | 復職可否は健康状態と業務遂行可能性で判断 |
| 企業からの提案は“任意” | 長期休職の場合、キャリア相談として提案されることはある | 退職勧奨にならないよう、選択肢提示に留める |
| 強制・圧力は違法リスク | 転職活動の有無を理由に不利益を与えるのはNG | 解雇権濫用・ハラスメントと見なされる可能性あり |
休職中に転職活動を行うかどうかは、「プライベート領域」に属するため、企業が介入すべきではありません。したがって休職者が転職活動を“しない”と判断した場合でも、企業はこれを尊重する必要があります。
解雇・自然退職のリスクと「解雇権濫用」の注意点
休職者の取り扱いの中でもっとも慎重に対応すべきテーマが「退職」と「解雇」の扱いです。
特に中小企業では、制度が明文化されていないまま個別対応を行い、のちに大きな労務トラブルへ発展するケースが少なくありません。ポイントは、「自然退職」と「解雇」はまったく別物であり、企業側の判断余地とリスクが大きく異なるという点です。
まず、自然退職とは「就業規則に定めた休職期間を満了してもなお勤務ができない場合、その時点で雇用契約が終了する」という扱いを指します。
これはあくまで就業規則に基づくものであり、企業の一方的な意思による契約終了ではありません。そのため、正しく運用されていれば労務リスクは比較的小さいとされています。
一方で「解雇」は、企業側が従業員との労働契約を一方的に終了させる行為です。特に私傷病による休職中の解雇は、“解雇権の濫用(濫用)”と判断される可能性が非常に高いため、原則として避けるべきといえます。
参考記事:【企業向け】退職とは?種類・手続き・注意点を知ってトラブルを防ぐ
まとめ
休職制度は、中小企業にとって従業員の健康と事業継続を両立するための重要な仕組みです。
しかし、法律で細かな運用方法が定められていないため、企業ごとにルールが異なり、適切に整備されていない場合は復職判断や給与・手当の処理、退職扱いなどでトラブルが発生しやすくなります。
従業員が安心して働ける環境を整えることは、単にトラブルを防ぐだけではありません。長期的には定着率向上や組織の安定にもつながります。
制度を整え、丁寧で公平な運用を続けることが、中小企業における健全な組織づくりの基盤となりますので、積極的に整備しましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
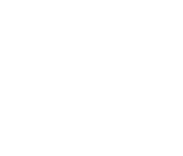 会員登録
会員登録












