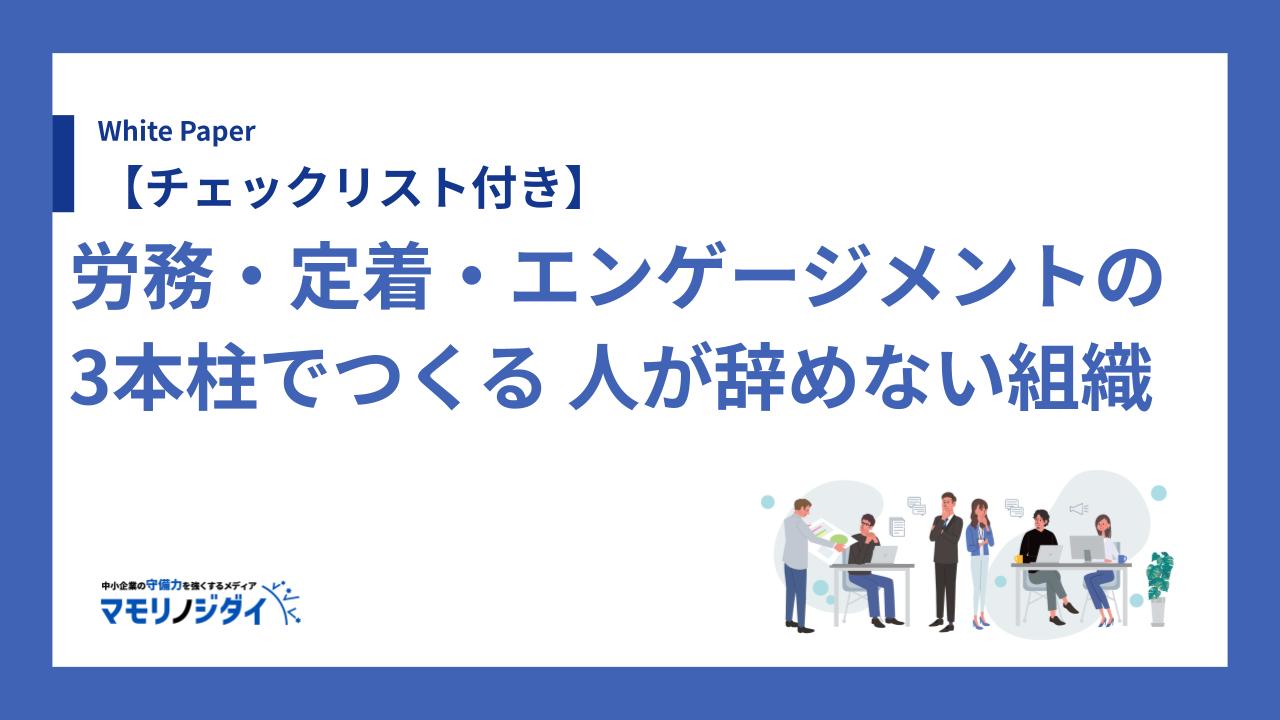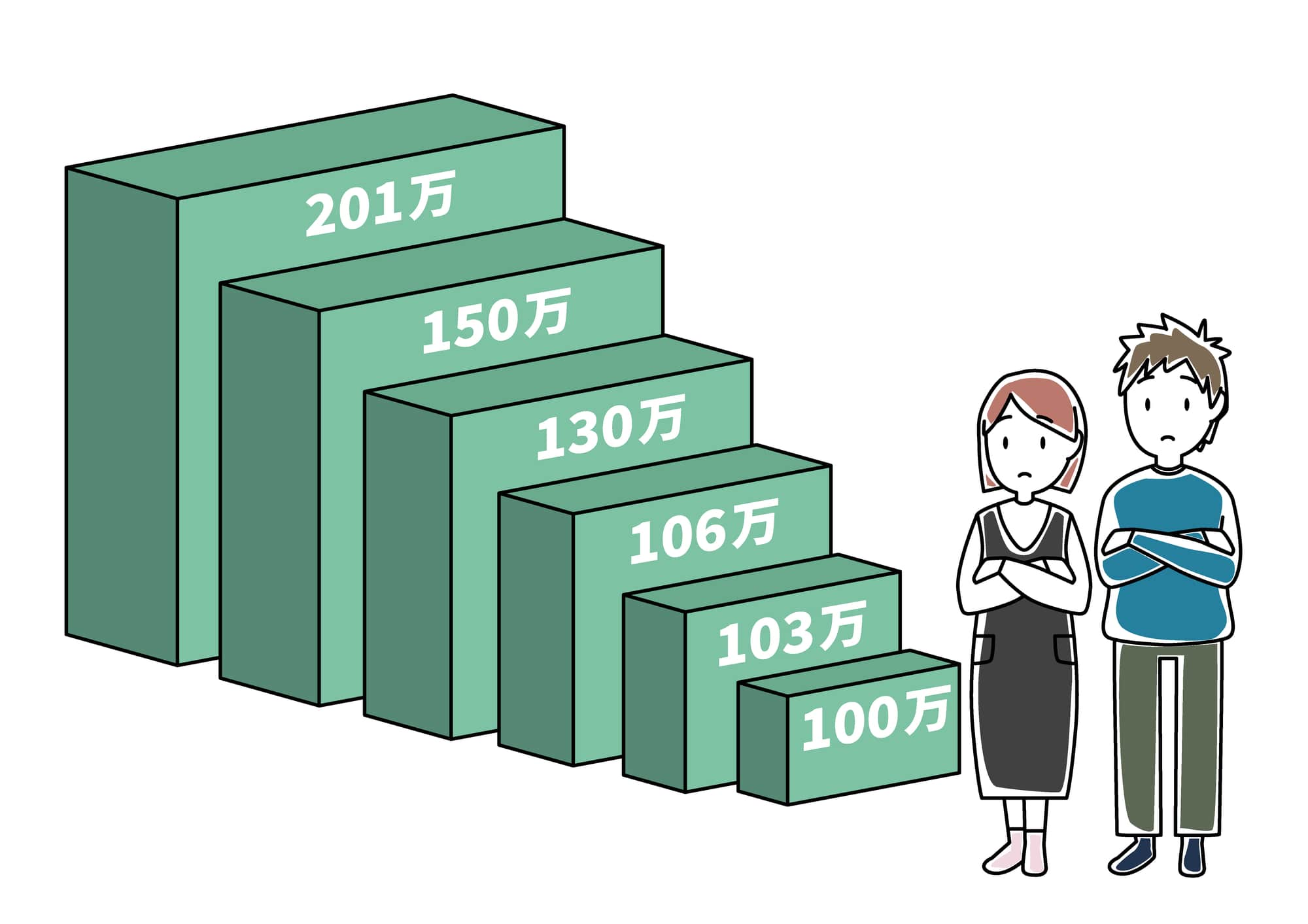ジョブ型雇用とは?特徴・メンバーシップ型との違い・導入ポイントをわかりやすく解説

近年、多くの企業で注目されているのが「ジョブ型雇用」です。特にテレワークや副業の普及、成果主義の浸透といった働き方の変化を背景に、従来の「メンバーシップ型雇用」からの転換を検討する動きが活発化しています。
本記事では、ジョブ型雇用の定義から、メンバーシップ型との違い、企業・従業員双方のメリット・デメリット、導入プロセスや成功事例をわかりやすく解説しました。
また以下の資料では中小企業の人事担当の方に向けて、労務・定着・エンゲージメントの観点から人が辞めにくい組織の作り方を解説していますので、こちらも参考にしてください。
目次
ジョブ型雇用とは?わかりやすい定義と基本理解
ジョブ型雇用とは、あらかじめ定義された「職務」に基づいて人材を採用・配置・評価する雇用形態を指します。企業が必要とする職務内容を明確に定義し、その職務を遂行できるスキルや経験を持つ人材を外部から採用するのが基本的な考え方です。
従来の日本企業に多い「メンバーシップ型雇用」では、ポテンシャルや将来性を重視して人を採用し、入社後に業務を割り振っていくのが一般的でした。これに対し、ジョブ型雇用では業務ありきで人を選ぶという、明確な違いがあります。
中小企業では一人が複数業務を担うことも多く、職務を細かく切り過ぎると運用が回りません。まずは“成果が測りやすい職種”から職務を定義するなど、現実的な設計が重要です。
「職務記述書(ジョブディスクリプション)」の役割
ジョブ型雇用において中核的な役割を果たすのが、「職務記述書(ジョブディスクリプション)」です。
これは、職種ごとの業務内容・必要なスキル・責任範囲・成果目標などを明文化したもので、採用から評価、昇進、報酬設計に至るまで、すべての人事施策の基盤となります。
この文書が明確であればあるほど、企業と従業員の間で期待値が一致しやすくなり、ミスマッチの防止にもつながるのです。また、職務に基づく評価制度を整備することで、人事の透明性や納得感の向上にも寄与します。
ただし、日本企業においては「業務の境界が曖昧で、柔軟な異動や兼務が前提」となっているケースも多く、職務記述書の設計には十分な検討と現場のヒアリングが欠かせません。
ジョブ型とメンバーシップ型との違いを3つの視点で比較
日本企業では長らくメンバーシップ型雇用が主流でしたが、近年はジョブ型への移行を進める企業が増えています。
ここでは、実務で特に差が出やすい「採用・配属の考え方」「評価・処遇の基準」「雇用の安定性と柔軟性」という3つの視点から、両者を比較して整理しました。
採用・配属の考え方
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用では、「人を採用する」のか「職務に対して採用する」のかという根本的な発想が異なります。企業の成長戦略や人材ニーズに応じて、どちらの型を選ぶかが大きく影響するのです。
| 項目 | ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 |
| 採用 | 特定の職務・スキルに応じた人材を採用 | 将来的な活躍を期待したポテンシャル採用 |
| 配属 | 採用時の職務に即したポジションに配属 | 採用後に部署や職種を柔軟に決定・異動 |
ジョブ型は採用段階で役割が明確になっているため、即戦力人材を求める場面に向いています。一方、メンバーシップ型は長期的な育成や社内ローテーションを前提としており、汎用性のある人材活用が可能です。
評価・処遇の基準
評価制度の設計は、従業員のモチベーションや定着率に大きく影響します。ジョブ型とメンバーシップ型では、何をもって「貢献」とするかの基準が異なるので注意しましょう。
| 項目 | ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 |
| 評価基準 | 職務ごとの成果やスキル、目標達成度を重視 | 人柄、勤務態度、勤続年数、上司の評価など |
| 処遇基準 | 個人の職務内容・成果に応じて設定される | 組織内の階層・年功による傾向が強い |
ジョブ型は透明性が高く、成果が報われやすい反面、成果主義のプレッシャーも伴います。メンバーシップ型は相対評価が中心になりやすく、上司や周囲の関与度も高くなりがちです。
雇用の安定性と柔軟性
雇用形態としての安定性と、組織内での柔軟な動きやすさも両者で異なります。時代や業種によって、求められるバランスは大きく変化しますので、合わせましょう。
| 項目 | ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 |
| 雇用維持が難しくなる可能性 | 職務が消滅すれば雇用継続が困難になることも | 業務が変わっても社内異動で雇用を維持しやすい |
| 柔軟性 | 高度専門職に限定すれば柔軟な働き方が可能 | 組織内で柔軟な役割変更や配置転換が可能 |
ジョブ型ではスキルを活かして多様な働き方が可能になる一方で、企業側の再配置余地が狭まり、雇用が不安定になる可能性があります。メンバーシップ型は、雇用の継続性は高いものの、専門性の蓄積には向かない場面もあるのです。
なぜ今、ジョブ型雇用が注目されているのか
近年、ジョブ型雇用への関心が高まっている背景には、社会・経済・人材の価値観の変化があります。従来型の年功序列・終身雇用制度に限界が見え始め、職務や成果に基づく新しい雇用スタイルが必要とされているのです。
ここでは注目される主な要因を4つの視点から解説します。
参考記事:【中小企業向け】タレントマネジメントとは?導入メリット・成功事例・実践ステップを解説
経団連などによる提言と国の推進方針
経団連(日本経済団体連合会)は、かねてより「ジョブ型人事・雇用への転換」を提言している状況です。国もまた、働き方改革の一環として、職務明確化による多様な働き方の実現を掲げています。
実際に内閣府の成長戦略や厚労省の人材政策にも「ジョブ型雇用の推進」という文言が含まれ、企業側にも人事制度の見直しが求められる状況です。特に上場企業やグローバル展開企業では、職務ベースの制度設計が進みつつあります。
出典)内閣官房「ジョブ型人事指針」p.1
テレワーク・副業・成果主義の浸透
コロナ禍を契機にテレワークや副業が一般化し、場所や時間に縛られない働き方が当たり前になってきました。この変化は、曖昧な職務内容ではマネジメントが困難になるという課題を浮き彫りにしています。
その結果、「誰が・何を・どこまで」担うのかを明確にしたジョブ型雇用が注目されるようになったのです。加えて、成果主義の考え方が若手層にも浸透しつつあり、業務のアウトカムで評価されたいという声が高まっています。
専門人材・高度人材の確保競争
ITエンジニア、データサイエンティスト、AI人材など、専門スキルをもつ人材の採用競争が激化しています。こうした人材は「どんな業務を任されるのか」「スキルが活かせるか」を重視する傾向があり、職務内容が曖昧なメンバーシップ型では選ばれにくくなってきました。
ジョブ型であれば、明確な職務定義と成果連動の処遇が可能になるため、専門人材からの信頼性も高まります。特に中小企業が優秀人材を惹きつけるためには、ジョブ型導入が1つの武器です。
若年層・中堅層のキャリア自律志向
近年の若手社員は「キャリアを自分でデザインしたい」「会社に任せきりにしたくない」という価値観をもつ傾向が強くなっています。また、40代前後の中堅層にとっても、自分のスキルや経験が他社でどう活かせるかを意識する時代です。
ジョブ型雇用は、職務・成果ベースのキャリア形成を可能にするため、こうした層からの支持を得やすい制度といえます。
企業側から見たジョブ型雇用のメリット・デメリット
ジョブ型雇用は、特定の職務に対して必要なスキル・経験を持つ人材をマッチングすることで、企業と従業員の双方にとって合理的な雇用を実現できるものです。ここでは、企業の立場から見たメリットとデメリットをそれぞれ整理しました。
参考記事:リテンションとは?意味・目的・リスク・施策事例をわかりやすく解説
企業側のメリット
ジョブ型雇用を導入することで、企業は人材配置の最適化や評価制度の透明化、採用の質の向上といった多くの恩恵を受けることができます。特に専門性の高い人材を求める企業にとっては、スキルベースでの採用・登用が可能になる点が大きな魅力です。
業務と人材のマッチ度向上
ジョブ型では「どの業務に、どのスキルをもつ人材を割り当てるか」が明確になるため、必要な人材を的確に採用・配置できるようになります。これにより、配置ミスや人材活用の非効率を防ぐことができ、結果として生産性の向上が可能です。
評価・処遇の透明化
職務記述書に基づいて期待成果や責任範囲が明確になることで、従業員の評価が「属人的な印象」ではなく、客観的な基準に基づいて行われるようになります。これにより、人事評価に対する不満を減らし、処遇への納得度向上が可能です。
採用のスキルベース化
従来の「ポテンシャル採用」ではなく、実務経験や保有スキルに基づく「即戦力採用」がしやすくなります。採用活動において、候補者に対し具体的な業務内容を提示できるため、選考のミスマッチが減り、選ばれる企業としての魅力も高まるのが特徴です。
企業側のデメリット
一方で、ジョブ型雇用には企業にとっての課題も少なくありません。制度設計や職務明確化に伴う初期負担、柔軟な異動の難しさ、人材マネジメントの硬直化リスクなど、特に組織運営の面で大きな影響が出る可能性があります。
制度整備・導入コストがかかる
ジョブ型を導入するには、まずすべての職務に対する記述書を整備し、それに紐づく評価制度・報酬体系・等級制度を再設計する必要があります。このプロセスには多くの時間とリソースが必要であり、外部コンサルの活用が前提となるケースも少なくありません。
組織内での柔軟な異動が難しくなる
ジョブ型では職務ごとに雇用契約が成立しているため、異なる業務への配置転換には本人の合意が必要です。そのため、急な欠員対応や、プロジェクトごとの人材シフトが柔軟に行えなくなる可能性があります。
雇用の硬直化リスク
業績悪化や事業再編で職務自体が消滅した場合、そのポジションに紐づく雇用も終了することがリスクです。メンバーシップ型のように「異動による再配置」が難しいため、企業としても従業員としてもリスクが高まります。
従業員側から見たジョブ型雇用のメリット・デメリット
ジョブ型雇用の導入は、企業側だけでなく従業員の働き方やキャリア形成にも大きな影響を与えるのが特徴です。職務内容や成果に基づく評価が進むことで、個々の専門性が活かされる場面が増える一方、自律性が求められる厳しさも伴います。
ここでは、従業員の視点から見た利点と懸念点を整理しました。
従業員側メリット
ジョブ型雇用では、業務内容と成果が明確に定義されるため、努力やスキルが正当に評価されやすくなります。また、職務に対する責任が明確になることで、従業員自身のキャリア形成やスキル選択の自由度も高まるのです。
成果・専門性で評価されやすい
業務の成果が直接評価につながるため、「年功序列」や「曖昧な基準」に左右されることなく、自分の専門性や実績をもとに評価されやすくなります。特に自らの能力に自信がある人材にとっては、公平で納得感のある評価が受けられる点が魅力です。
キャリアの自己決定性が高まる
職務が明確に定義されていることで、「どんなスキルを伸ばせば次のポジションを目指せるのか」「自分のキャリアパスに合った業務とは何か」といった視点を持ちやすくなります。
結果として、キャリア選択において受け身ではなく、主体的な判断がしやすくなるのです。
従業員側デメリット
一方で、ジョブ型雇用では個々の業務範囲が限定されやすく、従来のような柔軟な配置転換や上司・同僚による手厚いサポートが得にくくなることもあります。また、スキルや知識の獲得も個人の責任とされやすく、成長環境が整っていない場合には不安要素です。
配置転換やフォロー体制が弱まる可能性
特定の職務に基づいた契約となるため、社内異動によるキャリア形成や、部署間のサポート体制が希薄になりがちだといえます。例えば体調や家庭の事情などで業務変更を希望しても、柔軟に対応されにくいです。
スキルアップの自己責任化
ジョブ型では「スキルがある人を採用・登用する」前提のため、育成機会や研修制度が手薄になるリスクもあります。これまでのように企業側が包括的にキャリアを支援してくれるとは限らず、常に自発的に学び続ける姿勢が必要です。
ジョブ型雇用の導入に必要なステップ
ジョブ型雇用を効果的に導入するためには、制度だけでなく運用面や社内文化の整備まで含めた総合的な取り組みが求められます。
とくに中小企業においては、スモールスタートで段階的に進めることが現実的です。以下では、導入の際に検討すべき主なステップを整理します。
適用職種の選定と対象範囲の明確化
すべての職種に一律でジョブ型雇用を適用するのではなく、まずは専門性が高く成果が明確に測れる職種から導入を始めるのが一般的です。
特にリソースが限られる中小企業においては、「成果が測定しやすく、業務範囲が比較的明確な職種」から着手するのが現実的といえます。具体的には、エンジニアやデザイナー、マーケターといった専門職のほか、バックオフィスでも「経理の決算領域」や「法務の契約関連業務」などは、ジョブ定義がしやすく導入のハードルが低い傾向にあります。
一方で、総務や営業などは、状況に応じて業務範囲が広がりやすい職種です。こうした職種には、ジョブ定義をあえて広めに設定する「ハイブリッド型」の運用を検討するなど、自社の実態に合わせた柔軟な設計が求められます。
対象範囲を限定し、スモールステップで始めることで、社内の混乱を最小限に抑えながら導入効果を段階的に検証することが可能になります。
職務記述書(ジョブディスクリプション)の作成
ジョブ型雇用の要となるのが、職務記述書になります。仕事内容・責任範囲・成果指標・必要なスキルなどを明文化し、企業と従業員の間で期待値をすり合わせる役割です。
この文書が曖昧であると、評価や処遇に対する不満が生まれやすくなるため、業務分析や現場ヒアリングを丁寧に行いながら作成することが重要といえます。
最小限、以下の項目が揃えたうえで運用が始めましょう。
- 職務名/ミッション(1行)
- 主な業務(5〜7項目)
- 成果指標(2〜4項目)
- 権限・責任範囲
- 必須スキル/歓迎スキル
- 関係部署・連携相手
賃金・等級・評価制度の見直し
職務ベースの人事制度に移行する場合、従来の年功序列や職能資格制度との整合性を取るため、報酬制度の見直しが不可欠です。例えば、成果に応じた変動報酬や等級制度の再構築などを検討しましょう。
特に既存社員との公平性をどう担保するかは重要なポイントであり、移行期間中の説明や透明性確保も同時に進める必要があります。
参考記事:【中小企業向け】同一労働同一賃金対策ガイド|派遣や再雇用の実務まで徹底解説
社内教育と意識改革のセット導入
ジョブ型雇用では、従業員に求められる役割や責任の重みが変わるため、制度だけでなくマインドセットの転換も必要です。管理職層には職務管理のスキルが、現場従業員には成果志向やキャリア自律の考え方が必要になります。
そのため、制度導入と並行して、研修やワークショップなどを通じた社内教育が欠かせません。単なる制度変更で終わらせず、行動変容を促す土壌づくりが肝となります。
試験導入・改善サイクルの設計
いきなり全社導入を目指すのではなく、まずは一部部署やプロジェクトでの試験導入を通じて、制度の実効性や運用上の課題を見極めるアプローチが有効です。
トライアル導入後には必ずフィードバックを取り、改善を重ねながら全社展開へと進めていくことが成功の鍵となります。特に中小企業では経営層や現場の密なコミュニケーションを活かして、柔軟に制度を進化させていく姿勢が必要です。
ジョブ型雇用の導入企業事例
ジョブ型雇用は、大企業を中心に導入が進んでおり、特に人材のグローバル化や専門性強化を課題とする企業では重要な施策として位置付けられています。ここでは、実際に制度を導入した企業の事例を紹介し、どのように運用されているかを具体的に見ていきましょう。
資生堂:管理職層への段階導入
資生堂は、グローバル競争のなかで日本法人の生産性と専門性の課題を感じたことをきっかけに、ジョブ型雇用を導入しました。特に管理職層におけるスキルの不均衡や役割の曖昧さを解消する目的が強く、国内の管理職約1,700名を対象に新たな雇用制度を展開しています。
この導入に際しては、従来の年功序列的な考え方から脱却し、「業務内容に応じた評価・処遇の仕組み」へとシフトする必要がありました。その一環として「ジョブグレード制度」が導入され、20以上のジョブファミリーを定義。それぞれに対して職務記述書(ジョブディスクリプション)を整備し、社員が自らの職務と成果責任を明確に認識できるようにしました。
日立製作所:キャリア自律とセットで推進
日立製作所は、グローバル市場への事業展開を背景に、統一された人事制度の必要性を感じていました。これを受け、2021年に「ジョブ型人財マネジメント」の導入を開始。新卒・中途の両方でスキルベースの採用を強化するなど、雇用制度の見直しを進めています。
特徴的なのは、「デジタル人財採用コース」を新設し、個別のスキルや役割に応じた処遇を実現している点です。一律の初任給ではなく、職務内容に応じて待遇を決定する仕組みがとられています。
さらに、これらの制度改革と並行して職場環境の整備や社員への教育も進め、全社的な移行を段階的に推進しています。
実際、ジョブ型雇用はコロナ禍での一時的な対策ではなく、2011年から計画されていた長期的な人事戦略の一環として実行されてきました。海外売上比率の高まりに対応するため、グローバル共通の人材マネジメント基盤を整備し、国内外を問わず全社一体の制度構築を進めています。
KDDI:専門人材の獲得と定着を重視
KDDIは2020年8月、ジョブ型の要素を取り入れた「KDDI版ジョブ型人事制度」を導入しました。背景には、従来の通信事業を中心とした人材育成が、特定スキルへの偏りを生み、組織としての柔軟性を欠いていたという課題があります。
この制度では、若手社員のチャレンジ精神を引き出し、外部から採用した人材を着実に成長させることを目指しています。特徴的なのは、いわゆる「ハイブリッド型」である点です。職務をあえて大きな単位で定義し、例えば「採用」「人事制度設計」「給与計算」といった業務もすべて「人事」というジョブに統合している状況です。
このような職務定義の工夫によって、社員は特定の専門性を高めつつも、別の領域へとキャリアを拡張する道も残されています。
また、制度の導入と並行して社内教育の仕組みやキャリア支援策も充実させており、人材の流動性と定着のバランスを両立させる点がKDDIの大きな特徴です。
「ジョブ型=万能」ではない?導入時の注意点と現実的なバランス
ジョブ型雇用は多くのメリットがある一方で、すべての企業や業務に適しているとは限りません。導入にあたっては、自社の組織特性や企業文化を踏まえた慎重な設計と運用が求められます。
職務の明確化が逆に組織の柔軟性を奪うケース
ジョブ型では、職務を明確に定義することで人材配置や評価の透明性が高まる一方、定義された職務以外の仕事に対応しづらくなるリスクもあります。
特に変化の激しい現場や、多様な業務をこなすことが求められる中小企業においては、「これは自分の業務ではない」と業務範囲を限定してしまうことがリスクです。結果的に柔軟性や協働体制を損なう恐れがあります。
制度として職務を明確にしたとしても、現場運用において一定の余白を残しておく設計が重要です。
メンバーシップ型の良さを活かした“ハイブリッド型”という選択肢
ジョブ型とメンバーシップ型は、どちらが優れているというものではなく、それぞれに利点と課題があります。
例えばKDDIのように、ジョブの定義をある程度広く捉えることで専門性と柔軟性のバランスを保つ「ハイブリッド型」の導入も注目されています。これは、日本型の組織風土とグローバル基準の人材マネジメントを融合させる実践的な手法です。
自社のカルチャーや業務内容に応じて、どのモデルが最も適しているかを検討する視点が求められます。
制度だけでなく「運用」と「風土」の設計が鍵
ジョブ型雇用の導入においては、制度の整備だけでなく、その運用を担う管理職層や人事担当者の理解と実行力が重要です。
また、社員が「与えられた職務」に閉じこもるのではなく、主体的にスキルを磨き、周囲と協働する文化を育てる必要があります。こうした組織風土があってこそ、ジョブ型は本来の効果を発揮するのです。
単なる制度変更ではなく、「人の動き方」「組織の価値観」そのものに目を向けることが、ジョブ型導入の成功には欠かせません。
まとめ
ジョブ型雇用は、業務内容を明確に定義し、それに見合ったスキルや成果で評価する仕組みです。特にグローバル企業や専門性の高い職種では導入が進んでおり、スキルベースの採用や処遇の透明化といったメリットが期待されています。
一方で、制度の整備や運用に手間がかかる点や、柔軟な異動が難しくなるといったデメリットも見逃せません。企業規模や文化によっては、メンバーシップ型とのハイブリッドで設計する方が現実的な場合もあります。
従業員側から見ても、専門性を高めやすくキャリア形成の自律性が高まる反面、スキルアップを自己責任で進める必要があるなど、一定の覚悟が求められる仕組みです。
導入を成功させるには、単なる制度変更にとどまらず、運用を担う人材の教育や、社員全体のマインドセットの変革が不可欠といえます。評価・処遇の仕組み、採用方針、組織風土をトータルで見直すことで、はじめてジョブ型雇用の真価が発揮されるといえるでしょう。
企業の持続的な成長に向けて、自社に合った「ジョブ型雇用」の在り方を検討することが、これからの時代に求められる重要な経営判断のひとつです。
特に中小企業においては、いきなり全社に導入するのではなく、まずは「導入目的の明確化」と「対象職種の選定」から着手することをおすすめします。
ジョブディスクリプション(職務記述書)をテンプレート等で作成し、限定的な範囲で「試験導入→改善」のサイクルを回すことから、自社に最適な形を模索していきましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
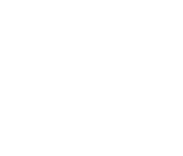 会員登録
会員登録