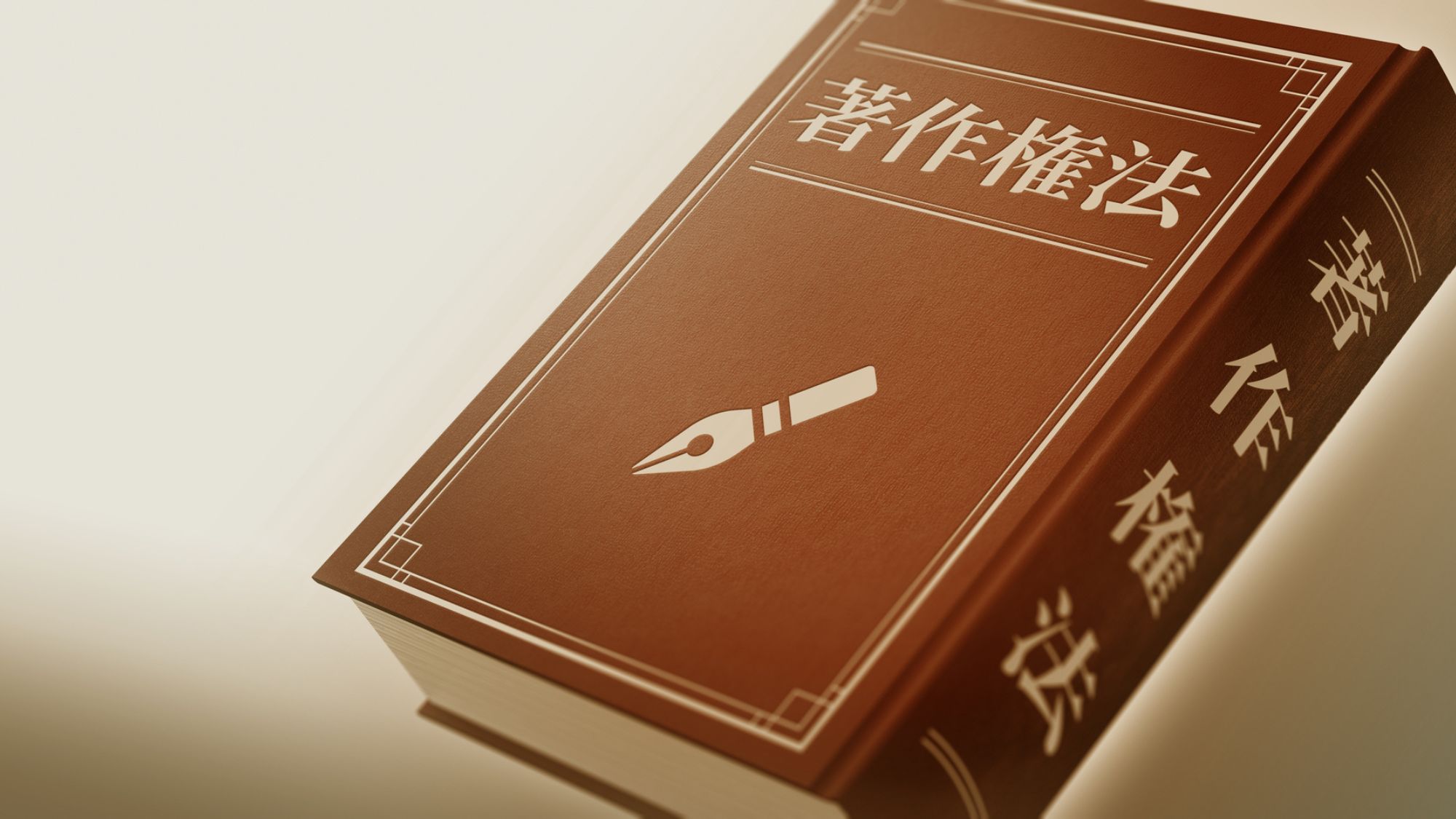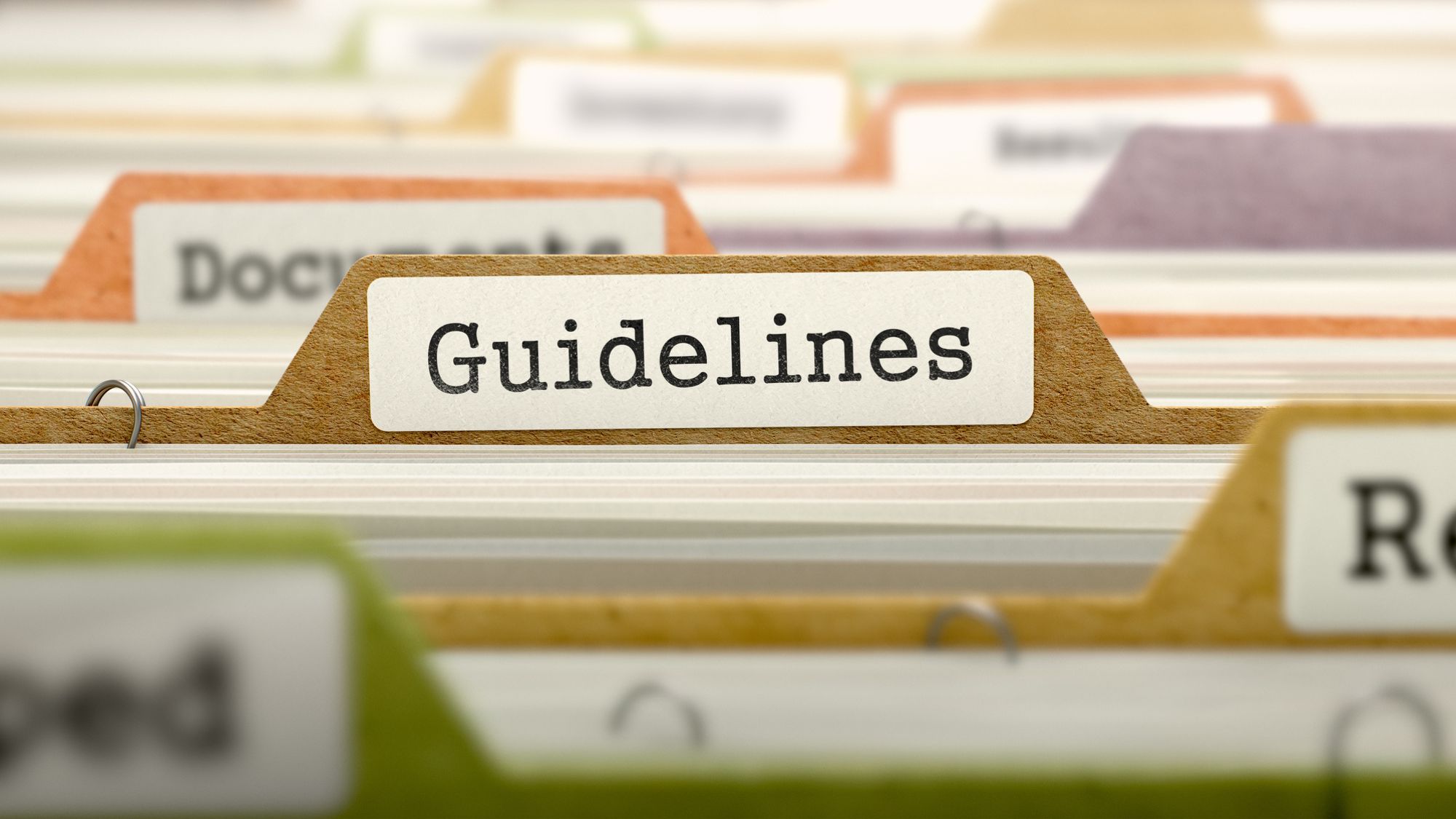コンプライアンス研修とは?目的、効果、研修ネタの事例を徹底解説

コンプライアンス研修とは、企業が従業員のコンプライアンス意識を高めるために取り組む研修を指します。正しく研修を行うことで、企業の法令遵守違反のリスクを未然に防げることがメリットです。
企業の経営層の方のなかには「コンプライアンス研修の内容は?」「研修資料のネタはどうやって作ったらいいの?」などの悩みを持っている方も多いことでしょう。
そこで今回はコンプライアンス研修について、目的、期待される効果、扱うべきテーマ(ネタ)などを網羅的に解説します。研修を実施したい方は、ぜひこの記事をご一読ください。
目次
コンプライアンス研修とは
コンプライアンス研修は、企業が法令や規則を遵守し、社会的責任を果たすための従業員教育を行うことを目的としています。
特に現代ではSNSの普及など、コンプライアンス違反のリスクが高まっている状況です。法律違反の側面だけでなく、ブランド毀損の観点でも研修を行う必要があります。
全社員が企業として守るべき規範を理解し、実際の業務において適切な行動を取れるよう、正しく知識を伝えることが重要です。
コンプライアンスとは
コンプライアンス(compliance)を直訳すると「法令遵守」となります。
企業活動におけるコンプライアンスには、法律・規制に従うことはもちろん「企業理念にのっとった行動を取る」「一般常識を理解し正しい行動を取る」といった内容も含まれます。
つまり法的な義務を守るだけでなく、顧客や同僚を含めたステークホルダーとの信頼関係を築くために、公正で透明性のある経営が求められるのです。コンプライアンスを守ることで、企業の安定した経営につながります。
企業で起きやすいコンプライアンス違反とは
ここでは、特に企業内で発生しやすいコンプライアンス違反の例を紹介します。
情報漏洩
情報漏洩は、個人情報や機密情報が外部に流出することで発生する重大なコンプライアンス違反です。
顧客データ・従業員の個人情報が漏れた場合、企業イメージが低下します。法的制裁のリスクもあります。
例えば「営業担当者が、自宅作業のため顧客情報を個人用パソコンに移してしまう」などの違反例があります。
「情報管理の甘さ」や「不正アクセスへの対策不足」が原因となることが多いため、適切な管理体制やセキュリティ対策が必要です。
過重労働・過労死
過重労働・過労死も、労働基準法や労働安全衛生法に違反する重大なコンプライアンス問題です。特にマネージャー層への研修が必要になります。
企業が適切な労働環境を提供しない場合、大きな批判を受けるリスクがあります。従業員の労働時間の管理や、適切な休息を確保する仕組みを整えましょう。
SNSや転職用の情報サイトなどで企業の労働環境問題を告発できる時代ですので、特に厳重な対策が必要だといえます。
ハラスメント
特にセクシャルハラスメントやパワーハラスメントは、企業内で起こりやすいコンプライアンス違反の一つです。
ハラスメントが起きると、労働環境の悪化を招き、従業員のパフォーマンスに悪影響を与えます。また訴訟、社会的な非難を引き起こす可能性があります。
このようなことを避けるためにも、ハラスメントを防止するためのポリシーを明確にしましょう。そのうえで、従業員に対して継続的な教育を行う必要があります。
コンプライアンス研修は義務?
コンプライアンス研修は、法的にすべての企業に義務付けられているわけではありません。
しかし2020年6月から「労働施策総合推進法」の改正に伴って「パワーハラスメントの防止措置」が義務付けられました。中小企業の事業主も2022年4月1日から義務化されています。
このパワハラ防止措置の内容には「事業主の方針の明確化および周知、啓発」という項目があります。
そのため、企業としてはコンプライアンス研修にパワハラ防止措置としての内容を盛り込むことが必要です。
また、義務ではなくても、企業リスクを最小限に抑えるためにコンプライアンス研修の導入は望ましいといえます。社会的信用を守るためにも、研修を実施しましょう。
参考:厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」
コンプライアンス研修の目的
コンプライアンス研修の主な目的は、社員一人ひとりが法律や企業ルールを理解し、日々の業務で適切な行動を取ることができるようになることです。
具体的に3つの項目に分けてコンプライアンス研修の目的を紹介します。
ブランド毀損のリスク回避
コンプライアンス違反が起きると、ブランド毀損につながります。メディアやSNSを通じて、企業の評判が一瞬で崩れるリスクがあることを認識しましょう。
コンプライアンス研修を通じて社員に正しい行動規範を教えることで、ブランドイメージを保護することが重要です。研修によって「企業として推奨する行動」「やってはいけない行動」などを社員全体で共有しましょう。
企業ルールの共有
コンプライアンス研修は、法令遵守に加えて、企業独自のルール・ポリシーを社員全体に共有する重要な機会です。
企業ごとに業界や事業内容に合わせたルールがあり、それらを知らずに業務を進めることはリスクを伴います。内部統制を強化するためにも、研修などを通じて全社的に認識をすり合わせておきましょう。
なかでも「情報管理の方法」「労働時間の取り扱い」「取引先との契約の内容の取り扱い」「ハラスメントの事例確認」などは、特に重要です。
社員意識の向上
コンプライアンス研修を通じて、社員の法令遵守の意識を高められます。「自身の行動が企業全体にどのような影響を与えるか」を理解することが大切です。
社内ルールやガバナンスの意識が高まることで、業務上の行動を見直すきっかけにもなります。
例えば「社内データを自分のパソコンに移す」「部下を強く叱責する」などの行為は、罪悪感なく行いがちな行動です。きちんと研修をすることで意識が高まり、こうしたミスを未然に防げます。
コンプライアンス研修で扱うべきテーマ(ネタ)
これから自社でコンプライアンス研修を行う方に向けて、取り扱うべきテーマを紹介します。
法律と社会ルールの理解
法令遵守を徹底するためには、労働法や取引法といった基本的な法律を理解することが必須です。
これらの法律を社員が適切に理解することは、企業全体のコンプライアンスを強化するうえで最も重要な要素となります。
具体的に「労働法や取引法」「個人情報保護と情報セキュリティ」「著作権や肖像権」の3つの観点から守るべき法律を解説します。
労働法や取引法に関する知識
労働法は、従業員の権利を保護し、適切な労働環境を確保するために設けられている法律です。「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」「労働契約法」に細分化されます。
労働時間や賃金、休暇制度に関する法令や、取引法による契約の取り扱いなど、基礎的な知識を社内全体で理解することが重要です。
参考:厚生労働省「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」
個人情報保護と情報セキュリティ
「個人情報保護法」など、個人情報に関する法令の遵守は、企業にとって重要な課題です。
情報漏洩が発生すると、企業の信用を損ない、法的制裁を受ける可能性があります。「個人情報の適切な管理」と「情報セキュリティ対策の理解」が必要です。
法令に違反せずとも、個人情報の取り扱いによって顧客にネガティブなイメージを植え付ける可能性があることを認識しておきましょう。
著作権や肖像権の遵守
著作権や肖像権に関する知識は、特にクリエイティブな業務に携わる社員にとって必須の知識です。SNS、生成AIが普及している現代において、著作権・肖像権の範囲を正確に理解しておく必要があります。
違法な使用や権利侵害を未然に防ぐため、コンプライアンス研修ではこれらの法律についても詳細に説明しましょう。
社内行動規範の理解
コンプライアンス研修では、法令だけでなく「企業独自の行動規範」や「社内ルール」についても明確に伝えることが必要です。
これにより、社員が企業の価値観や期待される行動を理解し、一貫した行動を取ることができるようになります。
自社のルールや行動規範
各企業には、業界や業務内容に応じて異なる行動規範があります。例えば、倫理的な取引や適切な情報管理など、企業の信頼性を保つために守るべきルールを全社員で共有し、徹底することが重要です。
またこの部分には企業のミッション・ビジョン・バリューや、社訓などの説明も含まれます。企業全体の方向性を正しく伝えましょう。
ハラスメント対策と職場環境の改善
職場でのハラスメントを防ぐためには、従業員が以下を理解しておくことが必要不可欠です。
- ハラスメント行為とは何か
- 何がハラスメントに当たるのか
- どんなネガティブな影響があるのか
世間一般としての価値観はもちろん、企業内での明確なルールを設けたうえで研修で伝えましょう。これにより「従業員の定着」「採用強化」などにつながります。
不正行為や虚偽申告への対策
企業内で発生する不正行為や虚偽申告は、重大なコンプライアンス違反です。これを防ぐために、研修では内部統制の重要性や、違反行為が発覚した際の対応方法について教育する必要があります。
またこのほか「不正行為を防ぐためのルール、環境づくり」も大切です。例えば社内データを社外に持ち出せないよう、明確に権限設定するなどのガバナンスを強化しておきましょう。
現代企業に必要なトラブル防止策
現代企業が直面するリスクの一つとして、SNSやメディアの対応が挙げられます。これらのメディアが企業の評判に与える影響は大きく、適切な対応を学ぶことが必要です。
SNSの適切な利用と炎上防止
SNSは企業にとって強力なマーケティングツールである一方で、ブランド毀損のリスクもあります。従業員による不適切な情報発信により企業が批判を受け、炎上するリスクにも注意してください。
- コンプライアンス研修で取り扱うべき主な内容は、以下の通りです。SNSの適切な利用方法
- リスク管理
- 炎上を防ぐための対応策投稿のNG例
- 炎上した際の対応
従業員が「こういう場合はどうしたらよいか」など、課題や対策を話し合うきっかけにもなります。自発的な自衛を促進するためにも、研修には力を入れましょう。
メディア対応と企業イメージ管理
特に広報・マーケティング部においてメディア対応はコンプライアンスの面で重要です。
誤解を招く発言、誤報によって企業のイメージに大きな打撃を与える可能性があります。コンプライアンス研修を通じて、危機管理やメディア対応の基本を伝え、企業イメージを守るためのスキルを周知しましょう。
自社に合ったコンプライアンス研修のネタを探す方法
コンプライアンス研修のネタを選ぶ際には、できるだけ自社特有のものにカスタマイズする必要があります。たとえば事例を探す際にも、極力同じ業界のものを選びましょう。
ここでは、自社にマッチする事例を選ぶ方法をお伝えします。
省庁・関連団体の違反事例から探す
自社に適したコンプライアンス研修のテーマを見つける方法として、まず省庁や関連団体が発表している違反事例に目を向けることが有効です。
厚生労働省や金融庁などが公開している過去の違反事例や法改正の情報を参考に、自社の研修の事例として紹介しましょう。
例えば厚生労働省では「長時間労働削減に向けた取組」のページで、労働基準関係法令違反に係る公表事案を公表しています。こうした行政の資料をもとにして、原因と対策を資料化することができます。
参考:厚生労働省「労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和5年9月1日~令和6年8月31日公表分)」
同業他社の違反事例から探す
自社と同じ業種の企業で違反事例を絞ることも有用です。
例えばメディア業界、ヘルスケア業界でいうと、DeNA株式会社の「WELQ問題」は代表的な例です。また保険業界だと「日本郵政グループ」の顧客情報の不正利用は、記憶に新しいことでしょう。
このように、自社と同じ業界で検索することで、コンプライアンス違反の事例を収集するのも、手段のひとつです。
研修講師・コンサルタントに相談する
社内で適切な研修資料を作成できない場合は、コンプライアンス研修の専門家である研修講師やコンサルタントに相談してみましょう。
専門家は多様な業界や企業の研修事例に精通しており、自社の業界特有のリスクに応じたテーマの提案が可能です。
また、最新の法規制の動向や企業倫理に関するアドバイスを受けることで、時代に合った研修内容を構築できます。
コンプライアンス研修の実施方法
コンプライアンス研修を効果的に実施するためには、企業のニーズや社員の特性に合わせた方法を選択することが重要です。
学習効果や、研修の実施工数、参加者数を加味したうえで、適切な方法を選びましょう。
対面での研修
対面でのコンプライアンス研修は、リアルタイムでの対話やフィードバックが可能であることが利点です。受講者の理解度をその場で確認できます。
またディスカッションやグループワークを取り入れることが可能です。受講者が自ら考え、作業を行うことで知識を深く学べる方式だといえるでしょう。
さらに、対面研修は社内のコミュニケーション促進にもつながります。例えば企業理念についてチームごとにディスカッションしてもらい「実務にどう生かすか」を具体的に定めることが可能です。
eラーニングやオンライン研修
eラーニングだと録画されている教材をいつ、どこにいても確認できます。特に多拠点展開している企業やリモートワークを取り入れている企業にとっては有効な方法です。
ただし他社の目がないので、従業員によっては「集中して視聴できない」「視聴していないが、虚偽の報告をしてしまう」などの問題が起きる可能性があります。
「本当に受講したか」を確認するとともに、テストなどを設けて理解度を確認しましょう。
オンライン研修は、ZOOMなどでリアルタイム開催する方法です。拠点が多く、一カ所に集まれない企業などで有効な方法といえます。
コンプライアンス研修の効果を高めるポイント
コンプライアンス研修は、単に実施するだけではなく、その効果を最大限に引き出すために工夫が必要です。
ここでは、コンプライアンス研修の効果を高めるためのポイントを紹介します。
継続的な研修を行う
コンプライアンス研修は、一度実施するだけでは不十分であり、継続的に行うことが非常に重要です。
法律や規則は時代に合わせて変化していくため、それに伴ってコンプライアンスの内容も更新されていきます。継続的な研修を通じて、最新の法令や規制、業界の動向を常に学べるようにしましょう。
また、一度ではコンプライアンス違反の重要度を理解できません。だんだんと意識が薄れてしまいます。
このようなことを防ぐため、定期的な研修により社員の意識を高め、コンプライアンスに対する理解を深められるようにしてください。
実践的かつ参加型の内容を取り入れる
コンプライアンス研修では、実践的な内容や参加型のアプローチを取り入れるようにしましょう。
例えば、実際の違反事例を基にしたケーススタディや、グループディスカッションを行うことで、受講者が自ら考え、議論を通じて学べます。
また、ロールプレイやシミュレーションを用いて、現場での判断力や適切な対応方法を訓練することも効果的です。
実践的な研修にすることで、座学だけの研修に比べて受講者の興味を引きやすく、学んだことをすぐに業務に活かせます。
マネジメント層が積極的に関与する
コンプライアンス研修の効果を高めるためには、マネジメント層の積極的な関与とサポートが不可欠です。
経営層や管理職がコンプライアンスの重要性を強く訴え、研修への参加を推奨することで、全社的な意識向上につながります。
反対に経営層が関与しないと、研修の重要性が低く感じられ、従業員も本腰を入れて学ぶ姿勢になりません。
さらに、研修後も管理職が社員の業務をモニタリングし、適切なフィードバックを行いましょう。「学んだ内容が定着しているか」「業務に落とし込まれているか」を確認することが重要です。
外部講師や専門家を招く
外部講師やコンプライアンスの専門家を招いて研修を実施することは、最新の法改正や業界特有のリスクに対応するために非常に有効です。
専門家は講習に慣れています。そのため、安心して説明を聞けるほか、参加者を巻き込んだインタラクティブなコンテンツづくりも得意です。
また、外部の視点を取り入れることで、社内では見落としがちなリスクや課題を浮き彫りにすることができ、企業全体のコンプライアンス強化につながります。
外部講師の導入はコストがかかる場合もありますが、専門的な知識や経験を持つ講師の研修は、社員のスキルアップや企業リスクの回避に大きく貢献する投資といえるでしょう。
従業員の階層や部署に応じてカスタマイズする
コンプライアンス研修は、社員の階層や部署ごとにカスタマイズすると、より効果的です。従業員によって、必要なコンプライアンスの知識は違います。
例えば、経営層には「企業全体のリスク管理や法的責任」に関する研修を強化すべきです。一方、一般社員には「日常業務に関連するコンプライアンス事項」にフォーカスした内容が必要といえます。
また一般社員のなかでも、営業部門には「顧客との契約や取引に関する内容」が適しています。IT部門には「情報セキュリティや個人情報保護」が必要です。このように、各部門の業務に直結した内容を研修に盛り込みましょう。
まとめ
今回はコンプライアンス研修について、網羅的に解説しました。コンプライアンス研修は、企業が法令を遵守し、社会的責任を果たすために欠かせない取り組みです。継続的に行うとともに、実践的かつ参加型の内容を取り入れながら、企業全体のコンプラ意識を醸成しましょう。
SNSなどで企業の評判がすぐに広まるようになった現代だからこそ、コンプライアンス研修は必要不可欠なものになっています。
今回紹介した研修テーマを参考にしつつ、企業が健全で持続的な成長を遂げるために、研修を行ってください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録