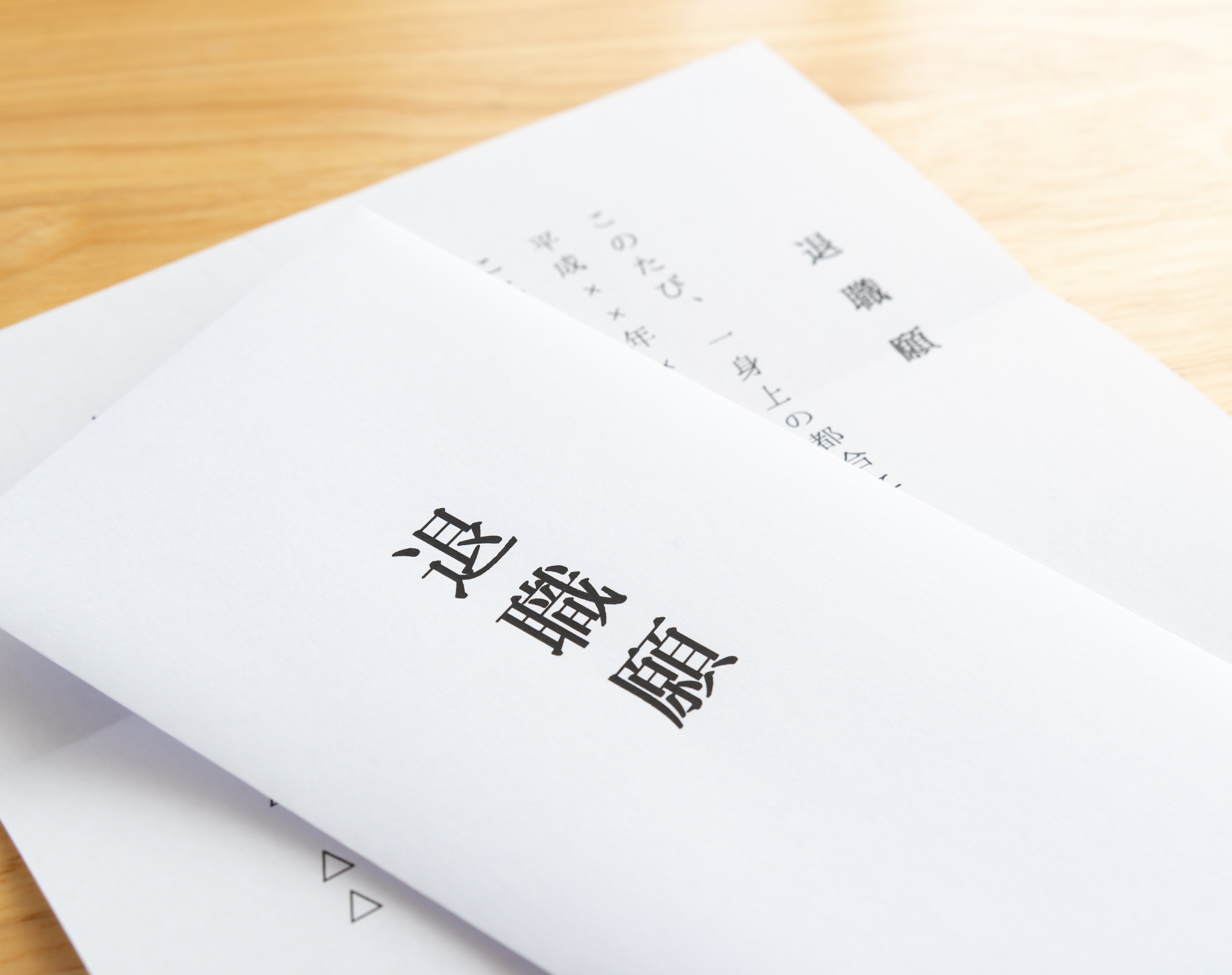就業規則とは?記載内容や中小企業が注意すべき点をわかりやすく解説
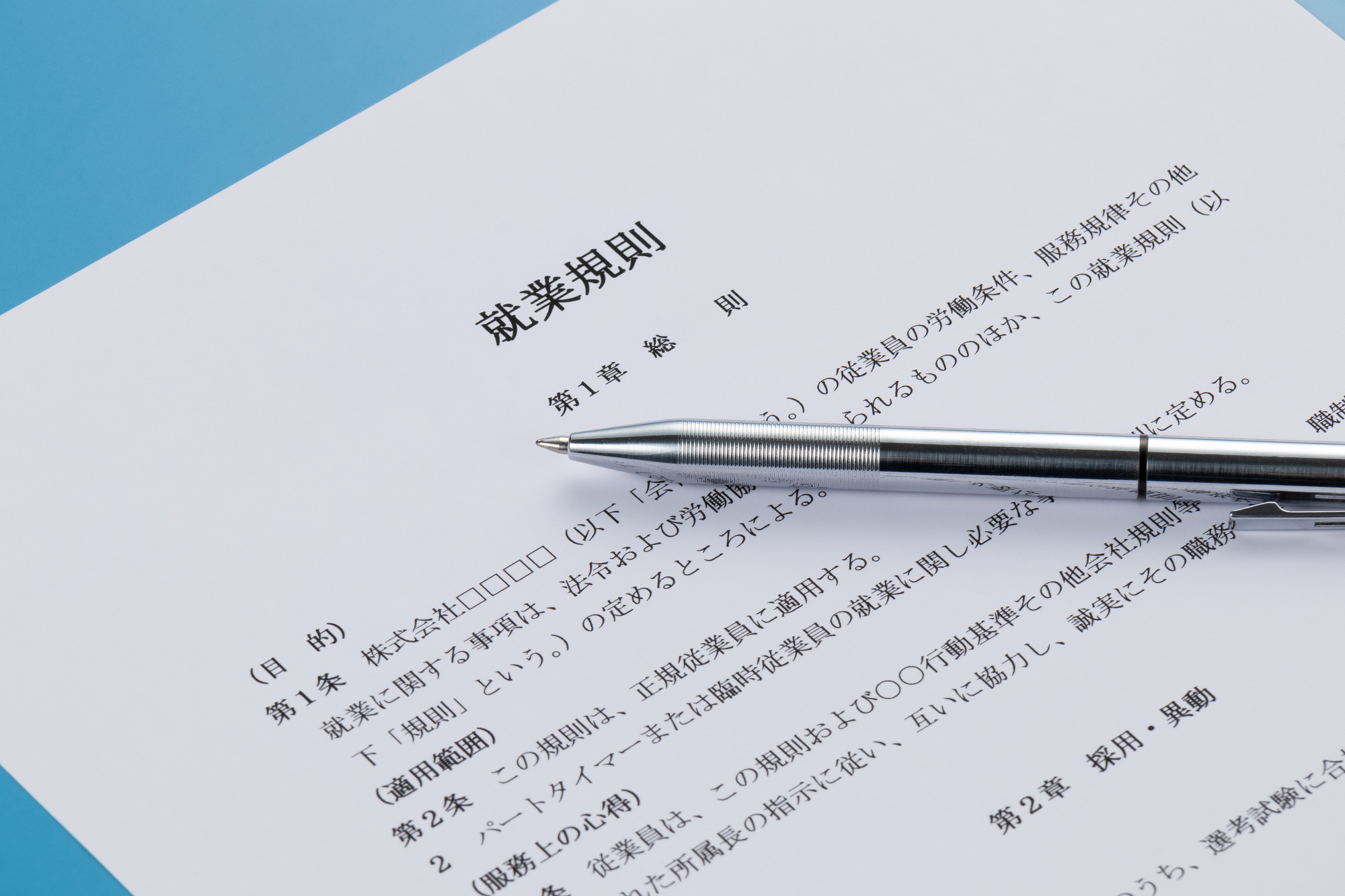
「就業規則=会社のルール」程度に捉え、その潜在的な価値に気づいていない方も多いのではないでしょうか。
就業規則は、ただ「会社が労働者に守らせたいことをまとめたもの」ではありません。
労使間の関係を強化したり、新たな人材確保の機会を得たりするためのツールにもなるのです。
この記事では、就業規則に関する基本的な知識をはじめ、中小企業が注意すべき点、効果的な活用方法などについてわかりやすく解説していきますので、是非参考にしてください。
目次
就業規則に関して抑えておくべき基礎知識
まずは、就業規則に関する基礎知識や、就業規則がないとどのような不都合が生じるのか、といった点について紹介していきます。
就業規則とは
就業規則とは、職場におけるルールや労働条件などについて事業者側が定めた規定の総称です。
就業規則の内容は、労働基準法第89条によって定められており、主に以下のような内容を記載する必要があります。
- 始業時刻と終業時刻
- 休憩時間
- 賃金関連の事項
- 退職関連の事項
- 安全や衛生に関する事項
- 災害補償や業務外でのケガなどに関する事項
就業規則には、必ず記載しなければいけない「絶対的必要記載事項」と、会社独自の制度を実施している場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」、事業者側が任意で記載できる「任意記載事項」の3種類があります。
それぞれの詳細については、後述します。
従業員の人数によっては中小企業も作成必須
就業規則の作成は、大企業だけに課されているものではありません。
常時10人以上の従業員を雇っている場合、中小企業でも作成義務が生じます。
この「常時10人以上」というのは、「常態として」という意味合いがあります。
一時的に10人未満になるようなことがあっても、基本的に10人以上の従業員がいるのならば就業規則の作成は必須です。
なお「従業員」とは、正社員のみを指すのではなく、パートやアルバイト、契約社員なども含まれます。
ただし、直接雇用しているわけではない「派遣社員」は、従業員の定義から除外されることを覚えておきましょう。
就業規則がないとどうなる?
雇用している労働者の人数が常時10人未満であれば、就業規則を作成する義務はありません。
では、作成義務がなければ就業規則は不要なのでしょうか?
結論からお伝えすると、「義務ではなくとも作成すべき」となります。
なぜならば、就業規則が存在することで以下のようなメリットがあるからです。
- 職場内の秩序が守られやすくなる
- 労働関連のトラブルに対して迅速に対応しやすくなる
- 従業員への処分が必要になっても、就業規則で決められたルールに従えばよいため対処しやすくなる
従業員の数が常時10人未満の企業であっても、就業規則を作成して届け出れば、10人以上の企業と同様の効力が発生します。
雇用関連のリスクマネジメントを実施するためにも、企業規模を問わず就業規則は作成しておくべきです。
参考記事:就業規則がない企業は違法?従業員10人以下でも作成すべき理由とリスクを解説
【従業員10人未満の会社向け】就業規則は作成すべき?
従業員が常時10人未満の場合、就業規則の作成・届出義務はありません。しかし、会社のルールを明確にし、労務トラブルを未然に防ぐためには作成が推奨されます。従業員の意欲向上や助成金申請に役立つメリットもあるからです。
作成義務がなくても就業規則を作成するメリット
従業員が10人未満の会社であっても、就業規則を作成することには大きなメリットがあります。作成・届出の法的義務はありませんが、職場の基本的なルールを文書化することで、使用者と従業員双方にとって多くの利点が生まれるからです。
主なメリットは以下のとおりです。
- 労務トラブルの未然防止
労働時間、賃金、休日、服務規律などの労働条件やルールが明確になることで、「言った・言わない」といった不要な誤解や認識の違いを防げます。万が一トラブルが発生した場合でも、就業規則が公正な解決の基準となります。 - 従業員の意欲向上と定着率アップ
働く上でのルールや待遇が明確であれば、従業員は安心して業務に集中できます。公平な評価や処遇の基準が示されることで、モチベーションの向上につながり、結果として優秀な人材の定着にも貢献できるのです。 - ハラスメントなどへの明確な対応
職場のハラスメント防止規定や懲戒に関する規定を設けることで、問題行動に対する会社の毅然とした姿勢を示せます。これにより、健全な職場環境の維持が期待できるのです。 - 助成金の申請要件を満たせる
国が提供する各種助成金の中には、就業規則の整備が申請の要件となっている場合があります。将来的に助成金の活用を検討する際にも、あらかじめ整備しておくとスムーズです。
このように、就業規則は会社の秩序維持だけでなく、従業員の働きやすさや会社の成長を支える基盤となります。
10人未満の会社が就業規則を作成する場合の簡易的な手順
従業員が10人未満の会社では、就業規則の作成・届出は義務ではありませんが、作成する際も基本的なステップを踏むことが重要です。労働基準監督署への届出は不要ですが、効力を発生させるために、作成したルールを従業員に周知しなければなりません。
簡易的な作成手順は以下のとおりです。
- 記載内容の検討
会社の実態に合わせてどのようなルールが必要かを検討します。
必ず記載すべき「絶対的必要記載事項」に加え、必要に応じて「相対的必要記載事項」を整理します。 - 就業規則案の作成
検討した内容に基づき、就業規則の草案を作成します。法的な観点も必要となるため、可能であれば社会保険労務士などの専門家に相談すると安心です。 - 従業員の意見聴取
作成した就業規則案を従業員に提示し、意見を聴きます。
10人未満の場合は労働者代表の選出や意見書の作成・添付義務まではありませんが、従業員の理解を得て円滑に運用するために、内容を説明し、意見を聞く機会を設けます。 - 従業員への周知
もっとも重要なステップです。作成した就業規則は、従業員に周知して初めて効力を持ちます。
以下の方法で、従業員がいつでも確認できる状態にします。- 見やすい場所(休憩室など)への掲示
- 従業員一人ひとりへの書面での交付
- 社内イントラネットや共有フォルダなど、PCなどで常時閲覧できる状態にする
参考記事:【これを読めばOK】就業規則の変更手続きを徹底解説!従業員10人未満でも必要?
就業規則にまつわる労務トラブル
就業規則の不備や運用ミスは、深刻な労務トラブルに直結します。特に懲戒規定の運用や、従業員への周知を怠った場合、解雇の有効性や規則自体の効力が争われるケースは少なくありません。
懲戒規定を定める際の注意点と処分の種類
懲戒規定は、従業員が企業秩序に違反した場合のペナルティを定めるもので、労務トラブルに発展しやすい項目の一つです。規定を設ける際は、その内容と運用に細心の注意が必要です。
懲戒処分の種類
就業規則に懲戒規定を定める際に使用される主な懲戒処分は以下になります。
| 懲戒処分の種類 | 内容 |
| 譴責(けんせき) | 始末書を提出させ、将来を戒める |
| 減給 | 本来支給されるべき賃金から一定額を差し引く※1回の減給額は平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない(労働基準法第91条) |
| 出勤停止 | 一定期間の出勤を禁止し、その間の賃金は支払わない |
| 降格 | 役職や職位を引き下げる |
| 諭旨解雇 | 解雇事由に該当するが、情状酌量の余地がある場合に退職を勧告し、応じない場合に解雇する |
| 懲戒解雇 | 即時に雇用契約を解除し、退職金の全部または一部を不支給とすることもある |
懲戒規定を定める際の注意点
- 罪刑法定主義の原則
就業規則に懲戒の種類と事由をあらかじめ具体的に明記しておかなければ、懲戒処分はおこなえません。「どのような行為が、どの処分に該当するのか」を明確に定めておく必要があります。 - 懲戒権の濫用に注意
処分する際は、以下が問われます。- 違反行為の重大性に対して処分が重すぎないか(相当性の原則)
- ほかの同様の事例と比べて公平か(平等取り扱いの原則)
- 弁明の機会を与えたか(適正手続き)
これらを欠くと懲戒権の濫用として処分が無効になる可能性があります。
従業員から「就業規則はどこで見られますか?」と聞かれた際の正しい対応
従業員から「就業規則を見たい」と尋ねられた場合、企業は速やかに閲覧できる状態にしなければなりません。
就業規則は、従業員が10人以上の場合、作成・届出するだけでなく、従業員に周知することが労働基準法第106条で義務付けられています。
この「周知」とは、従業員がいつでも好きな時に就業規則の内容を確認できる状態にしておくことを意味します。
正しい対応としては、具体的な閲覧場所や方法を即座に案内することです。 もし「見せる必要はない」「上司の許可が必要」といった対応をとったり、保管場所がわからずすぐに提示できなかったりした場合、周知義務違反とみなされる可能性があります。
周知義務を怠ると、就業規則自体の効力が認められないリスクがあるため、日頃から周知を徹底しておくことが重要です。
就業規則に記載する内容
就業規則として記載するものは、以下の3種類となります。
- 絶対的必要記載事項
- 相対的必要記載事項
- 任意記載事項
なお就業規則の内容は、各企業が自由に決めていいわけではありません。
| 就業規則は、法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条)。 |
出典)厚生労働省 「1 就業規則に記載する事項 2 就業規則の効力 」p.1
労働基準法などの法律に抵触する就業規則はすべて無効となりますので、留意しておきましょう。
1.絶対的必要記載事項
絶対的必要記載事項とは、企業規模を問わず、例外なく必ず記載しなければならない内容のことです。
以下の3つが、絶対的必要記載事項に該当します。
| 労働時間関連 | ■「1日8時間労働」といった曖昧な形ではなく、始業と終業の時刻を明確に記載する ■休憩時間や休日、休暇について明記する ■従業員を交替制で就業させる場合は、就業時転換に関する事項も記載する |
| 賃金関連 | ■どういった規定に沿って賃金が決まるかを示す ■賃金の計算方法や支払い方法を規定する ■昇給の条件や昇給率を提示する |
| 退職関連 | ■定年・辞職・双方の合意による退職などの一般的な退職について規定する ■使用者側による解雇(懲戒解雇や普通解雇)の基準を明記する |
2.相対的必要記載事項
相対的必要記載事項とは、その企業固有の制度を実施している場合に、必ず記載しなければならない内容のことです。
独自制度を実施するかは各企業の自由ではあるものの、実施している場合は記載が義務付けられます。
相対的必要記載事項の例としては、以下のようなものがあります。
- 退職手当が適用される範囲や計算方法
- ボーナスに関する内容
- 食費や作業用品を労働者に負担させる際の規定
- 職業訓練に関する内容
- 表彰や制裁に関する内容
独自の取り組みを行っている場合は、忘れずに就業規則へ記載するようにしてください。
3.任意記載事項
任意記載事項とは、「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」以外に、企業として規定しておきたい内容を記載できるものを指します。
どういった内容を記載するかについての決まりはありません。自由に記載することができます。ただし、法令に反するような内容は認められません。
就業規則の作り方とサンプル
就業規則は、会社の基本的なルールブックであり、労働条件や従業員が守るべき規律を明文化したものです。法律で定められた基準を満たしつつ、自社の実態に合った内容を盛り込むことが重要です。
就業規則作成の基本的なステップ
- 現状の把握と記載事項の整理
自社の労働時間、休日、賃金体系などの現状を整理します。その上で、法律で必ず記載すべき「絶対的必要記載事項」と、社内でルールを設ける場合に記載が必要な「相対的必要記載事項」を洗い出します。 - 就業規則(案)の作成
整理した内容に基づき、条文を作成します。初めて作成する場合は、厚生労働省が提供している「モデル就業規則」をたたき台にするのが効率的です。 - 従業員代表の意見聴取
従業員10人以上の場合は、作成した(案)を労働者の過半数代表者または労働組合に提示し、意見を聴きます。その内容を「意見書」として書面にまとめてもらう必要があります。 - 届出と周知
従業員10人以上の場合、以下の3点を所轄の労働基準監督署に届け出ます。
- 就業規則(変更)届
- 意見書
- 作成した就業規則
もっとも重要なのは周知です。届出の有無にかかわらず、社内の見やすい場所への掲示、書面での配布、社内イントラネットへの掲載などにより、全従業員がいつでも確認できる状態にしなければ効力が発生しません。
就業規則の記載事項(サンプル)
以下は、モデル就業規則を参考にした一般的な記載事項の構成例です。
第1章:総則(目的、適用範囲など)
第2章:採用・異動等
第3章:服務規律(従業員が守るべきルール)
第4章:労働時間、休憩、休日、休暇
第5章:賃金(給与体系、手当、賞与など)
第6章:退職・解雇
第7章:安全衛生・ハラスメント防止
第8章:懲戒(違反行為に対する処分)
第9章:その他(育児・介護休業など)
自社に必要な項目を取捨選択し、法的な要件を満たしているか確認しながら作成を進めましょう。
就業規則の作成・見直しにお困りではありませんか?解説した内容を実務で使える、中小企業向けの「汎用的な就業規則テンプレート」をご用意しました。Word形式で自由に編集可能です。以下より無料でダウンロードし、貴社の労務環境整備にお役立てください。
中小企業が就業規則を作成する際に注意すべき点
中小企業が就業規則を作成する際、特に注意すべきなのは以下の3点です。
- 記載すべき内容は大企業と同じ
- 厚生労働省のモデル就業規則を鵜呑みにしない
- 就業規則の一方的な不利益変更は認められない
1.記載すべき内容は大企業と同じ
「自社は規模が小さいから、就業規則の内容も少量で問題ないだろう」と考える中小企業の経営層の方もいるかもしれません。しかし、それは大きな間違いです。
もちろん、大企業に比べればシンプルな就業規則になることが多い傾向にあるものの、就業規則は労働基準法第89条に則る必要があります。
したがって、大企業でも中小企業でも、記載しなければいけない項目の数に差異はないのです。
一概に、「中小企業だから就業規則に記載する量は少なくなる」というわけではない点に注意してください。
2.厚生労働省の「モデル就業規則」の内容を鵜呑みにしない
厚生労働省は、就業規則を作成する際のテンプレートとして、「モデル就業規則」を公開しており、誰でも閲覧やダウンロードができる状態になっています。
しかし、モデル就業規則は主に大企業を想定して作成されているため、中小企業の就業規則としては適切ではない項目も少なくありません。
たとえば、モデル就業規則の第5章では、「育児休暇」「生理休暇」「慶弔休暇」「病気休暇」「裁判員等のための休暇」など、様々な種類の休暇が記載されています。
これらの手厚い福利厚生に関する規定は、労働基準法等によって定められている法定休暇の範囲を超えるものです。
資本に余裕のある大企業ならば、上記のような充実した福利厚生を実現できるかもしれません。しかし、中小企業の場合は対応が難しいこともあるでしょう。
このように、モデル就業規則に記載されている項目は、中小企業にマッチしていないものもあります。
その他、「各業界特有の規定までは考慮されていない」といった問題もあるため、自社の規模や事業に適した形へカスタマイズすることが必須です。
参考記事:モデル就業規則とは?全14章を徹底解説!中小企業向けカスタマイズ方法も紹介
3.就業規則の一方的な不利益変更は認められない
就業規則は、法改正などに合わせて定期的に見直しを行う必要があります。
その際、不利益変更(従業員にとって不利な内容への変更)は原則的に認められません。
ワンマン経営になっている中小企業の場合、従業員の意思を尊重したり話し合ったりせず、経営者が独断で就業規則を変更してしまうこともあります。とはいえ、不利益変更が含まれている場合は無効となるケースも多いので注意が必要です。
ただし、すべての不利益変更が無効かというと、そうではありません。
厚生労働省も、以下のように述べています。
| 「労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性格からいって、当該規則各項が合理的であるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない」と解されています(秋北バス事件、最高裁昭和43年)。 |
出典)厚生労働省「就業規則の不利益変更は許されるか」p.1
原則として不利益変更は認められないものの、上記の通り「合理的な理由がある」と判断されれば、不利益変更のあった就業規則も有効となります。
なお、「合理的な理由」の例としては以下のようなものがあります。
- 労働組合の合意がある
- 従業員の大多数による合意がある
- 不利益の程度が許容される範囲である
- 企業として変更の必要性が高い
就業規則の変更手続きの流れと変更届のポイント
就業規則は、一度作成すれば終わりというものではありません。法改正への対応や、会社の経営状況、働き方の変化に合わせて、内容は随時見直し、変更していく必要があります。
ただし、就業規則の変更は、会社が一方的におこなえるものではなく、法律で定められた厳格な手続きを踏まなければなりません。
手続きを怠ると、変更した規則が無効と判断されるリスクもあります。ここでは、就業規則の変更手続きの基本的な流れと、特に注意が必要な「不利益変更」について解説します。
参考)厚生労働省「就業規則の変更はどのように行えばよいのでしょうか。」
就業規則変更の基本的な4ステップ
就業規則の変更は、従業員が常時10人以上の事業場の場合、以下の4つのステップで進めるのが基本です。10人未満の事業場では「労働基準監督署への届出」は不要です。
- 変更内容の検討・変更案の作成
法改正への対応や、社内の実情に基づき、どの部分をどのように変更するかを検討し、就業規則の変更案を作成します。 - 労働者代表の意見聴取
変更案が固まったら、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者を選出し、その人から変更案に対する意見を聴かなければなりません。
この手続きは、変更内容について「同意」を得ることまでを義務付けるものではなく、あくまで「意見を聴く」義務です。
労働者代表から反対意見が出た場合でも、その意見を記載した「意見書」を添付して届出を行えば、手続きとしては有効です。
ただし、後述する「不利益変更」の場合は、意見聴取とは別に、原則として労働者の「合意」が必要になります。 - 労働基準監督署への届出
「就業規則(変更)届」に、変更後の就業規則、および労働者代表の「意見書」を添付して、所轄の労働基準監督署長に届け出ます。意見書には、労働者代表の署名または記名押印が必要です。 - 従業員への周知
変更後の就業規則は、届出だけでは効力が発生せず、従業員に周知して初めて有効となります。
「不利益変更」をおこなう場合の注意点
就業規則の変更のうち、休日を減らす、基本給を引き下げる、手当を廃止するなど、従業員にとって労働条件が不利になる変更を「不利益変更」と呼びます。 不利益変更は、通常の変更よりもさらに慎重な手続きが求められます。
労働契約法第9条により、就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更する場合、原則として、会社は従業員と個別に合意しなければなりません。単に労働者代表の意見を聴いただけでは、不利益変更は認められないのです。
とはいえ、経営上の理由などから、全従業員の個別の合意を得ることが難しい場合もあります。 労働契約法第10条では、例外として、以下の2つの要件を両方満たせば、個別の合意がなくても変更後の就業規則が適用されるとしています。
- 変更後の就業規則を従業員に「周知」させること
- 就業規則の変更が「合理的」であること
この「合理性」は、単に会社に都合がよいというだけでは認められず、裁判などになった場合は以下の要素から総合的に判断されます。
- 従業員が受ける不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性(経営悪化の深刻度など)
- 変更後の就業規則の内容の相当性(不利益を緩和する代替措置があるかなど)
- 労働組合などとの交渉の状況
- その他の事情
不利益変更は、労務トラブル最大の火種となることがあります。変更の必要性を従業員に丁寧に説明し、理解を得る努力を尽くすことが不可欠です。
就業規則変更届と意見書のポイント
従業員10人以上の事業場が変更届を提出する際、特に「意見書」の取り扱いがポイントとなります。
労働基準法が求めるのは「意見を聴くこと」です。たとえ労働者代表が変更内容に「反対」と意見書に記載したとしても、その意見書を添付して届け出れば、法的な手続きは完了します。
もし労働者代表が意見書の作成自体を拒否した場合は、意見聴取を行った経緯を報告書としてまとめ、それを添付して届け出る対応もできるのです。
「就業規則(変更)届」は、決まった様式はありませんが、厚生労働省のウェブサイトなどで様式例が提供されています。
届出の際は、変更後の就業規則全文を提出するのが原則ですが、どこが変更されたのかを明確にするため「新旧対照表」を添付すると、労働基準監督署の確認もスムーズになります。
就業規則は「企業の守備力を高めるツール」となり得る
これまで解説してきた通り、就業規則は「雇用関連のトラブルを未然に防ぎ、職場の秩序を守る」という目的で作成されることがほとんどです。
つまり、リスクマネジメントの側面が非常に強いと言えます。
しかし、就業規則作成の目的をリスクマネジメントのみに留めてしまうのはもったいないです。
なぜならば、就業規則を上手く活用することで、人手不足というリスクを解消する「企業の守備力を高めるツール」となり得るからです。
中小企業の人手不足は深刻な状態
現在の日本では、少子高齢化の影響により、多くの企業が深刻な人手不足の状態に陥っています。
実際、2024年に日本商工会議所が2,000社以上の中小企業を対象に「人手不足の状況」について調査したところ、63%もの中小企業が「人手が不足している」と回答しました。
このことからも、企業にとって人材確保は大変重要な課題であることがわかります。
就業規則は活用方法次第で人材確保ツールと化す
そこで注目すべきなのが、就業規則です。
就業規則の内容が魅力的なものであれば、求職者からは強い興味を持たれますし、従業員の離職率も下がります。
また、従業員が自社の魅力を周囲に伝えることで、最近注目を集めている「リファラル採用」にも繋がります。
リファラル採用とは、自社の従業員や取引先などから、知人や友人を紹介してもらい採用につなげる、という手法のことです。
「採用のミスマッチが発生しづらい」「採用コストが抑えられる」など多くのメリットがあるため、最近ではリファラル採用に力を入れる企業も増えています。
このように、就業規則を活用することで、人手不足を解消するための人材確保ツールに昇華させることもできるのです。
どうすれば「人材が集まる就業規則」を作れるか
就業規則の価値は理解できたものの、具体的に何をすればいいのかわからない、というケースもあるでしょう。
しかし、難しく捉える必要はありません。
「従業員と真摯に向き合う」だけでいいのです。
まず、従業員へのヒアリングを徹底し、「働く側が何を求めているのか」を追求しましょう。
場合によっては、経営者自らが時間を取り、1 on 1形式で従業員一人ひとりの意見を聞くのも大変有効です。
大企業とは違い、こうしたフレキシブルな対応ができるのも中小企業の強みだと言えます。
そして、ヒアリングから見えてきたニーズを拾い上げ、就業規則に反映させていくのです。
魅力的な就業規則の例
魅力的な就業規則を作り上げるためには、ニーズに沿った内容を就業規則の中に盛り込んでいきます。
具体的な例としては以下の通りです。
| ヒアリングによって判明したニーズ | 就業規則に盛り込むべき内容 |
| 副業で収入を増やしたい | ■可能な限り柔軟に副業を許可する ■副業を支援・促進するための取り組みを実施する |
| お金よりも時間を大切にしたい | ■週休3日制を導入する ■休暇を取りやすくする |
| 家族の面倒をみるために自宅で仕事をしたい | ■在宅ワークがしやすい環境を作る ■育児休暇や介護休暇などの制度を充実させる |
当然、企業規模によってできることとできないことがあるかと思われます。
しかし、優秀な人材を確保するための採用コストの一環だと割り切り、思い切った対応に踏み出すことも重要です。
まとめ
就業規則は、雇用に関するリスクマネジメントにおいて欠かせないものです。
企業規模によっては作成義務がないものの、必ず作成するようにしましょう。
また、就業規則の作り方次第では、従業員の定着率向上や新たな人材獲得に繋げることも可能となるため、「人手不足」というリスクも回避できます。
企業にとって、「守り」こそが重要な今の時代。
雇用における様々なリスクを潰していくためにも、できる限りの時間と労力を費やし、隙のない、かつ魅力のある就業規則に仕上がるよう最善の努力をしてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録