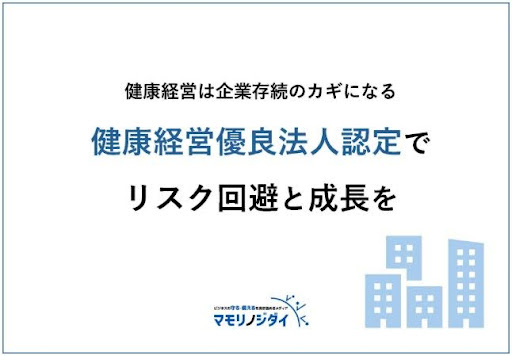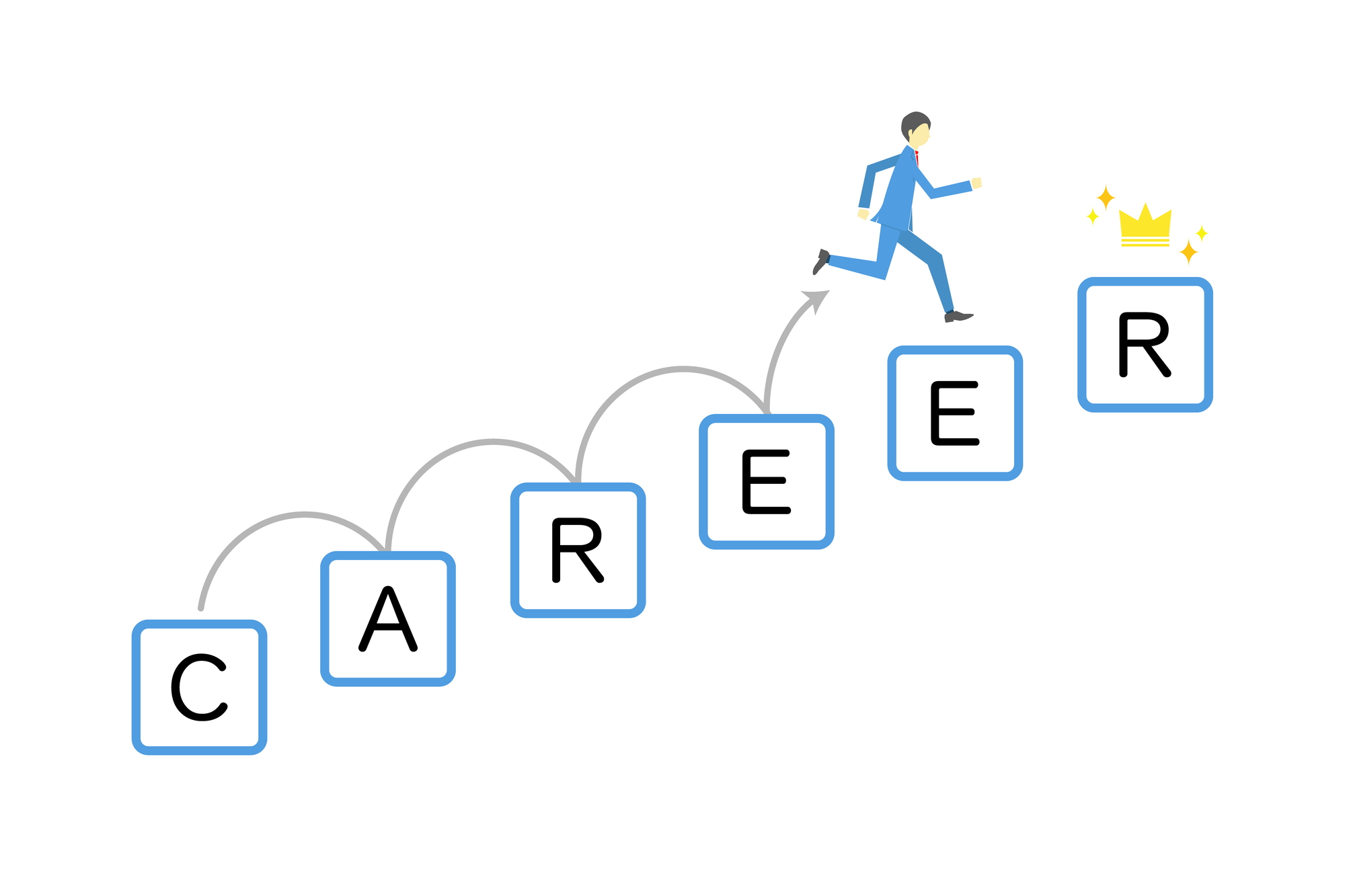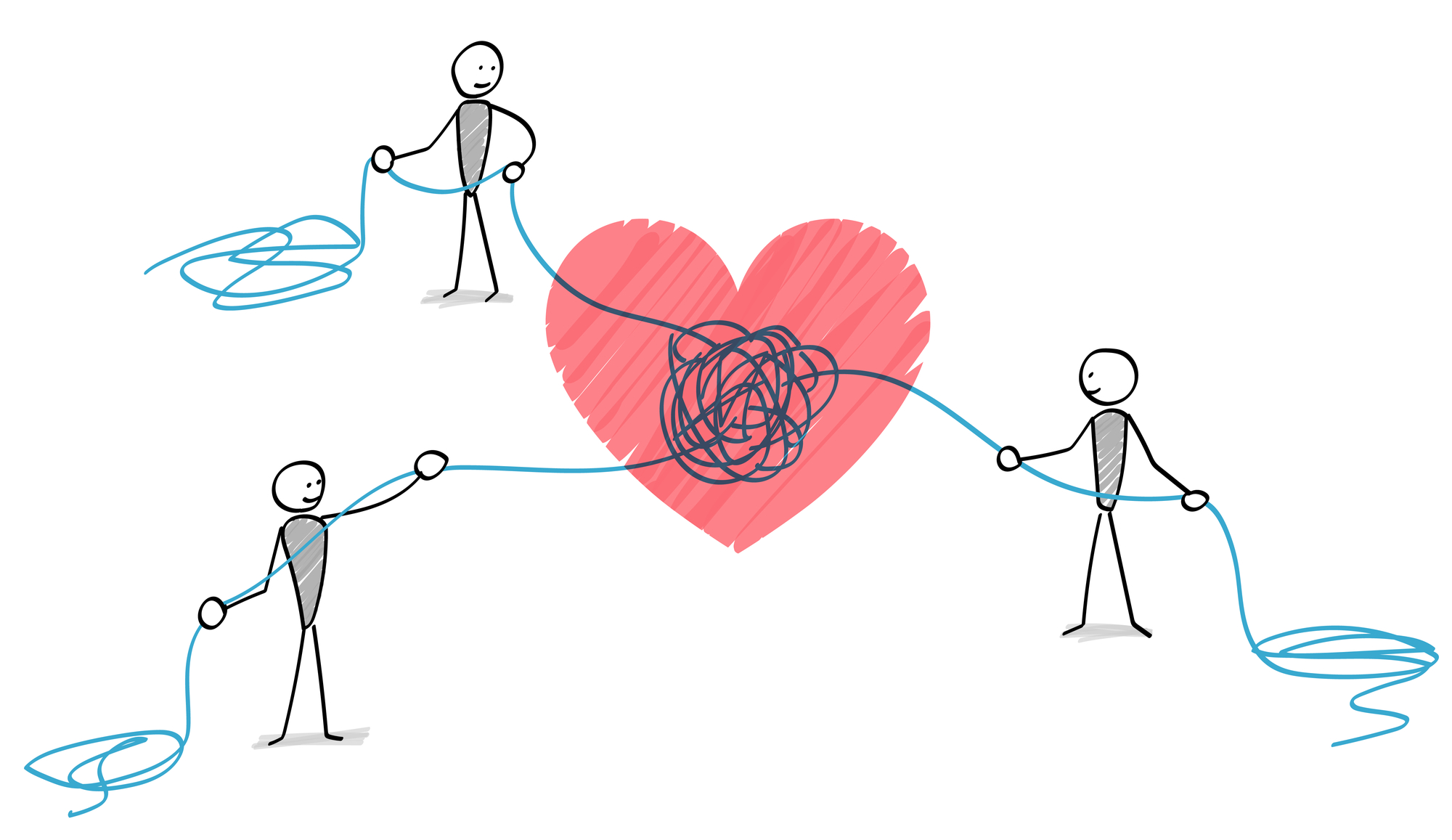ストレスチェックで職場の健康を守る!中小企業で義務化になった点など

近年、注目されているのが「職場でのメンタルヘルス対策」です。特に中小企業では、従業員の心の健康が会社の成長に直結するため、効果的な対策が求められています。
そんな中、注目を集めているのが「ストレスチェック制度」です。
この記事では、ストレスチェックの基本から実践的な導入方法まで、中小企業の経営者やマネージャーの皆さまにわかりやすく解説していきます。
目次
ストレスチェックとは
ストレスチェックは、従業員の心理的な負担の程度を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐために実施される検査制度です。
この制度の目的は、従業員が自身のストレス状態に気づき、メンタルヘルスケアに取り組むきっかけを作ることです。また、職場環境の改善につなげることで、働きやすい職場づくりを進めることも狙いに含まれます。
ストレスチェックの対象領域は「職場におけるストレス要因」「心身の自覚症状」「周囲のサポート状況」の3つです。厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」に基づくことが一般的です。
なお、ストレスチェックの結果は、従業員の重要な個人情報として扱われます。本人の同意なく事業者に提供することは禁止されており、実施者には守秘義務が課せられているため注意が必要です。
常時50人以上の従業員がいる企業は実施が義務!
2014年6月25日に交付された労働安全衛生法の改正によって「常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して、年1回以上のストレスチェック実施」が義務付けられました。
対象となる「労働者」には、正社員だけでなく、パートタイム労働者や契約社員なども含まれます。ただし、契約期間が1年未満の労働者や、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者は、義務の対象外です。
出典)厚生労働省「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」p1
出典)e-GOV「労働安全衛生法 第六十六の十」
また2024年9月30日の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」で、厚生労働省は従業員50人未満の事業所も義務とする方針を発表しました。今後、法令が整備され次第で規模問わず、すべての企業で実施が必須となる予定です。
出典)厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第7回資料」
ストレスチェックは、従業員の健康管理や働きやすい職場づくりのための重要なツールとして位置づけられています。今後は従業員50人未満の企業も導入を進めましょう。
ストレスチェックは中小企業にとってメリットばかり
ストレスチェックは単なる義務ではなく、中小企業にとって多くのメリットがある仕組みです。企業の安定した経営にもつながるため、積極的に活用することが求められます。
以下に、ストレスチェックの主なメリットを整理しました。
| 項目 | 簡単な説明 |
| 従業員のパフォーマンス向上 | ストレスを早期に把握し、適切な対応を取る。従業員が健康的に働ける環境を整備し、生産性向上につながる。 |
| 離職や休職リスクの軽減 | 高ストレス状態を事前に検知し、適切なフォローを行う。メンタルヘルス不調による離職や休職を防ぐ。 |
| 労働災害や法令違反を未然に防ぐ | メンタル不調による労働災害や、過重労働による法令違反のリスクを回避できる。 |
| 職場環境の改善に繋がるデータ収集 | 定期的なストレスチェックを実施することで、組織全体のストレス要因を分析できる。より良い職場環境を整えるための改善策を打ち出せる。 |
| 信頼される企業イメージの構築 | 従業員の健康管理に積極的に取り組むことで、「従業員を大切にする会社」として、採用や取引先からの信頼を獲得できる。 |
ストレスチェックを導入することで、職場の問題を可視化し、従業員が安心して働ける環境を整えられます。
また、企業のブランディングにも大きな影響を与える要素です。従業員の健康を重視する会社は、採用市場で有利になるとともに、取引先・顧客の信頼獲得につながります。
中小企業にとって、ストレスチェックは従業員の健康を守るだけでなく、企業価値を向上させる重要な施策の一つです。
特にこんな職場はストレスチェックが必須!
ストレスチェックは従業員50名以上の企業に義務付けられています。しかし、50人以下の企業でも、職場環境によっては積極的に導入すべきです。
特に以下のような職場では、従業員の健康を守り、企業としての安定経営を実現するために、早期にストレスチェックを導入しましょう。
| 項目 | 簡単な説明 |
| 業務量が過剰で残業が多い | 長時間労働が続くと、心身の疲労が蓄積し、メンタルヘルスの不調につながる。過労による生産性低下や離職リスクの増大を防ぐためにも、ストレスの把握が重要。 |
| 上司や同僚とのコミュニケーション不足 | 相談できる相手がいない職場では、ストレスを抱え込みやすくなる。職場内の人間関係が希薄だと、メンタル不調が悪化しても気づかれにくく、早期対応が難しい。 |
| 人員不足で休暇が取りづらい | 休日が確保できない職場では、心身のリフレッシュができず、ストレスが慢性化する。適切な労務管理が行われなければ、過労による離職や労働トラブルのリスクが高まる。 |
| 組織の目標が曖昧で不安が多い | 会社の方向性が不透明だと、従業員は「何を基準に仕事をすればいいのか」が分からず、不安を感じる。不明瞭な経営方針は、モチベーションの低下にもつながる。 |
| ハラスメントやパワーバランスの不均衡 | 上司や特定の従業員からの圧力が強い職場では、精神的負担が大きくなる。ハラスメントの放置は、企業の信頼失墜や訴訟リスクを招く要因にもなる。 |
ストレスチェックを行うことで「従業員に与えているメンタル面でのストレス状況」を可視化できます。
しかし、ストレスチェックだけで問題が解決するわけではありません。根本的な課題として、企業として「守り=労働環境の整備」に本気で取り組むことが必要です。
ストレスを感じにくい職場をつくるために、主に以下の点に取り組みましょう。
- 業務量の適正化
- コミュニケーションの活性化
- 適切な人員配置
- 明確な目標設定
- ハラスメント対策の強化
特に中小企業では、リソースが限られているからこそ、社員一人ひとりの健康とモチベーションを維持することが、事業の成長に直結します。
ストレスチェックはもちろん重要ですが、職場の現状を把握し、適切な労働環境を整えることが企業の守りを整備するために必要です。
【はじめての方へ】ストレスチェックを導入する流れ
ストレスチェックの導入は、計画的に進めることが重要です。以下、導入から実施までの具体的な流れを解説します。
厚生労働省のガイドラインに基づき、ストレスチェックの導入手順を8つのステップにまとめました。
- 導入前の準備
- 調査票の配布・記入
- ストレス状況の評価・面接指導の要否判断
- 本人に結果を通知
- 本人からの面接指導の申出
- 医師による面接指導の実施
- 就業上の措置の実施
- 集団ごとの集計・分析
出典)厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」
まず「導入前の準備」です。ストレスチェックを実施する目的や方針を明確にし、医師や保健師などの実施者を決定しましょう。
また、調査票の形式や結果の管理方法など、具体的な運用ルールを策定することが重要です。
次に「調査票の配布・記入」に移ります。ストレスの要因や心身の影響を測定する調査票を労働者に配布し、記入を依頼しましょう。
なお、ストレスチェックの受検は義務ではありません。ただし、受検を推奨することが望ましいため、記入を促すようにしてください。
受験が完了したら「ストレス状況の評価・面接指導の要否判断」です。記入された調査票を回収し、ストレスの程度を評価しましょう。
特に「心身のストレス反応」や「周囲のサポート」などの指標を基に、高ストレス者を特定し、必要に応じて面接指導を推奨します。
その後、本人に結果を通知しましょう。結果にはストレスのプロフィールやセルフケアのアドバイスが含まれます。事業者が結果を取得するには本人の同意が必要です。
この後は「本人からの面接指導の申出」が行われる可能性があります。申出は 本人の自由 であり、申出の有無が事業者に通知されることはありません。
その後、対象者には医師(産業医や外部の専門医)が、労働者の勤務状況やストレスの影響を確認し、必要なアドバイスを行ってください。面接指導の結果は「5年間の保存」が推奨されています。
企業としては、労働者と医師の意見を参考にしながら、職場環境や業務内容を調整しましょう。たとえば「業務転換」「労働時間の短縮」「休職措置」などです。
最後に個人のストレス結果を集団ごとに分析し、職場全体のストレス状況を把握します。
中小企業がストレスチェックで気を付けるべきポイント
中小企業にとって、従業員のメンタルヘルス管理は 「守り(ガバナンス)」を強化する重要な施策です。しかし、リソースの制約や従業員の不安を考慮すると、適切な運用が求められます。
「ストレスチェックを実施する際の重要ポイント」を表にまとめました。
| ポイント | 詳細 |
| 外部サービスの活用で手間を軽減 | オンラインツールや外部コンサルを活用し、調査票配布・集計を効率化する。 |
| 結果は匿名で扱い、従業員の信頼を確保 | 結果を匿名管理し、個別データが経営陣に直接伝わらないようにする。 |
| 定期的な実施で効果を高める | 年1回以上の定期実施を行い、継続的な職場改善を意識する。 |
中小企業では、業務負担を軽減しリソースを節約する工夫が必要です。特に、調査票の配布や回収、集計作業は手間がかかります。「外部企業との連携」「オンラインのストレスチェックツールの活用」などを進めましょう。
またストレスチェックの実施において、従業員が最も懸念するのは「結果が自分の評価や待遇に影響するのではないか」という不安です。この不安を払拭し、正直な回答を得るために、結果は匿名で管理しましょう。
さらに、ストレスチェックは一度実施すればそれで終わりではなく、継続的な実施が必要です。
単発のチェックでは、職場のストレス状況の変化を正しく把握できず、問題の早期発見が難しいといえます。年に一回ではなく、定期的なストレスチェックを通じて職場環境の改善を進めましょう。
厚生労働省の無料ストレスチェックソフトも活用できる
ストレスチェックの導入にあたって「ソフトウェアの購入費」や「運用リソース確保」が中小企業にとっての課題です。こうした中小企業の負担を軽減するために、厚生労働省は無料のストレスチェックソフトを提供しています。
出展)厚生労働省「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム ダウンロードサイト」
この無料ソフトは、ストレスチェックの実施から集計、結果のフィードバックまでをオンライン上で簡単に行えるツールです。コストをかけずにストレスチェックツールを導入できます。
社員数100名以下の企業のストレスチェックの導入事例を5つ紹介
中小企業にとってのストレスチェックのメリット、進め方をよりよく理解できるよう、社員数100名以下の企業における、ストレスチェック導入の具体的な事例を紹介します。
健康経営KPI"を定め、受検率アップを達成した事例
ある飼料販売企業(従業員28名)では、健康経営の一環としてストレスチェックを導入しました。
同社は「健康経営KPI」の一つとして「ストレスチェック受検率」を設定。初年度は91.6%だった受検率を、2年目には100%まで向上させることに成功しました。
この成果の背景には「健康で働き続けるために自身のストレス状態を知ることが重要だ」という会社のメッセージがあります。同社は、社内サイトや安全衛生委員会を通じて継続的に発信してきました。
その結果もあり、従業員の健康意識が高まり、全員が受検するようになったそうです。
出典)こころの耳「職場のメンタルヘルス対策の取組事例」
経営者から趣旨を説明し、社員の納得を得た上で実施した事例
ある水道工事会社(従業員15名)では、ストレスチェックの実施に先立ち、経営者自らが従業員に対して制度の意義を丁寧に説明しました。
結果は経営者から「正直に回答してほしい」というメッセージを強調したことが特徴です。また、一人でも受けない人がいては意味がないため、全員の協力を求めました。
このような丁寧な事前説明により、従業員全員の理解と協力を得ることができ、高ストレス者への面談など、その後の対応もスムーズに進めることができました。
結果として、職場のメンタルヘルス対策の仕組みづくりから、心の健康づくり計画の策定まで、包括的な取り組みへと発展させることができています。
出典)こころの耳「職場のメンタルヘルス対策の取組事例」
ストレスチェックの結果を踏まえて、設備投資を実施した事例
ある金属工業会社(従業員82名)では、2017年度のストレスチェックで高ストレス者の割合が20%と高水準であることが判明しました。
分析の結果、「身体的負担」と「職場環境」が主なストレス要因と特定したそうです。これにより、具体的な環境改善に着手しました。
工場棟と事務棟の屋根と外壁に遮熱塗料を塗布し、水銀灯をLED照明に交換。さらに冷暖房設備を導入するなど、大規模な設備投資を実施しました。
その結果、高ストレス者の割合は2019年度に12%、2020年度には6.2%まで減少。職場環境の改善が従業員のストレス軽減に直接的な効果をもたらした好例となっています。
出典)こころの耳「職場のメンタルヘルス対策の取組事例」
ストレスチェックの項目を工夫し、要支援者を見極めた事例
ある製造業の企業(従業員95名)では、厚生労働省の調査票をベースに、独自の質問項目を追加してストレスチェックを実施しています。
具体的には、職場での人間関係や仕事の満足度に関する項目を充実させました。この工夫により、数値上は高ストレスと判定されない場合でも、支援が必要な従業員を早期に発見できるようになったそうです。
また、結果を部署ごとに分析し、各部署に共通するストレス要因を特定し、改善することができています。
出典)こころの耳「職場のメンタルヘルス対策の取組事例」
健康診断結果と一緒にフォローすることで配慮を行った事例
ある小売業の企業(従業員65名)では、ストレスチェックと定期健康診断の結果を総合的に分析し、心身両面からの健康管理を実施しています。
特に、ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員については、健康診断の結果も考慮しながら、産業医との面談を設定しました。
このアプローチにより「メンタルの不調が身体症状として現れている」「身体の不調がストレスになっている」など、状況に応じたフォローが可能になっています。また、産業医からの助言を基に、勤務時間の調整や業務内容の見直しなどを進めているそうです。
出典)こころの耳「職場のメンタルヘルス対策の取組事例」
まとめ
企業の成長には、従業員が健康で安心して働ける環境が不可欠です。特に中小企業では、一人ひとりのコンディションが経営の安定を左右します。
ストレスチェックは、安定した職場環境づくりのために必要な仕組みです。長時間労働や人の入れ替わりが激しい職場では、特に効果的だといえます。
ツールを活用すれば手軽に実施でき、早期対策が可能です。ストレスチェックで企業を守るための第一歩を踏み出しましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録