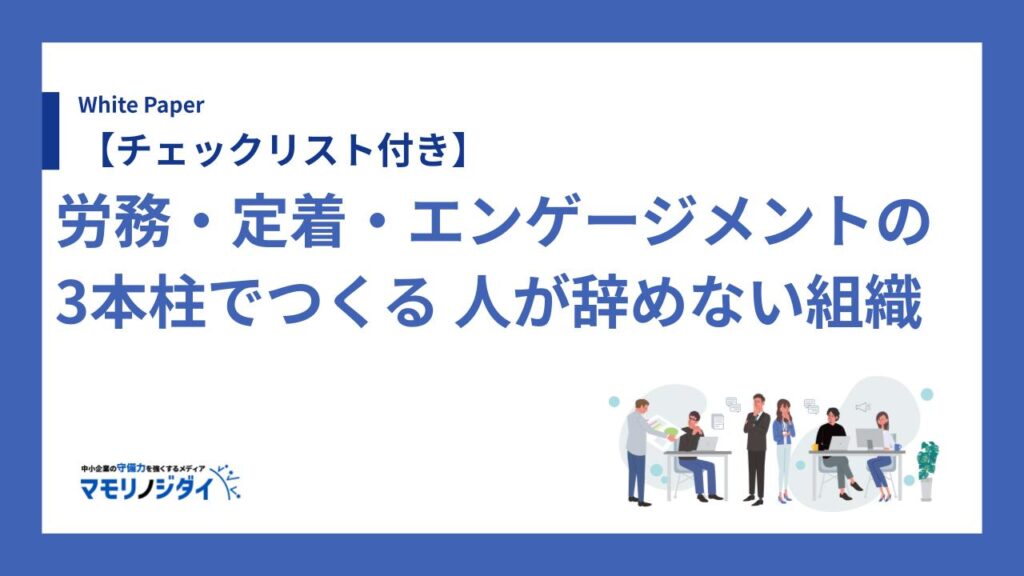103万円の壁が廃止され控除額引き上げへ!中小企業が知っておくべきこと

2024年12月20日、与党は「2025年度税制改正大綱」を決定しました。
その中には、国民民主党がこだわっている「103万円の壁の見直し」についても盛り込まれており、所得税の控除額を現行の103万円から123万円まで引き上げる旨が記されています。
しかし、控除額が引き上げられたことで、どのような影響があるのかについて、詳しく把握していないという方も多いでしょう。
そこで本記事では、この制度変更の背景や影響、そして中小企業が注意すべきことなどについて、実務的な観点からわかりやすく解説します。
目次
103万円の壁が廃止され123万円への引き上げが閣議決定
2024年12月20日に閣議決定した税制改正大綱の中で、所得税の課税対象となる年収について「103万円から123万円まで引き上げる」といった内容が記載されました。
所得税に関して、「基礎控除」と「給与所得控除」がそれぞれ10万円ずつ引き上げられ、従来の控除額よりも20万円増えた形です。
また、19~22歳の子供がいる親の税負担を軽くするために「特定扶養控除」も拡充され、現行の103万円から150万円まで引き上げられました。
引き上げの背景には、「物価高騰による国民の生活苦」や「働き控えによる企業の人手不足」といった理由が挙げられるものの、実際は政局が大きく影響しており、「勢力を拡大した国民民主党の意向に沿った」という側面もあります。
そもそも103万円の壁とは
103万円の壁とは、「所得税が課税される年収の境界線」のことです。
年間の給与所得が103万円を超えると所得税が課税されることから、103万円の壁と呼ばれるようになりました。
なお、103万円の内訳は「基礎控除48万円」と「給与所得控除55万円」となります。
103万円の壁が抱える問題は、年収が103万円を超えてしまうと所得税がかかるため、労働時間を調整する人が増えてしまうという点にあります。
いわゆる「働き控え」と呼ばれる現象です。
103万円の壁を超えてしまうと、本人に所得税がかかるだけでなく、世帯主の税負担も増えます。
配偶者の年間所得が103万円を超えれば配偶者控除がなくなりますし、扶養している子供の年間所得が103万円を超えれば扶養控除がなくなってしまいます。
世帯全体で見ると、看過できない税負担となってしまうのです。
また、使用者側にとっても、働き控えによって人手不足の状況に陥ってしまうリスクがあります。
このように、使用者側・労働者側のどちらにも不利益が発生するため、103万円の壁については、「制度の課題」として長年議論されてきました。
103万円の壁が撤廃されるのはいつから?
103万円の壁が撤廃され、控除額が引き上げられる明確な時期については決定していません。
実施時期については、当初から様々な議論がありました。
国民民主党は早期実施を求めていましたが、法改正や実務的な準備期間の必要性を考慮し、2025年1月から実施される見通しとなっているのが現状です。
123万円への引き上げが完全に確定したわけではない
「年収103万円の壁」の引き上げが大きな話題となり、引き上げについて閣議決定もされましたが、まだ確定したわけではありません。
103万円の壁の見直しを公約に掲げていた国民民主党は、「178万円」までの引き上げを求めています。
国民民主党は、123万円までの引き上げに対して「到底納得できない」という考えを明確に示しているため、今後どうなるかはまだ不明瞭です。
少数与党となってしまった現在の政権としては、勢力を拡大している国民民主党を敵に回したくはないものの、減税に繋がる控除額の増額に対して簡単に応じるわけにはいかないという事情もあります。
各政党の思惑が混在しているため、控除額の引き上げがどの程度になるかは、まだ予断を許さない状況です。
参考記事:103万円の壁廃止!中小企業にはどのようなメリット・デメリットがあるのか
103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁の違い
日本の税制・社会保障制度には、いくつかの重要な「年収の壁」が存在します。
それが、「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」です。
- 103万円の壁:所得税に関する境界線
- 106万円の壁:社会保険料に関する境界線
- 130万円の壁:国民年金と国民健康保険に関する境界線
それぞれの壁を超えた場合の影響は以下の通りです。
| 103万円の壁を超えた場合 | ■対象は「扶養されている人」 ■本人に所得税がかかる ■世帯主の配偶者控除や扶養控除がなくなる |
| 106万円の壁を超えた場合 | ■対象は「従業員51人以上の企業などで働く人」 ■原則、社会保険への加入が義務となる |
| 130万円の壁を超えた場合 | ■対象は「従業員が50人以下の企業などで働く人」 ■国民年金・国民健康保険の保険料支払い義務が発生する |
ただ、マイナス面ばかりではありません。
106万円の壁や130万円の壁を超えた際に納める社会保険料や国民年金については、将来的に「給付」という形で還元されます。
特に社会保険の一つである厚生年金については、従業員が負担している金額が大きいほど将来受け取れる金額が増えます。
従業員の老後を考えると、あながちマイナス面ばかりとは言えません。
103万円の壁撤廃によるメリット・デメリット
103万円の壁が撤廃されることは、働き方改革の一環として大きな注目を集めています。
この制度変更が、中小企業にとってどのような影響をもたらすのでしょうか?
この項目では、103万円の壁撤廃による中小企業のメリット・デメリットを解説していきます。
103万円の壁が撤廃されることのメリット
103万円の壁が撤廃されることによって中小企業側が享受できる最大のメリットは、「人手不足解消に繋がる」という点です。
103万円の壁が存在することで、パートやアルバイトで働く多くの人たちが、余計な税負担を防ごうとして労働時間を調整してしまいます。
そのため、働き控えが発生し、「人手が欲しい時でもシフトに入ってもらえない」などの問題に苦しめられる企業が多い状況でした。
しかし控除額が増えることで、税負担なしで労働時間を増やすことができるようになるため、人材確保の面での苦労が軽減される可能性が高くなります。
また、パートやアルバイトとして働く人たちにとっても、年収増加に繋がるため、業務へのモチベーションアップに期待できます。
パート・アルバイトとして働く人たちが、今までより長時間働けるようになることから、責任ある仕事を任せやすくなるという点も見逃せません。
103万円の壁が撤廃されることのデメリット
103万円の壁撤廃は、企業にとってメリットばかりではなく、デメリットもあります。
まず挙げられるデメリットは、「社会保険料の負担額が増える可能性がある」という点です。
社会保険は労使折半であるため、従業員に社会保険料を支払う義務が発生してしまうと、企業側も半額負担しなければなりません。
社会保険料の負担は、企業にとって非常に大きな問題です。
「社保倒産」という言葉があるほど、企業には重い負担となることも多いのです。
その他にも様々なデメリットが考えられます。
たとえば、国の税収が減ることで公共サービスが削減されてしまえば、それまで企業が受けられていたサービスが削られてしまうこともあり得ます。
また、税収が減ったしわ寄せとして、法人への増税が課される可能性も否定できません。
「103万円の壁撤廃」に際して中小企業が知っておくべきこと
103万円の壁が撤廃されることで、中小企業が把握しておくべきことは主に以下の2点です。
- 学生のパート・アルバイトの実働増加に期待できる
- 社会保険の負担によって危機に陥る可能性がある
前項のメリット・デメリットの項目でも簡単に触れましたが、より詳しく解説していきます。
学生のパート・アルバイトの実働増加に期待できる
103万円の壁撤廃と同時に、「学生の年収の壁」対策として、2025年から親の特定扶養控除のラインも、103万円から150万円まで引き上げられました。
その結果、学生は年収150万円までは満額の特定扶養控除を受けられるため、学生の働き控えが減り、学生をパート・アルバイトで雇っている企業は人材確保の面でプラスに働きます。
これまでは、多くの学生が扶養控除の関係で年収を103万円以下に抑える必要があったため、繁忙期でも働く時間を制限する人が多く、企業側としては人手不足に悩まされることも多かったのが現状です。
しかしこの制限が撤廃されれば、柔軟に働ける学生が増えるため、小売業やサービス業といった、特に学生アルバイトへの依存度が高い業態では強い追い風となるはずです。
社会保険の負担によって危機に陥る可能性がある
デメリットの項目でも紹介した通り、103万円の壁撤廃は良いことばかりではありません。
103万円の壁撤廃とほぼ同時期に、「106万円の壁」についても、最低賃金が引き上げられたことで必要性が薄れているという理由で撤廃される流れとなりました。
厚生労働省が撤廃案を提出し、審議会の部会が了承したため、2026年10月には年収要件廃止、2027年10月以降は企業規模要件廃止、となる予定です。
問題なのは、「企業規模要件の廃止」と「週20時間以上という労働時間要件の存続」です。
これまでは、社会保険の加入要件は「従業員が51人以上の企業」に限定されていたものの、この要件が撤廃されました。
さらに、年収に関わらず週20時間以上働く労働者は全員厚生年金へ加入することが義務付けられます。
このような事情から、新制度が施行されることで、多くの中小・零細企業が社会保険料の負担に苦しむ可能性が出てきました。
必ずしも経営基盤が強固でない中小企業にとっては、労使折半となる社会保険料の負担増は深刻な経営課題となりかねません。
まとめ
103万円という壁が引き上げられることは、中小企業にとって機会と課題の両面を持ち合わせています。
学生アルバイトの労働力確保という点では朗報である一方、社会保険料負担の増加という新たな経営課題も生じます。
この制度変更を乗り切るためには、人材活用の最適化と経営体質の強化を同時に進めていく必要があります。
できるだけ早い段階から準備を進め、計画的な対応を図ることが、中小企業の持続的な成長に繋がる鍵となることを強く意識してください。
関連記事
-
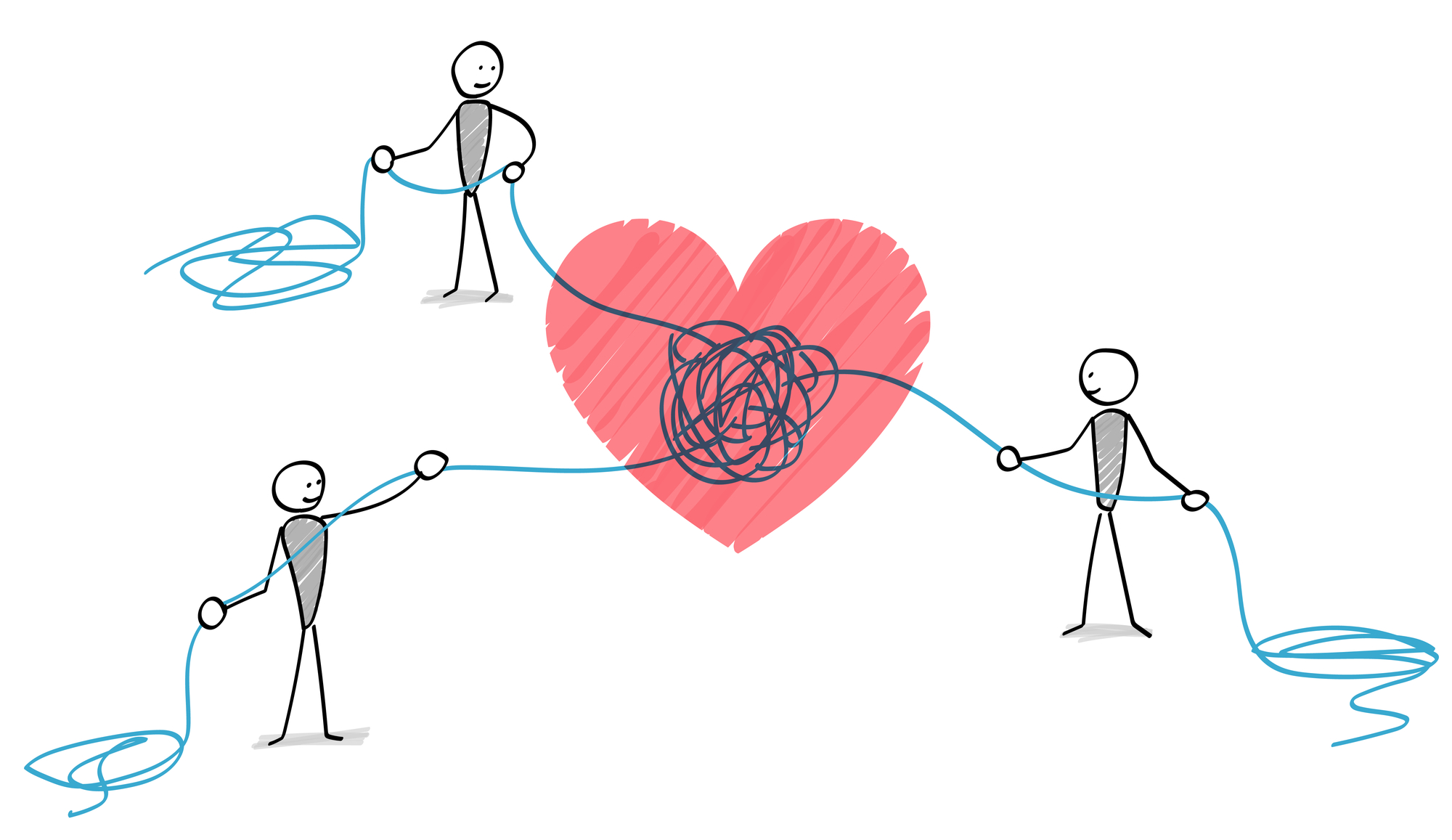
メンタルヘルス対策の新常識とは?中小企業が直面する課題と解決法
近年、ビジネスの現場でメンタルヘルスケアの重要性が高まっています。しかし、具体的に何から始めればよいのか、どんな対策が効果的なのか、悩んでいる経営者や人事担当者も多いのではないでしょうか。本記事では、企業におけるメンタルヘルス対策の基礎知識から実践的な取り組み事例まで、分かりやすく解説していきます。
-

出生時育児休業給付金と育児休業給付金の違いとは?中小企業の注意点を知ろう
育児休業は、従業員が出産や育児と仕事を両立するための重要な制度です。新たに「出生時育児休業給付金」や「出生後休業支援給付金」が創設され、制度がより複雑になりました。
これら出生に関わる給付金は、名称は似ていますが、さまざまな違いがあり、とくに中小企業にとっては、制度理解の不足から課題が生じるケースも少なくありません。
この記事では、出生時育児休業給付金と育児休業給付金のそれぞれの制度内容を詳しく解説し、具体的な違いを明確にします。
さらに、中小企業がこれらの給付金を円滑に運用し、従業員が安心して制度を利用できるよう、注意すべきポイントについても詳しく掘り下げていきます。
-
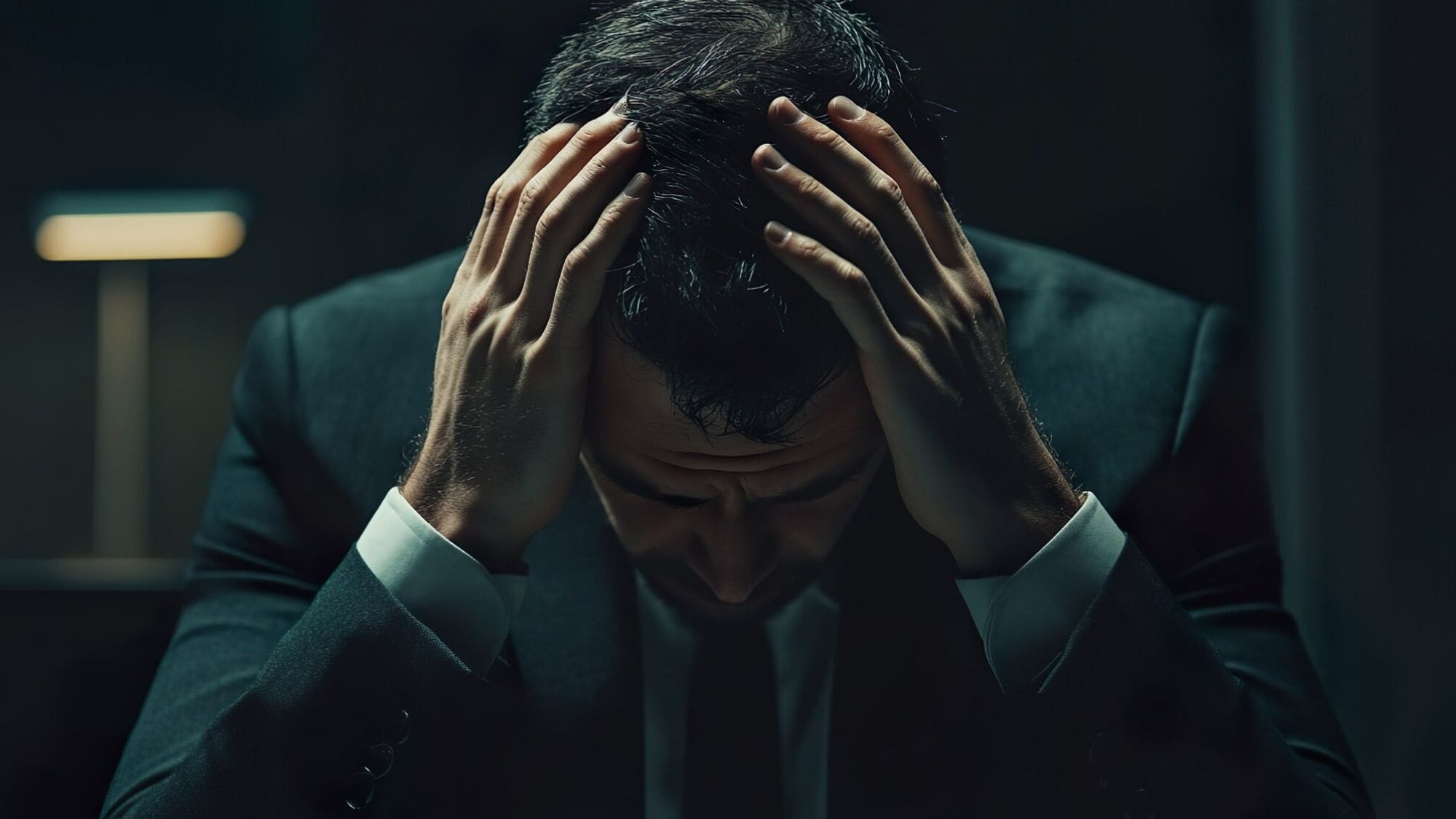
労働基準監督署に通報されたらどうなる?適切な対処法を知ろう
「労働基準監督署に通報されたらどうなるのだろう?」中小企業の経営者や人事担当者にとって、これは非常に気がかりな事態です。
労働基準監督署への予期せぬ通報は、会社の信用にかかわるだけでなく、その後の対応を誤ると罰則や企業名の公表といったリスクにつながる可能性もあります。
しかし、労働基準監督署へ通報される背景やその後の調査の流れ、適切な対応方法を知っていれば、慌てずに正しく対応することが可能です。
この記事では、「労働基準監督署に通報されたらどうなる?」という不安に対し、その実態から適切な対処法、そして未然に防ぐための予防策までをわかりやすく解説します。
-

残業規制は中小企業にも適用!上限や割増賃金率を把握してリスクを回避
働き方改革関連法の施行により、時間外労働(残業)の上限規制は、大企業のみならず中小企業にも適用されています。残業時間の上限超過は、罰則だけでなく企業イメージの低下にも繋がりかねません。この記事では、中小企業が把握すべき残業時間の上限、割増賃金率、そして企業が取るべき対策を解説し、残業リスク回避につながる情報を紹介します。
-

出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業の違いは?併用するメリットも紹介
2022年10月から「産後パパ育休」とも呼ばれる出生時育児休業制度がスタートしました。
しかし、「従来の育児休業と何が違うの?」「どちらを使えばいいのだろう?」といった疑問を持っている方も多いでしょう。
この二つの制度は、名前は似ていますが、目的やルールが異なる全く別のものです。
そこでこの記事では、出生時育児休業と育児休業の具体的な違いや、二つの制度を併用するメリット、企業が取るべき対策について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録