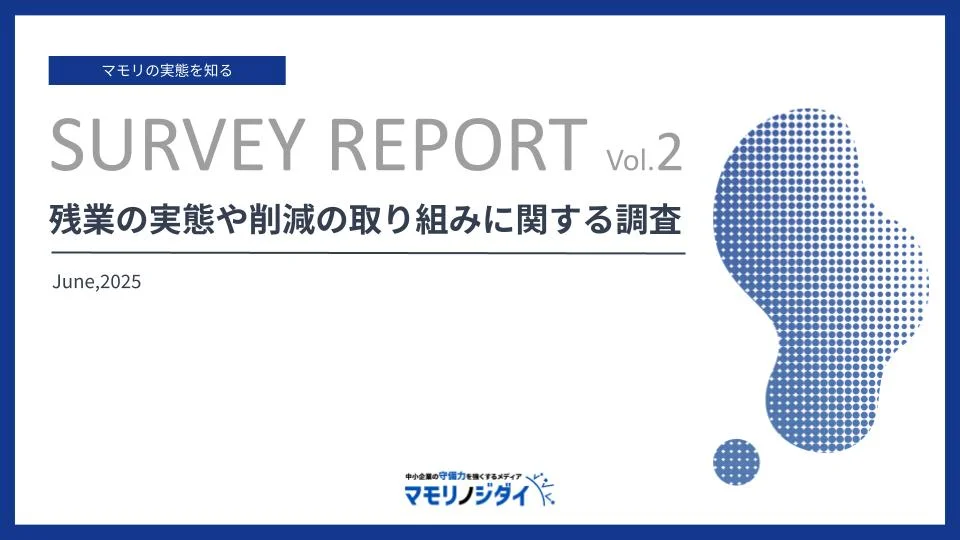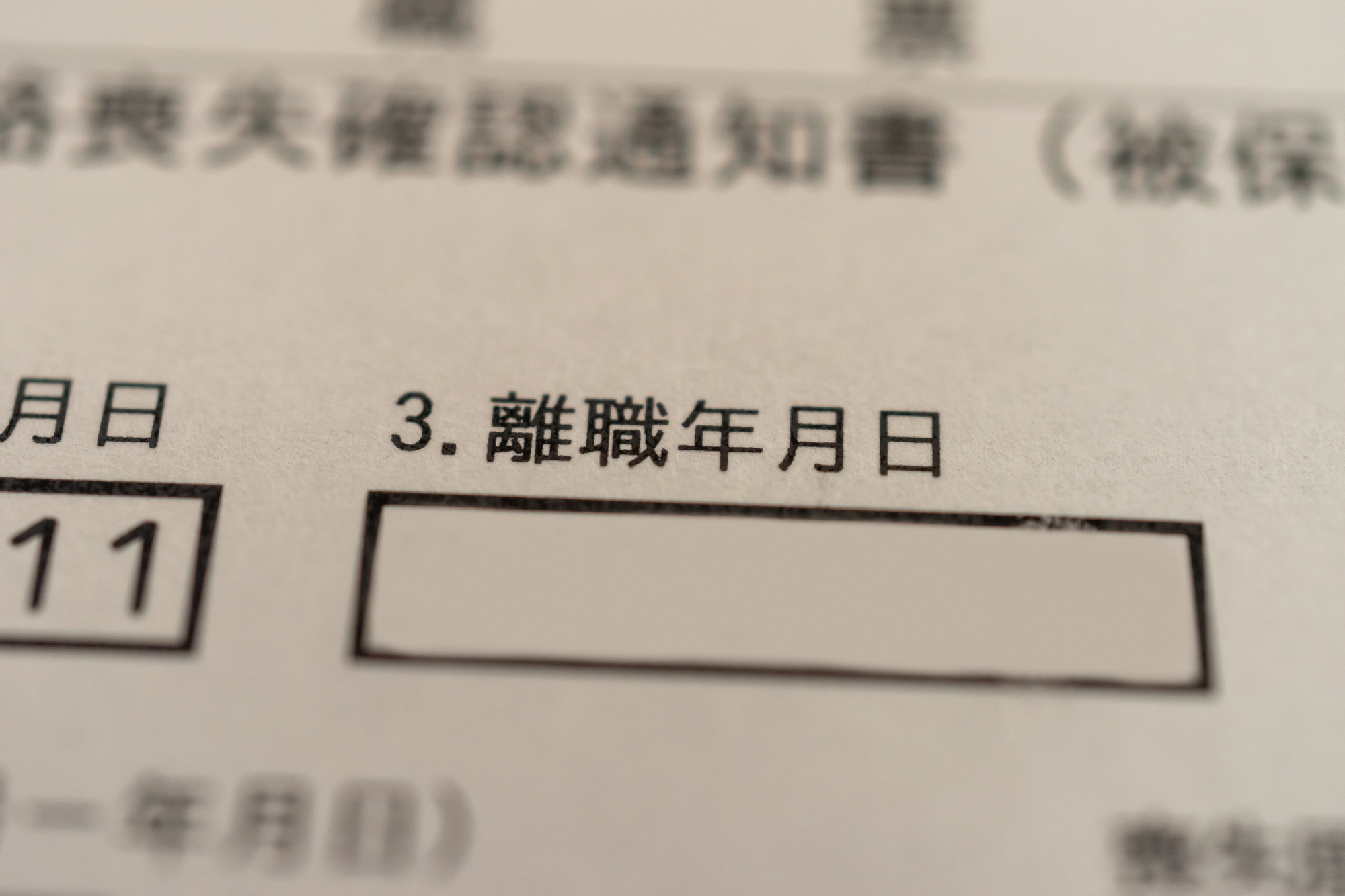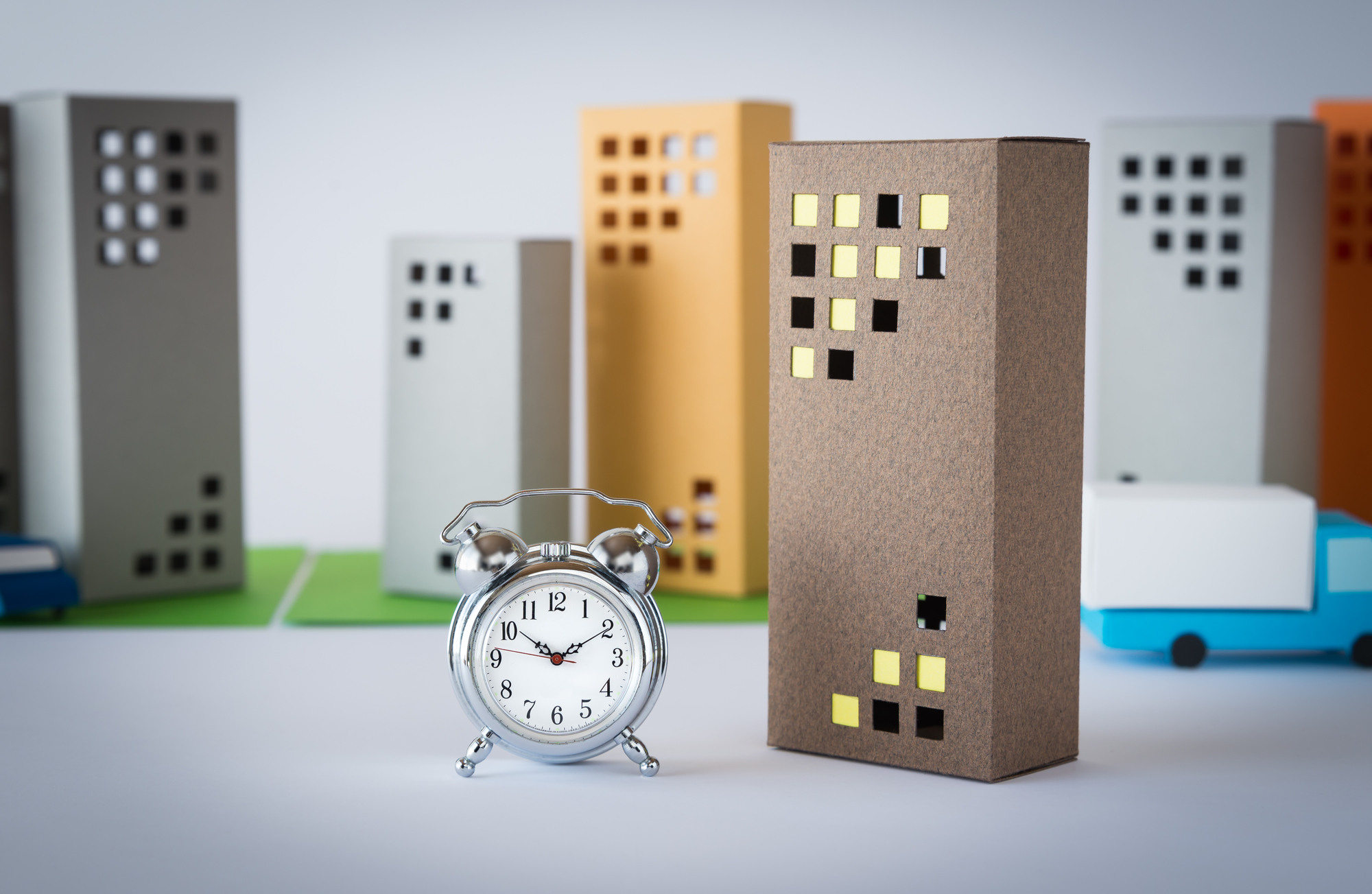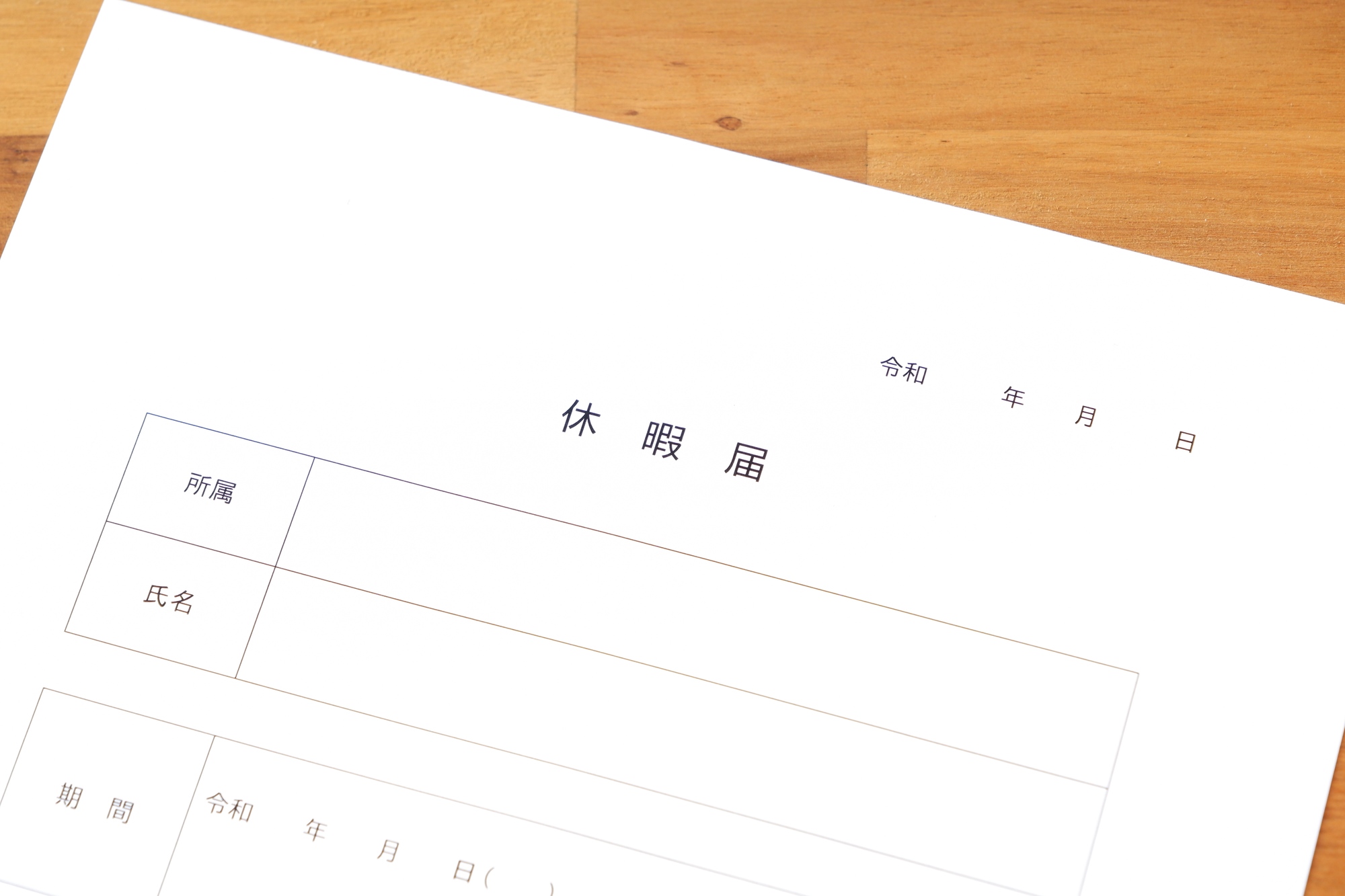法定労働時間を超えたら労働基準法違反?|所定労働時間との違いも解説

働き方改革が進んでいることから、企業による「従業員の残業時間」の管理が日に日に重要性を増しています。
そういった状況であるため、経営者や人事担当者は、「法定労働時間とは何か?」「残業規制の内容は?」「中小・零細企業にも適用されるのか?」といった点について漏れなく把握しておかなければなりません。
そこでこの記事では、法定労働時間についての基礎から、中小企業が知っておくべき残業のルールなどについて詳しく解説していきます。
目次
法定労働時間とは
まずは、「法定労働時間」の基礎知識について解説していきます。
従業員に違法な残業をさせてしまったり、正当な残業代を支払っていなかったり、といったリスクを排除するために、基本的な部分から抜け漏れなく学んでおきましょう。
まずは労働時間・休憩時間・残業時間の定義を把握すべき
「労働時間」「休憩時間」「残業時間」の字面だけを見ますと、ほとんどの方がその意味を理解できるはずです。
しかし、「労働基準法上の定義」となると、詳しく把握できていない方も多いのではないでしょうか。
法定労働時間や残業規制などを理解する上で重要になる基本的な知識であるため、正しく理解しておくようにしましょう。
厚生労働省によると、「労働時間」「休憩時間」「残業時間(時間外労働)」について、以下のように説明しています。
| 法定の労働時間、休憩、休日 ・使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 ・使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 ・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 |
出典)厚生労働省「労働時間・休日」
| 労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週40時間までと定められています。この法定労働時間を超えて労働をさせた場合が、労働基準法の(法定)時間外労働です。これが割増賃金の対象になります。 |
出典)厚生労働省「よくあるご質問(時間外労働・休日労働・深夜労働)」
労働基準法によって定められた労働時間の上限が「法定労働時間」
法定労働時間について、厚生労働省では以下のように説明しています。
| 法定労働時間(労働基準法第32条、第40条) 【原則】 使用者は、1週間に、40時間を超えて労働させてはならない。 使用者は、1日に、8時間を超えて労働させてはならない。 |
出典)厚生労働省「法定労働時間(労働基準法第32条、第40条)」
労働基準法によって定められたこれらの上限は、労働者の健康と安全を守ることを目的としており、過度な労働から労働者を保護するために設けられています。
この時間を超えて働かせる場合、「労使間で36協定を締結する」「適切な残業代を算出して支払う」など、企業は法に基づいて適切な手続きを踏まなければなりません。
法定労働時間は、労働者のワークライフバランスを考慮し、労働環境の改善を促進するための基盤でもあります。
したがって、企業は法定労働時間をもとに、労働者が安心して働ける環境を整えることが重要です。
労働時間の適正な管理は、企業の信頼性を高め、長期的な成長を支える要素となるため、経営者や人事担当者にとって法定労働時間に関する知識は不可欠です。
法定労働時間と所定労働時間の違い|中小企業が押さえるべきポイント
法定労働時間と所定労働時間の違いを一言でまとめると、以下のような形になります。
- 法定労働時間:労働基準法で定められた労働時間の上限
- 所定労働時間:企業が就業規則や労働契約によって定めた労働時間
所定労働時間を決めるのは企業であるものの、自由に決めていいというわけではなく、法定労働時間の範囲内で設定しなければなりません。
法定労働時間を超えた所定労働時間は、原則として違法となるので注意が必要です。
法定労働時間を超える時間外労働が発生する場合は、必ず時間外労働協定(36協定)を締結する必要があります。
法定労働時間を超える残業への規制は中小企業も対象に!
2019年4月から「働き方改革」の関連法案が施行されました。
これにより、大企業の残業規制(時間外労働の上限規制)の内容が明確になり、「月45時間」「年360時間」という残業時間の縛りに対して法的拘束力が発生しました。
| これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制⼒がなく、また特別条項を設けることで上限無く時間外労働を⾏わせることが可能となっていました。今回の改正によって、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられます。 |
出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」p.4
しかし、中小企業にとっても対岸の火事ではありません。
2020年4月からは、原則として中小企業も残業規制の対象となったのです。
なお、「工作物の建設の事業」・「自動車運転の業務」・「医者」・「鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業」の4種については、働き方改革関連法案施行から5年間の猶予期間がありました。
こちらもすでに猶予期間は終わり、2024年4月から残業規制の対象となっています。
その結果、中小・零細を含むほとんどの企業において、従業員が以下の範囲を超えた残業をすることができなくなりました。
- 年間720時間を超える時間外労働
- 月間100時間以上の時間外労働+休日労働
- 2~6か月平均の残業時間が一度でも80時間を超える
- 特別条項があっても、月45時間を超える残業が可能なのは年間で6ヶ月まで
中小・零細企業の経営者や人事担当者は、従業員にどこまで残業を許可しても問題ないのかについて、今一度よく確認するようにしてください。
法定労働時間を超えた場合はどうなるのか
これまで解説してきたように、法定労働時間を超えた残業に関する規制は、法改正によって強化されています。
では、法定労働時間を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
この項目にて、詳しく紹介していきます。
従業員が残業するには36協定の締結が必要
まず、法定労働時間を超えて従業員が残業するには、労使間で「36協定」の締結が必要です。
36協定は、労働基準法第36条に基づき、使用者と労働組合(または労働者の代表)との間で締結される協定で、これにより法定労働時間を超えた労働が可能になります。
| 【時間外労働協定(36協定)】 労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。 ※時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。 |
出典)厚生労働省「労働時間・休日」
36協定がない状態での残業は「法律違反」となり、企業に対して罰則が科される可能性があるので注意しましょう。
なお、36協定を締結したからといって無制限に残業を命じられるわけではありません。
前述の通り、上限については規制があるので、「どこまでの残業が問題ないのか」というラインについては詳細に把握しておくべきです。
残業代の算出には「月平均所定労働時間」を使用
残業代を算出する際に重要となるのが、「月平均所定労働時間」です。
月平均所定労働時間とは、1ヶ月あたりの平均的な労働時間のことで、深夜労働や法定外残業などの際に発生する割増賃金を算出するのに用いられます。
月平均所定労働時間の計算方法は以下の通りです。
| 1年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12=1か月の平均所定労働時間 |
出典)厚生労働省「割増賃金の計算方法」p.1
たとえば、年間の休日が「125日」で、1日の所定労働時間が8時間だとします。
この場合、「(365日 - 125日)× 8時間 ÷ 12ヶ月」となり、160時間が月平均所定労働時間となります。
残業代(割増賃金)の計算方法
法定労働時間を超えて労働を行った従業員には、割増賃金を算出して、残業代を支払う義務があります。
残業代の計算式は以下の通りです。
■残業時間 × 1時間当たりの基礎賃金 × 割増率 = 残業代
「1時間当たりの基礎賃金」は、前項で紹介した月平均所定労働時間を使い、以下の計算式で算出します。
| 月給÷1か月の平均所定労働時間=1時間あたりの賃金額 |
出典)厚生労働省「割増賃金の計算方法」p.1
なお、割増率については残業のケースによって異なります。
| 種類 | 支払う条件 | 割増率 |
| 時間外労働 | 法定時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 2割5分以上(1か月60時間を超える時間外労働については5割以上※中小企業は、2023年4月1日から適用) |
| 休日労働 | 法定休日(週1日)に労働させたとき | 3割5分以上 |
| 深夜労働 | 22時から5時までの間に労働させたとき | 2割5分以上 |
出典)厚生労働省「割増賃金の計算方法」p.1
たとえば、「休日労働+深夜労働」の場合ならば、35%+25%で、最低でも60%以上の割増率となります。
36協定の上限を超えると罰則あり
法定労働時間を超える場合、企業は従業員に対して残業手当を支払う義務があります。
しかし、単に超過勤務を許容するだけではなく、労働基準法に基づく36協定(労使協定)を締結しなければなりません。
| 労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。 |
出典)厚生労働省「36(サブロク)協定とは|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト」
この36協定により、企業は法定労働時間を超える労働を合法的に命じることが可能になります。
しかし、36協定を結んでも、原則として月45時間・年間360時間を超える残業を命じることできず、もし36協定の上限を超えた残業を課した場合は、労働基準法違反として企業側が罰則を受ける可能性があります。
| ■今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。 ■臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。 ・時間外労働が年720時間以内 ・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満 ・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内 ・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度 ■上記に違反した場合には、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがあります。 |
出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」p.4
企業として、「罰則を科された」という事実は大きなマイナスイメージとなってしまいます。
また、法定労働時間を超える労働が常態化することは、従業員の健康や生産性にも悪影響を及ぼす可能性があるという点も問題です。
労働時間の管理は、単なる法令遵守に留まらず、企業の信頼性や持続可能な成長に直結するため、企業として適切な対応を行うようにしましょう。
法定労働時間には「例外」が設けられている
労働基準法で定められた「1日8時間・週40時間」という法定労働時間は、一律で適用されているわけではなく、以下のような働き方の場合は例外となります。
- 変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 裁量労働制
それぞれの働き方について、厚生労働省では以下のように説明しています。
| 変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。 |
出典)厚生労働省「労働時間:変形労働時間制(変形労働時間制) 」
| フレックスタイム制(労働基準法第 32 条の3)は、1日の労働時間の長さを固定的に定めず、1箇月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決め、その生活と業務との調和を図りながら、効率的に働くことができる制度です。 |
出典)厚生労働省「フレックスタイム制の適正な導入のために」
| 裁量労働制とは、働いた時間にかかわらず、仕事の成果・実績などで評価を決める制度のことです。事業主は、業務の遂行の手段や時間の配分などに関して、具体的な指示を行ないません。 |
出典)厚生労働省「裁量労働制」
また、観光業や飲食業など、需要の変動が激しい業種において、特定の期間に労働時間が集中する場合にも、例外として認められることがあります。
従業員の労働時間管理は不可欠なリスクマネジメント
労働時間管理は、企業にとって法令遵守だけでなく、従業員の健康と生産性を守るための重要なリスクマネジメント手法です。特に中小企業でも、労基署による調査や是正勧告は毎年行われています。違反が発覚すると、罰則だけでなく取引先や採用市場での信用失墜にもつながるため注意が必要です。
適切な労働時間の管理は、過労やメンタルヘルスの問題を未然に防ぎ、従業員のモチベーション向上にも寄与します。
特に、現代のビジネス環境では、柔軟な勤務形態やテレワークが普及しており、それによって労働時間の把握が難しくなるケースも増えています。
こういった形に対応するためには、ITを活用した労働時間の記録と分析が不可欠です。
たとえば、労働時間をデジタルで正確に記録するシステムを導入することで、リアルタイムでの管理が可能となり、労働基準法違反のリスクを軽減できることでしょう。
従業員の労働時間の管理は、「義務だから仕方なくやる」というものではなく、組織全体の健全性を保ち、企業としての更なる成長を目指すために欠かせない取り組みなのです。
まとめ
法定労働時間や残業規制、36協定の重要性、労働基準法に違反した際の甚大なダメージなどについては、企業の経営層ならば必ず把握しておかなければいけないことです。
罰則を受けるだけでなく、企業としての信頼を失ってしまうことも不可避であることから、従業員の労働時間については正確に把握し、適切に管理できる体制を構築しておきましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録