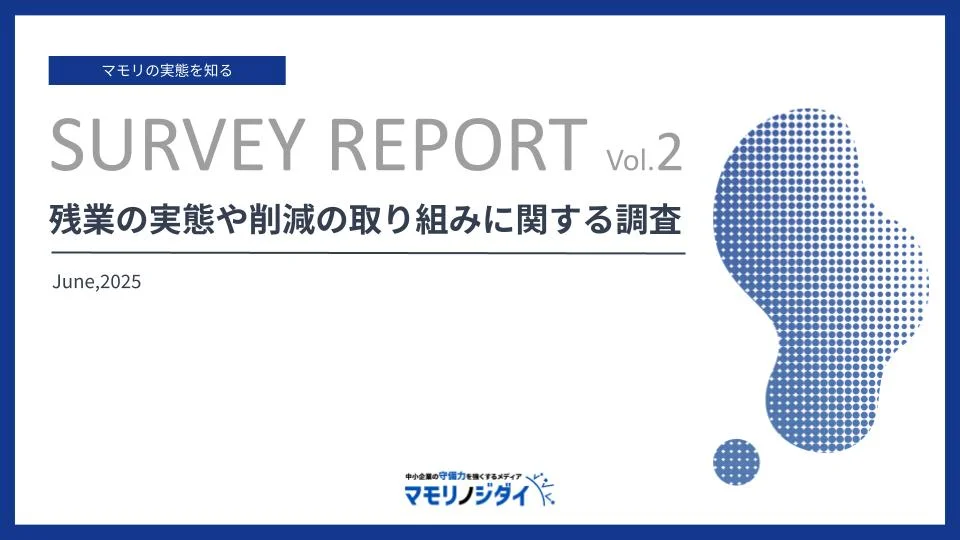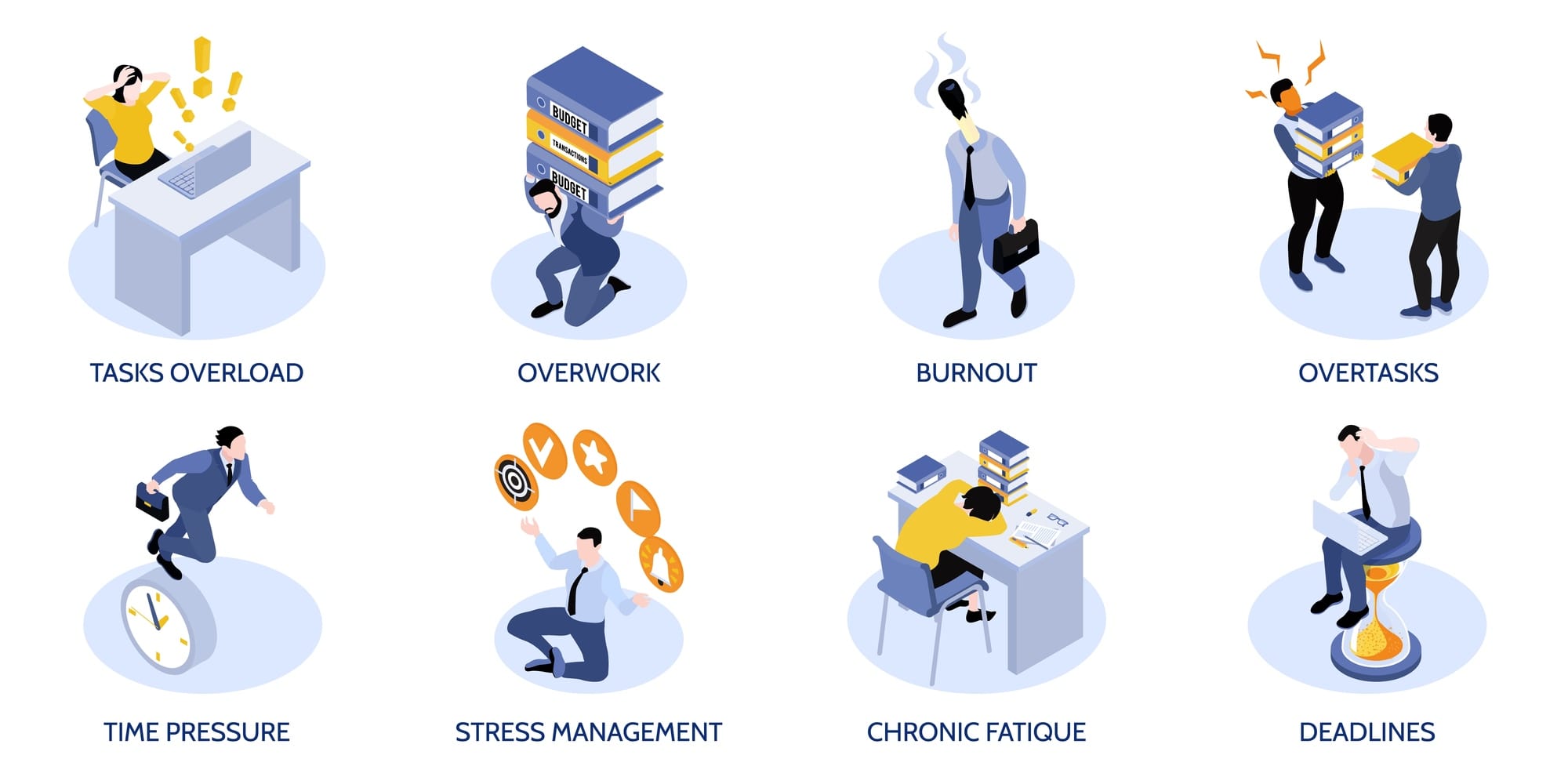「残業しろ」はパワハラ?残業強要の違法性やハラスメントに該当するケース

従業員に「残業しろ」と安易に指示する場面があるかもしれません。しかし、その一言が、思わぬ法的リスクや従業員とのトラブルにつながる可能性があります。
労働基準法では、従業員の健康と権利を守るため、時間外労働に厳しいルールを設けています。ルールを無視した残業の強要は、違法行為であり、パワハラとみなされることがあるのです。
この記事では、中小企業が陥りがちな「残業しろ」と強要することのリスクと、具体的な対策について解説します。
目次
「残業しろ」はパワハラに該当することもある
「残業しろ」と強要することはパワハラに該当し、違法になるケースがあります。とくに事業主には、パワハラ対策が義務付けられているので注意が必要です。
| 令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。 本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。 |
出典)厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
このように、パワハラ対策が義務となっていることから、「残業しろ」という言葉がパワハラである場合には、違法となってしまうのです。
どのようなケースで「残業しろ」という言葉がパワハラになるのか、このあとの章で解説していきます。
企業側から「残業しろ」と強要することが違法になるケース
企業が従業員に「残業しろ」と強要することは、労働基準法によって制限されており、主に以下の4つの例が違法となります。
36協定を締結していない状態で「残業しろ」と強要する
労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働を原則として禁止しています。
企業が従業員に「残業しろ」と時間外労働や休日労働をさせるためには、労働組合または従業員代表との間で「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
| 残業させる場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる「36(サブロク)協定」)を適正に締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。 |
出典)厚生労働省「36(サブロク)協定のない残業は法違反です!!」p.1
36協定を締結せずに「残業しろ」と強要した場合、企業は労働基準法違反となり、罰則を受ける可能性があります。
就業規則に残業に関する記載がない
36協定を締結していても、就業規則に残業に関する事項が記載されていなければ、企業は従業員に「残業しろ」と命じることはできません。
| 就業規則の規定例1(時間外労働に対する割増賃金率)割増賃金率を、1か月45時間を超える時間外労働について35%、1年360時間を超える時間外労働について40%に設定している場合 第○章 賃金 第○条 時間外労働に対する割増賃金は次の割増賃金率に基づき、次条の計算方法により支給する。 (1)1か月の時間外労働時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。なお、この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。 一 時間外労働45時間以下 25% 二 時間外労働45時間超〜60時間以下 35% 三 時間外労働60時間超 50% 四 三の時間外労働のうち代替休暇を取得した時間 35%(残り15%の割増賃金分は代替休暇に充当) (2)1年間の時間外労働時間数が360時間を超えた部分については、40%とする。なお、この場合の1年は毎年4月1日を起算日とする。 |
出典)厚生労働省「H30管理の手引き 就業規則の規定例(改正労基法(平成22年4月施行)によるもの)」p.1
このように、就業規則には、始業・終業時刻、休憩時間、休日、時間外労働・休日労働など残業に関する事項を記載する必要があります。
労働基準法の範囲を超えているのに「残業しろ」と強要する
36協定を締結し、就業規則にも残業に関する事項を記載していても、労働基準法で定められた時間外労働の上限規制を超えて「残業しろ」と強要することは違法です。
時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間とされています。
| 残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。 |
出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制」
特別な事情がある場合には、労使合意の上でこれを超えることも可能ですが、その場合でも上限規制が設けられています。
残業代を支払わない「サービス残業をしろ」と強要する
企業は、従業員に「残業しろ」と命じて残業をさせた場合、割増賃金を支払う義務があります。
| 賃金不払残業(サービス残業)は、労働基準法に違反する、あってはならないものです。 |
出典)厚生労働省「賃金不払残業(サービス残業)の解消のための取組事例集」p.1
割増賃金を支払わない、いわゆるサービス残業をしろと強要することは、労働基準法違反となります。
これらの4つのケースに該当する場合、従業員は企業に対して残業の拒否や残業代の請求を行うことができ、労働基準監督署への相談も可能です。
会社から「残業しろ」と言われても従業員側から拒否できるケース
従業員が残業を拒否できるケースは、会社の残業命令が違法な場合や正当な理由がある場合です。
以下のような理由がある場合、従業員は「残業しろ」と言われても拒否できます。
体調不良
労働契約法第5条では、会社は従業員の安全に配慮する義務が定められており、従業員の生命や身体の安全を確保しながら労働できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
| 第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 |
出典)e-GOV 法令検索「労働契約法」
病気や怪我による体調不良は正当な理由となり、たとえ「残業しろ」と言われても拒否することが可能です。
残業の要請内容が違法
従業員が残業を拒否できるケースとして、まず残業の要請内容が違法な場合が挙げられます。
具体的には、以下の場合になります。
- 36協定が締結されていない
- 労働契約書や就業規則に残業に関する規定がない
- 残業時間の上限規制(月45時間・年360時間)を超えている
- 適切な残業代が支払われていない
- 業務上の必要性がない
これらのケースでは、従業員は会社の「残業しろ」という命令を拒否できます。
妊娠中または出産してから1年未満
妊娠中や出産から1年未満の従業員に対しては、労働基準法第66条の定めにより、「残業しろ」と強制はできません。
| 第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。 ② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 ③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 |
出典)e-GOV 法令検索「労働基準法」
従業員が安心して出産・育児に臨めるよう、会社はこれらの法律を遵守し、柔軟な働き方を支援することが求められます。
育児や介護の必要がある
従業員が残業を拒否できるケースとして、育児や介護が挙げられます。
介護育児休業法では、3歳未満の子を持つ従業員は第16条の8、小学校就学前の子を持つ従業員は第17条、要介護状態の家族を持つ従業員は第18条で、労働時間の延長をしない旨が定められています。
| 第十六条の八 事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 第十七条 事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第十八条の二において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 第十八条 前条第一項、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 |
出典)e-GOV 法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
これらの法律により、育児や介護を行う従業員は、「残業しろ」と言われても拒否することが可能です。
「残業しろ」と強要するパワハラを生まないためにはどうすべきか
残業の強要は、従業員の心身に悪影響を及ぼし、最悪の場合、過労死や精神疾患につながる可能性があります。企業は、従業員が安心して働ける環境を作るために、パワハラ防止対策を講じる必要があります。
ハラスメントに関する研修を実施する
管理職を含む全従業員を対象とした研修で「残業しろ」と命じることがパワハラとなるケースなどを学ぶ必要があります。
とくに、管理職に対しては、部下との適切なコミュニケーション方法や指導方法を学ぶ機会を提供し、パワハラ防止に対する意識を高めることが重要です。
相談窓口を設置する
従業員が「残業しろ」といったパワハラを受けた際、気軽に相談できる窓口があると、パワハラ防止につながります。
| ・相談窓口をあらかじめ定め、従業員に周知する。 ・相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにする。パワーハラスメントが生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合やパワーハラスメントに該当するかどうか分からない場合であっても、広く相談に対応する。 |
出典)政府広報オンライン「NOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント」
相談窓口を設置したら、その存在を社内報やイントラネットなどで周知し、従業員が利用しやすいように配慮することも大切です。
また、社内の担当部署だけでなく、外部の専門機関と連携することも有効です。
経営者が率先してメッセージを発信する
「残業しろ」がパワハラにあたるケースなどについて、経営者が率先して発信することは、従業員の意識改革につながります。
また、経営者自身がハラスメントに関する研修に参加するなど、具体的な行動を示すことで、従業員の信頼を得ることができます。
まとめ
「残業しろ」と安易に指示することは、企業の成長を阻害するだけでなく、法的リスクも伴います。
中小企業において、従業員のワークライフバランスに配慮した働き方を推進することは、持続的な成長に不可欠です。
「残業しろ」と強要することのリスクを理解し、労働時間管理の徹底、業務効率化の推進、そして従業員とのコミュニケーションを密にすることで、健全な職場環境を実現できます。
もし、自社の対応に不安を感じる場合は、専門家や労働基準監督署に相談することも有効です。従業員一人ひとりを大切にし、互いに尊重し合える職場とすることが大切です。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録