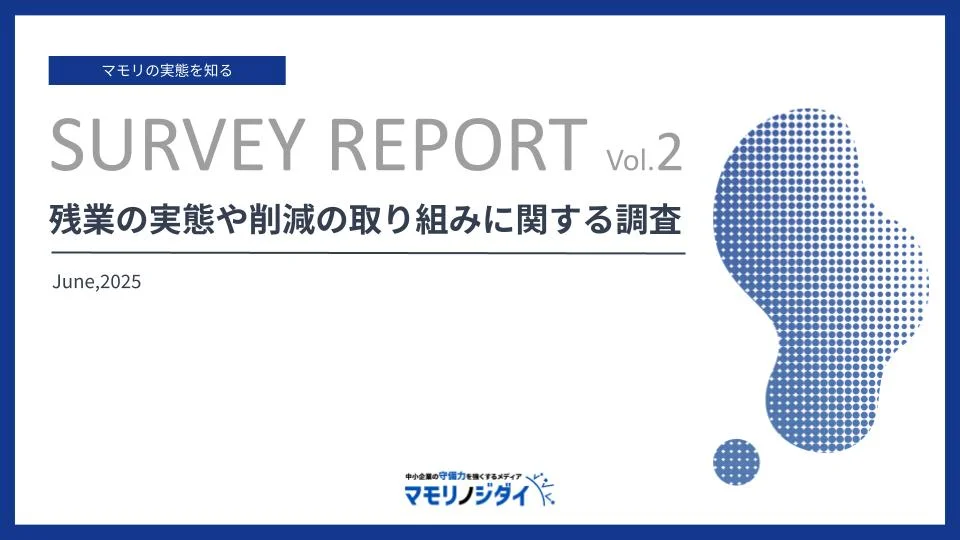サービス残業は自主的であっても違法の可能性あり!黙認や常態化のリスク
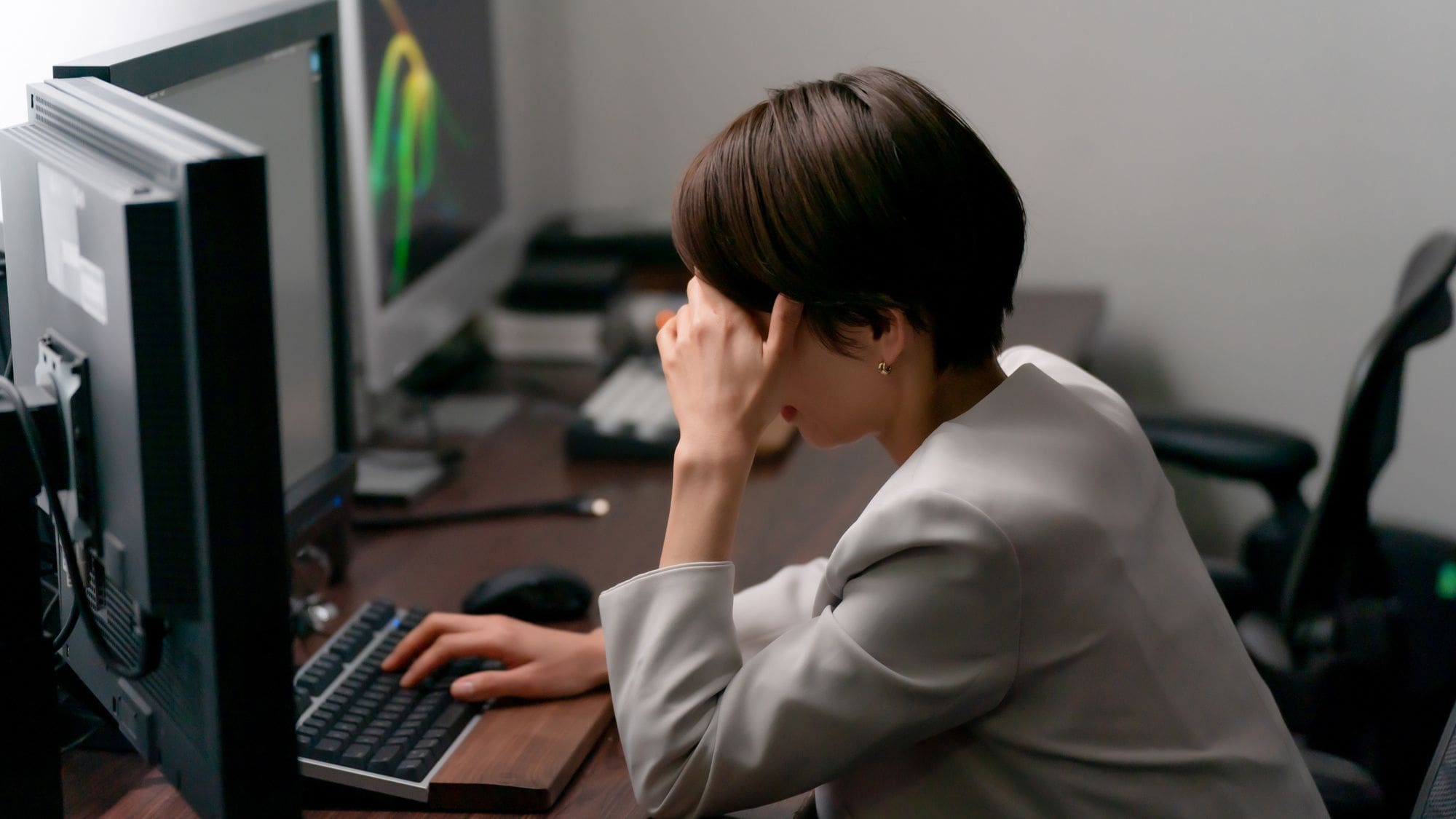
「うちの社員は自主的にしているからサービス残業も問題ない」という認識は非常に危険です。
たとえ本人の意思による行動であっても、実質的に業務遂行上必要不可欠な残業や、会社が黙認・推奨しているとみなされる場合は、サービス残業が違法となります。
サービス残業の黙認や常態化は、法的な罰則だけでなく、従業員のモチベーション低下、企業イメージの悪化、そして将来的な訴訟リスクにつながる重大な問題です。
この記事では、自主的なサービス残業がなぜ違法となり得るのか、そしてそのリスクと具体的な対策について、わかりやすく解説します。
目次
サービス残業とは?定義と自主的な残業との違い
サービス残業とは、労働時間として記録されず、賃金が支払われない時間外労働のことです。本来、労働基準法では、法定労働時間を超える労働には割増賃金の支払い義務があります。
| 賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。いわゆるサービス残業のこと。) |
出典)厚生労働省「『賃金不払残業解消キャンペーン月間』の実施について」
自主的な残業とサービス残業の大きな違いは「使用者の指揮命令下にあったかどうか」です。
たとえ従業員が自らの意思で行ったとしても、業務遂行上必要不可欠な行為であり、使用者が黙認・指示していたとみなされる場合は、サービス残業として違法となる可能性があります。
「自分の仕事が終わっていないから」「スキルアップのため」といった自主的な動機であっても、実質的に業務を強いられている状況であれば、サービス残業に該当し得るため注意が必要です。
「サービス残業は当たり前」という考え方は間違い!労基法違反のリスク
「うちの会社ではサービス残業が当たり前」「みんなやっているから仕方ない」といった考え方は、労働基準法に明確に違反する可能性のある危険な認識です。
| (時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」
このように日本の労働基準法は、労働者の適正な労働条件を保障するために、法定労働時間や割増賃金の支払い義務を定めています。
サービス残業を容認することは、これらの法律を無視することに他なりません。
本人の意思だけではNG!自主的なサービス残業が違法になる可能性も
「自主的に残業しているのだから問題ない」という認識は、サービス残業における大きな落とし穴です。
たとえ従業員本人の意思による行動であっても、実質的に使用者の指揮命令下にあったとみなされる場合は、時間外労働として扱われ、サービス残業に対して割増賃金の支払い義務が発生します。
勤務時間外に取引先と打ち合わせを行う
勤務時間外に、会社からの明確な指示はないものの、業務上の必要性から取引先と打ち合わせを行うケースは、自主的な行動に見えてもサービス残業となる可能性があります。
例:
- 納期厳守のために、終業後に取引先との調整が不可欠な場合
- 上司が状況を認識しつつも特に指示を出さず、従業員に一任している
これらの場合、実質的には使用者の指揮命令下にあったと解釈され、サービス残業を行った時間は労働時間として扱われるべきです。
残業時間を過少申告する
従業員が自らの判断で残業時間を過少に申告する行為は、自主的な行動に見えますが、問題があります。
例:
- 背景に使用者からの暗黙のプレッシャーや、残業を抑制するような企業文化が存在する場合
- 遅くまで残っていると評価が下がる
- 残業するなと言われている
実際には業務が終わらずにサービス残業を行い、自己判断で申告時間を短くすることは、明らかな違法行為です。
始業前に業務を開始する
始業時間前に、自主的に出社して準備や情報収集などの業務を開始する行為も、サービス残業に該当する可能性があります。
例:
- 「早めに来て準備しておくと効率が良い」「他の人に迷惑をかけたくない」といった従業員の自発的な動機によるものであっても、その行為が日常化している
- 使用者が始業前の業務を認識しながら特に制止しない場合
- 始業時間直前では業務が回らないほど業務量が多い
このような始業前の時間もサービス残業とみなされるため、労働時間として適切に管理されるべきです。
自宅に仕事を持ち帰る
終業時間内に業務が終わらず、自宅に仕事を持ち帰って処理する行為は、一見すると自主的な行動に見えますが、これもサービス残業となる可能性が高いのです。
例:
- 会社の方針として持ち帰り残業が禁止されていない、または黙認されている
このような状況での持ち帰りは、会社の業務体制や人員配置の問題に起因する可能性があり、従業員の自主性に委ねるべきではありません。
サービス残業を黙認し常態化してしまう企業側のリスク
サービス残業を黙認し、その状態が常態化してしまうことは、企業にとってさまざまなリスクを引き起こします。
サービス残業の常態化は、法的責任はもちろんのこと、従業員のエンゲージメント低下や企業イメージの悪化など、長期的な成長を阻害する要因となりかねません。
労働基準法違反による罰則を受ける
サービス残業を放置することは、労働基準法に明確に違反する行為です。
| 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」
法定労働時間を超えるサービス残業に対して適切な割増賃金を支払わない場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
発生するリスク:
- 企業イメージを大きく損なうだけでなく、社会的信用を失墜させる
- 労働基準監督署からの指導や是正勧告を受け、企業名が公表される
従業員の負荷が増大する
サービス残業の常態化は、従業員の心身に大きな負担を与えます。
発生するリスク:
- 疲労の蓄積
- ストレスの増大
- 集中力や生産性の低下
- モチベーション低下
- エンゲージメントの低下
- 離職率の上昇
未払いの残業代を請求される
労働者は、過去に遡った未払い賃金の請求権利を有しており、その期間は原則として3年です。サービス残業の記録が残っていれば、請求される可能性があります。
発生するリスク:
- 多額の未払い残業代支払い
- 遅延損害金の支払い
企業文化の悪化と不正の温床
サービス残業が常態化している企業では、「残業するのが当たり前」「定時で帰る人は評価されない」といった歪んだ企業文化が形成されがちです。
発生するリスク:
- 従業員の主体性や創造性を阻害し、組織全体の活力を低下させる
- 労働時間の改ざんや虚偽の記録といった不正行為が行われる
採用活動への悪影響
近年、労働者の権利意識は高まっており、企業を選ぶ際に労働時間やサービス残業の有無は重要な判断基準の一つとなっています。
発生するリスク:
- 「ブラック企業」というレッテルを貼られやすい
- 優秀な人材の確保が困難
サービス残業の常態化を防ぐための対策
サービス残業を根絶し、健全な労働環境を構築するためには、企業全体で組織的かつ継続的な対策に取り組む必要があります。
サービス残業対策の基本:厚生労働省のガイドラインを参考に労務管理を徹底する
厚生労働省は、労働時間管理や割増賃金の支払いなどに関するさまざまなガイドラインを公表しています。
これらのガイドラインを遵守し、自社の労務管理体制を見直すことが、サービス残業防止の第一歩です。
具体的な対策:
- 労働時間の正確な把握
- 適切な休憩時間の確保
- 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の遵守
- 勤怠管理システムの導入や見直し
- 労働時間に関する研修の実施
ガイドラインを理解し、それに沿った運用を徹底することで、法的なリスクを低減し、従業員の権利保護につながります。
参考)厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
サービス残業の自主的な行動を抑制:残業を「許可制」にする
安易なサービス残業を抑制するために、残業を原則として「許可制」とすることが有効です。
具体的な対策:
- 残業が必要な場合は、事前に上長への申請と許可を必須とし、その理由や時間、業務内容を明確にする
- 上長は、申請内容を精査し、本当に必要な残業か判断する責任を持つ
この制度を導入する際には、手続きだけでなく、残業を申請しやすい風土づくりも重要です。
「サービス残業する人は頑張っている」といった誤った認識を改め、効率的な働き方を評価する文化の醸成が必要です。
サービス残業削減への意識改革:ノー残業デーを設ける
週に1日または複数日、全従業員が定時で退社する「ノー残業デー」を設けることは、サービス残業削減に向けた具体的なアクションとなります。
具体的な対策:
- 管理職も率先して定時退社する
- 業務が終わらない場合の対応策(業務の再分配、スケジュールの見直しなど)も事前に検討
ノー残業デーを設けることで、従業員のワークライフバランスを意識させ、時間内に業務を終わらせるための意識改革を促します。
サービス残業が生まれない組織づくり:企業体質の改善を図る
サービス残業の根本的な解決には、企業全体の体質改善が不可欠です。「長時間労働が当たり前」という企業文化や、「残業しないと評価されない」といった誤った評価制度を見直す必要があります。
具体的な対策:
- 業務の効率化を図るためのツール導入
- 業務プロセスの改善
- 適切な人員配置
- 多能工化などを推進
- 管理職のマネジメント能力向上
部下の業務状況を把握し、適切な指示やサポートを行うことで、残業時間の削減につなげられます。
サービス残業の早期発見・是正に繋げる:内部通報制度の整備と活用
サービス残業の隠れた実態を明らかにするためには、内部通報制度の整備と活用が不可欠です。従業員が安心してサービス残業の実態を報告できる環境を整えることで、早期発見・是正につながります。
具体的な対策:
- 匿名での通報を可能にする
- 通報窓口の多様化
- 通報者への保護措置の明確化
- 通報内容への迅速かつ適切な対応
制度を整備するだけでなく、従業員に周知し、実際に活用されるよう啓発活動を行うことも重要です。
従業員一人ひとりの意識改革と、それを支える組織的な取り組みが、サービス残業のない健全な企業文化の醸成につながります。
まとめ
この記事では、中小企業に向け、自主的なサービス残業がもたらす法的なリスク、従業員への悪影響、そして企業全体の持続可能性を損なう可能性について解説しました。
「本人の意思」という言葉は、サービス残業を正当化する理由にはなりません。
労働基準法は、従業員の保護を第一に考えており、実質的に業務を強いられる状況下での労働は、たとえ自主的な申告であっても違法と判断される可能性があります。
サービス残業の常態化は、罰則や訴訟リスクだけでなく、従業員のエンゲージメント低下や離職、企業イメージの悪化といった、目に見えない損失にもつながります。
今こそ、労務管理体制を見直し、残業の許可制導入やノー残業デーの設定、そして何よりも従業員が安心して働ける企業文化を醸成することが、中小企業の持続的な成長に不可欠なのです。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録