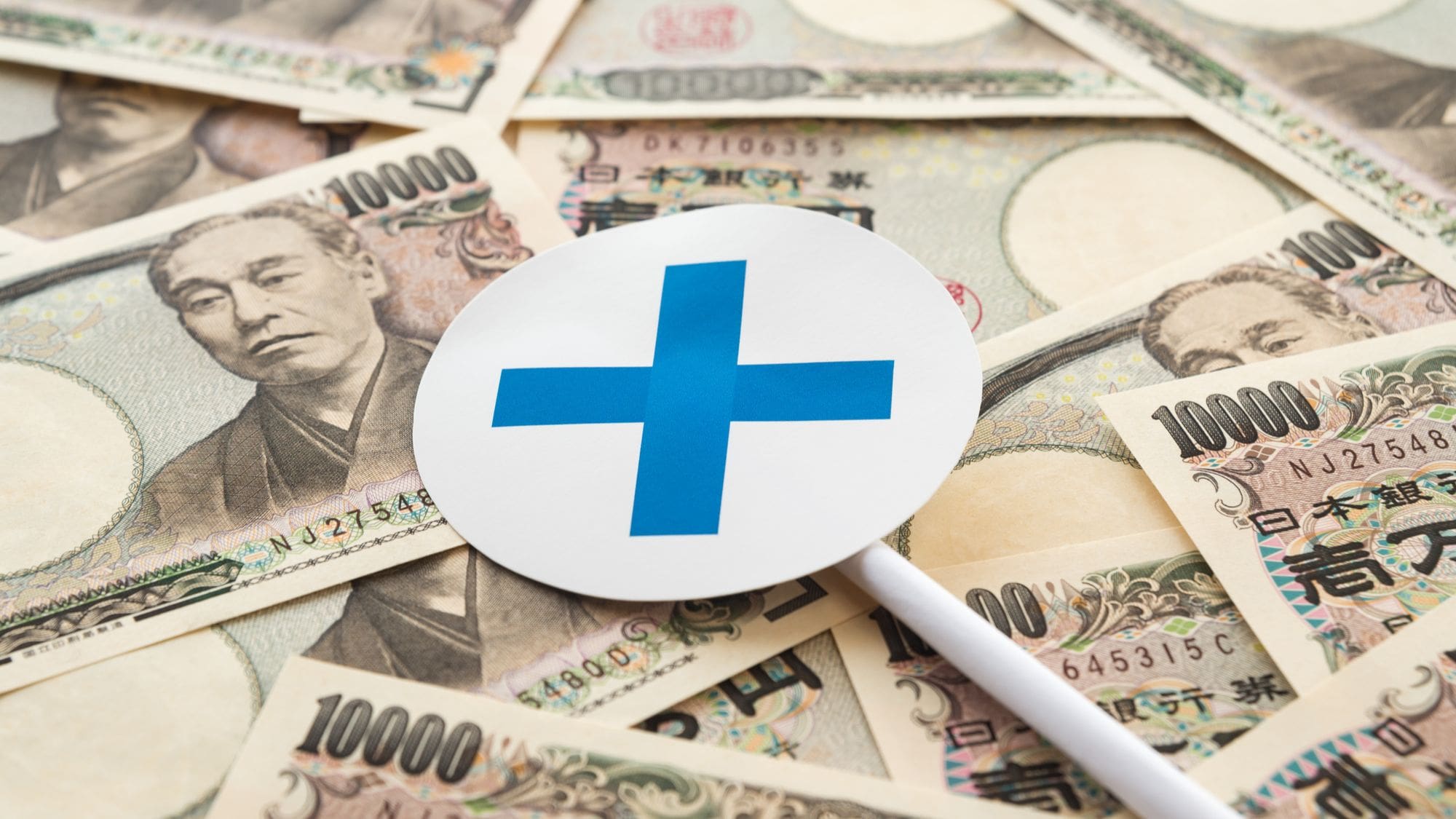個人情報保護法に違反したときの罰則は?対象の条文と一緒に企業がとるべき対策を解説

近年、特に企業には個人情報の適切な管理が求められています。特に中小企業も例外ではなく、「知らなかった」では済まされないのが現実です。
本記事では、個人情報保護法に違反した場合の罰則内容を、該当する条文とともにわかりやすく解説。あわせて、中小企業がとるべき対策や実際の違反事例も紹介します。
リスクを未然に防ぐためにも、ぜひご一読ください。
目次
そもそも個人情報保護法とは?中小企業に課せられる責任
個人情報保護法とは、個人の氏名や住所、顔写真、指紋情報など、特定の個人を識別できる情報を適切に扱うためのルールを定めた法律です。
2005年に施行され、改正を重ねながら現在はすべての事業者が対象となります。中小企業であっても「個人情報」を扱う以上、法令遵守は当然の責務です。
そのため、社内体制の整備や社員教育も含めた取り組みが求められます。以下に基本事項をまとめました。
| 項目 | 内容 |
| 制定年 | 平成15年(2003年)制定、平成17年(2005年)施行 |
| 法の目的 | 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利と利益を保護すること |
| 適用対象 | 公的機関・民間事業者を問わず、すべての個人情報取扱事業者 |
| 主な対象情報 | 氏名、住所、メールアドレス、電話番号、顔写真、指紋、マイナンバーなど |
| 中小企業の責任 | 安全管理措置、社員教育、本人同意の取得、漏えい時の報告義務など |
出典)政府広報オンライン「「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは?」
本法律は、たとえ社員数が少なくても、名簿管理や顧客対応の中で個人情報を扱う事業者すべてに適用される点が重要です。
【違反したらどうなる】個人情報保護法の主な罰則一覧
個人情報保護法に違反すると、企業や個人に対して行政処分や刑事罰が科されることがあります。
罰則は違反の内容や悪質性に応じて異なる点に注意です。命令違反、故意による持ち出し、立入検査拒否など、それぞれに該当する条文と罰則内容が明確に定められています。
主要な違反パターン別に罰則の内容を整理しましたので参考にしてください。
個人情報保護委員会の命令に違反した場合
個人情報保護委員会は、個人の権利利益を守るため、違反事業者に対して勧告・命令を行います。緊急性が高い場合は、勧告なしで即命令が出されることもあるため注意しましょう。
命令に従わなかった場合、法人には最大1億円の罰金、個人には懲役刑が科されることがあります。
| 項目 | 内容 |
| 該当条文 | 第148条、184条 |
| 命令の対象 | 違反行為の是正、再発防止措置等 |
| 個人への罰則 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 法人への罰則 | 1億円以下の罰金 |
出典)e-GOV「個人情報の保護に関する法律」
不正目的で個人情報を流用・持ち出した場合
業務上知り得た個人情報を、本人の同意なく不正に提供・盗用した場合は、刑事罰の対象です。
たとえ退職後の元社員であっても、違法行為であれば法人側も罰せられる可能性があります。目的の不当性が問われるため、特に重い処罰が科される点がポイントです。
| 項目 | 内容 |
| 該当条文 | 第179条、184条 |
| 命令の対象 | 不正目的での提供・盗用 |
| 個人への罰則 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 法人への罰則 | 1億円以下の罰金 |
出典)e-GOV「個人情報の保護に関する法律」
立入検査や報告義務への違反
個人情報保護委員会は、事業者に報告や資料提出を求めたり、立入検査を行う権限を持ちます。
これらに正当な理由なく応じなかったり、虚偽の報告をした場合は、法人・個人ともに罰則対象です。調査対応における誠実さが問われます。
| 項目 | 内容 |
| 該当条文 | 第146条、182条、184条 |
| 命令の対象 | 虚偽報告、検査拒否、質問に答えない等 |
| 個人への罰則 | 50万円以下の罰金(虚偽等であれば懲役6か月以下または罰金30万円以下) |
| 法人への罰則 | 50万円以下の罰金 |
出典)e-GOV「個人情報の保護に関する法律」
罰則が適用されるまでの流れ
個人情報保護法に違反しても、直ちに刑事罰が科されるわけではありません。
まずは個人情報保護委員会による調査や勧告が行われ、それでも是正されない場合に命令や罰則が適用されます。以下に具体的な流れをまとめました。
| 項目 | 内容 |
| ① 調査・検査 | 個人情報保護委員会による報告徴収や立入検査 |
| ② 勧告 | 是正や再発防止を求める行政指導 |
| ③ 命令 | 勧告に従わない場合に命令 |
| ④ 刑事告発・罰則 | 命令違反や重大な違反に対し刑事罰適用 |
委員会からの連絡には迅速・誠実に対応することで、事態の深刻化を防げます。
中小企業がとるべき個人情報保護の具体的対策
中小企業でも個人情報の取り扱いは厳格に行うことが必要です。基本的なセキュリティ対策だけでなく、社内ルールや教育体制の整備が求められます。
以下のポイントを押さえて、組織全体でリスクを最小化しましょう。
| 項目 | 内容 |
| 利用目的の明確化 | 収集時に利用目的を特定し、本人に通知または公表 |
| 安全管理措置 | パスワード管理、キャビネット施錠、アクセス権の設定など |
| 従業員教育 | 個人情報の扱い方、違反時のリスク、守るべきルールを定期教育 |
| 委託先の監督 | 委託契約時に個人情報保護の条項を明記し、適切な監督を行う |
| 漏えい時の対応体制 | 委員会への報告・本人通知フローを事前に整備 |
“知らなかった”では済まされない時代です。組織的な対応こそが最大の予防策といえます。
個人情報保護法違反に関する相談はどこにすべき?
万が一、個人情報保護法に違反するような取り扱いが疑われる場合、中小企業はどこに相談すべきなのでしょうか。主な相談先は、個人情報保護委員会が設置する「個人情報保護法相談ダイヤル」です。
個人情報保護法相談ダイヤルの基本情報は以下になります。
| 項目 | 内容 |
| 電話番号 | 03-6457-9849 |
| 受付時間 | 9:30~17:30(土日祝日・年末年始を除く) |
出典)個人情報保護委員会「個人情報保護法相談ダイヤル」
また、24時間対応のPPC質問チャットも用意されており、基本的な制度に関する疑問は気軽に解消できます。
出典)個人情報保護委員会「PPC質問チャット」
そのほか、よくある質問に関しては個人情報保護委員会のページから検索・確認することも可能です。
出典)個人情報保護委員会「FAQ索引」
中小企業に起きた個人情報保護法違反の事例
実際に中小企業でも、名簿の管理ミスや委託先の不備により個人情報漏えいが発生しています。下記は代表的な違反事例です。
新破産者マップ
破産手続き開始決定を受けた個人の氏名や住所などを、本人の同意なく地図付きでウェブ上に公開した事業者の事例になります。
個人情報保護委員会が勧告・命令を実施し、命令に従わなかったことで刑事告発へと至りました。情報を盾に金銭を要求する行為も行われており、極めて悪質な違反事例です。
出典)個人情報保護委員会「個人情報保護法の違反行為に係る事例等(個人データの違法な第三者提供等、その他)」
名簿販売業者の個人情報購入
不正に持ち出された個人データを、複数の名簿販売業者が購入・流通させていた事案です。
名簿提供時に記録を残さなかったほか、再委託先での管理もずさんであったため、個人情報保護委員会は事業者に対して再指導を実施しました。確認義務違反や不適正取得など、複数の違反が認定された事例になります。
出典)個人情報保護委員会「個人情報保護法の違反行為に係る事例等(個人データの違法な第三者提供等、その他)」
コールセンターサービスの不正持ち出し
コールセンターサービス事業者と、その関連事業者の委託先従業員によって、約928万人分もの個人情報が不正に持ち出された大規模な事案です。
安全管理措置や委託先監督の不備が原因とされ、複数の事業者に対して勧告・指導・報告徴収が行われました。再発防止策の徹底が求められています。
出典)個人情報保護委員会「個人情報保護法の違反行為に係る事例等(個人データの違法な第三者提供等、その他)」
まとめ
個人情報保護法は、企業の規模を問わずすべての事業者に適用される法律です。違反すれば、勧告や命令だけでなく、場合によっては重い罰則や刑事告発を受けることもあります。
中小企業にとっては「知らなかった」では済まされません。適切な管理体制や教育、記録の整備が求められます。
日常的な運用と監査の仕組みを今一度見直し、法令遵守の体制を強化しましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録