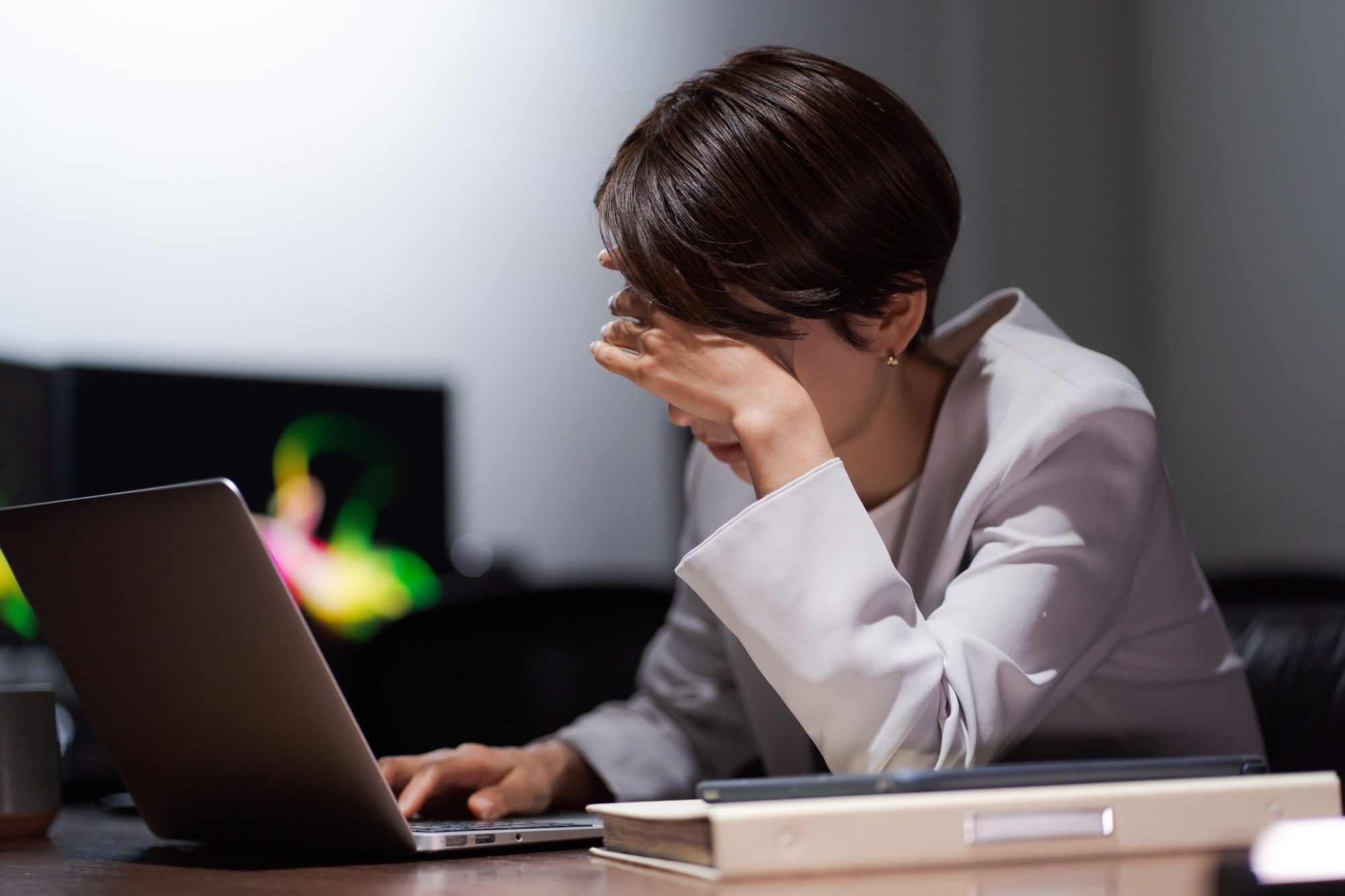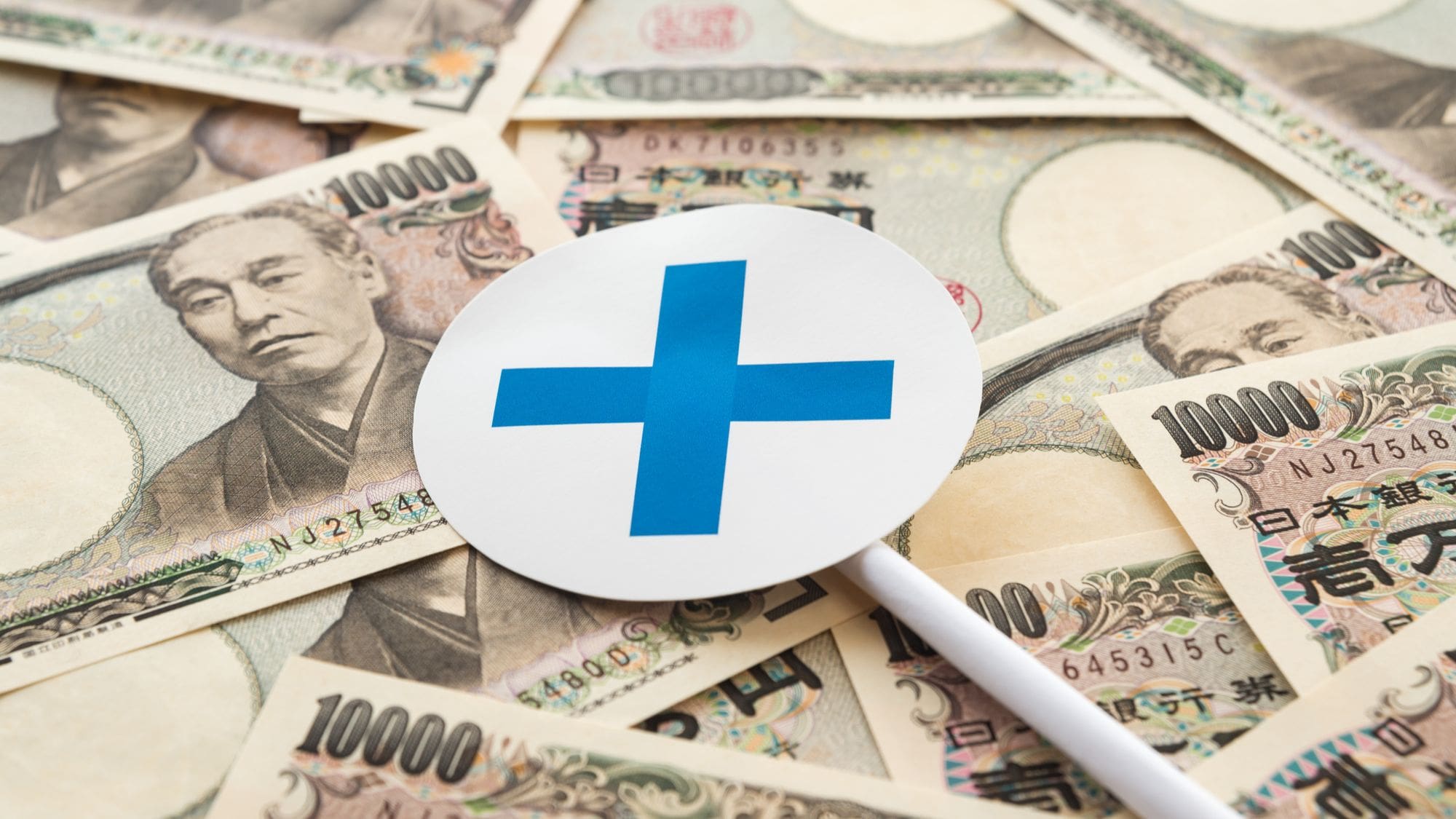4月・5月・6月は残業しないほうがよい月?社会保険との関係を解説

従業員の「残業」について、とくに4月・5月・6月は注意が必要だと聞いたことのある方がいるかもしれません。
4月・5月・6月が「残業しないほうがよい月」と言われるのには、社会保険料の計算が深く関わっています。
4月・5月・6月の残業が、社会保険料にどのくらい影響を与えるのか、社会保険料の負担軽減以外にも残業をしないほうがよい理由について、わかりやすく解説します。
目次
4月・5月・6月が「残業しないほうがよい月」と言われる理由
特定の時期の残業には注意が必要です。とくに4月、5月、6月は「残業しないほうがよい月」と言われることがあります。
この時期の残業が、その後の約1年間の社会保険料にどう影響するのか、詳しく解説します。
社会保険料の計算方法
社会保険料は、月ごとの給与額に直接料率をかけているわけではありません。基準となるのは「標準報酬月額」と呼ばれる金額です。
ただし、実際の給与額ではなく、国が定めた等級表にあてはめて決定されます。たとえば、報酬月額が22万円であれば、標準報酬月額は22万円の等級となります。
参考)厚生労働省 年金局「標準報酬月額の上限」
決定した「標準報酬月額」は、原則として年に一度見直しがおこなわれ、基準となるのが毎月の「報酬」です。
| 厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。 |
出典)日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
「報酬」とは、労働の対価として受け取るものすべてを指し、基本給はもちろんのこと、役職手当、通勤手当、家族手当、残業代も「報酬」に含まれるという点に注意が必要です。
4月・5月・6月の給与が年間の社会保険料に影響する理由
標準報酬月額を決めるための年1回の見直しは「定時決定」と呼ばれます。この定時決定において、翌1年間の標準報酬月額を計算するために参照されるのが、4月・5月・6月の3か月間に支払われた給与の平均額なのです。
| 毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)。 |
出典)日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
具体的には、4月、5月、6月に支払われた給与をもとに標準報酬月額を算出し、等級表にあてはめて標準報酬月額を決定します。この金額は、原則としてその年の9月から翌年の8月までの1年間にわたって適用されます。
つまり、もし3か月間の残業代を含む給与が高くなった場合、高い給与平均に基づいて計算された標準報酬月額が、その後の1年間に適用されることになるのです。
このメカニズムこそが、「残業しないほうがよい月」と言われる最大の理由です。
定時決定以外にも、被保険者の資格取得時や昇給や降給、役職手当の変更、あるいは毎月の残業時間の恒常的な増加・減少などにより、固定的賃金に大きな変動があった場合の随時改定があります。
これら改定の仕組みでは、4月・5月・6月の残業状況だけでなく、年間を通して影響を与える可能性があると言えます。
給与が翌月払いならば3月も残業をしないほうがよい月に含まれる
多くの企業では、たとえば「月末締め、翌月25日払い」のように、働いた月の翌月に給与を支払う「翌月払い」を採用しています。
もし会社が「月末締め、翌月払い」の場合、以下のようになります。
- 4月に支払われる給与には、通常3月分の残業代が含まれる
- 5月に支払われる給与には、通常4月分の残業代が含まれる
- 6月に支払われる給与には、通常5月分の残業代が含まれる
つまり、給与が翌月払いの企業では、標準報酬月額の算定に影響するのは、厳密には3月・4月・5月の残業となるのです。3月も残業しないほうがよい月に含まれるのは、翌月払い方式を前提としている企業です。
4月・5月・6月に残業しないことで社会保険料はどのくらい変わる?
標準報酬月額の仕組みを踏まえると、4月・5月・6月に残業を極力減らす、あるいは残業しないように努めることで、給与総額を抑えることが可能になります。
具体的な社会保険料の差額は、従業員の現在の給与水準、適用される社会保険料率によって変動するため、一概にいくら変わるか断定できません。
しかし、普段はあまり残業しない従業員が、4月・5月・6月の間に集中的に残業をしてしまい、この3か月間の平均給与が一時的に大きく跳ね上がった場合、標準報酬月額が高い等級で設定されてしまうリスクがあります。
従業員一人あたりと会社負担分と合わせると、年間で数万円から10万円程度の社会保険料が追加される可能性があり、中小企業にとっては決して小さくない負担となり得ます。
このコスト削減を考え、4月・5月・6月を「残業しないほうがよい月」としているのです。
4月・5月・6月だけじゃない!残業しないほうがよい理由
4月・5月・6月(あるいは翌月払いの場合の3月・4月・5月)の残業が、その後の1年間の社会保険料負担に大きく影響します。
しかし、「残業をしないほうがよい理由」は、社会保険料負担の軽減だけにとどまりません。経営者として、従業員が過度な残業をせずに働ける環境を整備することは、多方面にわたるメリットとリスク回避につながります。
ここでは、社会保険料以外の観点から見た、残業を抑制することの重要性をご説明します。
残業をしないほうがよい理由①従業員の健康維持と生産性向上
長時間の残業は、従業員の心身の健康を損なう大きな要因となります。疲労の蓄積は集中力の低下やミスを招きやすく、長期化すれば過労による健康障害や精神的な不調につながるリスクを高めます。
従業員が健康でいきいきと働けることは、中小企業にとって何よりの財産です。健康を害して休職や離職が増えれば、代替要員の確保や業務の引き継ぎなどで、企業は新たなコストと負担を強いられます。
残業を減らし、従業員の健康を守ることは、結果として欠勤率の低下やモチベーション向上につながり、全体の生産性を高めることになります。
残業をしないほうがよい理由②法令遵守とリスク管理
労働基準法では、労働時間の上限や残業に関するルールが定められており、36協定の範囲を超える違法な長時間労働や、適切な残業代の支払いを怠ることは、法令違反となります。
近年、「働き方改革」の推進により、残業時間の上限規制が設けられるなど、コンプライアンスへの要求は一層厳しくなっています。
法令遵守は企業の信頼性にかかわるだけでなく、違反が発覚すれば罰金や企業名公表といった重いペナルティもあり、中小企業の経営を揺るがしかねません。
過度な残業を抑制することは、こうした法的リスクを回避し、健全な企業運営をおこなう上で不可欠です。
残業をしないほうがよい理由③企業文化の醸成と採用・定着力の強化
慢性的な長時間労働が当たり前になっている企業文化は、従業員のエンゲージメントを低下させ、離職率を高める傾向にあります。とくに、ワークライフバランスを重視する現代の求職者にとって、過度な残業は敬遠される大きな要因となります。
残業を減らし、決められた時間内で最大のパフォーマンスを出すという意識を共有することで、より効率的でメリハリのある働き方が根付くのです。
このような企業文化は、従業員の満足度を高め、優秀な人材の流出を防ぐだけでなく、新たな人材採用においても企業の大きな魅力となります。採用難に直面する中小企業にとって、残業の少ない働きやすい環境は、競争力強化につながるのです。
残業をしないほうがよい理由④派遣社員やパート・アルバイトの場合
残業しないほうがよい月についての基本的な考え方は、派遣社員やパート・アルバイトの方々も、正社員と同様です。
社会保険の加入要件を満たしている場合、派遣社員などの報酬も標準報酬月額の算定に影響します。
派遣社員についても、健康管理、生産性、契約内容に基づく適正な残業管理は、委託元である中小企業としても配慮すべき点です。
まとめ
この記事では、4月・5月・6月の残業が社会保険料の標準報酬月額にどう影響し、どのくらい変わるかを解説しました。これは中小企業のコスト負担に直結します。
社会保険料だけでなく、従業員の健康や生産性向上のためにも残業をしないほうがよい理由は多数存在します。
4月・5月・6月を意識しつつ、年間を通じた適切な残業管理で、健全な経営を目指す必要があるのです。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録