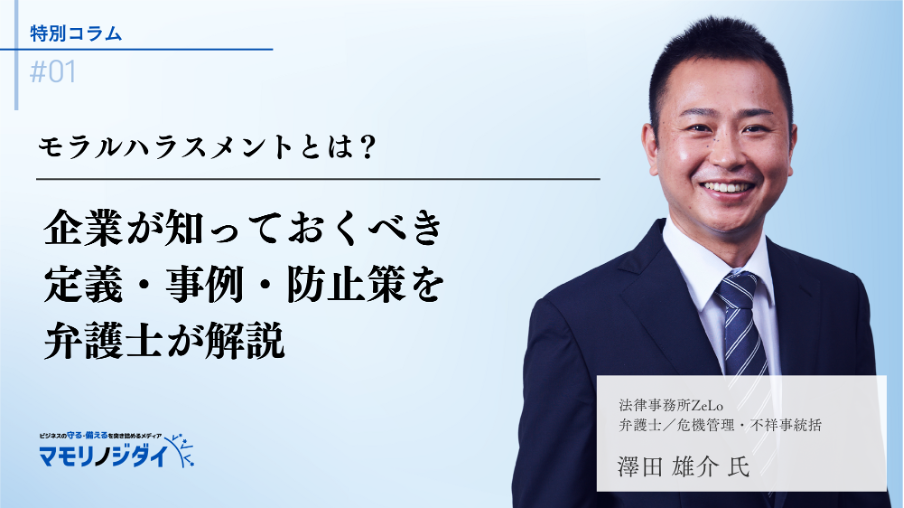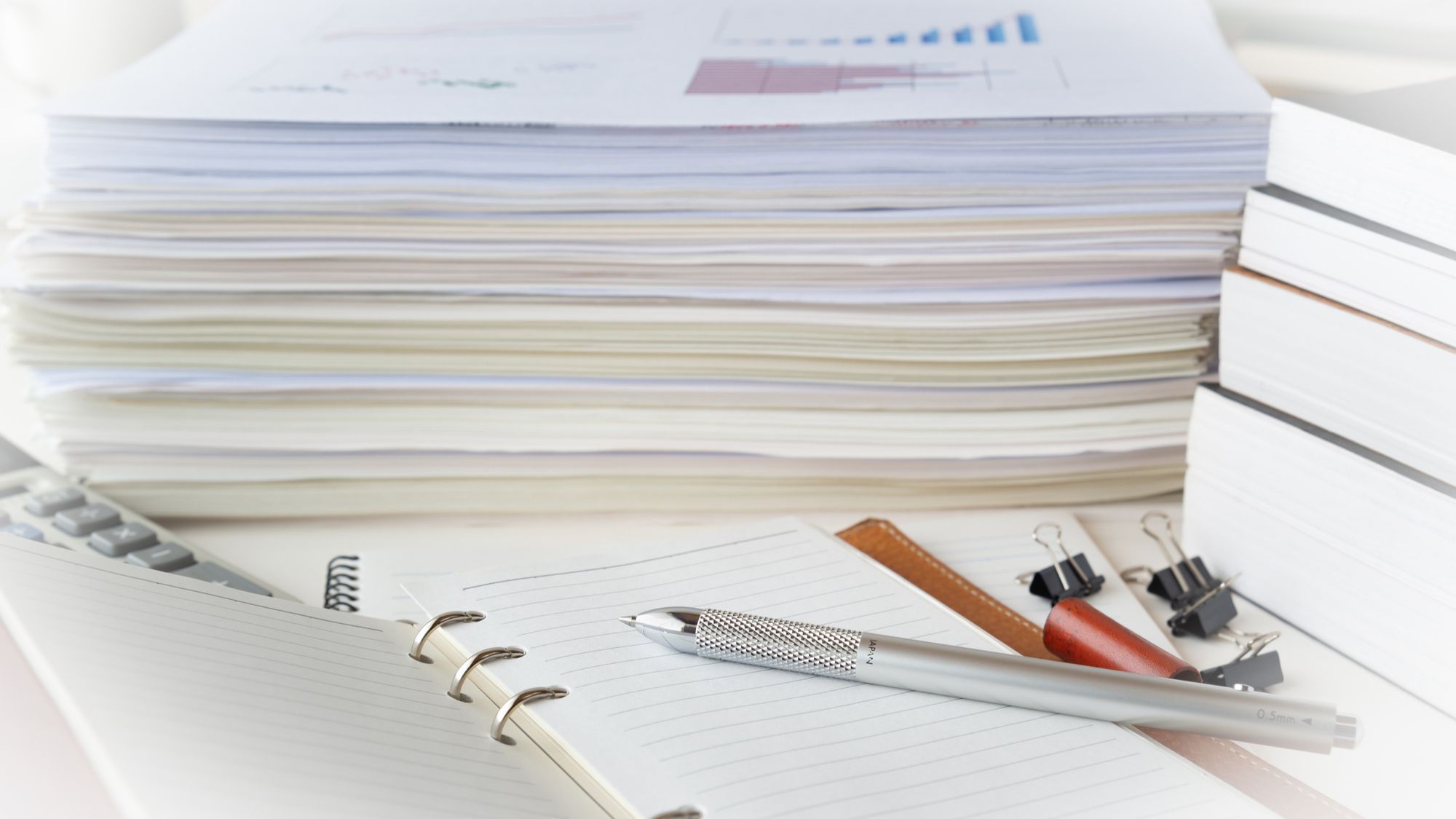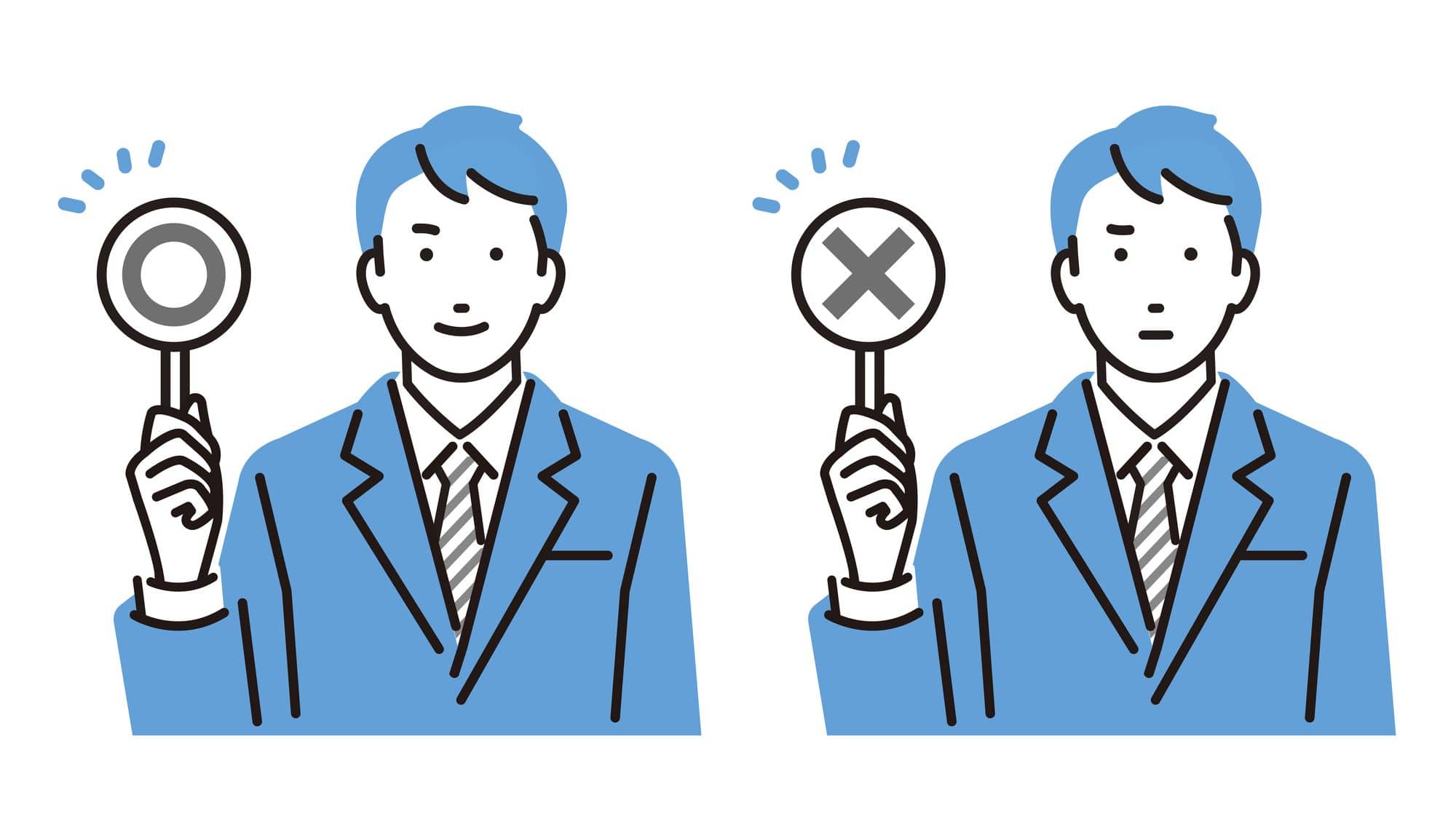労働安全衛生法の健康診断の義務とは?ルールを理解して安定した雇用を実現

労働者の健康を守ることは、企業の重要な責務です。労働安全衛生法では、事業者に労働者への健康診断実施を義務付けており、単なる形式的なものではありません。
労働者の健康状態を定期的に把握し、疾病の早期発見や健康障害の予防につなげることで、労働災害を防ぎ、安心して働き続けられる職場環境を整備するために不可欠な措置です。
労働安全衛生法に基づき健康診断のルールを正しく理解し、適切に実施することは、法令遵守はもちろん、労働者の信頼を得て安定した雇用関係を築く上でも重要なポイントとなります。
この記事では、労働安全衛生法における健康診断の義務、未実施のリスクと罰則、中小企業が適切に実施するための具体的なポイントを解説します。
目次
労働安全衛生法における健康診断の基礎知識
ここでは、労働安全衛生法の基本的な考え方と、健康診断がどのように位置づけられているのか、義務付けの理由について解説します。
労働安全衛生法とは?健康診断の位置づけ
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成促進を目的とした法律です。
労働安全衛生法は、労働者の健康管理や安全衛生教育、メンタルヘルス対策に至るまで、広範な分野をカバーしています。
中でも健康診断は、労働者の健康状態を把握し、健康保持・増進を図るための基本的な手段として、労働安全衛生法において明確に事業者の義務として規定されているのです。
具体的には、労働安全衛生法第66条で事業者は労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければならないと定められており、これは企業の規模にかかわらずすべての事業者に適用されます。
なぜ健康診断は義務なのか?労働安全衛生法の目的と企業の責任
労働安全衛生法第66条で事業者は労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければならないと定められており、これは企業の規模にかかわらずすべての事業者に適用されます。
| (健康診断)第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。 |
出典)e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」
また、企業には、労働契約法第5条に基づき、労働者への安全配慮義務があるのです。
| (労働者の安全への配慮)第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 |
出典)e-Gov 法令検索「労働契約法」
健康診断の実施は、この安全配慮義務を具体的に果たすための重要な手段の一つと位置づけられています。
労働安全衛生法における健康診断の種類
労働安全衛生法で定められている健康診断は、対象となる労働者や業務内容、実施のタイミングによっていくつかの種類に分けられます。ここでは、それぞれの健康診断の概要、対象者、主な目的について解説します。
一般健康診断
一般健康診断は、業種や職種にかかわらず、常時使用するすべての労働者を対象として定期的に実施される、最も基本的な健康診断です。労働者の一般的な健康状態を把握し、生活習慣病の予防や早期発見、健康の保持増進を目的としています。
一般健康診断には、主に以下の種類があります。
| 健康診断の種類 | 内容 | 根拠となる法令 |
| 雇入時の健康診断 | 常時使用する労働者を雇い入れる際に実施 | 労働安全衛生規則第43条 |
| 定期健康診断 | 常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期的に実施 | 労働安全衛生規則第44条 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際および6か月以内ごとに1回、定期的に実施 | 労働安全衛生規則第45条 |
| 海外派遣労働者の健康診断 | 労働者を海外の地域に6か月以上派遣しようとするとき、および海外に6か月以上派遣した労働者を帰国させ国内業務に就かせる際に実施 | 労働安全衛生規則第45条の2 |
| 結核健康診断 | 定期健康診断などで結核発病のおそれがあると診断された労働者に対し、おおむね6か月後に実施 | 労働安全衛生規則第46条 |
| 給食従業員の検便 | 事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務への配置替えの際 | 労働安全衛生規則第47条 |
参考)e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」
これらの健康診断の検査項目は、労働安全衛生規則で定められていますが、医師が必要でないと認める場合には一部省略できる項目もあります。
特殊健康診断
特殊健康診断には、以下の2種類が含まれます。
| 健康診断の種類 | 内容 | 根拠となる法令 |
| 特定の有害な業務に常時従事する労働者に対する健康診断 | 高圧室内作業、潜水業務、放射線業務、特定化学物質を取り扱う業務などに常時従事する労働者に対して実施 | 安全衛生法第66条第2項および第3項 |
| じん肺健康診断 | 粉じん作業に常時従事する労働者、または過去に従事した経験のある労働者に対して実施 | じん肺法 |
参考)e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」
e-Gov 法令検索「じん肺法」
労働安全衛生法における健康診断の未実施リスクと罰則
事業者がこの健康診断の実施義務を怠った場合、単に労働安全衛生法の法律違反となるだけでなく、さまざまなリスクを負うことになります。
ここでは、労働安全衛生法における健康診断の未実施がもたらすリスクと、それに伴う罰則について解説します。
健康診断未実施のリスク
事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断の実施義務を怠った場合、以下のような多岐にわたるリスクが発生します。
- 労働者の健康障害発生リスク
- 安全配慮義務違反
- 企業イメージ・信用の低下
- 行政指導・罰則
- 訴訟リスクの増大
健康診断未実施に対する罰則
労働安全衛生法第120条では、第66条の規定に違反した者(事業者等)は、50万円以下の罰金に処すると定められています。
この罰則は、法人の代表者や、実際に健康診断の実施に関する責任を負う担当者個人にも科される可能性があるのです。
また、労働安全衛生法第122条には両罰規定があり、法人の業務に関して違反行為が行われた場合、行為者とその法人に対しても罰金刑が科されます。
参考)e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」
労働安全衛生法に基づき中小企業が健康診断を適切に実施するためのポイント
リソースが限られがちな中小企業においては、計画的かつ効率的に健康診断を実施するためのポイントを押さえておくことが重要となります。
ここでは、労働安全衛生法に基づき、中小企業が健康診断を適切に実施するための具体的なステップと注意点について解説します。
健康診断の実施プロセス
中小企業が労働安全衛生法に基づき、健康診断を適切に実施するための最初のステップは、実施プロセスの確立です。
参考)e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」
1.対象者の確認
健康診断の対象となる「常時使用する労働者」を正確に把握します。パートタイマーやアルバイトでも、1週間の所定労働時間が常勤労働者の4分の3以上である場合は、原則として健康診断の対象となります。
2.実施する健康診断の種類
労働安全衛生法に基づき、主に以下の健康診断が必要です。
- 雇入れ時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
3.実施体制の準備
- 提携できる医療機関(健診機関)を選定
- 日程を調整
- 法令で義務付けられている健康診断の費用は、原則として事業者が負担
4.労働者への周知と受診勧奨
労働者に対し、健康診断の重要性、実施日時、場所などを事前に周知します。受診は労働者の義務でもあるため、必ず受診するよう丁寧に勧奨することが重要です。
受診率向上のために、勤務時間中の受診を認めたり、特定の期間内に受診を完了するよう促したりする工夫も有効です。
健康診断結果の記録と保存に関する注意点
健康診断を実施した後は、結果を適切に記録し、保存することが義務付けられています。
- 記録義務
事業者は、健康診断の結果を「健康診断個人票」に記録しなければなりません。この様式は厚生労働省によって定められています。
参考)厚生労働省「労働安全衛生規則関係様式」
- 保存期間
健康診断個人票は、5年間保存することが義務付けられています。これは労働安全衛生規則第51条で定められています。
参考)e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」
医師の意見聴取と事後措置
健康診断の結果、異常所見(有所見者)があった労働者に対しては、医師からの意見を聴取し、必要に応じて就業上の措置を講じる必要があります。
| 必要な措置 | 内容 | 根拠となる法令 |
| 労働者本人への結果通知 | 健康診断の結果は、必ず労働者本人に通知 | 労働安全衛生法第66条の6 |
| 医師の意見聴取 | 健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な就業上の措置について意見を聴く | 労働安全衛生法第66条の4 |
| 就業上の措置の実施 | 作業内容の変更、労働時間の短縮、配置転換、深夜業の回数減少など | 労働安全衛生法第66条の5 |
| 保健指導 | 健康診断の結果、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対しては、医師または保健師による保健指導を行うよう努める | 労働安全衛生法第66条の7 |
参考)e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」
健康診断におけるプライバシー保護
健康診断の結果は、個人の疾病情報を含む非常にセンシティブな個人情報です。事業者は、健康診断を実施する過程および結果の管理において、労働者のプライバシー保護に最大限配慮する義務があります。
- 目的外利用の禁止
- 秘密の保持
- 適切な管理
プライバシー保護は重要ですが、事業者の安全配慮義務を果たすためには、労働者の健康状態を把握し、リスクに応じた措置を講じることが不可欠です。
労働安全衛生法は、労働者の健康情報を安全配慮義務の履行に必要な範囲で事業者が利用することを認めています。しかし、利用目的を明確にし、必要最小限の情報に留めるなど、適切に取り扱うことが大切です。
まとめ
労働安全衛生法に基づく健康診断の実施は、すべての事業者に課された法的義務です。この義務を果たすことは、労働者の健康を守り、安全配慮義務を履行するために不可欠であり、未実施の場合には重いリスクや罰則が伴います。
とくに中小企業においては、健康診断を適切に実施し、結果を職場の健康管理に活かすことが、労働者が安心して働ける環境につながります。これが、労働者の健康と企業の持続的な発展、安定した雇用を実現するための基盤となるのです。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録