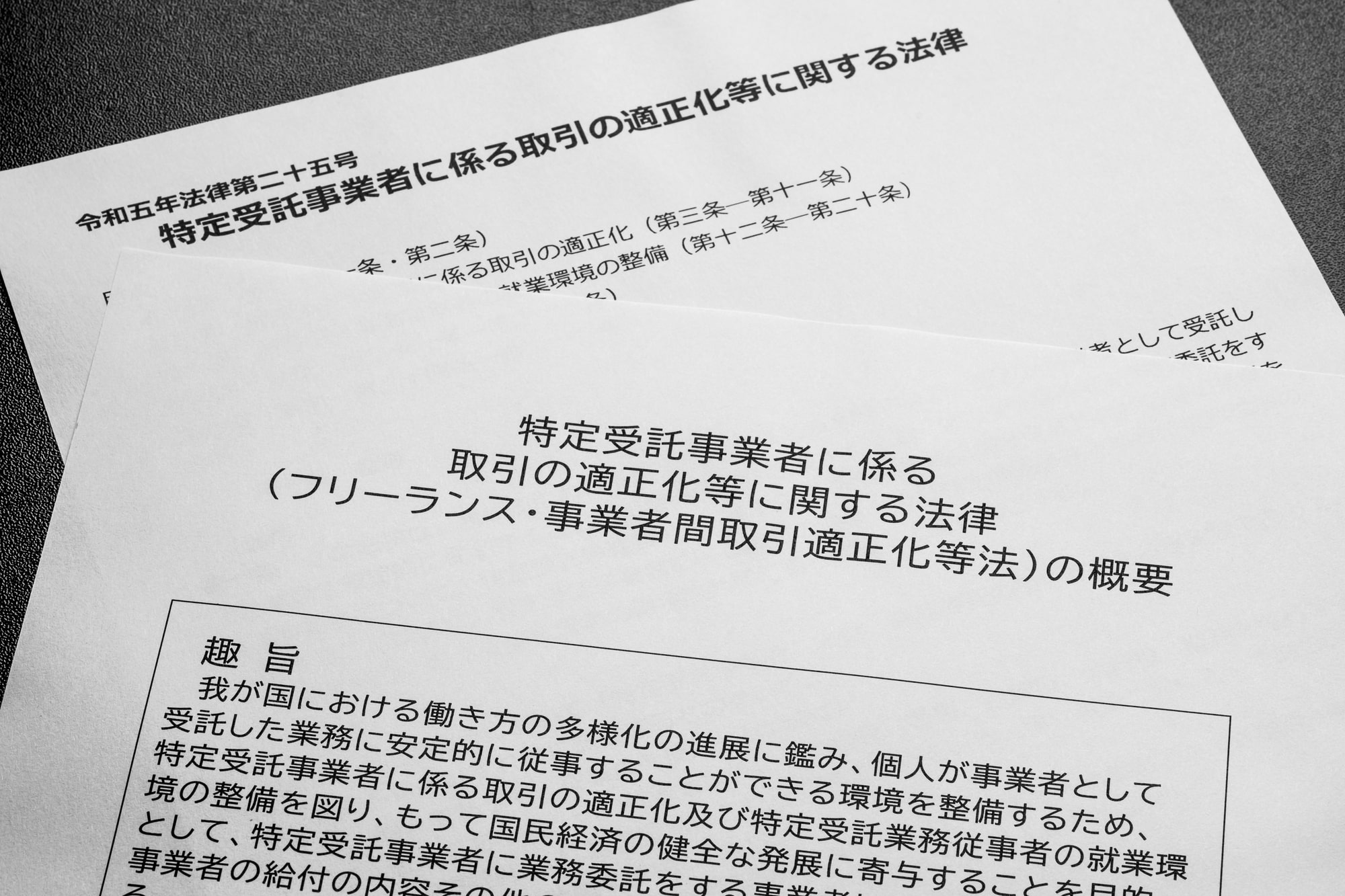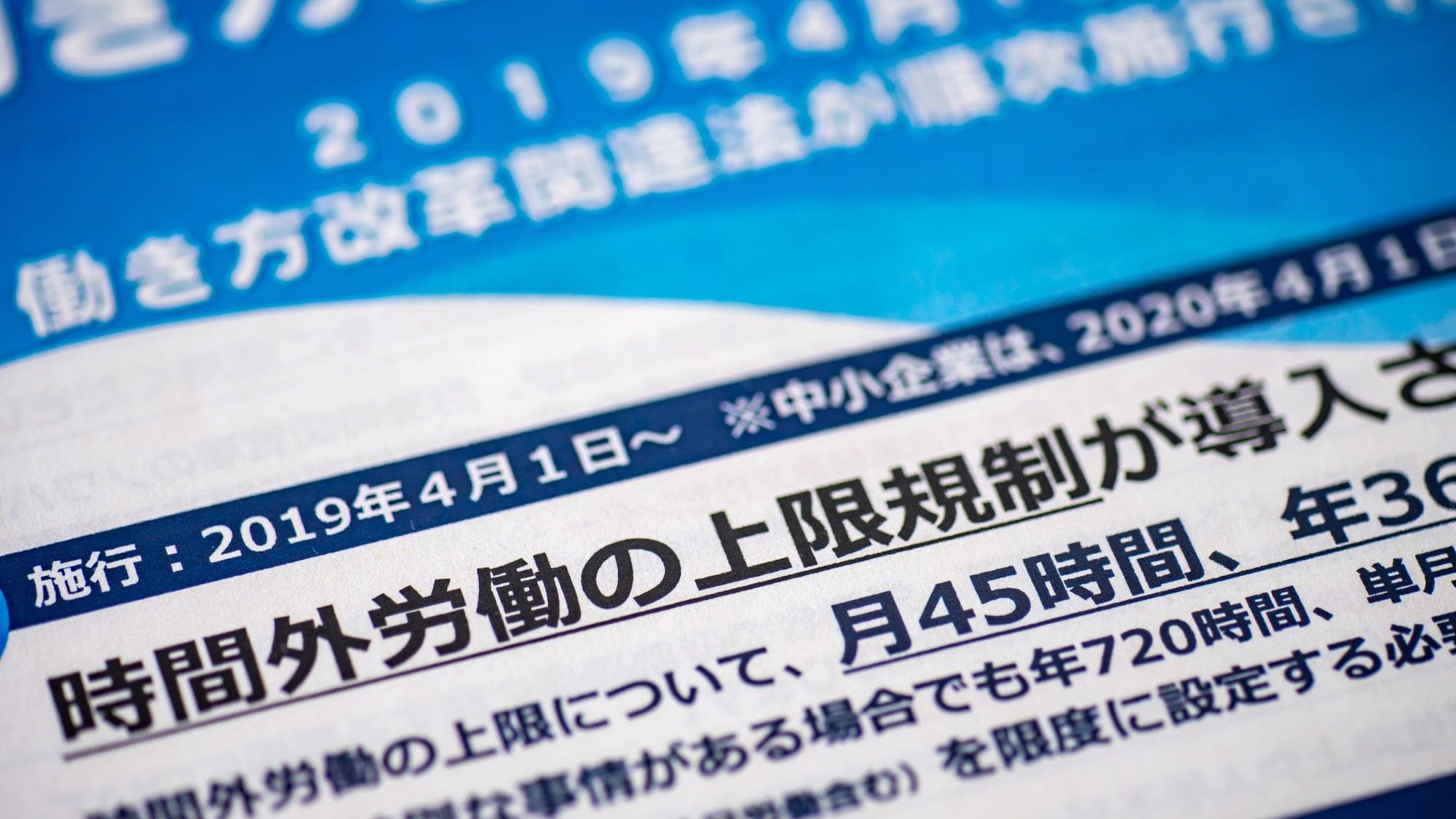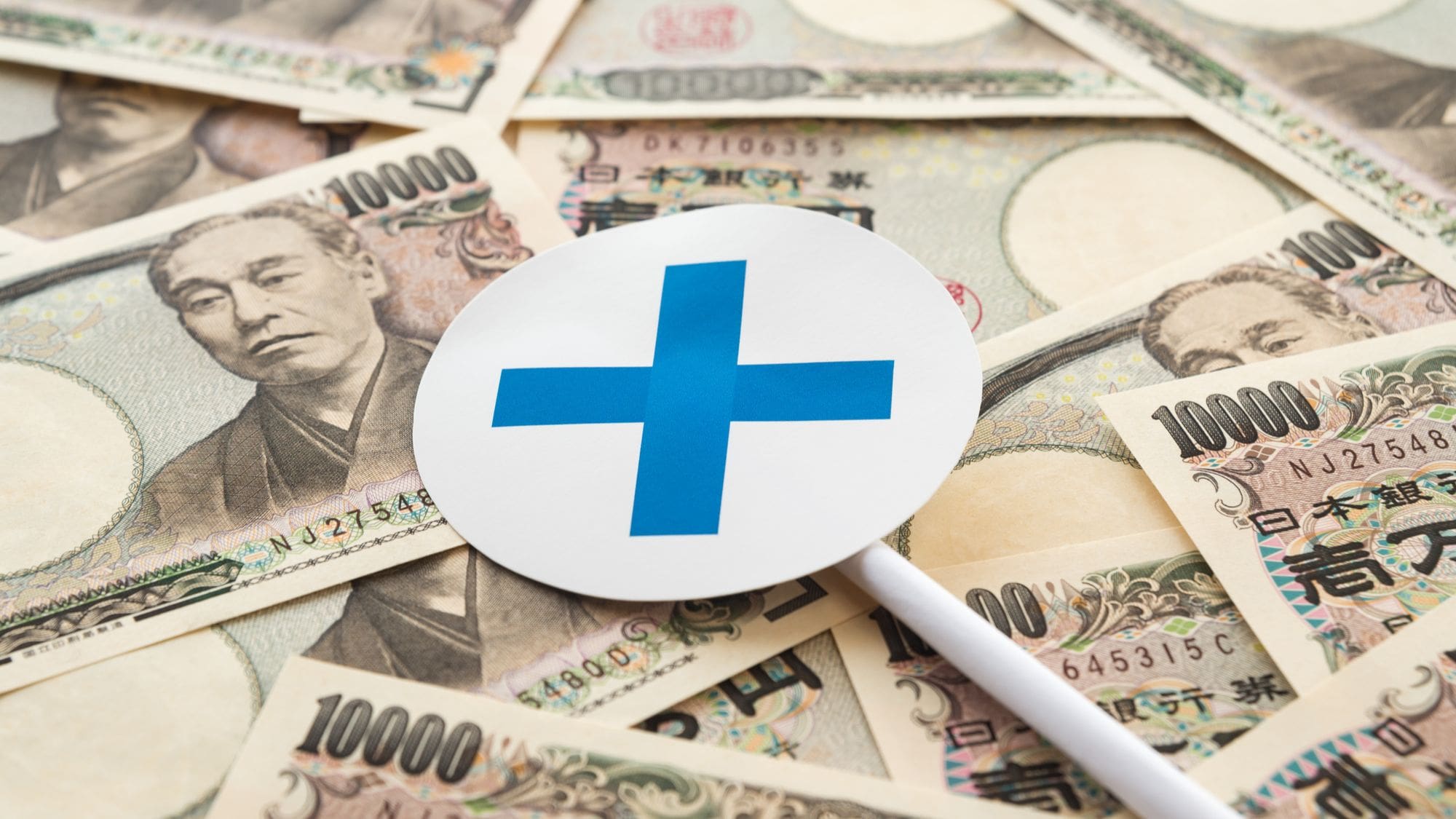【最新】下請法テキストで確認すべき違反事例と対応チェックポイント
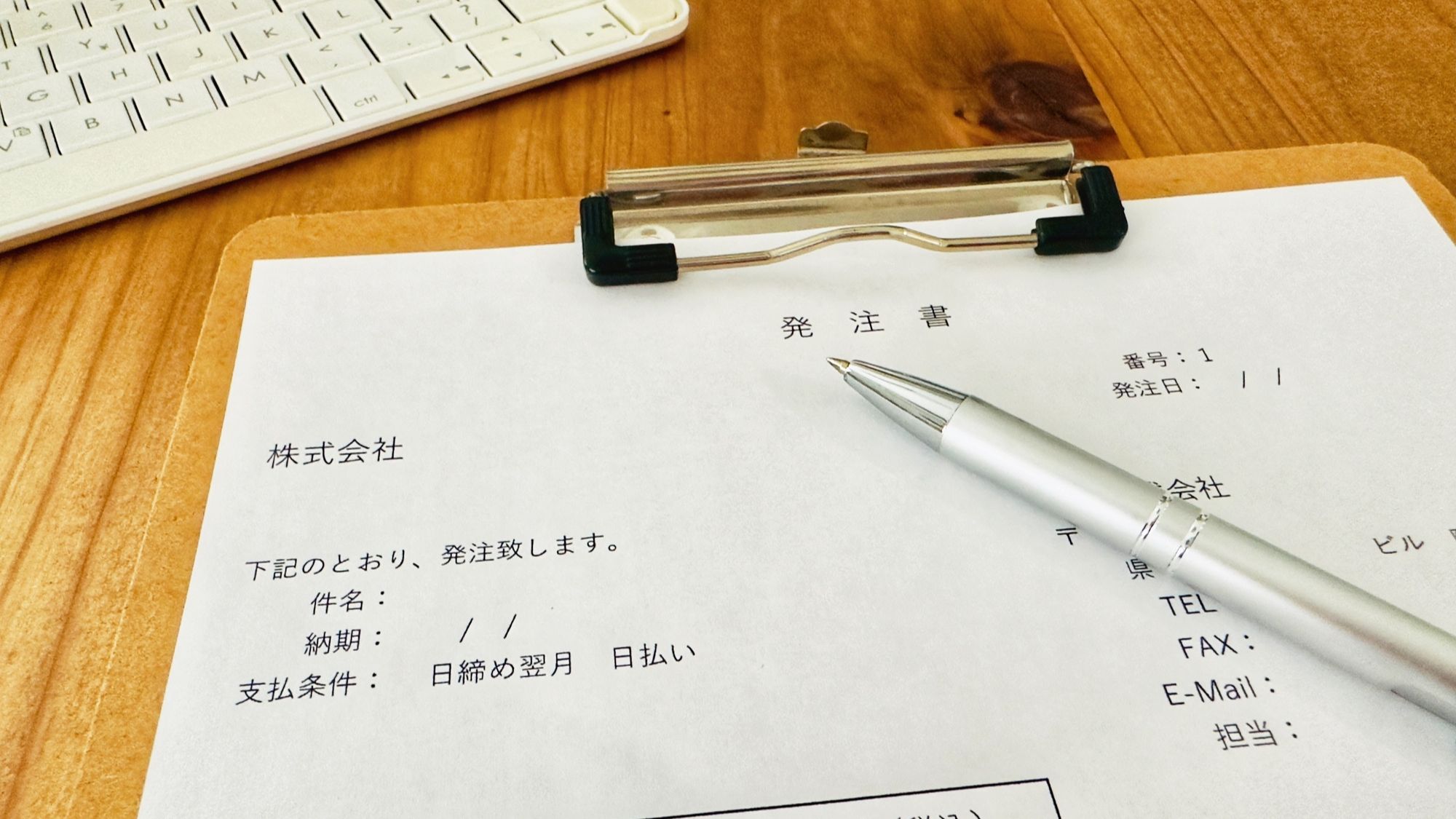
中小企業が取引上のトラブルに巻き込まれるのは、必ずしも下請けとしてだけではありません。発注側となることで、知らず知らずのうちに下請法に違反してしまうケースもあります。
下請法は、親事業者と下請事業者の間で公正な取引を促進するための法律です。この記事では、中小企業庁が公表する「下請法テキスト」をもとに、違反事例や改正ポイントを整理しつつ、チェックリストや研修など実務に活かせる具体策も紹介します。
なお、以下の資料は法令やコンプライアンスを遵守せず、失敗してしまった企業の事例や失敗の背景と影響、コンプライアンス違反防止の具体策まで、図表とともに分かりやすく解説しています。
下請法などの法令を遵守し続けるための参考となる情報満載なので、ぜひダウンロードしてみてください。
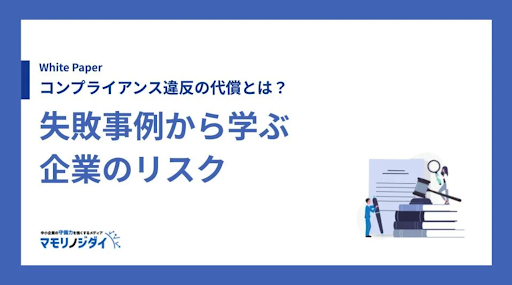
>>コンプライアンス違反の代償とは?失敗事例から学ぶ企業のリスクをダウンロード
目次
下請法テキストとは?【リンクあり】
中小企業が適正な取引関係を築くうえで重要となるのが、下請代金支払遅延等防止法(下請法)です。
この法律の理解を深め、実務に活かすために作成されたのが「下請法テキスト」です。中小企業庁と公正取引委員会が共同で公表し、公式なガイドラインとして広く活用されています。
下請法は、親事業者と下請事業者の間に生じる取引上のトラブルや不公正な取引慣行を防ぐために制定されました。とくに中小企業は、法務部を設けていない企業も多く、知らない間に法律違反をしているケースも起こり得ます。そのため、下請法を正しく理解し、自社の取引実態を見直すことが必要です。
▼下請取引適正化推進講習会テキスト
参考)中小企業庁「下請取引適正化推進講習会テキスト 」
参考記事:下請法とは?中小企業が知るべき4つの義務と禁止行為をわかりやすく解説
下請法テキストの役割
下請法テキストは、下請法の正確な理解と実務への定着を目的として作成された公式な解説資料です。中小企業が取引先との関係を適正に保つためには、下請法の内容を体系的に把握し、社内でのルールづくりに反映することが欠かせません。
このテキストは、現場の担当者や管理職が具体的な業務の中で下請法を意識できるよう構成されています。企業の法令遵守体制の構築や、社内研修の教材としても高い有用性があります。
下請法テキストの構成
下請法テキストは、実務での利用を前提に構成されています。具体的な構成は以下のとおりです。
1.下請代金支払遅延等防止法の内容
2.下請代金支払遅延等防止法第3条に規定する書面に係る参考例
3.電磁的方法による発注・取引記録の保存
4.一括決済方式の概要
5.電子記録債権を用いた支払の概要
6.本法違反行為の未然防止の取組
7.下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて
親事業者の責務や禁止事項、未然防止の取り組みになどについて詳しく記載されているため、必ず確認しましょう。
【中小企業は要注意】下請法テキストに書かれたペナルティ
下請法に違反した場合、公正取引委員会からの勧告や中小企業庁長官からの行政指導など、さまざまなペナルティがあります。
下請法に違反した場合、どのような事態になるのかを事前に把握しておきましょう。
参考)中小企業庁「下請取引適正化推進講習会テキスト 」p.92~95
報告・立入検査
下請法では、関係機関が必要と認めた場合に、親事業者および下請事業者に対して報告を求めたり、事業所への立入検査を実施できます。公正取引委員会は、取引の公正性を確保するために必要があると判断した場合に、こうした調査を行います。中小企業庁長官も、下請事業者の利益を保護する目的で、同様の措置を取ることが認められているのです。
また、親事業者または下請事業者が営む事業を所管する官庁も、中小企業庁の調査に協力する形で、報告や立入検査を行うことがあります。たとえば、運送業であれば国土交通省、テレビ放送業であれば総務省などです。
令和5年度には、公正取引委員会と中小企業庁により、親事業者約13万5,000名、下請事業者約57万名に対して調査が実施されており、違反の把握と是正に向けた取り組みが継続的に進められています。
勧告等
下請法に違反した親事業者に対して、公正取引委員会は違反行為の是正や必要な措置をとるよう勧告できます。勧告が行われた場合、原則として親事業者の社名、違反の内容、勧告の内容などが公表されます。
中小企業庁長官も、違反が認められた親事業者に対して行政指導を行うほか、公正取引委員会に対して措置請求を行うことが可能です。
もし親事業者が公正取引委員会の勧告に従わない場合には、独占禁止法に基づく排除措置命令や課徴金納付命令が出されることがあります。
一方で、親事業者が調査開始前に自ら違反行為を申し出て、一定の条件を満たした場合には、公正取引委員会の勧告や中小企業庁の措置請求が行われないこともあります。これは、下請事業者の被った不利益の早期回復を目的とした制度です。
罰則
下請法に違反した場合、一定の行為については両罰規定が適用され、違反を行った本人だけでなく、法人としての会社にも罰則が科されます。
対象となるのは、書面の交付義務違反、書類の作成・保存義務違反、報告に対する拒否や虚偽報告、立入検査の拒否や妨害、忌避などです。
これらに該当する場合、違反した個人および法人に対して、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
下請法の改正ポイント|コスト増に伴う適正代金の設定・対象取引追加など
2025年には下請法の改正があり、2026年1月1日から施行される予定です。
改正では、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)が新たに加わりました。原材料費や人件費の高騰に対応し、受託側が適正な価格を得られるよう保護が強化されています。
また、規制対象として、製造や販売に関連する製品の運送を外部業者に委託する行為が新たに加えられました。さらに従業員数を基準とした新たな対象要件(従業員数300人の区分を新設)も導入され、中小企業が「発注側」として規制対象になる場面が増加します。
参考)公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」
中小企業庁「下請法・下請振興法改正法の概要」
下請法テキストで学ぶ違反事例
下請法テキストでは、理論だけでなく具体的な違反事例も数多く紹介されています。これにより、企業担当者は「どのような行為が下請法に抵触するのか」を実務レベルで理解できます。
ここからは具体的な違反事例を見ていきましょう。
参考)中小企業庁「下請取引適正化推進講習会テキスト 」
参考記事:下請法違反の事例から学ぶ!企業を守るために知っておくべき重要なポイント
製造委託、修理委託における違反行為事例
製造や修理に関連する委託取引では、納期の一方的な変更や支払代金の減額要求が代表的な違反事例とされています。たとえば、親事業者が自己都合で納品期限を短縮したにもかかわらず、それに伴う追加費用を支払わなかった場合は、下請法違反となります。
また、完成品に軽微な不備があったことを理由に、代金の一部を一方的にカットする行為も違法です。
このような行為は、下請事業者にとって深刻な経営リスクとなります。日常的なやり取りの中で、意図せず違反を犯してしまわないよう注意が必要です。
情報成果物作成委託における違反行為事例
ソフトウェアやWebサービスの開発といった情報成果物作成の委託では、納品後の対応において違反が発生しやすい傾向があります。とくに問題となるのが、成果物を受け取ったあとに理由を示さず支払いを拒否するケースです。
また、仕様変更に伴って作業が追加されたにもかかわらず、その分の費用が一切支払われなかった事例も報告されています。こうした対応は、成果物の性質や業務の進行状況に関係なく、下請法上の「買いたたき」や「代金減額」に該当します。
成果物が目に見えにくい情報系の業務では、取引内容の明文化が重要です。契約段階で業務範囲を明確に定め、納品後の評価基準や支払条件も合意しておくことが望まれます。
役務提供委託における違反行為事例
労務や清掃、警備、運送といった役務提供に関する委託でも、下請法違反は起こり得ます。代表的なのは、業務完了後の報酬支払遅延や物品の買い取り強制などです。
たとえば、契約どおりにサービスを提供したにもかかわらず、親事業者側の経理処理の都合で代金支払が先延ばしにされる行為は、「支払遅延」として下請法違反になります。また、作業に必要な備品を下請事業者に自社指定で購入させ、その費用を一切補填しない場合も問題です。
下請法テキストで実務に活かす|チェックリスト・研修など活用法まとめ
下請法テキストは、実務に落とし込んで初めて意味を持つツールです。中小企業では、法令対応を担当する人員が限られていたり、業務の現場と法務の距離があることも多く、下請法への対応が後手に回るケースも見られます。
このような状況を踏まえ、下請法テキストをどのように日常業務に組み込んでいくかが重要です。ポイントとなるのは、業務フローへの反映、部門ごとの研修実施、そしてチェックリストの整備です。ここからは、それぞれの方法を具体的にご紹介します。
業務フローに合わせてチェックする
まず取り組むべきは、自社の取引フローに下請法の視点を取り入れることです。取引の流れを「発注前」「契約締結時」「納品後」といった段階に分け、それぞれのステップで下請法違反のリスクがないかを確認します。
たとえば、発注時には契約書の作成・交付が行われているか、契約内容は口頭ではなく書面で明示されているかを点検する必要があります。納品後の場面では、受け取りの遅延や一方的な値引きが発生していないかどうかがチェックポイントです。
中小企業では、複数の業務を一人が兼任していることもあるため、こうしたプロセスをあらかじめ可視化しておくことで、抜け漏れの防止につながります。
対象部門に合わせて研修をする
下請法テキストを最大限に活用するには、部門ごとの役割とリスクに応じた研修が不可欠です。とくに営業部門や購買・調達部門では、契約や発注に関わる実務が多く、法令違反のリスクが高まりやすくなるためです。
営業担当者は、顧客との関係構築に重きを置くあまり、取引先への過度な要請をしてしまう場合があります。一方、調達部門では、コスト圧縮のために無意識のうちに不当な減額要求を行ってしまうことも起こり得ます。
このような背景から、部門別に下請法の要点を押さえた研修の実施が大切です。中小企業であれば、集合研修だけでなく、短時間の動画研修やチェックシート形式のeラーニングを導入する方法も効果的です。
チェックリストを作成する
実務で法令遵守を徹底するためには、チェックリストの整備が有効です。下請法テキストをベースに、自社に必要な項目を抽出し、取引前後の確認事項として整理しましょう。
たとえば、「契約書は書面で交付されているか」「成果物の検収は適切なタイミングで行われたか」「代金支払は遅れていないか」など、具体的な項目を設定しておくことで、誰でも一定の基準で取引の適正性を確認できます。
中小企業では、属人的な運用になりやすいため、標準化されたチェックリストを用意することがミスや違反の予防につながります。定期的な見直しを行えば、制度変更や取引環境の変化にも柔軟に対応可能です。
まとめ
下請法テキストは、中小企業が取引上のトラブルを回避し、公正な取引関係を築くために欠かせない実務ツールです。勧告、罰則などのリスクを把握し、実際の違反事例から具体的な注意点を学ぶことで、自社の弱点を可視化できます。
また、改正ポイントや取引対象の拡大にも注目し、適正な価格設定や契約手続きを再確認することが重要です。部門別の研修やチェックリストの活用を通じて、組織全体での法令遵守体制を整備し、持続可能な取引基盤を構築しましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録