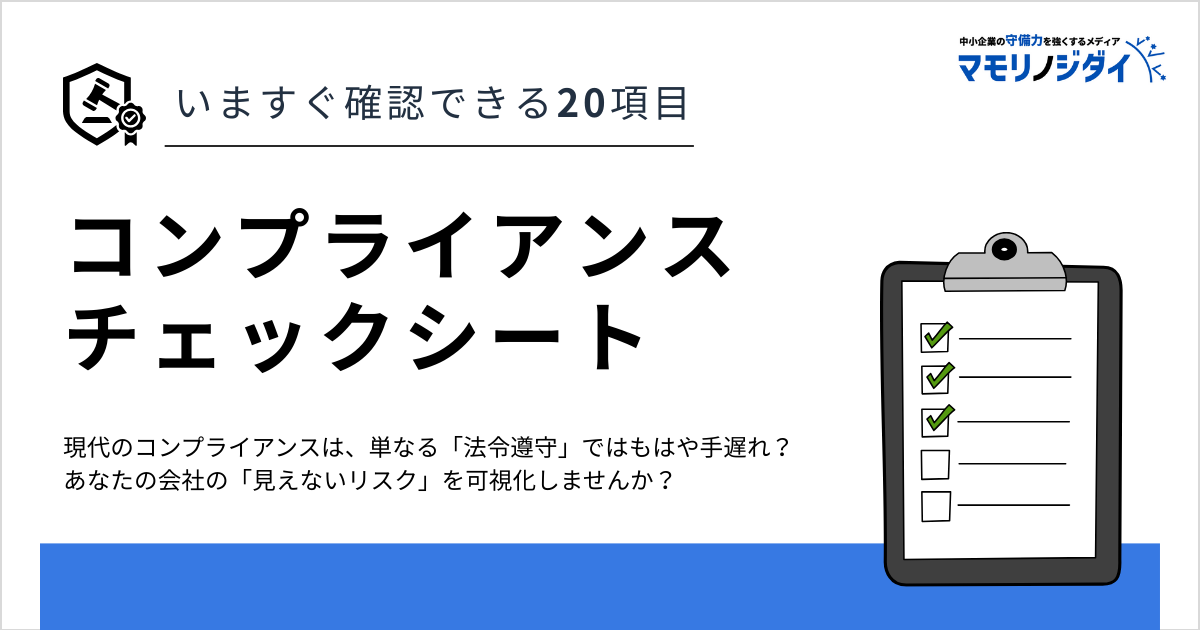クレームと苦情の違いを理解しよう!言葉の意味、ビジネスシーンでの使い方など

中小企業の現場では、日々の業務の中で「クレーム」や「苦情」への対応を迫られることがあります。
しかし、それぞれの言葉の意味を正しく理解していないと、対応の方向を誤り、さらなるトラブルを招く恐れもあります。
本記事では、「クレーム」と「苦情」の本来の意味やビジネス上の違い、さらに中小企業が注意すべき対応のポイントまでを網羅的に解説します。組織の“守り”を強化するために、ぜひこの機会に理解を深めておきましょう。
クレームと苦情の違いを理解することで企業のコンプライアンス意識が高まります。以下の資料ではコンプライアンス観点でのチェック項目を20個紹介していますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
【まずは本来の意味を整理】クレームと苦情の違いは?
「クレーム」と「苦情」は似ているようで、意味や対応の前提が異なります。正しく理解することで、現場での混乱を避け、適切な初動対応につなげることが可能です。
まずは言葉の定義と違いを確認し、類似語との区別も明確にしておきましょう。
クレームとは?
クレームとは「企業に対する改善要求や損害補償の要求」を意味します。単なる不満表明にとどまらず、「どうにかしてほしい」という具体的なアクションを伴うことが特徴です。
| 項目 | 内容 |
| 意味 | 改善要求・補償要求 |
| 性質 | 強めの主張・感情が混じることも |
| 必要な対応 | 丁寧な傾聴と迅速な事実確認・対応 |
ビジネスにおいては早期対応が求められる“緊急性の高い指摘”といえます。
苦情とは?
苦情は、サービスや製品に対する不満や不快感の表明を指します。
必ずしも「改善してほしい」という明確な要求があるとは限りません。「ただ伝えたい」というケースも多いのが特徴です。
| 項目 | 内容 |
| 意味 | 不満・不快感の表明 |
| 性質 | 改善要求を含まないこともある |
| 必要な対応 | 感情の受け止めと真摯な姿勢 |
苦情に関しては、誠実な受け止めと再発防止の意識が重要です。
【参考】コンプレインとの違い
英語の「コンプレイン(complain)」は「不満を述べる」という意味で、苦情に近いニュアンスを持ちます。
一方で日本語の「クレーム」は、「企業に対して改善を求める要求」として使われることが多く、ビジネスシーンではより強い意味合いを持っています。
【参考】カスタマーハラスメントとの違い
クレームや苦情がエスカレートし、従業員に対して過度な要求や人格否定が行われると、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」になります。正当なクレームとの線引きを明確にし、従業員を守る社内ルールの整備が不可欠です。
参考記事:カスタマーハラスメントから従業員と会社を守る! 対応マニュアル・事例も紹介
【中小企業必見】なぜ苦情・クレームが生まれるのか
クレームや苦情は、単なる“怒りの爆発”ではなく、原因が潜んでいることが特徴です。ここでは主な5つの原因を取り上げ、予防の視点から解説します。
サービスへの期待とのギャップ
顧客の中には、過去の類似サービスや口コミ、広告文などから勝手なイメージを膨らませていることがあるため注意が必要です。
中小企業ではマーケティングと現場が分断されていることも多く、「営業がこう言った」「Webサイトにそう書いてあったのに」といった齟齬が生じやすいといえます。
誇張表現やあいまいな言い回しを避け、実態に即した情報発信を行うことが予防の第一歩です。
コミュニケーション不足や誤解
言った・言わないの行き違いや、メールの返信が遅れたことによる不信感が、クレームのきっかけになることもあります。特に中小企業では「顧客対応が属人化している」「引き継ぎが不十分である」などで、顧客が情報を受け取れていないことが多いです。
連絡手段がメールやチャット中心になる中、トーンやニュアンスが伝わりにくいことも加わり、誤解が増幅されるケースもあります。「何を・いつ・誰が・どのように」伝えるかを仕組み化しましょう。
体調や精神状態による影響
クレームを言う側の状態に目を向けることも重要です。睡眠不足や体調不良、家庭や職場のストレスなど、心身が不安定な状態の人は、些細な出来事にも強く反応しやすくなります。
「そこまで怒ることではないのに」と感じても、相手にとっては大きな問題に思えるのです。このような場合、論理的に説明しても納得は得られません。
まずは感情を受け止め、冷静さを取り戻してもらう対応が求められます。従業員が一方的に矢面に立たないよう、エスカレーションや交代のルールも整えておきましょう。
組織の対応体制やレスポンスの遅さ
対応が遅れたこと自体よりも、「軽視された」「放置された」と顧客が感じたことが、苦情につながるパターンは少なくありません。
中小企業ではリソース不足により即時対応が難しい場面もありますが、最低限“受け取ったことの通知”だけでも早く返すことが重要です。また、社内に明確なフローがないと、問い合わせがたらい回しにされ、顧客の怒りが増幅します。
クレームの第一報を受けたときに「誰が何をすべきか」を事前に定め、担当者不在時の対応マニュアルを用意しておきましょう。
自己主張や立場の確認欲求
すべてのクレームが正当なものとは限りません。中には「自分の意見を認めさせたい」「優位性を示したい」といった、顧客自身の承認欲求や支配欲から発生するケースもあります。
このようなタイプの苦情は、実質的な解決よりも感情の発散が目的であることが多いため、対応には注意が必要です。安易に反論すると事態がこじれやすく、かといって無条件に受け入れると従業員への悪影響が及びます。
後述する「言い換え」を活用し、相手の“気持ち”に対して誠実に対応することが効果的です。
中小企業に多い“クレーム対応の落とし穴”とは?
クレーム対応は「その場しのぎ」で乗り切れるものではありません。企業全体の“守り”の質が問われる領域です。
しかし中小企業では、業務が属人化していたり、体制が整っていないために、重大な落とし穴に陥りやすい傾向があります。
ここでは、特に注意すべき3つの落とし穴を紹介しますので参考にしてください。
クレームの発生について社内共有されない
現場でクレームが発生しても、上司や他部署に情報共有されないケースは少なくありません。特に「自分の対応で何とか収めたから大丈夫」と判断してしまうと、同様の問題が別の場面で繰り返されてしまいます。
中小企業では人手不足の中で日々の業務が回っているため、トラブル対応の記録や共有が後回しにされがちです。しかし、クレームは“現場の声”でもあります。
社内にナレッジとして蓄積することで、再発防止やサービス改善につなげることが可能です。共有文化を醸成するよう努めましょう。
参考記事:組織内の不正行為を食い止めるには?不正防止のために中小企業がすべきこと
クレームについて軽視してしまう
「このくらいよくある話だ」「相手が感情的すぎる」といった理由で、クレームを軽視する姿勢は非常に危険です。最初は小さな不満であっても、企業の姿勢次第で炎上や風評被害に発展するリスクがあります。
中小企業では、限られたリソースの中で業務を回す必要があるため、“面倒な案件”として片付けられてしまうことがあります。しかしそのような姿勢は、対応する社員の士気を下げるのも確かです。
一件一件を組織の学びと捉え、マネジメント層が率先して重要性を示しましょう。
参考記事:中小企業にはコンプライアンスチェックが必須!チェックシート項目も紹介
原因の特定ではなく、社内の犯人さがしになってしまう
クレームが発生した際に、「なぜ起きたか」よりも「誰が悪いか」に焦点が当たる企業文化では、建設的な解決が望めません。
中小企業では顔が見える距離感で業務をしているため、特定の個人を責める方向に流れることもあります。しかし、個人を責めても本質的な問題は解決しません。
むしろ、社員が報告をためらい、問題が水面下で拡大するリスクを生みます。必要なのは“構造的な原因”の特定です。業務フローの見直し、情報共有の仕組み化など、仕組みとしての弱点に目を向けましょう。
苦情・クレームへの基本の対応ステップ
苦情やクレームにどう対応するかで、企業への信頼は大きく変わります。対応の仕方を間違えれば、問題が拡大し、悪評や損失につながるリスクもあります。
ここでは中小企業でも実践しやすい、基本的な4ステップを紹介します。
【ステップ1】まずは“傾聴”し話を最後まで聞く
クレーム対応の第一歩は、「話をさえぎらず、最後までしっかり聞くこと」です。
相手は多くの場合、怒りや不満の感情を抱えています。ここで反論したり言い訳したりすると、相手の怒りはさらに増幅するため注意しましょう。
「ご不便をおかけしました」と共感の姿勢で傾聴することで、相手は気持ちを落ち着かせやすくなります。
【ステップ2】誠実な謝罪と言い換えをする
話を十分に聞いた後は、まず謝罪の言葉を伝えます。
こちらに明確な過失がない場合でも、「ご迷惑をおかけしました」「不快な思いをさせてしまいました」といった表現で“気持ちへの共感”を示すことが大切です。
その際、以下のような言い換え例を覚えておくと、現場で役立ちます。
| NG表現 | 言い換え例(推奨) | 意図 |
| それは当社の責任ではありません | ご不便をおかけして申し訳ありません | 相手の気持ちに寄り添う |
| そういう決まりなので… | ご案内が分かりづらかったようで申し訳ありません | 説明不足を補う姿勢 |
| 担当が違うのでわかりません | 確認のうえ、責任をもってご連絡します | たらい回し感の排除 |
| そんなクレームは初めてです | 貴重なご意見として受け止めております | 否定せず受容する |
【ステップ3】事実確認と原因究明をする
謝罪をした後は、事実関係を丁寧に確認します。感情のケアだけでは問題の解決には至らず、再発の防止にもつながりません。
いつ・どこで・誰が・何を・どのようにしたかを整理し、関係者にヒアリングや記録の照合を行いましょう。このとき、顧客に対しては「正確な状況を把握するための確認です」と伝え、敵意ではないことを明確にします。
表面的な聞き取りで済ませず、背景にある業務プロセスの問題や、社内連携の弱点なども洗い出す姿勢が大切です。
【ステップ4】改善策の提示とフォローアップ
原因が特定できたら、再発防止のための改善策を顧客に丁寧に説明しましょう。「同じことが起きないよう、◯◯を見直しました」と具体的な内容を伝えることが、信頼の回復に直結します。
また、口頭だけで終わらせず、文書やメールでのフォローアップも重要です。「今後はこのような対応を行います」と再確認することで、顧客に安心感を与えることができます。改善策を社内に展開し、学びとして共有するところまでがクレーム対応です。
苦情・クレーム対応のNG行為と注意点
クレーム対応では、誠実な姿勢が重要である一方で、「やってはいけない対応」も明確に存在します。
中小企業においても、現場任せにせずNG行為を組織的に明文化しておきましょう。それが“守りの体制づくり”につながります。
話を遮る、否定する
相手の話を途中で遮る、あるいは「それは違います」と真っ向から否定するのは、火に油を注ぐ行為です。
たとえ相手の主張に事実誤認があったとしても、まずは最後まで聞ききる姿勢が重要となります。感情を整理する前に反論されると、顧客は「理解してもらえない」「軽視された」と感じることでしょう。
対応者が冷静さを失いかける場面でも、ひと呼吸おいて「お話ありがとうございます」と受け止めの言葉をはさむことで、関係の悪化を防げます。
謝罪だけ・形式謝罪に終始
「申し訳ありませんでした」と謝るだけで済ませたり、形だけの謝罪にとどまってしまうことが危険です。顧客は「本気で反省していない」「また同じことを繰り返すのでは」と不信感を抱きます。
特に中小企業では、対面や電話でのやり取りが多いため、口調や態度にも注意しましょう。大切なのは、謝罪のあとに“何をどう改善するのか”を明確に伝えることです。
責任を取る=謝る、ではなく、再発防止と信頼回復までのアクションが伴ってこそ、謝罪の意味が生まれます。
過剰要求を無条件に受け入れる危険性
「もう二度と買わない」と言われ、顧客の要求をすべてのむことはリスクです。過剰な要求に安易に応じると、組織としての線引きが崩れ、他の顧客や従業員にも悪影響を及ぼします。
たとえば「全額返金+金券」「担当者の謝罪文提出」など、明らかに過度な要求には注意が必要です。“カスタマーハラスメント”に発展する恐れもあります。
あらかじめ社内で対応ラインを決めておきましょう。
まとめ
クレームと苦情は、どちらも顧客との接点における重要なサインです。まずはそれぞれの意味の違いを正しく理解し、感情に流されず冷静に対応する力を養うことが、中小企業の“守り”を強化する第一歩となります。
クレームは単なるトラブルではなく、業務改善のヒントです。一人の対応者の力量に任せるのではなく、社内で共有し、対応ルールや記録の仕組みを整備しましょう。
感情ではなく構造で捉え、組織として成長する機会に変えることが中小企業の成長にとって必要な姿勢です。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録