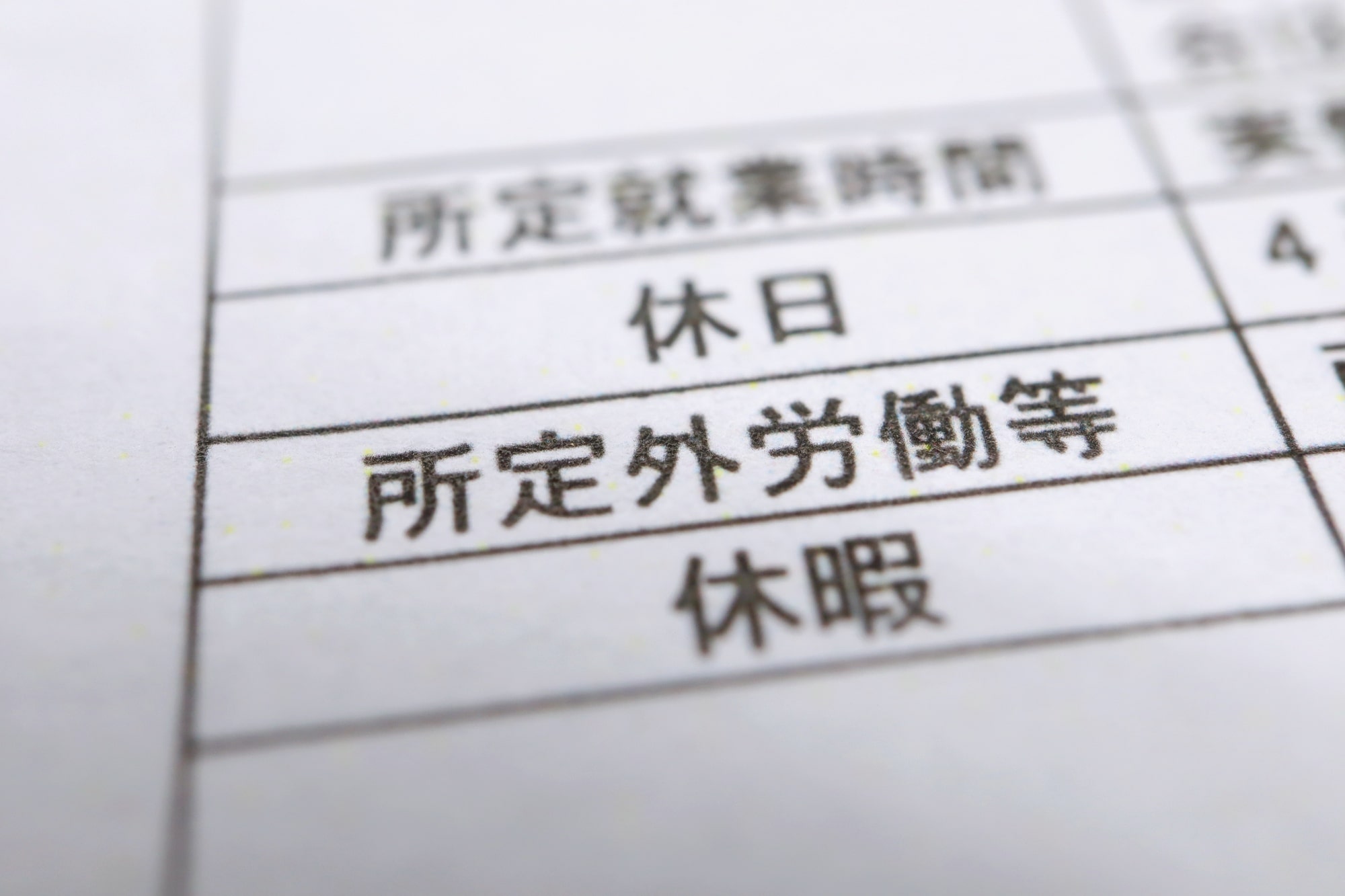【企業も知るべき】離職票とは何に使うもの?書き方、必要になる状況など
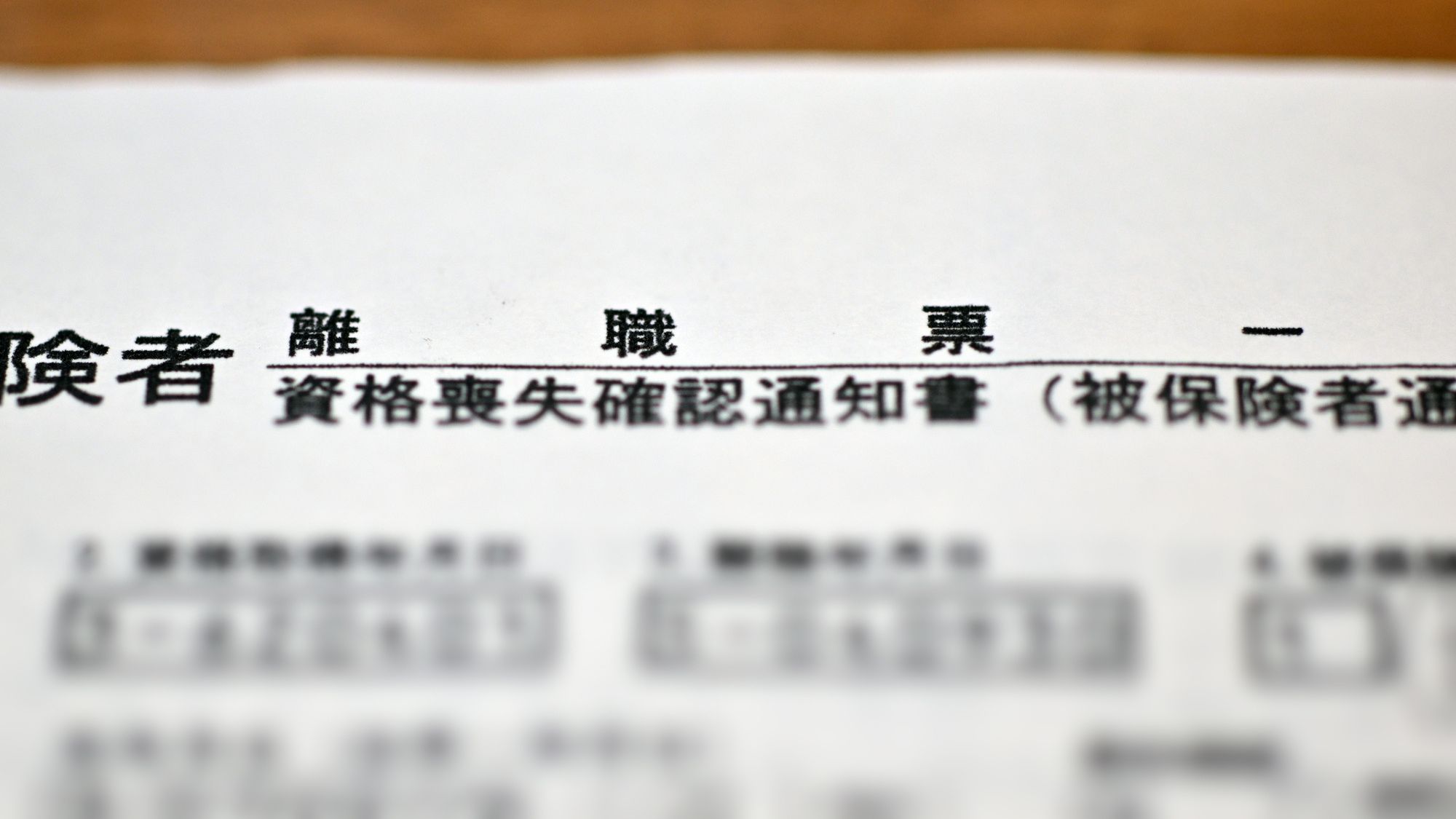
離職票は、退職者が失業給付(基本手当)を受給するために不可欠な公的書類であり、会社側には正確かつ迅速な発行が求められます。
しかし、中小企業においては、人事・労務担当者の専門性の欠如や業務の兼任、手続きの複雑さから、離職票に関するトラブルが発生することも少なくありません。
この記事では、企業側が離職票発行において直面しやすい課題を掘り下げ、発行条件から具体的な記入方法、提出のポイント、さらには万が一のトラブル時の対処法まで、網羅的に解説します。
目次
離職票とは?まずは基本を押さえよう
従業員の退職時に企業が発行する「離職票」は、退職者が失業保険(基本手当)の給付を受けるためにハローワークへ提出する非常に重要な公的書類です。正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、企業には適切に手続きをおこない、退職者へ交付する義務があります。
この離職票がなければ、退職者は原則として失業保険の受給資格を得られません。そのため、企業の人事労務担当者や経営者の方は、離職票の役割や種類、関連書類との違いを正確に理解し、スムーズな発行手続きをおこなうことが求められます。
離職票1・2の違いは?
離職票は、「離職票-1」と「離職票-2」の2種類で構成されています。それぞれ役割や記載内容が異なりますので、以下の表でその違いを明確にします。
| 比較項目 | 離職票-1 | 離職票-2 |
| 正式名称 | 雇用保険被保険者離職票−1 資格喪失確認通知書 | 雇用保険被保険者離職票−2 |
| 主な目的・役割 | ・失業保険の振込先金融機関指定 ・雇用保険資格喪失の通知 | 失業保険の給付日数・給付額決定用基礎情報(離職理由、賃金支払状況など)の証明 |
| 主な記入者 | ・退職者 ・一部企業やハローワーク | ・主に企業(事業主)が作成 ・ハローワークが確認 |
| 企業側の主な対応 | ハローワークから交付後、退職者へ交付 | ・「離職証明書」を作成 ・ハローワークへ提出 ・ハローワークから交付後、離職票-2として退職者へ交付 |
離職票-1は主に退職者自身が手続きを進めるための情報や振込先を記入するのに対し、離職票-2は企業が退職者の離職状況や賃金について証明する内容となっており、失業保険の給付内容を左右する重要な書類です。
企業としては、離職票-2の元となる「離職証明書」の正確な作成と提出が求められます。
離職票・退職証明書・資格喪失届の違いは?
退職に関連する書類には、離職票の他にも「退職証明書」や「雇用保険被保険者資格喪失届」などがあります。
これらは名称が似ていたり、手続きのタイミングが近かったりするため混同しやすいですが、目的や法的根拠、提出先が異なります。
| 比較項目 | 離職票 | 退職証明書 | 雇用保険被保険者資格喪失届 |
| 主な目的 | 退職者が失業保険(基本手当)を受給するために使用 | ・従業員が退職した事実を証明 ・転職先の企業への提出 ・国民健康保険・国民年金の手続き | 従業員が雇用保険の被保険者資格の喪失をハローワークに届け出るために企業が使用 |
| 法的根拠 | 雇用保険法 第76条第3項 | 労働基準法 第22条 | 雇用保険法 第7条 |
| 発行義務者 | 【企業】 ・退職者から請求があった場合 ・退職者が59歳以上の場合 | 【企業】 ・退職者から請求があった場合に発行義務 ・退職日以降遅滞なく | 【企業】 従業員の資格喪失の事実があった日の翌日から10日以内 |
| 主な提出先 | 【退職者】ハローワーク | 【退職者】 ・転職先企業 ・市区町村役場など | 【企業】 管轄のハローワーク |
| 様式 | 公的様式あり | 法定様式なし | 公的様式あり |
これらの書類の違いを正確に理解し、それぞれのケースに応じて適切な対応をおこなうことが、企業としての責任を果たす上で非常に重要です。とくに離職票に関する手続きは、退職者の生活に直結するため、迅速かつ正確な処理を心がけなければなりません。
離職票はどのようなときに必要?不要なケースは?
具体的にどのような場合に離職票が必要となり、逆に不要となる、あるいは発行を省略できるケースはあるのでしょうか。経営者として知っておくべきポイントを解説します。
離職票が必要となる主なケース
原則として、雇用保険の被保険者である従業員が退職する際には、離職票の発行手続きが必要となります。とくに以下のような場合は、企業として対応が求められます。
- 退職者が離職票の交付を希望する場合
これがもっとも一般的なケースです。企業は、退職の申し出があった際や退職面談時に、離職票が必要かどうかを本人に確認することが推奨されます。 - 退職者が退職日時点で59歳以上の場合
この場合は、本人が離職票の交付を明確に希望しない場合を除き、原則として企業は離職票を発行するための手続きをおこなう必要があります。これは、高年齢者の雇用継続や再就職支援に関連する制度のためです。
離職票が不要または発行を省略できる主なケース
一方で、以下のようなケースでは、離職票の発行が不要であったり、手続きを一部省略できたりする場合があります。
- 59歳未満の退職者が離職票の交付を明確に希望しない場合
退職者がすぐに次の就職先が決まっている、家業を継ぐ、学業に専念するなど、失業保険の受給を全く考えておらず、離職票を希望しないと明確に意思表示した場合です。
ただし、この場合でも、企業は「雇用保険被保険者資格喪失届」と離職者が離職票の交付を希望しないと記載した「離職証明書(離職票-2の元となる書類)」をハローワークに提出する必要があります。
後々のトラブルを避けるため、退職者が離職票を不要とした旨を、書面やメールなどで記録として残しておくことが賢明です。 - 死亡による退職の場合
従業員が在職中に亡くなられた場合は、失業保険の受給対象とはならないため、離職票の発行は不要です。ただし、「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出は必要です。 - 雇用保険の被保険者ではない従業員が退職する場合
そもそも雇用保険の加入条件を満たしていない従業員が退職する場合は、被保険者ではないため、離職票の発行対象外です。
企業としては、退職者の意向をしっかりと確認し、法的な義務を遵守した上で、適切に対応することが求められます。不明な点があれば、管轄のハローワークに確認することがもっとも確実です。
アルバイトやパートタイマーにも離職票は必要?発行条件と手続きを解説
雇用形態がアルバイトやパートタイマーであっても、一定の条件を満たせば雇用保険の被保険者となり、離職時には原則として離職票の発行手続きが必要になります。
アルバイトやパートタイマーの方が雇用保険の被保険者となる主な条件は以下のとおりです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
これには、契約期間の定めがない場合や、契約期間が31日未満であっても更新されることが明示されている場合なども含まれます。
雇用保険に加入している従業員が退職する際には、他の正社員と同様に離職票に関する手続きが必要となる可能性があります。
【企業側】離職票の発行手続きと流れ
会社側には、退職者からの請求があった場合、以下のような流れで離職票を速やかに発行する義務があります。
- 退職の確認と必要書類の準備
従業員の退職日が確定したら、離職票の発行準備に入ります。
準備する書類:
・雇用保険被保険者証
・出勤簿、賃金台帳(退職日以前2年間のもの)
・退職理由を証明する書類(退職願、解雇通知書など)
・雇用保険被保険者離職証明書(ハローワークから取得) - 雇用保険被保険者離職証明書の作成
この書類が離職票の元となる重要な書類です。3枚複写になっており、会社控え、ハローワーク提出用、離職票(本人交付用)となります。
記載事項:
・被保険者番号、氏名、生年月日
・事業主情報
・離職年月日、離職理由(具体的に記載)
・離職日以前2年間の賃金支払状況、出勤日数など
離職理由は、失業給付の受給資格や給付期間に大きく影響します。会社都合退職なのか、自己都合退職なのかを明確にし、具体的な事実に基づいて記載する必要があります。 - 退職者の署名・捺印の依頼(任意)
離職証明書の「離職者本人の判断」欄は、退職者自身が記載・署名捺印する箇所です。必ずしも必要ではありませんが、記載内容に異議がないことを確認する意味で、事前に退職者から署名・捺印をもらっておきましょう。
もし退職者から署名・捺印が得られない場合でも、会社はハローワークに提出できますが、その旨をハローワークに伝える必要があります。 - ハローワークへの提出
作成した「雇用保険被保険者離職証明書」に、雇用保険被保険者資格喪失届、および添付書類(賃金台帳、出勤簿など)を添えて、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
提出期限は、離職日の翌日から10日以内です。 - 離職票の交付
ハローワークで書類が受理され、内容が確認されると、「雇用保険被保険者離職票-1」と「雇用保険被保険者離職票-2」が会社に交付されます。これが「離職票」本体です。
会社は、ハローワークから交付された離職票を退職者本人に郵送または手渡しで渡します。
離職票を発行できる条件とは
離職票は、雇用保険の被保険者であった期間があっても、退職した全員がもらえるわけではありません。 厳密には、ハローワークに提出する「雇用保険被保険者離職証明書」の発行条件が、以下のとおり定められています。
- 59歳以上の退職者は、原則として、全員に対して離職証明書の発行が必要
- 59歳未満の退職者で離職票の発行を希望する場合、もしくは事業主が発行を必要と判断する場合
退職者は離職票をいつ、どこでもらえる?
会社が作成し、ハローワークを経由して、最終的に会社から退職者本人に郵送または手渡しで交付されます。 退職者が直接ハローワークに受け取りに行くことはできません。
会社がハローワークに離職証明書を提出した後、ハローワークでの処理に通常1週間~2週間程度かかります。その後、ハローワークから会社へ離職票が交付され、そこから会社が退職者に郵送するため、退職日から2週間~3週間程度が目安です。
ただし、会社の処理状況やハローワークの混雑状況によって、さらに時間がかかる場合もあります。
離職票の書き方と提出のポイント
離職票は、退職者が失業給付を受給するために不可欠な書類であり、会社が正確に作成・提出する義務があります。書き方と提出のポイントについて説明します。
離職票の記入項目一覧
離職票は、会社が作成する「雇用保険被保険者離職証明書」を基にハローワークが発行するものです。したがって、ここでは「雇用保険被保険者離職証明書」の主要な記入項目とそのポイントを説明します。
| 記入項目カテゴリ | 項目名 | 記載内容のポイント |
| 事業主の記載事項 | ・事業主の氏名または名称 ・所在地 ・電話番号 | 正確に記載 |
| 事業の種類 | 会社の主な事業内容を記載 | |
| 雇用保険事業所番号 | 会社に付与されている雇用保険の事業所番号を記載 | |
| 被保険者の記載事項 | 被保険者番号 | 退職者の雇用保険被保険者番号を正確に記載 |
| 氏名、フリガナ、生年月日、性別 | 退職者の情報を正確に記載 | |
| 離職年月日 | 雇用契約が終了した最終日を記載 | |
| 離職票交付希望の有無 (退職者本人の記載) | 59歳以上の退職者 | 原則として、離職票は必ず交付 |
| 59歳未満の退職者 | 離職票の交付を希望するかしないか、いずれかに〇をつけ、署名・捺印退職者が署名できない場合は、会社が代理で記名し、その旨を記載 | |
| 離職理由 (重要項目) | 具体的な離職理由 | 自己都合退職、会社都合退職、その他(期間満了など)を明確にし、具体的な内容を記述 |
| 「具体的事情記載欄(事業主用)」 | 離職に至った具体的な経緯を詳細に記載例:自己都合退職「〇年〇月〇日、一身上の都合により退職届提出、退職を承認した」会社都合「〇年〇月〇日、事業縮小にともない、〇年〇月〇日付けで解雇」 | |
| 「具体的事情記載欄(離職者用)」 | 離職者本人が会社の記載内容に異議がある場合に、自身の主張を記載会社が退職者から署名をもらう際に、この欄も確認してもらう | |
| 離職日以前の賃金支払状況等 | 離職日以前の賃金算定期間 | 離職日から遡って、賃金支払状況を記載原則として、離職日以前2年間の賃金と出勤日数を月ごとに記載 |
| 賃金支払基礎日数 | その期間の出勤日数(欠勤日は含まず、有給休暇は含む)を記載 | |
| 賃金 | その期間に支払われた賃金総額(通勤手当、住宅手当なども含む。賞与は含まない)を記載 |
記載ミスがあると発行に時間がかかってしまうため、確認を怠らないことが重要です。
離職票の提出は【マイナポータル】電子申請も活用できる
雇用保険関係の各種手続きは、ハローワークの窓口に直接書類を提出する方法の他に、電子申請を利用することも可能です。とくに「雇用保険被保険者離職証明書」の提出は、電子申請が推奨されています。
【電子申請のメリット】
- 24時間365日申請可能
- 手間と時間の削減
- ペーパーレス化
- エラーの事前チェック
【電子申請に必要なもの】
- GビズIDプライムアカウント
- 電子申請システム e-Gov
多くの給与計算・人事労務ソフトには、e-Gov連携機能が搭載されており、ソフトから直接電子申請が可能です。
まずGビズIDを取得し、その後e-Govを使って申請するのが基本の流れです。詳細は以下に記載しているので、参考にしながら対応してみてください。
【電子申請の流れ(一般的な例)】
- GビズIDプライムアカウントの取得
- e-Govにログイン
- 「雇用保険被保険者離職証明書」の申請様式を選択
- 必要事項を入力(離職理由、賃金情報など)
- 賃金台帳、出勤簿などの添付書類をPDFなどで添付
- 申請内容を確認し、送信
- ハローワークでの審査後、電子データで離職票(事業主控)が返送される
参考)マイナポータル「08 離職票をマイナポータルで受け取る」
参考記事:離職とは?中小企業が押さえるべき基礎知識・手続き・防止策を徹底解説
中小企業にありがちな離職票のトラブル
中小企業では、人事・労務担当者が専任でない場合や、少人数で複数の業務を兼任しているケースが多く、離職票の発行においてトラブルが発生しやすくなります。
離職票をなくした・再発行が必要
退職者から「離職票をなくしてしまった」「再発行してほしい」と連絡があった場合、会社は以下の手順で対応します。
- 退職者への確認
まずは退職者に対し、本当に紛失したのか、どこでどのように紛失したのかなどを簡単に確認します。また、離職票-1(雇用保険被保険者離職票-1)と離職票-2(雇用保険被保険者離職票-2)のどちらを紛失したのかも確認します。 - 会社保管分の確認
会社では、「雇用保険被保険者離職証明書」の事業主控(通常3枚複写の1枚目)を保管しているはずです。この控えを確認し、離職者情報、被保険者番号、離職日、離職理由などを把握します。 - ハローワークへの連絡と手続き
再発行は、原則として会社が管轄のハローワークに対しておこないます。 退職者が直接ハローワークで再発行を申請することはできません。
ただし、会社が再発行に応じないなどの特別な事情がある場合は、ハローワークが直接対応することもあります。 - 退職者への送付
ハローワークで再交付された離職票を、速やかに退職者へ送付します。この際、紛失のリスクを避けるため、簡易書留やレターパックなど、追跡可能な方法で送ることを強く推奨します。
離職票が10日過ぎても退職者に届かない
万が一、退職日から10日を過ぎても離職票が退職者の手元に届いていないと連絡があった場合、以下の手順で速やかに対応しましょう。
- 状況の確認と原因の特定
まず、社内で離職票の発行状況を確認します。
・ハローワークへの提出は完了しているか?
・ハローワークからはすでに交付されているか?
・退職者の住所情報は正しいか? - 退職者への丁寧な連絡と状況説明
状況が判明したら、すぐに退職者へ連絡し、現在の状況と今後の見通しを具体的に伝えます。 - 迅速な対応と再発防止策の検討
原因が判明したら、それに対する迅速な対応を最優先でおこないます。
・手続き遅延の場合:担当部署や担当者に速やかな処理を指示し、再発防止のために手続きフローの見直しやチェック体制の強化を検討
・ハローワーク側の遅延の場合:状況を退職者に伝えつつ、定期的にハローワークに状況を確認し、情報が入り次第退職者に共有
・郵送トラブルの場合:必要であれば再発行の手続きをハローワークに相談し、退職者の同意を得て再送
連絡があった時点で迅速かつ丁寧に対応することで、退職者との良好な関係を維持し、企業の信頼を守れます。
まとめ
この記事では、企業側が対応すべき離職票の発行手続きについて、その流れから必要な条件、具体的な記入項目、そして電子申請の活用方法まで、多角的に解説しました。
とくに、中小企業にありがちな手続きの遅延や離職理由に関する認識のずれといったトラブル事例とその対処法にも触れ、実務に即した情報を提供しています。離職票は、退職者が失業給付を受給するために不可欠な書類であり、その発行は会社側の重要な義務です。
正確な知識と適切な対応は、退職者の生活を支援するだけでなく、企業の信頼性向上にも直結します。
万が一、離職票に関する疑問やトラブルが発生した場合は、速やかに社内で状況を確認し、必要に応じてハローワークへ相談するなど、迅速かつ丁寧な対応を心がけるのが最適解です。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録