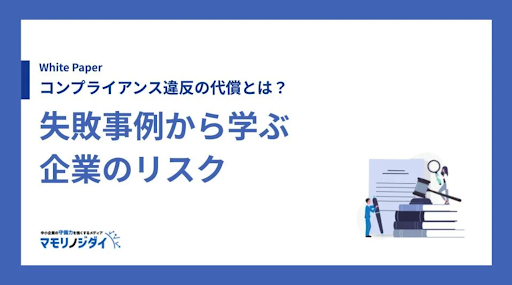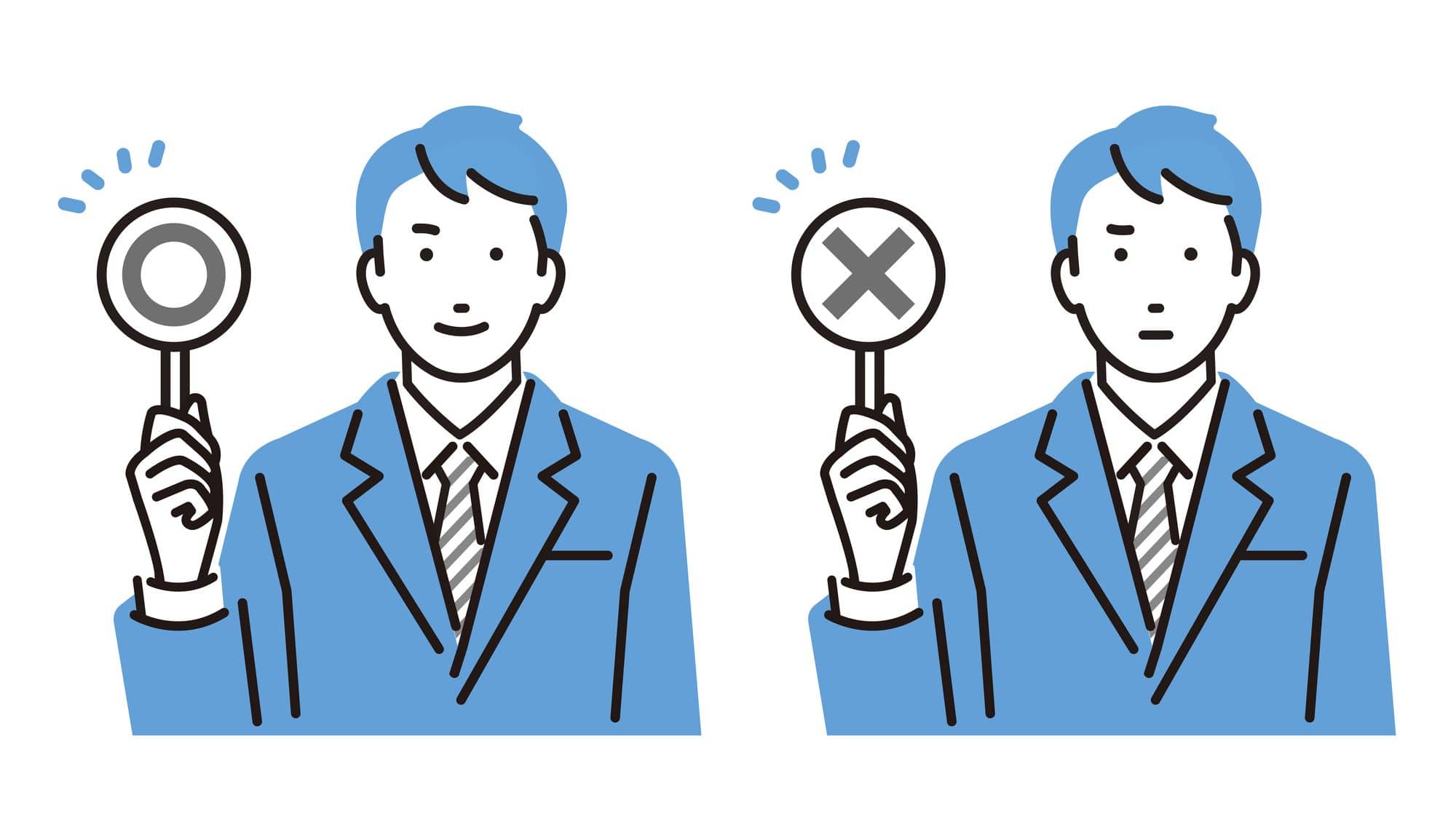【中小企業必見】独占禁止法とは?罰則や下請法との違いを簡単に解説
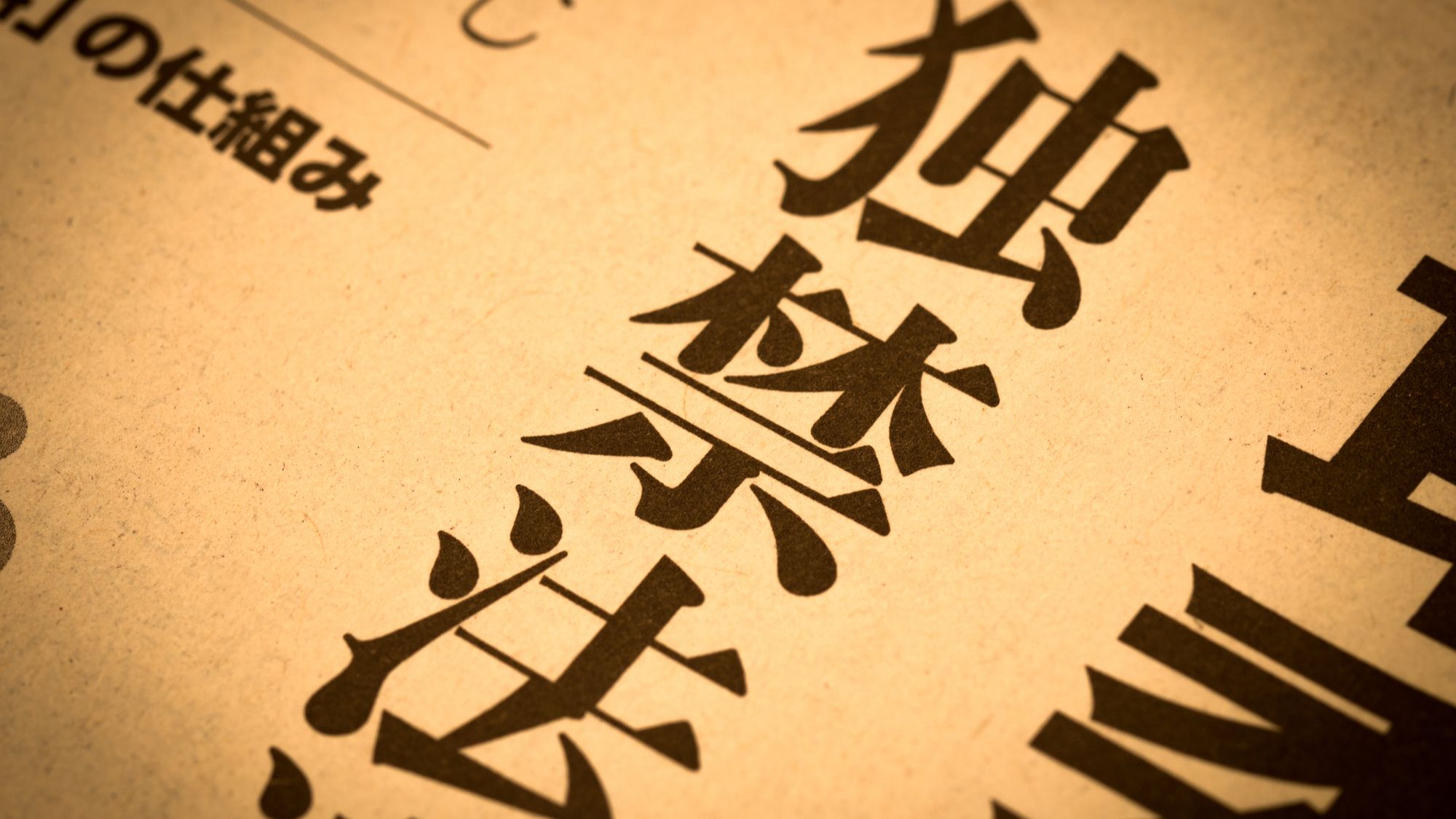
企業活動において、公正な競争を守らなければなりません。その基本となる法律が「独占禁止法」です。しかし、自社には関係ないと感じている中小企業の経営者や実務担当者も少なくありません。
この記事では、独占禁止法の概要を簡潔に解説し、違反事例や罰則、下請法との違い、さらには企業が講じるべき対策までをわかりやすく紹介します。コンプライアンス強化の第一歩として、ぜひ参考にしてください。
なお、以下の資料はコンプライアンス違反によって失敗してしまった企業の事例や、失敗の背景と影響、コンプライアンス違反防止の具体策まで、図表とともに分かりやすく解説しています。
独占禁止法違反を起こさないための参考となる情報満載なので、ぜひダウンロードしてみてください。
>>コンプライアンス違反の代償とは?失敗事例から学ぶ企業のリスクをダウンロード
目次
独占禁止法とは?最低限知っておきたい知識を簡単に解説
独占禁止法とは、企業が自由で公正に競争できる市場環境を守るために定められた法律です。
公正な競争が保たれることで、消費者にとっても価格や品質の面で利益が生まれ、経済全体の健全な発展が期待されます。特定の企業が市場を独占することで取引先や消費者に不利益が及ばないよう、競争環境を守る役割を担っているのです。
参考)公正取引委員会「独占禁止法の概要」
参考記事:【中小企業向け】独占禁止法とは?禁止行為・罰則・事例をわかりやすく解説
独占禁止法は自由な競争を促進するための法律
独占禁止法は、企業を縛り付ける法律というイメージがあるかもしれません。
しかし、この法律の目的は、企業同士が不当に競争を妨げたり、他社を排除したりする行為を防ぐことにあります。
企業間の競争が公正に行われることで、市場は活性化し、消費者にとってもより良い商品やサービスが提供されるのです。
たとえば、価格を横並びで決めたり、特定の会社だけと取引するよう強制したりする行為は、公正な競争を阻害するため禁止されています。こうした不正な行為を抑止し、企業活動が健全に行われる土台を整えているのが独占禁止法の役割です。
中小企業も無関係じゃない!意外と身近な違反リスク
「独占禁止法は大企業だけの話」と考える中小企業は少なくありません。しかし、実際には中小企業も違反の当事者や被害者になる可能性があります。
たとえば、取引先に対して過度な値引きを要求したり、他社との取引を制限したりする行為は、優越的地位の濫用として問題になるケースがあるのです。
また、地域の同業者と価格を合わせるよう話し合った場合、それがカルテルに該当することもあります。知らないうちに法に抵触しないよう、日々の取引内容を見直し、問題がないか常に確認することが大切です。
独占禁止法で禁止されている行為
独占禁止法では、禁止されている行為は以下のとおりです。
| 禁止行為 | 概要 |
| 私的独占の禁止 | 特定の企業が市場を支配し、他の競合他社の事業活動を妨害するような行為 |
| 不当な取引制限(カルテル)の禁止 | 複数の企業が事前に価格や販売量、市場の分割などを話し合いで決める行為 |
| 事業者団体の規制 | 事業者団体による競争の実質的な制限や事業者の活動制限、不公正な取引方法の強要など |
| 企業結合の規制 | 企業の合併・買収が、市場における競争を著しく減少させると判断される場合、公正取引委員会が規制を行う |
| 独占的状態の規制 | 市場で特定の事業者が過大なシェアを占め、競争が阻害されている状態を是正するための規制 |
| 不公正な取引方法の禁止 | 取引上の地位を利用して、取引先に不利益な条件を押しつける行為 |
参考)公正取引委員会「独占禁止法の規制内容」
独占禁止法に違反するとどうなるのか
独占禁止法に違反した場合、企業や関係者はさまざまな不利益を被ります。
具体的には、以下のとおりです。
- 経済的ペナルティを受ける
- 業務停止や是正命令が下る
- 刑事罰や損害賠償請求を受ける
- 間接的なダメージを受ける
それぞれ見ていきましょう。
経済的ペナルティを受ける
独占禁止法違反に該当すると課徴金納付命令が下される可能性があります。
課徴金とは、カルテル・入札談合等の違反行為防止という行政目的を達成するため、行政庁が違反事業者等に対して課す金銭的不利益のことです。
課徴金の額は、違反行為が行われた期間の売上額や購入額に一定の割合を乗じて算出されます。
| 不当な取引制限 | 支配型私的独占 | 支配型私的独占 | 共同の取引拒絶差別対価、不当廉売再販売価格の拘束 | 優越的地位の濫用 |
| 10%(4%) | 10% | 6% | 3% | 1% |
※( )内は違反事業者及びそのグループ会社がすべて中小企業の場合
違反の程度によっては、多額の課徴金が科されることになります。
参考)公正取引員会「課徴金制度」
業務停止や是正命令が下る
課徴金だけでなく、公正取引委員会から排除措置命令や業務改善命令が出される場合もあります。これらの命令は、違反行為をやめさせるとともに、将来的な再発を防ぐ目的で出される行政処分です。
たとえば、「違反行為の停止」「再発防止策の実施」「指名停止(入札の参加停止)」などが命じられます。
これに従わない場合は、刑事罰を受けることになります。
参考)公正取引委員会「排除措置命令と課徴金納付命令」
参考)内閣府「「独占禁止法における違反抑止制度の在り方等に関する論点整理」係る意見・情報募集に対し寄せられた意見・情報」p6
刑事罰や損害賠償請求を受ける
悪質な違反行為には、刑事罰が科されることもあります。たとえば、カルテルや入札談合に関与していた場合、法人だけでなく、関係した役員や担当者個人にも罰則が及ぶことがあります。
刑事罰が科されると、前科がつくため社会的信用を大きく失いかねません。また、被害を受けた企業や消費者から損害賠償請求を受ける可能性もあり、法的責任が長期化するリスクも考慮する必要があります。
参考)公正取引委員会「独占禁止法教室」
間接的なダメージを受ける
独占禁止法違反の影響は、目に見える罰則だけではありません。違反が報道されることで企業イメージは大きく損なわれ、社会的信用の低下につながります。
その結果、取引先からの契約打ち切りや新規取引の停止、金融機関からの融資条件の悪化など、経営面で深刻なダメージを受けることも少なくありません。また、社内外の信頼関係が崩れることで、社員の士気低下や採用活動への影響が懸念されます。
独占禁止法と下請法の違い
独占禁止法と下請法は、いずれも企業間取引に関するルールを定めた法律ですが、目的、規制対象、保護の対象範囲がそれぞれ異なります。どちらも中小企業にとって重要な法律であり、混同しやすいため、違いを明確に理解することが大切です。
ここからは、それぞれの法律の目的と規制内容の違いを見ていきましょう。
参考)公正取引委員会「独占禁止法・下請法について知りたい」
なお、以下の記事では下請法について詳しく紹介しています。こちらも参考にしてみてください。
下請法とは?中小企業が知るべき4つの義務と禁止行為をわかりやすく解説
目的の違い
独占禁止法の目的は、市場における自由で公正な競争を守ることです。すべての企業が対等な立場で競争できる環境を整え、消費者の利益と経済全体の健全な発展を図るために制定されました。競争を不当に制限するような行為を排除することが、法律の基本的な考え方です。
一方、下請法の目的は、親事業者と下請事業者の間における不公正な取引を防ぐことにあります。とくに中小企業などの下請事業者が、力のある親事業者から不当な要求を受けないよう保護するための法律です。つまり、取引関係における立場の違いに着目し、弱い立場にある事業者を守る役割を果たしています。
以下は「自社が下請法の対象に含まれるか」について、確認すべきポイントを紹介した記事です。こちらも参考にしてみてください。
下請法の対象かどうかを確認するには?中小企業が押さえるべきポイントを解説
規制内容の違い
独占禁止法では、企業間の競争を妨げる行為全般が規制対象となります。たとえば、価格カルテルや談合、買いたたき、優越的地位の濫用など、市場の競争を阻害する行為を広く取り締まっています。対象となるのは企業の規模にかかわらず、すべての事業者が規制の対象です。
それに対し、下請法は、親事業者が下請事業者に対して行う不適切な取引行為を規制しています。具体的には、支払いの遅延、返品の強要、発注書面の未交付などが該当します。
このように、下請法には独占禁止法の補完法としての役割があるのです。
具体例で学ぶ!独占禁止法の違反事例
日常的な企業活動の中にも、法令違反につながる行為が潜んでいます。ここからは、実際の違反事例を分類別に紹介し、それぞれの行為がどのように問題とされたのか、実務上の注意点とともに解説します。
各事例を通じて、法令の理解を深め、自社の取引に活かしていきましょう。
私的独占大手パソコン部品メーカーの事事例
ある大手パソコン部品メーカーは、国内パソコンメーカー5社に対して、自社のCPUを多く搭載させるために、CPUを多く買ってくれることを条件に、リベート(売上割戻金)や資金提供を持ちかけました。
これは、他社のCPUを採用させないようにするための圧力行為であり、「私的独占」に該当します。
参考)公正取引委員会「大手パソコン部品メーカーによる私的独占」
カルテル/不当な取引制限旅行業者の事例
複数の旅行業者が、修学旅行のバス代金や宿泊料について、事前に協議し合意していた事例です。この合意により、価格競争が排除され、消費者が自由に安いプランを選べない状況が生まれました。
こうした企業間の価格調整行為は、典型的なカルテルとされ、独占禁止法に該当します。
参考)公正取引委員会「旅行業者によるカルテル」
入札談合/不当な取引制限電気設備工事の事例
ある自治体の電気設備工事に関する入札で、参加事業者10社が事前に受注予定者を決め、ほかの事業者は価格調整に従って入札するという談合が行われていました。
このような行為は、公正な入札制度を形骸化させるものであり、公共事業における信頼性を大きく損ないます。自治体が発注する電気設備工事の分野における競争を実質的に制限しているため、不当な取引制限に該当します。
参考)公正取引委員会「電気設備工事の入札参加業者による入札談合」
【再販売価格の拘束】アイスクリーム製造販売業者の事例
アイスクリームメーカーが、自社商品を取り扱う小売店に対し、あらかじめ設定した販売価格を守るよう指示していた事例です。
このようにメーカーが小売価格を拘束する行為は、流通過程における価格の自由な決定を妨げるとして、独占禁止法の「再販売価格の拘束」に該当します。意図せず違反行為にあたることを防ぐためにも、契約内容の明文化と社内共有を徹底することが求められます。
参考)公正取引委員会「アイスクリーム製造販売業者による再販売価格の拘束」
【共同の取引拒絶】タクシー事業者の事例
タクシー事業者21社が、低額運賃で営業するタクシー会社に対して共通乗車券事業(タクシーチケッ事業)に参加することを拒んでいた事例です。
低額でタクシーに乗れると、顧客が低額の事業者に流れてしまうため、それに対する報復行為のような形で取引拒絶をしていました。
これは不公正な取引方法の「共同の取引拒絶」に該当します。
参考)公正取引委員会「タクシー事業者による共同の取引拒絶」
【優越的地位の濫用】大手家電販売業者の事例
大手家電量販店が、納入業者に対して店舗の新規オープンの際に、通常必要となる費用を支払わずに従業員等を派遣させていた事例です。
派遣の条件について合意することなく派遣されたスタッフは、自社商品に関係なく陳列・補充や接客を強いられました。
このように、取引上の立場を利用して不利益を押しつける行為は「優越的地位の濫用」に該当します。
参考)公正取引委員会「大手家電販売業者による優越的地位の濫用」
独占禁止法違反を防ぐために企業ができる対策
独占禁止法に違反しないためには、企業全体でコンプライアンス意識を高め、日常業務の中にリスク管理の視点を取り入れることが大切です。
ここからは、企業ができる基本的な対策を4つ紹介します。
営業・購買部門でも法的知識を持つ
独占禁止法は法務部門だけの問題ではなく、営業・購買など取引の前線に立つ部門でも理解しておくべきです。現場では価格交渉や取引先の選定など、法に関わる判断が日常的に行われています。
たとえば、買いたたきや特定企業の排除といった行為が、優越的地位の濫用に該当する可能性があります。社員一人ひとりが法的リスクを認識し、適切に行動できるよう、社内研修やガイドラインの整備が重要です。
自社の取引慣行をチェックする
長年続けている取引慣行が、独占禁止法に違反していないか見直すことが必要です。たとえば、再販売価格の拘束や不公平な返品条件が常態化していると、それだけで違反と判断される可能性があります。
まずは取引内容を書面で整理し、不当な優遇や一方的な条件が含まれていないかを確認しましょう。社内での定期的なチェック体制を整えることが、未然の防止につながります。
業界団体・共同取り組みには慎重に参加する
業界団体の活動や共同事業への参加は、有益な情報交換や事業機会につながる一方で、独占禁止法違反の温床となるリスクもあります。
とくに、価格に関する協議や取引先の排除を促すような話し合いは、カルテルや共同の取引拒絶と見なされる恐れがあります。団体活動に参加する際は、その内容が法に抵触しないかを必ず確認し、必要に応じて社内で共有しましょう。
気になる場合は、早めに専門家に相談を
「これは違反かもしれない」と感じたときは、迷わず弁護士や公正取引委員会の相談窓口への連絡が大切です。自己判断で対応を誤ると、違反行為が長期化し、結果として重い処分を受けるリスクが高まります。
専門家の助言を早期に受けることで、最小限の影響で問題を収束させることが可能になります。
まとめ
独占禁止法は、公正な競争を守るためにすべての企業に関わる重要な法律です。違反すると、課徴金や刑事罰だけでなく、社会的信用の低下といった深刻な影響を受ける可能性があります。
中小企業でも例外ではなく、日常業務の中にリスクが潜んでいることを理解することが大切です。取引慣行の見直しや法的知識の共有、そして気になる点があれば早めに専門家へ相談するなど、実務に活かせる対策を講じていきましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録