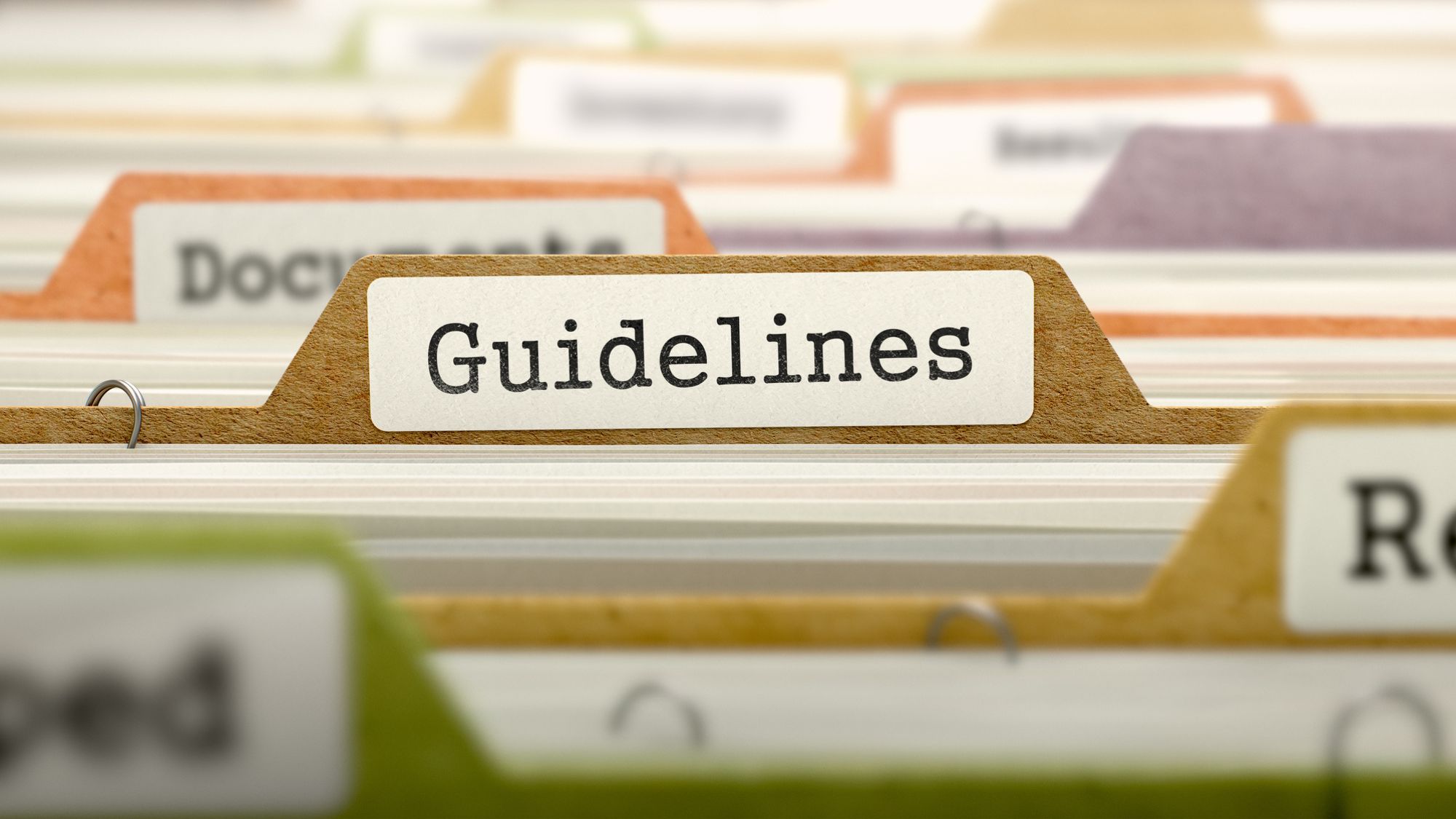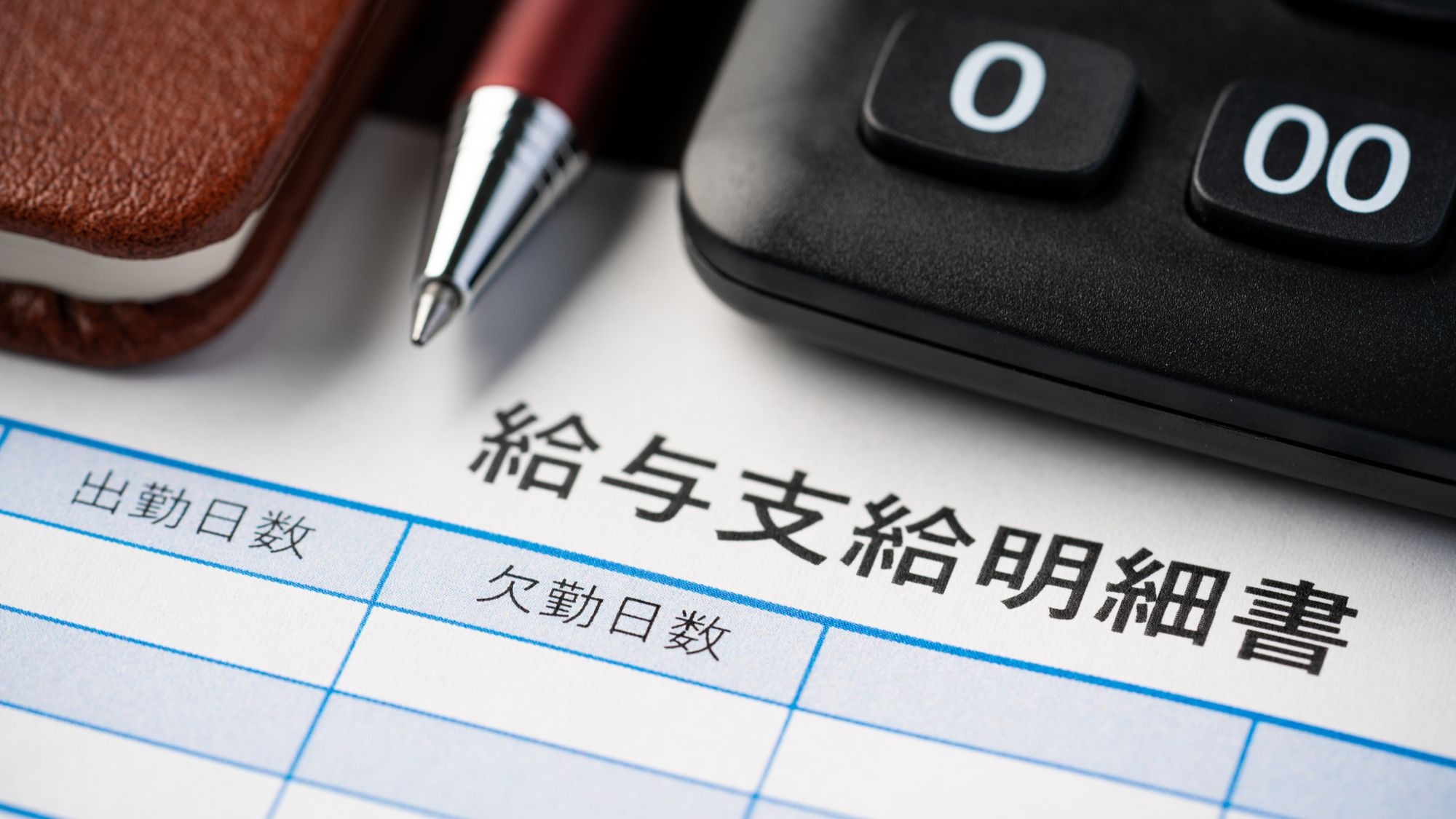企業におけるコンプライアンスの確立方法、その手法とは

コンプライアンス(compliance)は、直訳すると「法令遵守」を意味しています。
ただし、ビジネス用語としての「コンプライアンス」は、法律・規則・倫理観等を守りながら企業が組織活動を行うことを意味します。
そこで今回は、コンプライアンスはなぜ必要なのか、実際に起こった違反の事例、コンプライアンスを強化するメリット、コンプライアンスの強化方法などを紹介します。
コンプライアンス強化による企業価値の向上に興味がある方は、ぜひご一読ください。
コンプライアンスとは何か
コンプライアンス遵守は投資家や消費者からの信頼を得る基盤です。
コンプライアンス違反による制裁や評判低下は、企業にとって大きなマイナスになります。
近年ではコンプライアンスを軽視した企業が、SNSでの批判に晒され、ブランドの信頼性が失墜するケースも多々あります。
そのためコンプライアンス重視は企業にとって必須項目になっているのです。
コンプライアンス違反の事例
コンプライアンス違反の事例に関しては、日々報道がなされており、枚挙にいとまがありません。
結果として、社会的信用の失墜や売り上げの減少にとどまらず、企業が倒産に追い込まれるケースも少なくないため、細心の注意が必要です。
次項では、コンプライアンス違反の事例を複数紹介します。社内での情報共有や注意喚起の参考にしてください。
【コンプライアンス違反事例】電通:女性社員の過労死
2015年に電通に入社した女性社員は、配属されたデジタル広告部門で月に100時間を超える残業を課せられ、過労に苦しんでいました。同社では労働基準法に違反する長時間労働が常態化していたとされています。
さらに上司や同僚からのパワハラにより、同社員は精神的にも肉体的にも追い込まれ、同年12月に命を絶ちました。
これを受け、厚生労働省は電通に対し是正勧告を出し、電通は労働環境の改善を迫られました。
この事案は多くの報道がなされ、注目を浴びています。
労働基準法の遵守と職場環境の見直しが社会全体で再認識され、コンプライアンスの重視がより一層注目されるきっかけとなりました。
【コンプライアンス違反事例】ビッグモーター:修理費の水増し
2023年、ビッグモーターの複数の店舗で、顧客の車両にゴルフボールをぶつけたり、工具で傷をつけるなどして損傷を意図的に加え、保険金を不正に請求する手口が発覚しました。
この不正行為は、ビッグモーターの元従業員の告発により表面化し、各地の店舗でも同様の行為が常態化していたことが明らかになりました。
この事案では、社会的な批判が集中、業績が大きく悪化し、同社社長が辞任する事態に陥っています。
また不正を認識していたことを疑われた損保ジャパンなどの損害保険会社にも、金融庁から立ち入り検査がなされました。結果的に、損保ジャパンの会長も辞任しています。
【コンプライアンス違反事例】日野自動車:排出ガス試験の不正操作
2022年には、日野自動車が製造した一部のディーゼルエンジン車について、排出ガスの試験結果を不正に操作していたことが発覚しています。
日野自動車では、エンジンの性能が規制値を満たすように試験中に調整され、実際の運行では規制基準を超える排出ガスが放出されていました。
この不正は常態化しており、約20年間もの期間続けられていたようです。
結果的に日野自動車は企業の信頼性を大きく失い、 販売停止やリコールの対応が求められる事態に陥りました。
その後、生産担当などの取締役3人が辞任、歴代社長ら6人、調査報告書で不正への関与が指摘された元役員5人には、報酬の一部返納も求められています。
この不正事件は、自動車業界全体に対してコンプライアンス遵守の重要性を再認識させるきっかけとなりました。
【コンプライアンス違反事例】神奈川県職員:セクシャルハラスメント
2023年、神奈川県は地域県政総合センターの男性職員に対して減給処分を行いました。
この男性職員は複数の女性職員に対して、2018年ごろから繰り返しセクシャルハラスメントを行ったとされています。
職場内外で不適切な発言を繰り返したり、女性職員が断っているにもかかわらず何度も食事に誘ったりする行為が続いていたとのことです。
この行為は内部通報を受けて発覚し、職員は調査に対し「場を和ませるためにやった」と弁明しました。
減給処分が発表された当日、この職員は依願退職しています。
【コンプライアンス違反事例】三菱UFJ銀行:個人情報の不正利用
2024年、三菱UFJ銀行で顧客の個人情報や非公開情報が不正に利用されていたことが発覚しました。
同行の一部の従業員が業務範囲を超えて顧客の個人情報を無断で閲覧し、営業目的などで外部に共有した疑いがあるとされています。
その後、金融庁は三菱UFJ銀行に対して業務改善命令を出しました。
結果、三菱UFJ銀行には社会的な批判が集中、顧客の信頼を大きく損なう事になりました。
【コンプライアンス違反事例】兵庫県警:ハラスメント
2023年3月、兵庫県警はパワーハラスメントや虚偽申告を行ったとして、複数の警察官を処分しています。
50代の警部補は部下3人に対して、大声で叱責したり、腹部を殴るなどの暴力を振るったりしました。また育児休暇の取得の申し出に「今の職場が嫌なのか」と、言ったことが確認されています。
部下の一人が体調を崩し上司の警部に相談したものの、警部は上層部に報告を行わなかったことが分かっています。
その後、不祥事が発覚、パワーハラスメントと認定され、警部補と相談を受けた警部は処分されました。
また40代警部補は、週2~3日のペースで部下2人を連れ、居酒屋やスナックのはしご酒を繰り返したことが確認されています。
兵庫県警は、上司の立場を利用して酒席を強要する、アルコールハラスメントと判断しました。
身近に潜むコンプライアンス違反
コンプライアンス遵守の意識を持っていたとしても、気づかないうちに、コンプライアンス違反を犯しているという可能性もあります。
ここでは気を付けるべき、身近に潜むコンプライアンス違反の事例を紹介します。
身近に潜むコンプライアンス違反:企業情報の漏洩
会社の経営情報や顧客や従業員の個人情報など、業務を通じて得た情報は、家族や友人にも漏らしてはいけません。
もしも友人に業務を通じて得た情報をうっかり話してしまい、その結果、会社に損害が生じた場合、重大な責任を問われることがあります。
また、電車や飲食店など、多くの人が集まる場所では、情報漏洩に対して細心の注意が必要です。
身近に潜むコンプライアンス違反:備品の私的利用
企業では、従業員が業務で使用できる設備や備品が提供されています。
これらは業務に使用することが前提であり、私的に使用するとコンプライアンス違反となる可能性があります。
例えば、企業の備品であるビデオカメラを私的に使用する、というような行為はコンプライアンス違反で責任を問われることがあります。
身近に潜むコンプライアンス違反:データの社外への持ち出し
企業が保有する個人情報や企業情報をコピーしたり、持ち出したりする際は、細心の注意が必要です。
社外で業務を行うため、USBメモリにデータをコピーして持ち帰る、などの行為もコンプライアンス違反に問われる可能性があります。
業務上どうしてもデータを持ち出さなければならない場合は、必ず社内のセキュリティ規定に従い、企業の許可を得ることが必要です。
身近に潜むコンプライアンス違反:会社の許可を得ていない残業
残業は通常、企業の指示に基づいて行われるものであり、多くの企業では従業員が自己判断で勝手に残業することは認められていません。
企業には残業に対して適切な賃金を支払う義務があるため、自発的に残業を行う場合には事前に企業側の承認を得ることが必要です。
また、長時間働くことで健康を害し、労働災害が発生するリスクも高まるため、注意が必要です。
CSRとコンプライアンスを強化するメリット
一般的にCSR(Corporate Social Responsibility)と言われる企業の社会的責任は、社会課題の変化により、年々、重要度が増しています。
昨今、特に求められるようになったのは以下のような項目です。
宗教、性別、年齢などに基づかない公正な評価
地球環境への配慮
従業員、投資家、地域社会などのステークホルダーに対する、責任ある行動
このように、社会が企業に求める事柄は大きくなっています。
コンプライアンスの遵守は企業がCSRを果たすうえで必須の項目です。そこでここでは、CSRとコンプライアンスを強化するメリット を紹介します。
企業の評判・ブランドイメージを守る
コンプライアンスの遵守は、企業の評判やブランドイメージを保つことにつながります。
「安全性」「信頼性」の向上による、株価上昇や商品販売数の増加なども期待できるでしょう。
法的なリスクを軽減する
他社のデザインを模倣した著作権侵害、景品表示法違反、下請法違反など、コンプライアンス軽視による法的リスクは枚挙にいとまがありません。
このような法的リスクを避ける為、企業全体でコンプライアンスを強化することは極めて重要です。
ステークホルダーとの信頼関係の構築
企業がステークホルダー(従業員、取引先、顧客、投資家、地域社会など)との信頼関係を築く際、コンプライアンス遵守は欠かせない役割を果たします。
従業員のエンゲージメント向上
企業がコンプライアンスを遵守し、倫理的な姿勢を重視することで、従業員は自社に誇りを持ちやすくなります。
健全な企業文化の中で働けることが、モチベーションや満足度の向上につながり、採用率の向上だけでなく優秀な人材の流出も防ぎやすくなるでしょう。
取引先との円滑な関係構築
企業や従業員がコンプライアンスを遵守することで、取引先との取引がスムーズに進み、トラブルの発生リスクも減ります。
良好なビジネス関係を築く為にはコンプライアンスの遵守は欠かせません。
顧客の信頼の確保
企業が製品やサービスを提供する際にコンプライアンスを遵守していると、顧客からの信頼が高まり、リピート顧客やブランド支持者の増加にもつながります。
特に製品やサービスの安全基準を遵守することで、安心して利用できると顧客に感じさせ、信頼が高まります。
投資家との信頼関係の維持
投資家は企業の信頼性と透明性を重視しています。
コンプライアンスを遵守することで、財務報告やガバナンスが適切に行われていると判断され、投資先としての信頼が高まるでしょう。
コンプライアンス違反が発覚すれば株価が下がるリスクがあり、投資家に不利益をもたらす可能性があるため、コンプライアンス遵守は企業価値の維持に直結しています。
地域社会との協力体制の維持
地域社会はコンプライアンスを遵守し、社会的責任を果たす企業を歓迎します。
コンプライアンスを遵守することは、地域社会の一員としての責任を果たすことであり、企業が地域社会の信頼を得るための基盤となります。
特にCSRを通じた社会貢献が進む中、コンプライアンス遵守は信頼ある企業市民として評価されるために欠かせません。
企業がコンプライアンスを強化する為の手法
「コンプライアンスを遵守しましょう!」と従業員に伝えても、コンプライアンスの強化はできません。
そこでここでは、企業がコンプライアンスを強化する手法を紹介します。
コンプライアンスマニュアルの策定
コンプライアンスマニュアルは、従業員が法律や規則、倫理的な基準を守るための指針をまとめた資料です。
このマニュアルには、法令や業界の基準、企業が定めた倫理的な行動規範などが示されており、守るべき姿勢や行動指針が記載されています。
コンプライアンスマニュアルを策定し、企業が率先して指針を示すことは、コンプライアンスの強化にとって重要です。
コンプライアンス研修を実施する
コンプライアンスの強化にはコンプライアンス研修も有効な手段です。
ここではコンプライアンス研修の一例をご紹介します。
コンプライアンスマニュアルを周知するための研修
コンプライアンスマニュアルは策定するだけでは意味がありません。
策定したコンプライアンスマニュアルを周知する機会を設けることが重要です。
このような研修もコンプライアンス強化に役立ちます。
ハラスメント違反に関する研修
パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなど、ハラスメントに関する不祥事は後を絶ちません。
異なる価値観によって相手を傷つけたり、不快な行為となることを防ぐ為に、ハラスメント違反に関する研修は有効な手段です。
特定の業務に絞ったコンプライアンス違反の研修
企業によっては特定の業務に絞った研修を行う事も検討できます。
具体的にはデザインを模倣した著作権侵害、法令に反して商品を良く見せようとした景品表示法違反などが挙げられます。
SNS運用における研修
近年、SNSの普及に伴い、コンプライアンスを軽視した企業が、SNSで顧客からの批判に晒され、ブランドの信頼性が失墜するケースが数多くあります。
また顧客からではなく、従業員のSNS投稿で企業価値が損なわれるケースも多々あります。
従業員やアルバイトが職場での不適切な行為を撮影し、SNSに投稿、結果として企業のブランドイメージが失墜するような不祥事も後を絶ちません。
SNSは情報拡散力が強く、短時間で数多くの人々に届くため、コンプライアンス違反が発覚すると瞬時に情報が拡散されてしまうリスクがあります。
そのため、コンプライアンスを遵守し、社員教育を徹底することは非常に重要です。
コンプライアンス研修の依頼先
著作権侵害や景品表示法違反など、法律を扱う研修に関しては弁護士などの専門家に依頼しましょう。
他にも、ハラスメントに関する研修などは、社員教育などを扱う専門の企業などに依頼することもできます。
またコンプライアンスマニュアルの周知などは、マニュアル作成者が研修を行うのが最適です。
eラーニングの技術を活用する
特に社員数の多い大企業などは、全社員を研修の為に集めることは困難です。
そのため、eラーニングの技術を活用し、いつでも研修の動画を閲覧できるようにしておくような工夫も重要な要素です。
コンプライアンス通報窓口の設置
コンプライアンス通報窓口とは、コンプライアンス違反に対応するために設置された公益通報窓口の一種です。
従業員が社内で不正や問題行為を発見した時、通報するための窓口を設置することで、被害の拡大を防ぐ効果が期待できます。
通報窓口は内部通報窓口と外部通報窓口があります。
内部通報窓口は、社内の総務部や法務部に設置されることが多く、外部通報窓口は、社外の弁護士事務所、または通報受付代行サービスを活用する企業が一般的です。
通報窓口を設置する際は、内部通報窓口と外部通報窓口の両方を設置するようにしましょう。
まとめ
コンプライアンスは、現代の企業経営において欠かせない要素です。
コンプライアンスを強化することは、法令違反によるトラブルやリスクの回避だけでなく、企業価値の向上にもつながります。
コンプライアンスマニュアルの策定、コンプライアンス研修の実施など、有効な手段を講じ、コンプライアンス強化を実施していきましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録