BCM(事業継続マネジメント)を始めるには?導入手順をわかりやすく解説

災害や感染症、サイバー攻撃など、企業を取り巻くリスクが年々多様化・深刻化するなか、「もしもの時」に備える重要性が高まっています。こうした背景から注目されているのが、BCM(事業継続マネジメント)です。
「BCP(事業継続計画)は知っているけれど、BCMって何?」「自社のような中小企業でも必要なの?」と感じている方も少なくないでしょう。
この記事では、BCMの基礎知識から、導入メリット、そして実際の導入手順までをわかりやすく解説します。
“守り”だけでなく“攻め”の視点でも重要なBCM。自社の信頼を守り、成長につなげる第一歩として、ぜひ本記事を参考にしてください。
また、以下の資料では企業のガバナンス整備のコツを紹介しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。
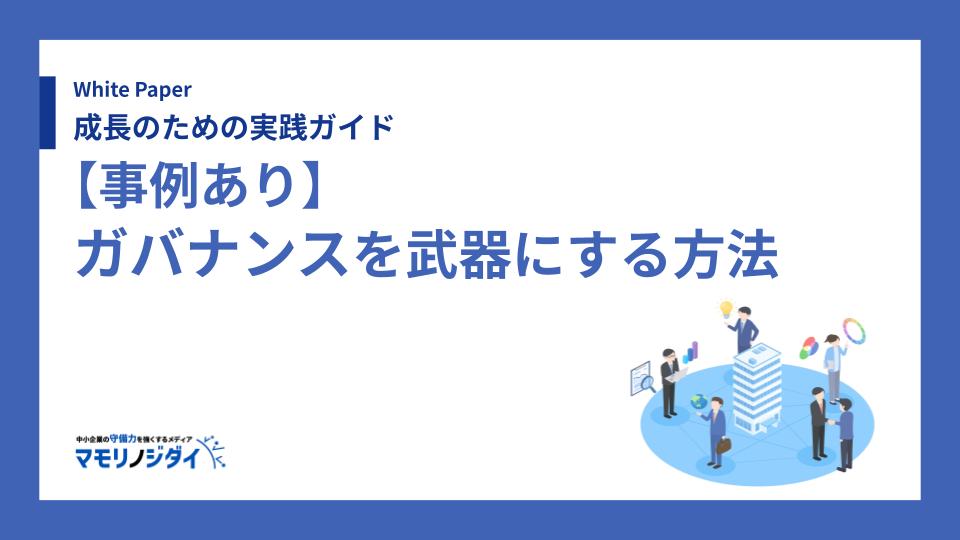
>>ガバナンスを武器にする──成長のための実践ガイドのダウンロードはこちら
まずBCMの意味をおさえよう!
BCM(事業継続マネジメント)とは、緊急事態が発生した際に企業活動を止めない、または速やかに復旧させるための「平常時からの取り組み全体」を指します。
単なる危機対応策ではなく、教育や訓練、設備の整備など、日頃の準備と体制構築こそが重要です。中小企業庁も、BCP(計画)を有効に機能させるためには、BCMという継続的なマネジメントが不可欠であると明言しています。
参考)中小企業庁「3 BCM(事業継続マネジメント)の効果と課題」
BCPとBCMの違い|計画(Plan)と運用(Manage)の関係性
BCP(事業継続計画)は、災害や事故が発生したときにどう行動すべきかを文書化した「計画」のことです。一方、BCMはその計画を確実に機能させるための「運用・管理の仕組み」を指します。
両者の違いを表で確認しましょう。
| 項目 | BCP(Business Continuity Plan) | BCM(Business Continuity Management) |
| 意味 | 事業継続のための計画書 | 事業継続のための運用体制・管理活動 |
| 目的 | 緊急時の行動指針を明確にする | 平時からBCPを実行可能にする体制構築 |
| 実施タイミング | 主に「有事」 | 主に「平時」 |
| 活動内容 | 手順書の作成、代替手段の整備 | 訓練・教育・点検・改善の継続運用 |
| 成果物 | 文書化されたBCP | 継続的な訓練・教育・マネジメント活動 |
たとえば、BCPがあっても社員が内容を知らなかったり、訓練が不十分であれば緊急時に役立ちません。つまりBCPは“設計図”、BCMは“その設計図を現場で動かす仕組み”です。
両者はセットで運用されることで、真の事業継続力が発揮されます。BCP対策に関しては、以下の記事で詳しく紹介していますので、参考にしてください。
参考記事:BCP対策とは?具体的なやり方、マニュアルの作り方などをわかりやすく解説
BCMS(事業継続マネジメントシステム)とは?国際基準で見る全体像
BCMS(Business Continuity Management System)とは、BCMを組織的かつ継続的に運用するためのマネジメントシステムです。
ISO22301という国際規格に基づいており、方針の策定、リスク評価、教育・訓練、見直しまでを体系的に管理します。PDCA(計画・実行・確認・改善)を回し続ける枠組みであり、取引先や金融機関への信頼性アピールにもつながる点が特徴です。
なぜ今、BCMが中小企業にも求められているのか
これまで事業継続対策といえば、大企業が取り組むものというイメージがありました。しかし、近年では中小企業にとってもBCMの必要性が急速に高まっています。
災害やパンデミックといった予測不能な事象の増加に加え、取引先や行政からの要請、経営戦略としての価値が見直されてきたことが背景にあるのです。
以下で詳しく解説します。
地震・感染症・サイバー攻撃…あらゆる事業リスクに備える時代
東日本大震災や新型コロナウイルスの感染拡大を経て、企業が抱える事業リスクは多様化・深刻化しています。さらに近年は、サイバー攻撃や気候変動による異常気象も深刻なリスクです。
こうしたリスクは企業規模に関係なく襲いかかるため、「備えを持たない中小企業ほど倒産リスクが高まる」といった警鐘も鳴らされています。
取引先・自治体・融資機関が「備え」を求めてくる理由
近年、災害や感染症、サイバー攻撃などのリスクが高まる中で、BCM(事業継続マネジメント)への取り組みが企業評価の一部となっている状況です。
取引先や自治体、金融機関は、緊急時にも事業を継続できる体制がある企業を優先し、取引・委託・融資などを判断する材料にしています。BCMは単なるリスク管理ではなく、信頼性の証明としてもが求められているのです。
| 相手先 | 求められる内容 | 背景と理由 |
| 取引先 | BCP(事業継続計画)の提示 | 災害や障害時にも納品やサービス提供を継続できるかを重視しているため |
| 自治体 | 入札・委託契約時にBCP策定を条件とすること | 災害対応力の高い事業者を地域の重要インフラとして確保するため |
| 金融機関 | 融資審査時にBCMの取り組み状況を確認 | 緊急時の経営破綻リスクを軽減し、貸倒れを防ぐため |
| 損害保険会社 | BCMの有無によって保険料に差を設けるケースも | リスク低減の取り組みを評価し、インセンティブとして保険料に反映するため |
このように、BCMの導入は取引上の信用獲得や資金調達の優位性にもつながります。中小企業であっても「備えがある会社」として評価されることは、大きな差別化要素です。
なお、金融機関からの信頼を得るためにはコーポレートガバナンス報告書も有効です。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
参考記事:中小企業経営者こそ知っておこう!コーポレートガバナンス報告書の作成・活用まで
BCMは“保険”ではなく、“攻め”の経営戦略でもある
BCMは単なる危機回避策ではありません。企業の競争力強化にもつながる「攻め」の戦略です。
たとえば、有事に素早く復旧できる体制なら、他社が混乱するなかでも事業を継続でき、顧客からの信頼を獲得できます。さらに、BCM導入により社内の情報整理や意思決定フローの明確化も進むため、平時の業務効率を高めることも可能です。
中小企業にこそ、柔軟かつ迅速な対応力を育むBCMの導入が有効といえます。
BCM導入で得られる3つのメリット
BCM(事業継続マネジメント)の導入は、単にリスクへの備えにとどまりません。企業の信頼性や組織力を高める効果もあります。
ここでは特に重要な3つのメリットを紹介しましょう。
メリット1|取引先からの信頼を獲得できる
BCMを導入し、緊急時でもサービスや供給を止めない体制を整えることで、取引先からの信頼性が高まります。特に大企業や官公庁との取引では、BCPやBCMの有無が選定基準になることもあるのです。
日常の業務では見えにくい部分ですが、いざというときに備えている企業かどうかは、ビジネス継続における信用の分かれ目です。
取引先からの信頼を得るためにサスティナビリティ経営も求められています。以下の記事で解説していますので、こちらもご覧ください。
参考記事:サステナビリティ経営とは?企業事例とメリット、導入のポイントを徹底解説
メリット2|緊急時の混乱を最小限に抑えられる
災害やトラブル発生時に、あらかじめ定めた対応マニュアルや代替手段があることで、組織内の混乱を抑え、迅速な対応が可能です。
責任分担や判断基準が明確なため、個人に過度な負荷がかかるのを防ぎ、業務の優先順位を見極めながら事業継続に向けて動けます。初動の差が復旧スピードを左右するため、BCMは非常時対応の要です。
メリット3|従業員・地域の安心につながる社会的価値
BCMは企業の内部統制強化だけでなく、従業員の安全確保や地域社会との連携強化にも寄与します。従業員が「この会社なら何かあっても守られる」と感じられる環境を整えることがメリットです。
また、地域の復旧活動に貢献する存在としての評価も得られ、企業の社会的責任(CSR)を果たす重要な要素になります。
従業員の安全配慮は労働安全衛生法の観点でも重要です。以下の記事では労働安全衛生法について詳しく紹介しています。
参考記事:中小企業が知っておくべき!労働安全衛生法改正の最新動向と対策【2025年・2026年を見据える】
中小企業でもできる!BCMの導入6ステップ
BCM(事業継続マネジメント)は大企業だけのものではなく、中小企業でも実践可能なプロセスです。
以下の6ステップに沿って進めれば、初めての導入でも着実に体制を整えることができます。
STEP1|基本方針の策定と体制の構築(まずはリーダーを決める)
最初に、自社のBCMの目的や方針を明文化し、推進体制を整備しましょう。まずは責任者を明確にし、社内横断的に協力できる体制を作ることが重要であり、経営層の関与も不可欠です。
STEP2|事業への影響度とリスクを洗い出す(BIAの考え方)
BCM導入においては、業務が停止した際に企業へどれだけの影響が出るかを把握する「BIA(Business Impact Analysis:ビジネス影響分析)」が重要になります。
これは、業務ごとの重要度や復旧までの猶予時間、停止による損失などを定量・定性の両面から洗い出し、優先的に守るべき業務を明確にするプロセスです。
たとえば以下のような表を作成して、自社の業務の影響度を比較・整理しましょう。
| 業務名 | 停止による影響(定量) | 停止による影響(定性) | 許容停止時間 | 優先度 |
| 顧客対応業務 | 売上損失:100万円/日 | 信頼低下、クレーム増加 | 24時間以内 | 高 |
| 受発注業務 | 売上機会損失:50万円/日 | 納期遅延、取引先からの信用失墜 | 48時間以内 | 中 |
| 総務・経理業務 | 特になし(短期的には) | 社内混乱、給与遅配リスク | 1週間以内 | 低 |
このように、「影響の大きさ」「停止の許容時間」「事業継続への優先度」を可視化することで、どの業務を最優先で守るべきか、どこにリソースを集中させるべきかが明確になります。
STEP3|リスク対応戦略と代替手段を検討する
リスクを洗い出したら、次はそのリスクをどう回避・軽減し、万が一発生しても業務を継続できるかを検討しましょう。
たとえば「地震でオフィスが使えなくなるケース」の場合、以下が該当します。
- リモートワーク体制を整備する
- クラウド環境に業務システムを移行する
- 代替の仕入先や配送ルートを確保しておく
ポイントは、「すべてを守る」のではなく「重要業務の継続に絞って戦略を組む」ことです。コストと現実性を見極めながら、実行可能な代替策を組み合わせていきましょう。
STEP4|BCP(計画)を文書化し、関係者と共有
どんなに優れた対応策も、口頭での共有や個人の記憶に頼っていては、いざという時に機能しません。BCPとして明文化し、関係者全員がいつでも確認できるように整備する必要があります。
文書には、緊急時の連絡体制、代替手段の運用方法、復旧手順、社内外への情報発信方法などを含めましょう。また、印刷・クラウド保存の両方を行い、停電や通信障害などにも対応できる形にしておくと安心です。
STEP5|社内で訓練・教育を実施して「絵に描いた餅」にしない
BCPの文書があっても、実際に使えなければ意味がありません。訓練や教育を通じて、計画を「実行できるもの」に落とし込むことが重要です。
たとえば、年1回の避難訓練やシステムダウン時の模擬演習などを通じて、従業員が緊急時にどう動くべきかを体感できる機会を設けましょう。新入社員やアルバイトを含めた全員が共通認識を持つことが、混乱の最小化につながります。
STEP6|定期的に見直し・更新して育てる
BCMは一度作って終わりではありません。事業環境の変化や新たなリスクの出現に応じて、計画を定期的に見直し、育てていくことが求められます。
たとえば、新しい取引先が加わった、従業員構成が変わった、リモートワーク制度を導入した、といったタイミングでBCPも更新が必要です。年1回の棚卸しと、災害や障害発生後のレビュー(事後検証)を通じて、より現実に即した計画へと進化させましょう。
まとめ
BCMは、災害や不測の事態が起きた際に企業の重要業務を継続・早期復旧させるための運用管理の仕組みです。単なるBCPの策定にとどまらず、教育・訓練・見直しを繰り返しながら「本当に使える体制」を整えることが求められます。
BCMは“守り”だけでなく、“攻め”の経営にも直結する施策です。基本方針の策定から段階的に進めることで、中小企業でも十分に対応可能といえます。
まずは自社のリスクを正しく把握することから、一歩を踏み出してみましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録











