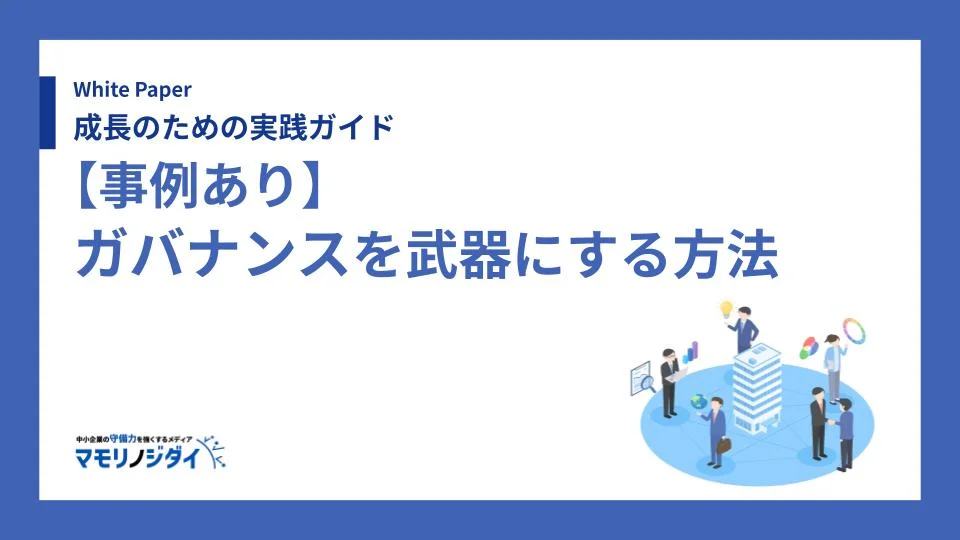財務諸表とは?読み方・分析方法・決算書との違いを初心者向けにわかりやすく解説

財務や会計関連の仕事をしていない人でも、「財務諸表」という言葉を聞いたことがある人は多いかと思われます。
しかし、「財務諸表が具体的にどのようなものなのか」「財務諸表を読むことで何がわかるのか」、といった点についてはよく知らないということも珍しくないはずです。
そこでこの記事では、そもそも財務諸表とはどういったものなのかについてや、財務諸表の読み方や分析方法などについて、わかりやすく解説していきます。
財務諸表の読み方を覚えて、自社や競合他社の分析に活用したいとお考えの場合は、ぜひ本記事をご一読ください。
財務諸表とは?
まずは、財務諸表の概要や、財務諸表からわかること、決算書との違いについてわかりやすく解説していきます。
財務諸表の概要
財務諸表とは、「企業の財務情報」や「その年に行った経済活動」を明確にするための一連の書類のことです。
わかりやすく一言でまとめると、「財務諸表 = 企業の成績表」となります。
資産や負債、当期の売上、どういった企業に投資しているか、などの情報を詳らかにし、自社の経営状況を内部・外部へ伝える役割を果たしています。
なお、日本会計基準に即した場合、財務諸表として以下4つの書類を必ず作成しなければなりません。
- 損益計算書
- 貸借対照表
- キャッシュフロー計算書
- 株主(社員)資本等変動計算書
企業規模によっては、他にも提出が義務付けられている書類があります。
例えば、上場企業の場合だと、金融商品取引法によって有価証券報告書の提出も必須です。
財務諸表でわかること
財務諸表を確認することで、以下のようなことがわかります。
- 売上高
- 利益
- 設備投資の内容
- 資産と負債のバランス
- お金の流れ
- 資金調達先 …など
簡単にいうと、「経済活動によってどの程度収益を得ているのか」「現状の資産状況はどうなのか」「どれくらいの借金があるのか」などが一目でわかる、ということです。
ステークホルダーがこういった情報を正確に把握することは重要です。
投資家なら「投資するに値する企業かどうか」を判断できますし、金融機関なら「融資しても問題ないかどうか」を判断できます。
経営状態を「財務諸表」という形で明確に示すことで、自社の将来性をアピールでき、積極的な投資や融資を受けやすくなるのです。
財務諸表と決算書の違い
まず、よく目にする「決算書」という表記は通称となります。
正しくは「決算報告書」という名称で、法的には「財務諸表」や「計算書類」と呼ばれる書類を総じた用語です。
したがって、「財務諸表」と「決算書」という言葉には、法律において何か大きな違いがあるわけではありません。
ただし、「財務諸表」と「計算書類」については、法的に明確な違いがあります。
具体的な違いについては、以下を確認してください。
| 財務諸表 | 計算書類 | |
| 準拠する法律 | 金融商品取引法 | 会社法 |
| 必要書類 | ■貸借対照表 ■損益計算書 ■キャッシュフロー計算書 ■株主資本等変動計算書 ■附属明細表 | ■貸借対照表 ■損益計算書 ■株主資本等変動計算書 ■個別注記表 ■附属明細書 |
財務諸表の中でも特に重要なのが「財務三表」
財務諸表の中でも、特に重視されるのが「財務三表」と呼ばれる以下の書類です。
- 貸借対照表(B/S)
- 損益計算書(P/L)
- キャッシュフロー計算書(C/F)
それぞれがどういった書類であるのか、以下の項目で解説していきます。
貸借対照表(B/S)
貸借対照表とは、基準となる時点での企業の財務状況を表す書類のことで、資産や負債がいくらあるのかを可視化することできます。
貸借対照表は、「資産の部」「負債の部」「純資産の部」に分かれ、左側に資産の内容を記載し、右側に負債と純資産の内容を記載する形となります。
それぞれの部門で把握できる内容は以下の通りです。
| 部門 | わかること |
| 資産の部 | 現金・売掛金・有価証券・商品や製品といった「現金化しやすい流動資産の金額」や、機械や装置・土地・建物といった「現金化しにくい固定資産の金額」が記載されている。企業がどのようなことにお金を使っているか、どれだけ現金化しやすい資産があるか、などがわかる。 |
| 負債の部 | 買掛金・未払いの税金・支払手形・短期借入金といった流動負債や、1年以上の支払い猶予がある固定負債が記載されている。その企業にどれだけの借金があるのかがわかる。返済期日の早い項目順に並んでいるため、上の方に記載されている金額が小さいほど経営状況としては安定していると考えられる。 |
| 純資産の部 | 資本金・利益準備金・積立金といった「返済する必要のないお金がどれくらいあるのか」が記載されている。企業として保有している純資産がわかる。 |
なお貸借対照表は、左側の「資産の部」と、右側の「負債の部」+「純資産の部」とが同額にならなければいけません。
このことから、貸借対照表は「バランスシート(B/S)」と呼ばれることもあります。
損益計算書(P/L)
損益計算書とは、一定期間における企業の売上や利益といった経営成績を表す書類のことです。
英語表記では「Profit and Loss Statement」となるため、略して「P/L」と表現されることもあります。
損益計算書は、「収益」「費用」「利益」の3要素から構成されます。
各構成要素に記載されている項目例については以下の通りです。
| 収益 | ■売上高 ■営業外収益 ■特別利益 |
| 費用 | ■売上原価 ■販売管理費 ■営業外費用 ■特別損失 ■法人税 |
| 利益 | ■売上総利益 ■営業利益 ■経常利益 ■税引前当期純利益 ■当期純利益 |
なお、企業が採用している会計基準によって項目が変わりますのでご注意ください。
上記は、あくまで一般的な項目例となります。
損益計算書は、損益分岐点の見極めにも役立つ書類であるため、ステークホルダーにとって欠かせない書類となっています。
キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書とは、企業の経済活動における資金の流れを記載した書類のことです。
英語表記では「Cash Flow Statement」となるため、略して「C/F」と表現されることもあります。
キャッシュフロー計算書は「営業活動」「投資活動」「財務活動」という3つの要素で構成されます。
それぞれの詳細については以下の通りです。
| 営業活動 | 本業でどれだけ利益を得ているのかがわかる。金額がプラスならば「現金に余裕がある」、金額がマイナスならば「資金的に不安定である」と判断できる。 |
| 投資活動 | 有価証券の売買や設備投資といった、企業の投資活動における現金の流れがわかる。有価証券の売買での成功や資産の売却などでプラスになり、設備投資などでマイナスとなる。 |
| 財務活動 | 資金調達・借入金の返済といった資金の流れがわかる。資金調達に成功すればプラスになり、返済が進んでいればマイナスとなる。 |
企業は、「黒字ならば倒産しない」というわけではありません。
黒字倒産という言葉がある通り、事業として利益が出ていても、倒産してしまう可能性があります。。
その理由は、「損益分岐点は超えているものの、一時的な現金の不足によって期日までに支払いができない」というようなケースがあるからです。
しかしキャッシュフロー計算書があれば、お金の流れが明確になるため、黒字倒産のリスクがあるかどうかを判断するのに役立ちます。
財務諸表を作成する目的
財務諸表を作成する主な目的は以下の通りです。
- 投資家の判断材料になる
- 株主が財務状況を把握できる
- 適正な会計処理が行われていることを税務署が確認できる
- 債権回収に問題がないことを訴求できる
- 取引先や従業員に経営状況が伝わる
以下の項目で詳しく解説していきます。
投資家の判断材料になる
企業が事業活動を拡大していくにあたって、投資家から資金を調達することができれば大きなアドバンテージとなるでしょう。
そして投資家は、企業に対して投資するかどうかを決める際、ほぼ確実に財務諸表を確認します。
企業の財務状況や経済活動、お金の流れを把握することで、投資するのに値する企業かどうかを判断するのです。
財務諸表を見て、「将来性がある」「今後も成長していく可能性が高い」と感じてもらえれば、投資を受けられる可能性が上がります。
株主が財務状況を把握できる
企業は、経営者のものでも取締役会のものでもなく、企業に対して出資している「株主のもの」です。
したがって、企業の持ち主である株主に対しては、経営状況を詳細に伝えなければなりません。
そこで役立つのが、財務諸表です。
企業の業績や経営状態をチェックできなければ、企業に対して提案や申し立てを行ったり、株を売却したり、といった行動を取るべきかどうかの判断ができません。
出資している株主に対して正確な財務状況を伝えるというのも、財務諸表を作成する目的・役割の一つです。
適正な会計処理が行われていることを税務署が確認できる
税務署に対して、適正な会計処理をしていることを明確にするというのも、財務諸表を作成する目的です。
税務署は、企業が問題なく決算を行っているかどうかを確かめるために、財務諸表を確認します。
しかし、財務諸表に記載されている内容に怪しい部分があれば、税務調査が入り、追徴課税を受ける可能性もあるでしょう。
企業としての信頼を損なわないよう、財務諸表の数字が間違っていないかについては綿密にチェックしてください。
債権回収に問題がないことを訴求できる
企業に対して債権を有している法人・個人は、財務諸表を確認して「今後の債権回収に問題がないか」を判断します。
財務諸表に不備があれば、「キャッシュフローに問題があるのではないか」「無駄な設備投資が多いのではないか」といった不安を与えてしまうかもしれません。
なお、債権を有している法人・個人の例としては以下の通りです。
- 銀行などの金融機関
- 個人投資家
- ベンチャーキャピタル
正確な財務諸表を作成することで、「債権回収については問題ない」というメッセージをはっきりと伝えられます。
取引先や従業員に経営状況が伝わる
企業の利害関係者は、株主や債権者だけではありません。
取引している企業や、自社で働いている従業員たちも、立派な利害関係者です。
取引先や従業員に対して、自社の健全性を示すことができるのも、財務諸表の大きな役割と言えるでしょう。
財務諸表を確認し、経営に問題がないと判断してもらえれば、取引先は今後も安心して取引を継続できます。また、従業員も何も心配することなく働き続けることが可能です。
財務諸表の読み方や分析方法
財務諸表の分析は、主に以下の5つの視点から行います。
- 生産性分析
- 収益性分析
- 安全性分析
- 成長性分析
- 効率性分析
どのように財務諸表を読み、どのように分析していくかについて、それぞれ詳しく解説していきます。
生産性分析
生産性分析とは、企業が保有する資源(ヒト・モノ・カネ)を使ってどの程度まで利益を出すことができるか、といった生産性について分析する方法です。
生産性分析を行う上での主な指標は以下の通りです。
- 労働生産性
- 労働分配率
労働生産性とは、「労働に対する価値・生産量」を表す指標です。
従業員1人あたりの「企業に対する貢献度」を測る指標で、従業員の労働にどれほどの付加価値があるのかを表します。
付加価値とは、売上額から材料費・外注費といった外部費用を引いた金額を指します。
労働生産性の計算式は以下の通りです。
※付加価値は(売上 - 外部費用)
| ■付加価値 ÷ 従業員数 = 労働生産性(円) |
そして労働分配率とは、従業員に対して、生み出された付加価値がどの程度配分されているか、を表す指標です。
労働分配率の計算式は以下の通りです。
| ■人件費 ÷ 付加価値 × 100 = 労働分配率(%) |
収益性分析
収益性分析とは、企業としてどれくらい収益を出せる力を持っているのか、について分析する方法です。
数値を算出する際は、主に貸借対照表や損益計算書を用います。
収益性分析を行う上での主な指標は以下の通りです。
- 売上高営業利益率
- 売上高総利益率
売上高営業利益率は、売上に対してどれほどの営業利益があるのかを見る指標となります。
収益性分析では最も重要となる指標で、本業でどれほど効率よく収益を得ているのかがわかります。
売上高営業利益率の計算式は以下の通りです。
| ■営業利益 ÷ 売上高 × 100 = 売上高営業利益率(%) |
売上高総利益は、売上に対する総利益の比率を見る指標です。
売上高営業利益率と同様、企業の収益率を見る場合に用いられます。
売上高総利益の計算式は以下の通りです。
| ■売上総利益 ÷ 売上高 × 100 = 売上高総利益(%) |
安全性分析
安全性分析とは、企業にどの程度の支払い能力があるのかを分析する方法です。
貸借対照表の流動資産・流動負債・純資産などの数値を使い、企業の安全性を測ります。
安全性分析を行う上での主な指標は以下の通りです。
- 流動比率
- 当座比率
- 自己資本比率
これらの指標が高いほど企業としての安全性が高く、支払いに関するリスクが低いといえます。。
ここではそれぞれの指標について解説します。
流動比率
1つ目の「流動比率」は、企業の負債に対する資産の割合を表す比率で、短期的な支払い能力があるかどうかがわかります。
短期間のうちに支払う必要のある負債(=流動負債)よりも、短期間での現金化が可能な資産(=流動資産)の方が多ければ、支払い能力があると判断できるでしょう。
しかし流動比率が100%を下回ると、支払い不能に陥る危険性があります。
流動比率の計算式は以下の通りです。
| ■流動資産 ÷ 流動負債 × 100 = 流動比率(%) |
当座比率
2つ目の当座比率とは、流動比率よりさらに短い期間における支払い能力がわかる指標です。
流動資産の中でも、預金や売掛金といった「特に現金化しやすい当座資産」のみを選択して算出するため、より正確な企業の支払い能力を見ることができます。
当座比率の計算式は以下の通りです。
| ■当座資産 ÷ 流動負債 × 100 = 当座比率(%) |
自己資本比率
3つ目の自己資本比率とは、会社の総資本のうち、返済不要な資本がどれくらいあるのかがわかる指標です。
純資産が多いほど自己資本比率が高くなり、財務状態が健全で倒産しにくい状態だと言えます。
自己資本比率の計算式は以下の通りです。
| ■純資産 ÷ 総資本 × 100 = 自己資本比率(%) |
成長性分析
成長性分析とは、長期に渡って企業が成長できるかどうかを分析する手法です。
1年単位での成績を単体で見るのではなく、一定期間における「売上や経常利益の推移」を見ることで、企業としての成長性を測ります。
成長性分析を行う上での主な指標は以下の通りです。
- 売上高伸び率
- 売上高研究開発費率
売上高伸び率とは、前期と比較して「売上にどれだけの増減があるか」を測る指標です。
損益計算書を用いて売上高の伸び率を算出し、伸び率が前期よりも高ければ成長できている、低ければ衰退傾向にある、と判断できます。
ただし、売上が増えていても営業利益が伸びていなければ、事業に投じた各種費用を回収できていないことになります。営業利益や経常利益のチェックも行いましょう。
売上高伸び率の計算式は以下の通りです。
| ■(当期売上高 - 前期売上高) ÷ 前期売上高 × 100 = 売上高伸び率(%) |
売上高研究開発費率とは、売上高のうち、研究開発費がどれくらいの割合になっているかを示す指標です。
商品やサービスの開発には研究費用が欠かせませんが、投じた研究開発費と売上のバランスが適切なものになっているかどうか確認するのに役立つ指標となっています。
売上高研究開発費率の計算式は以下の通りです。
| ■研究開発費 ÷ 売上高 × 100 = 売上高研究開発費率(%) |
効率性分析
効率性分析とは、企業が効率よく利益を出せているかどうかを分析する手法です。
貸借対照表と損益計算書の数値を活用して、各種効率性を算出していきます。
効率性分析を行う上での主な指標は以下の通りです。
- 総資産回転率
- 売上債権回転期間
- 在庫回転期間
以下で詳しく解説します。
総資産回転率
1つ目の総資産回転率は、企業の総資産がどれくらい効率的に活かされているかを示す指標です。
総資産回転率が高いほど、資産に対して多くの売上を出せていることになるため、効率性がよい状態であると言えます。
総資産回転率の計算式は以下の通りです。
| ■売上高 ÷ 総資産 = 総資産回転率(回転) |
売上債権回転期間
2つ目の売上債権回転期間は、どの程度の期間で売上の債権を回収できるかを示す指標です。
回転期間が短いほど現金化が早まるため、企業としての資金繰りが円滑に進んでいると判断できます。
売上債権回転期間の計算式は以下の通りです。
| ■売上債権 ÷ (売上高 ÷ 12) = 売上債権回転月数 ■売上債権 ÷ (売上高 ÷ 365) = 売上債権回転日数 |
在庫回転期間
3つ目の在庫回転期間は、どの程度の期間で在庫をさばけているかを示す指標です。
在庫回転期間が短いほど、仕入れた商品が早く販売できているということになります。
在庫回転期間の計算式は以下の通りです。
| ■棚卸資産 ÷ 売上原価 ÷ 12 = 在庫回転期間(月数) |
まとめ
以上、財務諸表の読み方や分析方法、決算書との違いなどについて詳しく解説してきました。
財務諸表の読み方を知り、正しく分析することで、自社の状況や競合他社の経営状態を知ることができます。
ぜひ本記事を参考に、財務諸表の読み解き方を把握して経営にご活用ください。
関連記事
-

5Sとは? 目的やメリット、導入ステップとポイントを解説
5Sとは整理(Seiri)、整頓(Seiton)、清掃(Seiso)、清潔(Seiketsu)、躾(Shitsuke)の5つの日本語の頭文字を取った言葉です。5Sは、効率的な職場管理手法として世界中で広く活用されています。今回は製造業を中心に、生産効率向上やコスト削減などさまざまなメリットがもたらす可能性にも焦点を当てながら5S導入のポイントを紹介します。
-

デジタル化とは?意味やIT化との違い、進め方をわかりやすく解説
デジタル化の推進は、多くの企業にとって避けては通れない重要な課題です。
本記事では、デジタル化の本質的な意味から、企業が直面する課題、具体的な導入方法まで、わかりやすく解説します。 -

情報漏洩の有名な事例としてはどんなものがある?事例から学ぶ対処法も解説
デジタル化が進む現代において、企業が取り扱う情報の価値はますます高まっています。
その一方で、情報漏洩のリスクは企業規模を問わず、すべての組織にとって深刻な経営課題となりました。
ひとたび情報漏洩が発生すれば、金銭的な損害はもちろん、顧客や取引先からの信用を失い、事業の継続が困難になることさえあります。
そこでこの記事では、世間を騒がせた有名な情報漏洩の事例を紹介しつつ、中小企業が実践すべき具体的な対処法・予防策などについて詳しく解説していきます。
自社のセキュリティ体制を見直すきっかけとして、ぜひ参考にしてください。
-

ホワイト500とは?中小企業にメリットはある?認定要件・申請方法など
これは、従業員の健康管理を経営課題として捉え、戦略的に推進している法人を国が認定する仕組みです。経済産業省と日本健康会議が共同で運営しています。
この記事では、ホワイト500の概要やブライト500との違い、認定要件や申請手順、実際のメリットまで、中小企業の視点でわかりやすく解説します。「制度が気になるが何から手を付ければいいかわからない」と感じている方にとって、第一歩となる内容です。
また以下の資料では「健康経営優良法人認定」の効果や申請方法、メリットを紹介していますので、ぜひ無料でダウンロードしてご覧ください。
-

リスクマネジメントとは何か?必要性・プロセス・類語との違いを簡単にわかりやすく解説
企業経営は、予測不能な出来事の連続です。
自然災害、市場の急変、サイバー攻撃、そして人的ミスなど、事業の存続を脅かす「リスク」はあらゆる場所に潜んでいます。
このような不確実性の高い時代において、すべての企業にとって不可欠な経営活動が「リスクマネジメント」です。
この記事では、「リスクマネジメントとは何か?」という基本的な定義から、その必要性、具体的な実践プロセス、そして混同しがちな類語との違いまで、できるだけ簡単にわかりやすく解説していきます。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録