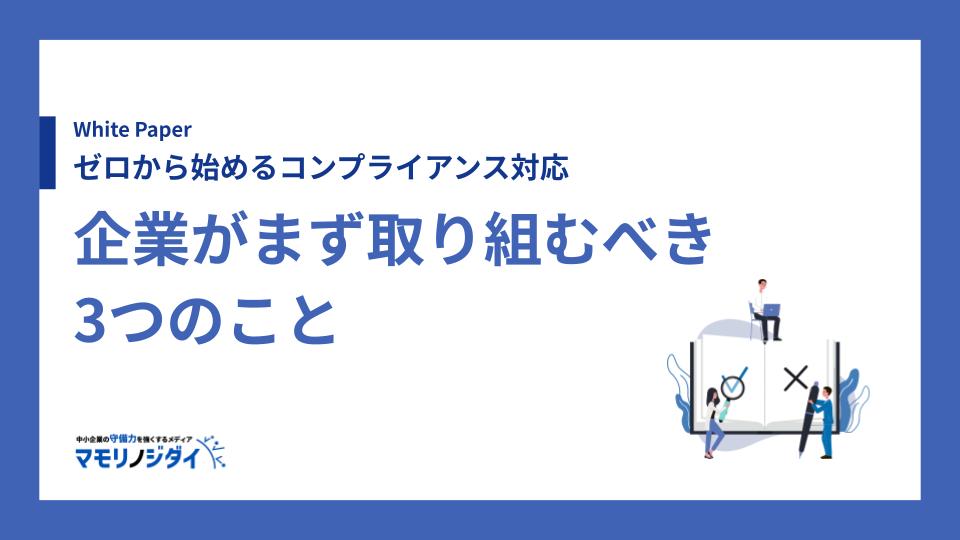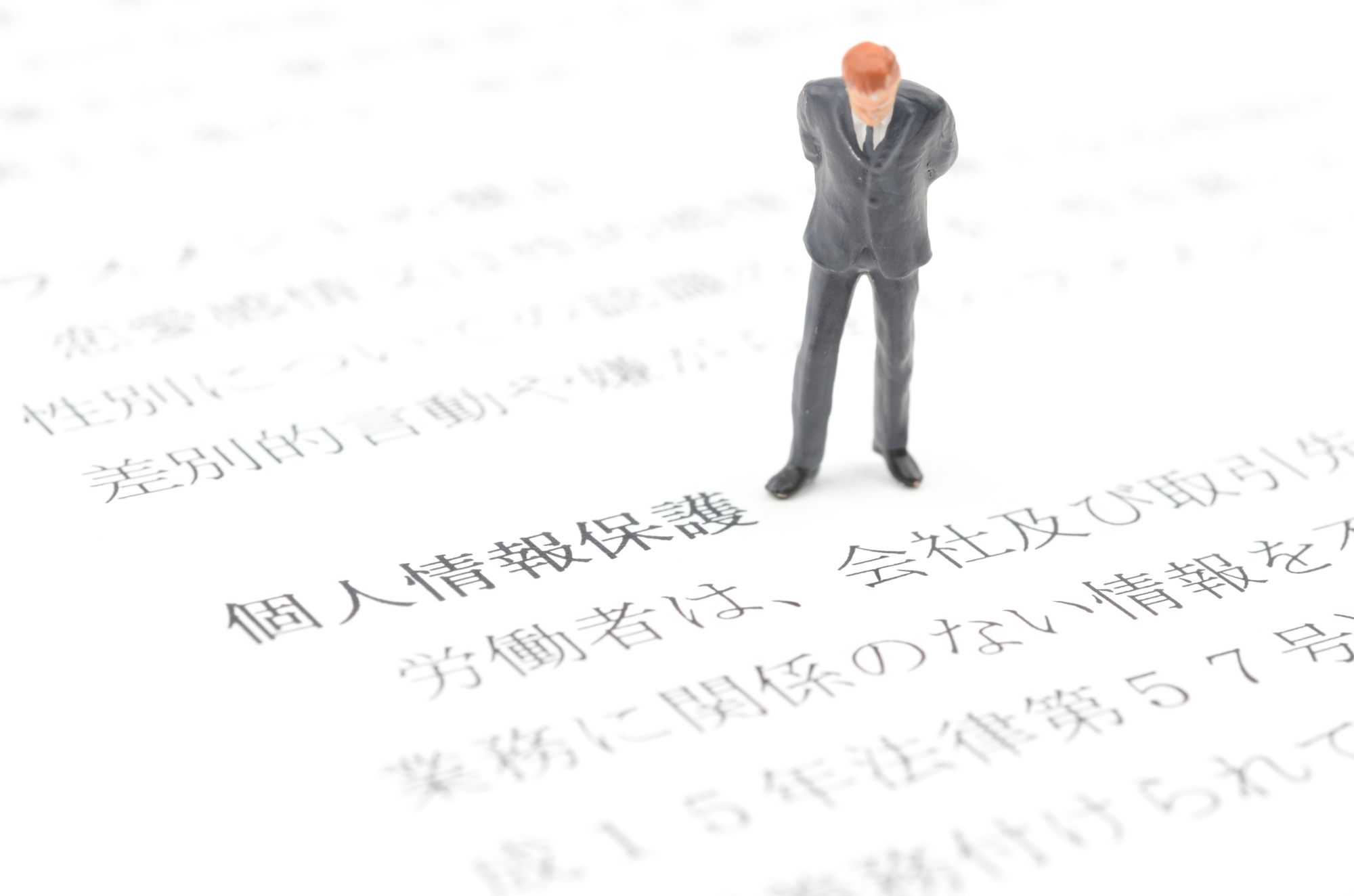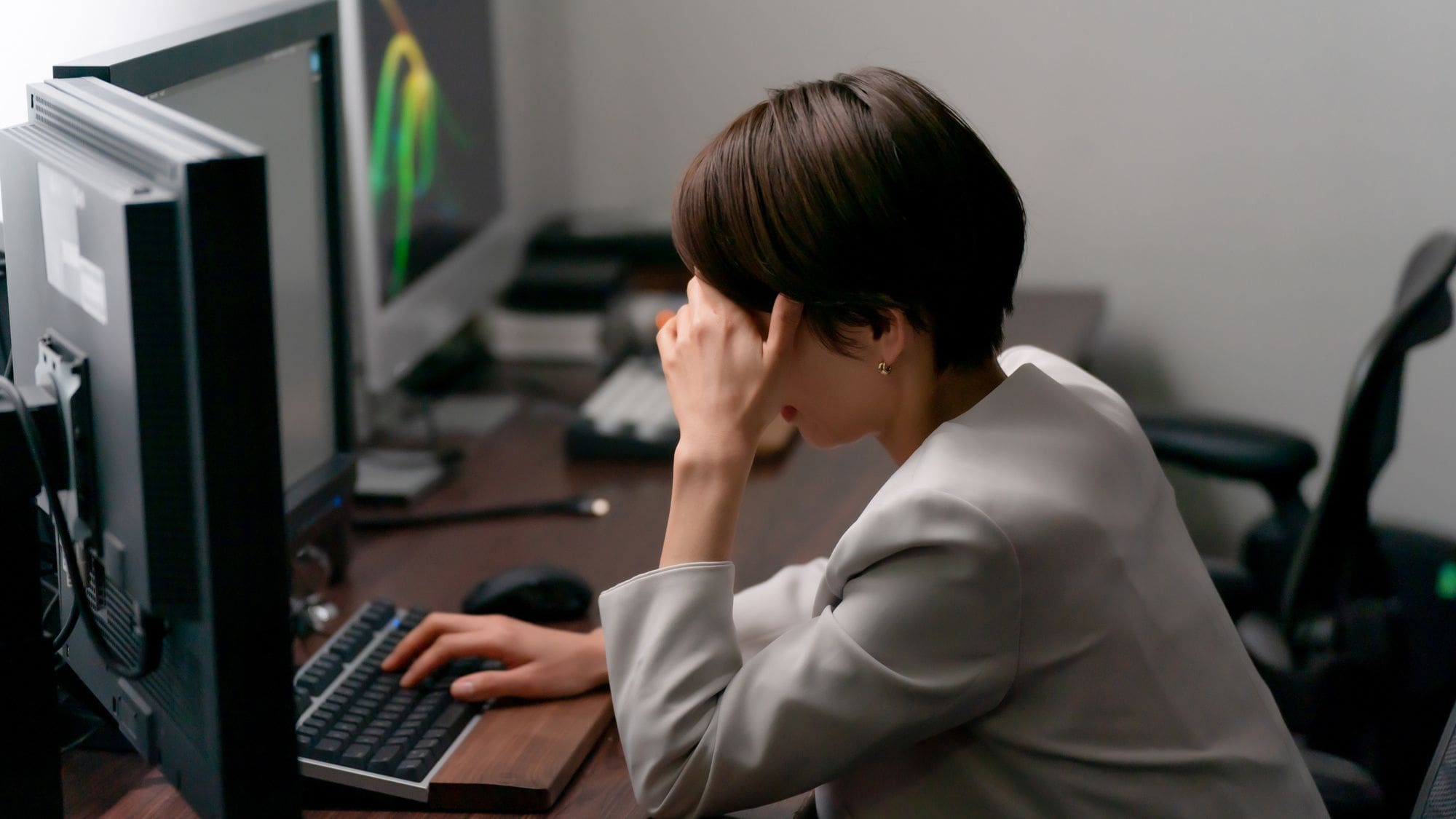社内規定とは?作り方、誰が作るべきか、法的効力の有無や実例を紹介
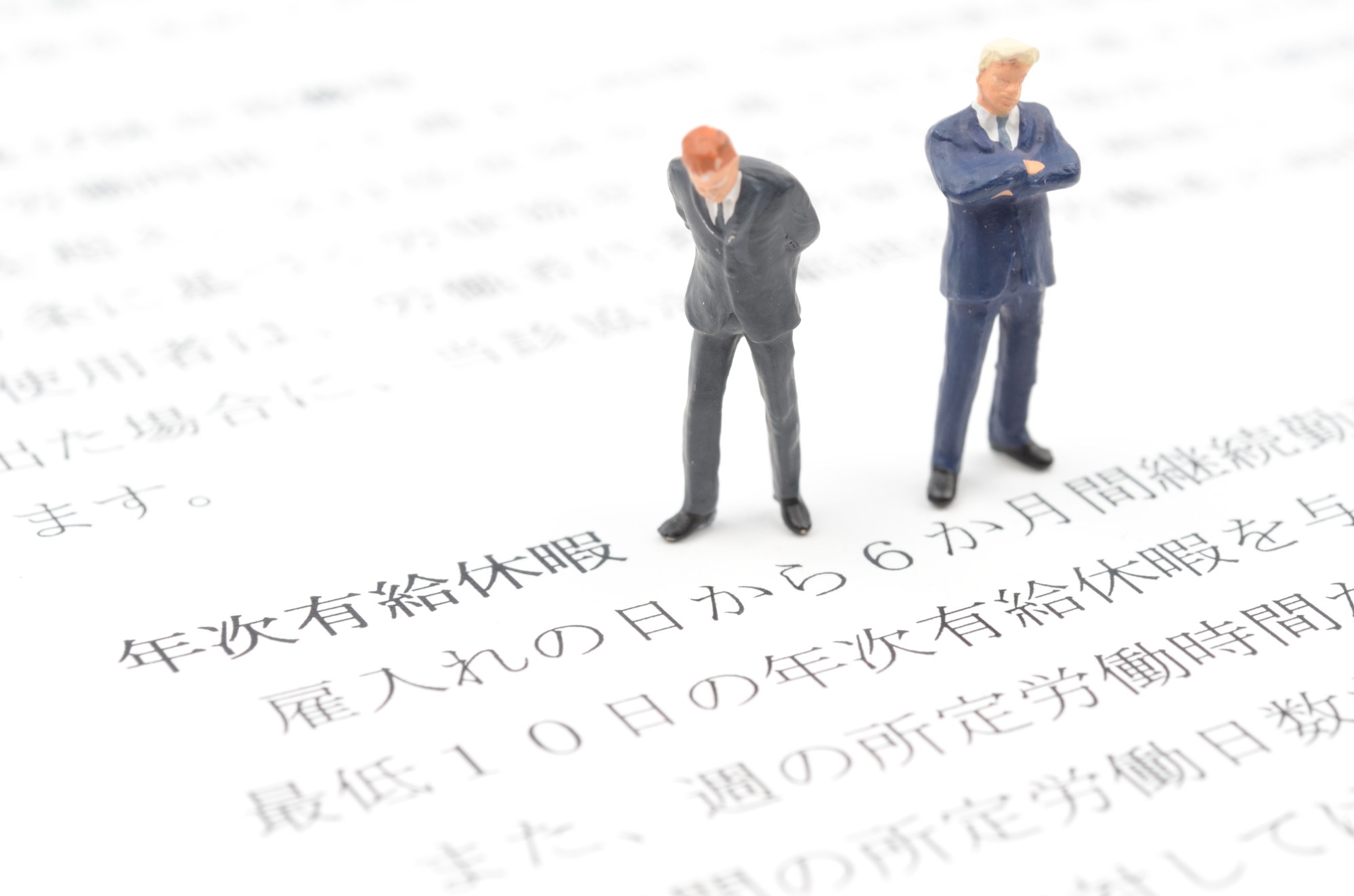
企業の運営において「社内規定」は、企業内の統制を保つために重要です。しかし、その内容や作成方法、法的な意味について詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。
本記事では、社内規定の基本的な意味や、具体的な作り方、法的効力などについて詳しく解説します。ぜひこの記事を参考に、自社の社内規定の作成・改善に役立ててください。
目次
社内規定とは
社内規定とは「企業内部のルール・手続きを明文化したもの」です。従業員が守るべき行動指針、業務手順などを定めます。
作成の目的は、組織全体の効率化と透明性につなげることです。
一般的には、業務マニュアルやガイドラインなども含まれ、従業員の行動を統制しトラブルを未然に防ぐ役割があります。
社内規定と社内規程の違いとは
「社内規定」と「社内規程」という言葉は混同されがちですが、意味は異なります。
「社内規定」とは、具体的な内容が記載された文書や規則そのものです。例えば「情報セキュリティ規定」や「労働時間管理規定」など、従業員が遵守すべき詳細なルールや手順を記載した文書がこれに該当します。
一方、「社内規程」とは、これらの個別の規定をまとめて管理するための体系的な枠組み、方針を指します。例えば「社内規程集」や「業務管理規程」といった形で、複数の規定を一元的に管理し、全体の統制を図るための骨組みです。
企業によっては使い方が異なる場合もあるため、両者の違いを理解しておくことが重要です。
就業規則との違い
就業規則は、労働基準法に基づき、企業が定める規則のことです。常時10人以上の従業員がいる場合、作成・届け出が法的に義務付けられています。
一方で、社内規定は法律で定められていないため、企業独自の運営方針やルールを自由に策定することが可能です。
参考:e-GOV「労働基準法 第八十九条」
モデル就業規則とは
モデル就業規則とは、厚生労働省が提供する就業規則の参考例です。
企業が就業規則を作成する際のガイドラインといえます。
企業はモデル就業規則をベースにカスタマイズしましょう。これにより必要な要件を網羅しつつ、より具体的な規則を整備することが可能です。
モデル就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、条件によっては記載が必要な「相対的必要記載事項」があります。
たとえば「労働時間、賃金、退職に関する事項」は絶対的必要記載事項に含まれます。
「退職手当、安全衛生に関する内容」は、相対的必要記載事項です。モデル就業規則を基に企業は自社の実情に合わせて規則をカスタマイズし、法令にも適合した内容を構築しましょう。
出典)厚生労働省「モデル就業規則について」
社内規定を定める目的
ここでは、社内規定をつくる目的について紹介します。以下の目的を達成できるように、項目・内容を盛り込むようにしましょう。
業務の効率化と標準化をするため
社内規定は業務を効率的に進めるために必要です。ルールを定めないと、従業員それぞれで行動が変わってしまい、統制が取れなくなります。
一方で、全ての従業員が共通のルールに従って行動することで、業務の標準化が図られます。また無駄な手間やミスを減らし、組織全体の効率性を高められることも魅力です。
リスク管理を徹底するため
社内規定は、トラブルやコンプライアンス違反を未然に防ぐために必要です。
明確な規定を設けることで、従業員が適切な行動を取る基準を持つことができ、リスクの発生を抑えられます。また規定に基づいて対策を定めておくことで、問題が発生した場合にもスピーディーに対応可能です。
組織の透明性・一貫性を高めるため
社内規定は組織の透明性・一貫性を保つためにも重要です。各業務やプロセスにおいて一貫した判断基準を設けることで、従業員が公平な評価や処遇を受けられます。
例えば、評価基準を明確に定めて周知すれば、従業員の信頼を獲得することが可能です。こうした取り組みによって、組織全体の一貫性が高まるとともに、離職率の低下にも貢献できます。
社員の安心感と信頼の醸成
明確な社内規定があることで、従業員が安心して業務に取り組めるようになるのもメリットです。規定に基づいて公平な処遇や評価が行われるため、社員間のいさかいがなくなり、信頼関係も深まります。
このように、社内規定は社員のモチベーションを高めることにも寄与します。間接的に「組織の成長を支える役割」を果たせることも魅力のひとつです。
社内規定に法的効力はあるのか
社内規定は、就業規則のように法律で義務付けられていないため、法的な強制力はありません。
ただし、先述したように就業規則には法的な効力があります。社内規定と就業規則で内容が被っている部分は、法的効力が認められます。
また社内規定に従わない従業員に対して、合理的な内容が認められた場合は処分を科すことは可能です。
社内規定のテンプレートは使うべきか?
社内規定を策定する際に、テンプレートを使用することは効率的な方法です。特に、初めて規定を作成する場合や、迅速に対応する必要がある際に役立ちます。
信頼できる機関がオープンにしているテンプレートは基本的な項目や形式が整っていることが特徴です。そのため時間と労力を大幅に削減できます。
ただし、テンプレートに頼りすぎてしまうと、「自社の独自性が失われる」「細部の見直しが不足する」といったリスクがあるため注意しましょう。自社に最適な内容にカスタマイズしてください。。
社内規定の具体例
ここでは、具体的に社内規定に盛り込むべき内容を紹介します。
組織・人事に関する規定
組織や人事に関する社内規定には、従業員の役職や昇進基準、評価方法、雇用形態の変更手続きなどが含まれます。
これらの規定を定めることで、公平かつ透明な人事運営を確保できることが魅力です。具体的には「従業員のモチベーション向上」「離職率の低下」に寄与します。
以下が具体例です。
| 項目 | 内容 |
| 昇進・昇格 | 従業員の昇進条件や昇格基準を定める |
| 人事異動 | 部門間の人事異動の手続きや基準を規定 |
| 評価基準 | 従業員のパフォーマンス評価の方法を明示 |
業務に関する規定
業務に関する規定には、「情報セキュリティ」や「業務マニュアル」「労働時間管理」などが含まれます。これらを定めることで業務内容の統制が取りやすくなり、効率化にも寄与することが魅力です。
以下が具体例となります。
| 項目 | 内容 |
| 情報セキュリティ | 機密情報の取り扱いや管理手順を規定 |
| 業務マニュアル | 各業務の詳細な手順やフローを記載 |
| 労働時間管理 | 労働時間の管理方法や遵守事項を定める |
その他の規定
その他、福利厚生、職場環境の安全性などの項目を盛り込みましょう。
「福利厚生」を定めることで、従業員の満足度向上につながります。また「安全衛生」は、働きやすい環境をつくるために必要です。
以下が具体例になります。
| 項目 | 内容 |
| 福利厚生 | 社員が利用できる福利厚生の詳細を規定 |
| 安全衛生 | 職場の安全基準や衛生管理の方法を明記 |
| 出張旅費 | 職場の安全基準や衛生管理の方法を明記 |
社内規定は誰が作成すべき?
社内規定は通常、人事部、総務部、法務部が中心となり規定を作成します。
これらの部署は「企業全体の方針」や「労働法規」を十分に理解している部署です。そのため規定が企業文化に適合するとともに、法的要件を満たしていることを確認しやすいといえます。
また、社内の各部署に確認してもらうことで、ハレーションを未然に防げます。人事部、総務部、法務部を中心にしつつ、各部署を巻き込むようにしましょう。
社内規定を作る際のステップ
具体的に社内規定を作る際のステップについて紹介します。
1. 責任者の選定
まずは、社内規定作成の責任者を選びましょう。
通常は人事部長や総務部長が適任です。
規定の内容によっては、法務部も関与します。責任者を明確にしておくと、作成プロセスの進行がスムーズに進みます。
2. 情報収集と現状調査
次に規定を策定するために必要な情報を収集し、現状を調査しましょう。他社の事例、業界ならではの内容を含めて調査をします。
そのうえで、社内の現状に即した情報を集めます。従業員からのフィードバックを取り入れることで、実用的な規定を作成できるため、意見を収集しましょう。
3. 社内規定案の作成とレビュー
情報収集と調査が完了したら、規定案を作成します。文書は従業員が理解しやすいよう、簡潔で分かりやすくすることが重要です。
初期案が完成したら、関係部署にレビューを依頼し、必要な修正を加えましょう。
法務部門やコンプライアンス担当者による法的確認も欠かせません。最終的に経営陣が承認し、完成とします。
4. 社員への説明とフィードバックの収集
規定案が完成し、承認を得たら、社員への説明を行います。
説明会や研修を通じて、新しい規定の内容や適用方法を詳しく説明し、社員が理解できるようにしましょう。その後、フィードバックを収集して、必要な場合はさらなる修正を加えることも検討します。
具体的な周知の方法については、後述しますのでご覧ください。
5. 運用開始と観察
社員からのフィードバックを反映した後、最終確認を行い、規定を正式に適用します。適用日を設定し、社員に再度通知を行いましょう。
その後は「適切に運用できているか」を確認する必要があります。適宜、社内規定作成チームが管理職層とミーティングをし、守れているかをキャッチアップしてください。
社内規定を作成する際の注意点
社内規定を作成する際には、注意点があります。
注意点を理解することで企業リスクを軽減でき、従業員に理解してもらいやすくなるため、事前に把握しておきましょう。
法令遵守ができるかを確認する
社内規定が法令に違反していないか確認することは、規定作成の基本です。規定自体が法律に反していると、コンプライアンス面で問題が発生します。
特に、労働基準法や個人情報保護法など、関連する法規制を遵守しましょう。法務部や外部の弁護士に確認を依頼することが必要です。
表現が明確かを確認する
規定の内容が曖昧だと、従業員が誤解したり解釈が分かれたりする原因になります。文書の表現は具体的でわかりやすいものにしましょう。
難解な専門用語は避け、簡潔な言葉を使用することで、従業員に理解してもらいやすくなります。
定期的な見直しをする
一度作成した規定は、時代の変化や業界の動向に応じて内容を見直すことが重要です。規定が遅れてしまうと、企業の柔軟性が損なわれます。また企業の実情に則していないと、従業員の不満を溜める原因にもなります。
年に一度や半期ごとに見直しを行う体制を整えることで、常に最新の状況に対応できる規定を維持することが可能です。
社内規定を社員に周知する方法
社内規定は作成するだけでは不十分であり、社員に効果的に周知することが重要です。具体的に周知する方法について紹介します。
社内イントラネットやメールを活用した通知
社内イントラネットやメールは、スピーディに情報を全社員に伝達するうえで効果的です。
新しい規定や改訂があった場合、イントラネットに掲載し、全員に通知メールを送ることで情報を共有できます。
ただし強制力が働きにくいため「見ていない従業員が生まれる」といったデメリットがあります。
資料やガイドラインの配布
イントラネットがない場合、社内規定を文書化して配布しましょう。紙の資料やデジタル版を提供することで、社員が必要なときに参照できます。
この際に、具体例やQ&A形式など具体的な内容が書かれていると、理解が深まるでしょう。
定期的な研修や説明会の実施
規定を深く理解してもらうために、定期的な研修・説明会を開くことは効果的です。
直接的なコミュニケーションができ、規定の意図・背景を詳しく伝えられます。また質疑応答によって、社員の納得度を高められることも特徴です。
周知方法のポイント
確実に従業員に周知するため 、定期的なフォローアップを行うことが重要です。「定期的に説明会を開く」「管理職から1on1で伝えてもらう」などの工夫を行いましょう。
また、フィードバックを収集し、社員の理解状況を把握することも効果的です。
規定が適切に守られているかを確認することはもちろん、従業員の不満を吸収できます。必要に応じて周知方法を改善しましょう。
社内規定を改定する際のステップ
最後に、既存の社内規定を改定する際のステップについて紹介します。適切な手順を踏むことで、規定の改定がスムーズに進み、社員への影響を最小限に抑えることが可能です。
1. 規定の見直しと改善点の洗い出し
最初のステップは、現行の規定について改善すべき点を洗い出すことです。
そのために関連部署や担当者と協力し、現状の規定がどのような課題を抱えているかを把握しましょう。定期的な見直しの中で、法令や市場のニーズの変更に対応できているかも検討することが重要です。
2. 変更案の作成と承認手続き
改善点が洗い出された後は、具体的な変更案を作成します。
内容が具体的で実用的であることを確認し、各部門や関係者によるレビューを受けましょう。現場の目線と合っているのか確認が必要です。
また、法務部にも確認してもらいましょう。最終的に経営陣の承認を得ることで、新しい規定が正式に採用されます。
3. 社員への通知と実施準備
承認を得た後は、改定内容を全社員に通知し、実施準備を行います。先述した方法を用いて社員に変更内容を通達しましょう。
その後、新しい規定が現場で運用されているかを確認してください。管理職層に対して、定期的に確認をしましょう。
まとめ
社内規定は企業の運営において重要な役割を担います。社内規定の策定は、社員の行動を統制できるためリスク軽減につながるほか、業務効率化にも寄与するものです。
さらに法令遵守や表現の明確化、定期的な見直しを行うことで、時代や業務環境に適した規定を維持できます。
改定時には従業員の不満を避けるためにも、適切に周知し、フィードバックを収集しましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録