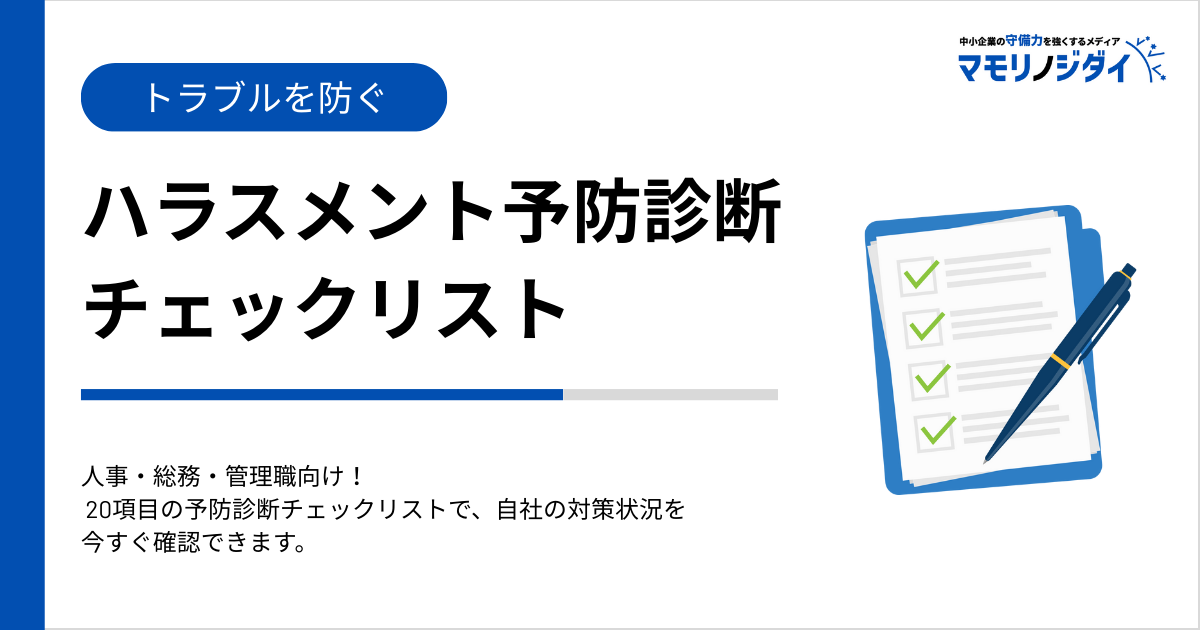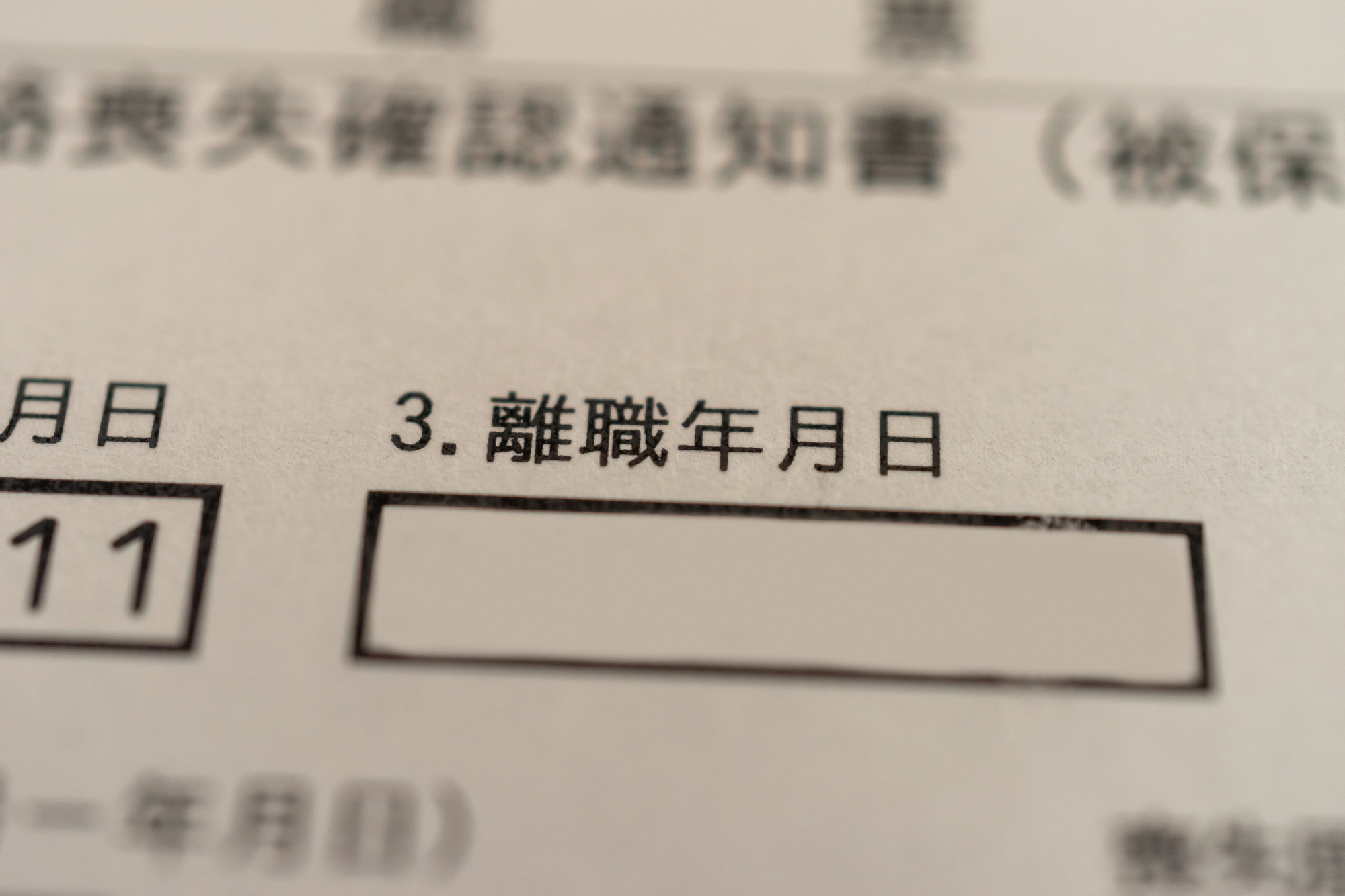マタニティハラスメントとは?厚生労働省の定義、事例、企業が行う対策など

マタニティハラスメントとは、妊娠や出産を理由に嫌がらせを受けたり、不当な扱いを受けたりすることです。特に職場での問題として注目されており、妊娠中の女性や出産後の母親が精神的・肉体的に大きな負担を抱える原因となっています。
職場環境の改善や法令順守の観点から、人事・総務などのバックオフィス担当者にとって、この問題への対応は重要な課題です。しかし「何から始めればいいかわからない」という声も少なくありません。
この記事では、マタニティハラスメントの定義や具体的な事例、リスク、そして対策のメリットや方法について詳しく解説します。参考にしていただき、自社のハラスメント対策にお役立てください。
目次
マタニティハラスメント(マタハラ)とは
マタニティハラスメント(通称:マタハラ)とは、妊娠・出産を理由にした職場での嫌がらせや不当な扱いを指します。働く女性が安心して妊娠・出産を迎えることを妨げる大きな障害となる問題です。
職場環境や制度への理解不足、または個人の偏見が原因で発生することが多く、日本社会でも深刻な問題として注目されています。企業としては未然に防止しなければいけません。
厚生労働省によるマタニティハラスメントの定義
厚生労働省はマタニティハラスメントを次のように定義しています。
| 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることです。 妊娠の状態や育児休業制度等の利用等と嫌がらせとなる行為の間に因果関係があるものがハラスメントに該当します。 |
出典)厚生労働省「あかるい職場応援団 3 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」
また「男女雇用機会均等法のあらまし」において、「制度等の利用への嫌がらせ型」と、「状態への嫌がらせ型」に分けて、より詳細に定義しています。
| 項目 | 内容 |
| 制度等の利用への嫌がらせ型 | 以下に掲げる制度又は措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの ・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置) ・坑内業務の就業制限及び危険有害業務の就業制限 産前休業 ・軽易な業務への転換 ・⑤変形労働時間制がとられる場合における法定労働時間を超える労働時間の制限、時間 ・外労働及び休日労働の制限並びに深夜業の制限 ・育児時間 |
| 状態への嫌がらせ型 | 以下に掲げる妊娠又は出産に関する事由に関する言動により就業環境が害されるもの ・妊娠したこと ・出産したこと ・坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、またはこれらの業務に従事しなかったこと ・産後の就業制限の規定により就業できず、又は産後休業をしたこと ・妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと、若しくはできなかったこと、又は労働能率が低下したこと |
出典)厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」p.34~35
このような定義に加えて、「男女雇用機会均等法(抄)」には、事業主に対してマタニティハラスメント防止のために、対処することを義務付けています。
| 第11条の3 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2 第11条第2項の規定(Ⅱ-1参照)は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。 |
出典)厚生労働省「あかるい職場応援団 3 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」
これからマタニティハラスメント対策を講じたい企業は、厚生労働省の定義をよく把握したうえで、男女雇用機会均等法に基づいて適切に対処しましょう。
プレ・マタニティハラスメントとは
マタニティハラスメントは、妊娠中だけに起こるものではありません。
妊娠や出産を予定・希望している女性に対して、直接的または間接的な不利益を与える言動や行動を「プレ・マタニティハラスメント」といいます。
たとえば、以下のような事例が該当します。
上司が「これから妊娠する可能性があるから重要な役職には就けない」と判断を下す
「子どもを持つならキャリアに影響する」「いつ妊娠するつもりなの?」など、個人のライフプランに対する過度な干渉や発言をする
不妊治療のための通院や休暇取得に対する非協力的な態度や、職場での孤立を生む行動を取る
プレ・マタニティハラスメントとは、こうした妊娠前の状態をもとに、不当な評価を受けたり、嫌がらせを受けたりすることを指す言葉です。企業は、プレ・マタニティハラスメントについても対策を講じなければいけません。
職場でのマタニティハラスメントの具体例と事例
マタニティハラスメントの具体的なパターンを「制度利用への嫌がらせ型」「妊娠・出産による状態に対する嫌がらせ型」の2つに分けて説明します。
制度利用への嫌がらせ型
制度利用への嫌がらせ型とは、先述した通り、「職場の育児・介護休業や産前産後休暇などの法定制度を利用しようとする従業員に対しての嫌がらせや圧力」を指します。
過去には、以下のような事例がありました。
| 営業所長Aに妊娠したことを告げ、業務軽減を求めたところ、「妊婦として 扱うつもりはないですよ」「万が一何かあっても自分は働くという覚悟がある のか」などの発言があり、制度の利用を阻害する発言や嫌がらせを受けたと して、労働者がAと会社に対して損害賠償を請求しました。 裁判所は、全体として社会通念上許容される範囲を超えているものであって、 使用者側の立場にある者として妊産婦労働者の人格権を害するものである とし、Aと会社に対して慰謝料35万円を連帯して支払うよう命じました。 (福岡地裁小倉支部 平成28年4月19日) |
出典)厚生労働省「職場のセクシュアルハラスメント 妊娠・出産等ハラスメント防止のためのハンドブック」p.13
この事例での問題点は「法定制度を利用する権利が妨げられていること」です。また会社としては「ハラスメントが原因で人材が退職してしまうこと」も問題だといえます。
状態に対する嫌がらせ型
状態に対する嫌がらせ型とは「妊娠・出産によって生じる身体的・精神的変化を理由に、従業員を責めたり、不当な扱いをするケース」となります。
このケースでは、最高裁判所にて以下のような判決が下っています。
| (参考)最高裁判決(平成26年10月23日)(事件番号:平成24(受)第2231号) 【概要】 医療機関に勤めていた理学療法士の女性が、妊娠した際に軽易業務への転換を請求したことを理由に副主任を免じられたことについて、妊娠等を理由とする不利益取扱いに当たるとして提訴。 【結果】 最高裁の判決においては、軽易業務転換を契機として降格させる措置は、特段の事情等がない限り、原則として、男女雇用機会均等法等が禁止する不利益取扱いに当たると判示。 |
出典)厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」p.29
この事例の根本的な問題は「妊娠中の身体的負担への理解が足りていないこと」です。
また、職場全体でのサポート体制が欠如していることも、被害者の精神的苦痛を増幅させています。「職場の文化・風土」という根本的な要因から、改善しなくてはいけません。
他にも、妊娠を予定または希望している段階で行われる「プレ・マタニティハラスメント」なども目立ってきました。
不妊治療による休暇を承認しなかったり、不当に異動・降格させるなどの悪質なケースも見受けられるようです。
性別やライフイベントを基準にした昇進・昇格の可否はハラスメントになります。正当な評価基準をもとにすることは、健康的な経営にとって必須です。
マタニティハラスメントが生じる原因
職場においてマタニティハラスメントが起こる原因を挙げ、それぞれについて詳しく解説します。
なお、マタニティハラスメント防止対策については後述しますので、参考にしてみてください。
職場環境や文化の問題
マタニティハラスメントは、職場環境や企業文化そのものが要因となる場合があります。
たとえば「成果主義」や「長時間労働」が常態化していると、妊娠・出産・育児により働き方が変わった従業員を「戦力外」とみなす風潮が生じやすくなる可能性があります。
また、育児休暇や産前産後休暇の取得を制度として整備していても、「利用しづらい雰囲気」が蔓延している場合は注意が必要です。組織全体での意識改革が求められます。
妊娠・育児に対する理解不足
妊娠や育児に対する知識や理解が不足していることも、マタニティハラスメントの一因です。
妊娠中のつわりをはじめとした体調不良、育児中の突発的な用事などに対する配慮が欠けることは、企業として問題となります。妊娠・育児中の従業員が「甘えている」や「特別扱いされている」といった誤解を受けないよう気を付けましょう。
このように理解がないと、偏見や不満を生み、職場の雰囲気を悪化させます。妊娠・育児に対して、正しい知識をきちんと検収することが必要です。
性別による役割分担への固定観念
古い慣習が残っている企業では「女性は家庭を優先するべき」「男性は仕事を最優先にするべき」といった性別による役割分担の固定観念が残っている場合があります。
このような固定概念は、女性従業員のキャリアアップを妨げることにつながるため注意が必要です。また、男性の育児参加も妨害することになるでしょう。
マタニティハラスメントが起きることはもちろん、企業全体の成長にも悪影響を及ぼす問題です。
マタニティハラスメントがもたらす悪影響
マタニティハラスメントは、被害者個人だけでなく、職場全体や企業の社会的評価にも深刻な影響を及ぼします。
以下では、間接的な影響も含め、具体的に解説します。
被害者への心理的・身体的な影響
マタニティハラスメントにより、被害者は深刻な心理的ストレスを抱えることがあります。「自己肯定感の低下」「不安」「抑うつ状態」などのリスクにつながる問題です。
さらに、妊娠中のストレスが増大することで、母体や胎児への健康リスクも高まる恐れがあります。こうした大問題を未然に防ぐためにも、マタニティハラスメント対策は必須です。
職場の士気・生産性の低下
マタニティハラスメントが発生すると、職場全体の雰囲気が悪化し、チームの士気が低下します。
「働きにくい環境であること」が表面化し、周囲の従業員のストレスも高まる恐れがあることが問題です。社内全体に不満・ストレスが広がる可能性があります。
また、マタニティハラスメントは「退職」や「配置転換」にもつながりかねません。頻発すると、業務効率が低下し、企業全体の生産性にも悪影響を及ぼします。
こうした状況が続くと、優秀な人材の流出が加速し、組織の競争力も損なわれるリスクが高まります。
企業の評判低下・訴訟のリスク
マタニティハラスメントが明るみに出ると、企業の評判が大きく損なわれます。
特に、昨今はSNSなどで誰でも情報発信できる時代です。被害者がマタニティハラスメントを告発することで、批判や不買運動につながる可能性があります。
また、マタニティハラスメントに関する訴訟が起こされた場合、企業は法的責任を問われ、高額な賠償金や罰金を支払うリスクもあります。
評判の低下・訴訟などで企業のブランドイメージが損なわれるうえ、売上・採用などの面で大きなデメリットがあるため、防止策は必須です。
マタニティハラスメントの防止対策
先述した通り、企業ではマタニティハラスメントを未然に防ぐために、対策を行う必要があります。組織全体で意識を高め、具体的な施策を実行することが重要です。
以下では、主な対策を解説しましょう。
ハラスメント防止方針の策定と周知
企業としての明確な姿勢を示すために、企業として「マタニティハラスメント防止方針」を策定しましょう。また、全従業員に周知することが必要です。
方針には「ハラスメントの定義」「禁止事項」「違反時の対応」「ハラスメントを感じた際に取るべき行動」を明記しましょう。
そのうえで社内ポータル、メールでの一斉送信などを通じて周知を徹底することが必要です。また書面での共有だけでなく、定期的に説明会を開催してください。
ハラスメント防止研修の実施
従業員一人ひとりの意識改革を促すために「ハラスメント防止研修を実施すること」が効果的です。自社でプログラムを組むことも可能ですが、専門的な企業に依頼することも視野に入れましょう。
特に管理職に対しては、重点的に教育してください。
男性には特に「妊娠・育児の大変さ」も含めて研修を行う必要があります。トラブルを未然に防ぐための具体的な対応策、リーダーシップスキルを重点的に教育しましょう。
匿名での相談窓口の設置
従業員が安心してハラスメントに関する相談ができる窓口を設置することで、トラブルの早期発見・解決につながります。
相談窓口を設置する際には匿名性・秘密保持を徹底しましょう。
被害者が安心して相談できる環境づくりが必須です。また、外部機関に担当者を設置することで、より公平感を高められます。
マタニティハラスメント防止のメリット
ここでは、マタニティハラスメント防止のメリットを紹介します。
職場環境の改善・生産性向上
マタニティハラスメント防止策を導入すれば、従業員が安心して働ける環境を整えられます。働きやすさを実感することで、職場の雰囲気が良好になり、互いを尊重する文化を醸成できることがメリットです。
職場環境が良好になると、従業員は気兼ねなく相談ができます。横のつながりが強化され、効率的に働くことが可能となり、生産性向上につながるといえるでしょう。
従業員満足度・定着率の向上
妊娠中・育児中の従業員に対する配慮が徹底されると、従業員が自社のファンになります。これにより職場全体の満足度が高まることもメリットです。
従業員満足度が向上し、離職も減少します。経験豊富な従業員が長期的に働けるようになると、採用・育成コストを削減することが可能です。
法的リスクの回避と企業イメージの向上
マタニティハラスメントの発生を防止することで、訴訟や行政指導といった法的リスクを回避できます。これにより、無駄なコストを支払わなくてよくなるのもメリットです。
また、マタニティハラスメント対策に積極的な企業は、社会的にも高く評価されます。
良好な企業イメージを築くことで「採用しやすくなる」「顧客からの信頼獲得ができる」「株主からの評価が高まる」といった利点も生まれます。
たとえば「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受ける「くるみんマーク」を取得することは、有効な対策のひとつです。
女性の採用促進や、働きやすさをステークホルダーにアピールできるなど、多くのメリットがあります。
ぜひ、積極的な取得を目指しましょう。
出典)厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて」
マタニティハラスメントを受けた際の対処法
最後に、自身が職場でマタニティハラスメントを受けた際の対処法を解説します。自分自身を守るために必要ですので、把握をしておきましょう。
事実を記録し証拠を確保する方法
マタニティハラスメントが起きた際は訴訟を起こす可能性もあります。まず、ハラスメントの事実を詳細に記録し、証拠を確保することが重要です。
日付や時間、発言内容、状況をできるだけ具体的に記録したメモを作成しましょう。また、メールやメッセージ、音声録音などの証拠を保存することで、事実確認に役立ちます。
社内外の相談窓口の活用
企業が設置している「ハラスメント相談窓口」に相談しましょう。迅速な対応や状況改善が期待できます。
社内で解決が難しい場合は、労働基準監督署など、外部の相談機関を利用するのも手段のひとつです。
労働基準監督署では「総合労働相談コーナー」を設けています。労働者からの相談も受け付けていますので、対応に悩んだ際には活用も考えましょう。
出典)厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
弁護士への相談
問題が深刻化した場合、法的支援を検討することが必要です。弁護士や労働問題に詳しい専門家に相談することで、適切なアドバイスや法的措置を受けられます。
ただし訴訟は最終手段です。まずは社内窓口や、労働基準監督署に相談することをこころがけましょう。そのうえで問題が解決しない場合は、法的支援を考えるべきです。
まとめ
マタニティハラスメントは、妊娠・出産を経験する従業員が不当な扱いや圧力を受けることを指します。職場環境や文化、理解不足などが主な原因です。
職場において、マタニティハラスメントが発生すると、被害者の心理的・身体的な健康に影響を与えるだけでなく、職場の士気や生産性にも悪影響を及ぼします。企業は、適切な防止策を講じるとともに、早期発見に力を注ぐようにしましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録