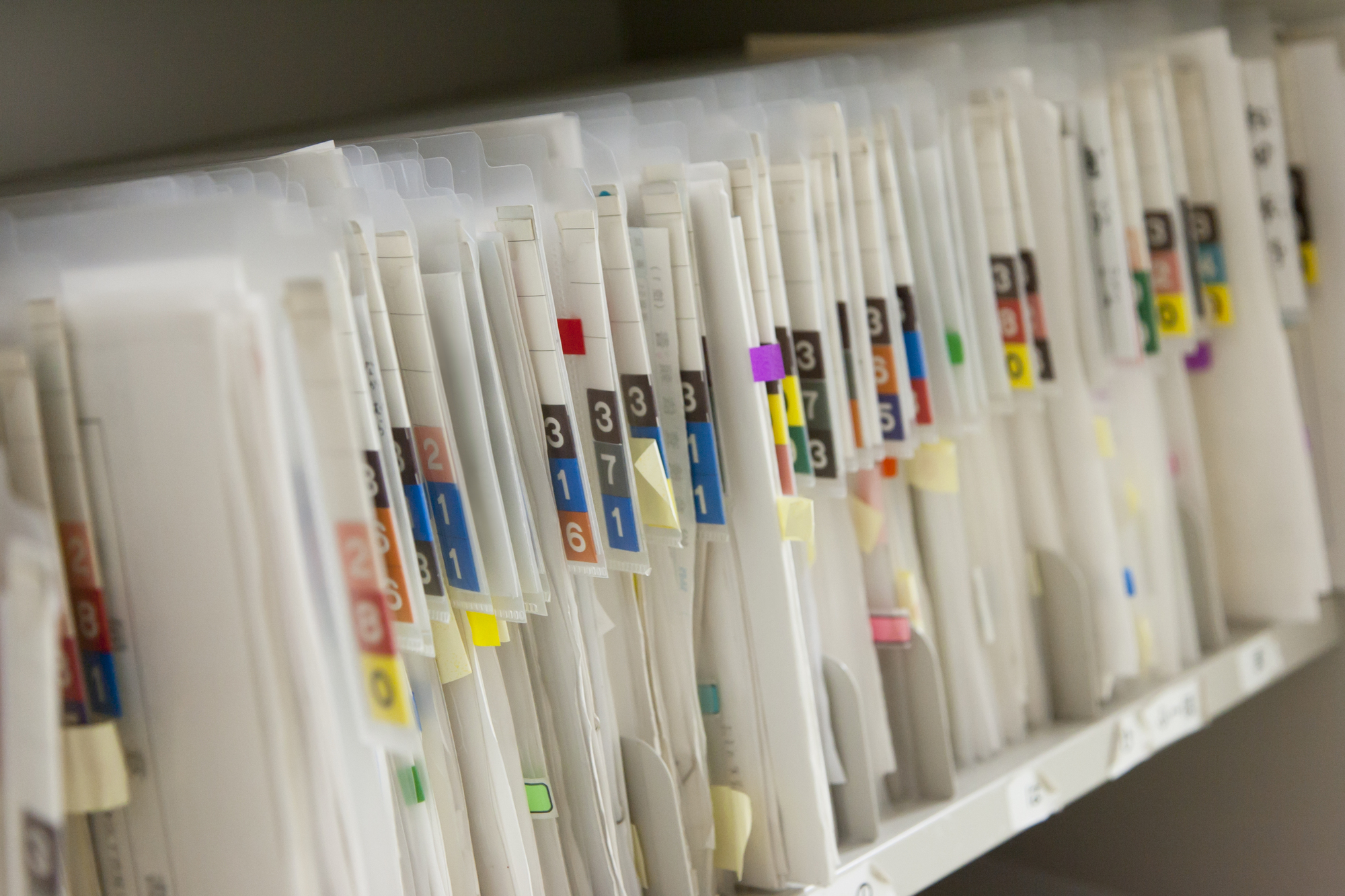情報セキュリティの3要素とは?中小企業が気を付けるべきことも解説

現代のビジネスにおいて、パソコンやインターネットは欠かせないツールとなりました。
しかし、その利便性の裏側には、常に情報漏洩やサイバー攻撃といったリスクが潜んでいます。
大企業だけでなく、あらゆる企業にとって「情報セキュリティ」は、事業を継続し、顧客からの信頼を守るための重要な経営課題です。
特に、専門のIT部門を持たないことが多い中小企業では、どこから手をつければよいのかわからないという声も少なくありません。
そこでこの記事では、情報セキュリティの根幹をなす「3つの要素(CIA)」という基本から、明日からでも実践できる具体的な対策までを、詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
そもそも情報セキュリティとは何か?簡単に解説
情報セキュリティと聞くと、「コンピューターウイルスから情報を守ること」や「ハッカーによる不正アクセスを防ぐこと」などをイメージするかもしれません。
もちろんそれらも重要ですが、情報セキュリティがカバーする範囲はもっと広範です。
簡単に言うと、情報セキュリティとは、企業が持つ様々な「情報資産」をあらゆる脅威から守り、その価値を損なうことなく、安全に活用できる状態を維持するための組織的な取り組み全体を指します。
ここで言う「情報資産」とは、顧客情報や技術情報といったデータだけでなく、それらを保存しているパソコンやサーバー、USBメモリといった媒体、さらにはソフトウェアやネットワークなども含まれます。
そして「脅威」とは、サイバー攻撃やウイルス感染といった悪意のあるものだけではありません。
従業員の操作ミス、機器の故障、地震や火災といった自然災害なども含まれます。
つまり情報セキュリティは、単なる技術的な対策にとどまらず、社内ルールの策定や従業員教育、物理的な管理体制の構築までを含んだ、総合的なリスクマネジメント活動なのです。
情報セキュリティの3要素(CIA)
情報セキュリティを考える上で、世界共通の基本的な考え方となるのが「情報セキュリティの3要素」です。
これは、守るべき3つの性質の頭文字をとって「CIA」とも呼ばれています。
この3つの要素をバランスよく維持することが、情報セキュリティ確保の基本となります。
機密性
機密性(Confidentiality)とは、許可された人、つまりアクセスする権限を持つ人だけが情報にアクセスできるようにし、権限のない人には情報が漏れないようにすることを指します。
情報セキュリティと聞いて、多くの人が真っ先に思い浮かべるのがこの機密性の確保でしょう。
この機密性が損なわれると、企業の内部情報や顧客の個人情報が外部に流出する「情報漏洩」といった事態を引き起こします。
情報漏洩は、企業の社会的信用の失墜や、顧客への損害賠償といった深刻な経営ダメージに直結しかねません。
機密性を維持するためには、「IDとパスワードによるシステムへのアクセス制御」や「ファイルやメールの暗号化」などを徹底してください。
これらの対策を通じて、情報へのアクセス権を厳格に管理することで、不正な閲覧や持ち出しを防ぐことができます。
完全性
完全性(Integrity)とは、情報が正確であり、破壊や改ざん、消去などがされていない状態を保つことを指します。
情報にアクセスできたとしても、その内容が不正確であったり、意図せず書き換えられていたりしては、情報を正しく活用することはできません。
たとえば、企業の財務データが不正に書き換えられたり、顧客からの注文データが知らぬ間に変更されたりすれば、事業に大きな混乱と損害をもたらすはずです。
完全性は、情報の信頼性を担保するための非常に重要な要素なのです。
完全性を維持するための具体的な対策例としては、「情報へのアクセス履歴(ログ)の取得と監視」や「情報が改ざんされていないか検知するシステムの導入」などがあります。
これらの対策により、情報が常に正しく、信頼できる状態にあることを維持しやすくなります。
可用性
可用性(Availability)とは、権限を持つ人が、必要だと感じた時にいつでも情報にアクセスしたり、システムを利用したりできる状態を保つことを指します。
いくら情報が厳重に守られ、内容が正確であっても、使いたい時に使えなければ意味がありません。
たとえば、サーバーがダウンして会社のホームページが見られなくなったり、ランサムウェア(身代金要求型ウイルス)に感染してファイルが開けなくなったりする事態は、この可用性が損なわれた状態です。
特に、ECサイトやオンラインサービスを提供している企業にとっては、サービスの停止が直接的な売上減少に繋がるため、可用性の確保は死活問題となります。
可用性を維持するためには、「サーバーやネットワーク機器の二重化」や「DDoS攻撃(大量のデータを送りつけてサービスを停止させる攻撃)への対策」などを意識しましょう。
情報セキュリティ関連資格一覧
情報セキュリティに関する知識やスキルは、専門職でなくともビジネスパーソンにとって重要度を増しています。
ここでは、情報セキュリティの専門性を証明するための代表的な資格をいくつか紹介します。
| 資格名 | 概要 |
| 情報処理安全確保支援士試験(SC) | サイバーセキュリティ分野の国家資格。高度な専門知識・技能が問われる。セキュリティ専門家を目指す人向け。 |
| 情報セキュリティマネジメント試験(SG) | 情報セキュリティ管理の基礎知識を問う国家資格。IT部門だけでなく、全部門の管理職や担当者が意識すべき資格。 |
| CompTIA Security+ | 実践的なセキュリティスキルを証明する国際的な認定資格。ハンズオンのスキルが重視される。 |
| CISSP (Certified Information Systems Security Professional) | 情報セキュリティ専門家向けの国際的な認定資格。広範な知識と実務経験が求められる。 |
| CISM (Certified Information Security Manager) | 情報セキュリティのマネジメント層向けの国際的な認定資格。戦略立案や管理体制構築のスキルを証明する。 |
これらの資格取得を目指すことで、情報セキュリティに関する体系的な知識を習得できるでしょう。
情報セキュリティ対策が甘いことで起こる身近な例
情報セキュリティの重要性を頭では理解していても、具体的なリスクとして実感しにくいこともあるかもしれません。
ここでは、対策の不備が原因で実際に起こりうる、身近な被害事例を3つ紹介します。
ホームページが書き換えられた
ホームページ改ざんと聞くと、高度な技術を持つハッカーによる特殊な攻撃を想像するかもしれません。
しかし、現実は異なります。
ほとんどの改ざん事件は、以下のような基本的な情報セキュリティ対策の不備が原因です。
- 推測されやすい安易なパスワードの使用
- 発見済みのセキュリティホール(脆弱性)の放置
- ファイアウォールといった基本的な防御システムの未導入
攻撃者は、特定の組織を狙うだけでなく、セキュリティ対策が甘いWebサイトを無差別に探し出して攻撃を仕掛けます。
つまり、企業の大小を問わず、どのような企業でも標的になりうるのです。
顧客のメールアドレスが漏洩した
メールの一斉送信時に、宛先を「To」や「Cc」に設定してしまう単純な操作ミスが、深刻な情報漏洩に繋がることがあります。
これにより、受信者全員がお互いのメールアドレスを閲覧できる状態となり、意図せず顧客や関係者のリストを流出させてしまうのです。
この人為的なミスは、個人情報管理の甘さを露呈し、企業の信用を大きく損ないます。
さらに、漏洩したメールアドレスが悪用され、受信者が迷惑メールやフィッシング詐欺の標的になる二次被害を生む危険性もはらんでいます。
一斉送信を行う際は、必ず宛先を「Bcc」に指定するか、専用の配信システムを利用することが、情報を守るための絶対条件です。
他人のIDで不正にオンライン株取引が行われた
不正アクセスは、外部からの攻撃だけとは限りません。
システムの開発者や管理者といった、信頼された内部関係者による「なりすまし」という形で、より深刻な被害が発生することもあります。
過去には、証券会社の社員がその立場を悪用し、作業中に数万人分もの顧客IDとパスワードを不正に入手した事件がありました。
犯人はその情報を使って顧客になりすまし、オンラインで勝手に株の売買を行ったのです。
このような内部犯行は、顧客の資産に直接的な被害を与え、企業の信用を根底から破壊します。
従業員のアクセス権限を適切に管理し、機密情報へのアクセスを厳格に監視することが、こうした被害を防ぐ上で極めて重要です。
中小企業が気を付けるべき7つの情報セキュリティ
大企業のように専門部署や潤沢な予算を確保することが難しい中小企業こそ、基本的な対策を地道に継続することが、自社を守る上で最も効果的です。
ここでは、IPA(情報処理推進機構)が公開している「情報セキュリティ5か条」などを参考に、中小企業が特に気を付けるべき実践的な対策を7つ解説します。
参考)IPA 独立行政法人 情報処理推進機構「情報セキュリティ5か条」
OSやソフトウェアを常に最新状態にする
パソコンのOSや、インストールされているソフトウェアは、発見された脆弱性(セキュリティ上の欠陥)を修正するための更新プログラムが定期的に提供されます。
この更新を怠ると、脆弱性を悪用するサイバー攻撃の標的となり、ウイルス感染や不正侵入のリスクが格段に高まります。
OSやソフトウェアの自動更新機能を有効にし、常に最新の状態で利用することを徹底してください。
特に、メーカーのサポートが終了した古いOSを使い続けることは非常に危険です。
ウイルス対策ソフトを導入する
ウイルス対策ソフトは、マルウェア(ウイルス、ワーム、ランサムウェア、スパイウェアなどの総称)の侵入を防ぎ、万が一パソコンに侵入されても検知・駆除する役割を果たします。
業務で使用するすべてのパソコンとサーバーに、信頼できるウイルス対策ソフトを導入しましょう。
導入するだけで満足せず、ウイルス定義ファイル(新種のウイルス情報が記録されたファイル)が常に最新の状態に保たれるように設定することも不可欠です。
最近のOSには標準でセキュリティ機能が備わっていますが、多層的な防御のために専用ソフトの導入が推奨されます。
パスワードを強化する
単純で推測されやすいパスワードは、不正アクセスの最大の原因の一つです。
パスワードは、第三者に推測されにくく、かつ、ツールによる攻撃にも耐えられるよう、長く複雑なものに設定する必要があります。
具体的には、「10文字以上」「英大文字・小文字・数字・記号を組み合わせて複雑にする」「複数のサービスで使い回さない」という点を徹底しましょう。
従業員全員にこのルールを周知し、実践させることが重要です。
可能であれば、パスワードを安全に管理できる「パスワードマネージャー」の導入や、ログイン時の本人確認を強化する「二要素認証」の積極的な活用を検討してください。
共有設定を見直す
ファイルサーバーやクラウドストレージは業務効率化に非常に便利ですが、共有設定のミスが思わぬ情報漏洩に繋がることがあります。
特に「リンクを知っている全員がアクセス可能」といった設定は、そのリンクが何らかの形で外部に漏れた場合、誰でもファイルにアクセスできてしまうため大変危険です。
ファイルやフォルダへのアクセス権は、業務上本当に必要なメンバーだけに限定する形にしましょう。
また、誰がどのファイルにアクセスできるのか、定期的に設定状況を確認し、見直す習慣をつけることが大切です。
脅威や攻撃の手口を知る
どれだけ技術的な対策を講じても、それを使う「人」の意識が低ければ、セキュリティは簡単に破られてしまいます。
特に、巧妙な手口で偽のメールを送りつけ、ウイルスに感染させたり、個人情報を盗み出したりする「標的型攻撃」や「フィッシング詐欺」の被害は後を絶ちません。
IPAなどが発信する最新のセキュリティ情報を定期的にチェックし、「不審なメールの添付ファイルは安易に開かない」「メール本文中のリンクを不用意にクリックしない」といった基本的な注意点を社内で共有・周知することが、被害を未然に防ぐ上で非常に効果的です。
退職・異動時のアカウント削除・機器回収の徹底
従業員の退職や部署異動が発生した際の情報管理も、セキュリティ上の重要なポイントです。
退職した従業員のアカウントが社内システムやクラウドサービスに残ったままだと、悪意を持って不正にアクセスされたり、アカウントが乗っ取られて情報漏洩の原因になったりするリスクがあります。
従業員の退職・異動時には、関連するすべてのアカウントを速やかに削除または停止する業務フローを確立しましょう。
大企業の場合、こうした管理が徹底されていることが多いですが、中小企業の場合は対応が甘いケースもありますので注意してください。
IT管理者が不在でも運用できる「簡易なセキュリティルール」の整備
中小企業の多くは、専任のIT管理者が不在であったり、他業務と兼任する担当者が1人だけ、というケースが少なくありません。
このような状況で、大企業のような複雑で網羅的なセキュリティ規定を導入しても、運用が追いつかず形骸化してしまうのが実情です。
そこで重要になるのが、ITの専門家でなくても全従業員が理解し、実践できる「簡易なセキュリティルール」を整備することです。
たとえば、「不審なメールは開かずにまず担当者へ報告する」「公共のフリーWi-Fiを使って業務ファイルを開かない」といった当たり前のルールをまとめて周知するだけでも、大きな効果があります。
まとめ
情報セキュリティは、もはや専門家だけが考えればよいという時代ではありません。
ビジネスのあらゆる場面でデジタル化が進む現代において、情報セキュリティは企業の存続を左右する重要な経営課題となっています。
特に、一度トラブルが発生すると事業基盤が揺らぎかねない中小企業にとって、その重要性は計り知れません。
完璧なセキュリティを目指すのは困難ですが、自社のリスクを正しく認識し、できることから着実に始めることが何よりも大切です。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録