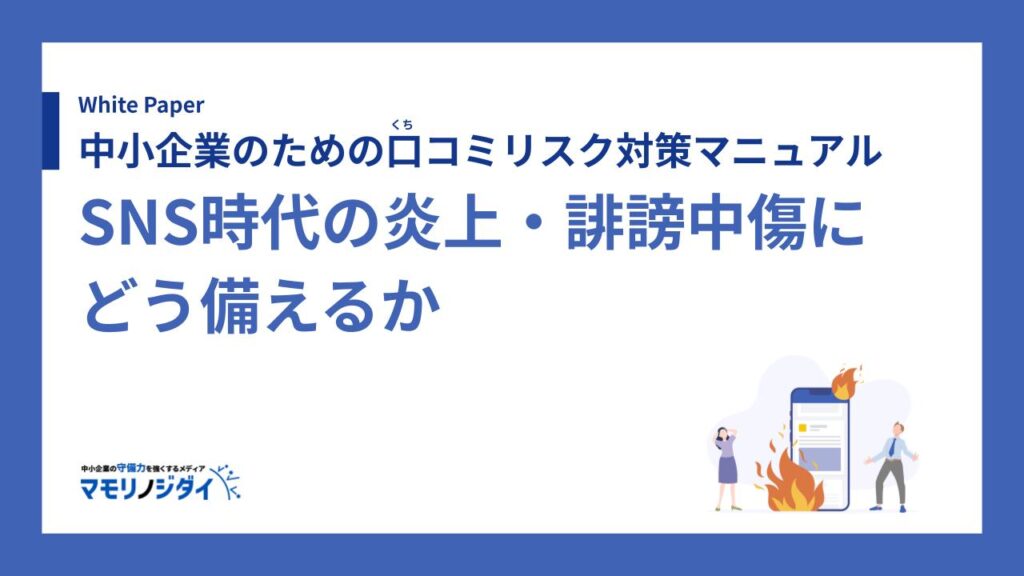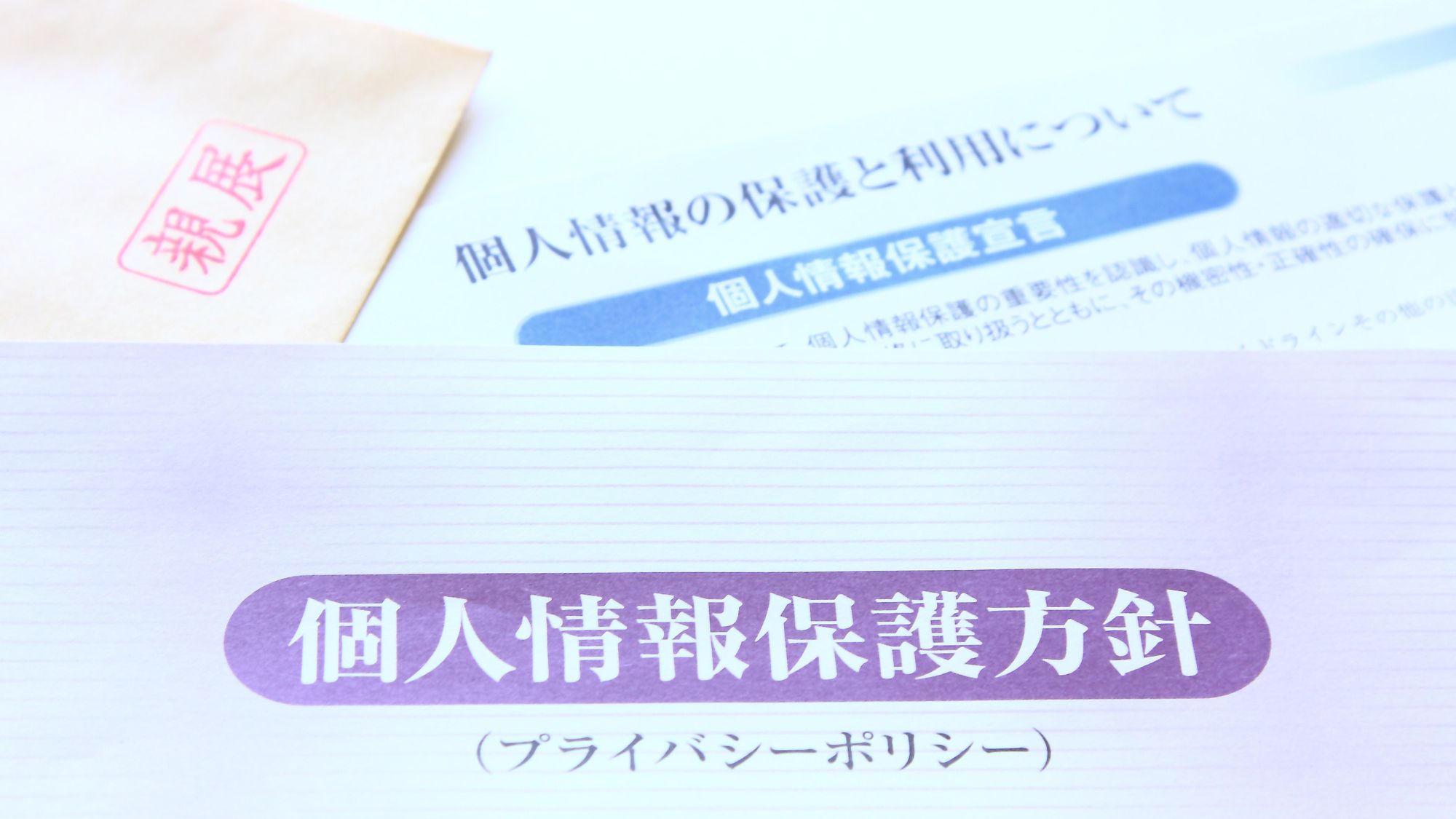【わかりやすい】公益通報者保護法にどう対応すべき?中小企業が必ず押さえるべきこと

たとえば、企業内でサービス残業が常態化している状況があるとしましょう。
この問題を認識した従業員が社内通報を行った場合、企業はその通報者に対して不利益な取り扱いをしてはいけません。これが、公益通報者保護法の基本的な考え方です。
この法律は、企業内部の法令違反や不正を是正につなげるための通報制度と、それを担う通報者を保護する枠組みを定めています。近年は制度の改正が進んでおり、大企業に限らず中小企業においても、一定の体制整備が求められている状況です。
本記事では、公益通報者保護法の基本的な内容に加え、中小企業が現実的に対応すべき実務、改正による影響点についてわかりやすく解説します。
公益通報者保護法は内部の声ですが、同様に外部の口コミリスクの管理も重要です。以下の資料では中小企業のコンプライアンス担当の方に向けてSNS時代の炎上・誹謗中傷への備えを記載していますので、ぜひこちらも無料でダウンロードしてご覧ください。
目次
そもそも公益通報者保護法って何?
公益通報者保護法は「労働者や役員が企業などの事業者による法令違反行為を通報した際に、その人の身分や立場を守るための法律」です。
ここでいう「公益通報」とは、パートタイム・派遣労働者、取引先社員、さらに退職から1年以内の退職者や役員も含め、不正の目的でなく組織内外の適切な窓口へ通報する行為を指します。
通報した人が不利益な扱いを受けないように、解雇や降格、減給といった処分は禁止されており、違反した場合は無効や損害賠償請求の対象です。
この法律の目的は、公益通報者を守るだけでなく、企業の内部での自浄作用を促し、社会全体で法令遵守を徹底させることにあります。特に中小企業の場合、大企業に比べて内部統制が弱いケースが多く「通報者保護制度を適切に整えること」が、コンプライアンスリスクを防ぐ第一歩です。
公益通報と内部告発の違いは?
「公益通報」に似た言葉に「内部告発」がありますが、実は意味と扱いが異なります。混同してしまうと、企業の対応を誤りかねないため、それぞれの違いを明確に理解しておくことが重要です。
以下の表は、公益通報と内部告発を比較したものです。
| 区分 | 公益通報 | 内部告発 |
| 定義 | 法令違反に関する事実を、労働者や退職者、役員が「公益通報者保護法」に基づいて通報する行為 | 組織内部の不正や問題を、外部に知らせる行為全般(法的保護の有無は問わない) |
| 通報先 | ①勤務先などの役務提供先 ②行政機関 ③報道機関・弁護士等 | 主に報道機関や世間に直接公表するケースが多い |
| 法的保護 | 一定の要件を満たせば「解雇・不利益取扱い禁止」など強力な保護が受けられる | 公益性が認められなければ保護対象外。名誉毀損など逆に責任追及される場合もある |
| 目的 | 消費者や取引先の利益、社会全体の安全を守ること | 社内是正を目的とする場合もあるが、告発者の不満や報復感情によるケースも含まれる |
| 企業対応 | 社内窓口の整備や調査体制を準備することが法律で求められる | 社会的信用の失墜リスクが大きいため、事前に内部通報制度を強化して防止することが重要 |
つまり、公益通報は「法律で定義された保護付きの仕組み」であるのに対し、内部告発はより広い概念で、必ずしも法的に守られるわけではありません。
内部通報制度との関係は?
内部通報制度とは、企業が自社内や外部に「通報窓口」を設け、従業員や関係者が法令違反・不正行為を安心して報告できる仕組みのことをいいます。これは、法令違反の早期発見や企業の信頼維持に欠かせないガバナンス体制の一部です。
公益通報者保護法は、この内部通報制度を実効的に機能させるために制定されています。制度があっても、通報者が「報復されるのではないか」と不安を感じれば利用されません。
そこで同法は、通報者を解雇・降格・嫌がらせなどから守り、安心して声を上げられる環境を保障します。
つまり「内部通報制度=企業が整える仕組み」「公益通報者保護法=通報者を守るルール」
という関係にあります。両者が補完し合うことで、法令違反を隠さず是正できる体制が整い、企業にとっての「守り」が強化されるのです。
参考)政府広報オンライン「組織の不正をストップ!従業員と企業を守る「内部通報制度」を活用しよう」
通報が「保護対象」になる条件とは
公益通報者保護法では、どんな通報でも自動的に保護されるわけではありません。通報先によって満たすべき要件が細かく異なり、その条件を外れると保護の対象外となってしまいます。
特に中小企業の場合、従業員が誤った手順で通報してしまうとトラブルに発展する可能性があるため、企業としても正しいルールを理解しておくことが重要です。以下の表に、1号(役務提供先への通報)、2号(行政機関への通報)、3号(報道機関等への通報)の違いを整理しました。
| 区分 | 通報先 | 保護要件のポイント |
| 1号 | 役務提供先(勤務先・派遣先など) | 違法行為がすでに発生またはまさに発生しようとしていること |
| 2号 | 行政機関 | ・違法行為が発生または発生しようとしていると信じるに足りる相当の理由(真実相当性)がある ・書面での通報(氏名・住所、事実内容、理由の記載) |
| 3号 | 報道機関・消費者団体・弁護士など外部 | ・2号通報と同じく真実相当性が必要 ・さらに以下のいずれかに該当する場合のみ保護 ①不利益取扱いの恐れ ②証拠隠滅の恐れ ③通報者特定の恐れ ④「通報するな」と不当な要求 ⑤20日経っても調査開始なし ⑥生命・身体・財産に急迫の危険 |
出典)消費者庁「通報者の方へ」
このように、通報先によって保護される条件が大きく異なる点が公益通報者保護法の特徴です。
通報が来たら中小企業はどう動くべき?知らないと罰則リスクに直結
公益通報者保護法の下では、従業員などから通報があった場合に適切に対応することが企業の責務です。特に中小企業の場合、「体制が整っていなかった」「知らなかった」という理由は通用せず、法令違反や行政処分に直結するリスクがあります。
ここでは、通報を受けたときに企業が最低限押さえておくべきポイントを整理します。
公益通報対応業務従事者を選任するポイント
公益通報を受け付け、調査・是正を行う「公益通報対応業務従事者」を選任することは、事業者に課せられた法的義務です(常時使用する労働者が300人以下の中小企業では努力義務)。
選任にあたっては、社内で通報窓口を担う部署や担当者に限定し、守秘義務を確実に履行できる人材を明示的に指定することが重要です。
さらに、従事者本人や従業員全体に対して「従事者制度の意義」「守秘義務の範囲」などを周知・教育することが、安心して通報できる環境づくりにつながります。
報復・不利益処分で中小企業が負う責任
公益通報を理由とした解雇は法律上無効です。降格・減給・配転や嫌がらせなども不利益取扱いとして禁止されています。
たとえ経営層に悪意がなかったとしても、通報後の人事措置が「報復的」と判断されれば企業は責任を問われる可能性があるので注意しましょう。また通報者から損害賠償請求を受ける可能性もあり、訴訟リスクに直結します。
中小企業にとっては一件の訴訟対応でも大きな負担となるため、通報後の処遇は特に慎重に管理することが不可欠です。
参考記事:中小企業もハラスメントの相談窓口設置が義務化!相談対応時のポイント
どんな罰則・行政処分の可能性がある?
公益通報者保護法では、通報者を特定する情報を漏らすなどの守秘義務違反については30万円以下の罰金刑が規定されています。これは唯一の直接的な刑事罰であり、軽視はできません。
一方で、通報を理由とした解雇・降格・減給・配転・嫌がらせ等の不利益取扱いについても禁止されています。裁判になれば復職や賃金支払い命令が下るリスクがあります。
降格・減給・配転などの場合も、通報者から損害賠償請求を受けたり、行政機関から助言・指導・勧告・企業名の公表といった処分を受ける可能性がある点にも注意が必要です。実務的には「刑事罰に準じる重い責任」が企業にのしかかります。
中小企業にとって、たとえ罰金や刑事罰に直結しなくても、行政処分や信用失墜が経営に与えるダメージは甚大です。つまり、通報者への対応を誤ることは「法令違反+企業ブランドの毀損」の両面でリスクを負うことにつながります。
2025年改正で何が変わる?知らないと罰則になる可能性も
2025年の公益通報者保護法改正は、中小企業にとって大きな影響を及ぼす内容となっています。
従業員だけでなく、取引先や委託先からの通報も保護対象です。そのため従来以上に幅広い内部告発リスクを想定した体制整備が求められます。
ここでは特に重要な改正ポイントを整理しましょう。
特定受託業務従事者も通報対象に追加|下請けからの内部告発も保護
改正後は、自社の委託業務に従事する外部の労働者(特定受託業務従事者)も通報者として保護されます。
たとえば、下請け企業の社員が自社の法令違反を発見して通報した場合も、公益通報として保護されるのです。これにより「外部だから関係ない」とは言えなくなり、取引先を含めたコンプライアンス体制の見直しが必須となります。
通報した従業員への解雇・契約解除がさらに厳罰化
従業員が公益通報を行ったことを理由に解雇や契約解除を行った場合、従来以上に厳しい処分が科されるようになります。改正法では「不利益取扱い」に該当する範囲が拡大され、無効とされるだけでなく、損害賠償請求や行政指導の対象にもなり得るため注意しましょう。
不利益取扱いを理由とする懲戒・解雇は「公益通報が原因」と推定される
重要なのは、改正法により「通報者への不利益取扱いが公益通報を理由とするもの」と推定される仕組みが導入される点です。
これにより、企業側が「通報とは無関係」と反証できなければ、懲戒・解雇などは違法と判断されるリスクが格段に高まります。中小企業にとっては、従業員への処分の正当性を明確に説明できる体制づくりが不可欠です。
参考記事:労働条件とは?労働条件明示の義務と記載すべき内容を解説
通報を妨害・特定する行為に罰則が追加
改正では、公益通報そのものを妨害したり、通報者の特定を目的として不当な調査を行うことに対しても新たに罰則が設けられます。
たとえば「誰が通報したのかを探す」行為や、通報の内容をもみ消す行為も対象です。企業自身が処罰の対象となり得ます。
中小企業も「通報を封じ込める」という発想自体がリスクになると理解しておくことが必要です。
中小企業の社内通報制度を強化する5つのステップ|ガイドライン準拠で安心
公益通報者保護法の改正を受け、中小企業も「社内通報制度の実効性」を確保することが強く求められています。以下の5ステップを押さえることで、法令対応と企業防衛を同時に実現可能です。
通報窓口を作る or 外部委託する
最初に取り組むべきは、従業員が安心して声を上げられる「通報窓口」の設置です。窓口は法務や人事部門に置くのが一般的ですが、中小企業では専任部署を持たない場合も多くあります。
その際は、弁護士や外部専門機関への委託が有効です。外部に任せることで通報者は「社内に知られるのでは」という不安を抱かずに済み、通報のハードルが下がります。また、外部窓口は中立的な立場から事実関係を整理しやすく、組織内で揉み消しが行われるリスクも減らせることも魅力です。
匿名通報・秘密保持・調査フローを整備
通報制度を形骸化させないためには、匿名通報の仕組みと秘密保持体制が不可欠です。通報者の身元が漏れる可能性があると、従業員は萎縮して声を上げられません。
さらに、受理から調査、改善策の実施までの流れを明文化し、マニュアルやフローチャートで共有しておくことも大切です。これにより担当者の裁量で対応が変わることを防ぎ、公平かつ迅速な調査が可能になります。
従業員が安心して通報できる教育と周知
通報制度を整備しても、従業員が「使うと不利益を受ける」と感じてしまえば意味がありません。そのためには、制度の存在や仕組みを分かりやすく周知すること、さらに教育を通じて安心感を醸成することが重要です。
具体的には、入社時研修や定期的な勉強会で制度の目的とルールを説明し、社内掲示板やイントラネットで窓口情報を明示しましょう。また、経営層や管理職から「通報を理由とした不利益取扱いは禁止」というメッセージを繰り返し発信することで、従業員の心理的ハードルを下げることができます。
参考記事:コンプライアンス研修とは?目的、効果、研修ネタの事例を徹底解説
不正発覚後の是正措置とフィードバック
通報を受けた後の対応こそが、制度の信頼性を決定づけます。調査で不正や法令違反が確認された場合、速やかな是正措置の実施と再発防止策の構築が必要です。
その上で、通報者や従業員全体に対して「調査を行った結果、改善策を取った」と適切にフィードバックしましょう。これにより、「通報しても何も変わらない」という失望感を避け、制度が生きた仕組みとして根付いていきます。
公益通報ハンドブックを活用した運用例
消費者庁が公表している「公益通報ハンドブック」は、企業が社内通報制度を実際に運用するうえで非常に役立つガイドラインです。通報窓口の設置方法から調査・是正措置の進め方、従業員教育の実施方法まで、実務に即したポイントが整理されています。
特に中小企業では、自社で一から制度を設計するのは難しいため、このハンドブックを参考に段階的に整備し運用することが有効です。以下の表で、ハンドブックの要点を整理しました。
| ハンドブックのポイント | 内容 | 実務での活用例 |
| 窓口の設置 | 内部・外部どちらでもよいが、通報者が安心して利用できる体制が必要 | 外部弁護士や専門機関に委託し、匿名性を担保 |
| 秘密保持の徹底 | 通報者の氏名や通報内容を漏らさないことが義務 | 担当者を限定し、情報管理マニュアルを策定 |
| 調査・是正措置 | 通報後は速やかに調査を実施し、是正策を講じる | 不正が確認された場合は改善計画を立て、結果を通報者にフィードバック |
| 教育・研修 | 従業員に制度の存在と利用方法を周知 | 年1回の研修やeラーニングで通報制度を説明 |
| 運用の見直し | 定期的に制度を点検・改善 | 通報件数や対応状況を分析し、取締役会で報告 |
このようにハンドブックは「制度の設計図」としてだけでなく、実際の運用や改善のチェックリストとしても活用できます。特に中小企業の場合、限られた人員の中で制度を形骸化させずに維持するには、こうした国の資料をベースにして社内ルールを整えることが重要です。
まとめ
公益通報制度は、大企業だけでなく中小企業にとっても「守りの仕組み」として重要な意味を持ちます。従業員や取引先からの通報を適切に受け止め、是正や改善につなげることで、不祥事の拡大や社会的信用の失墜を防ぐことが可能です。
特に2025年の改正では、下請けからの通報も保護対象に拡大され、不利益取扱いへの罰則や推定規定が導入されるなど、事業者に課される責任は一層厳しくなります。中小企業であっても「知らなかった」では済まされません。
中小企業にとってコンプライアンス対応はコストではなく「事業を守る投資」です。今こそ社内通報制度を強化し、組織の信頼を高めるチャンスと捉えましょう。
消費者庁のハンドブックは、PDFで無料で公開されています。まずはダウンロードして、自社の制度と照らし合わせてみませんか?

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録