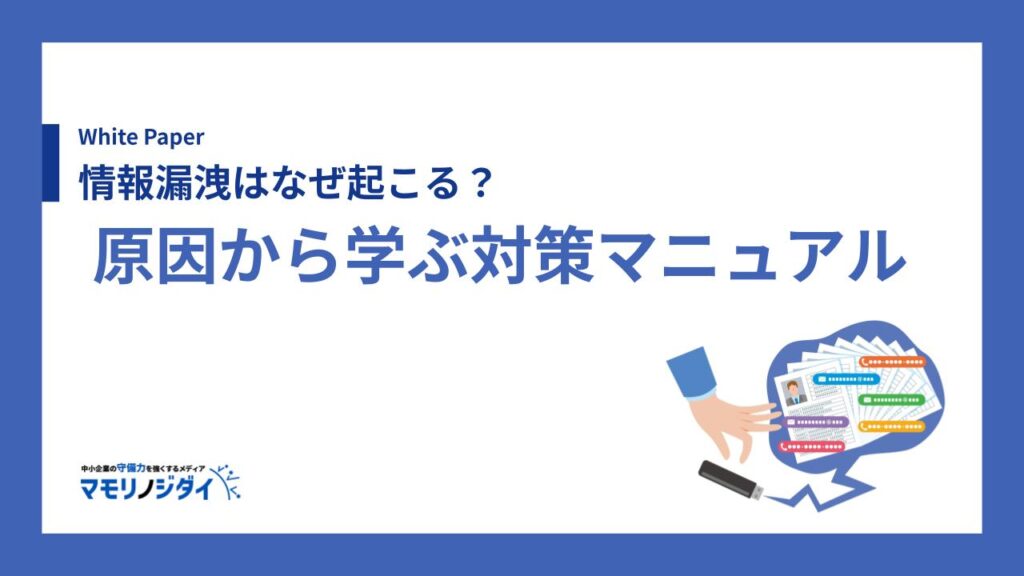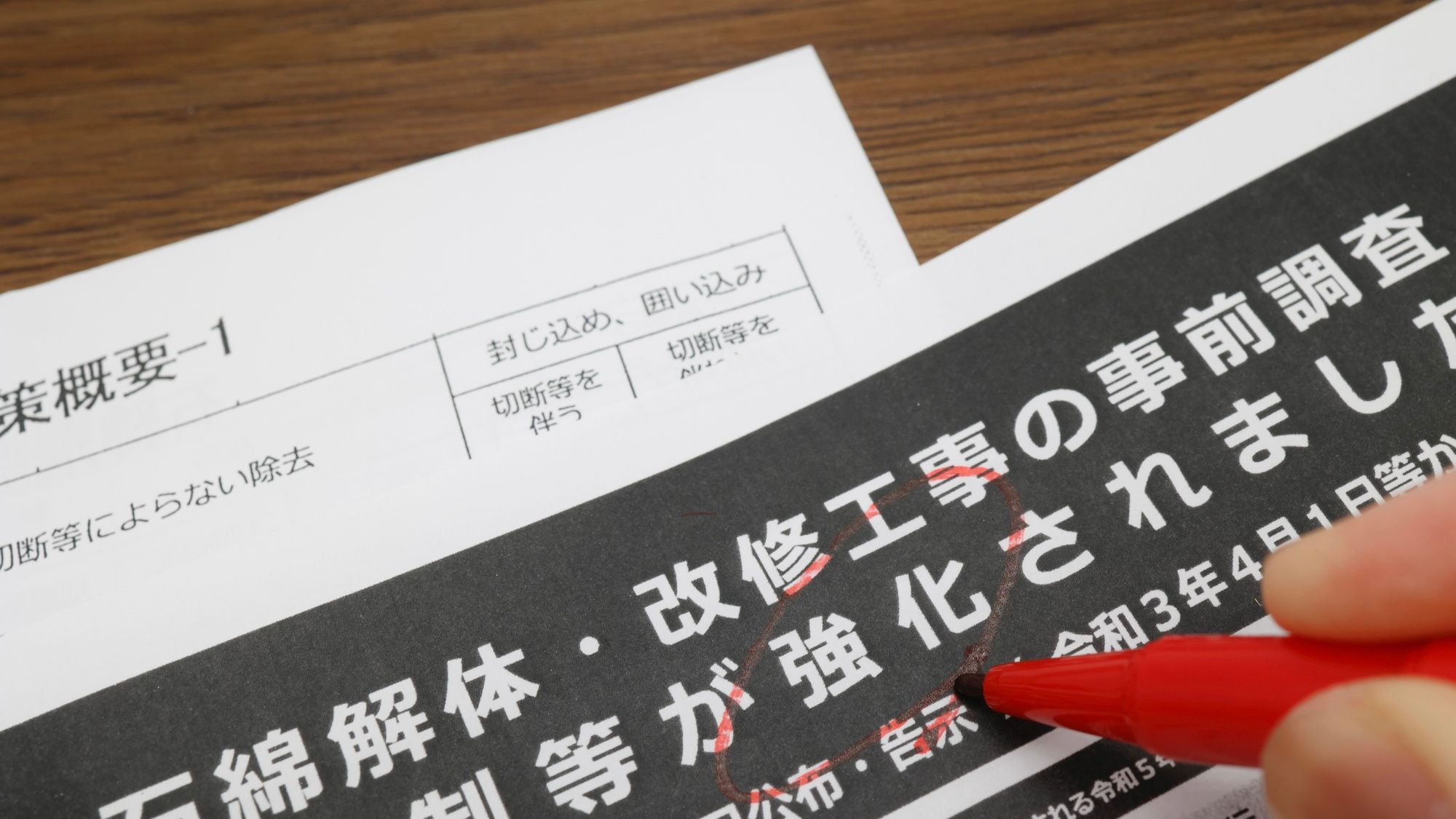危機管理を定める方法とは?計画マニュアル策定の手順について中小企業向けに解説

近年、自然災害や感染症、サイバー攻撃、SNS上の対応トラブルなど、企業活動に影響を及ぼすリスクは多様化しています。特に中小企業にとっては、一度のトラブルが取引や信用に直結し、回復に時間がかかるケースも少なくありません。
危機が発生した際、「誰が、何を、どの順で判断・対応するか」が定まっていなければ、混乱が拡大し、被害を最小限に抑えることが困難です。そのため、あらかじめ業務や役割ごとに対応手順を明確にしておくことが、組織を守る第一歩になります。
本記事では、危機管理の基本的な考え方から、中小企業でも取り入れやすい実践的なマニュアルの設計方法、具体的なリスクの種類、体制構築の留意点までを整理して解説します。
また、危機管理の代表的な項目が「情報漏洩の防止」です。以下から情報漏洩対策マニュアルを無料でダウンロードできますので、中小企業の経営者、情報システム部門の方はこちらも参考にしてください。
目次
そもそも「危機管理」とは?意味と基本の考え方
「危機管理」とは、企業が突発的に発生する危機的状況に対して、被害を最小限に抑え、事業や組織の存続を守るための取り組み全般を指します。
ここでいう「危機」とは、自然災害や火災、感染症パンデミック、サイバー攻撃、重大事故、さらにはSNSでの炎上など、多種多様です。
危機管理は、こうした事態が「発生してから」慌てて対応するのではなく、「起こるかもしれない」と想定してあらかじめ方針や行動を定めておくことが重要になります。事前に備えることで、緊急時にも冷静かつ迅速に対応することが可能です。
リスク管理との違いは?よく混同されがちなので要注意
危機管理とよく混同される言葉が「リスク管理(リスクマネジメント)」です。両者は似ているようでいて、対象とアプローチが異なります。
違いをわかりやすく整理したものを下表にまとめました。
| 項目 | 危機管理(クライシスマネジメント) | リスク管理(リスクマネジメント) |
| 主な目的 | 発生した危機への即時対応と被害最小化 | 事前にリスクを把握し、発生を防ぐ・軽減する |
| タイミング | 危機発生「後」の行動が中心 | 危機発生「前」の予防が中心 |
| 想定範囲 | 予期せぬ事故・災害・不祥事など突発的事象 | 法的リスク、財務リスク、情報セキュリティなど幅広い |
| 担当部門 | 経営層・総務・広報・安全衛生など多部門連携 | 主にリスク管理部門、内部統制、経営企画など |
リスク管理で「起こる前に防ぐ」体制を整えつつ、それでも避けられない突発的な事態に備えるのが危機管理となります。両者はどちらか一方だけで十分というものではなく、相互に補完し合う関係です。
両輪で準備を進めることが、中小企業にとっても現実的な経営リスク対策となります。
なぜ中小企業にも危機管理が求められているのか?
「危機管理」というと大企業の話だと思われがちです。しかし、実際には中小企業ほど危機の影響を直接的に受けやすく、早急な対応が求められます。
資金や人材の余裕が限られている分、ひとつのトラブルが経営全体に直結してしまうからです。ここでは特に中小企業にとって避けられない理由を整理しましょう。
自然災害・感染症・サイバー攻撃などリスクの多様化
日本は地震や台風といった自然災害が多く、事業の継続を脅かすリスクは常に存在します。さらに新型コロナウイルスの流行で明らかになったように、感染症パンデミックによって従業員が一斉に出社できなくなる可能性も現実的です。
また、近年は技術進歩のため、中小企業がサイバー攻撃の標的になるケースが増えています。つまり、中小企業であっても「自然災害」「健康リスク」「情報リスク」などの脅威に備えなければならない時代なのです。
信頼失墜や炎上の発生のハードルが下がっている
SNSが普及した現在、ちょっとしたクレーム対応の不備や従業員の不適切な投稿が一瞬で拡散し、企業のイメージを大きく損なうことがあります。中小企業の場合、大手のように広報部門や危機管理専門の人材を抱えていることは少なく、「気づいた時には炎上していた」というケースも珍しくありません。
一度失った信頼を取り戻すには長い時間とコストがかかり、場合によっては経営の継続自体が困難になることもあります。そのため、炎上リスクに備えた危機管理体制は必須です。
BCP・内部統制は企業規模関係なく必要になっている
大企業を中心に浸透してきたBCP(事業継続計画)や内部統制の仕組みは、今や中小企業にとっても無関係ではありません。取引先から「緊急時の対応計画を見せてほしい」と求められることも増えており、危機管理が商取引や信用調査の前提条件になりつつあります。
また、法改正によりハラスメント防止や労働安全管理などの対応は中小企業にも義務付けられており、危機管理を「やらない選択肢」は現実的ではありません。むしろ限られたリソースを活かして、現実的で実行可能な危機管理計画を策定することが必要です。
「知らなかった」では済まされない!危機管理に関わる主要法令
危機管理を考える際には、企業規模にかかわらず遵守しなければならない法律が数多く存在します。
法律違反は行政処分や罰則というリスクだけではありません。従業員や顧客からの信頼失墜、さらにはSNS炎上といったリスクに直結します。
そのため、単なる法令遵守にとどまらず「危機管理の観点でどう備えるか」を意識することが重要です。
労働安全衛生法:従業員の安全を確保する義務
労働安全衛生法は、従業員の生命・身体の安全を確保するための基本法です。事業者は、災害や事故から社員を守るため、避難計画や安全マニュアルの整備、定期的な訓練などを講じる義務があります。
この法律に違反すると、労災事故時の企業責任が問われるだけでなく、重大な事故が発生した場合にはメディア報道やSNSでの批判により企業イメージが著しく毀損されるリスクもあります。
特に中小企業では「人数が少ないから大丈夫」と見過ごされがちですが、限られた人員だからこそ、一人ひとりの安全を守る体制づくりが欠かせません。
個人情報保護法:情報漏洩時の報告と再発防止の義務
個人情報保護法は、個人データが漏洩した際の報告義務や、本人への通知義務などを明確に定めています。これは上場企業に限らず、少人数の顧客管理・従業員管理を行っている中小企業にも当然適用される法律です。
違反が発覚した場合には、監督官庁による行政指導や業務改善命令だけでなく、顧客からの信用失墜や契約停止、SNS等での批判・炎上といった被害につながる可能性があります。
危機管理としては、漏洩が発生した際の初動対応フローを明文化し、関係各所への報告・通知、再発防止策の提示までをスムーズに行える体制を整えておくことが不可欠です。特にクラウドツールや外部委託を利用している場合は、委託先の管理状況にも目を配る必要があります。
サイバーセキュリティ基本法:事業者が果たすべきセキュリティ責務
サイバーセキュリティ基本法は、国や自治体だけでなく、民間企業にも「自主的なセキュリティ確保の努力義務」を求めています。特にランサムウェアや標的型攻撃、メールによる不正アクセスなどの脅威は、企業の規模を問わず発生しており、中小企業も例外ではありません。
このような攻撃によって、顧客情報や業務データが暗号化・流出し、業務が停止する、取引先や顧客からの信頼を大きく損なう、さらには金銭的な身代金要求や法的責任が発生するなどのリスクが考えられます。
危機管理の観点では、不正アクセスを受けた際の初動連絡体制(誰がどこに報告するか)や、業務復旧までのシナリオ・手順書をあらかじめ策定しておくことが重要です。
消防法:火災から従業員と資産を守る計画
消防法は、防火管理者の選任や消防計画の作成・提出、避難訓練の実施などを通じて、企業に火災の予防と初動対応体制の整備を義務付けています。これらを怠ると、火災発生時に従業員や顧客の安全を確保できません。
また、法令違反が発覚すれば、行政からの指導や是正命令、最悪の場合には営業停止や損害賠償請求といったリスクにつながるおそれもあります。
危機管理においては、BCP(事業継続計画)と消防計画を連動させ、火災発生時に「誰が」「どのような手順で」動くのかを事前に定めておくことが大切です。特に老朽化した建物や倉庫などを利用している中小企業では、配線や可燃物の管理、日常点検や定期訓練の実施を怠らないようにしましょう。
参考)e-GOV「消防法」
災害対策基本法:防災計画の策定と協力の義務
災害対策基本法は、地震・台風・豪雨などの自然災害に対して、国や自治体だけでなく地域社会全体が連携して備えることを目的とした法律です。企業も地域防災計画への協力責務を負っており、中小企業も例外ではありません。
大規模災害が発生した場合、従業員の安否確認や初動対応が遅れれば、人的被害の拡大や業務の長期停止につながる可能性があります。
また、対応が不十分であることが外部に露見することもリスクです。取引先からの信頼喪失や契約見直しといった問題も発生し得ます。
そのため危機管理としては、地震や風水害などを想定した避難ルートや安否確認方法、緊急時の業務継続手順(BCPとの連携)をあらかじめ明文化しておくことが重要です。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法):ハラスメント対策の義務化
この法律により、すべての企業に対してパワーハラスメントを含むハラスメント防止措置の実施が義務化されました(労働施策総合推進法)。この義務は、企業規模にかかわらず適用されており、中小企業であっても対応が求められます。
ハラスメントを放置した場合、職場内の人間関係の悪化や離職、訴訟リスクの発生に加えて、企業イメージの毀損につながる可能性もあるため、早期対応と事前対策が不可欠です。
危機管理の観点では、社内相談窓口の設置や対応マニュアルの整備に加えて、経営層が「ハラスメントを許容しない」姿勢を明確に打ち出すことが、再発防止と組織全体のリスク低減に直結します。
参考)e-GOV「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
労働基準法:不払残業や過重労働が招く経営リスク
労働基準法は、労働時間・賃金・休憩・休日・割増賃金など、従業員の労働条件に関する最低基準を定めた法律です。違反すると、労働基準監督署による是正勧告や罰則の対象となるだけでなく、労災認定や訴訟、SNSでの告発など、大きな影響を及ぼす事態に発展します。
特に中小企業では、「少人数だから黙認されるだろう」「お互いに融通が利く関係だから問題ない」と考えられがちです。しかし、一件の違反が従業員の不満や離職を引き起こし、社内の雰囲気悪化や採用難につながる例も少なくありません。
危機管理としては、労働時間や残業の適正な把握・記録、就業規則の整備、指摘を受けた場合の迅速な是正対応フローの構築が重要です。法令の趣旨を理解し、「守るべき基準」として社内で共有することが、トラブルを未然に防ぐ第一歩になります。
参考)e-GOV「労働基準法」
下請法:取引先との健全な関係を揺るがす違反リスク
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者による不当な取引条件の押し付けや支払い遅延などを防止し、下請企業との公正な取引を確保することを目的とした法律です。発注側にあたる中小企業にとっても、法令遵守は重要な経営課題となります。
この法律に違反した場合、公正取引委員会による勧告や企業名の公表といった行政処分の対象になるだけで済みません。取引先からの信頼を失い、契約解除・取引停止につながる可能性があります。
さらに、不払い・不当要求の事実が外部に漏れた場合、SNS等で批判が拡散し、企業イメージを大きく毀損するリスクも想定されます。
危機管理の観点では、書面による契約の徹底、発注・検収・支払い条件の明確化、定型の取引フローの整備が不可欠です。
景品表示法:「炎上」に直結する不当・誇大表示のリスク
景品表示法は、消費者を誤認させるような不当表示(優良誤認・有利誤認)や誇大広告、過大な景品の提供を禁止する法律です。違反が確認されると、企業は課徴金(売上の最大3%)の納付命令や行政処分を受けるだけでなく、消費者からの不信やSNSを通じた炎上・批判に発展する可能性が非常に高い分野でもあります。
特に中小企業では、販促活動を少人数で運営している場合も多いです。表示内容のチェック体制が不十分だと、悪意がなくても法令違反につながる恐れがあります。
そのため、危機管理としては、広告やキャンペーンを公開する前に、景品表示法の観点で内容を精査し、根拠資料(エビデンス)をあらかじめ確認・保管しておくことが重要です。
5ステップでわかる!中小企業のための危機管理計画の立て方
危機管理は「難しい」「専門知識が必要」と思われがちですが、実際には基本の流れを押さえれば中小企業でも十分に取り組めます。
ここでは、実務にすぐ活かせる5つのステップに分けて解説しましょう。
参考記事:コンプライアンスとは?中小企業がリスクから守るために知っておくべきこと
STEP1:自社に潜むリスクを洗い出す
まず取り組むべきは、自社にどのようなリスクが存在するのかを整理することです。自然災害やサイバー攻撃だけでなく、従業員の不祥事や取引先トラブルも視野に入れる必要があります。
経営層だけでなく現場の声も取り入れながら「想定し得る危機」をリスト化することが、計画づくりの出発点です。
STEP2:リスクの優先順位を決める
リソースの少ない中小企業では、洗い出したリスクをすべて同じ重みで扱うのは非現実的ですので、発生確率と影響度を軸に優先順位を決めましょう。
例えば、年に一度は必ず起きる水害対策と、十年に一度起きる可能性の地震では、準備の深さや投資配分も変わってきます。
STEP3:いざという時の「初動対応」を決める
危機管理で最も重要なのは、発生直後の初動です。初動を誤れば被害は一気に拡大します。
火災なら「誰が通報するのか」、情報漏洩なら「どの部署が取引先へ連絡するのか」といった具体的な行動を明文化しておくことが、混乱を防ぐ最大のポイントです。
STEP4:混乱を防ぐ連絡体制と役割分担
有事の際には、誰が誰に何を伝えるのかが明確でなければなりません。社内の連絡網や緊急時の代替連絡手段(チャットツール・個人携帯など)を決めておくと安心です。
また、指揮をとる責任者、現場対応を行う担当者、外部対応を担う広報といった役割分担を明確にしておくことで、限られたリソースでも混乱を抑えられます。
STEP5:「計画倒れ」を防ぐ訓練と見直し
危機管理計画は作成して終わりではありません。定期的に訓練を行い、課題を洗い出して計画をアップデートすることで初めて機能します。
特に中小企業では人員の入れ替わりも多いため、新しいメンバーにも周知する仕組みを持続させることが大切です。「机上の計画」にせず、実効性を担保する運用こそが危機管理の肝になります。
これだけは必須!危機管理計画に盛り込むべき6つの要素
危機管理計画は「作れば安心」というものではなく、盛り込むべき要素が抜けていれば有事に機能しません。中小企業であっても、最低限押さえておくべき要素があります。
以下で一つずつ解説していきましょう。
①リスク分析:自社の弱点を把握する
まず計画の土台となるのがリスク分析です。自社の業種や地域特性によって想定すべきリスクは異なります。
例えば製造業ならサプライチェーンの途絶、IT企業ならシステム障害が大きなリスクです。自社の弱点を客観的に洗い出すことで、計画全体の精度が大きく変わります。
②対応手順:具体的なアクションプラン
リスクを洗い出しただけでは意味がありません。有事に「誰が」「何を」「どの順番で行うか」を具体的に定めることが必要です。
火災が発生したら誰が通報するのか、情報漏洩が起きたらどの部署が取引先へ連絡するのかといった手順を明文化することで、混乱を最小限に抑えられます。
③発動基準:計画を発動するタイミング
危機管理計画は「どのタイミングで動かすのか」を明確にしなければいけません。
例えば「システム障害が30分以上続いた場合」「SNSで不適切投稿が100件以上拡散された場合」など、客観的な基準を設定しておくことが重要です。基準があいまいだと、初動が遅れたり対応が過剰になったりするリスクが高まります。
④広報・連絡体制:信頼を守るコミュニケーション
危機発生時に社内外への情報発信が遅れたり誤ったりすると、被害は二次的に拡大しますので対策が必要です。従業員や取引先にどのように知らせるか、マスコミや顧客にどう説明するかといった広報フローを決めておきましょう。
特に中小企業の場合、対応を誤れば一気に信頼を失い、経営継続に直結するリスクとなります。
⑤緊急連絡網:いざという時の連絡リスト
有事の際に最も困るのは「誰に連絡すればよいかがわからない」ことです。役員や部署責任者、主要取引先や自治体の窓口まで、緊急時に必要となる連絡先をリスト化しておきましょう。
紙とデジタルの両方で持ち、停電やネットワーク障害時にも使える形にしておくことが望まれます。
⑥事後検証:次に活かす改善の仕組み
危機管理は「一度発生したら終わり」ではありません。対応が適切だったか、改善できる点はどこかを事後に必ず振り返り、計画へ反映させることが重要です。
中小企業ではリソース不足から検証が疎かになりがちですが、ここを怠ると同じ失敗を繰り返すことになり、企業の存続に直結するリスクを抱えることになります。
具体的にどんな危機がある?中小企業で起こりうるケース
危機管理を考える上で重要なのは、「自社には関係ない」と思わないことです。実際には中小企業ほどリスクに直面したときのダメージが大きく、回復のための体力も限られています。
ここでは、特に起こりやすい危機の代表例を見ていきましょう。
サイバー攻撃・情報漏洩:狙われる会社の「情報資産」
中小企業もサイバー攻撃の対象となりやすく、取引先情報や顧客データが狙われます。IT部門が弱い企業ほど被害を受けやすく、経営継続が難しくなることもあるため対策は必須です。
以下に代表的なリスクと対策を示します。
| 想定リスク | 代表的な対策 |
| 顧客・取引先情報の流出 | アクセス権限の最小化、暗号化の徹底 |
| ランサムウェア感染 | 定期的なバックアップと復旧訓練 |
| フィッシング詐欺 | 従業員向けセキュリティ研修 |
こうした対策は単発ではなく継続的に実施する必要があります。特に教育と技術的対策を組み合わせることで、被害を最小限に抑えることが可能です。
自然災害:事業の継続を脅かす天災
地震や豪雨といった自然災害は予測が難しく、事業そのものを止めるリスクを抱えています。日本に拠点を置く企業にとっては避けられない課題であり、BCP策定の根幹をなす分野です。
具体的には以下のような対策を講じましょう。
| 想定リスク | 代表的な対策 |
| 建物・設備の損壊 | 耐震補強、代替拠点の確保 |
| 停電・ライフライン停止 | 発電機・非常用電源の備蓄 |
| サプライチェーン断絶 | 代替取引先リストの準備 |
自然災害への備えは費用対効果の判断が難しい部分もありますが、被災後の損失は比較にならないほど大きくなります。最低限の備えを優先的に整えることが重要です。
感染症・パンデミック:従業員の出社不能に備える必要性
感染症流行は一度に多くの従業員が出社できなくなるリスクを伴うものです。特に中小企業は代替要員が少ないため、数人の欠勤が経営に直結することもあります。
そのため以下のような対策を講じましょう。
| 想定リスク | 代表的な対策 |
| 集団感染による欠勤 | 在宅勤務体制の整備 |
| 感染拡大 | 健康チェック・衛生管理の徹底 |
| 事業停止 | 優先業務の絞り込みと代替計画 |
感染症対策は「予防」と「代替体制」が鍵です。事前にリモートワーク環境や業務の優先順位を決めておくことで、混乱を最小化できます。
従業員トラブル・内部不正:組織を内側から崩壊させるリスク
内部からの不正や労務トラブルは、外部の攻撃以上に企業を弱らせることがあります。退職や労務訴訟に発展する前に、早めの対策が欠かせません。
| 想定リスク | 代表的な対策 |
| 内部不正・横領 | 職務分掌と承認フローの徹底 |
| ハラスメント問題 | 相談窓口の設置、研修の実施 |
| 労務トラブル | 勤怠管理システムの導入 |
内部の問題は表面化しにくいため、相談体制の整備やルールの明文化が大切です。経営者自身が「見て見ぬふり」をせず、仕組みとして防止する姿勢が求められます。
参考記事:契約書のリーガルチェックとは?中小企業が法務リスクを回避する方法
SNS炎上・レピュテーション:一瞬で拡散する企業の悪評
SNSの普及により、企業の対応や発言が一瞬で拡散し炎上に発展する可能性があります。小さな不適切表現や誤解が、信頼失墜や売上減少に直結する時代です。
| 想定リスク | 代表的な対策 |
| 誤投稿・不適切発言 | SNS運用ルールの策定と研修 |
| クレーム対応の拡散 | 危機広報マニュアルの整備 |
| デマ・風評被害 | 事実確認と迅速な一次対応 |
炎上は完全に防ぐことは難しいものの、「対応のスピードと透明性」が被害を最小限にします。普段から想定問答や対応体制を準備しておくことが信頼維持の鍵です。
参考記事:【2025年最新】コンプライアンス違反の事例6選!リスクを学んで企業の対策を
ありがちな失敗パターン!危機管理が機能しない理由
危機管理計画を立てていても、実際の現場で機能しないケースは少なくありません。多くの場合、その背景には「計画と現実の乖離」「属人化」「初動の遅れ」といった構造的な問題があります。
これらは中小企業に特有のリソース不足とも関係しており、理解しておくことで失敗を未然に防げます。具体的に失敗例と対策を紹介しましょう。
机上の空論で現場が動かない
立派な計画を作成しても、実際に現場で実行できなければ意味がありません。実務を担う従業員が理解していなかったり、手順が複雑すぎたりすることで「計画倒れ」になるケースが多くなります。
| 想定される失敗 | 改善のための対策 |
| 分厚い計画書が現場で読まれない | シンプルなチェックリスト化 |
| 担当者以外が内容を知らない | 全社員への訓練・周知徹底 |
| 実情に合わない手順 | 定期的なレビューと現場の声の反映 |
危機管理は「読んで理解できること」よりも「即座に行動できること」が重要です。現場で使える形に落とし込むことが成否を分けます。
担当者依存で属人化している
危機管理を一人の担当者に任せきりにすると、危険です。退職や不在時に組織全体が機能不全に陥ります。
属人化は中小企業ほど起こりやすく、組織的なリスクを高めてしまう問題です。
| 想定される失敗 | 改善のための対策 |
| 特定の人しか計画を理解していない | 複数人での役割分担とクロストレーニング |
| 担当者不在で対応が遅れる | マニュアル化と代替要員の設定 |
| 知識が形式知化されていない | 文書化・共有ストレージでの管理 |
危機管理は「属人化を防ぐ仕組み」を整えることが最優先となります。計画を複数人で共有し、代替性を確保しましょう。
初動対応が遅れて被害が拡大
危機発生直後の数分〜数時間の対応で、その後の被害規模は大きく変わります。初動の遅れは情報伝達や意思決定の不備が原因であることが多く、中小企業にとって致命傷になりかねません。
| 想定される失敗 | 改善のための対策 |
| 誰が最初に動くか決まっていない | 初動対応の役割を明確化 |
| 情報伝達が遅れる | 緊急連絡網・チャットツールの活用 |
| 判断が遅れる | 発動基準を具体的に定める |
初動対応を確実に行うには、日常的に「シミュレーション」を行っておくことが不可欠です。訓練によって行動が習慣化されれば、危機の際にも素早く対応できるようになります。
まとめ
危機管理は「大企業だけの課題」ではなく、むしろ限られた人員や資金で事業を継続しなければならない中小企業こそ優先度が高い取り組みです。
また、危機管理は経営層や担当者だけの責任ではなく、全社員が当事者意識を持つことで初めて実効性を持ちます。組織全体で危機に強い文化を育てることが、最終的には企業の信頼やブランドを守り、長期的な成長につながるのです。
中小企業にとって危機管理は「コスト」ではなく「投資」という意識を持ちましょう。日々の事業を守るために、そして予期せぬ出来事に直面したときに事業を止めないために、今こそ一歩踏み出して計画を整備していくことが必要です。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録