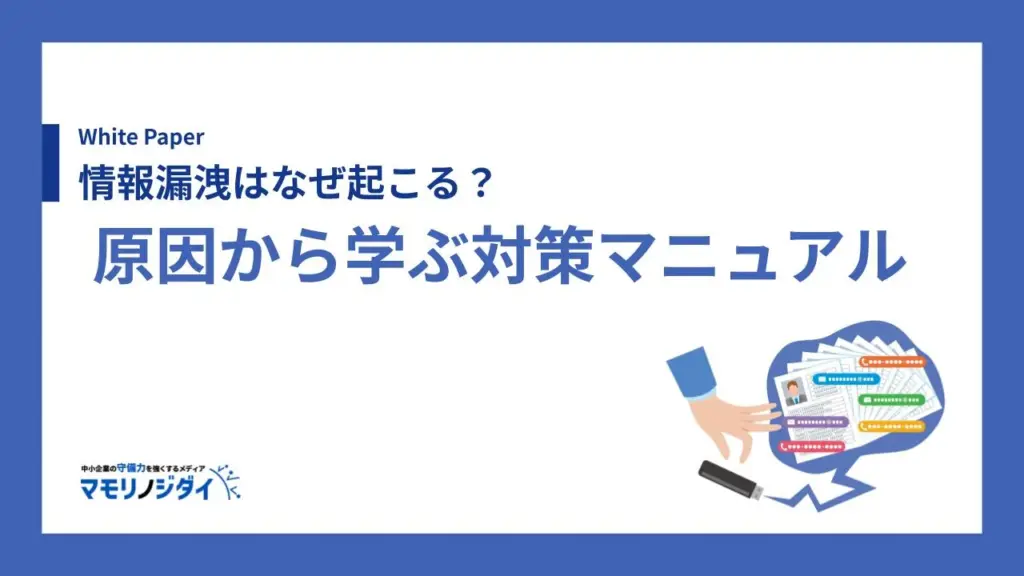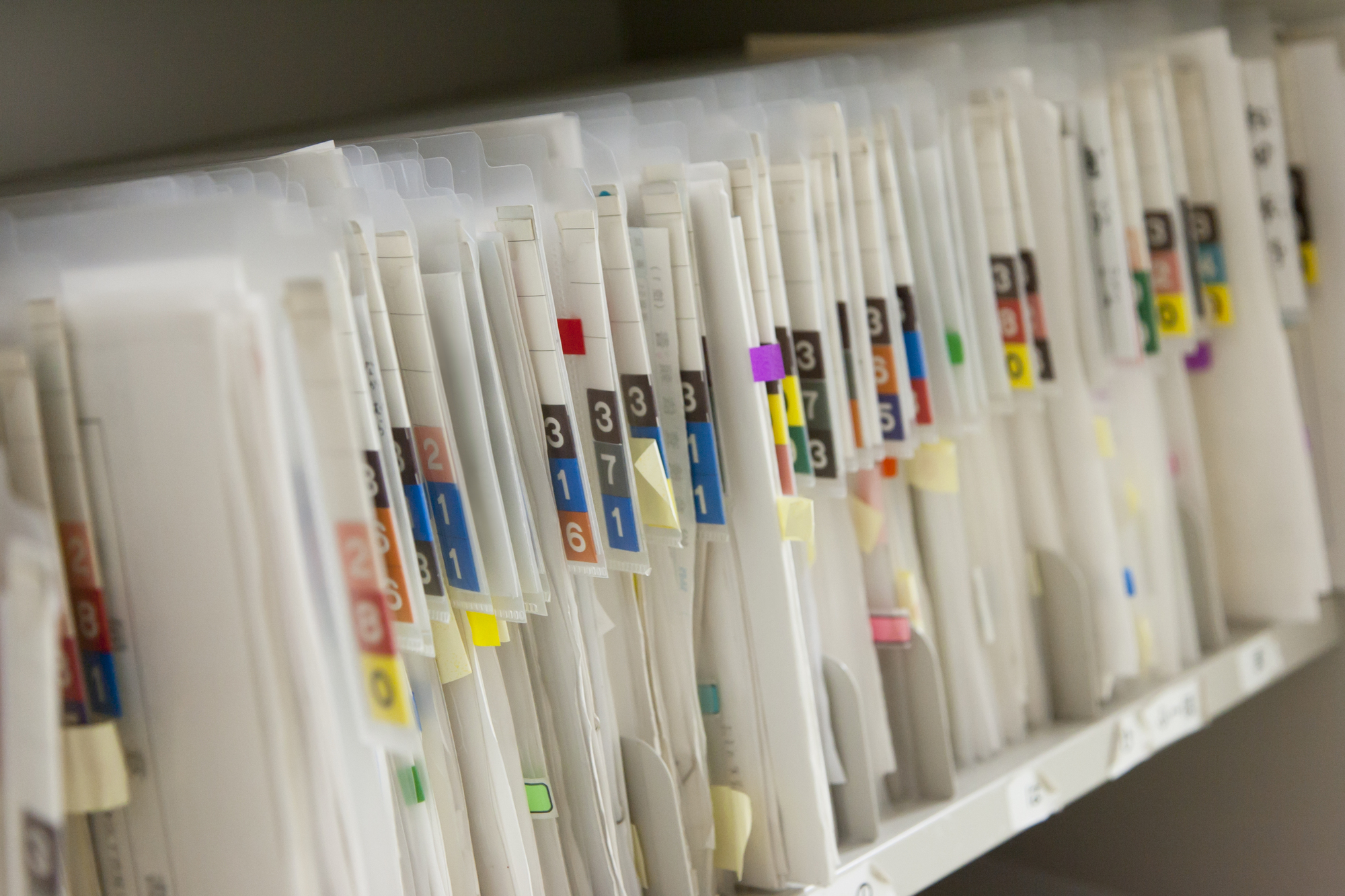UTM(統合脅威管理)は古い?必要ない?中小企業ができる対策をわかりやすく解説

近年、サイバー攻撃の高度化と巧妙化が進むなかで、「UTM(統合脅威管理)」が中小企業の情報セキュリティ対策として注目を集めています。
UTMとは、ファイアウォールやアンチウイルス、迷惑メール対策、Webフィルタリングなど、複数のセキュリティ機能を1台に統合したソリューションです。
一方で、「UTMはすでに時代遅れではないか」「導入したが効果を実感できない」といった声も見られるようになってきました。コストや運用面の課題、クラウドサービスとの整合性など、導入時に注意すべきポイントも少なくありません。
本記事では、UTMの基本的な仕組みから、導入によって得られるメリット、つまずきがちな課題、そして導入前に確認すべきチェックポイントまでを、中小企業の視点でわかりやすく解説します。
またUTMはUTMは顧客情報や個人情報漏えいリスクの低減にも有効です。以下の無料の資料では中小企業の経営層、情報システム担当の方向けに漏えい事故の対策マニュアルを紹介していますので、参考にしてみてください。
目次
UTMとは?一言でわかるセキュリティの新常識
UTM(Unified Threat Management/統合脅威管理)とは、複数のセキュリティ対策を1台の機器でまとめて行える製品・サービスのことです。ファイアウォール、ウイルス対策、迷惑メール対策、不正侵入検知など、従来は別々に導入・管理していたセキュリティ機能を「オールインワン」で提供するのが特徴です。
特に、専任のIT担当者を持たない中小企業では、手間や知識の不足を補いながらセキュリティ水準を底上げできる手段として、UTMの導入が進んでいます。
インターネットの出入口に設置することで、社内ネットワークを通過する通信を一元的に監視・制御する“門番役”です。
これが現場の声!UTM導入で得られる3つのメリット
UTM(統合脅威管理)を導入することで、中小企業が抱えるセキュリティ運用の課題を一気に軽減することが可能です。ここでは、実際の導入現場でもよく挙がる「3つのメリット」をご紹介します。
参考記事:システム監査とは?実施目的・監査基準・手順・IT監査との違いについて解説
セキュリティ対策を“丸投げ”できる安心感
UTMは、ファイアウォール、アンチウイルス、スパム対策、不正侵入検知など、複数のセキュリティ機能を1台に集約して提供する仕組みです。ITの専門知識が乏しい企業でも、複雑な設定やソフトの個別管理をせずに済むようになります。
特に中小企業にとっては、「何をどう守ればよいのか分からない」という不安が大きなハードルとなりがちです。その点、UTMを使えばベンダーやSIerのサポート込みで“セキュリティ対策を一括運用”できるため、経営者や管理部門にとって安心材料となります。
システム費と人件費の“見えないコスト”を削減
複数のセキュリティ製品を個別に導入・運用していると、それぞれに初期費用・更新費・人的管理コストが必要です。UTMを導入すれば、こうした分散したコストを1台に集約できるため、結果的にコスト削減につながります。
また、セキュリティ機器の障害対応やアラート管理などの「見えない運用負荷」もUTMにより軽減され、本来の業務に集中できる時間が増えることもメリットです。
取引先や顧客からの信頼UP
取引先とのやり取りにおいて「セキュリティ体制の有無」は、今や企業評価の大きな判断基準になっています。UTMの導入は、社内のセキュリティ体制をわかりやすく“見える化”できる手段となり、対外的な説明にも有効です。
例えば、RFP(提案依頼書)やコンプライアンスチェックの中で「どのようなセキュリティ対策を講じているか」を問われた際にも、UTM導入を明示することで信頼性の高い企業であることを証明可能です。
UTMで何ができる?1台でセキュリティをフルカバー
UTM(統合脅威管理)で具体的にできることを機能別に紹介します。以下の表では簡単に優先度をまとめました。
| 機能 | 内容 | 導入優先度 |
| ファイアウォール | 外部からの不正アクセスを遮断。基本的な境界防御の要。 | 必須 |
| アンチウイルス | マルウェア・ランサムウェアを検出・駆除。PCやサーバを守る防線。 | 必須 |
| アンチスパム | スパムメールやフィッシングメールを自動的にブロック。 | 必須 |
| IDS/IPS | ネットワーク内部の異常や不正通信を検知・遮断。 | 可能であれば導入 |
| アプリ制御 | 業務外アプリ(例:SNS・ストレージ)の利用を制限。 | 可能であれば導入 |
| SSLインスペクション | HTTPSなどの暗号化通信の中身もチェック可能。 | 可能であれば導入 |
| Webフィルタ | 有害・業務外サイトの閲覧制限やカテゴリ別ブロック。 | 可能であれば導入 |
参考記事:事例から学ぶ!中小企業におけるコンプライアンス違反の落とし穴と対策
それでは、順に紹介しておきましょう。
不正アクセスをブロックするファイアウォール
ファイアウォールは、外部からの不正アクセスを遮断し、社内ネットワークを守る最前線の防御システムです。IPアドレスやポート番号などをベースに通信を制御することで、未知の攻撃やウイルス感染の拡大を防ぎます。
中小企業では、IT担当者が専任でいないケースも多く、日常的な監視が難しいのが実情です。だからこそ、自動でリスクの高い通信をブロックしてくれるファイアウォールは“最小の労力で最大の効果”を発揮できる機能といえます。
外部からの攻撃が増加する今、導入必須のセキュリティ機能です。
ウイルス感染を防ぐアンチウイルス
アンチウイルス機能は、マルウェアやランサムウェアなどのウイルス系脅威を検知・駆除する対策です。ファイルの読み取りやダウンロード時にスキャンを行い、感染前に脅威を排除します。
特にランサムウェアは中小企業を狙った被害が急増しており、社内ファイルや顧客データが一斉に暗号化されるケースも少なくありません。アンチウイルスは、そうしたリスクを未然に防ぎ、業務停止を回避するための“生命線”です。
PCだけでなく、サーバやメールなど広範囲にわたる監視が可能な点もポイントといえます。
迷惑メールを自動で弾くアンチスパム
アンチスパムは、スパムメールやフィッシングメールを自動で判定し、受信箱に届かないように振り分ける機能です。怪しい送信元やURLを含むメールを遮断することで、従業員が誤ってクリックしてしまう事故を防ぎます。
特に中小企業では、情報セキュリティ教育が行き届かないこともあり、一通の偽メールが大きな情報漏洩につながるリスクがあります。アンチスパムはそうした人的ミスを技術的に補完してくれる、“現場任せにしない”堅牢な仕組みです。
さらに、業務に関係のないメールが減ることで、作業効率向上にもつながります。
侵入者を見張るIDS/IPS
IDS(侵入検知システム)やIPS(侵入防止システム)は、ネットワーク内を流れる通信内容をリアルタイムで監視し、異常な動きを検知・遮断する仕組みです。これにより、マルウェアや内部不正など、ファイアウォールをすり抜けた攻撃にも対応できます。
例えば、社内PCが不正サイトと通信していた場合、それを即座に検知して遮断することで、感染拡大やデータ漏洩の被害を最小限に抑えることが可能です。やや専門的な設定が必要なため、ITスキルのある管理者がいる中堅企業以上におすすめですが、セキュリティの成熟度を高めるには欠かせない機能といえます。
危険なサイトへの接続を遮断するWebフィルタ
Webフィルタは、特定カテゴリ(例:アダルト・ギャンブル・掲示板など)のサイトや、不審なドメインへのアクセスを制限する機能です。カテゴリ単位やURL単位で制御が可能で、従業員が業務に関係のない、または危険なサイトへアクセスするのを未然に防ぎます。
特に教育機関・医療機関・行政などでは、セキュリティレベルが高く求められますが、一般企業でも情報漏洩リスクや社内の生産性低下を抑止する手段として有効です。ユーザー単位でのポリシー設定も可能なため、役職や部署に応じた柔軟な制限運用ができます。
業務外アプリの使用を制限するアプリ制御
アプリ制御は、LINEやYouTube、Dropboxなどの業務外アプリケーションの使用を制限できる機能です。情報漏洩や業務中の私用を防ぐため、社内統制の強化に直結します。
例えば、無料のファイル転送サービスを通じて機密ファイルが流出した…といったケースも、アプリ制御で事前に防ぐことが可能です。
技術的な制限でリスクを可視化・管理できるため、セキュリティポリシーを形骸化させずに運用できます。
暗号化通信もチェックできるSSLインスペクション
SSLインスペクションは、HTTPSなどで暗号化された通信内容を一時的に復号し、内部に潜むウイルスや不正通信を検知する技術です。従来の対策では“ブラックボックス”だった暗号通信を可視化できるため、近年の高度なマルウェアやC&C通信にも対応できます。
ただし、一部のクラウドサービスや金融系Webサイトとの相性に注意が必要で、証明書の管理や例外設定など、やや高度な運用が求められる機能です。中小企業で導入する場合は、ベンダーによる設定サポートやテスト導入がある製品を選ぶと安心できます。
UTMの導入・運用を検討する前に注意点を押さえておきましょう。特にリソースに限りのある中小企業においては、事前に以下のような“落とし穴”を理解しておくことで、導入後のトラブルや無駄なコストを回避することが可能です。
業務ツールが“誤検知”されることがある
UTMはセキュリティの観点から、さまざまな通信を自動で検知・制御します。そこで、一部の業務用クラウドツールやSaaSが“誤ってブロック”されるケースに注意が必要です。
例えば、Google DriveやZoom、Slackなど、業務上欠かせないツールが「不審な挙動」と誤認識されて遮断されると、業務が一時的に停止するリスクもあります。特にSSLインスペクション機能を有効化している場合に発生しやすく、導入時には「許可リスト(ホワイトリスト)」の設計と、事前の通信テストが重要です。
回線速度が遅くなるケースもある
UTMはすべての通信をスキャン・分析するため、処理内容によってはネットワーク速度に影響を与える場合があります。特に、低スペックなモデルを選んだ場合や、同時接続数が多い時間帯には体感速度の低下を招くことがリスクです。
この問題を防ぐには、社内の通信量・業務ツールの使用状況を事前に把握したうえで、スペックに余裕のある機種を選定することが肝要といえます。また、必要に応じてアンチウイルスやSSLインスペクションなど一部機能のスキャン対象を限定し、ボトルネックを回避する設定調整も検討すべきです。
導入後の“放置”がセキュリティホールに
UTMは「導入して終わり」の製品ではありません。定期的なファームウェアのアップデートや、脅威パターンの更新、ログ監視、ポリシーの見直しなど、継続的な運用が求められます。
しかし、中小企業ではIT専任者が不在だったり、日常的な運用体制が整っていなかったりするケースも少なくありません。これにより、脆弱性が放置されたままになってしまう“形骸化”リスクが生じます。
対策としては、運用まで含めたマネージド型(設定・監視をベンダーが代行)プランの活用や、アラート通知機能の活用による早期対応体制の整備が有効です。IT人材の負担を増やさずにセキュリティレベルを維持できる体制設計が重要になります。
後悔しないためにUTM導入前に確認したい3つのチェックポイント
UTM(統合脅威管理)は便利な一方、すべての企業にとって“万能”とは限りません。導入後に「思っていたより効果がない」「業務に支障が出た」といった事態を避けるために、以下の3つの視点での事前チェックをしましょう。
参考記事:情報セキュリティの3要素とは?中小企業が気を付けるべきことも解説
本当に必要な機能はどれ?
UTMにはファイアウォール、アンチウイルス、アンチスパム、Webフィルタ、アプリ制御、SSLインスペクションなど多数の機能が搭載されています。自社にとっては「必要最低限」かつ「過不足のない構成」を見極めることが重要です。
例えば、社内に独自のファイルサーバを設けておらず、ほとんどの業務をクラウド上で完結している企業であれば、アンチウイルスよりもWebフィルタやSSLインスペクションの方が優先度が高いケースもあります。
「なんとなく全部入り」で導入してしまうと、運用負荷やコストが過剰になることがリスクです。ベンダーとのヒアリング時には具体的な業務内容・リスクシナリオを提示したうえで、機能の要否を確認することが推奨されます。
社員数・ネットの使い方に合ってる?
UTMはモデルやスペックによって、対応できる最大ユーザー数・通信量・処理能力が異なる点を覚えておきましょう。実際、社員数10名未満の企業と100名規模の企業では、必要とされる性能も大きく変わります。
例えば、複数拠点で同時にクラウドツールを活用している場合、低スペックモデルでは回線遅延が発生しやすくなることがリスクです。逆に少人数で、セキュリティ強度を優先したい場合は、高機能よりも安定性・運用性に優れたモデルを選ぶ方がコスト効率が良いこともあります。
自社の社員数・回線契約・利用している業務アプリの種類と頻度を棚卸ししたうえで、モデルスペックとのマッチングを図りましょう。また、導入前に無料の体験版などを利用して、実際の業務環境での動作検証を行うことがおすすめです。
いざという時に対応してくれるサポートはある?
セキュリティ製品は「入れて終わり」ではなく、トラブル対応・設定変更・アップデート対応など、運用段階での支援が欠かせません。
中小企業では専任のIT担当者が不在のケースも多く、「急にネットに繋がらなくなった」「重要なWebサービスがブロックされた」などの緊急時にサポートがないと業務が止まってしまうリスクがあります。
導入前には、以下のような項目を確認しておくと安心です。
- 設定や運用に関するサポート体制(電話・チャット・メールの有無)
- トラブル発生時の初動対応時間(SLA)
- 機器交換時の対応(オンサイト対応・代替機の有無)
- マネージド型プランの有無(設定・監視をベンダーが代行)
「技術支援込み」の提案かどうかも、価格だけでなく検討材料の一つとして重視しましょう。
まとめ
機能だけでも、最低限のサイバー攻撃対策として有用です。
ただし、UTMは決して万能ではありません。機器のスペック不足による回線速度の低下や、誤検知による業務影響、さらには導入後の放置によるセキュリティホールなど、注意すべき点も少なくありません。
そのため、自社にとって本当に必要な機能は何か、利用人数やネット環境との相性、ベンダーのサポート体制など、導入前のチェックポイントを丁寧に見極めることが重要です。
セキュリティ対策は「コスト」ではなく「未来への投資」です。限られた予算の中でも、適切なUTMを選定し、適切に運用していくことで、将来の被害リスクを大幅に軽減できます。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録