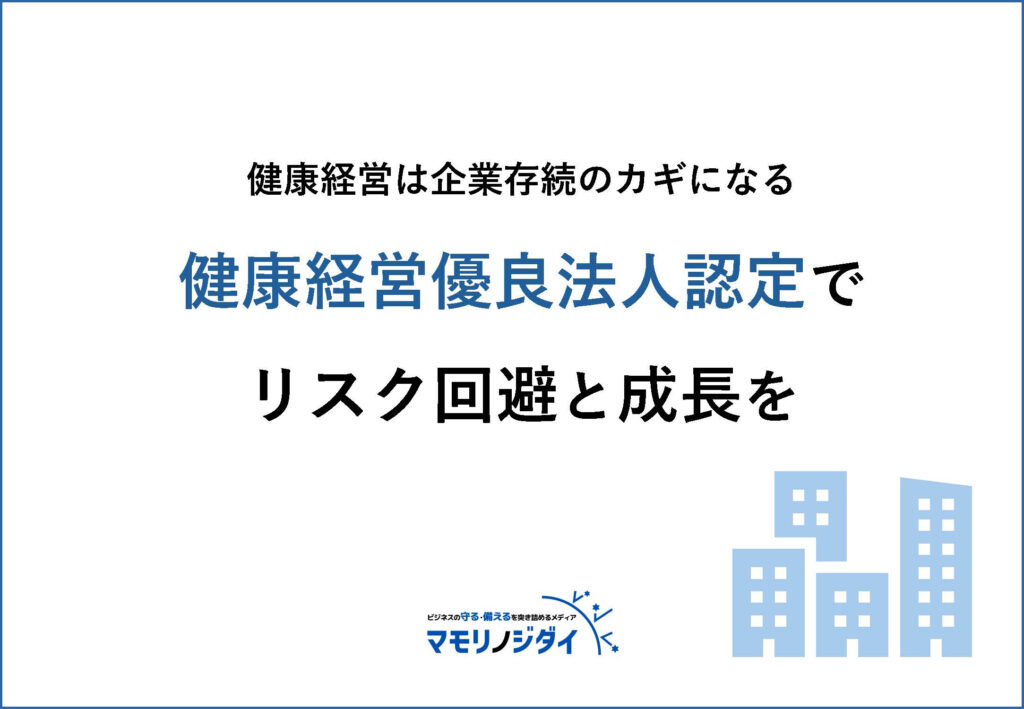ホワイト500とは?中小企業にメリットはある?認定要件・申請方法など

これは、従業員の健康管理を経営課題として捉え、戦略的に推進している法人を国が認定する仕組みです。経済産業省と日本健康会議が共同で運営しています。
この記事では、ホワイト500の概要やブライト500との違い、認定要件や申請手順、実際のメリットまで、中小企業の視点でわかりやすく解説します。「制度が気になるが何から手を付ければいいかわからない」と感じている方にとって、第一歩となる内容です。
また以下の資料では「健康経営優良法人認定」の効果や申請方法、メリットを紹介していますので、ぜひ無料でダウンロードしてご覧ください。
目次
ホワイト500とは?中小企業にも関係あるの?
「健康経営優良法人(ホワイト500)」制度は、従業員の健康管理を経営の視点から戦略的に捉える“健康経営”を優れた形で実践している法人を国が認定する仕組みです。
大企業を中心とした「大規模法人部門」と、中小企業等を対象とした「中小規模法人部門」という2つの部門があります。
つまり「中小企業には関係ない」というわけではありません。中規模・小規模の法人も制度対象となっており、自社の体制を整えるうえで活用できる制度設計の枠組みとして見直す価値があります。
例えば、認定取得が最終目的ではなく、まずは「健康経営に向けた実践プロセスを整備すること」そのものが、中小企業にも大きな意味を持つのです。
「健康経営」とは?制度の背景を簡単に解説
「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践していく考え方を指します。
これは、単に福利厚生の一環として健康診断や予防施策を行うのではなく、従業員の健康維持・増進を企業の生産性や持続可能性に直結する経営課題として扱う姿勢が特徴です。
企業に対しては「健康経営度調査」という統一基準の調査票を通じて取組状況を可視化し、優良法人を「健康経営優良法人」として認定しています。
背景としては、少子高齢化による労働人口減少、医療費の増加、労働災害やメンタルヘルスへの対応強化といった社会課題に企業が主体的に関与することが求められている点です。従業員の健康は、企業にとって“守り”の要でもあり“攻め”の競争力にもつながる資産と位置づけられています。
ホワイト500とブライト500の違い
ホワイト500とブライト500の違いは以下の表の通りです。
| 項目 | ホワイト500 | ブライト500 |
| 対象区分 | 大規模法人部門(主に上場企業など) | 中小規模法人部門 |
| 法人数の上限 | 上位500法人 | 上位500法人(中小企業のうち特に優良な企業) |
| 評価基準のベース | 健康経営度調査の評価スコア | 健康経営度調査+地域での活動・発信実績 |
| 特徴 | 社会的影響力・情報発信力が重視される | 地域との連携やロールモデル性が評価される |
| 情報発信に対する評価 | 必須ではないが積極性が加点対象になる | 情報公開・啓発活動が選定に強く影響する |
| 中小企業との関係 | 直接的な対象ではないが参考にはなる | 中小企業が申請・認定対象となる |
ホワイト500は「大規模法人部門」の中で、健康経営度調査の評価が特に高い上位500社に与えられる称号です。そのため、社会的な影響力や制度としての先進性、対外的な信頼度の高さが求められます。
一方でブライト500は、「中小規模法人部門」の認定法人の中から、特に地域に根ざした活動や健康経営の積極的な情報発信を行っている中小企業を選出する仕組みです。単にスコアが高いだけでなく、外部への好影響や地域貢献度が重視されます。
中小企業が目指す場合、ホワイト500は制度的に直接申請できませんが、ブライト500は積極的にチャレンジ可能な制度です。
ホワイト500の認定要件とは?
「ホワイト500(健康経営優良法人・大規模法人部門)」は、従業員の健康増進や働きやすい環境づくりに取り組む優良企業を、経済産業省と日本健康会議が共同で認定する制度となります。認定を受けるには、一定の企業規模と健康経営に関する取り組みの水準を満たすことが必要です。
大規模法人の条件(従業員数・保険加入状況など)
「ホワイト500」の対象となる大規模法人とは、次のような要件を満たす企業となります。
- 保険者が実施する「健康経営度調査」に回答していること
- 原則として従業員数が301人以上(中小企業向けには「ブライト500」など別制度あり)
- 健康保険組合、共済組合、全国健康保険協会などの保険者に加入していること
- 労働安全衛生法などの法令を遵守していること
また、企業単位だけでなく、医療法人や教育機関なども対象です。
評価項目は5つの観点でチェックされる
ホワイト500の認定審査では、「健康経営度調査」の回答をもとに、以下の5つの観点から評価が行われます。
| 項目 | 内容 |
| 経営理念・方針 | 経営者が健康経営を明文化し、社内外に発信しているか。 |
| 組織体制 | 健康経営推進のための担当者や委員会の設置状況など。 |
| 制度・施策実行 | 定期健康診断、メンタルヘルス対策、長時間労働抑制などの取り組み。 |
| 評価・改善 | 施策の成果指標(KPI)を設定し、継続的な改善が図られているか。 |
| 法令遵守・リスクマネジメント | 労働関係法令の遵守、ハラスメント対策、感染症対策など。 |
これらの項目は、単に制度があるかどうかではなく、「実際に機能しているかどうか」や「従業員の健康状態が改善しているか」など、実効性が重視される仕組みです。
参考記事:中小企業で生活残業が発生しやすい原因は?やめさせるための対策を紹介
ホワイト500認定の流れとスケジュール
ホワイト500(健康経営優良法人・大規模法人部門)に認定されるまでには、主に次の3つのステップを踏む必要があります。いずれも、経済産業省が指定するスケジュールに沿って進める必要があり、十分な事前準備が重要です。
Step1:健康経営度調査への回答
ホワイト500の認定を目指す最初のステップは、「健康経営度調査」への回答です。
この調査は、経済産業省と日本健康会議が主導して実施するもので、企業がどの程度健康経営に取り組んでいるかを可視化し、評価するための基礎資料となります。
調査項目は、経営理念への健康経営の位置付けや、組織体制の整備、制度設計と運用、情報開示など多岐にわたるのが特徴です各項目に対する自己評価をオンラインで回答しましょう。
この調査への回答は、ホワイト500申請に必須の条件であり、未回答の場合は申請そのものができません。
参考記事:社員のエンゲージメントを高めるには?言葉の意味・測定方法・向上施策など
Step2:フィードバックシートの確認・申請準備
健康経営度調査に回答すると、後日、回答内容をもとに分析されたフィードバックシートが企業ごとに提供されます。
これは、自社の健康経営の成熟度を客観的に把握できるものです。各評価領域における得点や全国平均との比較が記載されています。
このフィードバックをもとに、自社の取り組みの強みや弱みを見直し、必要に応じて改善策を講じることが重要です。また、ホワイト500の認定に向けては、このタイミングで正式な申請準備を開始します。
Step3:申請書提出〜認定審査の進み方
フィードバックシートを確認し、社内準備が整ったら、次はホワイト500の本申請に進みましょう。申請期間は通常、12月上旬から下旬にかけて設けられ、専用のWebシステムを通じて申請書類を提出します。
審査では、健康経営度調査のスコアが一定基準を満たしていることに加えて、申請書の記載内容と裏付け資料の整合性、組織全体での取り組みの実効性などが多角的にチェックされるのが特徴です。
特に、取り組みが単なる形式的なものではなく、経営層が主導して全社的に実施されているかどうかが重視されます。
ホワイト500認定のメリットとは?
ホワイト500の認定を受けることは、単なる企業アピールにとどまりません。社内外に多くの好影響をもたらします。
認定取得に向けた取り組みを通じて、従業員の健康意識を高め、定着率を向上させるだけでなく、採用活動や企業ブランディングにも効果があるものです。
以下で、その具体的なメリットについて解説します。
従業員の健康意識・定着率アップにつながる
ホワイト500の取得を目指すことで、企業は従業員の健康管理に本格的に取り組むことが必要です。定期健診の受診率向上やストレスチェック制度の整備、社内での運動促進や食生活改善など、日々の業務に健康を意識した施策が組み込まれるようになります。
こうした環境が整えば、従業員のモチベーションやエンゲージメントが高まることがメリットです。離職率の低下にもつながります。
また「健康に配慮してくれる会社で働いている」という安心感が、長期的なキャリア形成を考える上での企業選びの要素にもなるものです。
参考記事:月30時間の残業は従業員にとってきつい?企業側の注意点や取るべき対策
採用ブランディングや対外的評価にも効果あり
ホワイト500に認定されている企業は、就職活動中の求職者や転職希望者にとっても魅力的な存在です。「従業員を大切にする会社」としてのメッセージが強く伝わるため、採用活動におけるブランド価値の向上が期待できます。
加えて、経済産業省の認定を受けているという信頼性の高さから、取引先や投資家からの信用力も増し、競合との差別化にもつながります。健康経営を企業戦略の一部として明確に打ち出すことで、「働きやすい職場」をアピールできる点は、今後の人材確保にも大きな利点となるでしょう。
ESG投資や金融機関からの評価にも影響
ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の文脈では、企業の「人的資本」に対する取り組みが重視されつつあります。
ホワイト500の認定を受けた企業は、従業員の健康や働きやすさを重視する経営体制が整っていると見なされ、ESG投資家からの注目を集める可能性が高まるのです。実際に、金融機関によっては健康経営を実践している企業に対して、金利の優遇や融資審査での加点を行う事例も出てきています。
中小企業にとってのホワイト500の活用ポイント
ホワイト500は大企業向けの制度として設計されている一面もありますが、中小企業にとっても参考にすべき点は多く存在します。
たとえ実際に認定を目指さなかったとしても、その評価項目や制度の設計思想には、企業経営や組織づくりに応用できるヒントが詰まっているのが特徴です。
以下では、中小企業がホワイト500を有効活用するための視点を解説しましょう。
「ホワイト500を目指す過程」にこそ価値がある
ホワイト500の認定を取得するかどうかにかかわらず、その過程で求められる取り組み自体が、中小企業にとって非常に価値あるものです。
例えば、健康診断の受診率を上げる工夫や、ストレスチェックの結果を踏まえた職場改善、メンタルヘルスに関する社内相談窓口の整備などは、制度の有無に関係なく重要な施策といえます。
ホワイト500はあくまで「目指すべき姿」のひとつと捉え、認定そのものにこだわらず、自社に合った改善サイクルを確立していくことが大切です。
「健康経営度調査」をセルフチェックに使う
ホワイト500の認定には、経済産業省が実施する「健康経営度調査」への回答が前提となります。この調査票には、健康方針の有無や実行体制、具体的な施策、成果の測定など、企業の取り組みを多角的に問う設問があることが特徴です。
中小企業にとっても、この調査票を活用することで、自社の健康経営における現状と課題を客観的に把握できます。 例えば「経営層が健康課題を把握しているか」「組織として数値目標を持っているか」「従業員の声を施策に反映できているか」といった問いは、企業規模にかかわらず重要なチェックポイントです。
経営層への説明資料としての活用
ホワイト500は、経営層に健康経営の重要性を理解してもらうための「共通言語」としても活用できます。特に中小企業では、目の前の売上やコストに目が向きがちで、従業員の健康や職場環境への投資が後回しになることが、よくある傾向です。
そのような状況下で、「国が制度として健康経営を推奨していること」「実際に認定企業では生産性向上や離職率改善につながっていること」を伝えることは、施策の後押しとして非常に効果的です。また、調査票や評価指標をもとに、具体的に何から着手できるのかを説明することで、経営陣の理解と巻き込みを促すことができます。
ホワイト500に「意味がない」と言われる理由は本当?
ホワイト500は、経済産業省と日本健康会議による健康経営優良法人認定制度として、多くの企業から注目を集めています。しかし一方で、「ホワイト500は意味がない」「実態を反映していない」といった批判的な声があるのも事実です。
ここではその背景と中小企業にとっての活用のヒントを解説します。
「形骸化している」「実態と違う」といった批判の背景
ホワイト500に対する批判としてよく聞かれるのは、「認定を受けた企業が本当に働きやすい職場であるとは限らない」「外向けのアピールだけで、中身の改革が伴っていない」といった声です。
ただし、これは制度の欠陥というよりも、活用の仕方や運用姿勢の問題です。制度を「取得すること」が目的になってしまえば、当然中身が伴わないまま表面だけを整える企業も出てきます。
一方で、真摯に自社の健康経営に取り組んでいる企業にとっては、制度が進化するきっかけにもなり得るため、批判だけで制度の価値を否定すべきではありません。
「ホワイト企業=ホワイト500」とは限らない理由
「ホワイト500に選ばれているから、あの会社は間違いなくホワイトだ」と考えるのは早計です。
ホワイト500の認定はあくまで健康経営に関する一定の基準を満たしたことを示すものであり、労働時間、賃金、休暇制度、上司との関係性など、従業員の職場満足度全体を包括的に保証するものではありません。つまり、「ホワイト企業」と呼ばれるために必要な他の要素までは直接評価されていないのが現実です。
このため、ホワイト500=理想的な職場と短絡的に結びつけるのではなく、「一つの取り組み指標」として見るのが健全なスタンスです。
例えば、健康診断やストレスチェックといった具体的な施策が整っていることは認定の条件ですが、それが即、従業員の幸福や働きやすさに直結しているとは限りません。制度の「限界」を正しく理解したうえで、他の指標と組み合わせて職場改善を図ることが重要です。
中小企業が「参考にすべき指標」として活用する視点
ホワイト500に対して批判的な意見があるのは事実ですが、中小企業にとってはむしろ「健康経営をどう始めればよいか」を学ぶ参考材料になります。
特に、健康経営度調査票の設問項目や評価基準は、自社の現在地を把握し、改善のヒントを得るうえで非常に有効です。また、ホワイト500認定企業の取り組み事例は、無料で多数公開されており、中小企業でも実践可能な工夫を学ぶことができます。
例えば、「有給取得率の目標設定」や「メンタルヘルス相談体制の整備」「朝礼での健康情報共有」といった比較的取り組みやすい施策が多く含まれているため、リソースに限りがある中小企業でも段階的に導入可能です。
まとめ
ホワイト500は、企業の健康経営への取り組みを「見える化」し、内外にアピールできる仕組みとして注目を集めています。特に近年では、人的資本経営やESG投資への関心が高まる中、従業員の健康を経営課題として捉えることが、企業の成長戦略においても重要な位置づけです。
一方で、「取得そのもの」が目的化してしまい、本来の価値が十分に活かされていない企業も少なくありません。大切なのは、認定をゴールとするのではなく、「ホワイト500を目指す過程」や「健康経営度調査の観点」を、自社の実態を見つめ直すツールとして活用することです。
中小企業にとっては、制度そのものへの申請は難しい側面もありますが、調査項目や評価観点を自社の改善指標として活かすことは十分に可能です。経営層の理解促進や、従業員の定着・エンゲージメント向上にもつながるため、実務での活用価値は高いといえるでしょう。
ホワイト500は「ラベル」ではなく「気づきのきっかけ」として捉え、自社なりの健康経営のあり方を探るためのヒントとして、柔軟に活用していくことが重要です。
以下の資料では「健康経営優良法人認定」の効果や申請方法、メリットを紹介していますので、ぜひ無料でダウンロードしてご覧ください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録