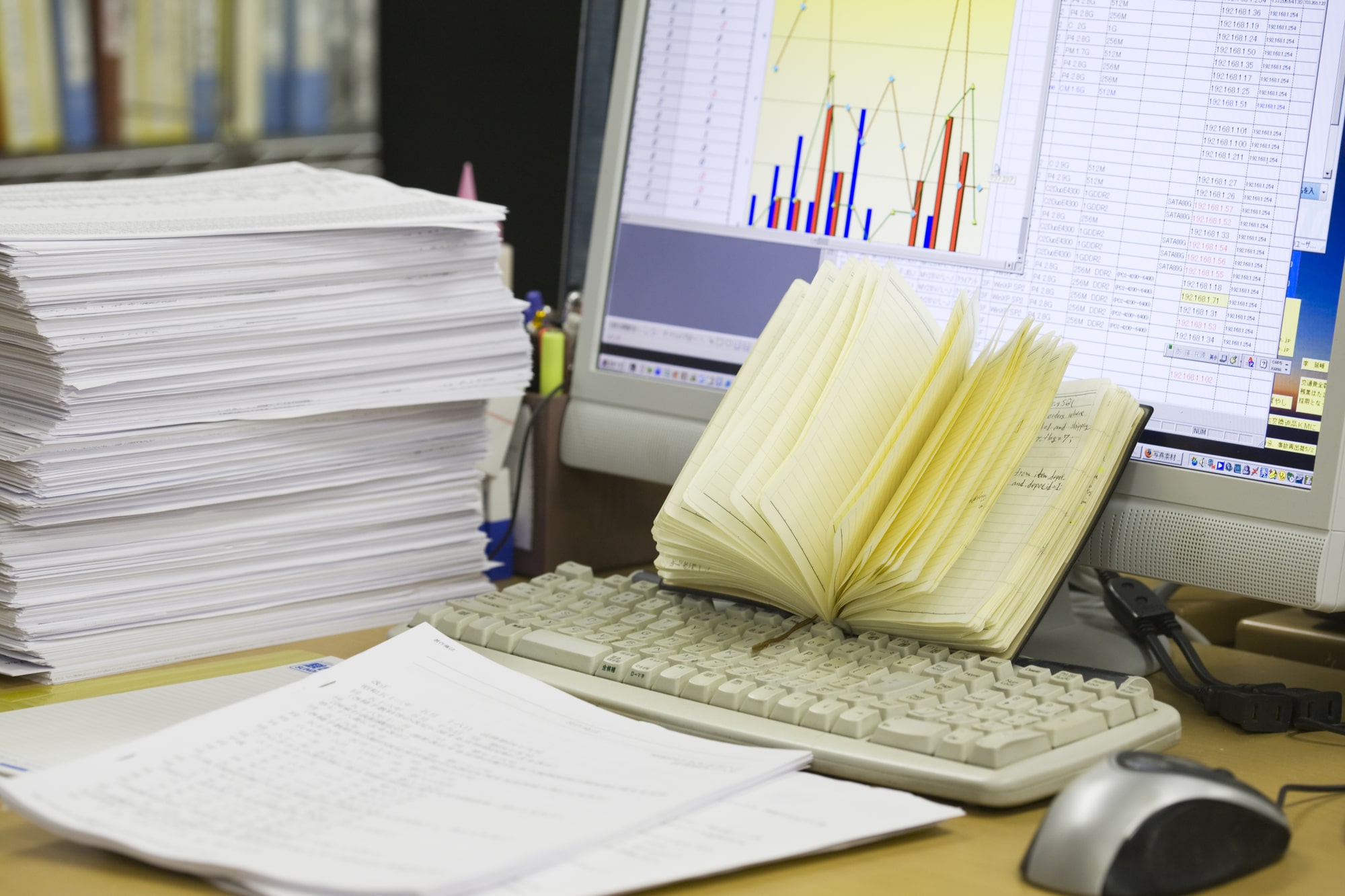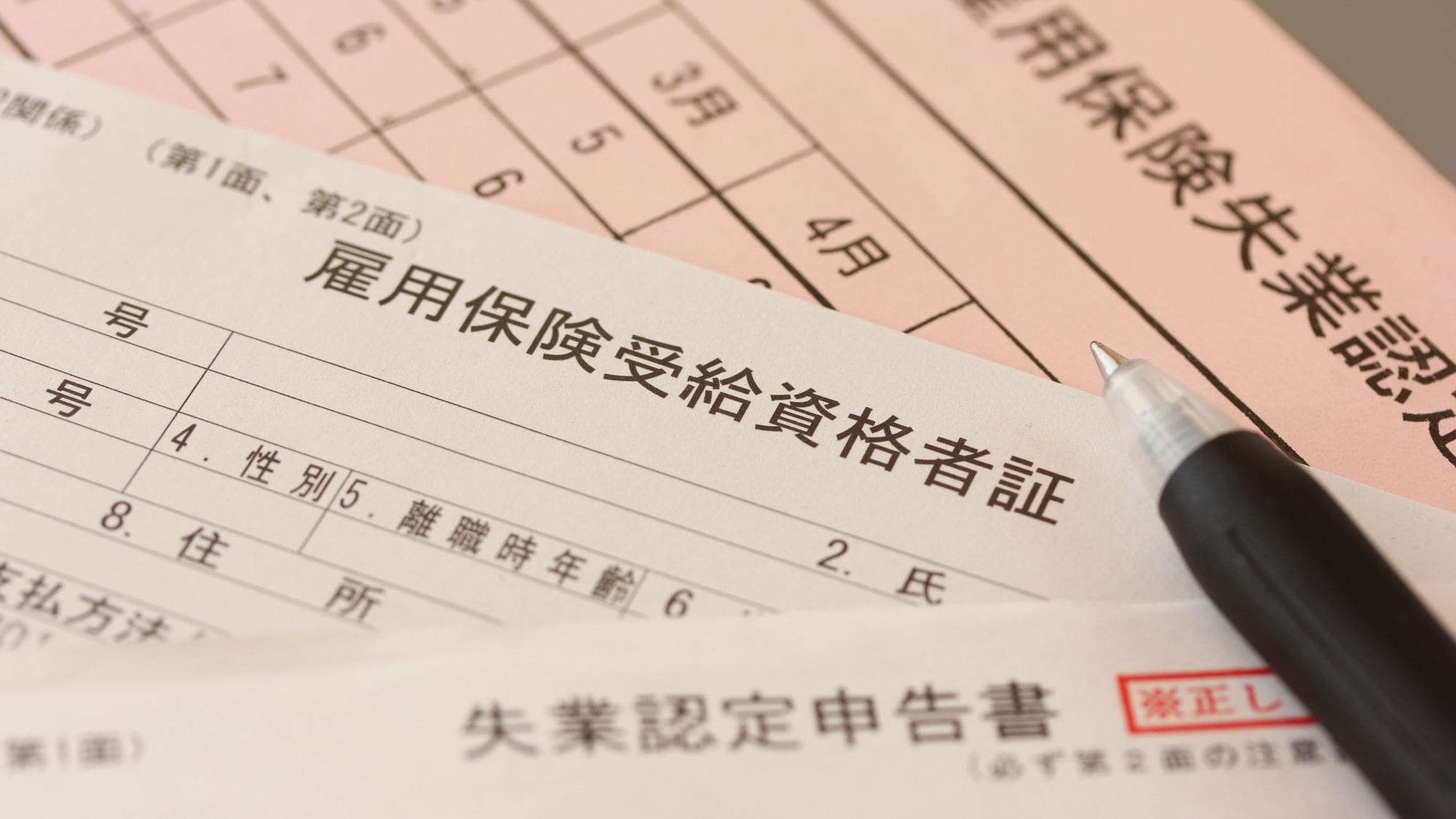オンライン面接のマナー完全ガイド|服装・背景・通信環境・場所の注意点

しかしオンライン面接は、「移動時間や交通費がかからない」というメリットがある一方で、対面とは勝手が違うため、「どのような服装が適切か」「特有のマナーはあるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
気軽に実施できるように思えるオンライン面接ですが、画面越しであっても、服装には配慮すべきですし、「どんな背景を設定するか」「通信環境に問題はないか」といった点も評価に影響する可能性があります。
そこでこの記事では、オンライン面接で意識すべき重要なマナーについて、服装、背景、適切な場所選び、機材の確認といった観点から徹底的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
オンライン面接とはどんなもの?
オンライン面接は、Web面接とも呼ばれ、パソコンやスマートフォンなどのデバイスを使用し、インターネット経由で行われる面接形式を指します。
「Zoom」「Microsoft Teams」「Google Meet」といったWeb会議ツールを利用して、求職者と面接官がリアルタイムでコミュニケーションを取るのが一般的です。
オンライン面接は、コロナ渦以降急速に普及が進み、2025年現在では多くの企業で採用選考のスタンダードな方法として用いられています。
求職者にとっては、企業へ訪問するための移動時間や交通費が不要になるメリットがあります。
企業側も、遠方の優秀な人材と接点を持ちやすくなるなど、オンライン面接は双方にとって効率的な選考方法として広く活用されています。
オンライン面接と対面面接の違い
オンライン面接と対面面接の最も大きな違いは、「コミュニケーションの質」です。
特に、表情やジェスチャーといった「非言語コミュニケーション」の伝わりやすさに違いがあります。
対面の面接では、求職者が部屋に入室してから退室するまでの一連の所作、姿勢、全身の雰囲気、細かな視線の動きや表情の変化、身振り手振りなど、非常に多くの情報が面接官に伝わります。
熱意や人柄といった「その場の空気感」も共有しやすいため、双方向の意思疎通がスムーズに行われるでしょう。
一方でオンライン面接は、パソコンやスマートフォンの画面(多くは上半身のみ)という限られた情報でやり取りを行います。
そのため、対面と同じ感覚でいると、熱意が伝わりづらくなってしまう可能性があります。
オンライン面接の際は、対面面接の時以上に意識的に表情を豊かにして、「相槌を大きく打つ」「ジェスチャーをカメラに映る範囲で少し大きめに行う」といった工夫をすべきです。
オンライン面接で意識すべきマナー
オンライン面接は自宅などで受けられるため、対面よりも気軽だと感じられるかもしれません。
しかし、画面越しであっても、面接官は「求職者のビジネスマナー」や「どれだけしっかりと準備しているか」などを厳しく評価しています。
この項目では、オンライン面接の際に気を付けるべきマナーについて解説していきます。
見えないからといってラフな服装で臨まない
「画面に映る上半身だけ整えればよい」という考えは非常に危険です。
オンライン面接であっても、服装は対面面接の基準に合わせるのが原則となります。
企業から特に指定がない限り、スーツ(または業界に合わせたオフィスカジュアル)を着用しましょう。
不意に立ち上がって書類を取る際など、下半身が映り込む可能性はゼロではありません。
だらしない印象を与えないよう、上下ともに整えておくのが賢明です。
また、画面越しでは、シャツのしわや寝ぐせなどの清潔感に関わる部分が、対面以上に目立ってしまうことがあります。
画面映りを事前にチェックし、身だしなみには細心の注意を払ってください。
服装自由と指示された場合でも、Tシャツやパーカーは避け、襟付きのシャツを選ぶなど、面接の場にふさわしい節度ある服装を心がけましょう。
背景がすっきりするように片づけておく
面接中、求職者の背景は常に面接官の視界に入ります。
散らかった部屋や、洗濯物などの生活感のある私物が映り込んでいると、「準備不足」「だらしがない」といったマイナス評価につながりかねません。
最も望ましい背景は、白や無地の壁です。
もし適切な壁がない場合は、カーテンを閉めるなどして、背景をシンプルに保つ工夫をしてください。
バーチャル背景の使用については、企業によって賛否が分かれるため注意が必要です。
PCのスペックによっては顔の輪郭が不自然に途切れたり、動きに遅延が生じたりする場合があります。
やむを得ず使用する場合は、無難なオフィス風や無地の画像を選び、必ず事前にテストしておきましょう。
ただし、可能な限り、そのまま映っても問題ないように整理整頓しておくことが最善の策です。
事前に通信環境やイヤホンの状態を確認しておく
オンライン面接において最も注意すべきなのは、通信トラブルです。
面接が途中で中断してしまうと、準備不足と判断されるだけでなく、伝えたいことも伝えられなくなってしまいます。
必ず、安定したインターネット接続が可能な環境を確保してください。
自宅以外でオンライン面接を受ける場合に、公衆Wi-Fiを利用しようと考える方もいるかもしれませんが、通信が不安定である上、セキュリティの観点からも面接での使用は避けるべきです。
また、使用するWeb会議ツールが初めての場合は、事前にアカウント作成やアプリのインストールを済ませ、必ず接続テストを行ってください。
可能であれば、家族や友人に協力してもらい、音声や映像の映り方をリハーサルしておくと万全です。
イヤホンを使用する場合は、事前に「問題なく使用できるか」について確認しておきましょう。
なお、ワイヤレスイヤホンは充電切れや接続不良のリスクがあるため、有線のイヤホンを使うべきです。
静かな環境で面接を受けられる場所を選ぶ
面接中に雑音が入ると、会話の妨げになり、お互いの集中力を著しく削いでしまいます。
面接は、静かでプライバシーが確保できる場所で受けるようにしてください。
自宅が最も望ましいですが、その場合でも注意が必要です。
家族や同居人がいる場合は、面接中であることを事前に伝え、静かにしてもらうよう協力を仰ぎましょう。
テレビの音、ペットの鳴き声、洗濯機や掃除機などの家電の動作音など、想定される雑音は極力排除しておく必要があります。
もし自宅でのオンライン面接の実施が難しい場合は、コワーキングスペースの個室ブースや、防音設備が整ったレンタルスペースの利用も選択肢となります。
カフェやファミリーレストランなどのオープンスペースは、周囲の雑音や情報漏洩のリスクがあるため、面接の場としてはふさわしくありません。
オンライン面接はスマホでも問題ないか?
企業から「スマートフォン可」という指定がない限り、パソコン(PC)を使用してオンライン面接に臨むことを強く推奨します。
スマートフォンでの面接には、以下のようなデメリットが存在するからです。
- 画面が小さいためお互いの表情が伝わりにくい
- 共有された資料が読みづらい
- 通知音や着信音が邪魔になることがある
- バッテリー切れを起こす可能性がある
これらのデメリットに対し、PCは画面が大きく安定しており、多くの場合、通信もスマホより安定しています。
面接官の表情をしっかり確認でき、資料共有にもスムーズに対応可能です。
やむを得ずスマートフォンを使用する場合は、必ず固定スタンドで目線の高さにカメラを固定してください。
また、「機内モード」にしてWi-Fiに接続するか、通知をすべてオフにする設定を行い、フル充電の状態で臨むといった対策が必須となります。
オンライン面接で聞かれること
オンライン面接で質問される内容は、基本的に対面面接と大きく変わることはありません。
- 自己紹介
- 転職理由・志望動機
- 職務経歴
- 自己PR
- キャリアプラン
上記のような定番の質問に対しては、対面面接と同様に、しっかりと自己分析を行い、自分の言葉で説明できるように準備しておく必要があります。
ただし、オンライン面接の特性上、対面よりも声が聞き取りにくかったり、微妙なニュアンスが伝わりにくかったりする場合があります。
そのため、面接官は「簡潔にわかりやすく話す能力」をより注意深く見ている可能性があります。
結論から先に述べ、具体的なエピソードを簡潔に付け加える「PREP法」などを意識するとよいでしょう。
また、冒頭のアイスブレイクとして、「オンライン面接には慣れていますか?」といった、形式特有の質問が投げかけられる場合もあるので、そういった質問にも準備しておくべきです。
企業側がオンライン面接で注意すべきこと
オンライン面接は、企業側にとっても求職者の本質を見極めるための工夫が求められます。
また、求職者に「この会社で働きたい」と思ってもらうための、自社の魅力付けの場でもあることを忘れてはなりません。
求職者が話しやすくなる雰囲気を作る
求職者は、慣れない環境でのオンライン面接に、対面時以上に緊張している可能性が高いと認識すべきです。
面接官は、まず求職者の緊張をほぐすことを最優先に考えましょう。
面接の冒頭では、天気の話やオンライン面接の経験について尋ねるなど、簡単なアイスブレイクを挟むと効果的です。
また、画面越しでは表情が伝わりにくいため、面接官は意識的に「笑顔」で接し、「大きめの相槌」を打つよう心がけてください。
求職者の発言を遮らず、最後まで真摯に耳を傾ける姿勢を見せることが、求職者のリラックスと本音を引き出す鍵となります。
カメラを見て話すようにする
面接官が求職者の本質を見極めようとPCの画面を熱心に見つめると、求職者からは「面接官が下を向いている」「手元の資料ばかり見ている」ように映ってしまいます。
これでは、威圧感や不安感を与えてしまいかねません。
求職者に安心感を与え、視線を合わせている感覚を持ってもらうためには、面接官は意識的に「PCのカメラレンズ」を見て話すよう心がける必要があります。
慣れるまでは難しいかもしれませんが、カメラの横に付箋を貼るなどして、視線を誘導する工夫も有効でしょう。
オンライン面接ならではのトラブルを想定しておく
オンライン面接において、通信環境の不具合、音声トラブル、映像のフリーズといった機材トラブルは、どれだけ準備しても起こりうるものとして想定しておくべきです。
企業側は、トラブル発生時の対応フローを事前に明確にしておく必要があります。
たとえば、「接続が切れた場合はチャット機能で連絡する」「5分以上復旧しない場合は電話に切り替える」といったルールを定め、面接の冒頭で求職者に伝えておくと、双方が安心して臨めます。
求職者側にトラブルが発生した場合も、それを理由に減点するのではなく、冷静に再接続を促すなど、柔軟な対応を見せることが重要です。
もちろん、企業側の通信環境や使用機材についても、事前に万全の状態かテストしておくことは言うまでもありません。
オンライン面接に関するよくある質問
オンライン面接は対面と勝手が違うため、求職者からは多くの疑問や不安が寄せられます。
ここでは、特によくある質問についてQ&A形式で回答します。
オンライン面接の際にカンペを使っても大丈夫?
求職者がカンペ(カンニングペーパー)を使用することは推奨されません。
面接官は、求職者が「自分の言葉」で考え、熱意を持って話しているかを見ています。
カンペを読み上げることに集中してしまうと、視線が不自然に泳いだり、下を向いたりするため、面接官には高確率で気づかれてしまいます。
結果として、「準備不足」「熱意が感じられない」といった、致命的なマイナス評価につながるリスクが非常に高いでしょう。
もし準備に不安がある場合は、文章をそのまま書いたカンペを用意するのではなく、話したい「キーワード」や「要点」のみを小さな付箋などに書き出し、PCのカメラ横など目線が大きく動かない位置に貼る程度に留めるべきです。
面接中にスマホの通知音が鳴ってしまった場合は?
万が一、面接中にスマートフォンやPCの通知音が鳴ってしまった場合、最も重要なのは慌てないことです。
まずは「申し訳ございません」と一言、はっきりと謝罪してください。
その後、速やかに通知音が鳴らない設定(マナーモードや通知オフ)に変更します。
謝罪した後は、その失敗を引きずることなく、すぐに面接の会話に意識を戻しましょう。
本来、面接に臨む際は、使用するWeb会議ツール以外のアプリケーションは全て終了させ、スマートフォンもマナーモードではなく「通知が一切鳴らない設定」にしておくのが基本的なマナーです。
途中で接続が切れてしまったらどうすればいい?
面接の途中で通信が途絶えてしまった場合も、まずは冷静に対応することが大切です。
機材トラブルは、誰にでも起こりうることだと認識しましょう。
最初に行うべきは、再接続の試行です。
使用しているツールの再起動や、PCの再起動を試みてください。
もし数分試しても復旧しない場合や、原因がわからない場合は、それ以上時間をかけるのではなく、速やかに企業側へ連絡を入れます。
事前に案内されている緊急連絡先に、「接続が切れてしまい、申し訳ございません。現在再接続を試みておりますが、復旧いたしません」など、状況を正確に報告してください。
その後、無事に再接続できた際には、改めて「先ほどは接続が途切れてしまい、大変失礼いたしました」と謝罪してから、面接を再開しましょう。
まとめ
オンライン面接は、場所を選ばない利便性がある一方で、対面面接とは異なる特有の「準備」と「マナー」が求められます。
服装や身だしなみはもちろんのこと、背景の整理整頓、安定した通信環境の確保、静かな場所の選定といった事前準備が、面接官に与える印象を大きく左右します。
画面越しでは熱意や人柄が伝わりにくいため、対面時よりも意識的に明るい表情を心がけ、ハキハキとした声で簡潔に話す工夫も重要になるでしょう。
オンラインであっても、面接は面接です。
本記事で解説したポイントを一つひとつ確認し、万全の準備を整えることで、オンライン面接を成功させることに役立つはずです。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録