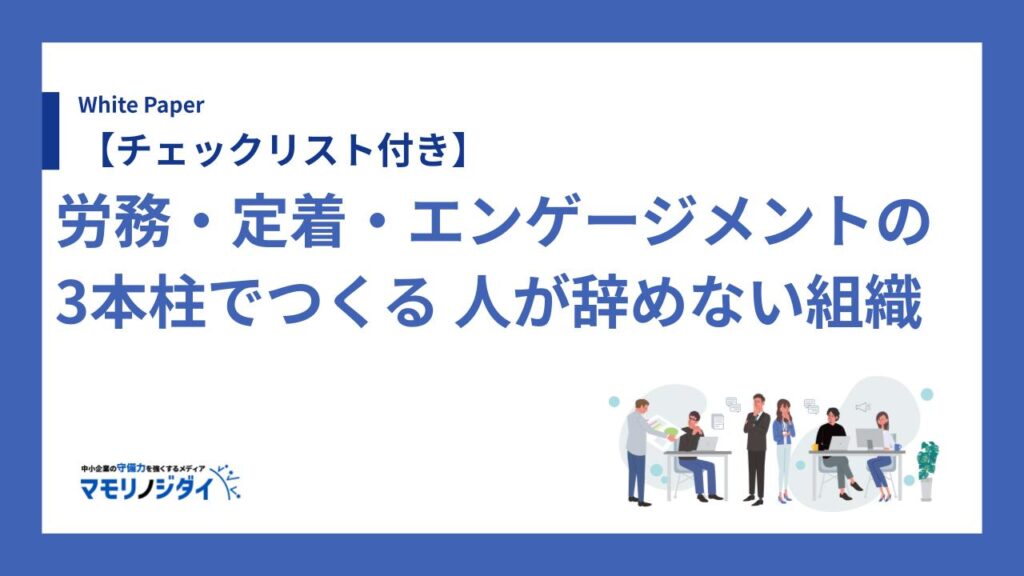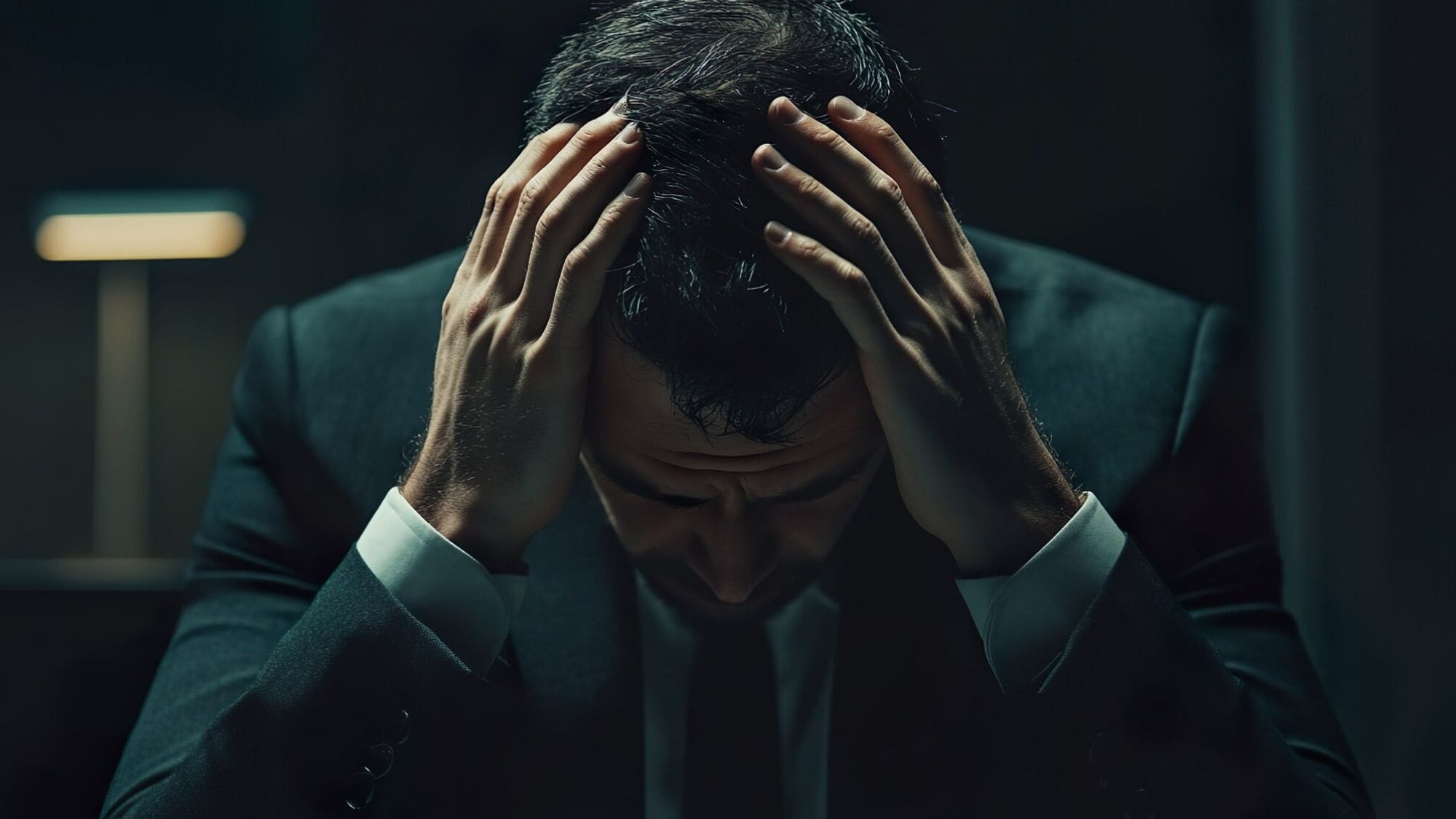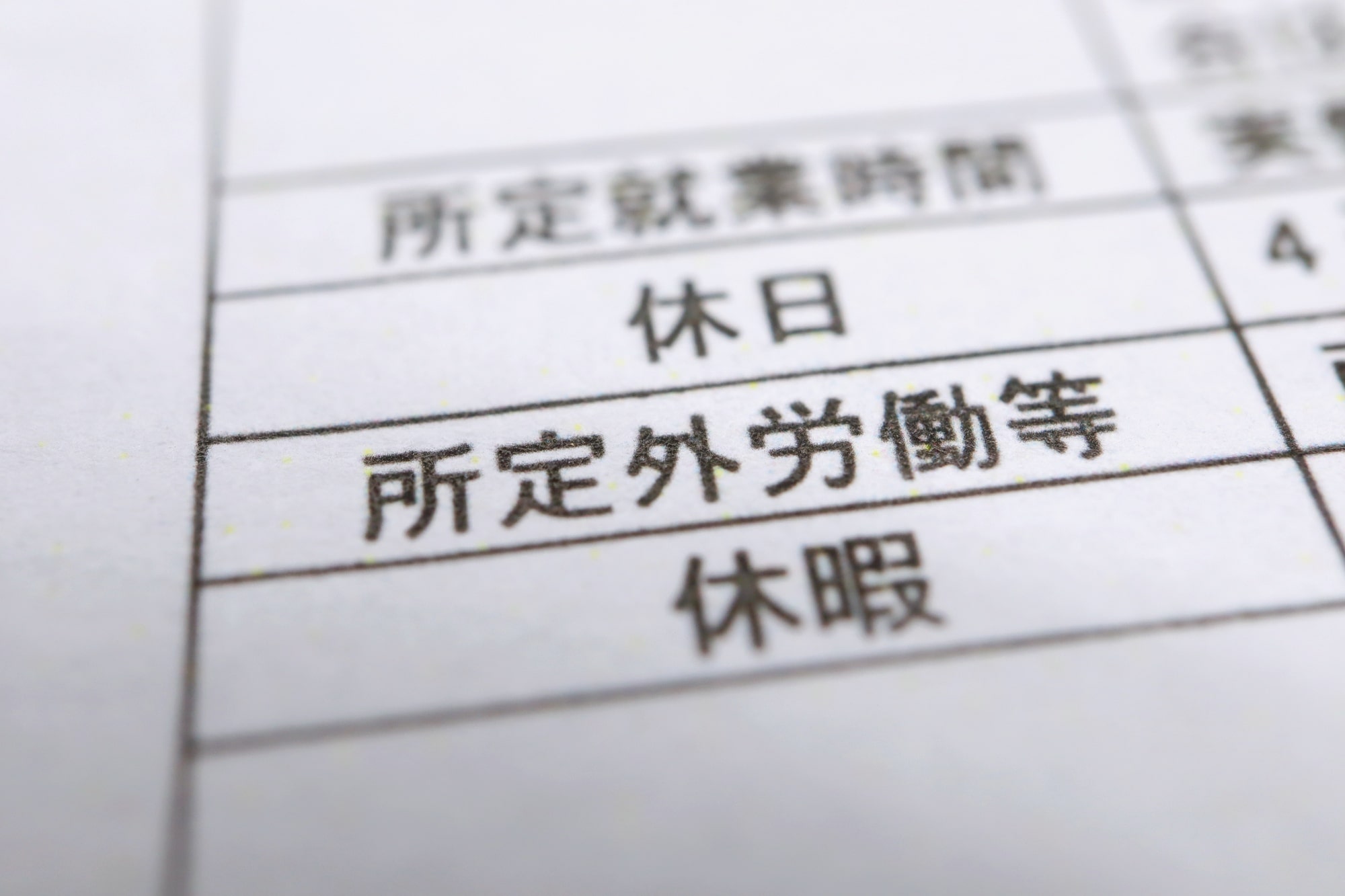アンラーニングとは?リスキリングとの違い・メリットやデメリット・事例

日々激しく変化していくビジネス環境の中、「既存の知識やスキルがあまり役に立たなくなってしまった」というケースが増えてきました。
そこで注目されるようになってきたのが「アンラーニング(学習棄却)」です。
「学習を棄てる」と聞くと、ネガティブなイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし実際は、今の時代に適応するために必要な考え方となります。
この記事では、アンラーニングの意味やメリット・デメリット、リスキリングとの違い、アンラーニングの具体的な事例などについて解説していきます。
デジタル化が進む現代に対応するため、この記事を通して是非アンラーニングへの理解を深めてください。
目次
アンラーニングとは
この項目では、アンラーニングの意味や、アンラーニングが求められるようになった背景、混同されやすい言葉である「リスキリング」「リカレント教育」との違いについて詳しく解説していきます。
アンラーニングの意味
アンラーニング(unlearning)とは、過去に学んだ知識や習慣、思考パターン、習得したスキルなどを意図的に棄てることであり、「学習棄却」や「学びほぐし」という意味があります。
なお「棄却する」といっても、持っている知識やスキルを完全に棄ててしまうわけではありません。
アンラーニングの対象となったスキルを今以上に伸ばすことをやめたり、一時的に使用を停止したりするだけです。
つまり、一旦棄却した知識やスキルであろうと、必要になればいつでも引き出して使用することも可能となります。
アンラーニングが求められるようになった背景
「なぜわざわざ保有している知識やスキルを棄てるのか」と疑問に感じる方も多いかもしれません。
しかし、時代の変化とともに、「通用しなくなった」もしくは「通用しづらくなった」という知識やスキルも存在するのです。
たとえば、営業はこれまで「対面」や「電話でのやりとり」がメインでした。
しかし今では、様々な業種において、「Web会議ツールを使用したオンラインでのやりとり」や「チャットツールでのテキストコミュニケーション」が重要になりつつあります。
このように、優先度の低くなったものを意識的に棄てて、今後必要となる知識について学んでいくことの重要性は年々高まりつつあります。
そのため、アンラーニングが注目されるようになったのです。
アンラーニングとリスキリングの違い
アンラーニングとリスキリングは、似ている部分もあることから混同されがちですが、違う概念です。
リスキリング(Re-skilling)とは、「学び直し」を意味する言葉を指します。
リスキリングは、DX化による自社のビジネスモデルの変化などに対応するため、新たなスキルを習得することです。
一方、アンラーニングは「棄てるべきスキルの取捨選択」に重点を置いています。リスキリングは「新たに学ぶこと」に重点を置いているため、根本的に考え方が異なるのです。
ただし、このような違いがあるとはいえ、アンラーニングとリスキリングには密接な関係があります。
どちらも「今のビジネス環境に対応するためのスキルを身に付けること」がゴールであり、アプローチの違いこそあれ、目指すところは同じだと言えるでしょう。
アンラーニングとリカレント教育の違い
リカレント教育も、アンラーニングと混同されやすい言葉です。
リカレント教育(Recurrent Education)とは、学校教育が修了した後も、生涯に渡り学習を継続することです。
場合によっては、会社を退職・休職して、専門の教育機関に通うというケースもあります。
リカレント教育とアンラーニングとの違いは「主体」です。
アンラーニングは、企業が主体となって実施される取り組みである一方、リカレント教育は個人が主体となり、個人の意志で学習が行われます。
「学ぶ」という点のみ共通しているものの、業務に必要な知識やスキルについて学ぶアンラーニングやリスキリングと、個人の意志で好きなことを学ぶリカレント教育とでは、大きな違いがあります。
アンラーニングのメリット
アンラーニングを実施することで、主に以下のようなメリットを得ることができます。
- 従業員に成長の機会を与えられる
- 業務効率の改善に期待できる
- 時代の変化に対応しやすい組織になる
それぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。
【メリット1】従業員に成長の機会を与えられる
経験や実績が豊富な人材の場合、大きな変化を好まず、新たなスキルを習得しようという意欲が低いケースも散見されます。
しかし、イノベーションが進む現代においては、過去の経験や既存スキルが通用しなくなってしまうスピードが速いため、スキルのアップデートは欠かせません。
この問題を解決できる方法のひとつが、アンラーニングです。
アンラーニングで内省を促せば、今後必要となるスキルを従業員自身に意識させられるため、自助教育的なメリットもあります。
このように、従業員に成長の機会を与えられるアンラーニングですが、実施の際は注意すべきこともあります。
それは、「過去の経験やスキルを否定しないこと」です。
伝え方によっては、「これまでの努力がなかったことにされた」と捉えられてしまうかもしれません。
時には逆効果になることもあるため、アンラーニング実施の際は相手を慮り、慎重に進めるようにしてください。
【メリット2】業務効率の改善に期待できる
アンラーニングによって従業員が新しいスキルを習得すれば、業務効率を改善できる可能性が生まれます。
たとえば、これまでアナログなやり方をしていた業務をIT化し、従業員たちがそれに対応できるようになれば、従来のリソースを大幅にカットすることも可能です。
ただし、業務フローを変更した場合、一時的に業務効率が下がってしまうこともあります。
従業員たちが新しい業務に慣れるまで一定の時間が必要なケースもあるため、「新体制に変えたら業務効率が下がったから、すぐ元に戻した」というようなことがないようにしましょう。
【メリット3】時代の変化に対応しやすい組織になる
アンラーニングによってスキルの取捨選択が促進される組織になれば、時代の変化に強い組織となります。
従業員たちが、必要に応じて不要なスキルを棄却し、時代に合わせたスキルを積極的に習得しようと動く環境が構築されていれば、業務の改善だけでなく、新事業の創出などにも繋がりやすくなります。
「変化」の例としては、「コロナ渦」が挙げられます。
コロナ渦によって、従来の業態では通用しなくなってしまったという企業は数多く存在しました。
しかし、状況に応じて柔軟に動ける人材が多い組織ならば、危機を乗り越えるために何をすればいいかを考え、状況を打開するために必要なスキルを学ぶ、という流れが自然に生まれやすくなります。
このように、アンラーニングによって変化に強い組織になるという点も、メリットのひとつと言えます。
アンラーニングのデメリット
アンラーニングには、メリットだけでなく、以下のようなデメリットも存在します。
- 従業員のモチベーション低下に繋がる可能性がある
- 組織単位で取り組まなければ効果が低い
- 成果が出るまでに時間がかかる
それぞれのデメリットについて解説していきます。
【デメリット1】従業員のモチベーション低下に繋がる可能性がある
アンラーニングによって新しいスキルを習得することにはメリットがあると理解しても、苦労して身に付けた既存スキルを棄てることには勇気が要ります。
場合によっては、スキルを棄てる不安に耐えられず、逆に業務へのモチベーションが下がってしまうこともあり得ます。
また、これまでの自分を否定されたと感じる従業員も出てくるかもしれません。
アンラーニングの進め方を間違えてしまうと、業務改善や従業員の成長に繋がらないどころか、モチベーションを奪ってしまうリスクが潜んでいるという点に注意が必要です。
【デメリット2】組織単位で取り組まなければ効果が低い
アンラーニングは、組織単位で取り組まなければ効果が低くなってしまうという点もデメリットのひとつです。
個人単位・部門単位でアンラーニングを実施しても、組織にひずみができるだけ、という結果になりかねません。
組織単位で取り組むため、まずは経営層がアンラーニングについてしっかり理解し、旗振り役となって動く必要があります。
【デメリット3】成果が出るまでに時間がかかる
アンラーニングを実施しても、すぐに結果が出ることはありません。
業務改善やイノベーションに繋がるようなスキルは、一朝一夕で身に付くものではないからです。
また、従業員がスキルを習得したからといって、すぐに上手く回るかどうかも不明です。
業務フローが変わる場合、試行錯誤する期間を要することも珍しくありません。
アンラーニングによる成果は、短期的に見るのではなく、長期的に見るようにすべきです。
アンラーニングのやり方
アンラーニングを行う際は、以下のステップに沿って進めるようにしてください。
- 内省
- 価値観の取捨選択
- 新たなスキルの習得
- フォローアップ
それぞれのステップについて、具体的に解説していきます。
1.内省
アンラーニングにおける最初のステップは「内省(自分について深く掘り下げること)」です。
まずは従業員たちに内省を促し、これまでの自分の考え方や業務の方法などを振り返ったり、自分の強みと弱みを整理したりしてもらいます。
なお内省を実施する際は、ただ頭の中で考えてもらうのではなく、専用のシートを用意して記録に残す形にするのがよいです。
記録として残れば、自分自身で後々振り返りやすく、上司や同僚と共有しやすくなるというメリットもあります。
2.価値観の取捨選択
アンラーニングの次のステップは、「内省によって認知した価値観を取捨選択すること」です。
内省で明らかになった価値観を、「今後も必要な価値観」「棄てるべき価値観」「変えるべき価値観」のように仕分けしていきます。
この工程は非常に重要なものであるため、従業員一人に任せるのではなく、360度評価を実施したり、上司との1 on 1ミーティングを行ったりしながら進めるのが望ましいです。
3.新たなスキルの習得
価値観の取捨選択が済んだことで、今後習得すべきスキルも見えてくるはずです。
しかし、組織からのサポートなしで、従業員たちがスキルを身に付けていくのは困難かもしれません。
したがって、「研修を実施する」「教育機関へ通うための資金を援助する」など、学びの補助を行うことも重要です。
4.フォローアップ
アンラーニングは、ただ実施するだけではあまり意味がありません。
- 実施した結果どういった成長があったのか
- 次に取り組むべきことは何か
このような点を確認するための振り返りも必要になります。
価値観の取捨選択の際と同様、こちらも上司との1 on 1ミーティングなどを行い、従業員たちのアンラーニングを丁寧にフォローアップしていくべきです。
アンラーニングを効率的に進めるためのポイント
アンラーニングは、ただ漫然と実施するだけでは効果が薄まってしまいます。
効率的にアンラーニングを進めるためには、以下のようなポイントを意識するようにしてください。
- 従業員にアンラーニングの重要性を理解させる
- アンラーニングに取り組むための最適な環境を作る
- アンラーニングに対するフィードバックの機会を設ける
それぞれ、詳しく解説していきます。
1.従業員にアンラーニングの重要性を理解させる
組織が変化に適応し続けるための第一歩として、アンラーニングの重要性を従業員たちにしっかりと伝え、理解してもらう必要があります。
十分な説明をしないまま、「とにかくこのプログラムに沿ってアンラーニングを進めるように」といった指示を出しても、従業員のモチベーションは上がりません。
その結果、アンラーニングが形骸化してしまう恐れがあります。
こういった事態を避けるためには、全従業員がアンラーニングの価値を理解し、前向きに取り組めるよう体制を整えましょう。
1 on 1でのミーティングを実施して丁寧に説明したり、アンラーニングに関する説明会を開いたりしてください。
2.アンラーニングに取り組むための最適な環境を作る
アンラーニングの重要性が社内に周知されるだけでは不十分です。
従業員がアンラーニングに対してのモチベーションを高めたとしても、実際に実行できる環境が整っていなければ浸透しにくくなる可能性があります。
- アンラーニングを進めるためのマニュアルを作成する
- スキル習得にかかる費用を負担する制度を用意する
- アンラーニングに関して相談しやすい体制を作る
こうした環境整備を進めることで、従業員も安心してアンラーニングに取り組めるようになります。
3.アンラーニングに対するフィードバックの機会を設ける
従業員が「このやり方でよいのか」「スキル習得は順調に進んでいるのか」と不安にならないように、従業員のアンラーニングに対するフィードバックの機会を設けるようにしましょう。
上司が部下に対しヒアリングを行い、相談に乗ったり、アドバイスをしたりといった機会が定期的にあれば、従業員が抱えている不安が取り除かれ、より前向きにアンラーニングに取り組めるはずです。
アンラーニングの具体的な事例
これまで、アンラーニングのやり方やメリット・デメリットなどについて解説してきましたが、アンラーニングを実施することで実際にどうなるのか、といった事例を知りたい方もいるでしょう。
この項目では、アンラーニングを企業全体で進めたことで、成功を収めている具体的な事例について3つ紹介していきます。
YouTubeのアンラーニング
2005年の創立当初、YouTubeは「オンラインマッチングサービス」としてリリースされたものの、このサービスは失敗に終わってしまいます。
しかし、失敗した「オンラインマッチングサービス」を運営する過程で生まれた「ビデオ共有プラットフォーム」を活かすことに成功したことで、現在のような持続的成長に繋がりました。
このプロセスが、まさに多くの企業にとって学ぶべきアンラーニングの実例と言えます。
YouTube創業者たちが当初のビジョンを手放し、新たな機会を受け入れることで、世界最大級の動画プラットフォームに成長したのです。
YouTubeのアンラーニングでは、ユーザー生成コンテンツとメディアの両方を統合し、全世界で多様な視聴者に対応することで大きな成功を収めました。
富士フイルムのアンラーニング
アンラーニングを実践することで、フィルム事業からの大胆なシフトを成功させた企業が、富士フイルムです。
デジタル化が進む中、フィルムの需要が急激に低下し、既存のビジネスモデルが通用しなくなってきました。
そこで、従来のフィルム事業で培った技術を異なる分野に適用する新しい方向性を見いだしたのです。
富士フイルムは、これまでの経験と知識を、化粧品や医薬品、バイオテクノロジーなどの分野に応用することで、新たな収益源を創出しました。
特に、写真フィルムの技術を活かしたコラーゲン製品や医療用材料の開発では、大きな成功を遂げています。
組織全体における思考の転換と、従業員一人ひとりの意識改革によって、新しい挑戦を恐れない企業文化の創出にもつながりました。
このプロセスこそ、アンラーニングそのものです。
富士フイルムは、過去の成功体験や既存知識を意識的に手放し、新しい市場や技術を模索する柔軟性が獲得できたと言えます。
アサヒビールのアンラーニング
1987年に発売されて以来、大きな成功を収めてきた「アサヒスーパードライ」は、辛口と切れの良さで人気でした。
しかし、時を経て消費者の嗜好や市場環境が大きく変化していきます。
特に2020年の酒税法改正によるビール酒税の軽減が追い風となり、社内でもこの風に乗らなければ今後の成長が難しいのではという意見が増えてきたようです。
そこでアサヒビールは、これまで36年間続いていた伝統的な製法や味に固執するのではなく、消費者の期待を超える新しい製品開発という道を選びました。
2022年に発売された「新スーパードライ」は、これまでの味やパッケージデザインを一新し、味わいの強化と製品の魅力を再定義した内容となっています。
結果的に、アサヒビールはこのアンラーニングによってビール業界のシェアを取り戻し、時代とともに進化するブランドとしての地位を確立しています。
まとめ
以上、アンラーニングの意味や実施するメリット・デメリット、アンラーニングのやり方、実際の事例などを紹介しました。
過去の知識や既成概念を意識的に棄却することで、新たな学びを得やすくするアンラーニングですが、適切な方法で進めなければ混乱につながる可能性があります。
しかし、今回紹介した企業の成功事例からもわかるように、適切なアンラーニングが、組織や個人が市場の変化に柔軟に対応し、革新的な成果を生み出すカギです。
社内のアンラーニングを進めるためには、その重要性を全員が理解し、企業文化に根づかせることが不可欠となります。
時間と労力はかかりますが、達成できたときの力は強く大きなものとなるはずです。
企業の更なる成長のためにも、ぜひアンラーニングの導入を検討してみてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録