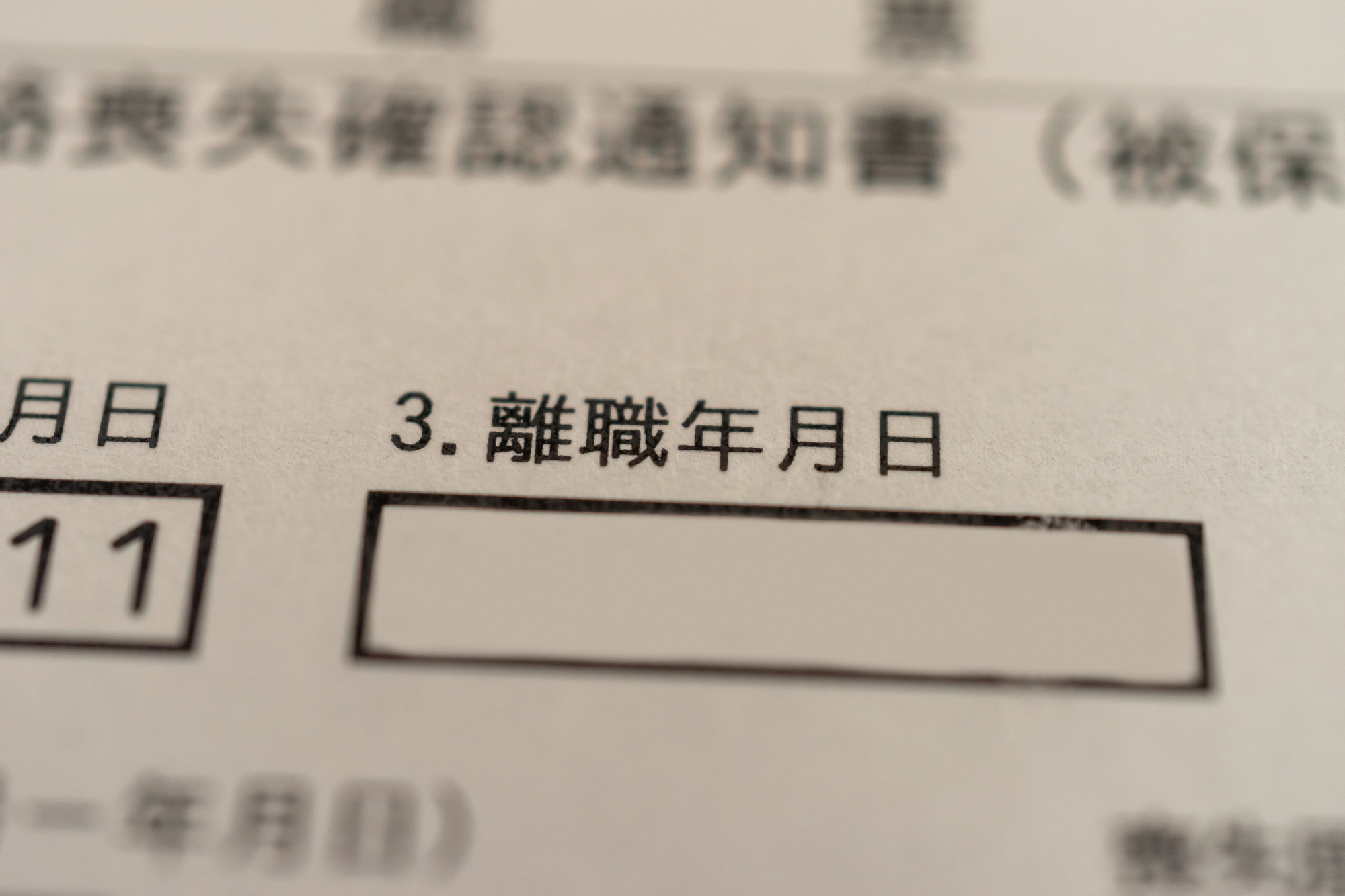フレックスタイム制とは?メリット・デメリットや残業代の扱いを簡単に解説

働き方改革が進む中、従業員がより柔軟に働ける環境を整備することは、企業にとって重要な課題となっています。
その解決策の一つとして注目されているのが「フレックスタイム制」です。
導入する企業も一定数存在する一方で、仕組みの複雑さや勤怠管理の難しさから導入を躊躇するケースも少なくなく、普及率は決して高いとは言えません。
しかし企業によっては、フレックスタイム制を導入することでメリットの方が多いこともあるため、検討もせずに選択肢から外してしまうのはもったいないでしょう。
そこでこの記事では、フレックスタイム制の基本的な仕組みから、企業側・従業員側のメリットとデメリット、導入に必要な準備までわかりやすく簡単に解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
フレックスタイム制とは何かについて簡単に解説
フレックスタイム制について、厚生労働省では以下のように説明しています。
| フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、⽣活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。 |
出典)厚生労働省「フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き」p.2
従来のように、「9時から18時まで」といった固定的な勤務時間にとらわれず、生活スタイルや業務の繁忙期・閑散期に合わせて働く時間を調整できるのが最大の特徴です。
ここでは、フレックスタイム制の具体的な仕組みや導入目的、普及の現状について解説します。
フレックスタイム制の仕組み
フレックスタイム制を正しく理解するためには、「清算期間」「総労働時間」「コアタイム」「フレキシブルタイム」という4つのキーワードを把握する必要があります。
まず、清算期間とは、労働時間を集計する期間のことで、上限は3ヶ月以内と法律で定められています。
企業は、この清算期間内に従業員が働くべき「総労働時間」を設定します。
また、1日の労働時間は、「コアタイム」と「フレキシブルタイム」に分けられるのが一般的です。
コアタイムは「必ず勤務しなければならない時間帯」、フレキシブルタイムは「いつ出社してもいつ退社してもよい時間帯」のことです。
従業員は、コアタイムには必ず在席しつつ、フレキシブルタイムの範囲内で自由に出退勤時間を調整し、清算期間全体で定められた「総労働時間」を満たすように働きます。
なお、コアタイムを設けずにすべての時間を従業員の裁量に任せる「スーパーフレックス制度」を導入する企業も存在します。
フレックスタイム制を導入する目的
企業がフレックスタイム制を導入する主な目的は、生産性の最大化です。
画一的な労働時間管理では、仕事が少ない日でも定時まで会社にいなければならなかったり、逆に集中して進めたい業務があっても時間が足りなかったりと、非効率な状況が生まれることがあります。
しかしフレックスタイム制を導入すれば、業務量に応じたメリハリのある働き方が可能になります。
また、多様な働き方を認めることで、従業員のワークライフバランスを支援する狙いもあります。
育児や介護、通院など、個人の事情に合わせて時間を調整できれば、離職を防ぎ、長く働き続けられる環境を提供できるため、結果として従業員満足度を高めることができるのです。
参考記事:離職率の平均はどれくらい?日本の企業規模別・業界別の離職率を紹介
フレックスタイム制はなぜ普及しない?
いくつものメリットがあるフレックスタイム制ですが、日本企業全体での導入率は依然として高いとは言えません。
普及を阻む大きな要因の一つは、日本特有の「集団で働く」という労働文化です。
チーム全員が同じ時間に顔を合わせて働くことを重視する職場では、個々の時間がバラバラになるフレックスタイム制は「連携が取りにくい」と敬遠されがちです。
さらに、取引先との兼ね合いも影響しています。
顧客が9時から17時で稼働している場合、自社の従業員がその時間帯に不在であれば、ビジネスチャンスを逃したり、クレームに繋がったりする懸念があります。
労働時間の管理が複雑になることも、導入のハードルとなっています。
日々の労働時間が変動するため、残業代の計算や過重労働の防止といった労務管理の負担が増大することを懸念し、導入に踏み切れない企業も少なくありません。
フレックスタイム制を導入するメリット
フレックスタイム制の導入は、従業員にとって働きやすさが向上するだけでなく、企業側にも採用競争力の強化やコスト削減といった経営的なメリットをもたらします。
ここでは、代表的な3つのメリットについて詳しく解説します。
従業員のワークライフバランスが保たれやすい
従業員にとってのフレックスタイム制の最大の利点は、「私生活と仕事を両立しやすくなる」という点です。
たとえば、朝に子供を保育園へ送ってから出社したり、夕方の早い時間に退社して資格取得の勉強や趣味の時間に充てたりすることが可能になります。
また、役所や病院へ行くために平日の日中に時間を確保することも容易になるでしょう。
満員電車のラッシュアワーを避けて通勤できることも、従業員にとっては大きなメリットです。
通勤によるストレスや疲労を軽減できれば、業務への集中力が高まり、結果としてパフォーマンスの向上も期待できます。
個人のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方は、精神的なゆとりを生み出し、心身の健康維持にもつながるはずです。
無駄な残業時間が発生しにくくなる
従来の固定時間制では、仕事が早く終わっても定時までは退社しづらい雰囲気があり、結果として「付き合い残業」や「生活残業」が発生しやすい傾向がありました。
しかし、フレックスタイム制では「やるべき仕事が終われば早く帰る」という働き方が基本となるため、無駄に会社に残る時間を削減できます。
業務が忙しい日には長く働き、落ち着いている日には早めに切り上げるという調整を従業員自身が行うことで、月間の総労働時間を適正な範囲に収めやすくなるのです。
これにより、企業全体としての残業代コストを削減できる可能性があります。
従業員が「時間を意識して働く習慣」を身につけることで、ダラダラと長く働くのではなく、限られた時間で成果を出そうとする意識改革にもつながるでしょう。
参考記事:日本の平均残業時間が長い理由とは?中小企業が意識すべき残業を減らす方法
人材を確保しやすくなる
少子高齢化に伴い労働人口が減少する中、優秀な人材の確保は企業にとって喫緊の課題です。
求職者は、給与や仕事内容だけでなく、「働きやすさ」や「柔軟な勤務体系」を企業選びの重要な基準としています。
フレックスタイム制を導入していることは、従業員の自律性を尊重し、働きやすい環境づくりに力を入れている企業であるという強力なアピール材料になります。
特に、「子育てや介護」と「仕事」を両立したい層や、副業・兼業を希望する層など、多様なバックグラウンドを持つ人材からの応募が期待できるでしょう。
また、既存の優秀な従業員がライフステージの変化を理由に離職してしまうことを防ぐ効果も期待できるため、長期的な視点での人材戦略において非常に有効な手段と言えます。
フレックスタイム制を導入するデメリット
フレックスタイム制には多くのメリットがある一方で、運用上の課題やデメリットも存在します。
導入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないよう、あらかじめデメリットを把握し、対策を検討しておくことが重要です。
勤怠管理に手間がかかる
フレックスタイム制における最大の課題は、勤怠管理の複雑化です。
従業員ごとに出退勤時間が異なるため、管理者は個々の労働時間を正確に把握する必要があります。
特に注意が必要なのが、残業代の計算です。
フレックスタイム制では、1日単位で残業を判断するのではなく、清算期間全体の総労働時間を超えた分を時間外労働として扱います。
清算期間が1ヶ月を超える場合は、月ごとの週平均労働時間が50時間を超えた分も割増賃金の対象となるなど、計算ルールが複雑になります。
また、不足時間があった場合の翌月への繰り越し処理や、欠勤・有給休暇との兼ね合いなど、給与計算担当者の負担は確実に増加するはずです。
従来のアナログな管理方法では対応しきれないケースが多く、専用の勤怠管理システムの導入などが必要になる場合もあります。
参考記事:中小企業の勤怠管理、正しくできていますか?基本からシステム選びまで徹底解説
従業員同士のコミュニケーションが取りづらくなる
従業員の勤務時間がバラバラになることで、社内コミュニケーションが希薄になる恐れがあります。
「相談したい相手がまだ出社していない」
「急ぎの確認事項があるのに既に退社している」
このような状況が頻発すると、業務の進行に遅れが生じてしまうでしょう。
また、全員が揃う時間が限られるため、全体会議やチームミーティングの日程調整が難航することもあります。
対面でのコミュニケーションが減ることで、チームの一体感が損なわれたり、情報共有の漏れが発生したりするリスクも考慮しなければなりません。
雑談から生まれるアイデアや、ちょっとした相談による問題解決の機会が減少し、組織全体の活力が低下しないよう、チャットツールの活用やコアタイムの有効利用といった工夫が求められます。
突発的な顧客対応に対応できない
顧客や取引先からの問い合わせ、クレームなどの突発的な事象に対応しづらくなることもデメリットの一つです。
たとえば、顧客が始業する朝9時に電話がかかってきても、担当者がフレックスタイム制で11時に出社予定だった場合、迅速な対応ができません。
「担当者が不在でわからない」という回答が続けば、顧客からの信頼を失う可能性があります。
特定の担当者に業務が属人化している場合、このリスクはさらに高まるでしょう。
フレックスタイム制を導入する場合でも、部署内で常に誰かが対応できる体制を整えたり、顧客に対して連絡可能な時間帯を明示したりするなど、顧客からの信頼を失わないためのルール作りが不可欠です。
フレックスタイム制を導入する際に企業側が準備しておくべきこと
フレックスタイム制を導入する場合、単に「明日から時間を自由にします」と宣言するだけでは不十分です。
この項目では、フレックスタイム制を導入する際に企業が行うべき準備について紹介していきます。
就業規則の改定と労使協定の締結
フレックスタイム制を導入するためには、まず就業規則にその旨を規定する必要があります。
具体的には、「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねること」を明記しなければなりません。
これは、労働基準法で定められた必須要件です。
次に、労使協定を締結します。
労使協定では、以下のような項目を定める必要があります。
- 対象となる労働者の範囲(全社員か、特定の部署か)
- 清算期間(労働時間を集計する期間)
- 清算期間における総労働時間(所定労働時間)
- 標準となる1日の労働時間(有給休暇取得時の計算基準などに使用)
- コアタイムとフレキシブルタイムの開始・終了時刻
特に清算期間が1ヶ月を超える場合は、労使協定を労働基準監督署へ届け出る義務が発生します。
法的な不備がないよう、社会保険労務士などの専門家に確認を仰ぎながら進めましょう。
参考)厚生労働省「フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き」
勤怠管理体制の整備
前述の通り、フレックスタイム制では労働時間の管理が複雑になります。
そのため、従業員の出退勤時刻や労働時間の過不足をリアルタイムで把握できる仕組みを整えなければなりません。
特に、「不足時間を翌月に繰り越す処理」や「清算期間を通じた残業時間の集計」に自動対応できる勤怠管理システムの導入は、管理コスト削減のために非常に有効です。
また、管理職に対しても、部下の労働時間管理に関する教育を行う必要があります。
フレックスタイム制であっても、企業は労働時間を把握する義務があり、深夜労働や休日労働に対する割増賃金の支払いは通常通り発生します。
管理職が制度を正しく理解していなければ、知らぬ間に未払い残業が発生したり、長時間労働を助長したりするかもしれません。
従業員への周知徹底
制度をスムーズに運用するためには、従業員への説明と意識改革が欠かせません。
制度の仕組みやルール、禁止事項などをまとめたマニュアルを作成し、説明会を実施して周知徹底を図りましょう。
特に、「自由な時間に出退勤できる」といっても、「好き勝手に休んでいいわけではない」「業務に支障が出ないようチーム内で調整する義務がある」といった職業倫理やマナーについてもしっかりと伝える必要があります。
また、顧客対応や会議のルール、緊急時の連絡体制などを明確にしておくことで、フレックスタイム制導入後の混乱を最小限に抑えることができるはずです。
フレックスタイム制に関するよくある質問
フレックスタイム制の導入に際してよくある質問をまとめましたので、導入を検討する場合はぜひ参考にしてください。
コアタイムとは何?
コアタイムとは、フレックスタイム制において「必ず勤務していなければならない時間帯」のことです。
たとえば、「11時から15時まではコアタイム」と定めた場合、従業員はこの時間帯には必ず出社(または在宅勤務)していなければなりません。
コアタイムを設けることで、会議の設定や確実な連絡が取りやすくなり、コミュニケーション不足というフレックスタイム制の弱点を補うことができます。
なぜフレックスタイム制はずるいと言われることがある?
一部の従業員だけがフレックスタイム制を利用できる場合や、運用ルールが曖昧な場合に、「あの人だけ好きな時間に来てずるい」「早く帰れていいな」といった不公平感が生まれることがあります。
特に、工場のライン業務や店舗スタッフなど、職種によって導入が難しい部門がある企業では、部門間での不公平感が問題になりがちです。
また、遅く出社した従業員が、早く出社して定時で帰る従業員を見て「まだ仕事中なのに帰るのか」と不満を持つケースもあります。
こうした不満を解消するためには、制度の対象範囲を明確にし、成果で評価する人事制度への転換など、全社的な意識改革が必要です。
フレックスタイム制はどんな職種に向いている?
フレックスタイム制は、個人の裁量で業務を進めやすい職種に向いています。
具体的には、エンジニア、デザイナー、研究開発職などが挙げられます。
これらの職種は、成果物が明確であり、必ずしも他者と時間を合わせて作業する必要性が低いためです。
一方、顧客対応が必要な営業職、店舗での販売職、医療・福祉関係、製造ラインの担当者などは、時間が固定されていることが多く、導入のハードルが高い傾向にあります。
ただし、チーム制を導入して交代で対応するなど、工夫次第で導入できるケースも増えています。
まとめ
フレックスタイム制は、従業員が始業・終業時刻を自律的に決定できる制度であり、ワークライフバランスの向上や業務効率化に大きく貢献します。
企業にとっても、優秀な人材の確保や無駄な残業コストの削減といったメリットが期待できます。
しかし、導入には勤怠管理の複雑化やコミュニケーション不足といった課題も伴いますので、フレックスタイム制導入の際には十分な準備をするようにしてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
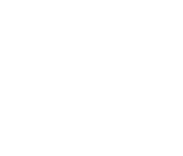 会員登録
会員登録