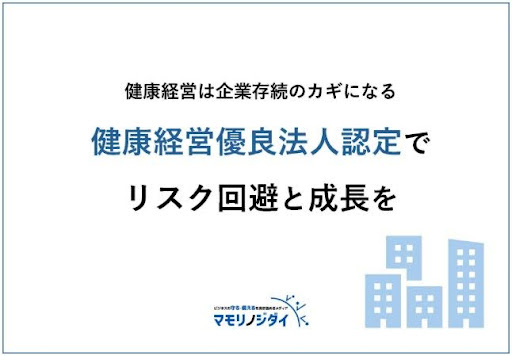サステナビリティ経営とは?企業事例とメリット、導入のポイントを徹底解説

サステナビリティ経営とは、企業が環境や社会に対して長期的な視点で責任を果たしながら、持続可能な成長を目指す経営手法のことです。
地球温暖化や資源の枯渇、社会的格差の拡大といったグローバルな課題に対応するため、企業は従来の利益追求だけでなく、持続可能な社会の実現に貢献する役割を担っています。
また、国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)との関連も深く、これに基づいた戦略的な取り組みが多くの企業で進められています。
本記事では、サステナビリティ経営の基本概念から具体的な企業事例、導入のためのポイントまでを詳しく解説します。
企業が社会的責任を果たしながら競争力を高めるために、どのような取り組みが求められているのかを学んでいきましょう。
目次
サステナビリティ経営の基本概念
サステナビリティ経営の基本概念について、経営の定義と背景やSDGsとの関係性、サステナビリティ経営が求められる理由を解説します。
サステナビリティ経営の定義と背景
サステナビリティ経営とは、企業が環境や社会に配慮しながら、持続可能な成長を目指す経営手法のことです。
これは、企業活動を通じて長期的な利益を追求しつつ、地球環境や社会に対する責任を果たすことを目的としています。
サステナビリティ経営の背景には、地球温暖化や資源の枯渇、社会的不平等といったグローバルな問題があり、企業はこれらの課題に対応することが求められています。
SDGsとサステナビリティ経営の関係性
国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」は、サステナビリティ経営において非常に重要な役割を果たすと言われています。
SDGsは2030年までに達成すべき17の目標を設定しており、貧困の削減や環境保護、平等な社会の実現などが含まれています。各国が目標の達成を実現しようと、さまざまな試みをしている状況です。
企業は、これらの目標に基づき、環境保全や社会貢献活動を実施することで、持続可能な社会づくりに貢献しています。
サステナビリティ経営が求められる理由
サステナビリティ経営が注目される理由は、企業の長期的な成長とステークホルダー(顧客、投資家、従業員、地域社会など)の期待に応えるためです。
現代社会において、消費者や投資家は企業の社会的責任に対する意識が高まり、持続可能性への取り組みを重視しています。
これに対応しない企業は、信頼を失うリスクがあり、結果的に市場競争力を低下させる可能性があります。
脱炭素経営のKPI
サステナビリティ経営をするにあたり、関係性が深いものとして挙げられるのが「脱酸素経営」です。
脱炭素経営とは
脱炭素経営とは、企業が温室効果ガスの排出を削減し、カーボンニュートラル(実質的な二酸化炭素排出量ゼロ)を目指す取り組みのことです。
具体的には、再生可能エネルギーの活用や、エネルギー効率の向上、低炭素技術の導入などが含まれます。
脱炭素経営は、気候変動問題への対応策として企業にとって欠かせない要素となっています。
脱炭素経営が求められている理由
世界的に温暖化対策が求められる中、多くの国が2050年までにカーボンニュートラルを目指しています。
この流れに対応するため、企業は脱炭素経営を進めることで規制対応を強化し、持続可能な成長を目指しています。
企業は温室効果ガス削減の具体的な目標を設定し、その達成度をKPI(重要業績評価指標)として管理することが重要です。
サステナビリティ経営のメリット
サステナビリティ経営のメリットは、主に3点あります。
- 企業価値向上による長期的な成長
- 環境・社会リスク回避
- 従業員のエンゲージメント向上と人的資本の獲得
ここではそれぞれのメリットについて、詳しく解説します。
企業価値向上による長期的な成長
サステナビリティ経営は、企業価値を向上させる要因として注目されています。
環境や社会に配慮した活動を行う企業は、消費者や投資家からの信頼を得やすくなり、商品の購入や投資家の増加につながるからです。
CSR(企業の社会的責任)活動と連携することで、企業の社会的評価が高まります。サステナビリティ経営の導入は、企業の長期的な成長に必要不可欠な要素といえるでしょう
環境・社会リスク回避
サステナビリティ経営は、環境や社会的リスクを回避する手段としても効果的です。
企業は、環境問題や社会的不平等に対処することで、法的リスクや市場リスクの軽減を図ることができます。
ハラスメント等の危機を脱し、社会的にクリーンな会社づくりをするためにも、サステナビリティ経営は有効です。
従業員のエンゲージメント向上と人的資本の獲得
サステナビリティ経営は、従業員の働きやすさにも直結します。多様性を重視し、従業員を資本として考えるため、従業員の離職率低下や生産性向上に繋がるからです。
求職者にとって魅力的な企業は、採用面においても効果を発揮します。優秀な人材が集まりやすく、「人手不足」の解消もできるでしょう。
サステナビリティ経営は、幅広く企業の価値を高め、企業課題を解決する糸口となるのです。
サステナビリティ経営の実践方法とポイント
サステナビリティ経営を実践する方法とポイントについて解説します。
環境に配慮した取り組みの実例と方法
企業が行うべき環境に配慮した取り組みとしては、再生可能エネルギーの利用、省エネ設備の導入、廃棄物削減などがあります。
これらの取り組みは、企業の環境負荷を軽減し、持続可能な社会の実現に寄与します。
では、取り組みをどのように進めたら良いのか、具体的な方法を以下に紹介します。
環境目標の設定と計画の具体化
まず、環境に配慮した取り組みを効果的に進めるためには、明確な環境目標を設定することが重要です。
例えば、「CO2排出量の30%削減」や「再生可能エネルギーの使用割合を50%に拡大」など、具体的な数値目標を定めると良いでしょう。
目標を設定することで、取り組みの成果を測定しやすくなり、組織全体で統一した意識を持つことができます。
また、短期・中期・長期の計画を策定し、それぞれのステップで達成すべき目標を細分化することで、着実に進める基盤を整えます。
再生可能エネルギーの導入方法
再生可能エネルギーを取り入れるためには、導入コストや運用方法を考慮した計画を立てる必要があります。
工場やオフィスの屋根にソーラーパネルを設置する、風力発電や地熱発電の電力を購入するなど、施設や地域に応じた方法を選びましょう。
また、初期費用が高くなる場合には、エネルギー企業とのパートナーシップや補助金制度を利用することで、コスト面での負担を軽減することが可能です。
さらに、エネルギー消費のデータを定期的に収集し、導入効果をモニタリングすることで、改善点を見つけ、より効果的な活用につなげてください。
省エネ設備の導入と最適化
企業がエネルギー消費を抑えるためには、効率の良い設備やシステムの導入が必要となります。
例えば、LED照明への切り替え、高効率エアコンや冷暖房設備の導入、自動で消灯や温度調整を行うエネルギー管理システムの導入などが有効です。
さらに、設備導入後も定期的にメンテナンスを行い、効率が低下しないよう管理してください。
従業員にも節電意識を高める教育を行い、日常的なエネルギー使用を見直す文化を促進しましょう。
サプライチェーンにおける実践方法
サステナビリティ経営では、企業単体だけでなく、サプライチェーン全体における持続可能性を確保することが重要です。
サプライチェーンとは、原材料の調達から製品の製造、流通、販売に至るまでの一連のプロセスを指し、製品が消費者の手に届くまでのすべての流れが含まれます。
サプライチェーン全体における持続可能性を確保するには、まず各プロセスでの環境負荷や労働環境に関する現状を把握し、具体的な改善目標を設定することが必要です。
例えば、製造過程でのエネルギー消費や排出される温室効果ガスを削減する目標を設けるほか、物流段階では低排出の輸送手段を採用するなどの対策が考えられます。
また、廃棄物管理やリサイクル率向上のための仕組みを整えることも重要です。
こうした取り組みを進めるために、サプライチェーン内のデータを収集・分析し、改善状況を定期的に評価することが求められます。
サステナビリティを実現することで、企業活動が環境や社会に与える影響を最小限に抑え、持続可能な未来に貢献することが可能となるのです。
ガバナンス強化や経営の透明性向上のポイント
サステナビリティ経営を成功させるためには、ガバナンスの強化と経営の透明性の向上が不可欠となります。
企業は、まず内部統制を強化し、明確な責任体制を確立することが重要です。
経営層が定期的にサステナビリティ関連のリスクやパフォーマンスを評価し、必要に応じて方針を見直す体制を整えましょう。監査機能を強化し、内部監査や外部監査を活用することで、不正の防止や改善点発見の促進につながります。
また、経営の透明性を向上させるためには、定期報告も重要です。サステナビリティに関する目標・進捗・課題を、外部に対しても公表することが求められます。
年次報告書やESGレポートを活用して、環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する取り組み状況や達成度合いをわかりやすく発信してください。
加えて、投資家や株主との対話を積極的に行い、ステークホルダーの声を経営に反映させることも必要です。透明性を高めるとともに信頼関係を構築しましょう。
上記を徹底すれば、ガバナンス強化と経営の透明性向上が実現し、サステナビリティ経営の持続的な成功が期待できます。
サステナビリティ経営の導入ステップ
サステナビリティ経営の導入は、企業が持続的な成長を達成し、社会的責任を果たすために不可欠なプロセスです。
以下のステップに従い、効果的に取り組みを進めることで、企業全体の競争力と社会的信用を高めることができます。
経営戦略への統合と具体的な目標設定
企業がサステナビリティ経営を成功させるためには、経営戦略そのものにサステナビリティを組み込み、測定可能な目標を設定することが必要不可欠です。
例えば、「2030年までにCO2排出量を50%削減する」「2035年までに再生可能エネルギーへの移行を80%達成する」といった具体的な数値目標を掲げることで、社内外の関係者に明確なビジョンを示し、コミットメントを強化します。
実行計画の策定と社員教育
目標を達成するためには、達成に向けた実行計画を緻密に策定し、全社的な体制を構築することが肝要です。
まずは、部門別に役割と目標を設定し、サステナビリティに対する責任を明確にしましょう。
また、社員がサステナビリティの意義を理解し、自発的に取り組めるよう、定期的な研修や意識向上プログラムを実施することが重要です。
これにより、全社員が統一された目標に向けて動き出し、組織全体でのシナジーを生み出します。
成果の測定と継続的な改善
サステナビリティ経営の成果を最大化するためには、定期的な成果の測定と改善を繰り返すサイクルが欠かせません。
KPI(重要業績評価指標)を活用して活動の進捗を評価し、目標達成の度合いを定量的に確認することで、取り組みの有効性を検証してください。
また、得られたデータに基づき、改善が必要な点を迅速に特定し、次のアクションプランに反映させましょう。
このように継続的に質を高めるプロセスを確立することで、サステナビリティ経営の取り組みは長期的に持続可能となり、企業全体のレジリエンスも向上します。
サステナビリティ経営の成功事例
ここでは、実際にサステナビリティ経営に成功した事例をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
国内企業の事例
国内企業の成功事例は以下の通りです。
富士通
富士通は、再生可能エネルギーの導入やCO2排出量削減に積極的に取り組んでいます。
具体的な取り組みの結果、CO2排出量の年間削減率が目標値を上回る成果を上げ、環境負荷の低減に大きく寄与しました。
また、エコ商品の開発にも注力しており、環境に配慮したビジネスモデルを確立しています。
富士通は、上記の取り組みの中で製品ライフサイクル全体を見据えた環境影響評価を行い、エネルギー効率やリサイクル可能性を高める点に特に注意を払ったそうです。
サステナビリティ経営におけるPDCAサイクルがうまく回った事例と言えるでしょう。
三井物産
三井物産は、再生可能エネルギーの活用や環境配慮型事業への投資を行っています。
その結果、風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー事業の収益が増加し、環境配慮型の事業モデルが着実に拡大していきました。
同社はグローバルに事業を展開しており、持続可能な発展を目指す姿勢が評価されています。
これらの取り組みを行う際には、現地の環境やコミュニティへの配慮を徹底し、地域ごとのニーズに対応したプロジェクトの実施に注力しました。
三菱商事
三菱商事は、ESG(環境・社会・ガバナンス)を経営戦略の柱として掲げています。
同社の気候変動対策や資源の有効活用の結果として、温室効果ガスの削減目標達成に向けた進捗が見られ、同業他社との協働を通じて持続可能な社会の実現に貢献しているためです。
これらの取り組みを進める際には、事業活動が地域社会や環境に与える影響を事前に十分に評価し、持続可能性を保つためのリスク管理を徹底することに配慮しているのでしょう。
グローバル企業の事例
グローバル企業の成功事例は以下の通りです。
IKEA
IKEAは、環境負荷を抑えたサステナビリティ経営を掲げ、再生可能エネルギーや持続可能な素材の使用に積極的に取り組んでいます。
同社は「2030年までにすべての製品を100%再生可能素材またはリサイクル素材で作る」という目標を掲げ、サプライチェーン全体での素材の調達方法や製造プロセスを見直しているのです。
また、店舗や物流センターにソーラーパネルを設置し、現在では世界中のIKEA店舗が使用する電力の80%以上を再生可能エネルギーで賄っています。
この取り組みにより、IKEAは温室効果ガス排出量の削減にも成功し、製品のリサイクルプログラムを導入して顧客が不要になった家具を引き取り、再利用やリサイクルを推進しています。
このように、IKEAはサステナビリティ経営におけるPDCAサイクルをうまく回しながら、グローバルなスケールでの環境負荷低減を実現しているのです。
ユニリーバ
ユニリーバは、環境と社会に配慮した「サステナビリティ・リビング・プラン」を掲げ、サステナビリティ経営を推進しています。
この計画では、2030年までに自社の事業運営からの温室効果ガス排出量を半減すること、また使用するプラスチック包装の100%をリサイクル可能にすることを目標としているのです。
同社は製造過程における水の使用量や廃棄物の削減にも注力し、リサイクル可能な素材の使用を拡大するなどの取り組みを進めています。
また、サプライヤーやパートナー企業とも連携して、サプライチェーン全体での環境負荷の低減に取り組んでいます。
このように、地域社会やステークホルダーとの協力も進めることで、ユニリーバはグローバル企業としての責任を果たしつつ、持続可能な未来を目指しているのです。
サステナビリティ経営を成功させるためのヒント
サステナビリティ経営を成功させるためには、トップマネジメントのリーダーシップと全社的な取り組みが必要です。また、社員教育を通じて、サステナビリティに対する意識を高めることが重要となります。
継続的な改善と透明性のある情報開示を行うことが、信頼を高めるポイントです。
社内外に取り組みを浸透させ、効果を実感するまでには、中長期的な計画が必要になります。すぐに結果を出そうとせず、根気強く対処していきましょう。
まとめ
サステナビリティ経営は、企業が長期的な視点で環境や社会に対する責任を果たしながら、経済的な成長を目指す重要な経営手法です。
SDGsとの関連性や脱炭素経営の重要性を理解し、具体的な取り組みやメリットを把握することで競争力を高めることができます。
また、成功事例から学び、ガバナンスの強化やサプライチェーン全体での持続可能性を意識することが成功のカギです。
持続可能な社会を実現するために、企業は環境や社会への責任を重視し、全社的な取り組みを継続的に進めることが求められています。
サステナビリティ経営は、企業の未来を切り開くための重要な戦略であり、今後ますますその必要性が高まっていくでしょう。
上記で解説した内容を参考にしながら、サステナビリティ経営の導入を検討してみてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録