ARTICLE 記事一覧
-
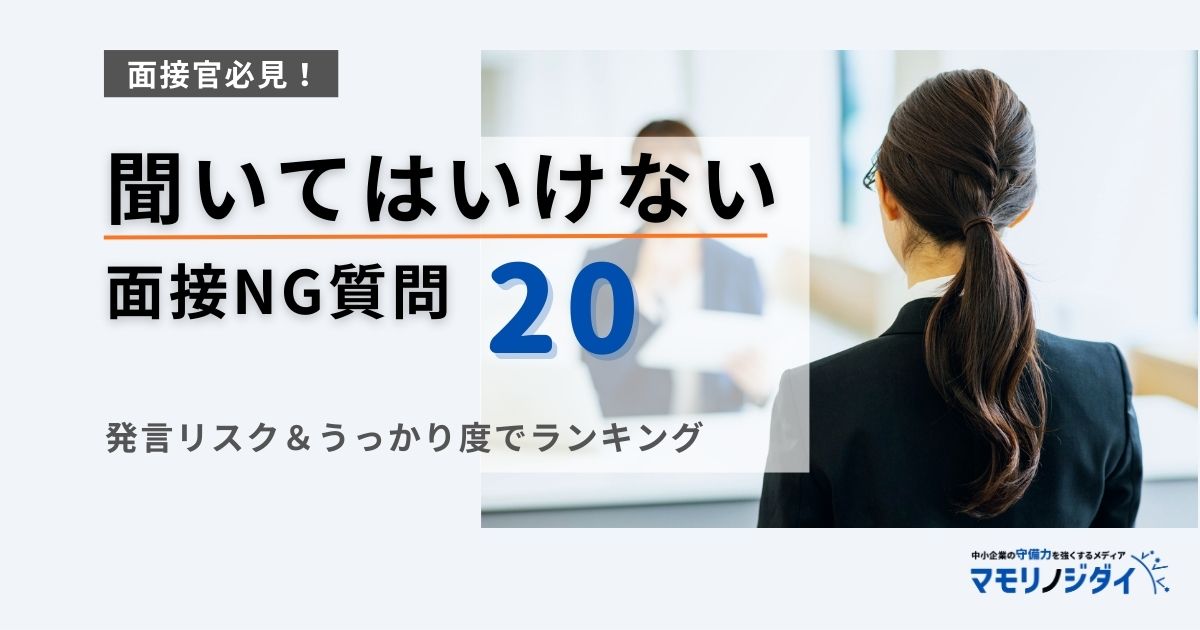
【面接官の基本】聞いてはいけないNG質問ランキング20 発言リスク&うっかり度で評価
4~5月は、新卒採用がもっとも盛り上がる時期です。マモリノジダイ読者の人事担当者の方にとっては、面接で忙しくなる季節ではないでしょうか。
そうしたなかで注意しなくてはならないのが【NG質問】です。
せっかく優秀な求職者との面接をセッティングできたとしても、質問内容によっては内定辞退、SNSで炎上、最悪のケースでは訴訟に発展してしまうこともあります。
-
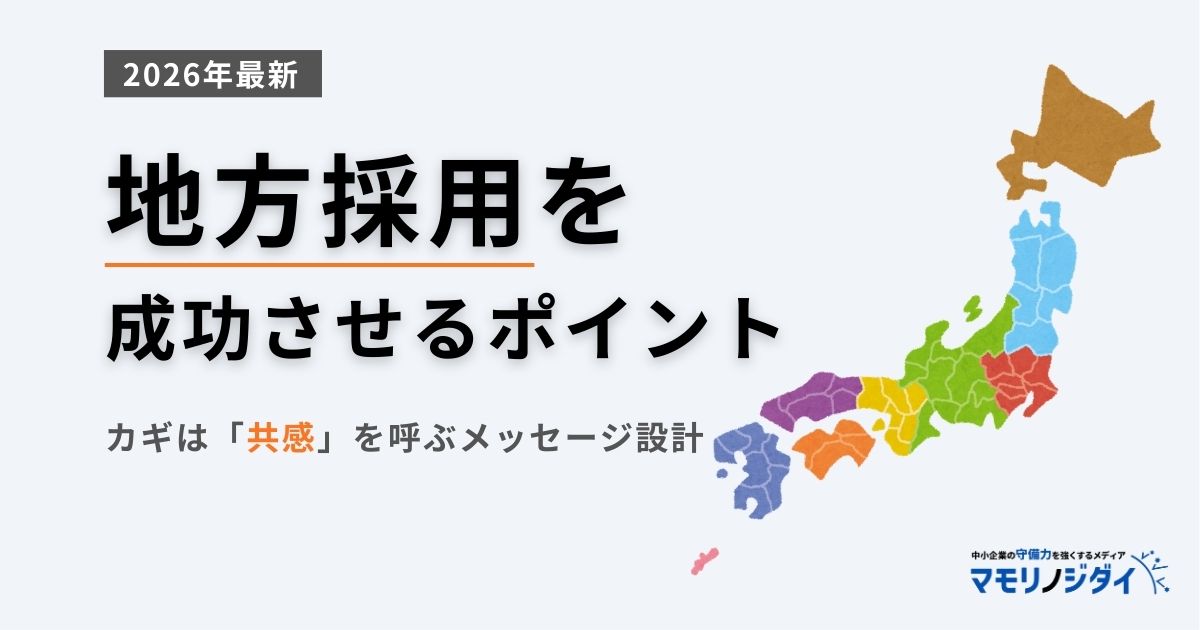
【2026年最新】地方採用を成功させるポイント!カギは共感を呼ぶメッセージ設計
今回、マモリノジダイ編集部では複数の資料とデータをもとに地方採用の現状と可能性について調査しました。
大手・大都市圏と戦わず、地方企業「だから」成功する、最新の採用ノウハウとメッセージ設計のヒントを紹介します。 -
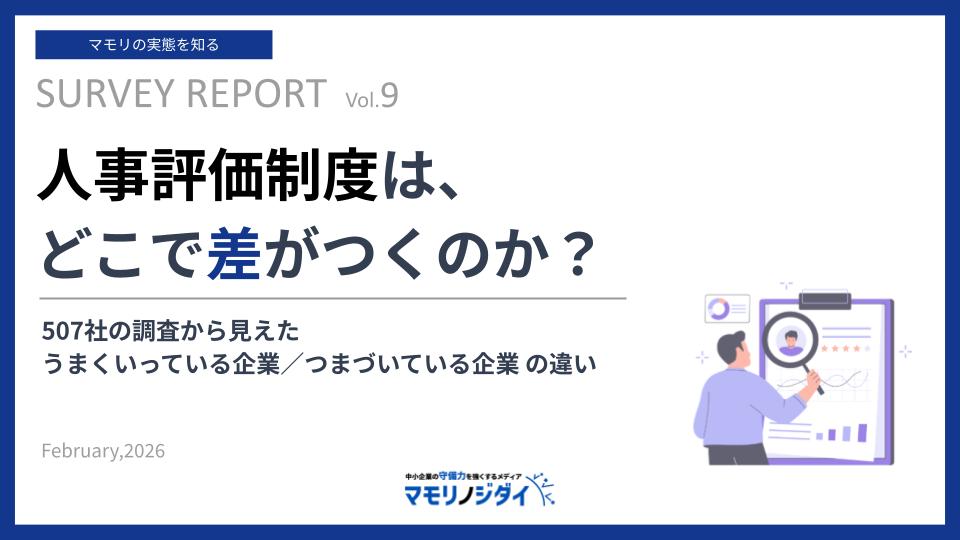
【507社の企業が回答】人事評価制度は、どこで差がつくのか?うまくいっている企業/つまづいている企業の違い
「人事評価制度に関する制度の整備状況」や「人事評価制度に対する従業員の要望」などを把握するべく、507社に対して人事評価制度に関する様々なアンケートを実施しました。
-
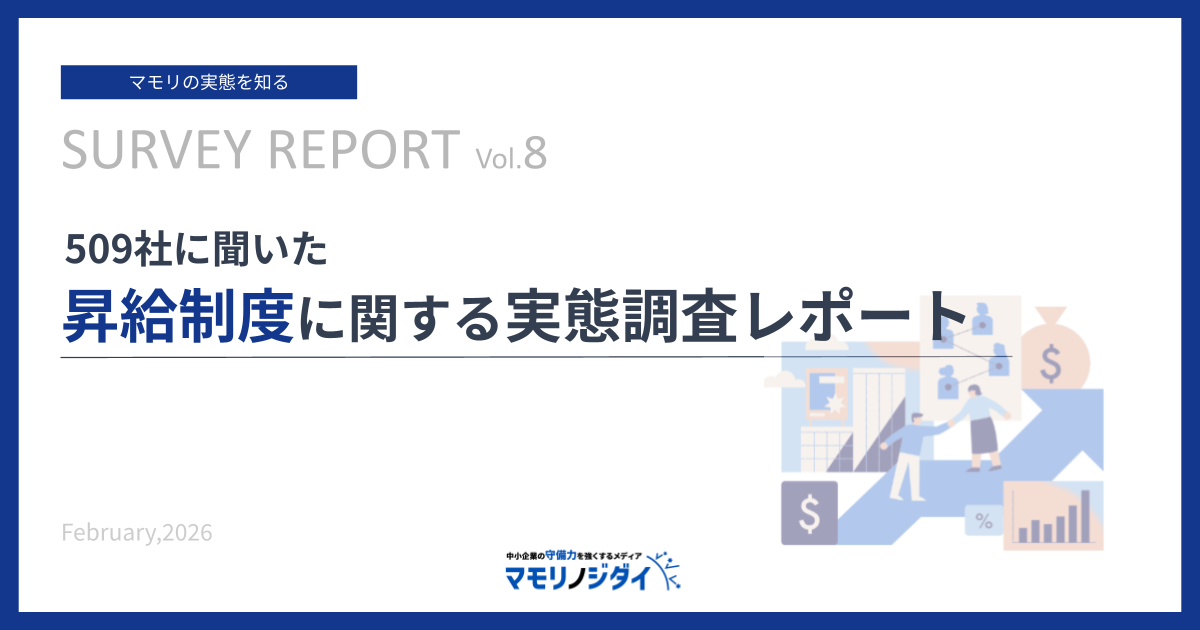
【509社の企業に聞いた】昇給制度に関する実態調査レポート
「昇給に関する制度の整備状況」や「昇給制度に対する従業員の要望」などを把握するべく、509社に対して従業員の退職に関する様々なアンケートを実施しました。
-

地域採用(エリア限定職)とは? 難しい理由・メリットデメリット・制度設計のポイントを解説
地域採用は、「エリア限定職」「地域限定正社員」などとも呼ばれ、転居を伴う転勤を前提としない雇用区分です。
「転勤なし」を希望する求職者が増えている昨今、人材確保の切り札として「地域採用」の導入を検討する企業が増えています。
しかし、いざ導入しようとすると、「給与設定をどうすべきか」「将来的に支店がなくなったらどうするのか」といった運用面での不安や、「募集しても思ったように人が集まらない」という壁に直面するケースも少なくありません。
地域採用は、従業員の定着率向上などの大きなメリットがある一方で、組織の柔軟性を損なうリスクもあり、戦略的な制度設計が求められます。
そこでこの記事では、地域採用の基本的な定義や注目される背景から、企業にとってのメリット・デメリット、そして「地域採用は難しい」と言われる理由について解説していきます。
地域採用を導入した後に後悔しないための成功のコツも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
-
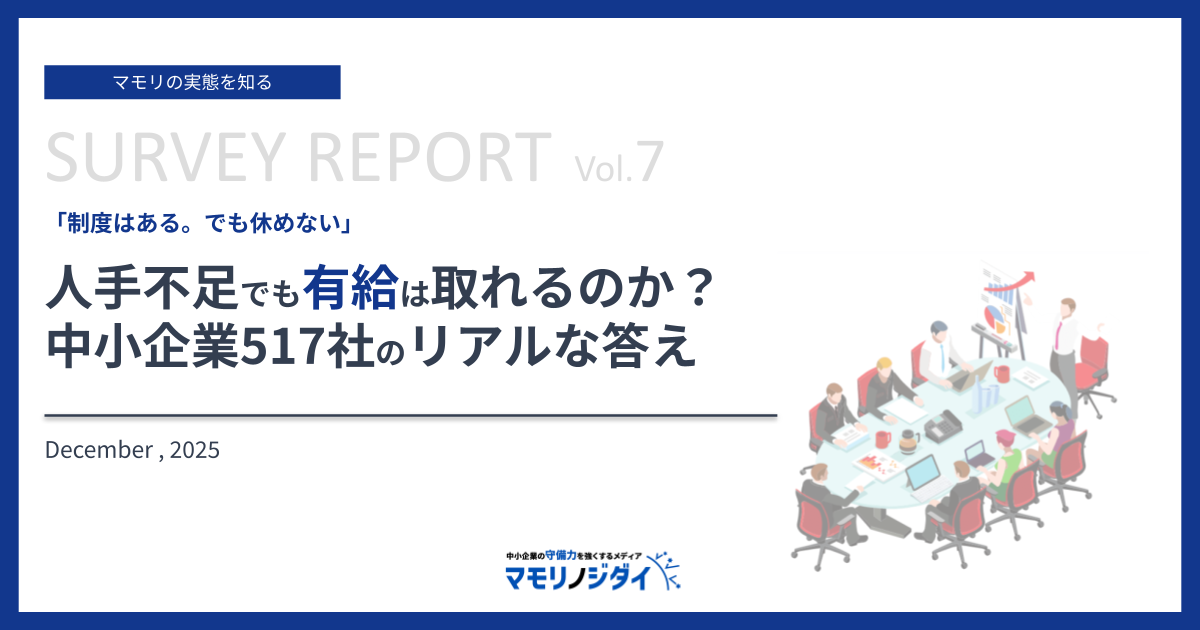
【517社の企業が回答】有給取得に関するルール整備やサポートの実態は?
「有給取得に関する制度の整備状況」や「有給取得を推進するための取り組み」などを把握するべく、517社に対して従業員の有給取得に関する様々なアンケートを実施しました。
-

採用コストが高い?新卒・中途の適正単価の計算と回収期間を縮める方法
「採用にかかる費用が高騰している」「大金を払って採用してもすぐに辞めてしまう」など、多くの中小企業が、このような悩みを抱えています。売り手市場が続く昨今、採用単価の上昇は避けられない課題です。
しかし、コストの高さ自体が問題なのではありません。かけたコストに見合う成果を得られていないことが最大のリスクなのです。
この記事では、採用コストの正しい計算方法や相場観といった基礎知識から、コストパフォーマンスを最大化するための具体的な戦略までを解説します。採用活動を単なる出費で終わらせず、企業の成長を支える投資へと変えていきましょう。
ただ人を採用するだけではなく、採用した人材が定着し、組織に貢献して初めて採用コストは回収されます。まずは「人が辞めない組織づくり」の基盤を見直してみませんか?
労務管理・定着支援・エンゲージメント向上のポイントをまとめた資料をぜひご活用ください。
-

【中小企業向け】デジタルフォレンジックとは?費用や調査のやり方を簡単に解説
「退職予定者が顧客リストを持ち出したかもしれない」「経理担当のパソコンから不審なログが見つかった」など、中小企業において内部不正や情報の持ち出しリスクは対岸の火事ではありません。
事実関係を解明し、会社を守るための有力な手段が「デジタルフォレンジック」です。聞き慣れない言葉かもしれませんが、簡単に言えば「デジタルの鑑識」のことです。
この記事では、デジタルフォレンジックの基礎知識から、調査のやり方、費用相場まで、経営者や担当者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
デジタルフォレンジック以前に重要なのは、トラブルを「未然に防ぐこと」です。社内のどこにリスクが潜んでいるのか、情報漏洩の主な原因と具体的な対策のまとめ資料をご用意しました。
以下で無料ダウンロードできますので、この記事とあわせて貴社のリスク管理にお役立てください。
-

ジョブ型雇用とは?特徴・メンバーシップ型との違い・導入ポイントをわかりやすく解説
近年、多くの企業で注目されているのが「ジョブ型雇用」です。特にテレワークや副業の普及、成果主義の浸透といった働き方の変化を背景に、従来の「メンバーシップ型雇用」からの転換を検討する動きが活発化しています。
本記事では、ジョブ型雇用の定義から、メンバーシップ型との違い、企業・従業員双方のメリット・デメリット、導入プロセスや成功事例をわかりやすく解説しました。
また以下の資料では中小企業の人事担当の方に向けて、労務・定着・エンゲージメントの観点から人が辞めにくい組織の作り方を解説していますので、こちらも参考にしてください。
-

企業が抱える人材育成の課題とは?解決策や具体的な育成例を紹介
「優秀な人材がなかなか育たない」
「現場が忙しすぎて教育に時間を割けない」このように、多くの企業が人材育成の重要性を理解していながらも、具体的な方法やリソース不足に悩み、思うような成果を出せずにいます。
少子高齢化による人手不足が進む今、社員一人ひとりの能力を最大限に引き出すことは、企業の存続を左右する最重要課題です。
そこでこの記事では、人材育成の基礎知識や類語との違いといった基本から、多くの企業が直面する共通の課題、そしてOJTやeラーニングといった具体的な育成手法のメリット・デメリットまで、人材育成に関して幅広く解説していきます。
-

中小企業の海外進出を成功へ導く!駐在員の年収・英語力・事務所のポイント
中小企業にとって海外進出は、新たな市場を開拓する大きなチャンスであると同時に、未知のリスクとの戦いでもあります。
その成否を握る最大のカギは、現地に派遣される「駐在員」の存在です。しかし、多くの企業が「誰を派遣すべきか」「給与はどう設定するか」「現地でのサポートはどうあるべきか」という課題に直面しています。
適切な人選や待遇、そしてリスク管理ができていない場合、駐在員の早期帰任や現地トラブルなど、経営に大きなダメージを与える可能性があるのです。
この記事では、海外駐在員の基礎知識から、給与のリアル、事務所の形態、そして企業の「守り」としてのサポート体制まで、中小企業が知っておくべきポイントを網羅的に解説します。
-

事業承継とは?中小企業向け税制・補助金・M&Aをわかりやすく解説
「黒字廃業」という言葉が現実味を帯びる昨今、中小企業にとって事業承継は避けては通れない最重要課題です。
多くの経営者が「いつかは」と考えていますが、具体的に何から始めるべきか、税金や法律はどうなるのか、漠然とした不安を抱えています。
この記事では、承継の基本・3つの手法・税制や補助金情報を分かりやすくまとめ、会社や従業員を守るために知っておきたいポイントを整理します。
-

福利厚生で「選ばれる会社」へ!導入メリット・人気の種類と節税になるルールを解説
中小企業の経営において、人材の確保と定着は常に悩ましい課題です。「優秀な人材を採用したいが、大企業のような高い給与は出せない」「社員には長く働いてほしいが、具体的な施策が思いつかない」とお悩みの企業も多いのではないでしょうか。
そこで注目したいのが「福利厚生」の充実です。福利厚生は、単なる従業員へのサービス提供にとどまらず、企業としての魅力を高め、節税効果も期待できる重要な経営戦略の一つです。
この記事では、福利厚生の基礎知識から、中小企業におすすめの種類や選び方、経費として計上するためのルールまでをわかりやすく解説します。自社を「選ばれる会社」へと成長させるためのヒントとしてご活用ください。
-

その一言、大丈夫?職場のマイクロアグレッション|意味と原因、具体例、対策
「良かれと思って言ったのに、相手を傷つけてしまった」「職場の雰囲気がなんとなく悪いが、原因がわからない」という原因は、悪意のない「小さな攻撃=マイクロアグレッション」かもしれません。
個人の尊厳を傷つけ、職場のエンゲージメントや生産性を低下させるマイクロアグレッションは、今や見過ごすことができません。
この記事では、マイクロアグレッションの意味、具体的な事例、発生原因、そして組織と個人で取り組むべき対策を解説します。
職場のハラスメントや人間関係の課題解決のヒントをお探しではありませんか?ハラスメントの実態調査から、具体的な対策事例、研修のポイントまでを網羅した資料を無料でダウンロードいただけます。
多様な人材が安心して働ける職場づくりに向け、ぜひご活用ください。
-
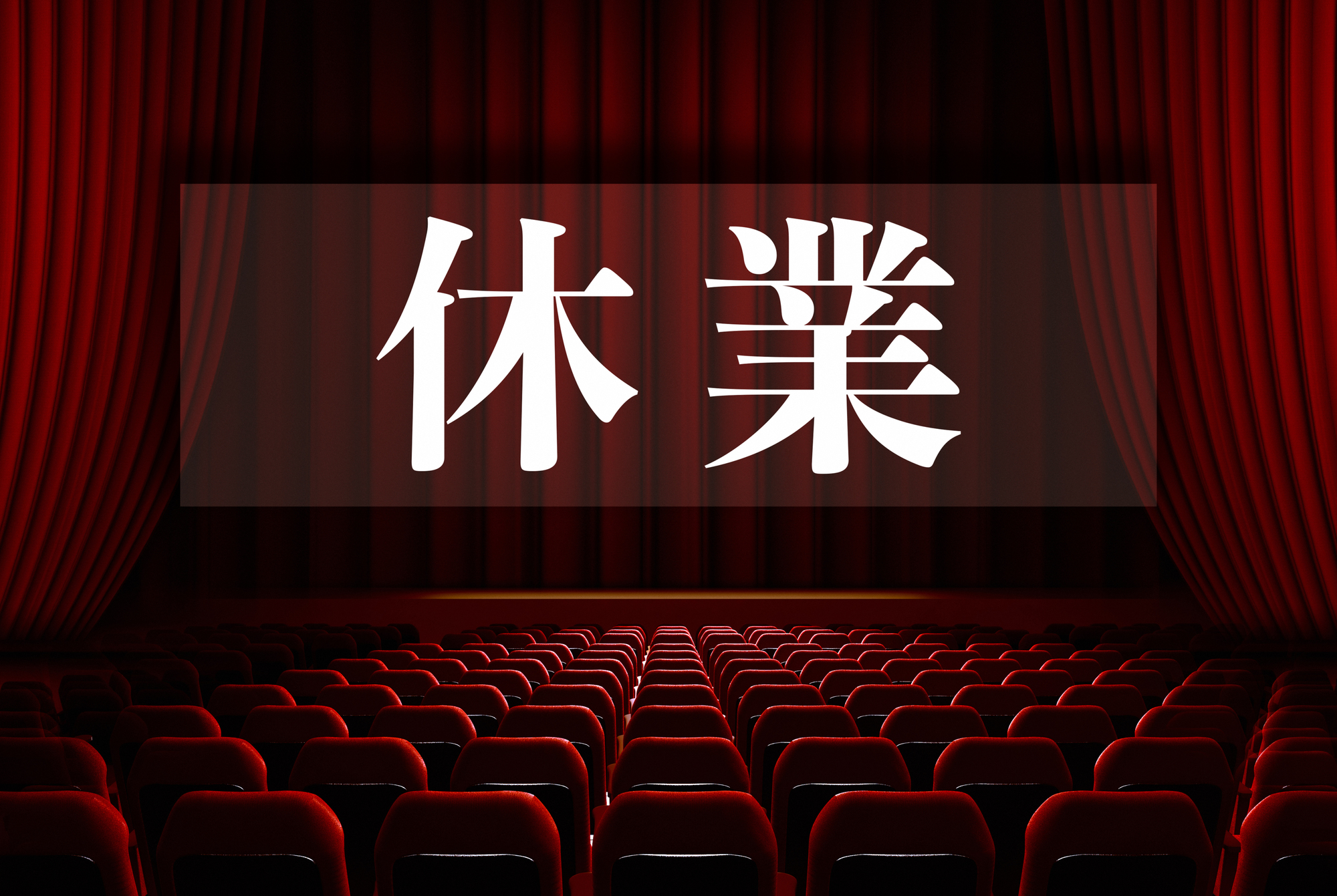
休業手当が出ないと違法?労働基準法に基づく支払い義務と計算方法、手続きの完全ガイド
「急な受注減で工場を休止させることになった」「社内設備の故障で仕事ができない」といった事態に直面した際、避けて通れないのが休業手当の問題です。従業員に仕事を休んでもらう以上、会社には給与の補填をおこなう義務が生じます。
しかし、休業手当を「いくら支払えばいいのか?」「パートやアルバイトにも必要なのか?」と迷う経営者も少なくありません。休業手当を適切に支払わないと、労働基準法違反となるだけでなく、従業員との信頼関係を大きく損なうリスクがあります。
この記事では、休業手当の定義から正確な計算方法、注意点まで、実務に役立つ情報を網羅して解説します。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録






