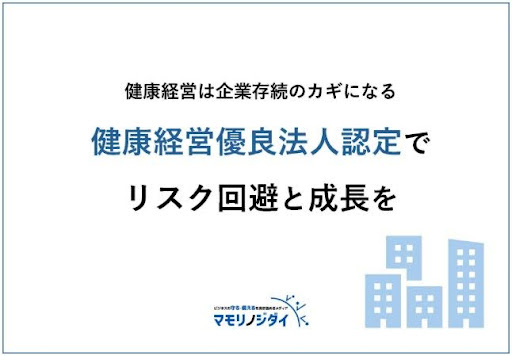カーボンニュートラル時代を生き抜く中小企業の経営術とは?脱酸素との違いも

2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、中小企業を取り巻く経営環境は大きく変化しています。
取引先からの要請や規制強化など、さまざまな課題に直面する中、多くの経営者がどこから手をつければよいのか、費用はどうするのかといった悩みを持っています。
しかし、カーボンニュートラルへの取り組みは、単なる負担ばかりではなく、ビジネスチャンスでもあるのです。
この記事では、中小企業がカーボンニュートラルに取り組むための方法を学び、経営を守りつつ成長させるためのヒントをお伝えします。
目次
カーボンニュートラルとは?
地球温暖化や気候変動への対応が国際的な課題となっており、多くの国や企業が2050年までにカーボンニュートラルを達成するための目標を掲げています。
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指す取り組みです。
これには、企業や個人が排出するCO2などの温室効果ガスを再生可能エネルギーの利用や省エネ対策で削減し、残った排出量を森林保全や環境技術による吸収・除去で相殺するという考え方が含まれます。
出典)環境省「カーボンニュートラルとは - 脱炭素ポータル」
なぜ今中小企業にとってカーボンニュートラルが重要なのか
気候変動への対応が国際的な課題として深刻化する中、企業規模にかかわらず、持続可能な経営を求められる時代となっています。
中小企業にとっても、環境への責任を果たすという社会的な要素以外に、ビジネスの未来を守り、新たな事業チャンスを創出する重要な要素となるのです。
カーボンニュートラルへの対応は、コストの増加以外に新たなビジネスチャンスを生み出すきっかけにもなります。
省エネ技術の導入や再生可能エネルギーの活用は、長期的な経費削減につながります。
また、環境に配慮した商品やサービスを提供することで、新しい市場を開拓する機会が生まれるのです。
カーボンニュートラルをはじめとする環境対策が進む中小企業は、顧客や取引先、投資家からの信頼を集めやすくなります。
この信頼が、中小企業の価値を向上させ、事業を拡大させる土台になります。
日本政府におけるカーボンニュートラル支援策の活用
カーボンニュートラルへ取り組みを行う企業に対し、日本政府はさまざまな支援策を打ち出しています。
これらを活用することで、中小企業はリソース不足を補い、カーボンニュートラルへの対応をスムーズに進められるでしょう。
「グリーンイノベーション基金」を活用
グリーンイノベーション基金は、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、革新的な技術開発を支援するため、経済産業省によって設立されました。
この基金は、エネルギー転換や温室効果ガス削減に貢献するプロジェクトに対し、10年間で約2兆円を投じる大規模な支援策です。
中小企業が活用する際は、対象となる14分野に関連した革新的な技術開発や生産プロセス改善といった具体的な提案が必要になります。
省エネ設備の導入や研究開発のための支援を受けるなどに活用できるでしょう。これにより、中小企業もカーボンニュートラルへの貢献と事業の成長を同時に実現できます。
出典)経済産業省「グリーンイノベーション基金」
「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」を活用
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制は、企業が脱炭素化に向けた設備投資を行う際、税負担を軽減する制度です。
中小企業が活用する際は、温室効果ガス削減や省エネに貢献する設備の導入に対し、最大で法人税額20%控除、もしくは特別償却50%を選択できます。
適用を受けるには、所定の要件を満たした事業計画の作成と認定が必要となりますが、初期投資の負担を軽減しながらカーボンニュートラルへの対応を進めることができます。
出典)経済産業省「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」
中小企業ができるカーボンニュートラルへのアプローチ
カーボンニュートラルが、中小企業にとっても避けられない経営課題であることは理解していても、限られたリソースの中でどのように取り組むべきか悩む方もいます。
以下では、中小企業が実践できる具体的なアプローチを紹介します。
再生可能エネルギーの導入
中小企業におけるカーボンニュートラルの取り組みの中で、最も効果的な手段の一つが再生可能エネルギーの活用です。
事務所や工場で、太陽光発電パネルの設置や再生可能エネルギーを供給する電力会社への契約変更などを行うことで、CO2の排出量を大幅に減らせます。
その際、政府や自治体からの補助金を活用することで、初期費用を抑えることが可能です。
温室効果ガスの排出量を可視化
カーボンニュートラルを実現するためには、温室効果ガスの排出量を定期的に確認して現状を把握することが重要です。
専門家やツールを活用し、事業活動で排出されるCO2の量を測定し、削減目標を設定しましょう。
簡易的な測定ツールや無料のオンラインツールを活用することで、中小企業も低コストで始められます。
省エネ対策の実施
省エネ対策は、中小企業でもすぐに始められるカーボンニュートラルへのアプローチの一つです。
中小企業がすぐ始められるアプローチの例:
- LED照明への切り替え
- 効率の高い空調設備の導入
- 断熱対策の実施
- エアコンの温度設定ルールの徹底
- 使用機器の電源に関するルールの徹底
このような取り組みは、エネルギーに関するコストの削減だけでなく、持続可能な企業文化の形成にもつながります。
日本企業のカーボンニュートラル取り組み事例
すでにカーボンニュートラルの取り組みを進めている企業は、日本国内でも多くあります。
ここでは、5社から中小企業が参考にできる事例を探っていきます。
三井不動産に学ぶカーボンニュートラル
三井不動産は「2050年カーボンニュートラル」を目標に掲げ、不動産業界で以下のような温室効果ガス削減の取り組みを行っています。
- 太陽光発電設備の導入
- 省エネ改修の推進
- 再生可能エネルギーを利用した建物運営
- テナントや地域と連携した持続可能な街づくり
自社に合わせた省エネ設備の導入や取引先との協力により、中小企業も競争力を高められます。
イオンに学ぶカーボンニュートラル
イオンは「イオン 脱炭素ビジョン2050」を掲げ、以下のように店舗での省エネ設備導入や再生可能エネルギーの活用を積極的に推進しています。
- LED照明への切り替え
- 空調の効率化
- 環境配慮型の商品開発・販売
とくに、比較的取り組みやすい省エネ対策から着手していることと、ステークホルダーを巻き込んだ活動展開は、中小企業が学ぶべき点と言えるでしょう。
トヨタ自動車に学ぶカーボンニュートラル
トヨタ自動車の「2050年カーボンニュートラル」に向けた取り組みは、製造業における環境対策のお手本となっています。
製品開発から製造工程まで、以下のような取り組みを展開しているのが特徴です。
- 電気自動車や燃料電池車など次世代自動車の開発
- 工場での太陽光発電の導入・省エネ技術の活用
- リサイクル部品・環境に配慮した材料の活用
事業活動全体でCO2削減を進めていることが特筆すべき点となっています。
ヤマト運輸に学ぶカーボンニュートラル
物流業界におけるカーボンニュートラルに対する取り組み事例は、ヤマト運輸が代表的です。ヤマト運輸では、以下のような具体的な取り組みを行っています。
- 配送車両の電動化
- 環境配慮型の配送センター導入
- 配送ルートの最適化
- エコドライブの推進
- 荷物の積載効率向上
- 再配達削減に向けた受取場所の多様化
- 環境に配慮した梱包材の採用
日常業務の改善によりCO2削減に力を入れている点は、中小企業も参考になります。
大日本印刷に学ぶカーボンニュートラル
大日本印刷では、生産工程での省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用を推進する以下のような取り組みを行っています。
- 環境負荷を低減する技術の開発
- 環境配慮型の包材・建材の提供
- CO2排出量の可視化と削減
- 従業員への環境教育
CO2排出量の可視化や環境教育は、中小企業でも進めやすい取り組みと言えます。
中小企業におけるカーボンニュートラルの課題と克服法
カーボンニュートラルが求められる時代の中で、中小企業も無関係ではいられなくなっています。しかし、大企業と比較するとリソースが限られている点は大きな課題です。
ここでは、中小企業が直面するカーボンニュートラルの課題と、それを克服する具体的な方法を紹介します。
最大の課題は資金とリソース不足
中小企業がカーボンニュートラルに取り組む上で、最も大きな障壁は資金とリソース不足です。
省エネルギー設備の導入、再生可能エネルギーへの切り替え、排出量の可視化と管理には、初期投資や専門的なノウハウが必要となります。
克服法:
公的支援を最大限活用することで、資金やリソース不足を解決できます。政府や地方公共団体では、中小企業向けの補助金や助成金を多数提供しています。
また、専門家によるコンサルティングが受けられるプログラムを活用することも可能です。
正確なCO2排出量の測定と検証の難しさも課題
中小企業が独自に自社のCO2排出量を把握することは、難しいでしょう。
削減計画を策定するには高精度なデータが必要ですが、現在の測定技術や算出方法では、正確さに欠けることがたびたび問題になっています。
克服法:
簡易的なツールからはじめ、現状ではCO2排出量がどのくらいあるのか、把握することが大切です。
計測を重ねることにより、データが蓄積されるため、検証が進めやすくなります。
まとめ
カーボンニュートラルは、大企業だけの課題ではありません。中小企業でも、エコアクション21などを活用し、できることから着実に始められます。
企業の持続可能性を高め、新たな機会を生み出す経営戦略として、カーボンニュートラルの取り組みを進めていきましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録