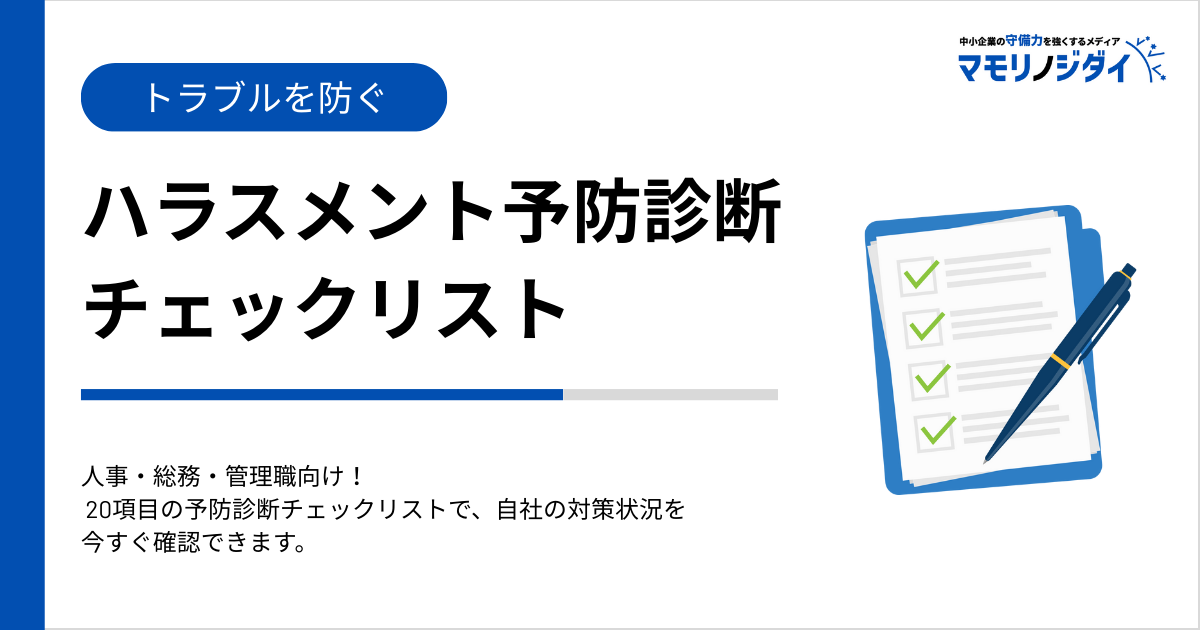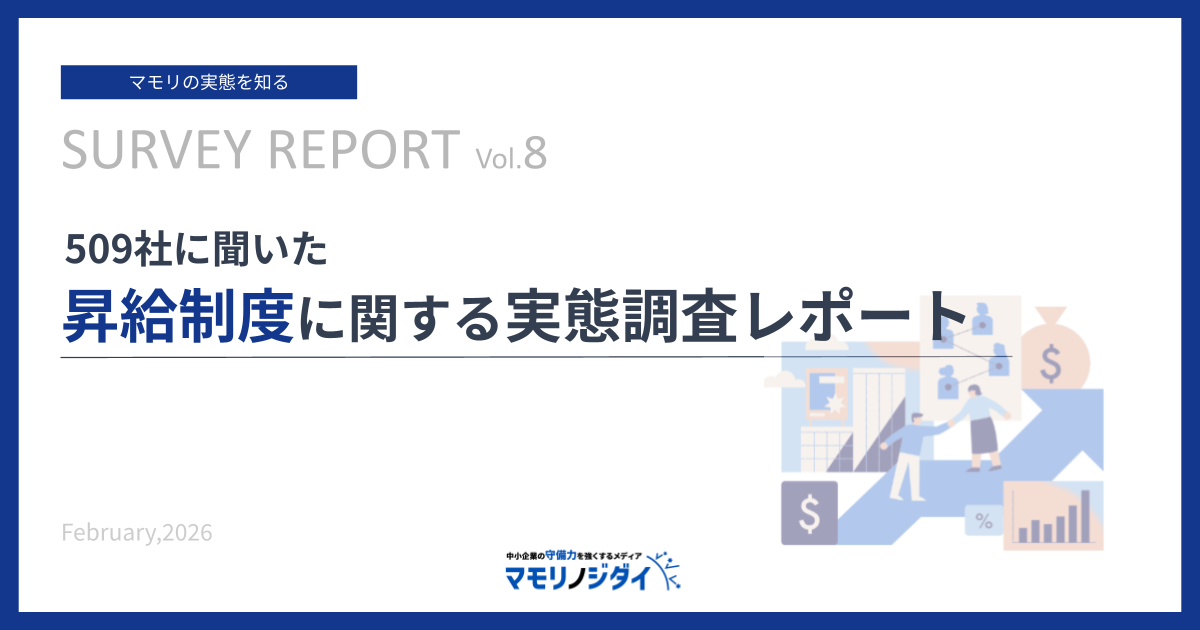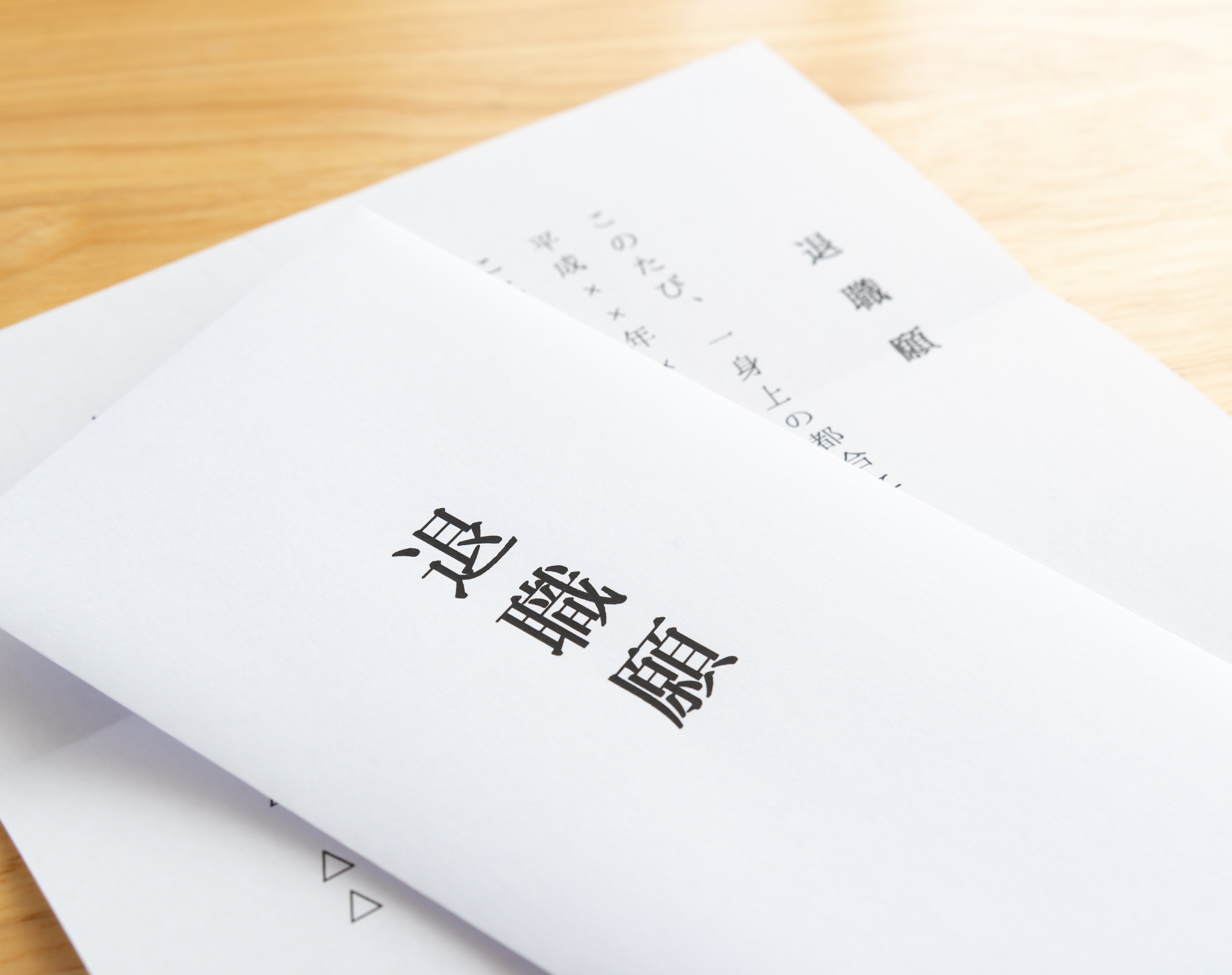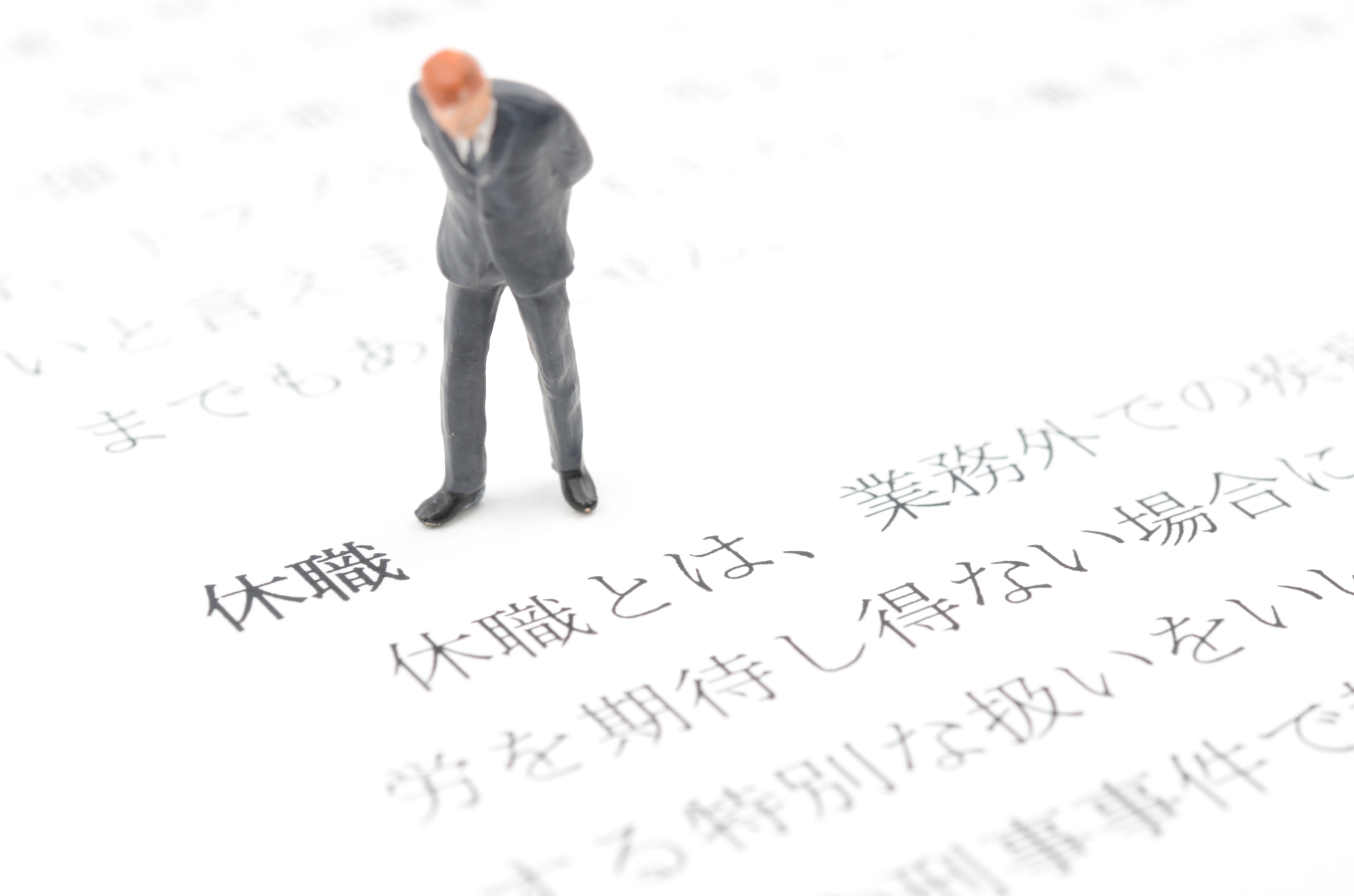クレームを生まない組織作りとは?クレーム対応のコツや例文も紹介

お客様からのクレームは企業にとって避けたいものですが、適切に対応することで顧客満足度向上や企業成長の機会となります。
クレームを未然に防ぐ組織作りは重要であり、社内体制の構築、マニュアル整備、従業員教育などが挙げられます。
しかし、顧客の期待は多様で「お門違いなクレーム」も存在するため、完全に防止することは難しいでしょう。
重要なのは「クレームは必ず発生する」という前提に立ち、発生した際に迅速かつ適切に対応し、顧客の信頼を損なわないことです。
クレームを分析し、対応策を検討、マニュアル化することで、あらゆるタイプのクレームに対応できるよう備えましょう。
この記事では、これらの情報を通して、中小企業がクレームを「成長の機会」へと転換するヒントを提供することを目指しています。
目次
なぜクレームは発生するのか?
クレームが発生する原因は多岐に渡りますが、大きく分けると以下の3つに分類できます。
| クレーム発生原因 | 具体例 |
| 商品・サービスの不具合 | 製品の欠陥、品質の低下、サービスの手順ミスなど |
| 従業員の対応 | 従業員の知識不足、説明不足、不適切な言動など |
| 顧客の誤解・期待とのギャップ | 顧客が商品・サービスに対して抱いていた期待と、実際の内容との間にずれが生じた場合 |
これらの原因を理解することで、クレームを未然に防ぐための対策を講じることが可能になります。
クレームを生まない組織を作るためのポイント
クレームを最小限に抑え、顧客満足度を高めるためには、組織全体でクレーム予防に取り組むことが重要です。以下に、クレームを生まない組織を作るための具体的なポイントを紹介します。
クレーム対応を担当者だけに任せない
クレーム対応は特定の担当者だけに任せるのではなく、組織全体で共有すべき課題として捉えることが重要です。
クレーム情報を社内で共有し、原因を分析することで、再発防止策を講じることが可能になります。また、担当者への負担を軽減し、精神的な負担を軽減する効果も期待できます。
クレームに対してのマニュアルを整備する
クレーム対応のマニュアルの整備は、担当者による対応のばらつきをなくし、迅速かつ適切な対応を実現するだけでなく、二次クレームを防ぎ、顧客満足度向上に不可欠です。
マニュアルには、以下の内容を含めると安心です。
- 基本的な心構え
- 状況に応じた謝罪の言葉の例
- 事実確認の手順と質問例
- 解決策の提示方法
- FAQ
- エスカレーションフロー
- 二次クレームを防ぐための注意点
- 記録と報告の手順
- 個人情報保護
- マニュアルの更新頻度など
とくに、共感と傾聴、否定的な言葉を使わないこと、曖昧な返事をしないこと、迅速な対応を心掛けることは、二次クレームを防ぐ上で重要です。
定期的な見直しと研修を行うことで、クレーム対応の品質向上と二次クレームの防止につなげます。
組織内での情報共有を徹底する
クレーム情報は、担当者だけでなく、関連部署や経営層にも共有することが重要です。情報共有を徹底することで、問題の早期発見、迅速な対応、再発防止策の策定につながります。
社内共有ツールや会議などを活用し、スムーズな情報共有体制を構築しましょう。
それでもクレームは必ず発生する
どんなに予防策を講じても、顧客の期待水準は多様であり、「お門違いなクレーム」も存在するため、クレームの完全な防止は困難です。
重要なのは、「クレームは必ず発生する」という前提に立ち、発生したクレームに対して迅速かつ適切に対応し、顧客の信頼を損なわないことです。
クレームを調査・記録し、対応策を検討、マニュアル化することで、あらゆるタイプのクレームに対応できるよう備えることが現実的であり、何より「二度と同じクレームを起こさない」ことが重要となります。
上手なクレーム対応のコツ【例文付き】
以下に、状況別のクレーム対応のコツと例文を紹介します。
自社の商品やサービスに不具合があった場合
- まずはお詫びの言葉を述べる:お客様の不快な気持ちに寄り添い、真摯に謝罪することが大切です。
- 事実確認を行う:具体的にどのような不具合があったのか、状況を丁寧にヒアリングします。
- 解決策を提示する:交換、修理、返金など、適切な解決策を提示します。
- 感謝の言葉を伝える:クレームを伝えていただいたことに感謝の意を伝えます。
例文:
「この度は、弊社の製品の不具合により、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。詳しく状況をお伺いできますでしょうか?(事実確認)… 状況を把握いたしました。大変申し訳ございませんが、至急代替品をお送りさせていただきます。(解決策)貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。」
現場担当者にミスや問題行動があった場合
- 事実確認を丁寧に行う:お客様の言い分だけでなく、担当者の話も聞き、客観的に状況を把握します。
- 必要に応じて謝罪する:担当者のミスが事実であれば、会社として謝罪します。
- 再発防止策を説明する:今後同じことが起こらないよう、どのような対策を講じるのかを説明します。
例文:
「この度は、弊社の担当者の対応により、ご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございません。詳細を伺ってもよろしいでしょうか?(事実確認)… 状況を確認いたしました。担当者の不適切な言動により、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今後は、社員教育を徹底し、再発防止に努めてまいります。」
自社に非が無い場合
- お客様の言い分を丁寧に聞く:お客様の感情を理解し、最後まで話を聞くことが重要です。
- 冷静に状況を説明する:事実に基づき、丁寧に状況を説明します。
- 理解を求める:お客様に納得していただけるよう、丁寧に説明を尽くします。
例文:
「貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。詳しくお話をお聞かせいただけますでしょうか?(傾聴)… 状況を承知いたしました。ご指摘の点につきましては、〇〇という状況でございまして…(説明)… このように、今回は弊社の責任ではないことをご理解いただければ幸いです。」
参考記事:正しいクレーム対応とは?NG行為やクレームを減らす予防法
中小企業にとってクレームは「宝の山」でもある
クレームは、企業にとってネガティブな出来事と捉えられがちですが、見方を変えれば、顧客の貴重な意見を直接聞くことができる貴重な機会でもあります。
クレームを真摯に受け止め、改善することで、商品・サービスの品質向上、顧客満足度向上、ひいては企業成長につなげられるでしょう。
まとめ
クレームを生まない組織を作るためには、組織全体でクレーム予防に取り組むことが非常に重要です。
一部の担当者だけに責任を負わせることは避けましょう。経営層を含む全従業員がクレーム予防の意識を持ち、日々の業務に取り組むことで、未然に防げるクレームは数多く存在します。
しかしながら、どんなに注意を払っていても、クレームを完全にゼロにすることは難しいのが現実です。
万が一クレームが発生した場合は、迅速かつ適切に対応し、顧客の信頼を損なわないように努めることが求められます。
初期対応の遅れや不適切な対応は、顧客の不満を増大させ、二次クレームに繋がる可能性もあるため、注意が必要です。
丁寧な謝罪と状況のヒアリングを行い、誠意をもって対応することで、顧客の理解を得られる場合も少なくありません。
とくに中小企業では、クレームを単なるネガティブな出来事として捉えるのではなく、「宝の山」と捉え、成長の糧とすることで、更なる発展を遂げられるのです。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録