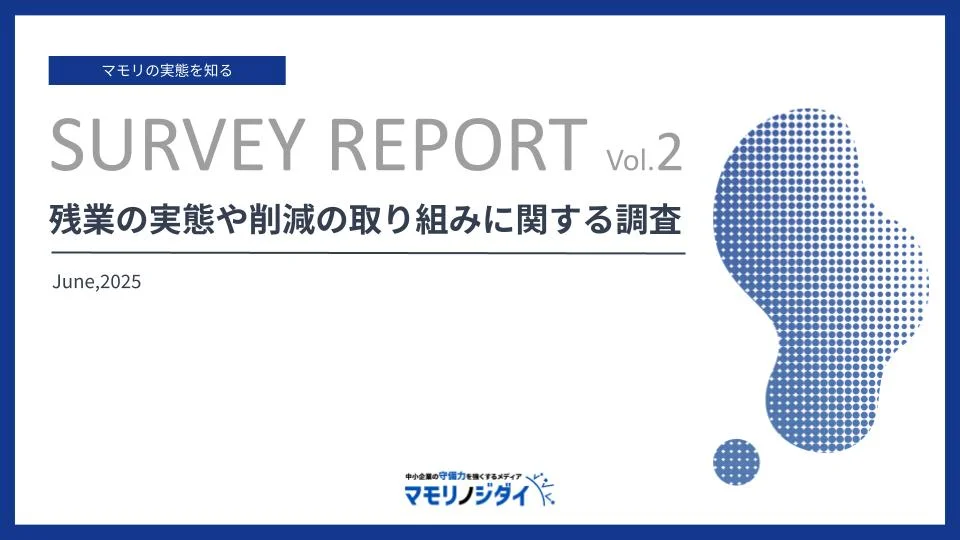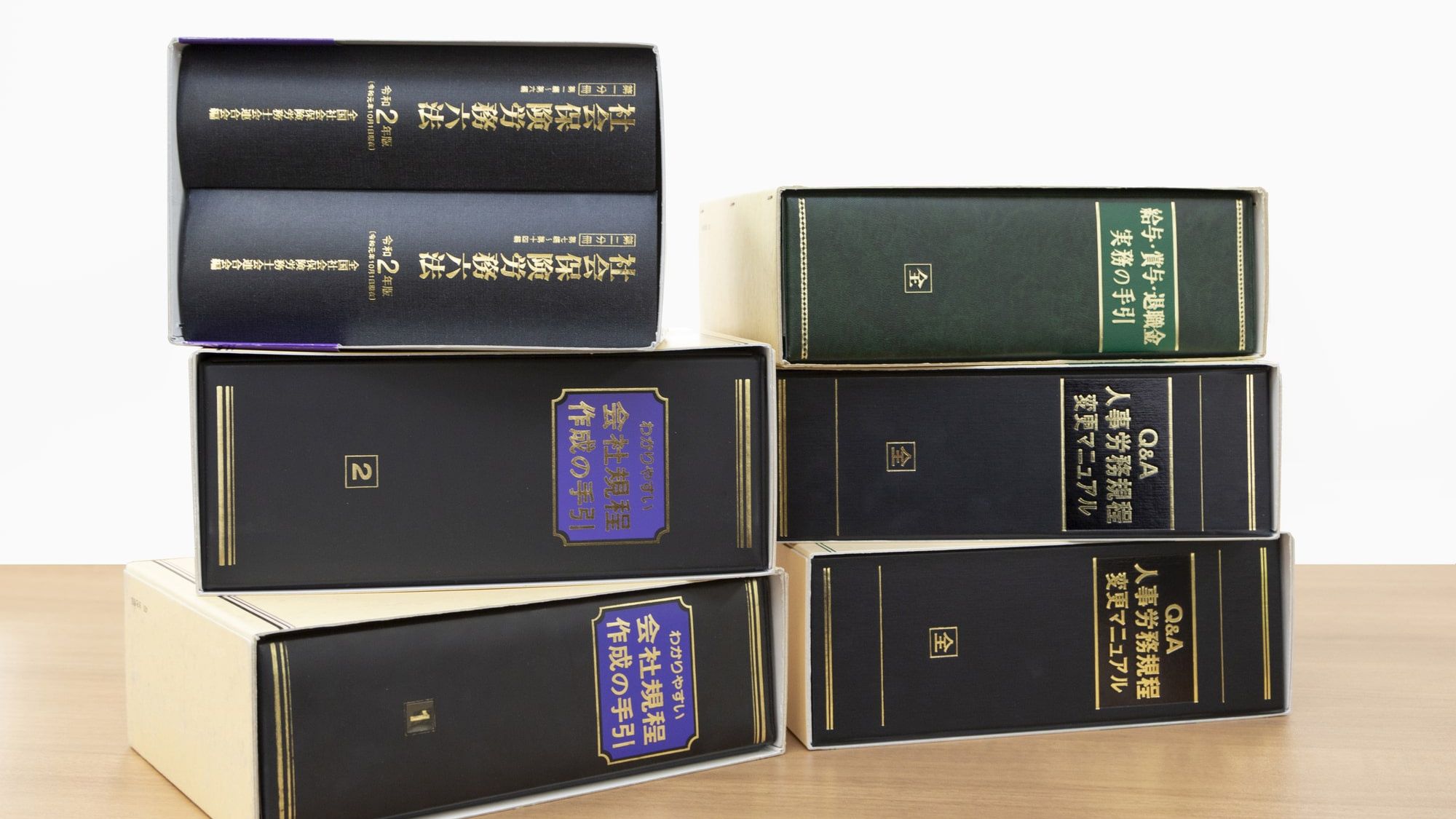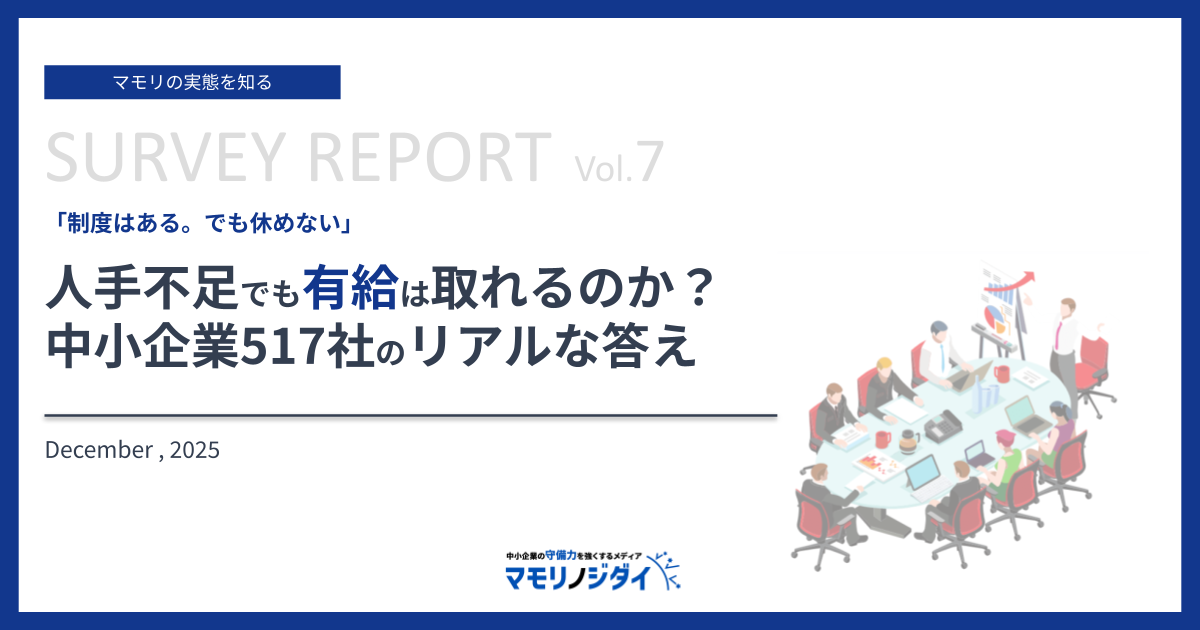残業時間の上限を超えるとどうなる?中小企業が把握しておくべきポイント
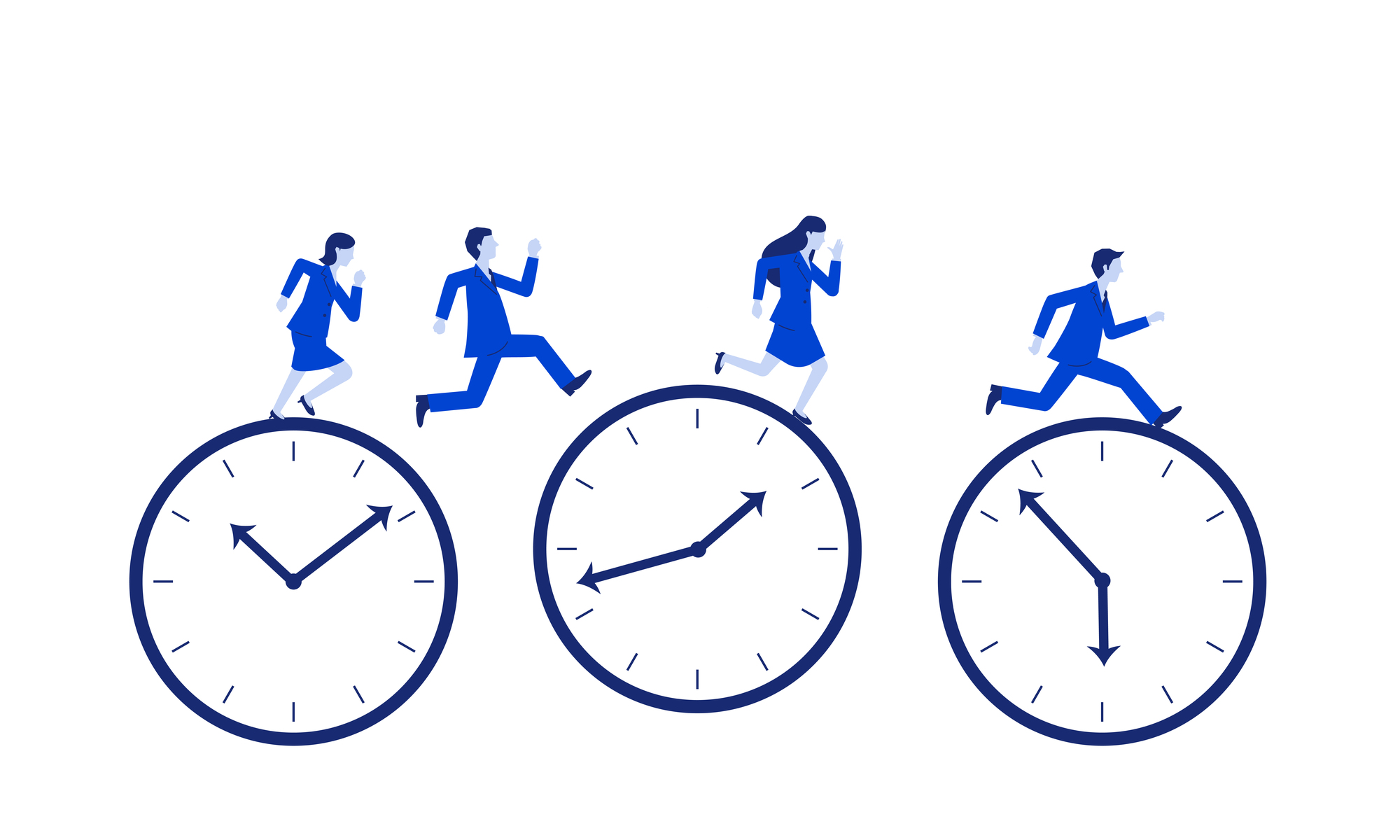
働き方改革関連法により、企業は従業員の残業時間を厳密に管理する必要に迫られました。
「従業員側に文句がないのならば、残業してもらってもいいだろう」
このような考え方はもはや通用しないのです。
いくら従業員が「残業したい」と言っても、守らなければならないラインが明確に決められており、違反すれば罰則が科される可能性もあります。
そこで本記事では、残業規制に関して、特に中小企業の経営層が意識すべきことを中心に詳しく解説していきます。
目次
「残業時間の上限規制」とは
「残業時間(時間外労働)の上限規制」とは、働き方改革の一環として導入されたものです。
この規制は、労働時間の過剰な増加を防ぎ、労働者の健康と生活の質を向上させることを目的としています。
規制の内容としては、原則「月45時間」・「年360時間」を超える残業は許されない、というものです。
臨時的な事情があり、労使間での合意もあるという場合のみ、上記の上限を超えることが許されるものの、以下のルールは必ず守らなければなりません。
| ■時間外労働が年720時間以内 ■時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満 ■時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内 ■時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度 |
出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」p.4
この規制は、過労死やメンタルヘルスの問題が深刻化している日本において重要な取り組みです。
企業には、時間外労働の上限を守るための労働環境の整備や、労働者の健康を守るための対策が求められています。
残業時間の上限規制について知っておくべき基礎知識
この項目では、残業時間の上限規制を遵守し、企業としての責務を果たすために必要な基礎知識について紹介していきます。
法定労働時間を超える残業には36協定の締結が必要
従業員に対して、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える残業や、法定休日(毎週少なくとも1日)を超える休日労働をさせる場合は、必ず労使間で36協定を締結しなければなりません。
| 時間外労働(残業)をさせるためには、36協定が必要です! ■労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。 ■法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結所轄労働基準監督署長への届出が必要です。 ■36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。 |
出典)厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」p.1
どんな事情があろうと、36協定を締結せずに法定労働時間や法定休日の範囲を超える残業をさせることはできませんので注意が必要です。中小企業では、総務担当者が経理や庶務と兼務していることも多く、36協定の更新や届出を“つい後回し”にしてしまうケースがあります。しかし未締結のまま残業をさせれば、従業員に不満がなくても明確な法違反となります。
働き方改革によって残業時間の上限規制が強化
働き方改革とは、労働環境の改善や労働時間の見直しを通じて、働きやすい職場環境を作り出すという政府が推進する取り組みのことで、2019年4月から施行されました。
「月45時間」「年360時間」という残業時間の縛りに変更はありませんが、働き方改革によって「法的拘束力」が発生した点が大きな特徴です。
| これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制⼒がなく、また特別条項を設けることで上限無く時間外労働を⾏わせることが可能となっていました。今回の改正によって、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられます。 |
出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」p.4
これまで、法的な拘束力がないという理由から上限時間を守っていなかった企業も、2019年4月以降は罰則が科される可能性があるため、残業規制の内容を厳守しなければなりません。
業種や企業規模によって規制の適用時期が異なる
2019年4月から始まった残業時間の上限規制ですが、業種や企業規模によって適用時期が異なります。
まず、「建設事業」・「自動車運転の業務」・「医師」・「鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業」の4種においては、5年間の猶予期間があり、2024年4月から適用されます。
なお「建設事業」・「自動車運転の業務」・「医師」の3種については、適用開始後も他業種と比べて規制内容が大幅に緩和されている点が特徴です。
| 建設事業 | ■災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」・「2~6カ月平均80時間以内」という規制が適用されない。 |
| 自動車運転の業務 | ■特別条項付き36協定を締結する場合、年間の時間外労働の上限が960時間となる。 ■時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」・「2~6カ月平均80時間以内」という規制が適用されない。 ■時間外労働が月45時間を超えることができるのは年間6カ月まで、という規制が適用されない。 |
| 医師 | ■特別条項付き36協定を締結する場合、年間の時間外労働の上限が最大1860時間となる。 ■時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」・「2~6カ月平均80時間以内」という規制が適用されない。 ■時間外労働が月45時間を超えることができるのは年間6カ月まで、という規制が適用されない。 ■医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがある。 |
そして、大企業は2019年4月から規制が適用されていますが、中小企業には1年間の猶予が与えられ、2020年4月からの適用となっています。
厚生労働省が定める「中小企業」とは、各業種ともに、以下のどちらかの条件に該当する企業となります。
| 業種 | 資本金または出資の総額 | 常時使用する労働者数 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他(製造業・建設業・運輸業など) | 3億円以下 | 300人以下 |
参考)厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」
参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」p.5
残業時間の上限を超えた場合の罰則
従業員に、残業時間の上限を超えた労働をさせてしまうと、法人に対して罰則が科される可能性があります。
罰則の内容は、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
刑事罰を受けてしまうと、罰則によるダメージだけでなく、「刑事罰を科された企業」というイメージがついてしまうため、信用問題になります。
したがって、大企業だけでなく中小企業も、「規制に沿った形で適切に残業が行われているか」について細心の注意を払わなければなりません。
参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制」
中小企業が抱えがちな残業時間の上限規制に対する課題
中小企業には、残業時間の上限規制について以下のような課題を抱えているケースが多いです。
- 残業に関して経営者の意識が低い
- 人手不足によりサービス残業がなければ仕事が終わらない
- 2024年問題への対応が十分ではない企業も少なくない
それぞれ、詳しく解説していきます。
残業に関して経営者の意識が低い
中小企業経営者の中には、「長時間労働は美徳」という古い価値観を持った方もいます。
「プライベートを犠牲にして仕事に没頭したことで成功を収めた」というような自らの成功体験を忘れられない方に多いです。
こういった経営者の場合、従業員にも自身の価値観を押しつけ、上限規制を超えるような過度の残業をさせてしまうケースが出てきてしまいます。
しかし、時代は変化しており、現代においてこのような価値観は通用しません。
残業に対しての認識が甘い経営者は、ワークライフバランスの重要さを学び、従業員に無駄な長時間労働をさせないことを強く意識するようにしましょう。
人手不足によりサービス残業がなければ仕事が終わらない
残業時間の上限規制が実施されても、従業員の仕事量が変化するわけではありません。
「今までは長時間労働でなんとか終わらせていた」という仕事がある場合、上限規制によって労働時間が短くなると、規制の範囲内で仕事を終わらせることができないという従業員も出てくるでしょう。
その結果、上限規制を守るために、タイムカードや出勤簿に記載された時間以外で働く、いわゆる「サービス残業」をする従業員が出てきてしまいます。
しかし、賃金を払わずに働かせるサービス残業は、多くの場合「違法」であり、従業員を苦しめるうえに企業側にとってもリスクとなるのです。
サービス残業がなければ業務が回らない状態になっていないか、今一度現場の状況をよく確認するようにしてください。
2024年問題への対応が十分ではない企業も少なくない
2024年問題とは、2024年4月からトラック運転手などの特定の職業においても残業時間の上限規制が適用されることによって、物流業界で起こるかもしれない様々な問題のことを指します。
物流業界は、荷物を運ぶトラック運転手の長時間労働によって支えられてきました。
しかし2024年4月以降は、「残業は年間960時間以内」という上限を守らなければいけなくなったほか、厚生労働省が定めた「改善基準告示」により、1カ月あたりの拘束時間や1日あたりの休息時間も制限されたのです。
- 1か月の拘束時間:原則として284時間以内
- 1日の休息期間:原則として継続11時間与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
こうした問題に対しても、どのように取り組んでいくべきか十分な検討が必要です。
参考)厚生労働省「トラック運転者の改善基準告示」
中小企業は残業時間の上限規制にどう立ち向かうべきか
残業時間の上限規制は、中小企業にとって大きな障壁となる可能性があります。
この項目では、上限規制に対してどのように立ち向かえばいいのかについて解説していきます。
従業員の勤怠管理を徹底する
残業時間の上限規制に違反しないためにまずやるべきことは、徹底した従業員の勤怠管理です。
全従業員の勤怠状況を詳細に把握することで、誰がどれくらい残業しているかが浮き彫りになります。
残業が多いということは、以下のような問題が発生している可能性があります。
- 特定の従業員に業務が集中している
- 残業代を稼ぐため意図的に労働時間を増やしている
- 部署として人手が足りていない
こうした問題を認識・解決するためには、勤怠管理の徹底がマストになるため、必ず行うようにしてください。
なお、適切に勤怠を管理するためには、勤怠管理システムの導入が有効です。
紙のタイムカードや手作業での管理と比べて大幅に効率が向上するうえ、人事担当者は正確なデータをもとに従業員の勤怠状況を把握できます。
また、従業員の勤務状況や残業時間をリアルタイムで把握することができるため、労働基準法に反する過重労働の防止にも役立ちます。
業務効率化を図る
業務の効率化を図り従業員の負担を減らすという方法も、残業時間を減らす対策法の一つとなります。
たとえば、業務マニュアルを整備したり、自動化できる部分は人力で対応するのではなくITシステムに任せたり、といったようなやり方です。
業務効率化が進めば、同じ労働時間でより多くの成果を出せるようになるため、必然的に残業時間も減らすことができます。
したがって、勤怠システムだけでなく、作業を短縮するためのシステム導入については積極的に検討するようにしましょう。
導入に際しての費用はかかるものの、最適なシステムを選別することによって、長期的には「人的コスト」や「残業規制に違反するリスク」を削減できます。
代替休暇制度を活用する
代替休暇制度とは以下のような制度で、2023年4月からは中小企業も対象となっています。
| 1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。 |
出典)厚生労働省「月60時間を超える法定時間外労働に対して」p.4
月60時間を超える残業は従業員を疲弊させてしまう恐れがあるものの、代替休暇を取って休んでもらうことで健康維持に役立ちます。
また、企業にとっても残業代の支払いを抑えることができるので、労使双方にメリットのある制度と言えるでしょう。
ただし、代替休暇を取るかどうかは従業員が選択するため、強制はできないという点のみ注意が必要です。
まとめ
残業時間の上限を守らず、従業員に規制を超えた残業をさせてしまうと、企業側が罰則を科されてしまう可能性があります。
仮に企業として刑事罰を科されてしまえば、取引先や消費者からの信用を失うという取り返しのつかない事態を招いてしまうこともあり得るのです。
万が一にもそのようなことがないように、残業時間の上限規制について理解を深め、万全の対策を行うようにしてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録