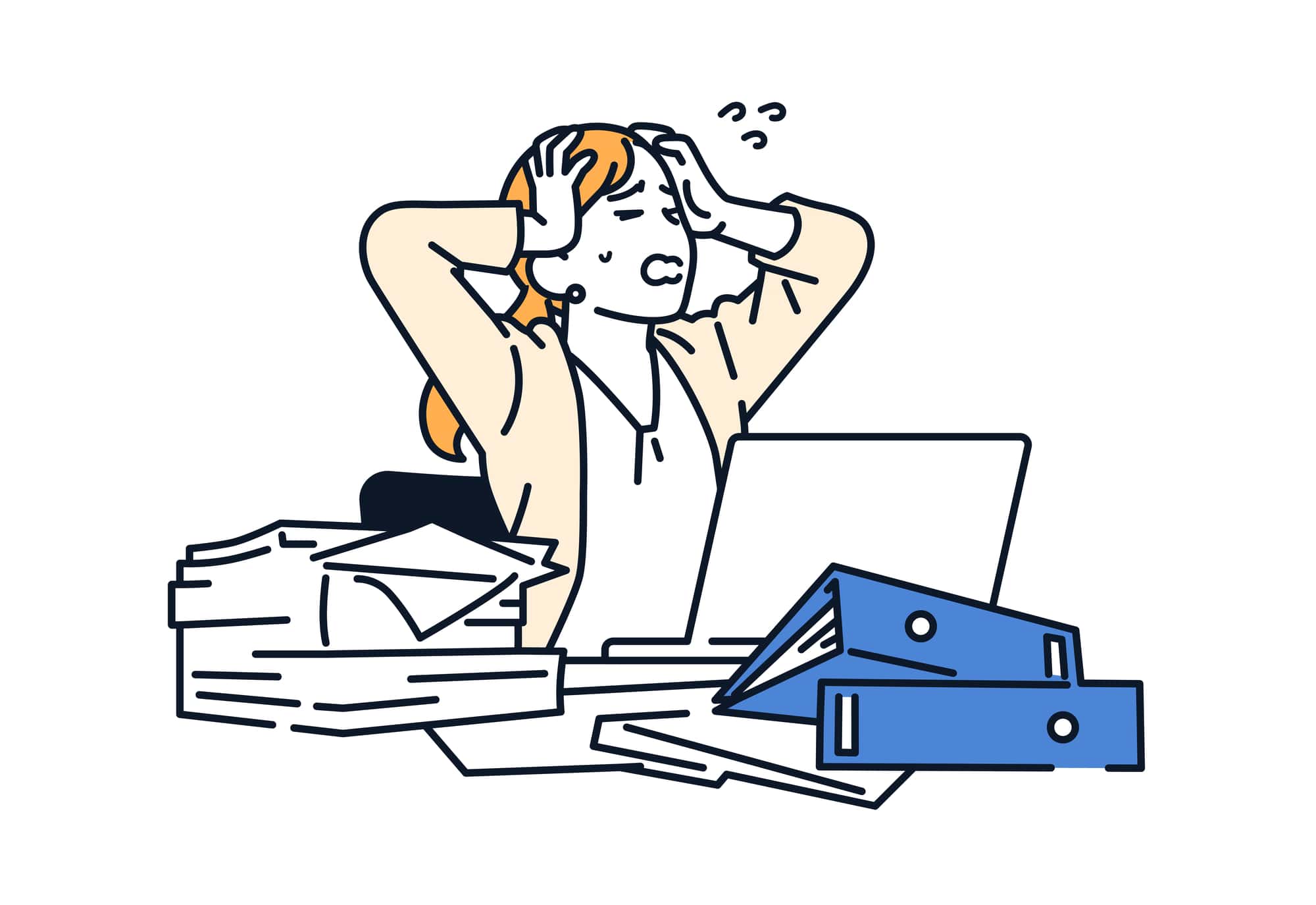労働環境とは?日本企業の現状と改善事例に学ぶ持続可能な働き方

人手不足や離職率の高さに悩む中小企業の経営層・人事担当にとって、労働環境の整備は“待ったなし”の課題です。
近年、働き方改革の推進により、多様な働き方への注目が集まっていますが、とくに中小企業では予算や人材の制約から、改善に苦心しているケースも少なくありません。
この記事では、労働環境の現状と課題を整理し、中小企業でも実践できる具体的な改善方法や活用可能な支援制度についてご紹介します。
目次
労働環境とは?
労働環境とは、従業員を取り巻くあらゆる環境要因のことを指します。
具体的には、勤務時間や賃金などの労働条件、オフィスの設備や空調などの物理的環境、さらには人間関係やコミュニケーションなどです。
厚生労働省では、快適な職場環境の形成に関する基準として、空気環境や温熱条件、視環境、音環境、作業空間などを定めています。これらの要素が適切に整備されることで、従業員は心身ともに健康で働くことができます。
出典)厚生労働省「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」
労働環境の重要性
適切な労働環境の整備は、企業の持続的な成長に欠かせない要素となります。良好な労働環境は従業員の心身の健康を保護し、モチベーションの向上に寄与するためです。
具体的には、生産性の向上、離職率の低下、優秀な人材の確保などにつながります。一方で、劣悪な労働環境は従業員のストレスや疲労を蓄積させ、メンタルヘルスの悪化や労働災害のリスクを高めてしまいます。
企業にとって、労働環境の整備は法令順守だけでなく、組織の成長戦略としても重要な意味を持つことになるのです。
労働環境と職場環境の違い
労働環境と職場環境は、密接に関連しながらもその範囲が異なります。労働環境が労働時間や賃金、安全衛生などの労働条件全般を指すのに対し、職場環境は主にオフィスの設備や人間関係など、より直接的な就業環境を指すことが多いです。
たとえば、残業時間の削減は労働環境の改善になりますが、オフィスのレイアウト改善は職場環境の整備にあたります。ただし、両者は相互に影響し合う関係にあり、職場環境の改善が労働環境全体の向上につながると考えましょう。
効果的な環境改善を実現するには、両者のバランスを考慮しながら、総合的な取り組みを進めることが重要です。
日本における労働環境の現状と課題
近年、日本の労働環境を取り巻く問題は深刻化の一途をたどっています。具体的には以下のとおりです。
- 長時間労働や過重労働の問題
- 人手不足による負担と生産性低下
- ハラスメント問題
これらの問題は従業員の心身の健康だけでなく、企業の生産性や持続的な成長にも大きな影響を及ぼすことになります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
長時間労働や過重労働の問題
日本では長時間労働や過重労働が深刻な問題です。過労による健康被害や自殺、労働生産性の低下が社会問題化しており、企業の働き方改革や労働時間短縮の推進が求められています。
政府も法改正を進め、働き方改革を促進しているものの、現場では依然として過重労働が続いている状況です。労働者の健康維持と効率的な働き方が今後の課題となります。
・出典)厚生労働省 「しごとより、いのち」
人手不足による負担と生産性低下
少子高齢化の進行により、深刻な人手不足が多くの企業を悩ませています。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、企業の52.1%は人材(人手)不足が生じているという結果がでています。
この状況下で、従業員への業務負担は増加の一途をたどっているのです。また、十分な教育や訓練を行う時間的余裕がないと、業務の質が低下し、結果として企業全体の生産性が落ちる要因にもなります。
とくに中小企業では、人材採用の競争力が大企業に比べて弱く、この問題が一層深刻化しているのです。
・出典)独立行政法人労働政策研究・研修機構 「人材(人手)不足の現状等に関する調査」(企業調査)結果及び「働き方のあり方等に関する調査」(労働者調査)結果」
ハラスメント問題
職場におけるハラスメントは、従業員のメンタルヘルスに重大な影響を与える深刻な問題です。パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、さらには妊娠・出産・育児に関するマタニティハラスメントなど、その形態は多様化しています。
2020年からは、パワハラ防止法が施行され、企業には防止対策が義務付けられることになりました。しかし、ハラスメントの定義や範囲が曖昧なため、適切な対応が取れていない企業も多く存在します。
この問題の解決には、明確な防止方針の策定や相談窓口の設置、そして従業員への継続的な教育が不可欠です。
・出典)厚生労働省 「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」
【中小企業必見】労働環境・職場環境を改善する具体的な方法
生産性向上と従業員の定着率を高めるためには、労働環境の改善が不可欠です。とくに中小企業では、限られた経営資源の中で効果的な施策を実施する必要があります。
具体的な方法は、以下のとおりです。
- 多様な働き方の導入
- メンタルヘルス対策
- ITツールを活用した業務効率化
それぞれ詳しく見ていきましょう。
多様な働き方の導入
柔軟な働き方の導入は、従業員の満足度向上に直結します。たとえば、フレックスタイム制度を取り入れることで、個人のライフスタイルに合わせた勤務が可能です。
また、リモートワークは通勤時間の削減や業務の効率化につながります。ほかにも、時短勤務制度は育児や介護との両立を支援する重要な施策です。
コストを考慮しながら段階的に導入すると、持続可能な体制を構築できます。まずは一部の部署や従業員から試験的に始めてみましょう。
メンタルヘルス対策
従業員の心の健康を守ることは、企業の生産性維持に直結します。ストレスチェック制度の導入は、法定義務の対象でない小規模事業場でも効果的な取り組みです。
定期的な個別面談やカウンセリング体制の整備も重要です。外部の専門家と連携すると、より専門的なサポートが可能になります。
管理職向けのメンタルヘルス研修を実施し、部下の変化に気づける体制を作りましょう。早期発見・早期対応が、重要な鍵となります。
ITツールを活用した業務効率化
業務効率化のためのITツール導入は、投資に見合う効果が期待できます。クラウド型の勤怠管理システムにより、労働時間の正確な把握と管理が可能です。
また、タスク管理ツールの活用で、業務の進捗状況を可視化できます。ほかにも、チャットツールやビデオ会議システムは、コミュニケーションの円滑化に役立ちます。
しかし、導入時には従業員への丁寧な研修が必要です。使い方に慣れるまでは一時的に業務効率が落ちる可能性もありますが、長期的な視点で取り組みましょう。
労働環境の改善に成功した事例
ここからは、中小企業において労働環境の改善に成功した事例を3つ紹介します。
- 従業員の働きがい向上とビジョンの共有ができる評価制度の導入
- 働きやすい職場環境づくりと助成金活用で生産性の向上
- 現場も事務も全ての社員がテレワーク可能に
順番に見ていきましょう。
従業員の働きがい向上とビジョンの共有ができる評価制度の導入
株式会社小金澤商店は、職務分析と職務評価に基づく新しい評価制度を導入しました。従業員一人ひとりの役割や期待される成果を明確にすることで、働きがいの向上とビジョンの共有を実現しています。
評価制度の特徴は、結果・情意・能力の3つの観点から総合的に評価する点です。販売、配送、管理・事務といった職務ごとに求められる能力を定義し、雇用形態に関係なく公平な評価ができます。
この制度により、パートタイムや有期雇用労働者の処遇についても合理的な説明が可能になりました。評価基準が明確になったことで、従業員は自身のキャリアパスを具体的にイメージできるようになっています。
また、この制度は単なる待遇決定のツールではなく、従業員の成長を支援する教育の仕組みとしても機能しています。目標達成に向けた努力や工夫を適切にフィードバックすることで、さらなる成長へのチャレンジを促す効果が表れているのです。
成果としては、従業員の会社への信頼感が高まり、仕事への意欲が向上しました。評価の透明性と納得性が確保されたことで、組織全体のパフォーマンス向上にもつながっています。
出典)厚生労働省「CASE STUDY:株式会社小金澤商店」
働きやすい職場環境づくりと助成金活用で生産性の向上
クリーニング エイトドライは、従業員が働きやすい職場環境の整備と助成金を活用した業務効率化により、生産性の大幅な向上を実現しました。
就業規則の整備からスタートし、労働条件の透明性を高めることで、従業員の安心感と信頼関係を構築しています。正社員とパートタイム社員の双方に配慮した制度設計により、長期的な人材確保と定着を実現しました。
待遇面では、完全週休2日制の導入や退職金制度の整備、半日有給休暇制度の採用など、従業員のワークライフバランスを重視した取り組みを進めています。これにより、休暇を取得しやすい環境が整いました。
業務効率化では、助成金を活用してPOSレジシステムを導入しました。その結果、受付対応時間が約半分に短縮され、新人スタッフの育成期間も大幅に短縮されています。また、顧客管理の効率化と受付品質の向上により、従業員間のコミュニケーションも活性化されました。
このような取り組みにより、従業員の勤務意欲が向上し、人件費の増加や労働力の減少をカバーできる生産性の向上を実現しています。
出典)厚生労働省「CASE STUDY:クリーニング エイトドライ」
現場も事務も全ての社員がテレワーク可能に
株式会社菊正塗装店は、コロナ禍を契機に全社的なデジタル化を推進し、現場監督から事務職まで全ての社員がテレワークできる体制を整備しました。
6年前から段階的に進めてきたペーパーレス化の取り組みは、緊急事態宣言を機に大きく前進しています。全社員にノートPCとスマートフォンを貸与し、VPN接続によって社外からも安全に業務システムにアクセスできる環境を実現しました。
勤怠管理もスマートフォンアプリを活用し、GPS機能で始業・終業時の位置情報を記録できます。グループウェアによる予定の共有やチャットツールの活用で、場所を問わないコミュニケーションも可能になりました。
この取り組みにより、現場監督職の社員は直行直帰が基本となり、事務職も交代制での出社が可能になっています。業務の効率化と共に、従業員一人ひとりのワークライフバランスの向上にも寄与しました。
出典)厚生労働省「CASE STUDY:株式会社菊正塗装店」
中小企業が活用できる支援制度や補助金
中小企業の労働環境改善を後押しする様々な支援制度や助成金があります。具体的には以下のとおりです。
- 働き方改革推進支援助成金
- 両立支援等助成金
- 退職金共済(中小企業退職金共済制度)
事業規模や目的に応じて、適切な制度を選択すると、より働きやすい職場づくりを実現できます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
出典)厚生労働省「職場環境を整備・改善したい」
働き方改革推進支援助成金
中小企業の働き方改革を支援するために、厚生労働省は環境整備に必要な費用を助成する制度を設けています。事業規模や目的に応じて、適切なコースを選択すると、効果的な改革が可能です。
| コース | 内容 |
| 業種別課題対応コース | 生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援 |
| 労働時間短縮・年休促進支援コース | 時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた取り組みを支援 |
| 勤務間インターバル導入コース | 勤務終了後から次の勤務までに一定時間の休息を確保する制度の導入を支援 |
| 団体推進コース | 労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成 |
申請にあたっては、事前に自社の状況を確認し、実現可能な目標を設定することが重要です。社会保険労務士による無料相談も利用できるため、申請手続きや具体的な改革の進め方について、専門家のアドバイスを受けましょう。
・出典)厚生労働省 「労働時間等の設定の改善」
両立支援等助成金
仕事と育児・介護の両立支援に取り組む企業を応援する制度が、両立支援等助成金です。この制度は4つのコースに分かれており、企業のニーズに合わせて選択できます。
| コース | 内容 |
| 出生時両立支援コース | 男性の育児休業取得を推進する企業に最大60万円を支給 |
| 育児休業等支援コース | 休業取得や職場復帰をスムーズにするための取り組みを支援(休業中の代替要員確保にかかる費用の補助など) |
| 介護離職防止支援コース | 介護を理由とする離職を防ぐための制度整備を支援 |
| 不妊治療両立支援コース | 治療と仕事の両立に向けた職場環境の整備を支援 |
| 育休中等業務代替支援コース | 育児休業中の従業員の業務を他の従業員が代替する際の支援 |
| 柔軟な働き方選択制度等支援コース | 柔軟な働き方を推進する制度の整備に取り組みの支援 |
この制度を上手に活用すると、従業員が安心して働ける職場環境の整備を進められます。
・出典)厚生労働省 「事業主の方への給付金のご案内」
退職金共済(中小企業退職金共済制度)
中小企業退職金共済制度は、従業員の将来に安心を提供する国の退職金制度です。厚生労働省管轄の独立行政法人が運営しており、安定性の高さが特徴です。
掛け金は毎月5,000円から30,000円の範囲で選択できます。この掛け金は全額事業主負担となりますが、損金として処理できる点が税務上のメリットです。
新規加入から4ヶ月目以降の1年間は、掛け金の一部を国が助成してくれます。従業員一人当たり最大5,000円まで補助があるため、企業の負担を抑えられます。
福利厚生面でも充実しており、加入者は提携施設の割引サービスを利用可能です。従業員の満足度向上にもつながる制度といえるでしょう。
・出典)独立行政法人勤労者退職金共済機構 「掛金」
・出典)独立行政法人勤労者退職金共済機構 「中退共提携割引サービスのご案内」
・出典)厚生労働省 「中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成」
まとめ
労働環境の改善は、企業の持続的な成長と従業員の幸せを両立させるために欠かせない取り組みです。長時間労働やハラスメントの解消、多様な働き方の導入など、課題は山積していますが、ITツールの活用や支援制度の利用により、着実に改善を進められます。
中小企業においても、両立支援等助成金や退職金共済制度など、様々な支援策が用意されています。これらを効果的に活用しながら、従業員が生き生きと働ける職場づくりを進めていくことが、企業の未来を明るくするポイントです。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録