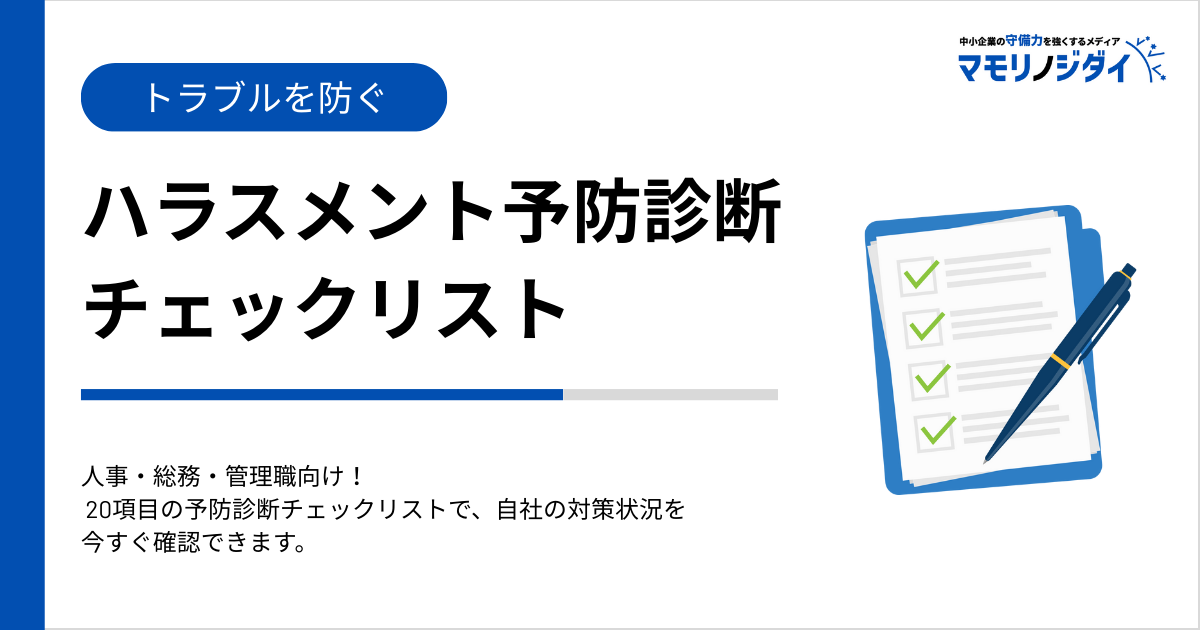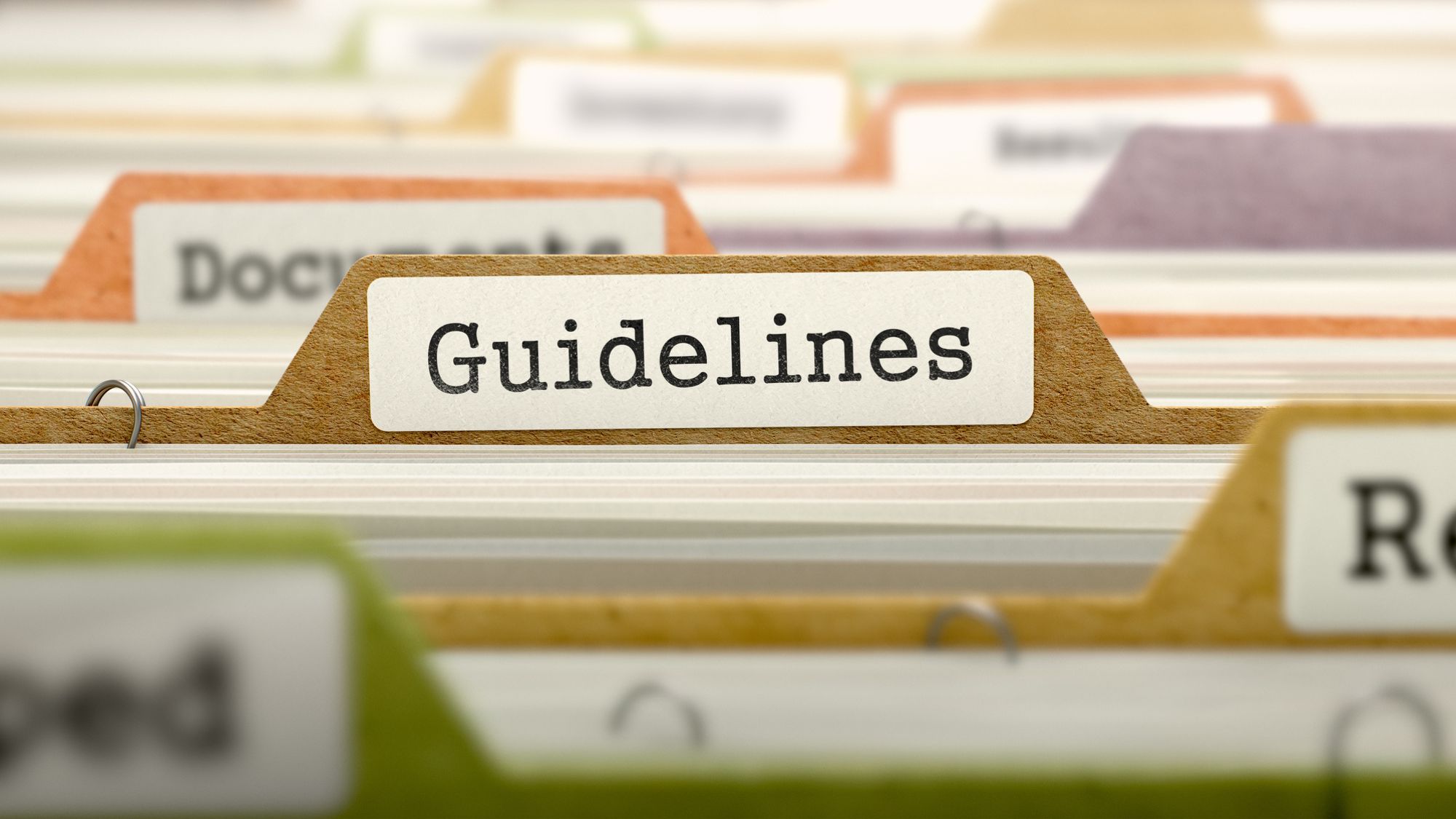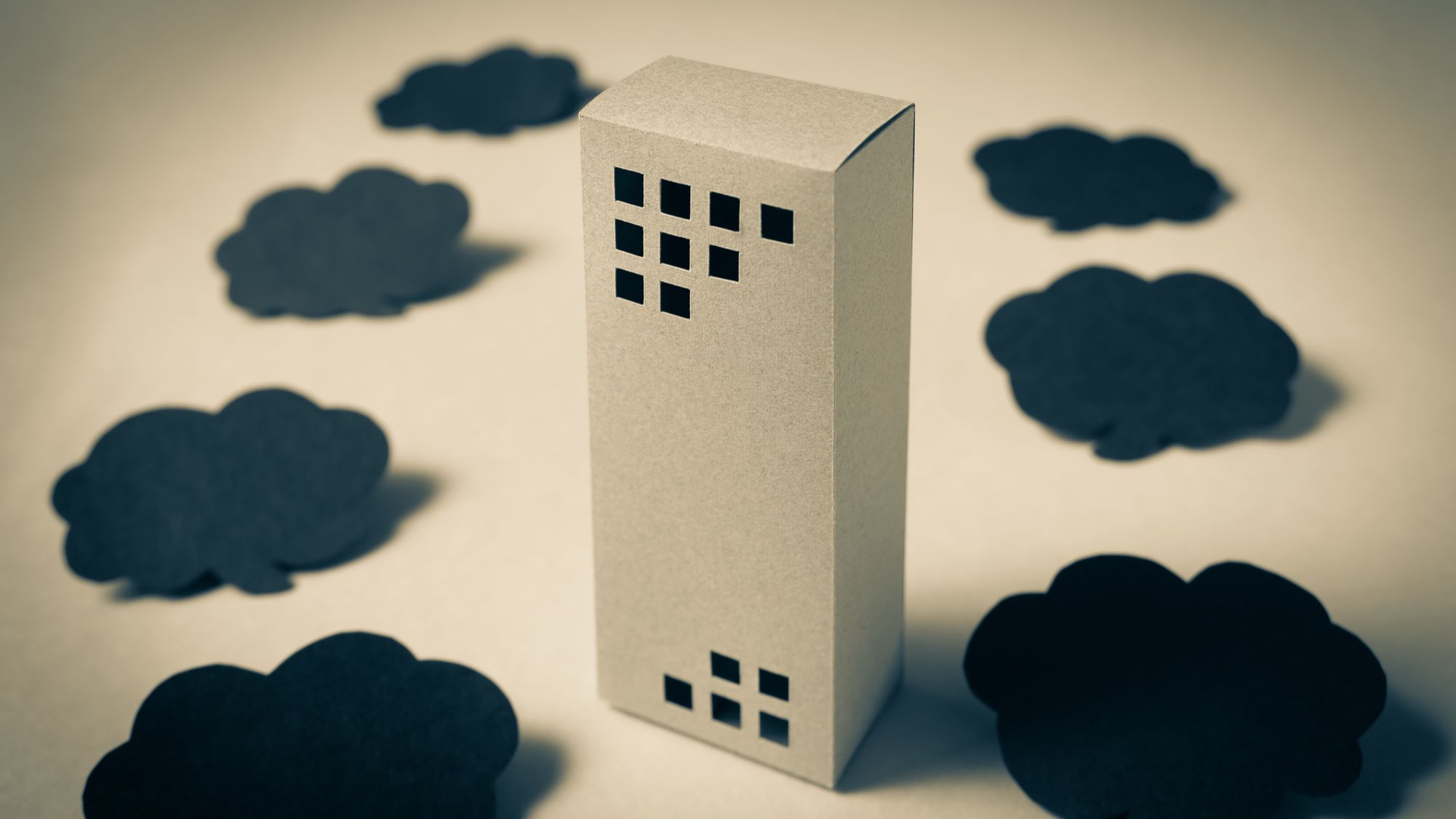職場でのモラルハラスメントって何?中小企業が知っておくべきリスクと対策

中小企業の経営者やバックオフィス担当者にとって、従業員が安心して働ける職場環境を整えることは企業の成長と持続可能性に欠かせない要素です。
そのうえでモラルハラスメント(モラハラ)は大きなリスクになります。モラハラは、直接的な暴力や権力の乱用ではなく、言葉や態度による精神的な嫌がらせが特徴です。
発生してしまうと、職場全体の士気や生産性を低下させる可能性があります。さらに、問題を放置すると、中小企業にとっては経営基盤を揺るがす可能性がある重大な問題です。
本記事では、モラハラの基本的な定義やパワハラとの違いを明確にしたうえで、企業が直面するリスクや具体的な防止策、適切な対処法について詳しく解説します。
中小企業だからこそできる実効性の高い対策を学び、健全な職場環境を守るための第一歩を踏み出しましょう。
なお、以下の無料の資料では中小企業の経営層、人事・労務部門の方向けに向けてハラスメント予防診断チェックリストを紹介していますので、参考にしてみてください。
目次
厚生労働省のモラルハラスメントの定義を理解する
知らないうちに加害者や被害者にならないためにも、モラルハラスメントの定義を正しく理解しておくことは、重要です。まずは言葉の定義を紹介します。
モラルハラスメントとは、精神的ないじめや嫌がらせのことです。言葉や態度、無視などによって、継続的に相手の心を傷つけ、尊厳を侵害する行為を指します。
厚生労働省の定義では、ハラスメントは「ひとを悩ますこと、地位や立場を利用した嫌がらせ」です。また厚生労働省の資料では、フランス・スウェーデン・ベルギー・イギリスなどの諸外国の取り組みも紹介されています。
多くの国で、モラルハラスメントを「労働者の尊厳を侵害する継続的な行為」として明確に定義し、予防・是正措置を企業に義務づけていることが特徴です。日本企業にとっても学ぶべき点は多いといえます。
なお、以下の記事ではモラルハラスメントに関して専門家が詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。
参考記事:モラルハラスメントとは?企業が知っておくべき定義・事例・防止策を弁護士が解説
出典)こころの耳「ハラスメント」
出典)厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせに関する諸外国の取組」
実は法律で義務化!パワハラ防止法と中小企業の対応
モラルハラスメント(モラハラ)は、パワーハラスメント(パワハラ)の一種として捉えられる可能性もあります。
2020年6月施行の改正労働施策総合推進法、通称「パワハラ防止法」では、事業主に対して、以下の3つの措置義務が課されました。
| 義務 | 内容 |
| ① 企業方針の明示・周知 | ハラスメントを許さない旨を社内規定などに定め、全従業員に周知徹底する必要があります。 |
| ② 相談体制の整備 | 社内外に相談窓口を設置し、被害者が安心して相談できる体制を構築することが求められます。 |
| ③ 事後対応の実施 | ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ適切に事実確認・加害者への対応・再発防止策を講じる必要があります。 |
なお、大企業は2020年6月から、中小企業は当初努力義務とされていましたが、2022年4月からは中小企業にもこの「パワハラ防止法」が義務化されています。
参考)厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」
参考)e-GOV「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
パワーハラスメント(パワハラ)と何が違う?
モラルハラスメント(モラハラ)とパワーハラスメント(パワハラ)はどちらも中小企業の職場で問題となる嫌がらせ行為です。ただし、加害者と被害者の関係性やハラスメントの手法には違いがあります。
パワハラは、上司から部下への権力関係を利用した攻撃的な行為が中心です。暴言や過剰な業務負担、無理なノルマの押し付けなどが該当します。
一方、モラハラは権力の有無に関係なく発生し、同僚や部下から上司への嫌がらせも含まれることが特徴です。
つまり、パワハラは「力の優位性」を背景にした直接的な攻撃となります。対して、モラハラは「関係性に関係なく発生する圧力」です。
そのため、モラハラはパワハラに比べて中小企業では顕在化しにくいのが特徴です。対策が遅れることで職場全体の雰囲気を悪化させるリスクが高まります。
参考記事:パワーハラスメントの定義を知って職場のトラブルに備えよう!厚生労働省の定義をもとに解説
【必見】職場でよく見られるモラルハラスメントの例
職場でよく見られるモラハラの典型的な事例を紹介します。
無視や侮辱などの心理的な攻撃
職場でのモラハラの代表例が、無視や侮辱といった心理的な攻撃です。たとえば「会議で意見を述べても意図的に無視される」「同僚の前で過度に批判される」といった行為が該当します。
また、直接的な言葉だけではありません。皮肉や冷笑といった態度もモラハラに含まれる場合があります。
これらの行為が日常的に繰り返されると、被害者のメンタルヘルスが深刻に悪化することは避けられません。結果として業務パフォーマンスの低下や退職を招く恐れがあります。
業務とは関係のない要求
モラハラの一形態として「業務と無関係な要求を強いるケース」があることに注意しましょう。
たとえば「上司が部下に対して私的な用事を押し付ける」「業務時間外に不必要な雑用を頼む」といった行為です。こうした要求は、業務効率の低下だけではなく、被害者に不公平感や屈辱感を与えます。
特に中小企業では、上下関係が近いため、こうした私的な依頼が見過ごされがちです。だからこそ、業務と私生活の線引きを明確にし、不当な要求が行われない環境を整えましょう。
過度なプライベート干渉
モラハラには、プライベートへの過度な干渉も含まれます。
たとえば「私生活に過剰に立ち入る」「交際関係や家庭の事情について執拗に詮索する」などです。また、結婚や出産といったライフイベントに対して、無神経なコメントを繰り返すことも含まれます。
中小企業がスピード感のある経営を進めるために、コミュニケーションは必要不可欠です。しかしビジネスとプライベートは明確に線引きするようにしましょう。
モラルハラスメントが中小企業に与えるリスクは甚大
モラルハラスメント(モラハラ)を放置することは、中小企業にとって致命的です。目に見えにくい嫌がらせが、企業全体の生産性・信頼性の低下を引き起こす可能性もあります。
離職・休職者の増加で現場が崩壊する
モラルハラスメントの最大の被害者は、日常的に攻撃や排除にさらされる社員本人です。しかし、実は職場全体にも深刻な影響を及ぼします。
モラハラによりストレスを抱えた従業員は、うつ病などの精神疾患を発症し、休職や退職を余儀なくされることがリスクです。
特に中小企業では、少人数のチームに依存している業務構造が多く、1人の離脱が全体の生産性低下に直結します。代替要員の確保が困難な現場では、残された従業員への負担が一層増し、さらなる離職やミスの連鎖を招くこともあるのです。
最悪の場合、事業継続に支障が出るレベルでチームが崩壊することもあり、これは中小企業にとって死活問題といえるでしょう。
口コミ・SNSで企業イメージが低下する
かつては社内で泣き寝入りすることが多かったモラハラ被害も、近年ではSNSや口コミサイトを通じて外部に可視化される時代です。退職者が「ブラック企業」と名指しで書き込むケースもあり、それが採用活動や取引先との信頼関係に悪影響を及ぼす可能性は非常に高くなっています。
例えば企業レビューサイトに「上司のモラハラがひどい」「相談しても何もしてくれない」などの書き込みがされると、求職者はエントリーを控え、優秀な人材は集まりづらくなることは避けられません。
参考記事:レピュテーションリスクから会社を守る!風評被害との違い・事例・対策
訴訟や損害賠償リスクで経営が揺らぐ
モラルハラスメントは「精神的な攻撃」による人権侵害とされ、企業が加害者を放置していた場合、「安全配慮義務違反」や「使用者責任」を問われる可能性があります。
さらに、2022年4月から中小企業にも義務化されたパワハラ防止法の遵守、という観点でも重要です。適切な相談体制や再発防止策を講じていなかった場合、行政指導や企業名の公表といった制裁を受けるリスクもあります。
モラルハラスメントを防ぐために中小企業ができることとは?
モラルハラスメント(モラハラ)を未然に防ぐためには、企業全体での取り組みが不可欠です。
特に中小企業では、社員同士の距離が近い分、ハラスメントが発生しやすい環境になりがちといえます。しかし、逆に言えば「迅速かつ柔軟な対応がしやすい」という強みです。
ここでは具体的な取り組みを項目ごとに紹介します。
「行動基準」を明文化して全社員に共有する
モラハラの抑止には、まず「どこからがNGなのか」を明確にすることが必要です。曖昧な基準のままでは、加害者が自覚なくハラスメント行為を続けてしまうリスクが高まります。
そこで重要なのが、就業規則や行動規範に「モラルハラスメントの定義と禁止事項」を盛り込み、文書として明文化することです。具体的には以下のような行為を例示し、「これらの言動は許容されない」と明記します。
- 人格を否定する発言(例:「使えない」「辞めれば?」など)
- 無視・排除などの陰湿な対応
- 評価と関係ない私情での扱いの差別
加えて、入社時や人事面談などのタイミングで繰り返し説明し、全社員に対する周知徹底を図ることが不可欠です。
相談窓口と通報制度の整備はマスト
モラハラ対策の要は「声をあげられる環境作り」です。いくらルールを定めても、被害者が安心して相談できる仕組みがなければ意味がありません。
そのためには、社内に「相談窓口」や「内部通報制度(ホットライン)」を設けることが必須です。窓口担当者には、相談内容の守秘義務や対応マニュアルを明確にし、被害者が報復を恐れずに話せる体制を整えることが求められます。
また、外部の専門機関(社労士事務所やEAPなど)と連携し、社内では話しづらいケースにも対応できる外部相談窓口を用意するのも有効です。
管理職向けのモラハラ研修を定期的に実施
加害者となるのは、必ずしも悪意ある人間とは限りません。多くの場合、「無自覚な管理職」がモラハラ加害者になることが実情です。
たとえば、「厳しく指導したつもりが、相手は人格否定と受け取っていた」というようなズレはよくあります。このような事態を防ぐには、管理職やマネージャー層に対するモラハラ研修の定期実施が効果的です。
研修では以下のような内容を扱うとよいでしょう。
- モラハラの定義と具体例
- 業務指導との違い
- 部下のSOSサインの見抜き方
- ハラスメント対応時の初動対応
年1回の定期研修に加え、昇進時・人事異動時などのタイミングで集中研修を組み込むのもおすすめです。
事前に加害者の特徴を知っておき、過度な行動には早めに注意を促す
モラハラの芽を摘むには、「起きてから対応する」のではなく、「起きる前に予兆を察知する」ことが重要です。厚生労働省などの資料でも、モラハラの加害者に見られる典型的な傾向が整理されています。
たとえば、以下のような特徴がある場合は注意が必要です。
- 自己中心的で相手への配慮に欠ける
- 部下に完璧を求めるが、自分には甘い
- 気分や好き嫌いで対応を変える
- 指摘や反論に対して極端に攻撃的
こうした傾向が見られる社員に対しては、上司や人事が早期にモニタリングを行い、必要に応じてフィードバックや研修を実施することが望まれます。被害者が出てからでは遅いため、未然に抑止できる体制の構築が鍵です。
モラルハラスメントが発生した場合はどう対処すべき?
事前に対策をしていても、モラルハラスメント(モラハラ)が発生する可能性はあります。この場合、迅速かつ適切な対応が必要です。
ここではモラルハラスメントが発生した際の企業としての対処法について項目ごとに紹介します。
まずは事実関係のヒアリングと記録
ハラスメント事案への対応で最も重要なのが「事実確認」です。被害者からの申し出や通報があった場合は、即座に関係者へのヒアリングを行い、できる限り詳細かつ客観的な記録を残しましょう。
特に以下の点は明確にしておくことが求められます。
- 発言や行為があった日時・場所
- 発言内容や具体的な態度(メールや録音など証拠があれば保存)
- 第三者の目撃証言があるか
- 被害者の心理的・身体的影響の有無
調査にあたっては、被害者の心理的負担を最小限に抑えるよう配慮することが前提です。また、調査の公平性を担保するために、可能であれば社外の専門家や第三者委員を関与させることも検討すべきです。
被害者・加害者それぞれのケア体制
事実確認と同時に、関係者へのケアも迅速に行いましょう。
被害者に対しては、メンタルヘルスケアや就業環境の調整(部署異動・休職対応など)を柔軟に提供する姿勢が求められます。外部のカウンセリングサービスやEAP(従業員支援プログラム)を活用するのも効果的です。
一方で加害者に対しても、行動の背景や認識に誤解がなかったかを確認しつつ、再発防止に向けた教育や研修を実施することが大切です。再教育の機会を与えることで、職場全体の人間関係改善にもつながります。
なお、両者の直接対話を強要することは避け、人事・管理部門が間に入り、冷静かつ安全な対応を進めることが鉄則です。
必要に応じて懲戒処分を検討
事実関係の調査によって、モラルハラスメントの存在が認定された場合は、就業規則に基づいて適切な懲戒処分を下す必要があります。
懲戒の判断にあたっては、以下の項目を総合的に勘案し、「口頭注意」「始末書」「減給・降格」「出勤停止」「懲戒解雇」など、段階的かつ合理的な処分を選択することが重要です。
- 行為の悪質性(頻度・継続性・業務妨害性)
- 被害者への影響度(精神疾患・離職・休職等)
- 過去の注意指導の有無
特に中小企業においては、懲戒処分の根拠が曖昧なままだと、逆に加害者から訴訟を起こされるリスクもあります。必ず就業規則上の懲戒事由や手続きに準じて対応すべきです。
就業規則と相談体制の整備で再発を防ぐ
モラハラ対応は一過性のものではなく、組織全体で「再発防止」に取り組む文化の構築が不可欠といえます。そのために見直すべき2つの柱が「就業規則」と「相談体制」です。
| 整備項目 | 具体的な内容 |
| 就業規則の見直し | ・モラルハラスメントを禁止行為として明文化 ・違反時の懲戒内容を具体的に記載 ・調査と対応のプロセスも規則内で明文化 |
| 相談体制の強化 | ・社内相談窓口担当者の教育を徹底 ・外部相談機関(弁護士、EAPなど)との連携 ・匿名通報の仕組みと報復禁止の明文化 |
| 社内周知と研修 | ・全社員への定期的なハラスメント研修 ・就業規則と通報制度の社内イントラ掲示や説明会 ・管理職への個別研修、面談 |
これらを定期的に見直し、全従業員への周知・研修も継続的に行うことで、モラハラの「芽」を未然に摘む職場風土を形成できます。
企業がモラルハラスメントで訴えられたらどうする?
職場におけるモラルハラスメント(モラハラ)は、企業にとって法的責任が問われる深刻な問題です。対応を誤れば、損害賠償請求や企業イメージの毀損、従業員離れなど多くのリスクに直結します。
ここでは、万が一訴訟リスクが顕在化した場合に備えて、企業が取るべき4つの重要な対策について解説しましょう。
中立的な調査体制を整備し、外部専門家の力も借りる
モラハラ被害を申し立てられた場合、まず求められるのは事実関係の客観的な把握です。しかし、社内調査だけでは「公平性」に疑念を持たれることも少なくありません。特に中小企業では調査機能が限られており、対応にバイアスがかかりやすくなります。
このため、弁護士や社労士、産業カウンセラーなど外部の中立的な第三者を交えた調査委員会の設置が有効です。調査手続きの透明性を確保し、被害者・加害者双方の言い分を丁寧に聴取したうえで、証拠や背景事情を整理しましょう。
調査報告書は後の労働審判や訴訟でも重要な証拠資料となります。
被害者救済とプライバシー保護を徹底する
被害者の救済は、訴訟リスクの回避だけでなく、社内の信頼関係の再構築に不可欠です。以下のような対応が求められます。
| 対応内容 | 説明 |
| 配置転換や休職の検討 | 心身の不調があれば、柔軟な働き方(異動・休職など)の提供を検討する。 |
| 社内外の相談機関への橋渡し | 産業医、カウンセラー、弁護士などの外部専門家と連携し、必要に応じて紹介・対応を行う。 |
| プライバシーの保護 | 調査結果や処分内容などの情報は関係者以外に漏れないよう、厳重に管理し、個人情報を保護する。 |
特にプライバシー保護は法的にも重要です。個人情報保護法や労働契約法に抵触しないよう配慮を徹底する必要があります。
「使用者責任」による企業の法的責任を再確認
従業員が業務中に他の従業員に対して違法行為(モラハラ)を行った場合、企業が「使用者責任」を問われる可能性があります。自分では意識していなくても相手にストレスをかけているケースがあるため、特に注意しましょう。
たとえ企業が加害行為に直接関与していなくても「適切な防止策を講じていなかった」と判断されれば、損害賠償責任が発生するおそれがあります。これは中小企業であっても例外ではありません。
自社の就業規則や相談体制、研修制度などが十分だったかを見直すとともに、「予見可能性」と「結果回避義務」を果たせたかが問われることを理解しておきましょう。
労働審判・民事訴訟に備えて準備をする
万が一、モラハラに関して労働審判や民事訴訟に発展した場合に備えて、事前準備が成否を分けます。以下のポイントを押さえましょう。
| 項目 | 説明 |
| 調査記録や面談記録の保管 | ヒアリング内容や事実認定過程の記録が重要な証拠に。 |
| 関係者への対応履歴 | 被害者・加害者への措置、上司や人事の対応内容も明確に残す。 |
| 社労士・弁護士との連携体制 | 労務リスクに強い専門家に相談し、主張の整理や証拠準備を行う。 |
また、和解を選ぶかどうか、記者会見や社内報告の対応まで、企業の危機管理能力が問われるフェーズとなります。事態の深刻度を見誤らず、落ち着いた対応が必要です。
まとめ
モラルハラスメント(モラハラ)は、目に見えにくい嫌がらせです。しかし、企業にとって甚大なリスクをもたらします。
特に中小企業では、社員同士の距離が近く、モラハラが発生しやすいです。しかし放置すれば職場環境の悪化や企業の信頼性低下につながる可能性があります。
中小企業だからこそ、モラルハラスメント対策を積極的に行い、企業の「守り」を強化しましょう。社員が安心して働ける職場を維持することが、企業の成長と持続可能性に直結します。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録