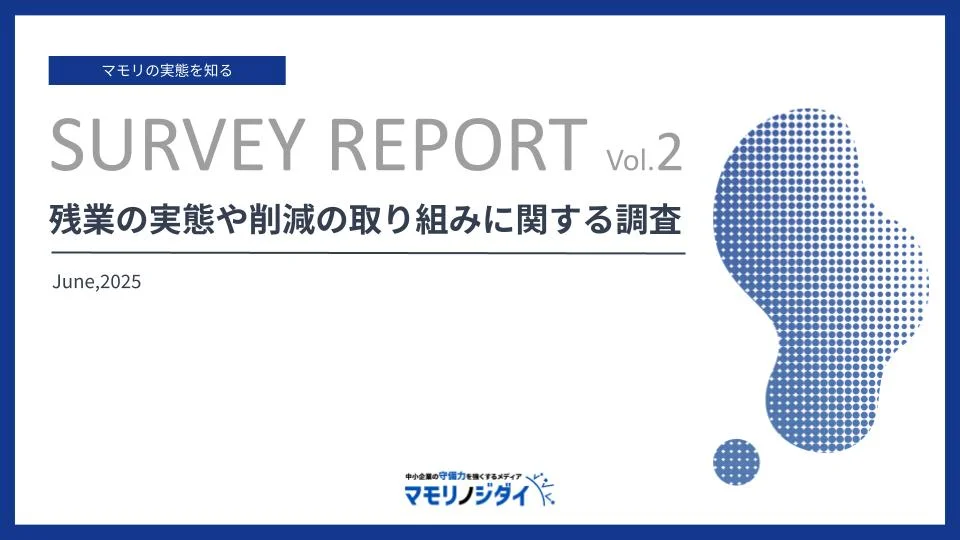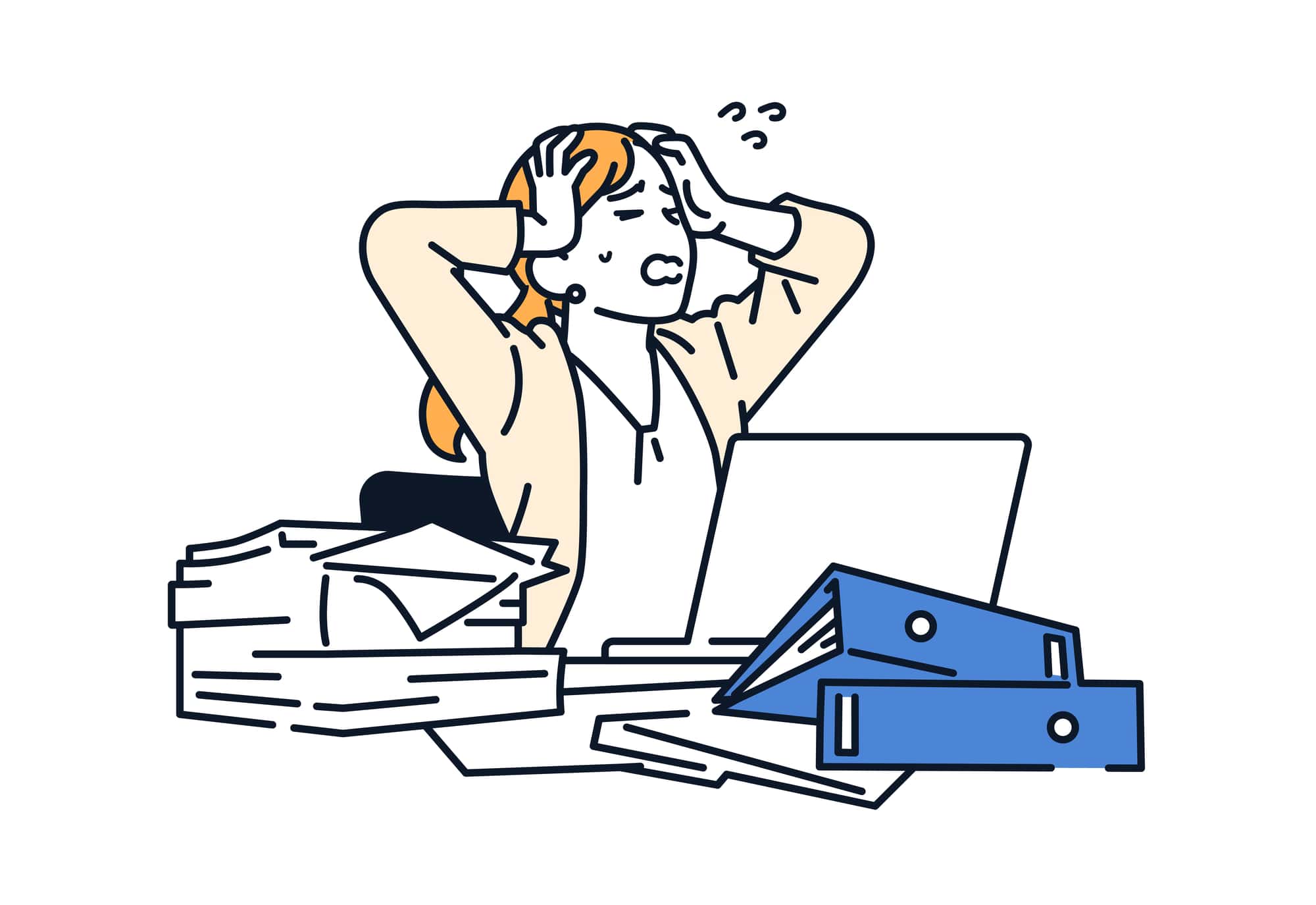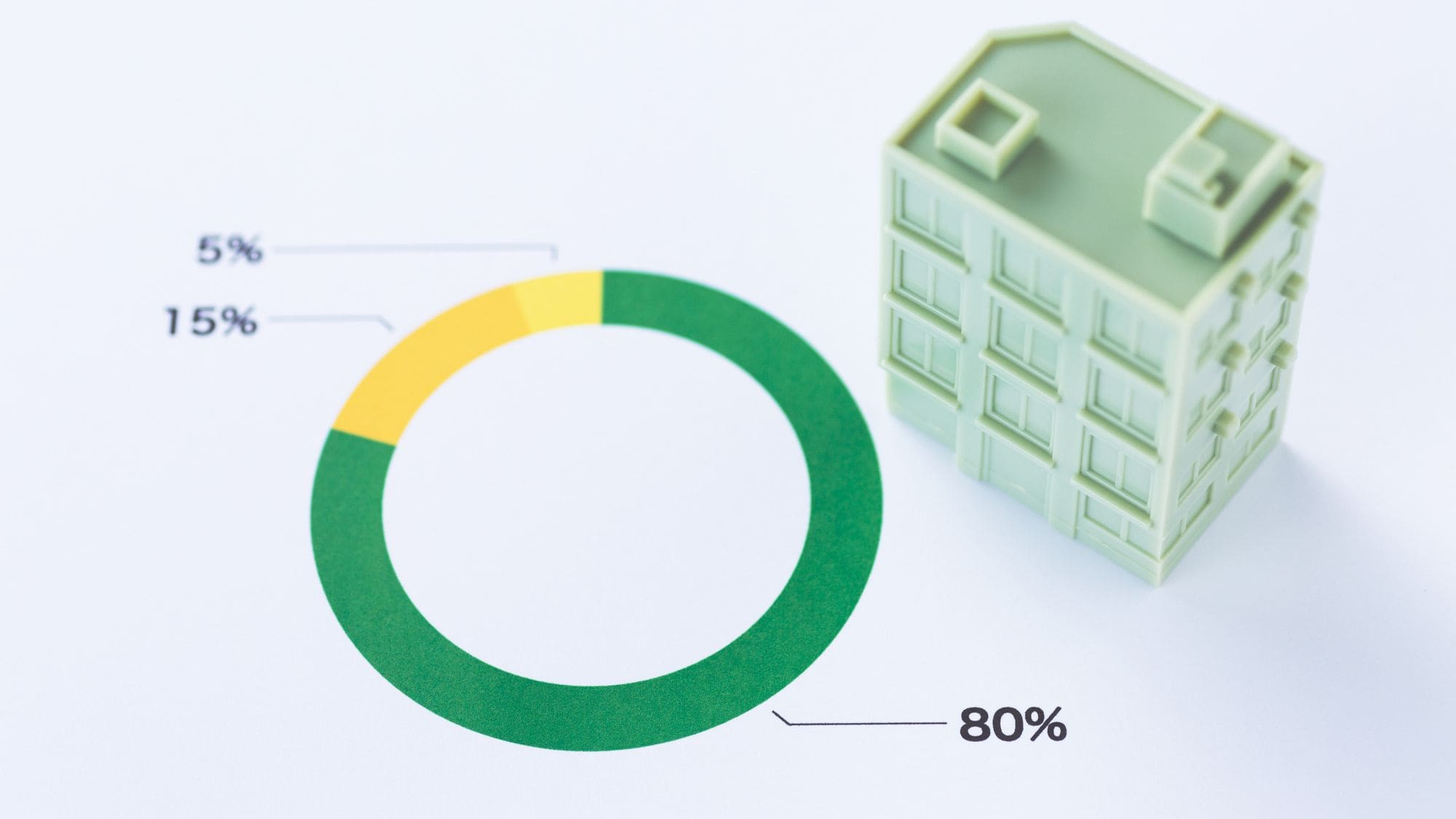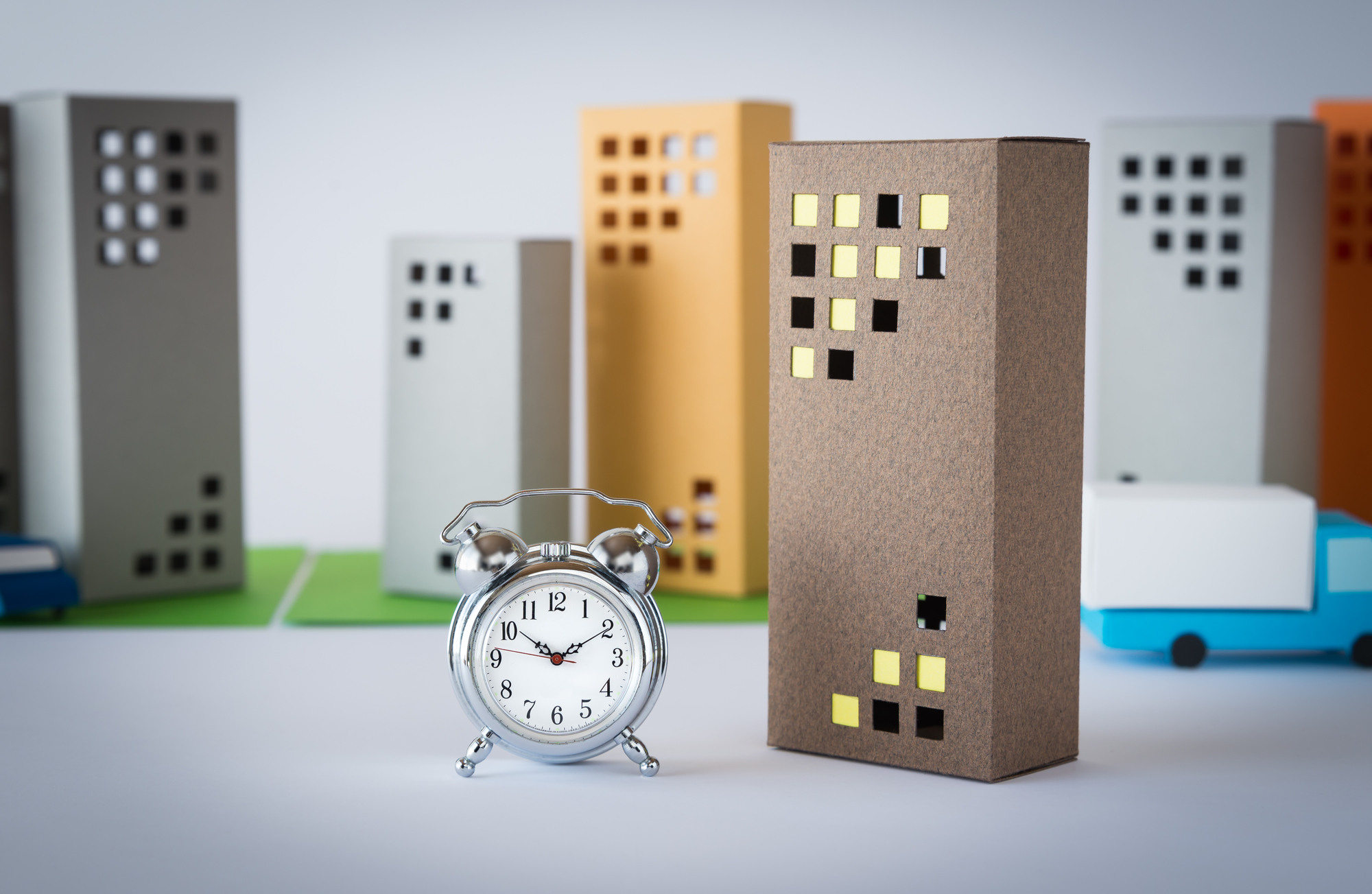36協定なしの残業は違法!残業時間の上限や違反時の罰則も把握しよう
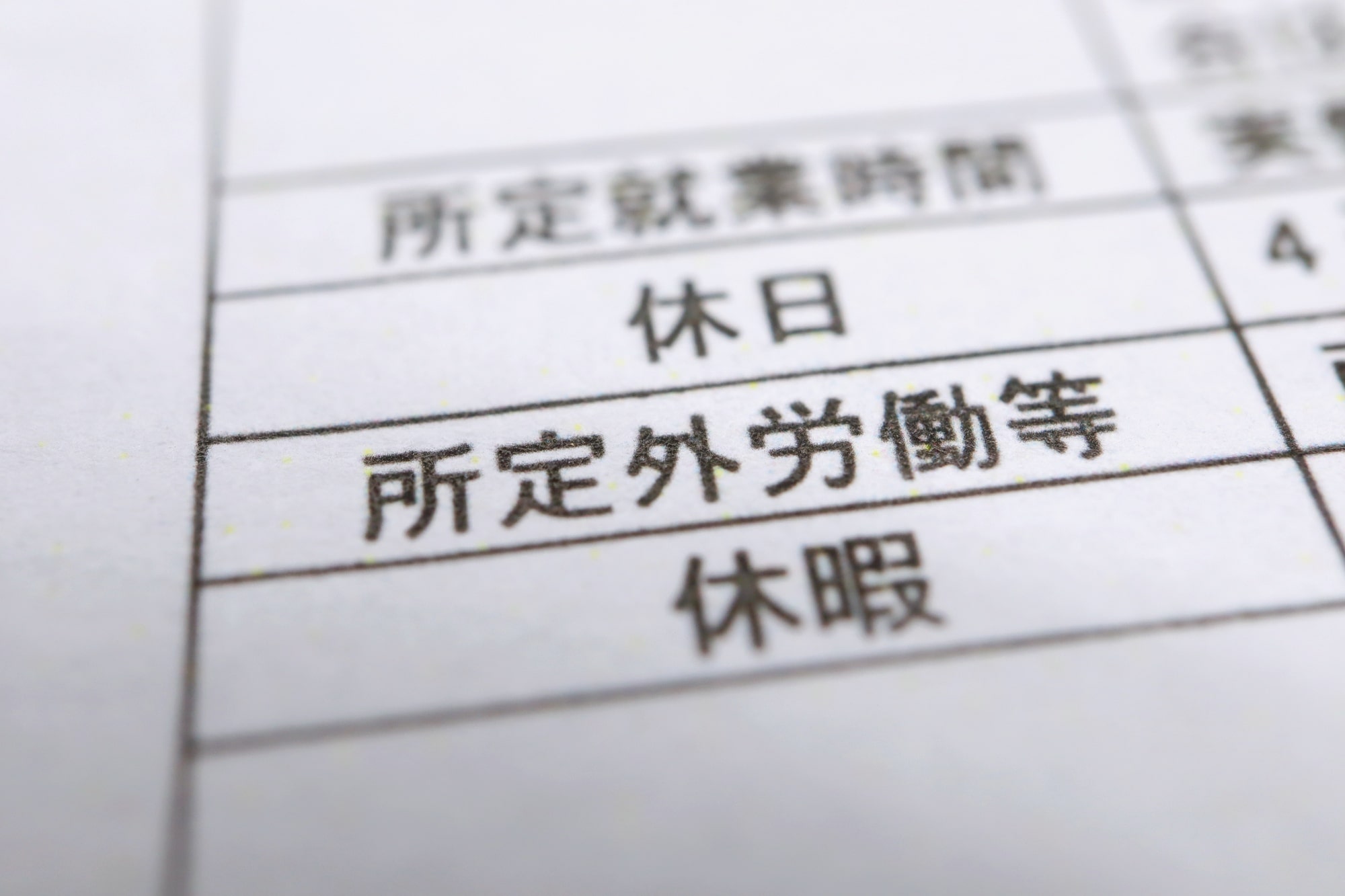
36協定は、労働基準法で定められた残業(時間外労働・休日労働)時間に関する労使協定であり、従業員に法定労働時間を超える残業をさせる場合に必ず締結・届出が必要です。
36協定を締結せずに残業をさせた場合、法律違反となり罰則が科せられるだけでなく、企業イメージの悪化にもつながりかねません。
この記事では、36協定の概要から残業時間の上限、違反時の罰則まで、中小企業の経営者が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
目次
36協定とは?
36協定とは、労働基準法第36条に定められた、残業(時間外労働・休日労働)に関する労使協定のことです。
| 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働や法定休日(毎週少なくとも1日)に労働を行わせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。 |
出典)厚生労働省「36協定の適正な締結」p.1
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて従業員に残業をさせる場合に、企業は事前にこの協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
企業が36協定を締結する相手
36協定は、企業と従業員の代表者との間で締結されます。
| 「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」締結の際は、その都度、当該事業場に➀労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労 働組合、②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者) と、書面による協定をしなければなりません。 |
出典)厚生労働省「「 36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合、その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください。」p.1
具体的には、労働組合がある場合は労働組合、ない場合は従業員の過半数を代表する者(過半数代表者)が締結の相手となります。
36協定で締結する内容
36協定では、以下の内容を締結する必要があります。
- 残業(時間外労働・休日労働)をさせる必要のある具体的な理由
- 対象となる従業員の範囲
- 残業(時間外労働・休日労働)をさせる可能性のある時間数(1日、1か月、1年)
- 協定の有効期間
- その他、必要な事項
これらの内容を明確にすることで、従業員の残業時間を適切に管理し、健康を守ることができるのです。
36協定を締結せずに残業をさせた場合、企業は労働基準法違反となり、罰則を受ける可能性があります。
参考)厚生労働省「36協定の適正な締結 1ページ」
36協定を締結しても残業時間の上限は原則「月45時間」
36協定を締結することで、企業は従業員に法定労働時間を超える残業をさせることが可能になります。
しかし、36協定を締結したとしても、残業時間には上限が設けられています。
| 時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。 |
出典)厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」p.1
これは、労働者の健康とワークライフバランスを考慮し、過度な残業を抑制するための措置です。
ただし、特別な事情がある場合には、労使合意の上で「特別条項付き36協定」を締結することで、残業時間の上限を超えることが認められます。
しかし、その場合でも、残業時間について以下の条件を守る必要があります。
- 月100時間未満
- 複数月平均80時間以内
- 年720時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月まで
残業時間の上限規制は、労働基準法で定められており、違反した場合には罰則が科される可能性があるのです。
改正労働基準法により36協定違反時には罰則が科される
改正労働基準法により、2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)から、残業の上限規制が導入されました。
36協定を締結していても、残業時間の上限規制に違反した場合、労働基準法第119条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される、また、企業名が公表される可能性があります。
36協定違反となるケースは、以下のようなものが挙げられます。
- 36協定を締結せずに残業(時間外労働・休日労働)をさせた
- 36協定で定めた上限時間を超えて残業(時間外労働・休日労働)をさせた
- 特別条項の要件を満たさないにもかかわらず、特別条項を適用した
企業は、36協定の内容をあらためて確認し、残業時間数を適切に管理することが重要です。
参考)e-GOV 法令検索「労働基準法 第119条」
36協定の対象外となるケース
従業員の残業時間を管理する上で欠かせない36協定ですが、実はすべての業務や従業員に適用されるわけではありません。
ここでは、中小企業が知っておかなければならない36協定の例外について、以下で詳しく解説します。
18歳未満の従業員
労働基準法第60条により、18歳未満の年少者は残業が禁止されています。そのため、36協定を締結していたとしても、18歳未満の従業員に残業をさせることはできません。
学生アルバイトなどを雇っている中小企業は、18歳未満の従業員の働き方について、適切に管理する必要があります。
参考)e-GOV 法令検索「労働基準法 第60条」
管理監督者
労働基準法第41条2号に定められている「管理監督者」は、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません。そのため、36協定の対象外です。
管理監督者とは、経営者と一体的な立場で職務を行い、労働時間などの規制になじまない人のことを指します。
具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
- 経営上の重要な決定に関与していること
- 労働時間について裁量権を持っていること
- 地位にふさわしい待遇を受けていること
特に中小企業においては、現場担当者兼管理監督者など、複数の役割を担うことも少なくありません。
管理監督者が36協定の対象にならないことは、念頭に置いておく必要があるのです。
参考)e-GOV 法令検索「労働基準法 第41条2号」
妊産婦の従業員から請求があった場合
労働基準法第66条により、妊産婦(妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性)の従業員から請求があった場合、残業(時間外労働・休日労働・深夜業)をさせることはできません。
36協定を締結していたとしても、妊産婦の従業員から請求があった場合は、適用できないことを覚えておきましょう。
参考)e-GOV 法令検索「労働基準法 第66条」
育児・介護をしている従業員から請求があった場合
育児・介護休業法第16条、第16条の2、第18条の2、第19条の2により、育児や介護を行う従業員から請求があった場合、残業(時間外労働や深夜業)を制限する必要があります。
36協定を締結していたとしても、育児・介護をしている従業員から請求があったなら、36協定の対象外になるのです。
参考)e-GOV 法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条、第16条の2、第18条の2、第19条の2」
新技術・新商品等の研究開発業務
労働基準法第36条11では、「新技術・新商品等の研究開発業務」の上限規制が適用外とされています。
専門的、科学的な知識や技術を有する者が従事し、新たな技術、商品、またはサービスの創出を目指す業務を指します。
これらの業務は、高度な専門知識や創造性を必要とし、多くの場合、長期的な時間と労力を要するため、労働時間の上限規制が適用除外とされているのです。
参考)厚生労働省「確かめよう労働条件 Q&A」
参考)e-GOV 法令検索「労働基準法 第36条11」
36協定において中小企業が把握しておくべきこと
36協定は、従業員に残業をさせる場合に必要となる重要な労使協定です。中小企業の経営者として、以下の点に注意し、適切に36協定を運用しましょう。
従業員の安全配慮義務を遵守する
残業による長時間労働は、従業員の健康を害するだけでなく、労働災害のリスクを高める可能性があります。
そのため、36協定を締結したとしても、企業は以下の点に留意し、従業員の健康管理に努める必要があるのです。
- 残業時間の上限を遵守する
- 定期的な健康診断を実施する
- 従業員の健康相談窓口を設置する
- 過重労働による健康障害防止に関する措置を講じる
月45時間を超える残業が必要な場合は特別条項を締結する
原則として、残業時間の上限は月45時間、年360時間です。しかし、特別な事情がある場合には、労使合意の上で特別条項付き36協定を締結することで、上限を超えることが認められます。

出典)厚生労働省「36協定届の記載例(特別条項)」p.1
特別条項を締結する際には、以下の点に注意が必要です。
- 特別条項を適用できるのは、臨時的な特別な事情がある場合に限られる
- 特別条項で定める残業時間の上限は、月100時間未満、年720時間以内とする
- 特別条項を適用する場合でも、できる限り残業時間を削減するよう努める
特別条項締結時もできる限り残業時間を減らす
特別条項を締結した場合でも、残業時間の削減に向けた取り組みは重要です。
| ⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。(指針第8条) |
出典)厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」p.2
以下のような対策を講じることで、残業時間の削減が期待できます。
- 業務の効率化
- 人員配置の見直し
- フレックスタイム制や裁量労働制の導入
- ノー残業デーの設定
残業時間の削減は、従業員の健康管理だけでなく、生産性の向上や離職率の低下にもつながります。
まとめ
36協定は、従業員の健康を守り、働きやすい職場環境を実現するために重要な制度です。
中小企業においては、労働時間管理が曖昧になりがちですが、36協定を適切に運用することで、法令遵守はもちろん、従業員のモチベーション向上や生産性向上につながります。
自社の36協定を見直し、必要に応じて専門家へ相談するなど、適切な労務管理体制を構築することが重要です。従業員が安心して働ける環境づくりにより、企業は持続的な成長が可能となるのです。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録