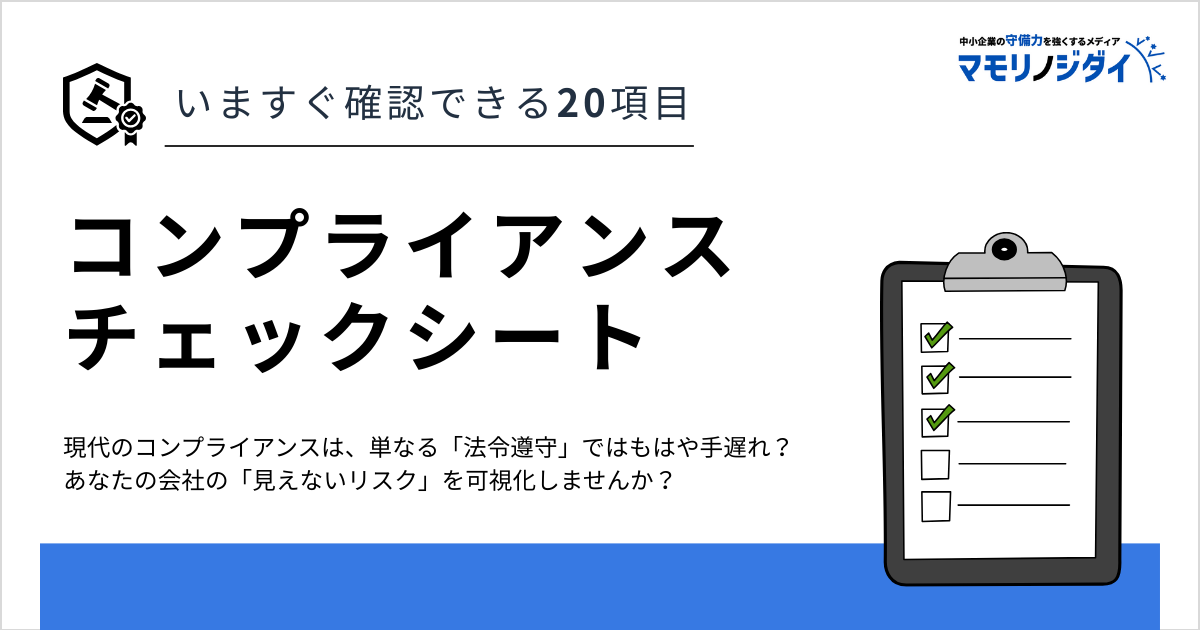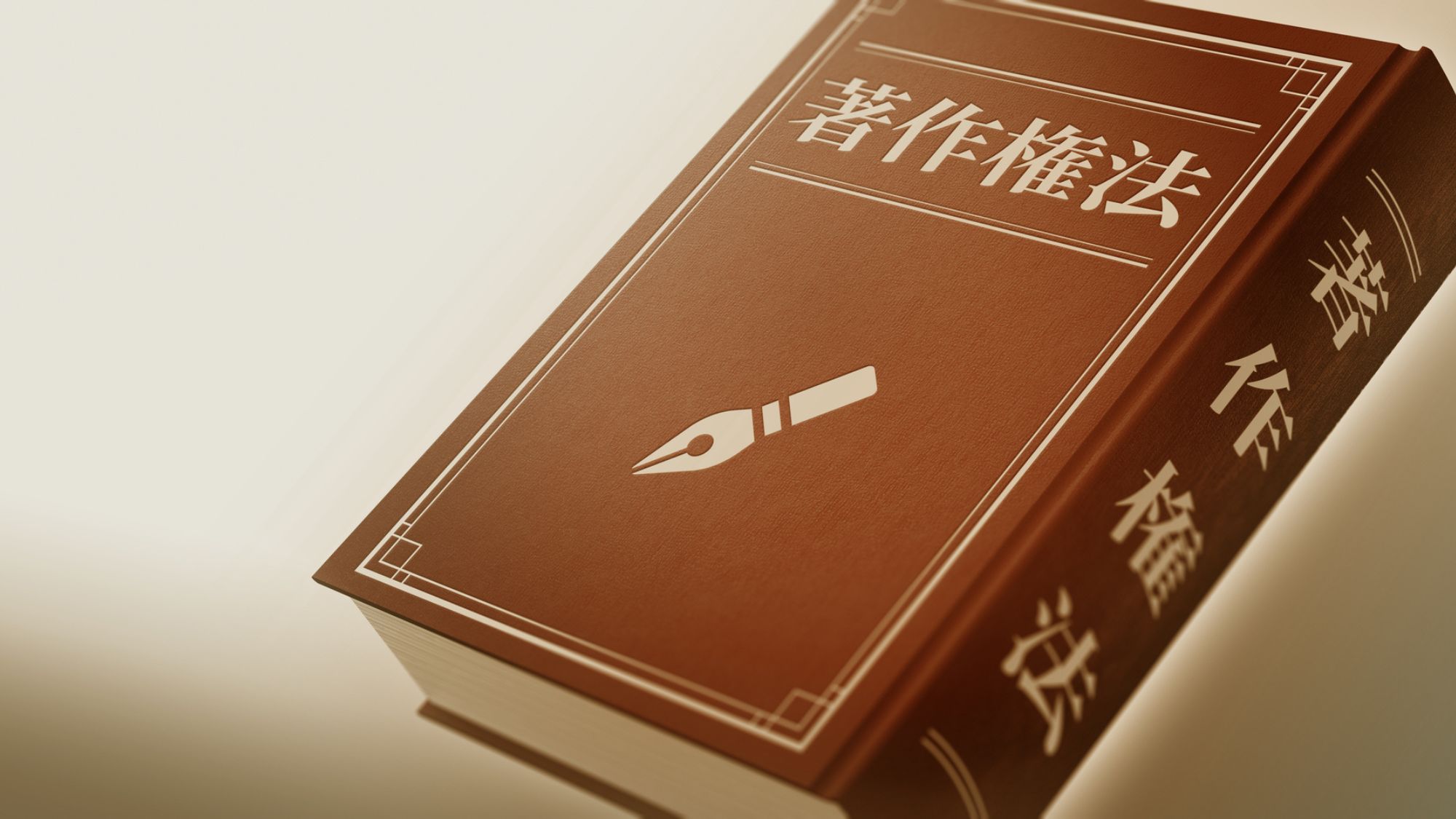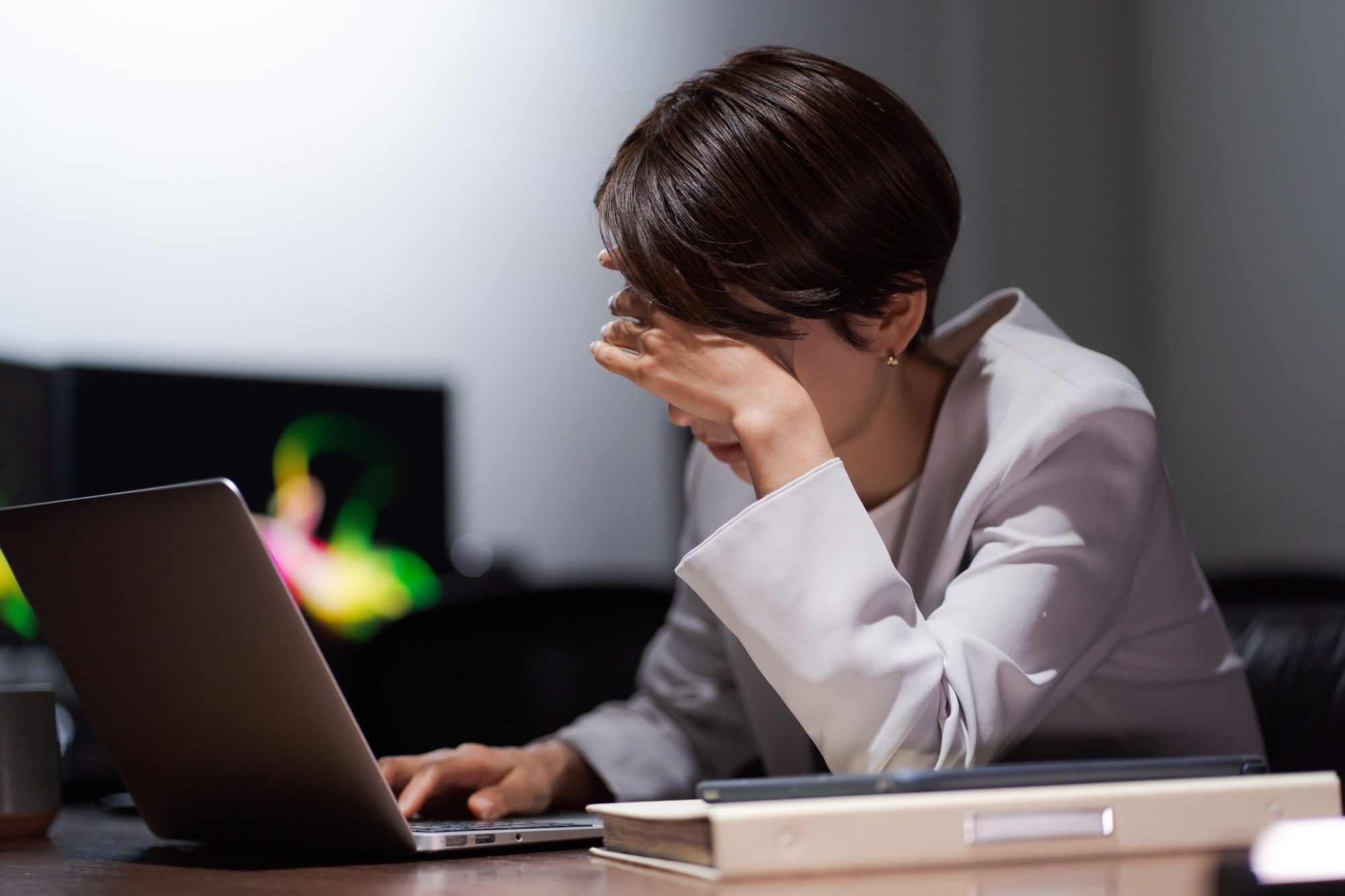【わかりやすい】景品表示法ってなに?企業が知るべきガイドライン、違反事例など
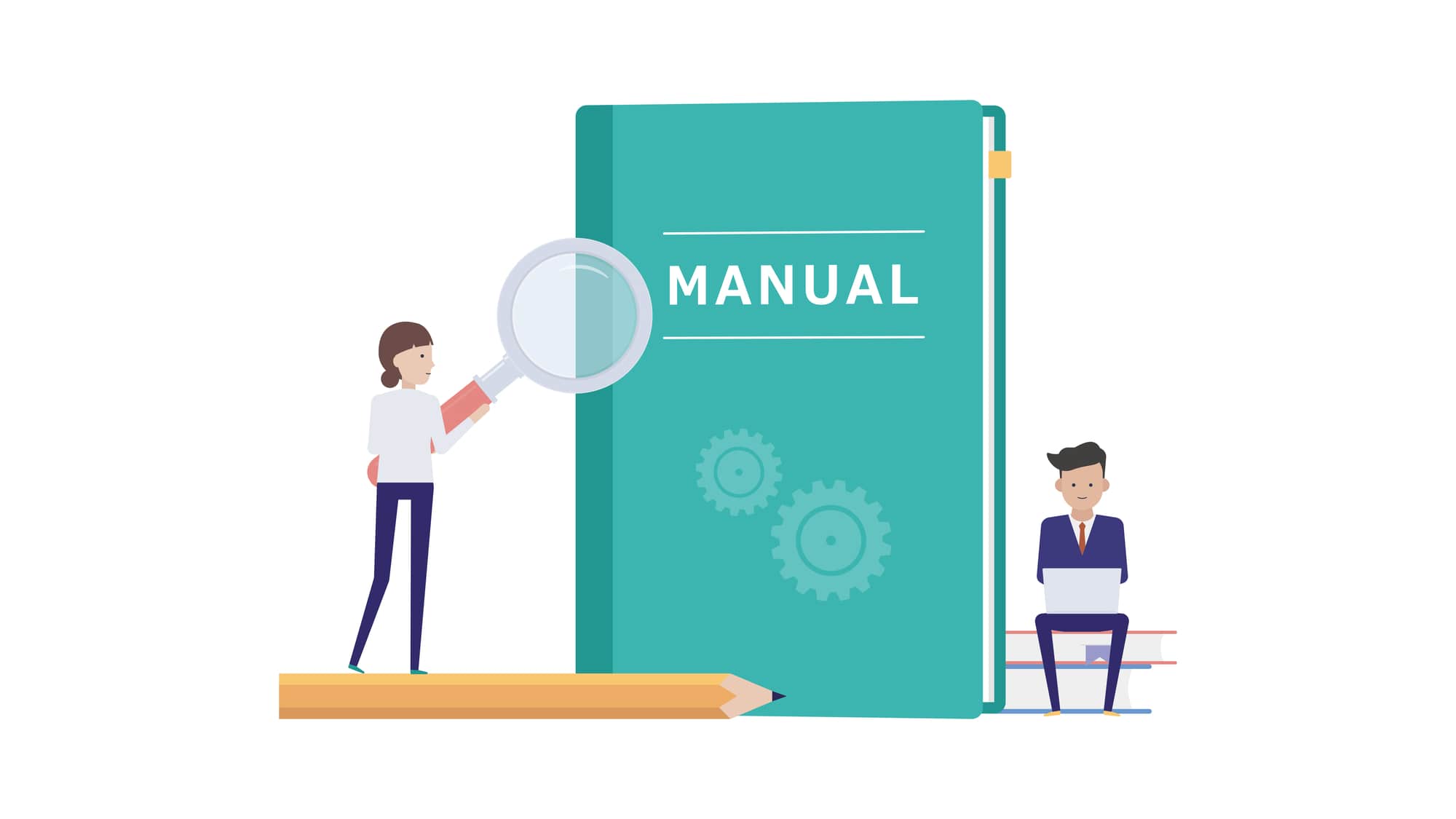
企業がマーケティング活動を行う際、商品の広告やキャンペーンの内容は消費者にとって重要な判断材料です。しかし誤解を招く表示をしてしまうと、消費者とのトラブルの原因になります。
そこで、消費者を守り、公正な市場競争を維持するために制定されているのが「景品表示法」です。
中小企業にとって、景品表示法を遵守することは「企業の安定した経営」を続けるうえで重要な守りです。本記事では、景品表示法の基本から違反事例、違反を防ぐための対策までをわかりやすく解説します。
目次
【基本】景品表示法の目的・概要とは?
景品表示法は、消費者が適正な判断をできるようにし、公正な市場競争を確保するために制定された法律を指します。正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。
企業が商品やサービスを販売する際、広告や宣伝を通じて情報を提供します。しかし誇大広告や誤解を招く表示があれば、消費者は不利益を被る可能性があるのは事実です。
そのため、景品表示法は、事業者による不当な表示や過大な景品提供を規制し、消費者を保護する役割を果たしています。
参考)消費者庁「景品表示法」
参考)e-GOV「不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)」
この法律の対象となるのは、食品や日用品、サービスなど幅広い商品・業種です。広告媒体もテレビCMやチラシ、Webサイト、SNSなど多岐にわたります。
中小企業にとっては、マーケティング活動の中で無意識のうちに違反してしまうリスクもあるのが注意点です。景品表示法のルールを理解し、消費者との信頼関係を損なわないよう配慮しましょう。
景品表示法には2つの主要ルールがある
景品表示法には、企業が守るべき2つの主要なルールがあります。それが「不当表示の禁止」と「景品類の制限」です。
それぞれの概要を確認します。
①不当表示の禁止(広告・宣伝のルール)
企業が提供する商品やサービスの品質、価格、効果などについて、実際よりも著しく優れていると誤認させる広告や宣伝は禁止されています。大きく分けると以下の2つです。
| 項目 | 詳細 | 例 |
| 優良誤認表示 | 実際よりも品質や性能が優れているように見せる | 「当社の洗剤はどんな汚れも100%落とせます」と表示したが実証していない |
| 有利誤認表示 | 価格や条件が実際よりも有利であると誤解させる | 「今だけ50%オフ!」と表示し、実は通常価格と変わらない |
このルールに違反すると、消費者庁から措置命令が出され、企業の信頼が損なわれるだけでなく、課徴金が課される場合もあります。
②景品類の制限(販促キャンペーンのルール)
販促キャンペーンにおいて、消費者に提供する景品の価値や金額には一定の制限が設けられています。これは、過大な景品提供によって消費者が本来の商品価値を適切に判断できなくなるのを防ぐためです。
具体的には、以下のような規制があります。
| 項目 | 詳細 |
| 一般懸賞 | 景品の上限額は、取引額の20倍(上限10万円) |
| 総付景品 | 景品の上限額は取引価額の10分の2(1000円以下の場合は200円) |
| 共同懸賞 | 最高額は30万円、総額は懸賞に係る売上予定総額の3% |
参考)消費者庁「景品規制の概要」
中小企業でも、プレゼントキャンペーンやノベルティ配布を行うことは珍しくありません。誤って過大な景品を提供してしまうと違反になるため、事前にルールを確認しておくことが重要です。
【要注意】中小企業が違反しやすい景品表示法のポイント
景品表示法に違反すると、企業の信頼を損なうだけでなく、行政処分や課徴金の対象になる可能性があります。特に中小企業では、広告や販促活動のルールを十分に理解せずに実施してしまうケースが少なくありません。
以下は、中小企業が違反しやすい景品表示法のポイントです。
| 項目 | 内容 |
| 根拠のない効果・品質の誇張 | 実際よりも優れた効果や品質を謳う |
| 架空の通常価格を設定 | 実際には販売していない価格を基準に「割引」と表示 |
| 「No.1」「業界最高」などの誇張表現 | 客観的な根拠がないのに業界トップを名乗 |
| 不適切な比較広告 | 客観的な根拠なしに、他社商品と比較し、自社の優位性を強調 |
| プレゼントキャンペーンの過大景品 | 規制を超えた高額な景品を提供 |
| 誤解を招く「無料」表記 | 実際には条件があるのに無料と表記 |
| ステルスマーケティング(ステマ) | PRであることを隠して広告を行う |
| ガチャの確率表示違反 | ガチャの提供割合を実際と異なる形で表記 |
中小企業が特に注意すべきポイントは、「根拠のない誇張表現」と「誤解を招く価格表示」です。
たとえば、「通常価格〇円の50%オフ!」と記載する場合、その「通常価格」が過去に一定期間販売されていた実績が必要になります。
また、「No.1」といった表現は、客観的なデータや調査結果がなければ使用できません。
くわえて、販促キャンペーンで「無料」「プレゼント」といった表記をする際にも注意が必要です。実際には条件があるのに「無料」と記載すると、消費者に誤解を与えるため、適切な注釈を付けることが求められます。
広告や販促活動を行う際には、消費者庁のガイドラインを確認し、事前にリーガルチェックを行いましょう。
景品表示法に違反すると企業はどうなる?
景品表示法に違反した場合、企業は法的なペナルティを受けるだけでなく、ブランドイメージの失墜や取引先からの信頼低下など、経営に大きな影響を及ぼします。以下の表では、景品表示法違反によって生じる具体的なリスクを整理しました。
| リスク項目 | 内容 |
| 行政処分・課徴金 | 景品表示法に違反すると、消費者庁から措置命令が下されるほか、悪質な場合は課徴金が科される。 |
| 企業イメージの低下 | 違反事例は消費者庁のWebサイトなどで公表され、社会的な批判を浴びる可能性がある。特にSNSで拡散されると、消費者からの信頼回復が難しくなる。 |
| 取引先・顧客の信用低下 | 景品表示法違反が発覚すると、取引先からの信用が失われ、新規契約の締結が困難になる。また、既存の取引先が「コンプライアンス違反」として契約を解除するケースも。 |
| 消費者からのクレーム増加 | 違反内容によっては、消費者からのクレームが急増し、裁判や集団訴訟に発展するリスクもある。特に返金対応が発生した場合、企業の負担は大きい。 |
景品表示法違反は、単なる法律違反にとどまらず、企業の信頼・売上・業務負担に多大な影響を及ぼします。特に「知らなかった」では済まされないケースも多いため、企業は日常的に法令を遵守する仕組みを構築し、違反リスクを最小限に抑える必要があります。
景品表示法に対応するために企業は何をすべき?
景品表示法の違反を防ぐためには、企業が適切なルールを策定し、社内の体制を整えることが不可欠です。以下の表では、企業が取るべき具体的な対策を整理しました。
| 対策 | 内容 |
| 広告・販促ルールのチェックリストを導入 | キャンペーン実施の際に確認するチェックリストを作成し、担当者と法務がチェックする。 |
| 法改正に合わせたガイドラインの確認 | 消費者庁が発表する最新のガイドラインを定期的に確認し、社内のルールを更新する。 |
| 社内のコンプライアンス教育 | 従業員向けの研修を実施し、違反事例をもとに学ばせる。特に広告担当者や経営層には、定期的な研修を行う。 |
| 不正表示を防ぐための広告審査フローの構築 | 法務部門やコンプライアンス担当者が広告・販促物を事前チェックできる仕組みを整える。 |
景品表示法の遵守は、中小企業の信頼性を守る上でも非常に重要です。適切なルールを策定し、従業員全員が法令を意識しながら業務を行える環境を構築しましょう。
これにより中小企業のリスクを最小限に抑え、守りを万全に固められます。
【事例で学ぶ】景品表示法の違反例
実際に消費者庁の資料をもとに、景品表示法に違反した企業の事例を紹介します。事実だけでなく、そこから得られる学びも記載しますので、参考にしてください。
優良誤認表示の事例
ある教育塾では、過去の合格実績を大きく見せるために、実際の合格者数よりも多い数字を広告に記載していました。
たとえば、特定の入学試験において「合格者数267名」と表示されていましたが、実状は表示数の半分以下となっていた事例です。消費者に対して実際よりも優れた結果を誇張して伝えるものであり、景品表示法の「優良誤認表示」に該当します。
参考)消費者庁「景品表示法の主な違反事例及び運用に係る主なガイドライン等について」 p.6
この事例の問題点は、誇張された情報が受験生や保護者に誤解を与え、実際の実績よりも優れたサービスを提供しているように見せかけたことです。
数字を誤認していただけであれば、チェック体制を強化しましょう。ただし、背景に企業の隠ぺい体質などがある場合、文化の改善が必要になります。
有利誤認表示の事例
ある企業が販売する振袖は「通常価格○○円、コーディネート価格は○○円!」と表示されていました。しかし、この「通常価格」とされる金額は根拠のない架空の価格だった、という事例です。
このような表示は、あたかも大幅な値引きが行われているように消費者に誤認させるものであり、景品表示法の「有利誤認表示」に該当します。
参考)消費者庁「景品表示法の主な違反事例及び運用に係る主なガイドライン等について」 p.5
中小企業が、割引価格やセール表示を行う際には、過去の販売実績を基にした正確な価格表示を行いましょう。消費者、顧客をだますことにならないよう、真摯にビジネスを推進する姿勢は重要です。
不当表示の事例
ある食品メーカーは、自社製品のパッケージに「○○産」と表示し、国内で生産されたものであるかのように見せかけていました。しかし、実際には外国産の原材料が混合されており、消費者に誤解を与えるものだったのです。
商品の原産国に関する虚偽の表示は、景品表示法の「不当表示」に該当します。
参考)消費者庁「景品表示法の主な違反事例及び運用に係る主なガイドライン等について」 p.7
当然のことですが、企業は製品の原産地や成分の情報を正確に記載する必要があります。チェックのルール作りはもちろん、企業としての姿勢の改善が必要です。
まとめ
景品表示法は、企業が広告や販促活動を行う際に消費者に誤解を与えないよう定められた重要な法律です。特に大手と比較してルール整備が不足しがちな中小企業では、知らずしらずのうちに違反してしまうリスクがあります。
中小企業としては、法令遵守のための社内体制を整え、広告チェックリストの導入やガイドラインの確認、コンプライアンス教育を徹底することが不可欠です。まずはよく法律を理解したうえで、企業としての守りを強化しましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録