下請法の概要と公正取引委員会の役割とは?問い合わせ方法や勧告事例を紹介
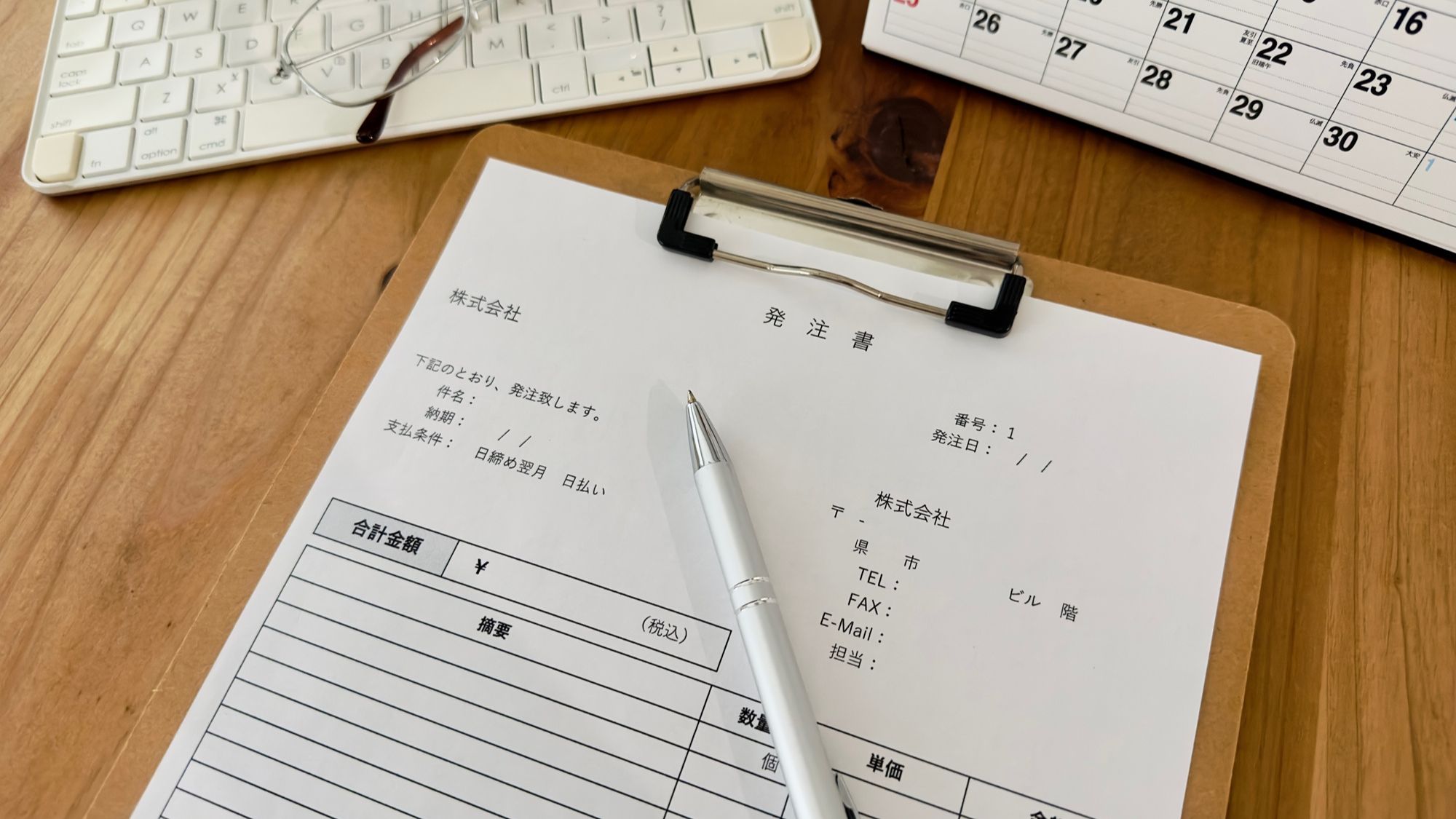
親事業者と下請事業者との間で、力の不均衡により不公正な取引が行われるケースも少なくありません。そのような事態を防ぎ、下請事業者を保護するために存在するのが「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」です。
そして、この下請法の適正な運用を監視し、違反行為に対しては厳正な措置を講じるのが「公正取引委員会」の役割です。
この記事では、下請法の基本的な概要から、公正取引委員会の役割、違反事例を紹介し、企業が取るべき対応方法について解説します。また、企業が公正取引委員会とどのように関わっていくべきかについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
下請法の概要
下請法は、下請け業者が不当な取引条件や支払い遅延などで不利益を被ることを防ぐために設けられた法律です。
| 第一条 この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。 |
出典)e-Gov 法令検索「下請代金支払遅延等防止法」
下請法の主要な目的は、下請け業者に対する不当な扱いを排除し、公正な取引を推進することです。
たとえば、契約内容を不明瞭にしたり、支払いを遅延させたりする行為を規制しています。また、下請け業者が取引先に対して過剰な負担を強いられないように、取引条件を適切に示すことが求められます。
下請法における公正取引委員会の役割
下請法は、弱い立場に置かれがちな下請事業者を保護し、公正な取引秩序を維持するための法律ですが、法律が存在するだけで、目的が達成されるわけではありません。そこで重要な役割を担うのが、公正取引委員会です。
公正取引委員会は、下請法が実際に守られているかを監視し、違反の疑いがある場合には調査を行う権限を持っています。下請事業者が不当な扱いを受けることを防ぐために、第三者機関である公正取引委員会による監視と介入が必要不可欠となります。
ここからは、公正取引委員会の詳細や調査の流れについて解説します。
参考)公正取引委員会「企業のルール違反にイエローカード! ~公正取引委員会の役割~」
公正取引委員会とは
公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する独立行政委員会です。
主な目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の不正な活動を排除することによって、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促すことです。
大きな目的の一環として、下請法の運用も担当しています。下請取引における不公正な行為は、自由な競争を阻害する要因となり得るためです。
具体的には、下請法に違反する行為がないかどうかの監視、違反の疑いがある親事業者への調査、そして違反が認められた場合の指導や勧告、さらには再発防止に向けた取り組みの促進などを行います。
また、下請事業者からの相談や違反の申告を受け付ける窓口としての機能もあり、弱い立場の下請事業者が声を上げやすい環境づくりにも努めています。
公正取引委員会による調査の流れ
調査が開始されるきっかけは様々です。下請事業者からの申告が最も代表的ですが、それ以外にも、公正取引委員会が自ら定期的に行う書面調査や立入検査、関係省庁からの情報提供などがあります。
調査が始まると、公正取引委員会は親事業者や下請事業者に対して、取引に関する資料の提出を求めたり、事情聴取を行ったりします。これは主に書面や任意のヒアリングで行われますが、刑事告発に相当すると判断された事件の調査を行う場合は、裁判官が発する許可状によって強制調査(犯則調査)が可能です。
最終的に、企業から意見を聴く「意見聴取手続」を経て、排除措置命令や課徴金納付命令が出されます。
参考)公正取引委員会「企業のルール違反にイエローカード! ~公正取引委員会の役割~」
下請法に違反した場合のペナルティ
下請法を遵守しない企業は、法的な制裁や企業イメージの損失など、重大なリスクに直面する可能性があります。
- 行政指導や勧告
- 公表措置
- 罰金
- 損害賠償
- 経営の信頼失墜や取引停止
公正取引委員会による調査の過程で、報告を求められた際に報告しなかったり、虚偽の報告をしたり、あるいは立入検査を拒んだり妨害したりした場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、金銭的なダメージだけでなく、社名が公表されることによる企業イメージの低下といったデメリットもあるのです。
公正取引委員会が公表した下請法勧告事例
公正取引委員会は、下請法違反が認められた企業に対して勧告を行い、その内容を公表しています。これらの事例を学び、自社が同様の過ちを犯さないための重要な教訓としましょう。
ここからは、勧告事例を3つ紹介します。
【事例1】食品製造販売企業
食品製造業の企業は、下請事業者に製造を委託した商品について、納期を過ぎても商品の一部を受け取らず、その商品の保管を下請事業者に無償で強制していました。さらに、受け取っていない商品に関しては、代金の支払いが行われず、下請事業者に対して不当な負担を強いることとなりました。
このような行為は、「受領拒否の禁止」や「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に該当しているとして、公正取引委員会から改善を求める勧告が出されています。
参考)公正取引委員会「(令和7年3月27日)株式会社シャトレーゼに対する勧告について」
【事例2】自動車部品メーカー
自動車部品メーカーの企業は、下請事業者に製造を委託した製品のために、自社が所有する金型や治具、検具などを貸与していました。しかし、発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対して合計3,733個の金型等を無償で保管させていたのです。
この行為は、下請事業者に対して不当な経済上の利益を提供させるものであると判断され、
公正取引委員会は、この企業に対して勧告を行い、今後同様の違反行為を行わないように指導しました。
また、下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じることといった勧告も行っています。
参考)公正取引委員会「(令和7年3月7日)株式会社フタバ九州に対する勧告について」
【事例3】ブライダル企業
ブライダル企業は、下請事業者に対しておせち料理やディナーショーチケットの購入を強制し、下請法に違反していました。
要請を断った一部の下請事業者に対して再度購入を要請するなどの行為が行われていたことに加え、購入代金の振込手数料まで下請事業者に負担させていたのです。
このような行為は、「購入・利用強制の禁止」に違反しており、公正取引委員会から勧告を受けました。
参考)公正取引委員会「(令和7年3月6日)株式会社日本セレモニーに対する勧告について」
企業と公正取引委員会の関わり方
公正取引委員会は、企業が法令を遵守し、公正な取引を行えるようにサポートする役割も担っています。企業にとって、法令遵守意識を高め、下請法違反のリスクを未然に防ぐためには、公正取引委員会が提供する情報を活用したり、直接コンタクトを取ったりすることが重要です。
ここからは、企業と公正取引委員会の関わり方について解説します。
相談・申告・情報提供
下請法に関して疑問や不安を抱いた場合、あるいは自社が下請法の規制対象となる取引を行っているにもかかわらず、親事業者から不当な扱いを受けていると感じた場合には、公正取引委員会に相談したり、申告したりできます。
公正取引委員会は、全国の事務所・支所に相談窓口を設けています。
たとえば、「自社のこの取引は下請法の適用対象になるのでしょうか」「親事業者からこのような要求をされたのですが、問題ありませんか」といった具体的な内容について、アドバイスを受けられるのです。
また、下請法に違反する事実があると思われる場合には、誰でも公正取引委員会にその事実を申告できます。
さらに、直接の当事者でなくても、下請法違反が疑われる情報を公正取引委員会に提供することも可能です。
これらの相談、申告、情報提供は、公正取引委員会が違反行為を早期に発見し、適切な措置を講じるための重要な手がかりとなります。企業がこれらの制度を積極的に活用することは、公正な取引環境の実現につながるのです。
参考)公正取引委員会「相談・申告・情報提供・手続等窓口」
講習の受講
公正取引委員会は、下請法の普及啓発と企業の法令遵守意識の向上を目的として、下請法に関する講習会を定期的に開催しています。これらの講習会は、親事業者向け、下請事業者向け、あるいは双方を対象としたものなど、様々なレベルや内容で実施されているのです。
講習会の主な内容としては、下請法の概要、親事業者の義務や禁止行為、違反事例の解説、などが挙げられます。
講習会に参加することで、企業は下請法に関する最新の情報を得られるだけでなく、自社のコンプライアンス体制を見直し、強化する良い機会となります。
参考)公正取引委員会「下請法・優越的地位の濫用規制に関する講習会」
まとめ
この記事では、「下請法」と「公正取引委員会」をテーマに、下請法の概要から公正取引委員会の役割、違反時のペナルティ、実際の勧告事例、そして企業と公正取引委員会の関わり方について解説しました。
下請法は、立場の弱い下請事業者を保護し、公正な取引秩序を維持するために極めて重要な法律です。そして公正取引委員会は、その実効性を担保するために監視や調査、指導・勧告などを行っています。
公正取引委員会が提供する相談窓口や講習会などを積極的に活用し、下請法への理解を深めていきましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録











