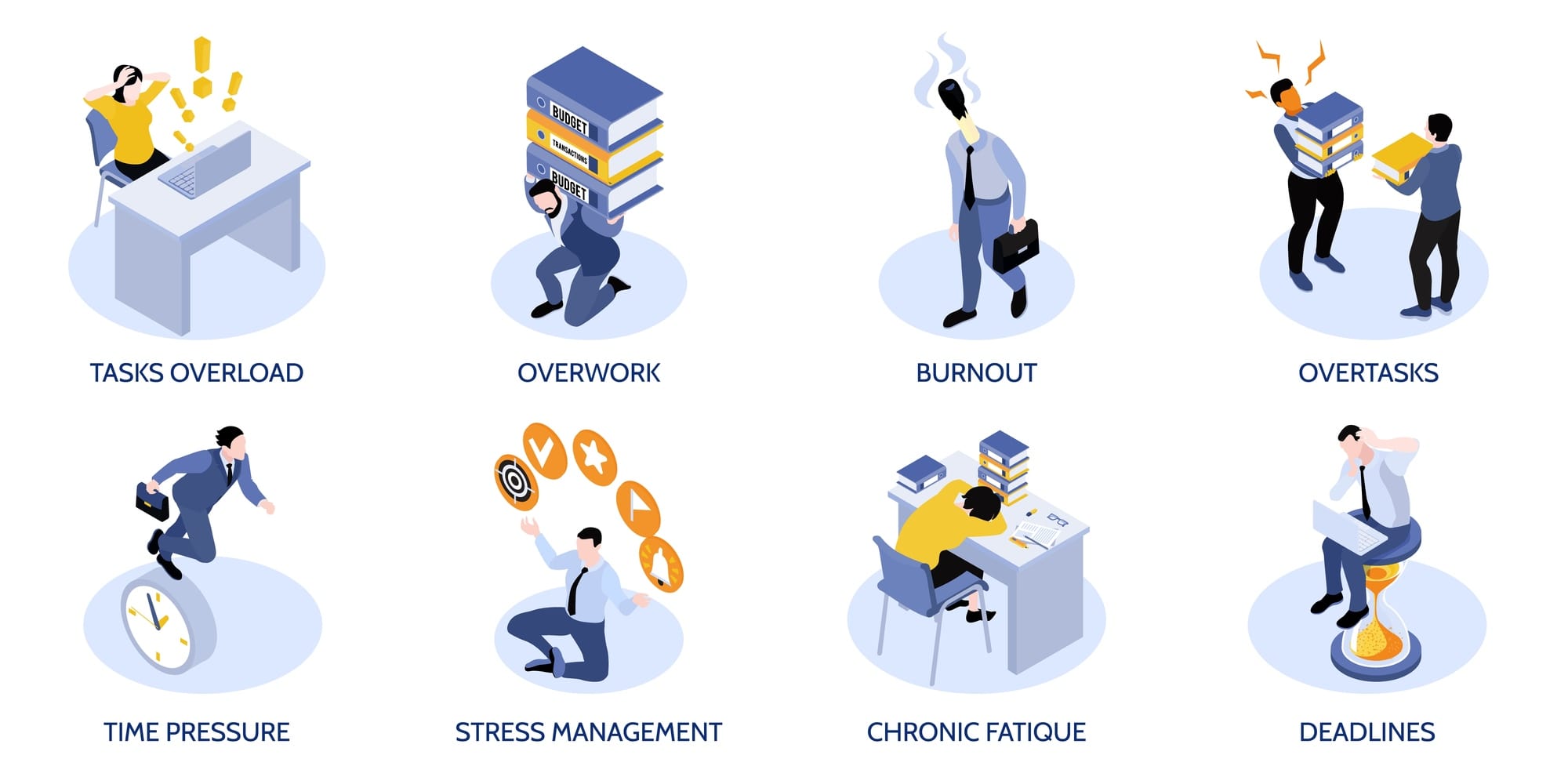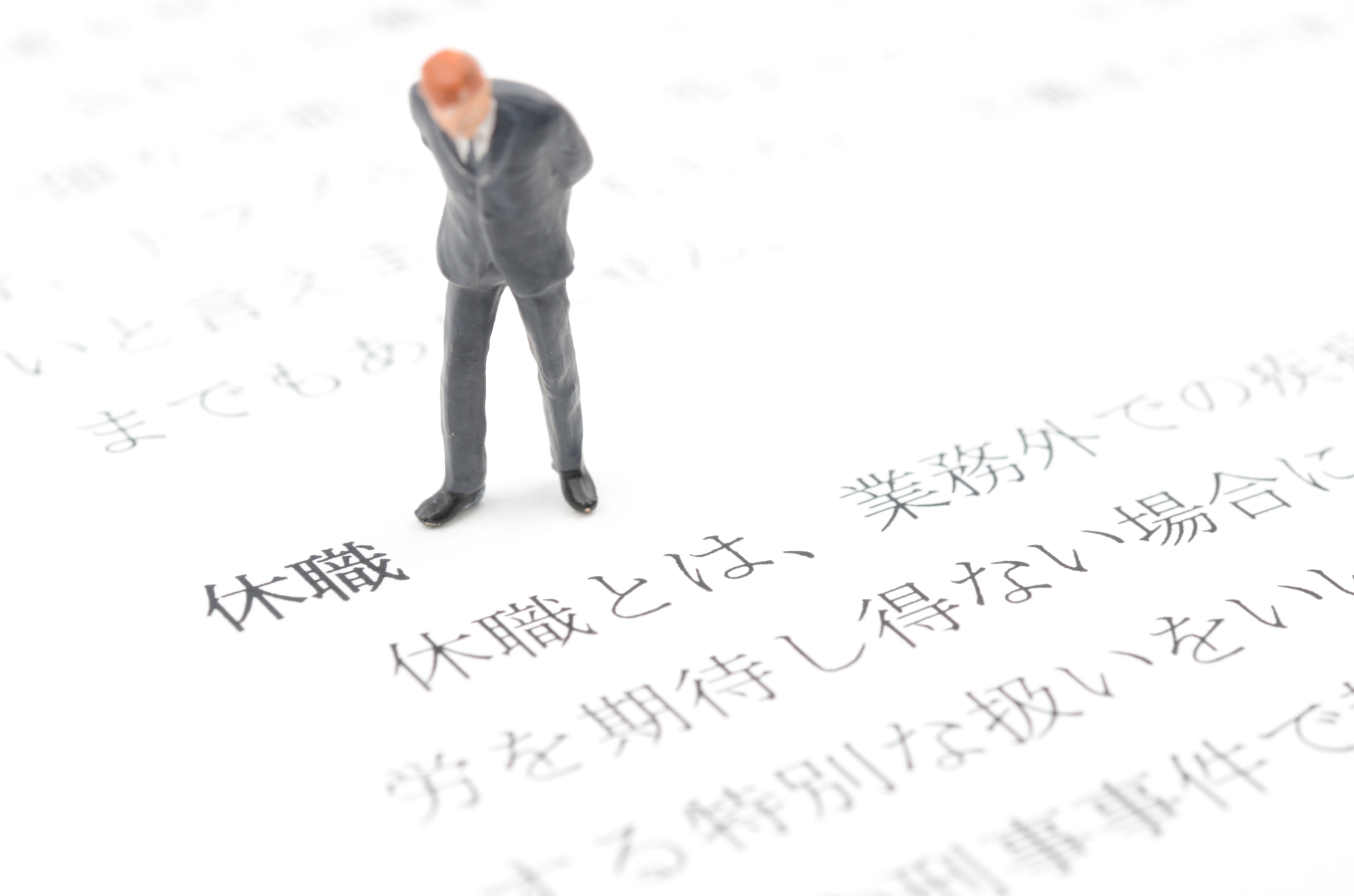【これを読めばOK】就業規則の変更手続きを徹底解説!従業員10人未満でも必要?

会社のルールブックである「就業規則」。法律の改正や会社の成長に合わせて、内容変更の必要が出てくることがあります。
この記事では、就業規則の変更は何をすればよいか、 手続きの方法について解説し、従業員が10人未満の会社でも就業規則の変更は必要なのかといった疑問をお持ちの方向けに、わかりやすく、知りたい情報を網羅していきます。
そもそも「就業規則の変更」とは?
就業規則とは、会社で働く上のルールや労働条件について定めた、いわば会社の憲法やルールブックのようなものです。
具体的には、以下のような会社で働く上で基本となる大切な事柄が定められています。
- 労働時間や休憩、休日に関すること
- お給料(賃金)の計算方法や支払い方に関すること
- 退職に関すること
- 服務規程(働く上での会社のルール、守るべきマナーなど)
そして、「就業規則の変更」とは、文字どおり、一度作成された就業規則の内容を以下のような場合に新しく変えることです。
例:
- これまでなかった新しい休暇制度を追加する
- リモートワークに関するルールを設ける
- 給料の計算方法を見直す
- 会社の組織改編に合わせて部署に関する規定を修正する
このように、既存のルール削除、内容修正、新しいルールの追加などの作業全般を指します。
参考記事:就業規則とは?記載内容や中小企業が注意すべき点をわかりやすく解説
就業規則変更は労働基準法で定められている
就業規則の作成だけでなく、変更した場合も、原則として労働基準監督署への届け出が必要であると労働基準法で定められています。
| (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 |
出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」
就業規則の変更は、単に社内ルールを書き換えるだけでなく、労働基準法に定められた手続きや内容のルールに従っておこなう必要がある、法的な手続きでもあるのです。
10人未満の中小企業でも就業規則変更は必要?
従業員10人未満の企業には、就業規則を作成したり、変更した際に労働基準監督署に届け出たりする法的な義務はありません。
だからといって就業規則を作らない、あるいは一度作ったきり変更しないでいることは、以下のようなリスクをともないます。
- 労使トラブルの発生
労働時間、休日、賃金、服務規律などが不明確なままだと、「言った」「言わない」の水掛け論になりやすく、従業員との間でトラブルに発展する可能性
- 法律違反のリスク
法改正があった際に、就業規則がない、あるいは古いままになっていると、知らず知らずのうちに法律に違反した運用をしてしまう恐れ
- 従業員の不信感
労働条件が不明確だったり、会社のルールがコロコロ変わったりすると、従業員は不信感を抱き、働くモチベーションが低下する可能性
従業員10人未満の企業であっても、就業規則を作成し、会社のルールや労働条件を明確にしておくことは重要です。
トラブルを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける環境を作るためにも、就業規則の作成や変更が推奨されます。
中小企業が就業規則変更をするタイミング
一度定めた就業規則も、さまざまな理由で変更が必要になります。主な理由は以下のとおりです。
- 法改正への対応
労働に関する法律は、社会情勢の変化に合わせて度々改正されます。会社の就業規則もそれに合わせて変更しなければ、法律違反になってしまうことがあります。
- 会社の状況変化への対応
会社の状況は常に変化します。こうした実態に合わせて就業規則を変更しないと、ルールと実態に差が生じ、運用に支障が出たり混乱が生じたりします。
- 時代の変化や多様な働き方への対応
働き方や職場に求められる基準は時代とともに変化しています。新しい働き方に対応したり、より良い職場環境を作るために就業規則を変更することがあります。
- ルールの明確化によるトラブル防止
就業規則の記述をより明確にしたり、新しいルールを追加したりすることで、将来のトラブルを未然に防ぐための変更をおこないます。
- 従業員の要望や意見の反映
従業員からの提案や意見を反映して、より働きやすい環境を作るために就業規則を変更することもあります。
とくに中小企業においては、トラブルを避け、働く環境を整える上で、就業規則を適切に変更していくことは非常に大切です。
【4ステップ】就業規則変更の正しい手順と手続き
就業規則を変更する際には、労働基準法をはじめとする法令で定められた一定の手順を踏む必要があります。この手順を正しく守らないと、変更した就業規則が無効になったり、後々トラブルの原因になったりする可能性があるのです。
ここでは、就業規則変更に必要な主な手順を4つのステップに分けて解説します。
【手順1】就業規則変更案の作成
就業規則のどこを、どのように変更したいのか、具体的な案を作成する作業です。
この段階でおこなうこと:
- 就業規則を変更する理由の明確化
- 変更したい内容を具体的に検討
- 修正・削除する、または新たに追加する条文を決める
- 変更後の条文をわかりやすく作成
必要に応じて、社会保険労務士などの専門家に相談しながら進めることも想定されます。
【手順2】従業員代表からの意見聴取と「意見書」の作成
就業規則を変更する際は、原則として、会社の従業員の過半数を代表する者(従業員代表)の意見を聴かなければなりません。
参考)e-Gov 法令検索「労働基準法」
「意見書」とは、この意見聴取を証明するための書類です。就業規則変更案について、従業員代表からどのような意見が出たのかを記載します。
【手順3】労働基準監督署への「就業規則変更届」の提出
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を変更した場合、就業規則変更届を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。
就業規則変更届の様式は、決められていませんが、厚生労働省や各都道府県労働局のウェブサイトから様式例をダウンロードできます。
参考)厚生労働省「就業規則(変更)届 様式例」
労働基準監督署への提出が必要な主な書類は以下のとおりです。
- 就業規則変更届
- 変更後の就業規則本文(または新旧対照表)
- 従業員代表者の意見書
- 返送用封筒・送付状(郵送時)
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に、持参、郵送、または電子申請システムを利用して提出できます。
【手順4】変更後の就業規則の周知義務
労働基準法第106条により、使用者は、就業規則を労働者に周知しなければならないと定められています。
参考)e-Gov 法令検索「労働基準法」
就業規則変更の効力は、原則として、この周知が完了した後に発生します。届け出はしていても、周知が不十分だと、変更した内容を従業員に適用できない場合があるため、周知は確実におこなう必要があります。
中小企業によくある就業規則変更の失敗と対策
中小企業では、担当者が他の業務と兼任していることが少なくありません。そのため、就業規則変更をおこなう際に、知らず知らずのうちに重要な手順や注意点を見落としてしまい、後々トラブルに発展するケースが見られます。
ここでは、中小企業で就業規則変更によくある失敗例とその影響、そして対策について解説します。
法改正への対応漏れ・遅れ
| 失敗例 | 育児・介護休業法や労働安全衛生法などの法改正があったにも関わらず、就業規則を最新の内容に変更しないまま運用してしまう |
| 対策 | 定期的に労働関連法の改正情報チェックの習慣をつける 厚生労働省や都道府県労働局のウェブサイト、または社会保険労務士からの情報などを活用する |
従業員代表からの意見聴取の不実施または形式化
| 失敗例 | 従業員代表からの意見聴取を忘れてしまう 就業規則変更案の内容説明を十分におこなわず、単に署名・捺印だけをもらって形式的に終わらせる |
| 対策 | 必ず従業員代表を選出し、変更案の内容を丁寧に説明し、意見の聴取時間を十分に設ける 聴取意見を意見書に記載し、就業規則変更届に添付することも忘れない |
就業規則変更届の提出漏れ
| 失敗例 | 就業規則を変更した後に労働基準監督署への変更届の提出を忘れてしまう |
| 対策 | 就業規則変更の手順をリストアップし、漏れなく実行する体制を作る必要書類を事前に準備しておく |
変更後の就業規則の周知不足
| 失敗例 | 就業規則を変更したにも関わらず、従業員にその内容をしっかりと知らせていない いつでも就業規則の内容を確認できる状態にしていない |
| 対策 | 労働基準法で定められている周知義務をしっかりと果たす重要な変更点については、説明会などを開催して丁寧に説明する |
不利益変更に関する従業員の同意取得の軽視
| 失敗例 | 労働条件を従業員にとって不利益となるように変更する場合に、個別の従業員からの十分な説明と同意を得ずに、就業規則の変更のみで一方的に労働条件を変更してしまう |
| 対策 | 不利益変更に該当する場合は、原則として個別の従業員からの同意が必要変更内容の必要性や合理性、代償措置などを丁寧に説明し、従業員が納得した上で同意を得る |
参考)厚生労働省「就業規則の不利益変更は許されるか」
自社の実態に合わない内容にしてしまう
| 失敗例 | インターネットで公開されているひな形をそのまま利用する 他社の就業規則を参考にしすぎて、自社の事業内容や組織文化、働き方などに合わないルールを作ってしまう |
| 対策 | ひな形はあくまで参考に留め、必ず自社の実態に合わせて内容を調整する必要なルールが網羅されているか、変更内容が自社の状況に合っているかを十分に検討する |
これらの失敗を避けるためには、就業規則変更の手順を正しく理解し、それぞれの段階で必要な手続きや注意点を丁寧に確認しながら進めることが大切です。
参考記事:中小企業が厚生労働省のテンプレート「モデル就業規則」を用いる際の注意点
まとめ
この記事では、就業規則の変更について、その必要性から具体的な手順、手続きまでを詳しく解説しました。
就業規則の変更は、法改正への対応や会社の状況に合わせるために不可欠であり、従業員10人未満の企業でも作成・変更・周知は強く推奨されます。
正しい手順は、変更案の作成、従業員代表からの意見聴取(意見書作成)、労働基準監督署への就業規則変更届の提出、そして従業員への周知です。
これらの手続きを怠ると、変更の効力が認められない、トラブルになるなどの失敗につながる可能性があります。とくに不利益変更には注意が必要です。
自社の就業規則が現状に合っているか、法改正に対応できているか、確認してみてください。
適切な就業規則の変更は、法を遵守し、従業員が安心して働ける環境を作るために非常に大切です。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録