固定残業代を計算するには?2種類の計算方法と注意点を紹介

固定残業代は、残業時間の有無にかかわらず一定額を支払う制度で、その計算方法や運用には注意が必要です。計算を誤ると、従業員とのトラブルや、最悪の場合、訴訟に発展する可能性もあります。
この記事では、固定残業代の基本的な知識から、2種類の計算方法、そして導入時の注意点まで、中小企業の経営者の皆様が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
固定残業代とは?
固定残業代とは、実際の残業時間にかかわらず、毎月定額で支払われる残業代のことです。企業側と従業員側に、それぞれメリット・デメリットが存在します。
固定残業代の定義
固定残業代とは、実際の残業時間にかかわらず、毎月一定時間分の残業代を給与に含めて計算し、支払う制度です。みなし残業代、定額残業代と呼ばれることもあります。
| 「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。 |
出典)厚生労働省「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」
企業は、あらかじめ残業時間と金額を設定し、基本給に含める、あるいは手当として計算して支給します。一方で従業員は、設定された残業時間内であれば、実際に残業時間が少なくても一定額の残業代を受け取れるのです。
ただし、設定された残業時間を超過した場合は、企業は超過分の残業代を計算して支払う必要があります。
固定残業代のメリット・デメリット
固定残業代は、企業と従業員双方にメリット・デメリットがあります。
企業側のメリットは以下の通りです。
| 企業側のメリット | 企業側のデメリット |
| ・残業代の計算が簡略化できる ・人件費の管理がしやすい ・従業員の残業時間を抑制できる可能性がある | ・実際の残業時間よりも多く支払うケースがある ・従業員のモチベーション低下につながる可能性がある ・長時間労働を助長する可能性がある |
従業員側のメリットは以下の通りです。
| 従業員側のメリット | 従業員側のデメリット |
| ・残業時間が少なくても一定額の残業代が保証される ・残業代の計算がわかりやすい | ・実際の残業時間に見合わないことがある ・長時間労働を強いられる可能性がある ・基本給を低く設定している場合がある |
固定残業代は、適切な運用がなされれば、企業と従業員双方にメリットをもたらす制度です。しかし、不適切な運用は、従業員のモチベーション低下や長時間労働につながる可能性もあるため、注意が必要です。
固定残業代を計算する2種類の方法
固定残業代の計算方法は、大きく分けて「手当型」と「組込型」の2種類があります。それぞれの計算方法と特徴について解説します。
参考)J-STAGE「固定残業代に関する一考察」p.88
手当型の固定残業代と計算方法
手当型の固定残業代は、基本給とは別に固定残業代を手当として計算して支給する方法です。
給与明細に「基本給〇円、固定残業手当〇円」のように、それぞれの金額が明確に記載され、固定残業時間を超えた場合は、超過分の残業代が別途支払われます。
手当型固定残業代の計算方法
- 時間単価を算出する:基本給÷1か月の平均所定労働時間
- 固定残業代に含まれる残業時間を算出する:固定残業代÷時間単価
- 超過分の残業代を算出する:時間単価×超過時間×割増率
| 手当型固定残業代のメリット | 手当型固定残業代のデメリット |
| ・基本給と残業代が明確に区分されるため、従業員が自身の給与を把握しやすい ・企業側も、残業時間の管理が比較的容易 | ・基本給を低く設定している場合がある ・固定残業時間を超えない場合でも、一定額が支払われるため、企業にとってはコスト増加の可能性がある |
組込型の固定残業代と計算方法
組込型固定残業代は、基本給の中に固定残業代を含めて計算し、支給する方法です。
給与明細には「基本給〇円(〇時間分の固定残業代を含む)」のように記載され、固定残業時間を超えた場合は、超過分の残業代が別途支払われます。
組込型固定残業代の計算方法
- 基本給から固定残業代を分離する:基本給÷(1+(固定残業時間×割増率÷1か月の平均所定労働時間))
- 固定残業代を算出する:基本給-分離した基本給
- 時間単価を算出する:分離した基本給÷1か月の平均所定労働時間
- 超過分の残業代を算出する:時間単価×超過時間×割増率
| 組込型固定残業代のメリット | 組込型固定残業代のデメリット |
| ・基本給が高く見えるため、求職者へのアピールになる場合がある ・企業側は残業代の計算を簡略化できる | ・基本給と残業代の区分が不明確になりやすく、従業員が自身の給与を把握しにくい ・固定残業時間を超えない場合でも、一定額が支払われるため、企業にとってはコスト増加の可能性がある |
固定残業代を導入する際の注意点
固定残業代は、適切な運用をすれば労使双方にメリットのある制度ですが、導入にあたってはいくつかの注意点があります。
求人広告などへの明示
求人および雇用契約締結時、固定残業代を導入する際は、以下の明示が必須です。
求人時
- 固定残業代の計算方法(時間数、金額)
- 固定残業代を除いた基本給
- 超過分の割増賃金支払い
雇用契約時
- 賃金の計算方法
- 固定残業代の内訳(基本給と割増賃金の区分)
これらは書面等で明示し、労働者が理解できる状態にする必要があります。
参考)厚生労働省「事業者・労務管理担当の方のQ&A」
適切な時間設定
固定残業時間の設定は、実際の残業時間に見合った時間数にする必要があります。
過度に長い固定残業時間の設定は、従業員の健康を害する可能性があり、違法と判断されるリスクがあります。
固定残業時間を超える可能性が高い場合は、適切な時間外労働に関する36協定の締結が必要です。
一方で、残業が発生しない月でも固定残業代を支払う必要があることにも注意が必要です。
残業時間の適切な管理
固定残業代を導入しても、従業員の労働時間を正確に把握しなければなりません。固定残業時間を超えた場合は、超過分の割増賃金を支払う必要があるからです。
適切な労働時間管理を行わない場合、未払い残業代が発生し、訴訟に発展する可能性があります。
参考)厚生労働省「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」
判例から学ぶ固定残業代のポイント
固定残業代制度を導入する際は、有効性が判例によって厳しく判断されることを理解しておく必要があります。
参考)厚生労働省「割増賃金不払い 具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性」
小里機材事件(昭和63年7月14日最高裁第一小法廷判決)
この裁判では、「基本給の中に残業代が含まれている」という会社の主張が認められませんでした。
なぜなら、給料のうち固定残業代はいくらなのかはっきり決められていなかったからです。また、法律で決まっている残業代の計算額が固定残業代を上回った場合に、差額を支払うという約束もありませんでした。
この判決からわかること
- 給料のうち固定残業代部分を明確に分けなければならない
- 実際の残業代が固定残業代より高くなったら差額を支払わなければならない
テックジャパン事件(平成24年3月8日最高裁第一小法廷判決)
この裁判では、月41万円の基本給の中に残業代が含まれていたのかが争われました。
会社は「180時間を超えた残業にだけ別途手当を払う」という契約でしたが、裁判所は「基本給の中に通常の給料と残業代が混ざっていて区別できない」と判断し、180時間以内の残業についても残業代を支払う義務があるとしました。
この判決からわかること
- 固定残業代として残業代を含める場合でも、基本給と明確に分けられていなければ、別途残業代の支払いが必要になる
日本ケミカル事件(平成30年7月19日最高裁第一小法廷判決)
この裁判では、「業務手当」という形による固定残業代の支払いが争点になりました。
雇用契約書や会社の賃金ルールに、業務手当が残業に対するものだと書かれていたこと、手当が実際の残業時間と大きくかけ離れていなかったことがポイントとなり、この業務手当は固定残業代として認められました。
この判決からわかること
- 契約書などに固定残業代制であることが明確に書かれている必要がある
- 実際の残業時間と固定残業代の計算が合っていなければならない
これらの判例から、固定残業代制度を導入する際には、内訳を明確にし、法定の割増賃金との計算に差額が発生した場合には支払う合意が重要であるとわかります。
まとめ
固定残業代は、適切な運用を行うことで、労務管理の効率化や、従業員の給与の安定化につながる有効な制度です。
しかし、計算方法を誤ると、従業員との信頼関係に亀裂が入り、トラブルに発展する可能性があります。適切な労務管理は、従業員の満足度を高め、企業の持続的な成長を支える重要な要素となります。
もし、固定残業代の計算方法や導入に関して不安な点があれば、社会保険労務士などの専門家への相談がおすすめです。
関連記事
-
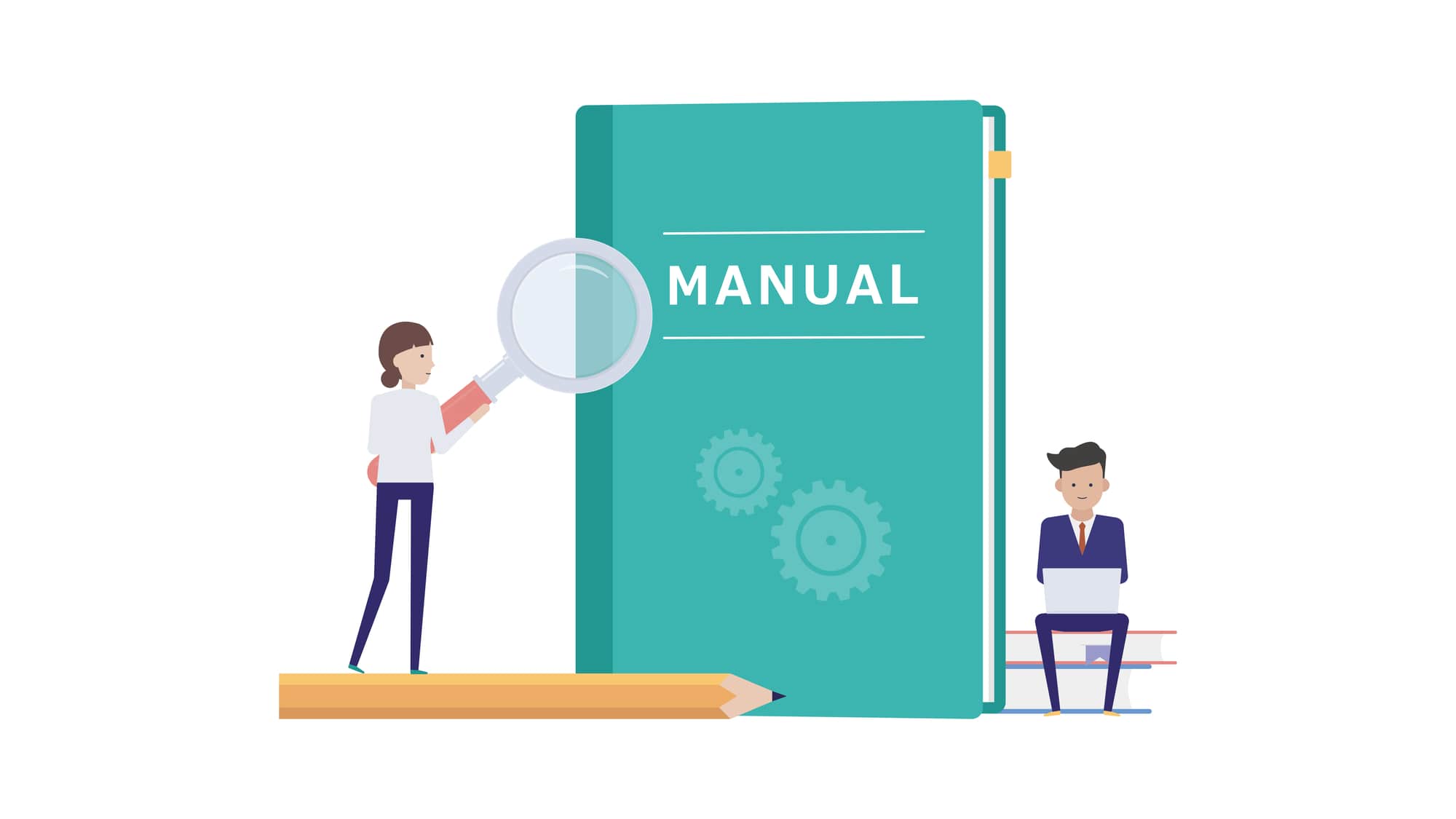
【わかりやすい】景品表示法ってなに?企業が知るべきガイドライン、違反事例など
企業がマーケティング活動を行う際、商品の広告やキャンペーンの内容は消費者にとって重要な判断材料です。しかし誤解を招く表示をしてしまうと、消費者とのトラブルの原因になります。
そこで、消費者を守り、公正な市場競争を維持するために制定されているのが「景品表示法」です。
中小企業にとって、景品表示法を遵守することは「企業の安定した経営」を続けるうえで重要な守りです。本記事では、景品表示法の基本から違反事例、違反を防ぐための対策までをわかりやすく解説します。
-

デューデリジェンスを中小企業で活かす!意味・種類・進め方を徹底ガイド
「デューデリジェンス(DD)」と聞くと、大企業のM&Aの話だと思っていませんか。実は、事業承継や新規事業への投資、業務提携など、中小企業にとっても身近なシーンで必要になる重要な調査プロセスです。
デューデリジェンスを適切に行えば、「こんなはずじゃなかった…」と後悔するリスクを大幅に減らせます。逆に、調査を怠ると、隠れた赤字や法的リスク、経営資源のミスマッチといった重大な問題を見逃しかねません。
この記事では、中小企業の経営者・管理部門の方に向けて、デューデリジェンスの意味や種類、進め方から注意点までをわかりやすく整理しました。
-
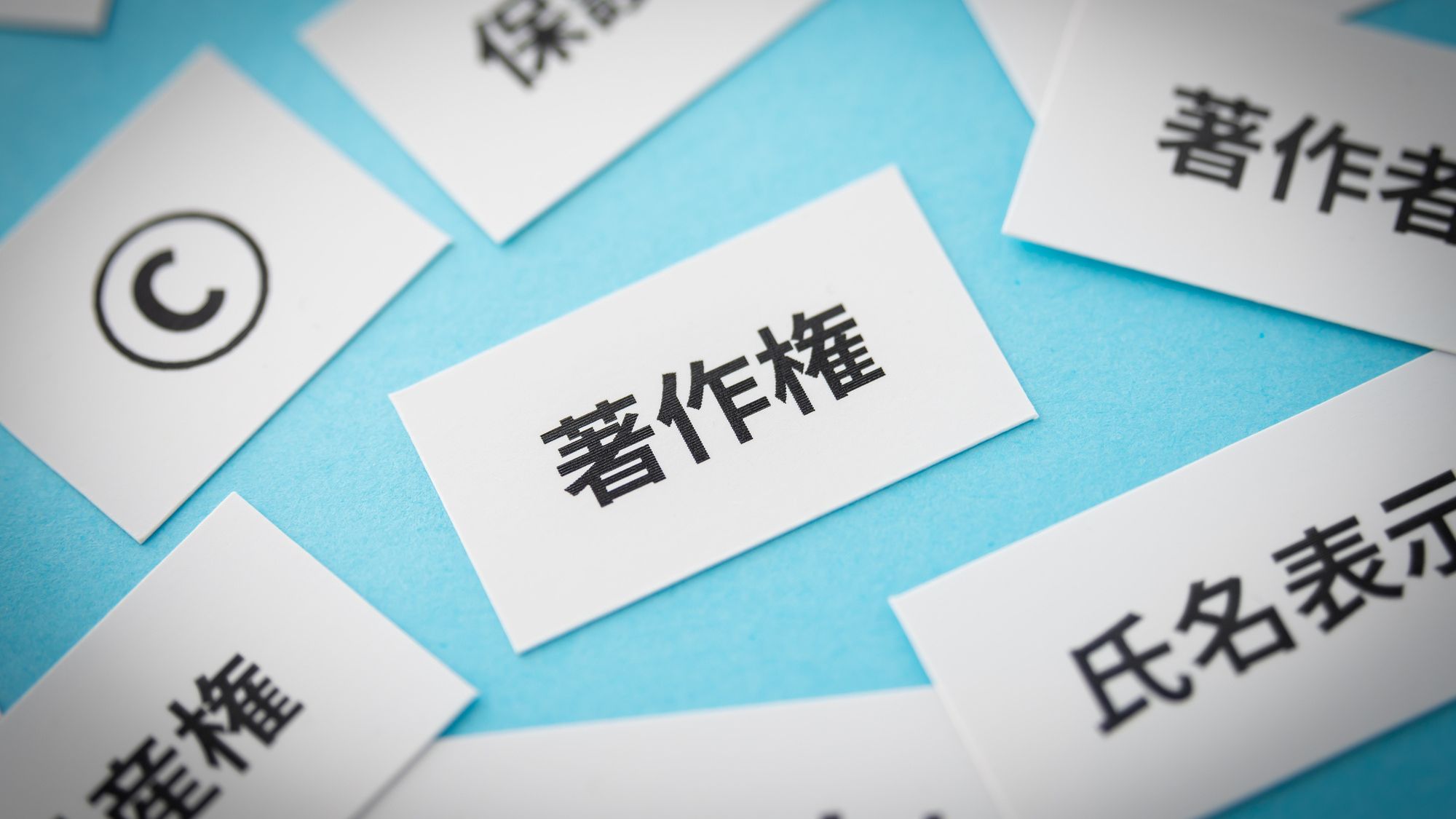
著作権法違反の罰則は?企業の事例でわかる違反行為と正しい対応策
インターネットやSNSの普及により、誰もが気軽に情報を発信できる時代になりました。しかしその一方で、他人の著作物を知らず知らずのうちに使ってしまい、著作権法に違反するリスクも高まっています。
とくに法務部を持たない中小企業では、社員の独断による作業によって、大きなトラブルにつながるケースも起こり得ます。
この記事では、著作権法違反の基本的な内容から、身近に起こり得る事例、実際の違反事例、違反時の罰則や対応方法までをわかりやすく解説するので、リスクを回避するための正しい知識を身につけましょう。
-

SOX法とは?制定されたきっかけ・対象企業・注意すべきポイントをわかりやすく解説
SOX法とは、企業の不正会計を防ぎ投資家を保護するために、アメリカで制定された法律です。
エンロン事件やワールドコム事件をきっかけに誕生し、日本でもJ-SOX法として導入されています。
本記事では、SOX法の基本概要から制定背景、日本版との違い、対象企業までわかりやすく解説します。
-

正しいクレーム対応とは?NG行為やクレームを減らす予防法
クレームに対してどのように対処するかというのはセンシティブな問題であり、対応を間違うと顧客から更なる怒りを買い、場合によっては炎上に発展してしまうケースもあります。この記事では、クレーム対応時のNG行為と対策法や、クレームを減らすための予防法を解説しつつ、クレーマーの言いなりになってしまうことによる企業側のリスクなどについても詳しく紹介していきます。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録






