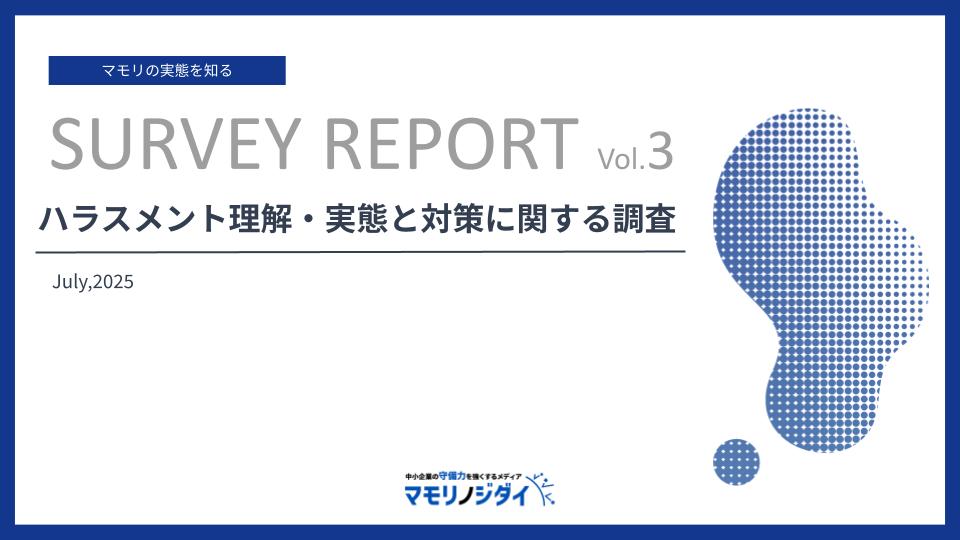中小企業で生活残業が発生しやすい原因は?やめさせるための対策を紹介

生活残業は、社員が生活費を補うために意図的に残業を増やす行動です。とくに中小企業では、給与水準の低さや管理体制の不備が原因となり、この問題が発生しやすい傾向があります。
この記事では、生活残業の基本的な定義から、その発生原因、具体的な社員の特徴、企業が負うリスク、そして実際の改善事例までを解説します。経営者として社員の働き方に目を向け、効率的な組織づくりを進めるためのヒントとしてご活用ください。
目次
生活残業とは?
生活残業とは、従業員が生活費を補うために意図的に残業を行う行為です。本来は定時内に完了できる業務を意図的に引き延ばし、残業代を得ることを目的とする行動です。
このような行動は、基本給だけでは生活が成り立たないという経済的な理由から生じることが多く、住宅ローンや教育費などの支出を補うために残業代をあてにするケースも見られます。
生活残業を放置すると、従業員の健康や生活の質に悪影響を及ぼすだけでなく、企業にとっても人件費の増加や生産性の低下といったデメリットが生じるため、企業は適切な対策を講じる必要があります。
中小企業で生活残業が発生する原因【企業・社員それぞれの事情】
生活残業は、企業と従業員の双方に起因する複合的な要因によって発生します。
ここからは、企業側と従業員側のそれぞれの要因について詳しく解説します。
企業側の要因|評価制度・環境・管理体制の曖昧さ
企業によっては、長時間労働を評価する風土が根強く残っている場合があります。このような環境では、定時退社よりも残業をすることが努力の証と見なされ、生活残業を助長する要因となるのです。
また、労働時間の管理体制が整っていない企業では、従業員の業務量や進捗状況を正確に把握できず、不要な残業が発生しやすくなります。さらに、残業が許可制でない場合、従業員が自由に残業できる環境が整ってしまい、生活残業が常態化するリスクが高まります。
社員側の要因|給与不足・ローン返済・生活不安
従業員側の要因としては、基本給の低さが挙げられます。生活費を賄うために、残業代に依存せざるを得ない状況が、生活残業を引き起こす要因となっているのです。
とくに、住宅ローンや教育費などの支出が重なると、定時の給与だけでは生活が困難になり、意図的に残業を増やす傾向が強まります。また、将来への不安から、貯蓄を増やす目的で生活残業を選択するケースも見受けられます。
参考)厚生労働省「労働時間制度等に関する実態調査結果について(速報値)」p.25
生活残業をする社員の特徴
生活残業をする社員には、いくつかの共通する行動や思考パターンがあります。
- 退勤時間がいつも同じ
- 仕事の進め方が非効率
- 残業ありきで仕事を組み立てている
これらの特徴を把握することで、企業は適切な対策を講じやすくなり、効率的な職場環境の構築に役立てることができます。
退勤時間がいつも同じ
通常、業務量や仕事内容に応じて退勤時間は日によって変動するものですが、生活残業をする社員は、意図的に業務を遅らせて定時後も働くことを習慣化していることがあります。
これにより、残業代を安定して得ることが可能になるためです。また、こうした社員は「定時に帰ると評価が下がる」という心理的なプレッシャーを抱えていることも多く、結果として同じ時間に退勤する傾向が強くなります。
仕事の進め方が非効率
仕事の効率をあまり意識せず、結果として作業時間が長引いてしまうのも、生活残業をする社員の特徴のひとつです。
本来であればもっと短い時間で完了できるはずの業務に、必要以上の時間をかけていることがあります。日中の業務時間中に集中力が散漫であったり、ほかの社員と比べて明らかに作業スピードが遅かったりする場合には、意図的に業務を長引かせている可能性も考えられます。
残業ありきで仕事を組み立てている
生活残業をする社員のなかには、最初から残業することを前提として一日の仕事のスケジュールを組み立てている人もいます。定時内にすべての業務を終わらせようという意識が希薄で、日中は比較的ゆっくりと仕事を進め、夕方以降の残業時間で本格的に業務に取り組むといったケースです。
このような働き方は、本人の生産性向上を妨げるだけでなく、周囲の社員の士気にも影響を与えてしまいます。
生活残業を放置することによる会社への悪影響
生活残業は単に社員の働き方の問題にとどまらず、企業全体に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。具体的には、以下のとおりです。
- 人件費が増え、経営を圧迫する
- ほかの社員のモチベーションが下がる
- 「ブラック企業」のイメージがつくリスク
それぞれ詳しく見ていきましょう。
人件費が増え、経営を圧迫する
生活残業を放置すると、ムダな残業代が積み重なり、結果として企業の利益率が低下する可能性があります。残業代は通常の時間給よりも割増されるため、長時間の生活残業が常態化すれば、その負担は企業の経営に大きな影響を与えます。
とくに、中小企業では人件費の増加が直接的なコスト圧迫要因となり、経営の安定を脅かしかねません。さらに、過剰な残業は従業員の生産性を低下させ、長期的には会社全体の競争力を弱めるリスクも伴います。
ほかの社員のモチベーションが下がる
生活残業を見過ごすと、ほかの社員に対する不公平感が生まれることがあります。たとえば、一部の社員が意図的に残業を増やして高い給与を得ている一方で、効率よく仕事を終わらせている社員が適切に評価されていない場合、職場全体の士気が低下する可能性があります。
このような状況が続くと、優秀な社員が不満を抱き、最終的には離職につながることもあるのです。組織の健全な成長を支えるためには、全社員が公平に評価される環境を整えることが重要です。
「ブラック企業」のイメージがつくリスク
生活残業を放置することは、外部から「ブラック企業」と見なされる原因にもなり得ます。
社員の口コミやSNSでの評判が広がると、採用活動にも悪影響を与え、人材確保が難しくなる可能性があります。
企業としては、働きやすい職場環境を整えることが、優秀な人材の確保と定着に不可欠です。
生活残業をやめさせるための対策
生活残業は企業にとってコスト増や生産性低下の要因となり、従業員にとってもワークライフバランスを損なう大きな問題です。そのため、適切な対策を講じることが重要です。
ここでは、生活残業を減らし、効率的な働き方を実現するための具体的な対策について解説します。
給与や待遇を見直し、残業に頼らない仕組みをつくる
生活残業が発生する大きな要因のひとつに、基本給の低さがあります。従業員が残業代に依存せずに生活できるよう、給与水準の見直しが必要です。
たとえば、基本給の引き上げや成果に応じたインセンティブ制度の導入が効果的です。また、職務や成果に基づく評価制度を整えることで、残業をせずとも十分な報酬が得られる環境を整えることが求められます。
さらに、福利厚生の充実も重要です。住宅手当や家族手当、退職金制度など、従業員が将来への不安を感じにくい待遇を整えることが、生活残業の根本的な抑止力となります。
残業を「許可制」にしてダラダラ残業を防ぐ
残業を減らすためには、そもそもムダな残業が発生しないような仕組みづくりが必要です。そのひとつが、残業を許可制にする方法です。
具体的には、管理職の事前承認がなければ残業ができないルールを設定し、ダラダラ残業を防ぐことが求められます。これにより、上司が部下の業務量や進捗を把握しやすくなり、適切な業務配分が実現可能です。
また、残業の必要性を都度確認することで、従業員自身が業務の優先順位を見直し、効率的な働き方を意識するきっかけにもなります。
「定時退社=悪」な空気を変える
日本の職場には「定時で帰る社員はやる気がない」といった暗黙のプレッシャーが存在する場合があります。これが生活残業を助長する一因となることが多いため、定時退社が評価される文化を醸成することが重要です。
たとえば、成果主義のインセンティブ制度を導入したり。ノー残業デーを設定したりする方法があります。また、経営層や管理職が率先して定時退社を実践し、その価値を社内に浸透させることも大切です。
これにより、効率重視の職場文化が根付き、生活残業の抑止につながります。
業務量・工数の可視化でマネジメント力を高める
生活残業を防ぐには、業務量や工数を可視化し、マネジメント力を高める必要があります。
具体的には、プロジェクト管理ツールや勤怠管理システムを活用し、各従業員の業務負荷を正確に把握することが重要です。これにより、適切な人員配置や作業効率の改善が可能になり、ムダな残業を減らす効果が期待できます。
また、業務の進捗状況を定期的に確認し、必要に応じてタスクの再分配や優先順位の見直しを行うことで、生産性の向上も図れます。
生活残業を防止した企業の事例紹介
生活残業の解消には、企業ごとの課題に応じた具体的な対策が求められます。
ここでは、建設業、医療・福祉業、製造業の各分野で、生活残業の削減に成功した事例を紹介します。
業務の見直しやDX化:建設業
建設業界では、長時間労働や人手不足といった業界特有の課題に対応するため、働き方改革を積極的に推進した事例があります。
業務プロセスのデジタル化や週休二日制の導入、ノー残業デーの柔軟な設定を進め、社員の労働時間の短縮と生産性向上を目指しました。
具体的には、オンライン会議システムの活用により、現場と本社間の移動時間を削減し、効率的な情報共有を実現しています。また、年次有給休暇の計画的付与制度を導入し、社員が積極的に休暇を取得できる環境を整備しました。
参考)働き方・休み方改善ポータルサイト「みづほ工業株式会社」
年間シフトの作成や休みやすい文化づくり:医療・福祉業
医療・福祉施設では、職員の働きやすさと休みやすさを両立させるため、年間シフトの導入や人員体制の強化、ICTの活用など、さまざまな取り組みを実施した事例があります。
これらの取り組みにより、職員の定着率が向上し、有給休暇の取得率も改善され、働きやすい職場環境の整備が進んでいます。また、保護者からも「子どもを預けるのはこの施設が良いが、働くのはほかの施設が良い」といった声が聞かれたことをきっかけに、職員の意見を取り入れた職場改善が進められました。
これにより、職員の満足度が向上し、保護者からの信頼も厚くなっています。
参考)働き方・休み方改善ポータルサイト「社会福祉法人山ゆり会」
勤怠データの見える化とカイゼン活動:製造業
製造業界では、働き方改革の一環として、勤怠データの見える化や多能工化の推進、カイゼン活動の活性化など、さまざまな取り組みを実施した事例があります。
これらの施策により、社員同士の助け合いの風土が醸成され、休暇取得のしやすい環境が整備されました。
また、管理職も一般社員と同様に労働時間管理を行い、育児や介護などの事情で時間制約のある社員も活躍できる体制が整っています。これらの取り組みにより、社員の意識改革が進み、生産性の向上や働きやすい職場環境の実現につながっています。
参考)働き方・休み方改善ポータルサイト「株式会社山本製作所」
まとめ
生活残業は、従業員が生活費を補うために意図的に残業を行う行為であり、企業にとっては人件費の増加や職場の士気低下、さらには「ブラック企業」と見なされるリスクを伴います。
その背景には、評価制度の不備や給与水準の低さ、管理体制の甘さなどが存在します。生活残業を防ぐためには、給与や待遇の見直し、残業の許可制導入、効率的な働き方を評価する社風の醸成、業務量の可視化といった対策が有効です。
これらの取り組みにより、健全な労働環境を築き、生産性の向上と従業員の満足度向上を目指しましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録