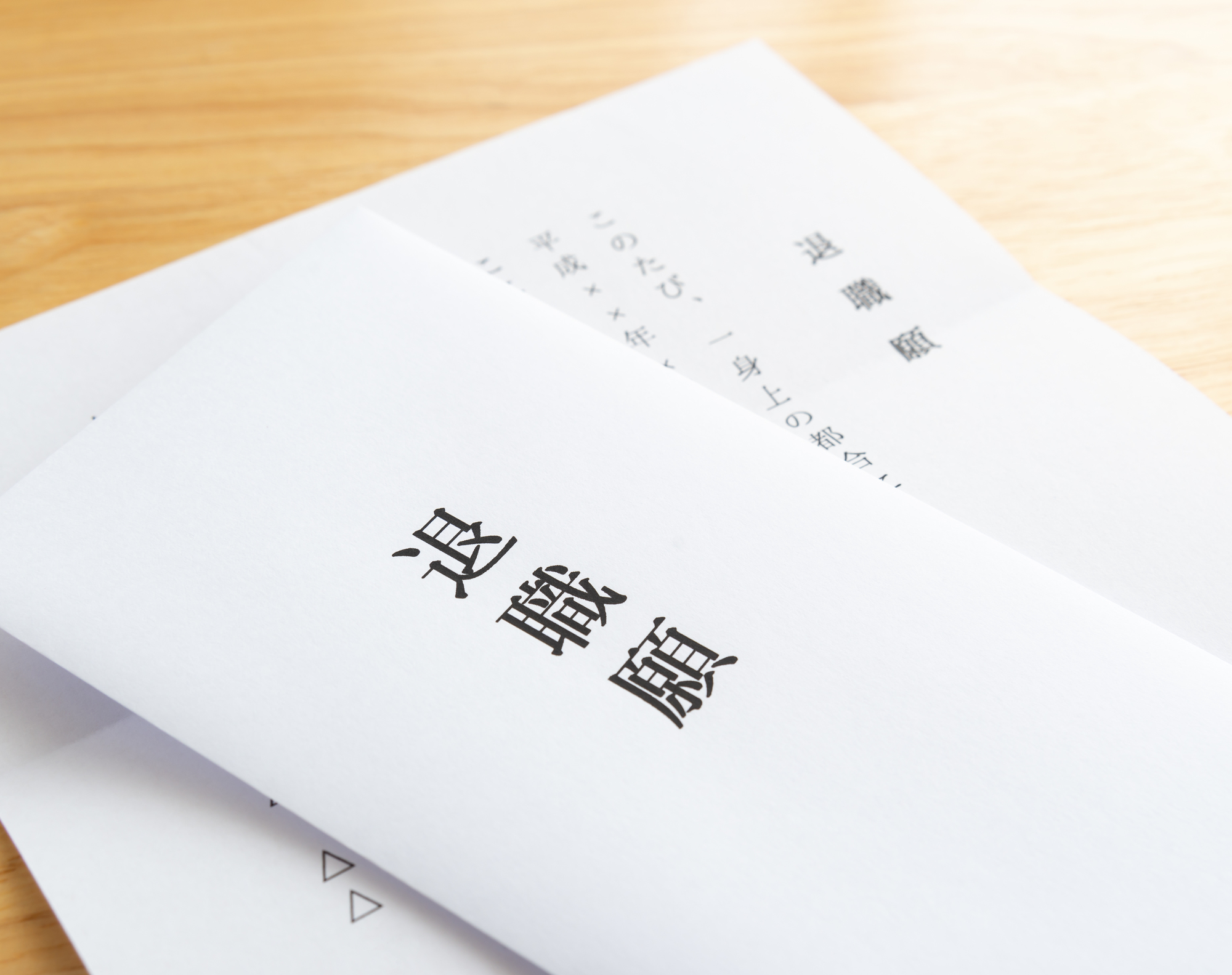労働条件とは?労働条件明示の義務と記載すべき内容を解説

中小企業の経営者や人事担当者にとって、「労働条件」の理解は避けて通れない重要なテーマです。従業員とのトラブルを防ぐためにも適切な対応が求められます。
この記事では、中小企業が知っておくべき労働条件の基本と、最新の法改正に対応するための実務ポイントをわかりやすく解説します。従業員との信頼関係を築くためにも、正しい情報を押さえておきましょう。
目次
労働条件とは?中小企業が知っておくべき基本と法的ルール
労働条件とは、労働者が働く際の基本的な取り決めを指し、賃金、労働時間、休日、業務内容などが含まれます。これらの条件は、労働者の働き方や生活に直結するため、企業が明確に定め、労働者に通知することが求められます。
| (労働条件の明示)第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 |
出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」
明確な労働条件の提示は、労使間のトラブルを未然に防ぎ、健全な労働関係を築くために不可欠です。
労働条件通知書の発行対象者
労働条件通知書は、すべての労働者に対して交付する義務があります。
正社員はもちろん、パートタイム労働者やアルバイト、契約社員、派遣社員など、雇用形態を問わず、労働者を新たに雇い入れる際には、労働条件通知書を交付しなければなりません。
参考)厚生労働省 愛媛労働局「労働条件の明示について」
労働条件通知書と雇用契約書の違い
労働条件通知書と雇用契約書は、いずれも労働者の労働条件を明示する文書ですが、その性質と法的効力には違いがあります。
労働条件通知書は、労働基準法第15条に基づき、使用者が労働者に対して労働条件を明示するための書面であり、交付が義務付けられています。
一方、雇用契約書は、労働者と使用者が労働契約の内容について合意したことを証明する契約書であり、法的な作成義務はありません。しかし、トラブル防止の観点から作成が推奨されています。
参考)J-Net21「雇用契約書の作成」
労働条件の明示事項
労働基準法第15条では、使用者が労働契約を締結する際、労働者に対して労働条件を明示する義務があると定められています。
この明示事項は、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の2つに分類されます。それぞれの内容を見ていきましょう。
参考)厚生労働省「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。」
参考)J-Net21「雇用契約書の作成」
絶対的明示事項
絶対的明示事項とは、すべての労働契約において、使用者が労働者に必ず明示しなければならない項目を指します。これらの事項は、書面での明示が義務付けられており、具体的には、以下の項目が該当します。
- 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業の場所および従業すべき業務に関する事項
- 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
- 賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
企業は、「労働条件通知書」や「労働条件通知書 兼 雇用契約書」を通じて、これらの情報を明確に伝える必要があります。
相対的明示事項
相対的明示事項とは、企業が就業規則や労働契約において定めを設けている場合に、労働者に対して明示しなければならない項目を指します。これらの事項は、企業が制度として導入している場合に限り、明示が求められます。
具体的には、以下の項目です。
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与およびこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品そのほかに関する事項
- 安全および衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰および制裁に関する事項
- 休職に関する事項
明示の方法については、書面での交付が推奨されますが、口頭での説明でも差し支えないとされています。ただし、労使間の誤解やトラブルを防ぐためにも、書面での明示が望ましいでしょう。
2024年4月に変わった労働条件の明示ルール
2024年4月1日より、労働基準法施行規則の改正に伴い、労働条件の明示義務に新たな項目が追加されました。
これにより、企業は労働者との契約締結時や有期契約の更新時に、以下の4つの事項を明示する必要があります。
- 就業場所・業務の変更の範囲の明示【すべての労働者】
- 更新上限の明示【有期契約労働者】
- 無期転換申込機会の明示【有期契約労働者】
- 無期転換後の労働条件の明示【有期契約労働者】
それぞれ見ていきましょう。
参考)厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」
参考)有期契約労働者の無期転換ポータルサイト「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。」
就業場所・業務の変更の範囲の明示【すべての労働者】
2024年の改正によって、就業場所・業務の変更の範囲の明示が必要になりました。
すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要です。
将来的な配置転換や異動の可能性を含めた範囲を明確にすることで、労使間の認識のズレを防ぐことを目的としています。
更新上限の明示【有期契約労働者】
有期契約労働者に対しては、契約締結時および更新時に「契約更新の上限の有無と内容」を明示する義務が新たに課されました。具体的には、通算契約期間や更新回数の上限を設定している場合、その内容を明確に伝える必要があります。
また、契約締結後に更新上限を新設または短縮する場合は、その理由を労働者に事前に説明することが求められます。
無期転換申込機会の明示【有期契約労働者】
改正により、有期契約労働者が通算5年を超えて契約を更新した場合に発生する「無期転換申込権」について、企業はその申込機会を明示する義務が追加されました。
これは、労働者が無期契約への転換を希望する場合、その権利を行使できることを明確に伝えるためです。
具体的には、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに明示する必要があります。
参考)厚生労働省「無期転換ルールについて」
無期転換後の労働条件の明示【有期契約労働者】
無期転換申込権が発生する契約更新時には、無期転換後の労働条件についても明示する義務が新たに設けられました。
これには、賃金、労働時間、業務内容など、無期契約後に適用される具体的な労働条件が含まれます。
また、企業は無期転換後の労働条件を決定する際、同一労働同一賃金の原則を踏まえ、正社員との均衡を考慮した説明を行うよう努める必要があります。
労働条件は変更できる?
一度締結した労働条件を変更できるのだろうかと疑問に感じている方も多いでしょう。
ここからは、労働条件の変更に関する基本的な考え方と手続きについて解説します。
一方的な条件変更はできない
労働契約法第9条では、使用者が労働者と合意することなく、就業規則を変更して労働条件を不利益に変更することを原則として禁止しています。
したがって、労働者の同意なしに賃金の引き下げや労働時間の延長などを一方的に行うことはできません。
また、労働者の同意を得る場合でも、その同意が自由意思に基づくものでなければ無効とされる可能性があります。たとえば、解雇をほのめかして同意を迫るような行為は、適切ではありません。
参考)厚生労働省「労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール」
参考)e-Gov 法令検索「労働契約法」
不利益な条件変更を行う方法
労働者にとって不利益となる労働条件の変更を行う場合、以下の条件を満たす必要があります。
- その変更が、合理的な内容であること
- 労働者に変更後の就業規則を周知させること
なお、合理的であるかの判断は、以下の事情に照らし合わせる必要があります。
- 労働者の受ける不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合等との交渉の状況
労働条件の変更は、労使間の信頼関係に大きな影響を与える重要な事項です。変更を検討する際は、法令を遵守し、労働者への丁寧な説明と適切な手続きを行いましょう。
参考)厚生労働省「労働契約法のポイント 労働契約法のポイント」p.4
参考)厚生労働省「労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール」
労働条件を明示しなかった場合の罰則
労働基準法第15条では、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間そのほかの労働条件を明示しなければならないと定められています。
この義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
これは、労働条件を明示しなかった場合や、法令で定められた方法で明示しなかった場合に適用されます。
出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」
まとめ
労働条件の明示は、企業が法令を遵守し、労働者との信頼関係を築くために不可欠です。明示義務を怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性があり、企業の信用低下や採用活動への悪影響も懸念されます。
とくに2024年4月の法改正により、明示すべき事項が追加されたため、最新のルールを把握し、適切な対応を行うことが求められます。労働条件通知書や雇用契約書の内容を定期的に見直し、法改正に対応した適切な対応を行いましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録