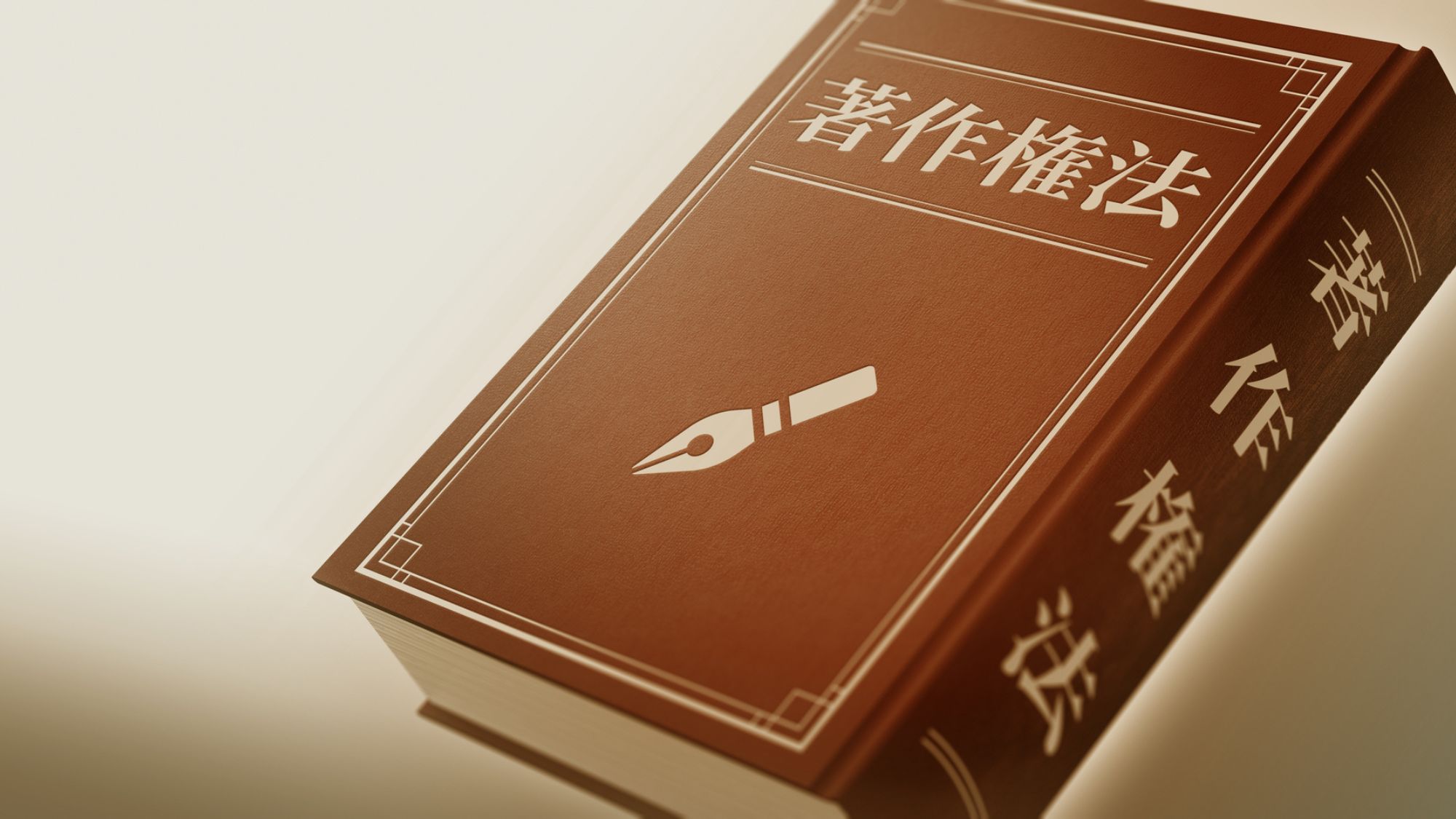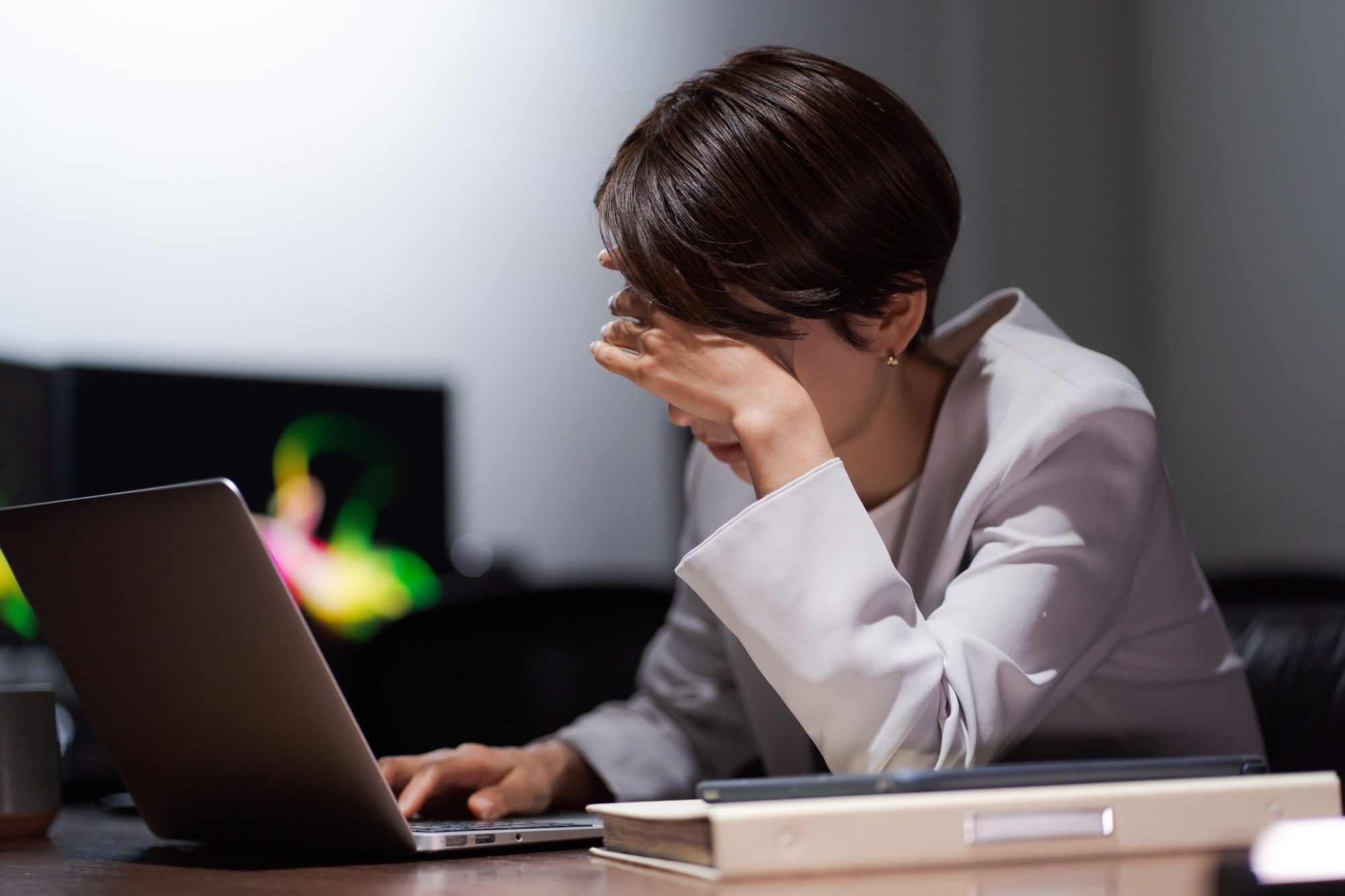会社法とは?役割・目的・主な記載事項をわかりやすく簡単に解説
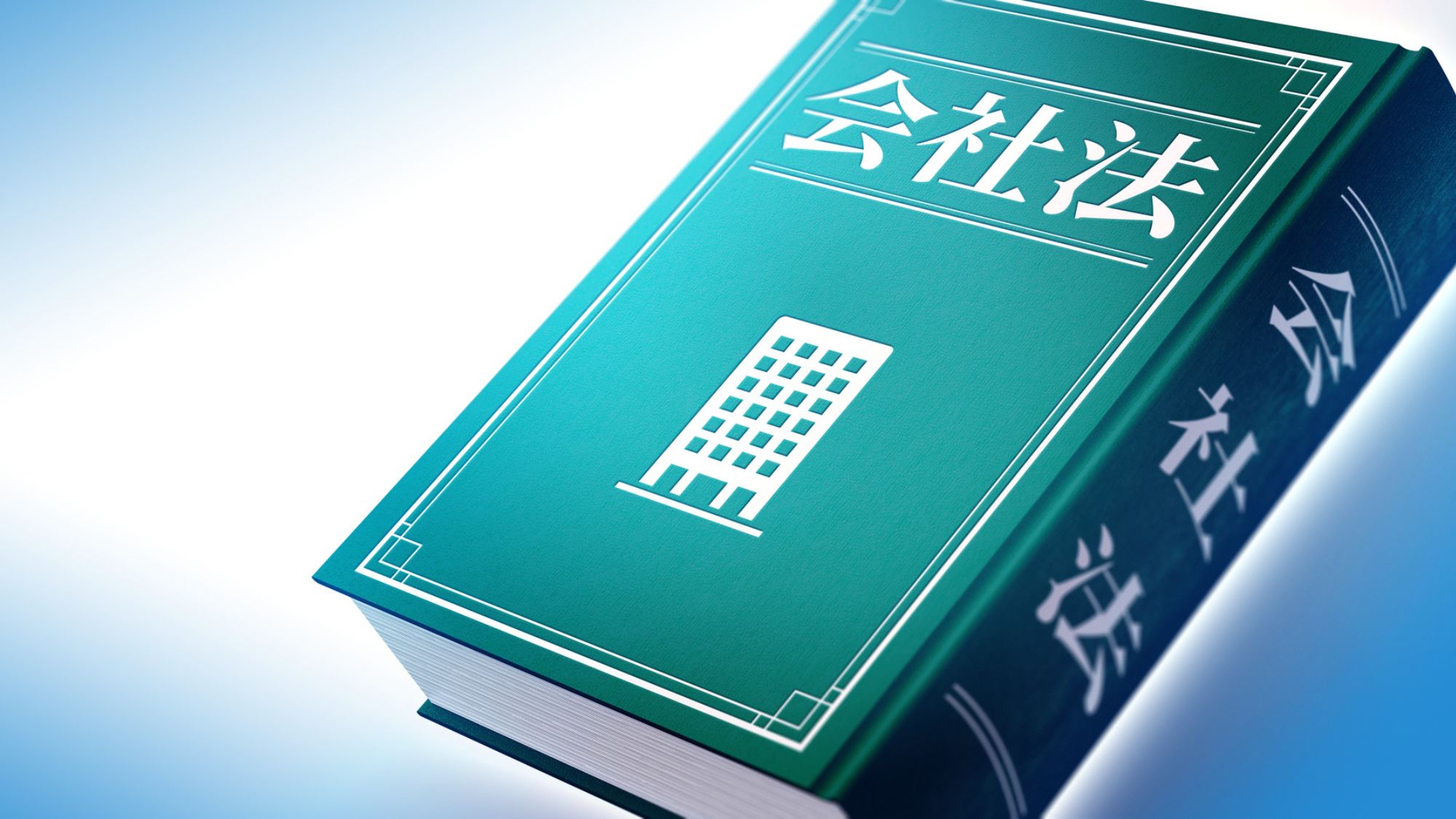
会社を設立・運営する上で避けて通れないのが「会社法」です。
しかし、「会社法とは何か」「どのような内容が定められているのか」について、正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。
本記事では、会社法の基本的な概念から実務上の注意点まで、わかりやすく解説します。
会社法についてよくわからないという経営者や法務担当者の方は、会社法を適切に理解し、法的リスクを回避しながら健全な企業経営を実現しましょう。
目次
会社法とは?簡単かつわかりやすく解説
会社法とは、株式会社をはじめとする会社の設立から解散まで、会社経営に関わる様々な事項を包括的に定めた法律のことです。
2005年に制定され、2006年5月から施行されました。
まずは、会社法とはどのような法律なのかについて、詳しく解説していきます。
なお、会社法の内容を実施するための細かなルールを定めた「会社法施行規則」というものもありますので、こちらも併せて参考にしてください。
▼内部リンク
会社法施行規則とは?実務とリスク回避のために知っておくべき基本ガイド
会社法の目的
会社法の目的は、会社の適正な運営と健全な発展を通じて、経済社会全体の発展に寄与することにあります。
具体的には、株主の利益保護と会社債権者の権利保護を両立させながら、企業の競争力向上を図ることを目指しています。
また、コーポレートガバナンス(企業統治)の強化により、経営の透明性と説明責任を確保し、企業価値の持続的な向上を促進することも重要な目的の一つです。
これらの目的達成のため、会社法は株主総会の運営方法から取締役の職務執行など、法人経営の細部に至るまで詳細な規定を設けています。
会社法の役割
会社法が果たす代表的な役割として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 企業活動の予測可能性確保
- ステークホルダー保護と紛争予防
- 柔軟な機関設計の実現
- 企業規模に応じた制度提供
- 企業ライフサイクル全体のサポート
会社法が上記のような役割を果たすことで、会社の設立手続きから組織運営、資金調達、企業再編に至るまで統一的なルールが定められ、企業活動の法的安定性が確保されています。
また、企業の実情に応じた「最適な組織構造を選択できる機関設計の柔軟性」が実現されている点も注目です。
これにより、中小企業から大企業まで、多様な企業形態に対応した法的枠組みとなっていて、起業の促進から既存企業の成長支援まで、企業のライフサイクル全体を法的にサポートする役割を果たしています。
会社法が成立した経緯
会社法が成立した背景には、「旧商法の複雑性」と「時代への対応不足」という課題がありました。
まず1990年代後半~2000年代前半では、会社に関する法律は商法の一部として規定されていましたが、条文が複雑で理解しにくく、急速に変化する経済環境に対応しきれない状況が続いていました。
この時期に企業統治改革の必要性が高まり、機関設計の柔軟化や資本制度の簡素化が強く求められるようになったのです。
そして2002年に、旧商法の複雑性と時代への対応不足という課題を受け、法制審議会において本格的な検討が開始され、2002年~2005年に制定作業が行われました。
その結果、2005年7月に会社法が成立し、2006年5月1日から施行開始となったのです。
会社法が施行されたことで、法人における機関設計の自由度が大幅に向上し、企業の実情に応じた柔軟な組織運営が可能となりました。
会社法で規定されている主な会社
会社法では、企業の目的や規模、出資者の関与度合いに応じて、複数の会社形態が規定されています。
この項目では、主要な会社類型である「株式会社」と「持分会社」について解説していきます。
株式会社
株式会社は、会社法で規定される最も代表的な会社形態で、資本と経営の分離を基本とする会社類型となります。
株主が出資した資本を基に事業を営み、株主は出資額を限度とする有限責任を負うという仕組みです。
株式会社の最大の特徴は、株式を発行することで多くの投資家から資金を調達できる点にあり、これにより大規模な事業展開が可能となります。
また、株式の譲渡により所有権の移転が比較的容易に行える点も重要な特徴です。
機関設計については、株主総会と取締役の設置が必須とされ、企業の規模や公開性などに応じて取締役会・監査役・会計監査人といった機関を設置する義務も生じます。
参考)会社法
持分会社
持分会社は、「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3つの会社類型の総称です。
株式会社と比べ、より「人的結合の性格が強い会社形態」となります。
持分会社の特徴は、出資者(社員)が原則として会社の経営に直接参加する点にあり、「所有と経営の分離」が前提の株式会社とは対照的な構造を持っています。
なお、持分会社の社員が負う責任については、以下のような違いがあります。
- 合名会社:全社員が無限責任を負う
- 合資会社:無限責任社員と有限責任社員が混在する
- 合同会社:全社員が有限責任を負う
近年では、合同会社の設立が増加傾向にあります。
これは、「設立コストの低さ」と「運営の柔軟性」が評価されているためです。
機関設計についても株式会社ほど複雑ではなく、社員総会と業務執行社員という比較的シンプルな構造で運営できるため、小規模事業や専門的サービス業での活用が進んでいます。
参考)会社法
会社法における株式会社の機関
この項目では、会社法で規定されている代表的な株式会社の機関について解説していきます。
会社規模を問わず設置が義務となっている「株主総会」「取締役」のほかに、規模や形態によって設置しなければならない機関もあります。
「知らないうちに会社法に違反していた」などということがないようにしてください。
株主総会
株主総会は、株式会社における最高意思決定機関として位置づけられ、全ての株式会社に設置が義務付けられている機関です。
株主総会では、取締役や監査役の選任・解任、定款変更、合併・分割などの重要事項について決議を行います。
なお、株主総会には「定時株主総会」と「臨時株主総会」があります。
それぞれの概要は以下の通りです。
| 定時株主総会 | 臨時株主総会 | |
| 開催時期 | 毎事業年度終了後一定時期(通常3か月以内) | 必要に応じて随時開催 |
| 開催頻度 | 年1回(必須) | 不定期(必要時のみ) |
| 法的義務 | 会社法により開催義務あり | 開催義務なし(必要時のみ) |
| 開催の主な目的 | ■取締役・監査役の選任 ■役員報酬の決定 ■定款変更(定例的なもの) ■計算書類の承認 ■剰余金の配当 | ■合併・分割・事業譲渡 ■増資・減資 ■緊急の定款変更 ■重要な経営方針の変更 ■役員の解任 |
また、2019年の法改正により、株主総会資料の電子提供制度が導入され、Webサイトでの資料提供が可能となり、株主の利便性向上が図られています。
参考)会社法
取締役・取締役会
取締役は、会社の業務執行に関する意思決定と実際の業務執行を担う機関で、全ての株式会社に1人以上の設置が義務付けられています。
取締役会は、3人以上の取締役で構成される合議体の機関で、取締役会設置会社では会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務執行の監督を行います。
上場企業などの公開会社では取締役会の設置が必須ですが、非公開会社は任意設置です。
取締役会を設置した場合、個々の取締役は業務執行を担当し、取締役会は全体的な経営方針の決定と監督機能を発揮します。
また、取締役会設置会社では代表取締役の選定が必要となり、代表取締役が会社を代表して対外的な法律行為を行うことになります。
取締役の任期は原則2年ですが、非公開会社では定款により最長10年まで延長可能です。
参考)会社法
代表取締役
代表取締役は、会社を代表して対外的な法律行為を行う権限を有する機関で、取締役会設置会社では必ず選定しなければなりません。
代表取締役は取締役の中から選ばれ、会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為を行う権限を持ちます。
取締役会非設置会社では、各取締役が会社を代表する権限を有しますが、複数の取締役がいる場合には、定款や株主総会決議により代表取締役を定めることも可能です。
代表取締役の権限は非常に広範囲にわたり、会社の日常的な業務執行から重要な契約締結まで、会社を代表して行うことができます。
ただし、その権限には一定の制限があり、何でもできるというわけではありません。
株主総会決議事項や取締役会決議事項については、それぞれの機関の決議を経る必要がありますし、会社に対して善管注意義務と忠実義務も負っています。
違反すれば、損害賠償の対象となる可能性があります。
参考)会社法
監査役・監査役会
監査役は、取締役の職務執行を監査し、会社の適正な運営を確保するための機関です。
監査役は株主総会で選任され、取締役から独立した立場で監査業務を行います。
大会社や取締役会設置会社では、監査役の設置が義務付けられているため、原則として設置しなければなりません。
なお、3人以上の監査役で構成される監査役会の設置が義務になるケースもあります。
監査役会設置会社では、監査役のうち半数以上は社外監査役でなければならず、監査の独立性と客観性を確保する仕組みが設けられています。
監査役の主な権限は、以下の通りです。
- 取締役会への出席・意見陳述権
- 業務・財産の調査権
- 違法行為の差止請求権
このような権利を行使し、会社の健全性維持に重要な役割を果たしているのです。
監査役の任期は4年。(非公開会社では定款により最長10年まで延長可能)
取締役よりも長期間設定されているのは、監査の継続性と独立性を確保するためです。
近年では、監査役の機能強化が進められており、より実効性の高い監査体制の構築が求められています。
参考)会社法
会計監査人
会計監査人は、会社の計算書類等の会計監査を専門的に行う機関で、公認会計士または監査法人がその職務を担います。
大会社では会計監査人の設置が義務付けられており、それ以外の会社でも任意に設置することが可能です。
会計監査人の主な職務は、以下のような書類の監査です。
- 計算書類
- 連結計算書類
- 臨時計算書類
これらの書類が、一般的に「公正妥当」と認められる企業会計の基準に従って作成されているかを監査します。
会計監査人は株主総会で選任され、その選任・解任・不再任については監査役(監査役会設置会社では監査役会)の同意が必要になります。
これは、会計監査人の独立性を確保するための重要な仕組みです。
また、会計監査人には取締役に対する監査報告書の提出義務があり、監査の過程で法令や定款に違反する重大な事実を発見した場合は、監査役への報告義務も課されています。
このように、会計監査人は企業の財務報告の信頼性確保において重要な役割を担っています。
参考)会社法
各種委員会(監査等委員会・指名委員会等)
監査等委員会や指名委員会といった各種委員会制度は、コーポレートガバナンスの強化を目的として設けられた仕組みです。
監査等委員会は、取締役の職務執行を監査するのが主な役割です。
監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役の半数以上は社外取締役でなければならず、従来の監査役制度と比べて取締役会の監督機能の強化が図られています。
指名委員会は、経営陣の選任・解任を決定するのが主な役割です。
指名委員会等設置会社では、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会を設置し、各委員会の過半数は社外取締役で構成することが義務付けられています。
両制度とも、経営の透明性向上と株主利益の保護を図る目的で設計されており、大企業や上場企業での採用が進んでいます。
参考)会社法
会社法で中小企業が注意すべきポイント
複雑な規定の多い会社法ですので、「中小企業としてはどういった点に気を付ければよいのかわからない」と困惑している方も多いでしょう。
この項目では、特に注意すべき点を3つ紹介します。
会社法における中小企業の定義を把握する
会社法における中小企業の取り扱いを理解するためには、まず「大会社」の定義を把握すべきです。
なぜならば、会社法には中小企業の定義がないからです。
会社法では、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社を「大会社」と定義しているため、これに該当しない会社が実質的に中小企業として扱われると考えてよいでしょう。
この区分は単なる分類ではなく、機関設計や会計監査人の設置義務など、会社運営に関わる重要な法的義務に直結しています。
たとえば、大会社に該当する場合は会計監査人の設置が義務付けられ、監査費用として年間数百万円から数千万円の負担が発生する可能性があります。
また、急成長により資本金や負債総額が基準を超えた場合、十分な準備期間のないまま大企業としての義務が発生する可能性があることにも注意が必要です。
会社として成長を続けている際は、定期的な財務状況の確認と将来計画の検討を欠かさないようにし、会社法上の大企業に該当しても問題ないように準備しておきましょう。
参考)会社法
「最新の会社法の内容」や「改正に向けた動き」を把握する
会社法は社会情勢の変化(デジタル化やガバナンスの透明化)に合わせ、継続的にアップデートされています。中小企業においても、最新の制度を把握しておくことは、法的リスクの回避だけでなく、経営の効率化を図る大きなチャンスとなります。
特に実務への影響が大きい、近年の主要な改正・導入ポイントは以下の3点です。
1. 実質株主確認制度の導入と透明性の向上
近年の法改正において、大きな注目を集めているのが「実質株主確認制度」です。
従来、企業が株主名簿で把握できるのは、信託銀行などの「名義上の株主」に留まることが多く、その背後にいる「真の出資者(実質株主)」を特定することは困難でした。
この制度の導入により、会社は名義株主に対して実質株主(議決権の指図権を持つ者など)の情報提供を請求できる権利を持つこととなりました。
- 経営の安定化: 不透明な買収工作や権利関係の混乱を未然に防ぎ、ガバナンスを強化できます。
- 株主対話の深化: 「真のオーナー」を把握することで、事業承継や安定株主対策をより的確に進めることが可能になります。
2. バーチャル株主総会の全面解禁
法整備により、非上場会社を含めた全ての会社において、定款を変更することで会場を設けない「完全バーチャル株主総会」の開催が可能になっています。
- コストと手間の削減: 会場の手配や当日の運営スタッフの負担を大幅に軽減できます。
- 参加のしやすさ: 遠方の株主もオンラインで参加できるため、株主総会の活性化につながります。
3. 従業員等へのインセンティブ拡充(株式報酬制度)
役員だけでなく、一般の従業員に対しても株式を無償で交付しやすくなるよう制度の整備が進んでいます。
- 優秀な人材の確保: 資金力に限りがある中小企業でも、自社の成長を分配する「株式報酬」を提示することで、リテンション(人材引き留め)の強化が図れます。
- 手続きの簡素化: 従来よりも機動的に株式を発行できる枠組みが整い、中小企業の活用ハードルが下がっています。
参考)法務省「法制審議会第201回会議(令和7年2月10日開催)」
状況に応じて専門家へ依頼する
中小企業が会社法を適切に遵守するためには、自社の状況を客観的に評価し、必要に応じて専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
「なんとかなるだろう」「おそらく問題ないだろう」という曖昧な判断のままでいると、知らないうちに会社法に違反しているというリスクが発生してしまいます。
特に、機関設計の変更、定款変更、株主総会運営、取締役の職務執行、会計処理などの分野では、専門的な知識と経験が必要となることが多いです。
コストはかかるものの、弁護士や公認会計士、税理士、コンサルティングサービスなど、具体的な課題に応じて適切な専門家を選んで相談することも重要です。
組織変更の際は会社法に則った形で手続きを進めよう
組織変更を行う際には、会社法に定められた厳格な手続きに従って進めることが不可欠です。
たとえば、株式会社から持分会社への変更、または持分会社から株式会社への変更のいずれの場合も、株主総会や社員総会での特別決議、債権者保護手続き、登記申請など、複数の段階を経る必要があります。
これらの手続きには法定の期間や順序が定められており、一つでも欠けると組織変更が無効となるリスクがあるので注意してください。
また、組織変更により会社の権利義務関係や税務上の取り扱いも大きく変わるため、事前の十分な検討と準備が必要です。
特に注意すべき点として、債権者への個別催告や公告の実施、反対株主の株式買取請求への対応、登記申請のタイミングなどがあります。
これらの複雑な手続きを確実に実行するために、自社のリソースでは対応できないと判断した場合は、専門家のアドバイスを受けながら綿密な計画を立てて進めるようにしましょう。
まとめ
会社法は、企業活動の法的基盤として、株式会社や持分会社の設立から運営まで包括的なルールを定めています。
したがって、企業の規模に関係なく、内容を詳細に把握して遵守する必要があります。
まだ理解が浅いという経営者や法務担当者の方は、まず自社の現状を分析し、機関設計を見直してみることから始めてみましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録