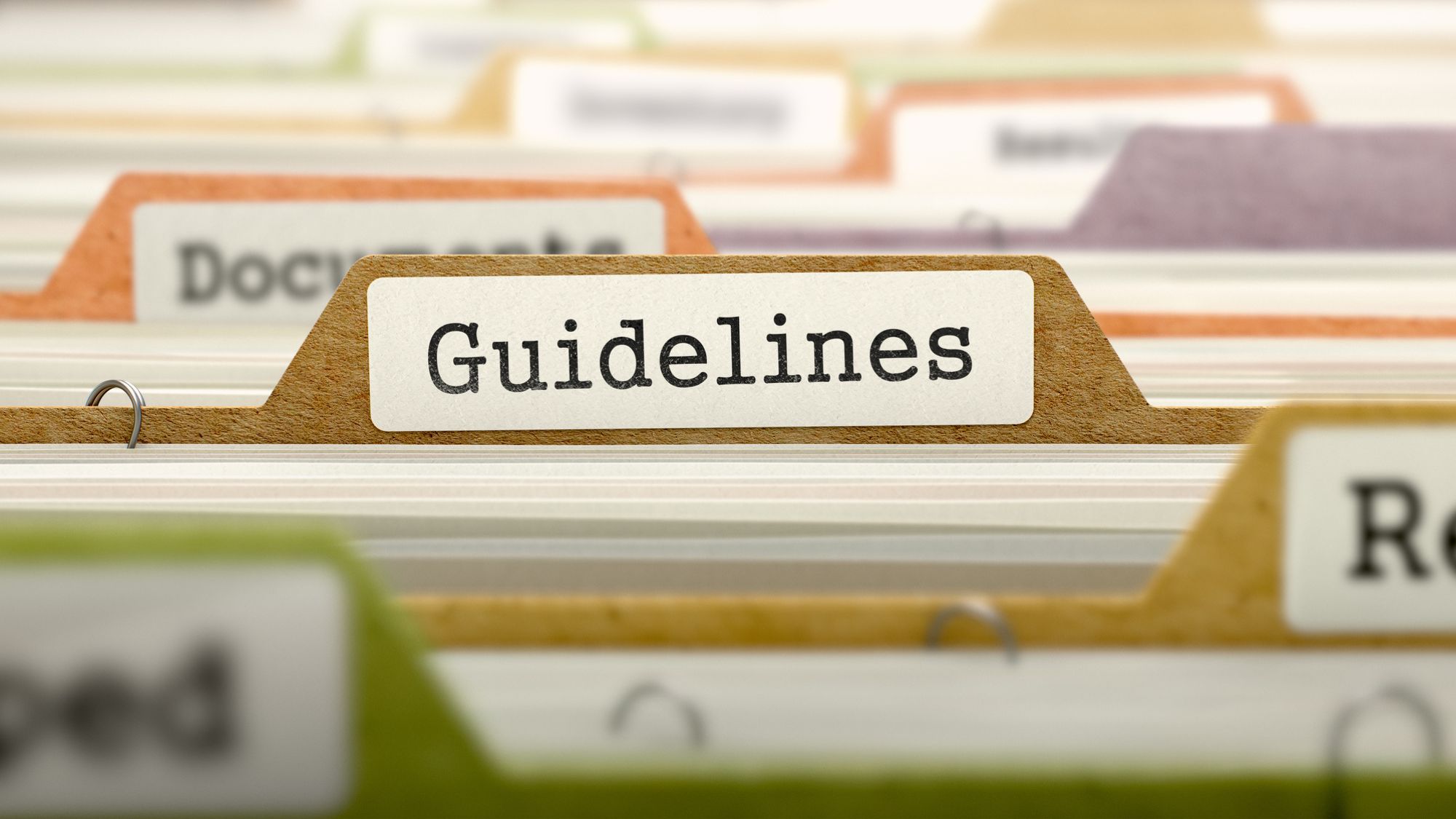下請法改正の施行はいつから?企業ができる対策や対象取引追加など変更点まとめ

2026年から施行される下請法の改正は、多くの中小企業に影響を与える可能性があります。とくに、代金の決定方法や規制対象の追加など、実務に直結する変更点が含まれており、従来の取引慣行を見直す必要が生じます。
多くの方が「うちには関係ない」と油断して、今回の改正を見過ごしているかもしれません。しかしこれまで下請法の適用外であった企業でも、今回の法改正によって新たに下請法の適用対象となる可能性があるのです。
この記事では、改正下請法の概要や主な変更点、中小企業が注意すべきポイント、そして今から準備できる対応策まで、わかりやすく解説します。
下請法改正の概要
下請法の改正は、下請取引に関わる不公正な取引慣行を是正し、取引の透明性と公正性を高めることを目的としています。
これまで軽微な改正はあったものの、大規模な改正は約50年ぶりとも言われています。法体系そのものが大きく見直され、中小企業を取り巻く商習慣に直接影響する内容が多数盛り込まれました。
中小企業にとっては、「自社には関係ない」と思っていた取引が法律の対象となるケースも増加します。そのため、改正内容を正しく理解し、早めに体制を整えておくことが重要です。
参考)公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」
公正取引委員会「下請法・下請振興法改正法の概要」
参考記事:下請法とは?中小企業が知るべき4つの義務と禁止行為をわかりやすく解説
下請法改正の施行期日
2025年5月16日に改正法案が可決され、同月23日に公布されました。
改正下請法は、2026年1月1日から施行されます(一部の規定は本法律の公布の日から施行)。
法改正による影響は、契約の締結・価格交渉・支払条件など日常的な業務に広く及びます。したがって、2026年1月1日までの期間で、契約書や社内ルールを見直し、最新の内容に更新しておく必要があるのです。
参考)中小企業庁「令和6年度における下請代金支払遅延等防止法に基づく取組」
下請法改正の背景
下請法改正の背景には、近年の取引形態や経済環境の変化により、従来の法律では対処しきれない実態が生まれてきたことが挙げられます。
とくに問題視されていたのが、発注側による一方的な価格決定や、過度な手形支払い、物流分野における不適正な委託取引などです。これらは中小企業にとって大きな負担となり、取引の公正性を損なう原因となっていました。
加えて、取引当事者の多様化や業種の広がりにより、従来の「下請」という概念ではカバーしきれない取引が増加しています。そのため、法の適用範囲や用語の見直しを含め、実態に即した制度へのアップデートが求められたのです。
改正下請法の主な変更点
改正下請法の主な変更点は、以下の6つです。
- 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
- 手形払等の禁止
- 運送委託の対象取引への追加
- 従業員基準の追加
- 面的執行の強化
- 「下請」等の用語の見直し
それぞれ詳しく解説します。
参考)公正取引委員会「下請法・下請振興法改正法の概要」
協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
発注者が受注者と事前協議を行わず、一方的に代金額を決定する行為が禁止されました。
コストが上昇している中で、協議することなく価格を据え置いたり、コスト上昇に見合わない価格を一方的に決めたりするなど、上昇したコストの価格転嫁についての課題が見受けられたためです。
今後の価格決定は、適切な協議に基づいて行う必要があります。
手形払等の禁止
これまで、発注者が受注者に対して120日手形などの長期手形で支払うことが慣行として残っていました。これが、受注側の資金繰りを圧迫する一因となっていたことは事実です。こうした実態を受けて、2024年5月の下請法施行規則の改正では、原則として手形払いが禁止されました。
さらに、電子記録債権や、発注者側が第三者に債権譲渡するファクタリングなど、下請事業者が期日前に現金を得ることが難しい支払い手段も禁止対象とされています。これにより、「形式上は支払っているが、実質的に資金繰りを遅らせている」支払方法は認められなくなりました。
運送委託の対象取引への追加
これまで対象外だった「物品の運送の委託」が、新たに対象取引に加わりました。具体的には、荷主から運送事業者への委託取引においても、下請法の規制対象となります。
近年、物流現場では荷待ち時間の長期化や一方的な業務変更が問題視されてきました。こうした不公正な慣行を防ぐため、運送業も法の保護対象に含まれることになったのです。
従業員基準の追加
下請法の適用にあたり、資本金だけでなく従業員数による基準が新たに導入されます。これにより、資本金が適用外でも、一定規模の従業員を抱える企業は対象となります。
具体的には、従業員300人超の企業が、従業員300人以下(個人を含む)の企業に発注する取引が対象です。
面的執行の強化
改正後は「面的執行」の概念が取り入れられます。現在は事業所管省庁には、調査権限のみが与えられています。
しかし、公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁の連携した執行をより拡充していく必要があるため、 事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与されました。
「下請」等の用語の見直し
下請法における用語の定義が、大きく見直されました。
なぜなら、「下請」という用語は、発注者と受注者が対等な関係ではないという印象を与え
るとの指摘があることに加え、 時代の変化に伴い、発注者である大企業の側でも「下請」という用語は使われなくなっているためです。
名称は、以下のように変更されます。
| 変更前 | 変更後 |
| 下請中小企業 | 受託中小企業 |
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請代金支払遅延等防止法 | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 |
コスト増加や規制強化も?中小企業における注意点
今回の改正によって適用基準や対象業務が拡大されるため、「従来は関係なかった」と考えていた企業も、新たに対応を求められるケースが増加します。
取引契約書の見直しや社内ルールの整備といった対応には、コストや時間の負担が伴うことも事実です。
ここからは中小企業における注意点を見ていきましょう。
参考記事:下請法の対象かどうかを確認するには?中小企業が押さえるべきポイントを解説
下請法は中小企業でも適用される
下請法は大企業だけの話ではありません。これまで親事業者という表現が用いられていたため、大企業というイメージがあるかもしれませんが、要件を満たした委託事業者であれば、中小企業でも適用されます。
また、いわゆる「トンネル会社規制」により、親会社から委託を受けた子会社が業務を再委託した場合、その子会社が下請法の適用対象となることがあります。
参考)公正取引委員会「ポイント解説下請法」p7
従業員基準が追加される
改正によって新たに従業員規模が追加されたため、資本金の額に関係なく、従業員数300名以上の企業が、従業員数300名以下の企業に発注する場合、親事業者(委託事業者)となります。
そのため、大企業同様に下請法を遵守しなければなりません。
適用業務範囲の拡大される
下請法の対象となる業務範囲も大幅に拡大されました。これまで対象外とされていた取引形態や業種が、新たに規制の枠組みに組み込まれることになります。
とくに注目すべきは、物流・運送業務の追加です。
発荷主が運送事業者に委託する契約も、下請法の対象となりました。中小企業においても自社の従業員数と運送事業者の従業員数を踏まえて、契約を行う必要があります。
改正に向けて企業が取り組むべきこと
2026年1月1日の施行に向けて、法令違反による行政処分や信用毀損を回避するために、実務レベルでの見直しが急務となります。
具体的な内容は、以下のとおりです。
- 取引契約書のひな形見直し
- 支払い条件・検収条件の確認
- 社内教育・コンプライアンス体制の整備
- 外部専門家や相談窓口の活用
それぞれ解説します。
参考記事:下請法違反の事例から学ぶ!企業を守るために知っておくべき重要なポイント
取引契約書のひな形見直し
まず優先すべきは、現在使用している契約書の見直しです。取引条件や支払い期日、委託内容を見直さないと、改正下請法の趣旨に反する内容が含まれている可能性があります。
既存のテンプレートが古い場合は、改正の内容に合った最新版へ更新していく必要があります。
支払い条件・検収条件の確認
契約の支払い条件や検収方法も、法令遵守の観点から改めて確認が必要です。とくに「価格の据え置き」や「手形払い」など、下請法が明確に定めるルールに抵触していないかどうかをチェックする必要があります。
また、検収が完了しないことを理由に支払いを遅延させる行為は、不当な扱いとみなされる場合があります。検収プロセスに合理性があるか、遅延を招く構造になっていないかもあわせて見直しておきましょう。
社内教育・コンプライアンス体制の整備
改正への対応は経営層や法務部門だけで完結するものではありません。実際に取引先と接する現場担当者が、法改正の内容や注意点を正しく理解していなければ、現場レベルでの違反につながる恐れがあります。
そのため、社内研修やマニュアルの見直しなどを通じて、コンプライアンス体制を全社的に強化することが重要です。部署を横断した対応ルールの整備や仕組みづくりを検討しましょう。
外部専門家や相談窓口の活用
自社だけで法改正対応を完結させるのが難しい場合には、早めに外部の専門家や公的相談窓口を活用しましょう。
また、顧問弁護士や中小企業診断士など、法務・経営に精通した専門家と連携すれば、リスクを最小限に抑えた対応が可能になります。自社だけで判断せず、第三者の視点を取り入れる姿勢が、今後ますます求められます。
まとめ
下請法改正は、大規模な見直しであり、中小企業を含む多くの事業者に影響を与えます。これまで対象外だった業務や企業が新たに規制の枠組みに入る可能性も高く、発注者・受注者の立場を問わず注意が必要です。
日々の業務に直結する項目が多いため、今後は、契約書の見直しや社内教育の強化、専門家への相談を通じて、法令遵守の体制を早急に整備することが重要です。
企業の信頼を守るためにも、改正内容を正しく理解し、着実に準備を進めていきましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録