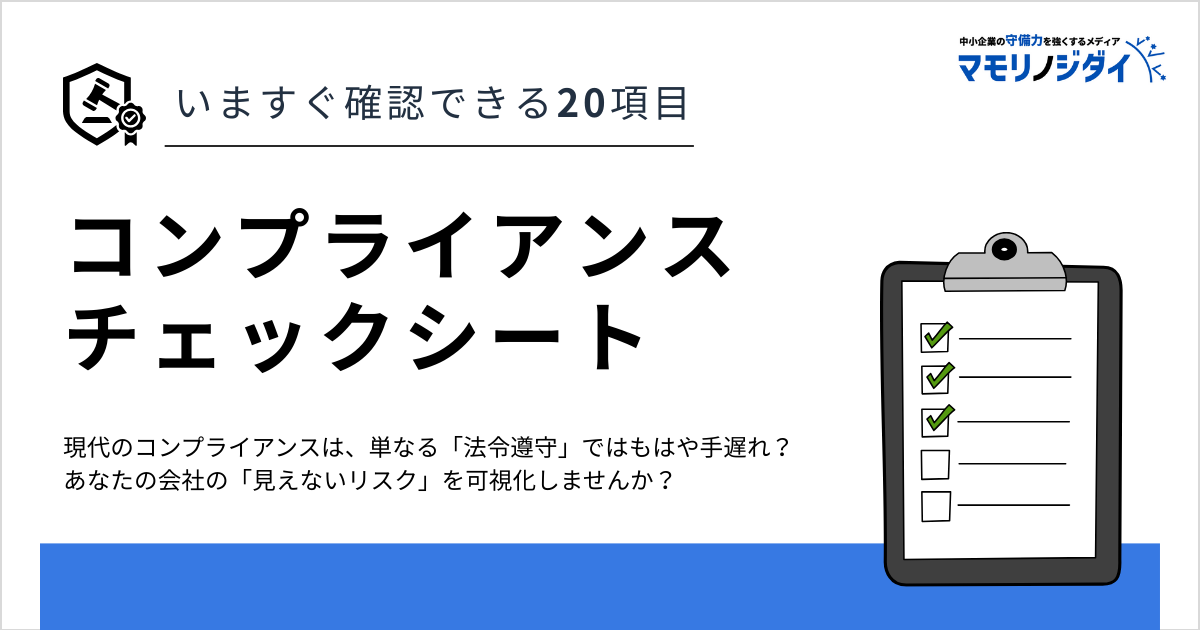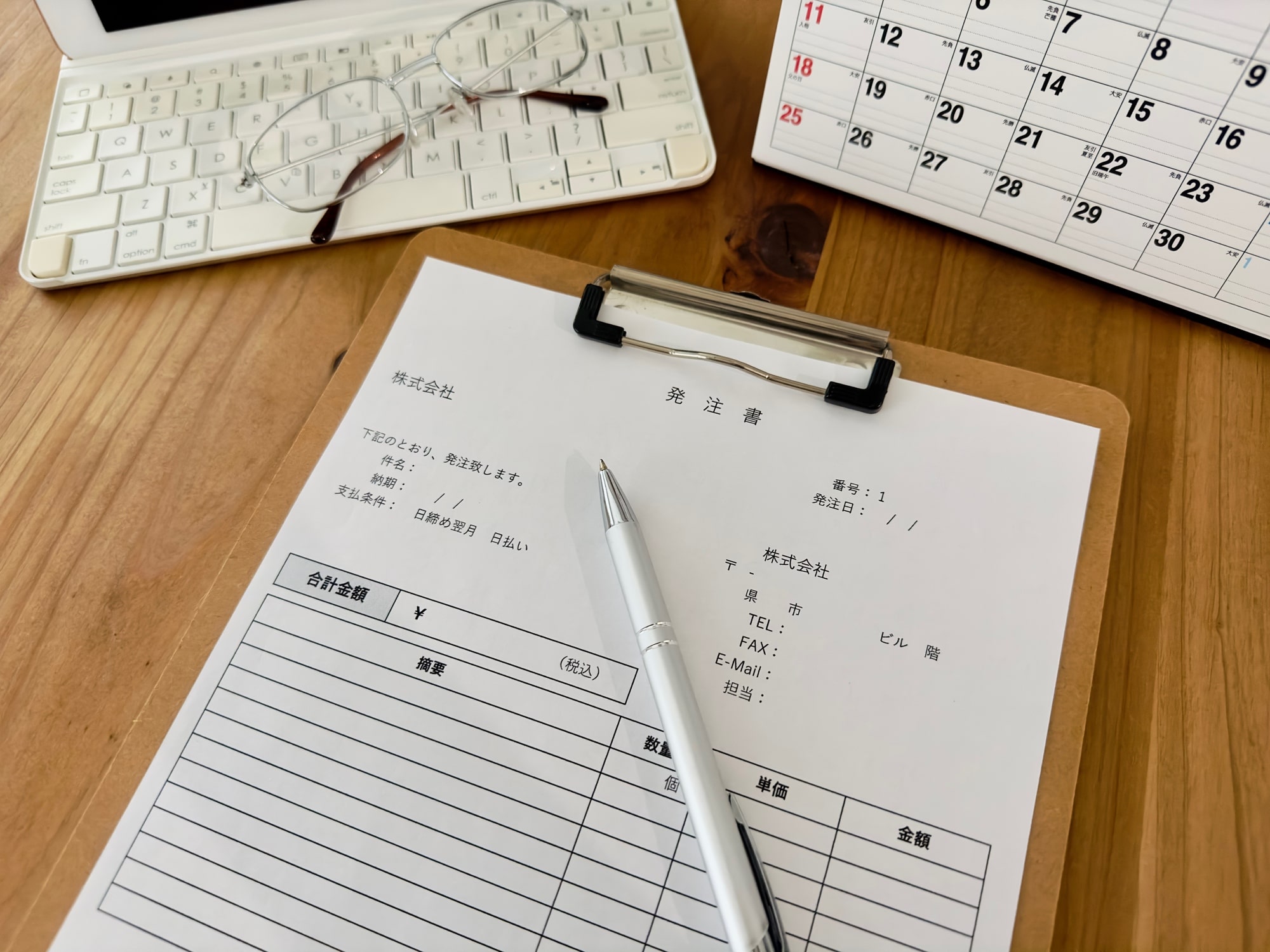デューデリジェンスを中小企業で活かす!意味・種類・進め方を徹底ガイド

「デューデリジェンス(DD)」と聞くと、大企業のM&Aの話だと思っていませんか。実は、事業承継や新規事業への投資、業務提携など、中小企業にとっても身近なシーンで必要になる重要な調査プロセスです。
デューデリジェンスを適切に行えば、「こんなはずじゃなかった…」と後悔するリスクを大幅に減らせます。逆に、調査を怠ると、隠れた赤字や法的リスク、経営資源のミスマッチといった重大な問題を見逃しかねません。
この記事では、中小企業の経営者・管理部門の方に向けて、デューデリジェンスの意味や種類、進め方から注意点までをわかりやすく整理しました。
デューデリジェンスはコンプライアンス違反を守るためにも寄与します。以下の資料では「中小企業が実施すべきコンプライアンス項目」をチェックシート形式で紹介していますので、ぜひダウンロードしてください。
目次
デューデリジェンスとは何か?基本をわかりやすく理解しよう
デューデリジェンス(Due Diligence)とは、直訳すると「相当な注意義務」です。ビジネスの現場では、取引や意思決定に先立って、対象企業や資産の実態を調査・把握するプロセスを指します。
M&Aをはじめとする事業提携や投資判断において、隠れたリスクや課題が発生しがちです。事前に洗い出すことで、後々のトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
一見、大企業の話に思えるかもしれませんが、実は中小企業にとっても、事業を守るうえで欠かせないチェックプロセスです。
M&Aだけじゃない!適用されるビジネスシーンとは
中小企業がデューデリジェンスを実施するケースは近年増えています。たとえば、親族外への事業承継や、他社との共同事業、新規設備の取得、出資を受ける際などです。
| ビジネスシーン | デューデリジェンスの目的・内容 |
| 事業承継・M&A | 財務・法務・人事などを調査し、隠れた債務やトラブルの有無を確認する |
| 業務提携・アライアンス | 相手企業の信頼性、契約内容、継続性のリスクを把握する |
| 新規事業への出資・投資 | 市場性、競合優位性、収益性を検証し、投資判断の裏付けとする |
| フランチャイズ・ライセンス契約 | 商標・契約条件・事業運営の体制などをチェックし、ブランドリスクを回避する |
| 不動産購入・賃貸 | 物件の法的権利関係、用途制限、老朽化などの確認によって将来の損失を回避する |
| 資金調達(出資・融資) | 自社が第三者から出資や融資を受ける際に、調査を受ける前提で体制を整えておく |
企業規模にかかわらず“事業を次につなげる準備”として、実施の検討が求められる時代になっています。
中小企業でも必要になるのはどんな時?
デューデリジェンスについて「うちは小規模だから関係ない」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし中小企業でも重要な意思決定や契約の場面では必須となるケースが増えています。
例えば、親族以外への事業承継、ベンチャーキャピタルからの出資、業務提携や共同開発、店舗の買収など、経営の“転機”ではリスクの洗い出しが不可欠です。
| シーン | 背景・目的 |
| 親族外への事業承継 | 買い手企業がリスクを把握するため、もしくは自社が事前に情報整理して信頼性を高める |
| 第三者への会社売却(M&A) | 財務や法務、労務などの実態を調査し、トラブル回避と企業価値の正当評価につなげる |
| 出資・投資を受ける場合 | 出資者から調査を受ける前提で、企業情報や体制を整備しておく必要がある |
| 業務提携・共同事業の開始時 | 相手企業の財務状況や信用調査、契約内容を確認し、リスクの少ない連携を図る |
| 事業用資産・店舗の買収 | 不動産の権利関係、資産の評価、将来の運営リスクを調査する必要がある |
このように、中小企業こそ「転ばぬ先の杖」として、リスクを可視化する体制が問われる局面が増えています。
目的を整理!なぜデューデリジェンスが重要なのか
デューデリジェンスの目的は一言でいえば「意思決定の“後悔”を未然に防ぐこと」です。
たとえ契約書が整っていても、相手の財務や契約状況に問題があれば、取引後に大きな損害や法的トラブルを招く可能性があります。事前にリスクを洗い出すことで、「この条件なら提携すべき」「この会社との統合は避けるべき」といった的確な判断を下すことが可能です。
また、売却側としても、自社の価値を正しく伝えたり、信頼性を示すための準備として有効といえます。つまり、買い手・売り手の双方にとって、“安心して次の一手を打つ”ための土台がデューデリジェンスなのです。
調査内容ごとに分類!デューデリジェンスの種類一覧
デューデリジェンスには、目的に応じて複数の調査分野が存在します。中小企業でも、M&Aや提携、出資の場面でこれらを組み合わせて実施することが一般的です。
ここでは、代表的な7種類を紹介します。
財務デューデリジェンス|赤字や簿外債務を洗い出す
最も基本となるのが財務デューデリジェンスです。過去の財務諸表や資産負債の状況、キャッシュフローの実態などを精査し、企業の“お金まわり”を正確に把握します。
特に中小企業の場合、未計上の債務(簿外債務)や、赤字部門の存在が発見されることも多い項目です。デューデリジェンスがなければ買収後に深刻な資金問題となることもあります。
主な調査対象は以下です。
- 財務諸表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書)
- 借入状況、リース債務
- 未払い費用、簿外債務の有無
- 収益性・資産評価の妥当性
法務デューデリジェンス|契約リスクや知財をチェック
法務デューデリジェンスでは、契約書、登記、知的財産、訴訟履歴など、法的なリスクがないかを調査します。
中小企業では、取引先との契約に不備があったり、著作権・商標の管理が甘いケースも少なくありません。これらの問題は、提携後や買収後に想定外の法的トラブルに発展する可能性があるため、外部の専門家と連携しながら慎重に進めることが重要です。
主な調査対象は以下になります。
- 各種契約書(取引・労務・賃貸など)
- 登記情報(法人・不動産)
- 訴訟や法的トラブルの履歴
- 知的財産権(商標・著作権など)の保有・登録状況
法務デューデリジェンスによってコンプライアンス違反のリスクを低減することが可能です。コンプライアンス違反の事例は以下で解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
参考記事:コンプライアンス違反の事例6選!リスクを学んで企業の対策を
ビジネスデューデリジェンス|市場や競合優位性を確認
事業そのものの将来性や競争力を確認するのが、ビジネスデューデリジェンスです。
たとえば、売上は伸びていても、成長市場ではなく、今後の見通しが暗い分野であれば、長期的なリスクを抱えることになります。「この事業に投資する価値があるのか?」という判断の土台となる調査です。
主な調査対象は以下になります。
- 事業モデル・ビジネススキーム
- 市場規模や成長性
- 主要顧客・取引先・サプライヤー
- 競合環境・ポジショニング
取引構造や収益モデルに直結する「下請け構造の健全性」も調査対象の一つです。下請法についてより知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。
参考記事:下請法とは?中小企業が知るべき4つの義務と禁止行為をわかりやすく解説
人事・労務デューデリジェンス|社内制度や雇用契約の整備
従業員に関わる情報を調べるのが人事・労務デューデリジェンスです。
特に中小企業では、制度の整備不足やブラックボックス化した人件費がリスクとなるケースがあります。また、買収後の労働条件変更や人員整理が発生する可能性もあるため、“人”にまつわるリスクを事前に洗い出しておくことが重要です。
主な調査対象は以下になります。
- 雇用契約書、就業規則
- 人員構成、報酬体系、残業実態
- 社会保険や福利厚生の整備状況
- 労働組合との関係、労務トラブル履歴
従業員の労働環境・安全対策は大きなリスク要因です。もっと深く知りたい方は、以下の労働安全衛生法の解説記事も参考にしてみてください。
参考記事:中小企業が知っておくべき!労働安全衛生法改正の最新動向と対策【2025年・2026年を見据える】
IT・システムデューデリジェンス|情報管理や運用体制の確認
見落とされがちですが、IT・システムの調査も近年重視されています。
ITトラブルは企業活動を一瞬で止めてしまうリスクがあり、特にセキュリティが甘いと情報漏洩やサイバー攻撃の対象になりやすいです。システム統合やクラウド移行のしやすさを事前に把握する意味でも、欠かせない調査項目といえます。
以下が主な調査対象です。
- 基幹システムの構成と運用体制
- クラウドサービス・SaaSの契約状況
- 情報セキュリティ対策(アクセス権限・脆弱性対応)
- IT資産(PC、サーバー、ライセンス管理)
特に情報セキュリティの観点で、個人データ取り扱いが杜撰な企業は評価低下の要因となります。以下の記事では個人情報保護員会について解説していますので、参考にしてください。
参考記事:個人情報保護委員会ってどんな組織?トラブルの際にはすぐ報告を!
不動産デューデリジェンス|物件の権利・用途・評価を調査
不動産を保有・使用している場合、その権利関係や評価額、用途制限、建物の状態などを確認するのが不動産デューデリジェンスです。中小企業でも、店舗・工場・オフィスの賃貸契約や保有不動産の管理状況が収益性に直結することがあります。
また、土地に未登記の建物や契約書の未整備があるとトラブルのもとになりかねません。“目に見える資産”の実態を把握する重要な工程です。
以下が主な調査対象になります。
- 所有権・賃借権の登記内容
- 土地・建物の評価(鑑定・固定資産)
- 用途地域・建築制限
- 契約書(賃貸借契約・管理契約)
ESG・人権デューデリジェンス|非財務リスクへの備え
近年注目されているのが、ESG(環境・社会・ガバナンス)や人権に関するデューデリジェンスです。
特に海外との取引や上場企業との提携を視野に入れる場合、サプライチェーン全体での人権尊重や環境配慮が求められるケースもあります。将来の取引停止やブランド毀損といった“非財務リスク”への備えとして、中小企業にも広がりつつある領域です。
以下が主な調査対象になります。
- 環境対応(省エネ・廃棄物処理・排出ガス)
- 労働環境(長時間労働、ハラスメント対策)
- 人権ポリシーや教育体制
- サプライチェーン全体のコンプライアンス状況
どうやって進める?デューデリジェンスの一般的な進行フロー
デューデリジェンスは、ただ調査を依頼するだけでは本来の効果を発揮しません。
目的を明確にし、関係者との連携を取りながら段階的に進めていくことが、的確な判断と円滑な交渉のために重要です。
ここでは、実務でよく採用される標準的な3ステップをご紹介します。中小企業が外部の専門家と連携する際にも役立つ流れです。
実施前の準備|目的とスコープの明確化
最初に行うべきは、調査の「目的」と「スコープ(範囲)」を明確にすることです。
たとえば「事業承継のリスク確認」なのか、「提携先の財務体質の確認」なのかによって、調査すべき内容は大きく異なります。
スコープが曖昧なままでは、調査が過剰になってコストが膨らんだり、逆に必要なリスクを見落とすおそれもあるため注意が必要です。
社内の関係部署と調整しながら、目的に応じた必要最小限の範囲を設定しましょう。
調査段階|資料収集・ヒアリング・現地確認など
次のステップは、実際の調査作業です。対象となる企業や資産に関する資料を収集し、内容を精査していきます。
財務諸表や契約書、人事データなどの書類を読み込むだけでは足りません。担当者へのヒアリングや、工場・店舗などの現地確認が行われるケースもあります。
中小企業の場合、社内に情報が分散していたり、書類の整備が不十分なこともありますが、できるだけ正確でタイムリーな情報を開示することが、信頼性の向上のために重要です。
結果のまとめ|レポート作成と契約反映の手続き
調査が完了すると、調査結果をまとめた「デューデリジェンスレポート(DDレポート)」が作成されます。
このレポートは、企業の財務状況や法的リスク、組織の健全性などを客観的に整理したものです。最終的な意思決定や契約内容の調整に活用されます。
中小企業にとっても、買い手や出資者に対して自社の価値や改善点を可視化できる貴重な資料です。必要に応じて契約条件を見直したり、指摘されたリスクへの対応を講じることで、取引後のトラブルを未然に防ぐことができます。
費用や期間はどれくらい?実務での相場感をチェック
デューデリジェンスを検討する際に気になるのが、コストと期間です。
実際の費用やスケジュールは、調査の範囲や企業の規模、依頼する専門家の種類によって大きく異なります。中小企業の場合でも、数十万円から数百万円規模のコストがかかるケースは少なくありません。
とはいえ、将来的なリスクを回避できると考えれば、“転ばぬ先の投資”としての位置づけが大切です。
以下は、一般的な相場の目安になります。
| 調査の種類 | 費用の目安(税込) | 期間の目安 |
| 財務・法務の基本調査 | 50万〜150万円程度 | 約2〜4週間 |
| 調査項目を拡張した本格調査 | 200万〜500万円以上 | 1〜2ヶ月(複数分野含む場合) |
| セルフDD(売却側の事前調査) | 30万〜100万円程度 | 約2〜3週間 |
費用を抑えるためには、事前に社内で必要資料を整理しておくことや、調査スコープを明確にすることがポイントです。また、専門家への相談も早めに始めることで、無駄のない進行と納得のいくコスト設定につながります。
デューデリジェンス実施で気をつけたい注意点
デューデリジェンスは、事前のリスクを把握できる有効な手段ですが、やり方を誤ると十分な成果が得られません。
ここでは、中小企業が実施する際に特に注意しておきたい3つの落とし穴と対策を紹介します。
情報開示の質に左右されることも
デューデリジェンスは、調査対象の情報が正確かつ網羅的に提供されてはじめて機能します。
そのため、社内に情報が散在していたり、経理・法務書類の整備が不十分な場合、調査の精度が下がり、意味のないレポートになることがリスクです。特に中小企業では「どこに何があるのか分からない」といった属人化も起こりがちといえます。
そのため、あらかじめ資料の棚卸しや電子化を進めておきましょう。
専門家に任せきりにすると判断できない
調査業務は専門家に依頼するケースが多いですが、すべてを“お任せ”にしてしまうことはリスクです。自社にとって何が問題なのかを正しく理解できないまま終わってしまうこともあります。
調査レポートを読んでも、その意味や重要性が分からなければ、契約交渉や改善判断につなげることができません。調査の過程で出てきた疑問点は逐一確認し、「何がリスクで、どう対応すべきか」を経営陣自身が理解しましょう。
目的に合わない調査はコスト増・逆効果に
調査範囲が広すぎたり、目的と無関係な領域にまで手を広げてしまうと、調査のボリュームが増えてコストがかさみます。また、本来得たかった情報が埋もれてしまうこともリスクです。
たとえば、資産買収なのに人事やESGまで深堀りする必要はない場合もあります。
だからこそ、最初の段階で「何のために行うのか」「どの分野に重点を置くのか」を明確にし、過不足のないスコープ設定をしましょう。
まとめ
デューデリジェンスは、大企業だけでなく中小企業にとっても、経営判断を“後悔のないもの”にするための重要なプロセスです。事業承継や業務提携、資産の取得など、企業にとって節目となる場面では、将来のリスクを見える化し、信頼できる取引につなげる手段として活用されています。
調査の切り口は多岐にわたりますが、共通して言えるのは、事前準備と目的の明確化が成功のカギであるということです。
中小企業が健全に成長し、外部との連携を円滑に進めていくためには、“企業を守る目線”を持った判断の積み重ねが欠かせません。
デューデリジェンスを正しく理解し、必要な場面で適切に活用できる体制を整えておきましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録