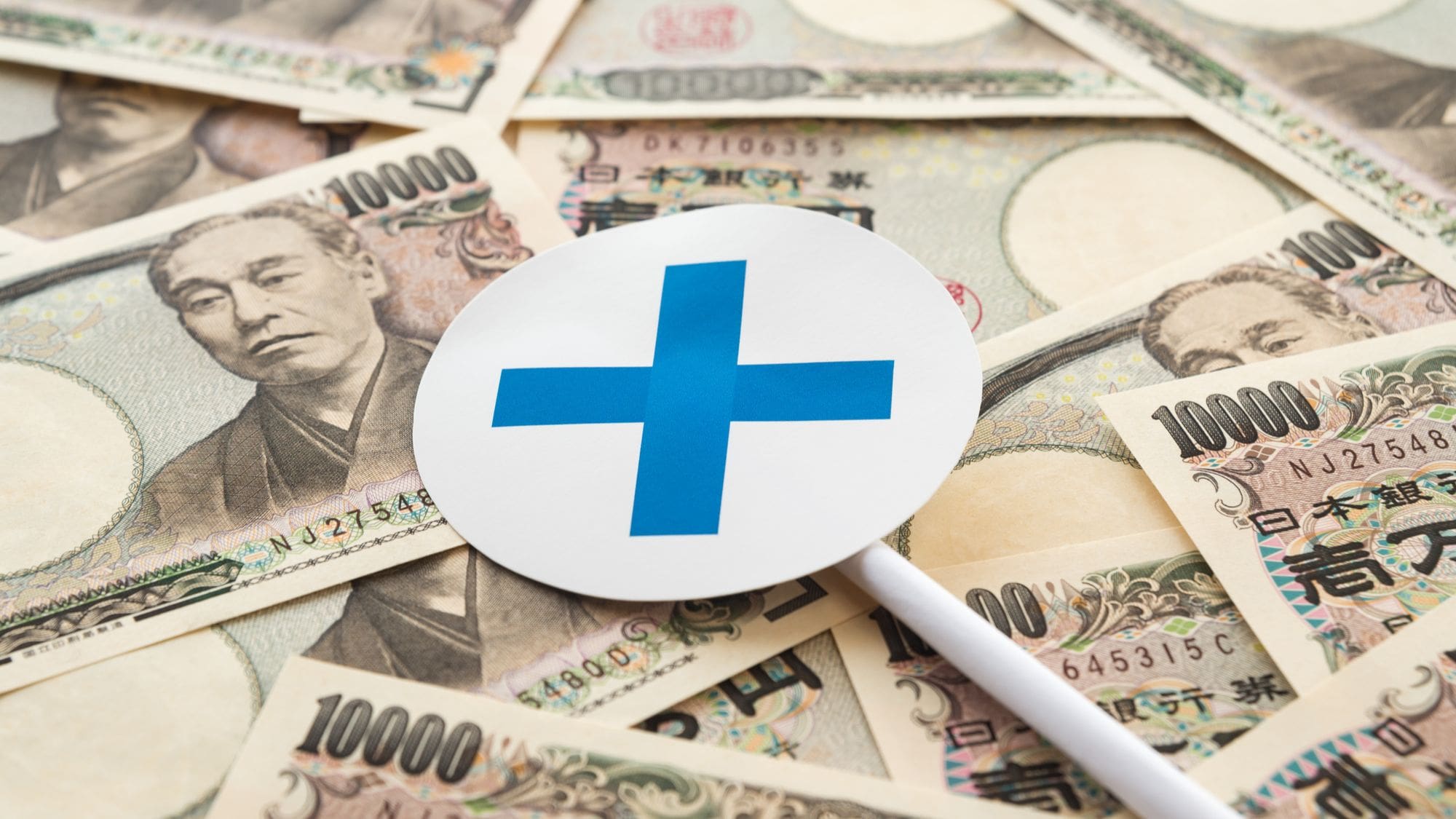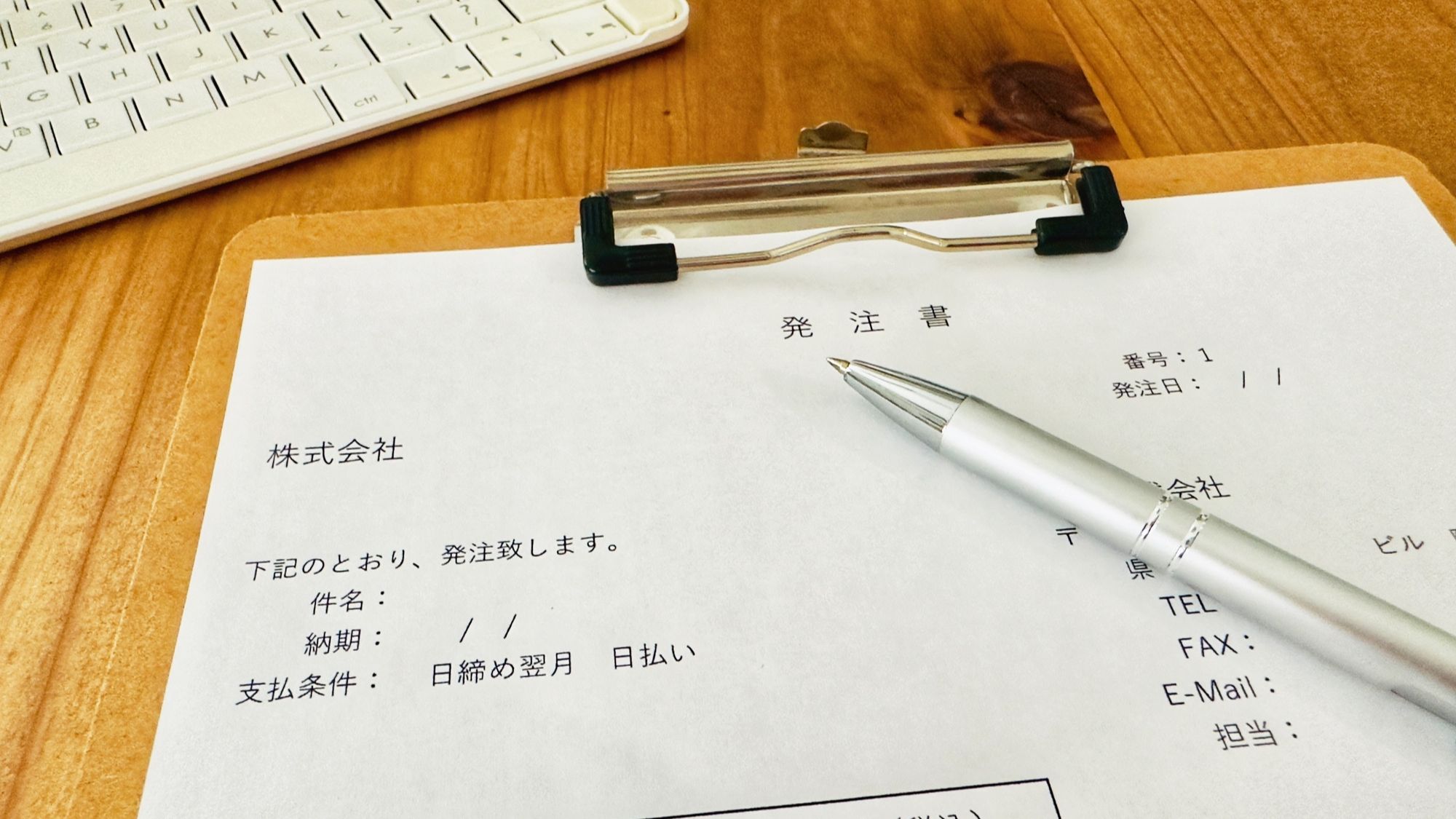中小企業がCSIRTを立ち上げるには?体制づくり・役割などを解説

サイバー攻撃の手口が日々巧妙化し、個人情報の漏えいや業務停止といった深刻な被害が中小企業にも広がっています。そんな中で注目されているのが「CSIRT(シーサート)」と呼ばれるセキュリティインシデント対応チームです。
「うちのような小規模企業で専任チームなんて無理では?」と感じる方も多いかもしれません。実はCSIRTは、兼任でもスタートでき、段階的に体制を強化していくことが可能です。
この記事では、CSIRTの基本的な意味から、SOCやPSIRTとの違い、中小企業でも導入できるステップ、外部支援の活用方法、そして形骸化させないための運用のコツまで、わかりやすく解説します。
また、以下の資料では情報漏洩の対策をマニュアル化して紹介していますので、こちらも参考にしてみてください。
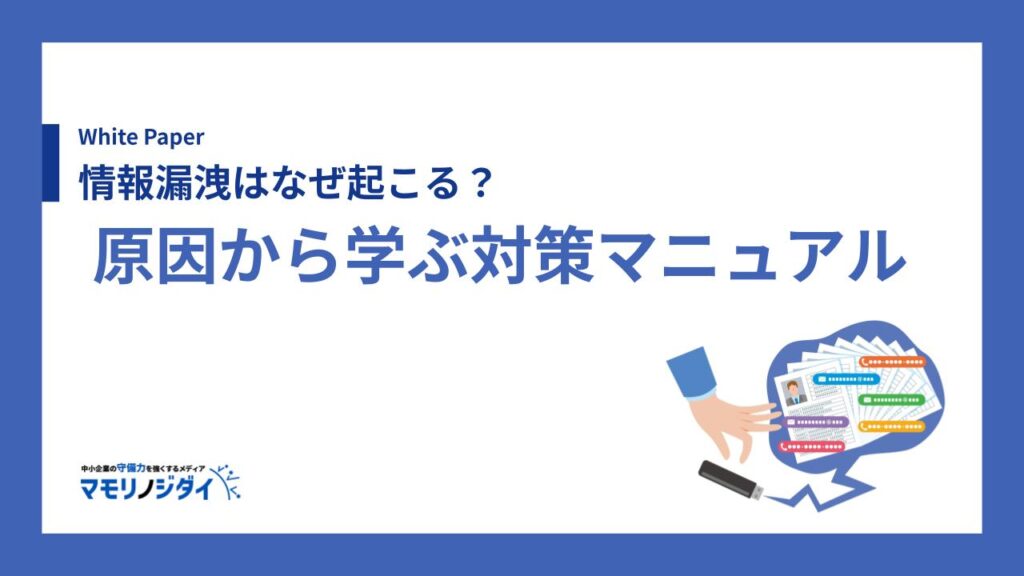
>>情報漏洩はなぜ起こる?原因から学ぶ対策マニュアルのダウンロードはこちら
目次
そもそもCSIRTとは?セキュリティ事故の「対応専門チーム」
社内ネットワークの不正アクセスや、取引先への誤送信、ランサムウェアによる業務停止など、いざというタイミングで対応するのが、CSIRT(シーサート)です。
中小企業にとっても、万が一の被害を最小限にとどめ、早期復旧を可能にする「企業防衛の要」として、CSIRTの存在が注目されています。
CSIRT(シーサート)の意味と読み方|何の略称?
CSIRTとは、「Computer Security Incident Response Team(コンピュータ・セキュリティ・インシデント・レスポンス・チーム)」の略称です。日本語では「セキュリティ事故対応チーム」と訳され、主に社内外のセキュリティインシデントに迅速かつ適切に対応する役割を担います。
「チーム」とは言っても、必ずしも専任の大規模組織である必要はありません。中小企業では、情報システム担当者や管理部門、経営層などが兼任で立ち上げるケースも多く、規模や業態に応じた柔軟な設計が可能です。
CSIRTが必要とされる背景とは?サイバー攻撃の高度化と被害の拡大
近年、標的型攻撃やランサムウェア、ゼロデイ攻撃など、サイバー攻撃の手口がますます巧妙化・高度化しています。特に中小企業は「セキュリティ対策が甘い」と見なされ、サプライチェーン攻撃の“足がかり”として狙われるケースが増加している状況です。
また、万一の事故が発生した際、「誰が何をするのか」が決まっていなければ、初動の遅れや対応ミスにつながり、損害が拡大するおそれがあります。こうしたリスクを軽減するためにも、あらかじめCSIRTを整備し、体制を定めておくことが重要なのです。
CSIRTとSOC・PSIRT・MDRの違いを一発で整理!
セキュリティ対応に関する用語は似たものが多く、混同されがちです。しかし、それぞれが担う役割は異なります。ここでは、CSIRTを中心に、SOC・PSIRT・SIEM・MDRとの違いと関係性を表を使って整理します。
| 用語 | 主な役割 | 対象範囲 | 中小企業での活用 |
| CSIRT | セキュリティインシデントへの対応 | 社内システム・ネットワーク全般 | 社内で兼任チームを編成する例が多い |
| SOC | セキュリティ監視・ログ分析 | 外部からの脅威・不審な通信 | 外部委託(MSS)での活用が主流 |
| PSIRT | 製品脆弱性への対応 | 自社製品(ソフト/ハード) | 製品を持つ企業が構築すべき体制 |
| SIEM | ログの統合・相関分析 | 複数のシステムログ | SOC内または外注先で運用される |
| MDR | 検知〜対応までを外部委託 | CSIRT+SOCの領域 | セキュリティ体制がない企業に有効 |
またこれらを整理することで監査にも有用です。以下では業務監査について詳しく解説していますので参考にしてみてください。
参考記事:業務監査とは?目的・監査範囲・会計監査との違い・チェックリスト例
CSIRTとSOCの違い|“監視”と“対応”の役割はここが違う
CSIRTと混同されやすいのがSOC(Security Operation Center)です。両者の関係性を明確に理解しておきましょう。
| 項目 | CSIRT(シーサート) | SOC(ソック) |
| 役割 | セキュリティ事故への対応(事後対応) | セキュリティの監視と検知(事前監視) |
| 主な活動 | インシデントの調査、対応、再発防止策の策定 | システムログの監視、脅威の検出、アラートの発報 |
| 関わるフェーズ | 発生後の対応(レスポンス) | 発生前の予防と検知 |
| 中小企業での形態 | 兼任チームでの構築が多い | 外部委託(MSS)を活用するケースが一般的 |
SOCが“見張り役”、CSIRTが“対応部隊”と考えるとイメージしやすいです。
PSIRTとは?製品トラブルの対応専門チーム
CSIRTが企業全体のセキュリティインシデント対応を担うのに対し、PSIRT(Product Security Incident Response Team)は製品の脆弱性や不具合に特化した対応チームです。
| 項目 | CSIRT | PSIRT |
| 対象 | 社内システム・ネットワーク全般 | 自社製品(ソフト・ハード)の脆弱性・不具合 |
| 活動内容 | 社内インシデントの調査・対応 | 製品脆弱性の対応・情報開示・ユーザー連携 |
| 主な関係者 | 情シス部門、経営層、広報 | 開発部門、品質管理、カスタマーサポート |
| 中小企業での必要性 | 必須に近い | 製品を提供している企業に限定される |
CSIRTがセキュリティインシデントに対応する一方、製品に脆弱性が見つかったときに迅速な告知・対応を行う体制がPSIRTです。
SIEMやMDRも登場|関連用語との関係をまとめて理解
セキュリティ分野では、CSIRTやSOCと並んで、SIEM(シーム)やMDR(エムディーアール)といったキーワードも登場します。以下に各用語の役割を整理しました。
| 用語 | フルネーム | 主な機能 | 中小企業での活用例 |
| CSIRT | Computer Security Incident Response Team | セキュリティ事故対応(事後) | 社内チームを編成し、インシデント対応計画を整備 |
| SOC | Security Operation Center | 監視・検知(事前) | MSS(外部監視サービス)を契約しログを監視 |
| PSIRT | Product Security Incident Response Team | 製品脆弱性対応 | 自社製品を持つ企業で設置・対応 |
| SIEM | Security Information and Event Management | ログの統合・相関分析 | SOCの支援システムとして導入されることが多い |
| MDR | Managed Detection and Response | 検知〜対応までを外部に委託 | SOCを持たない企業が外注で運用するケース多数 |
MDRは“CSIRT+SOC”をまとめて外部に任せられるサービスとして、近年中小企業でも注目されています。
【何をするチーム?】CSIRTのミッションを解説
CSIRT(シーサート)は、単なる「事件対応チーム」ではありません。インシデントが起きたときに慌てず迅速に動く初動対応だけでなく、普段からの備えや社員教育、システムの脆弱性チェックなどもミッションに含まれます。
ここでは、CSIRTが果たすべき主要な4つの役割について紹介します。
また、以下では個人情報のガイドラインを紹介しています。セキュリティインシデントと、関係性が深いテーマですのでこちらも参考にしてみてください。
参考記事:個人情報保護法のガイドラインを知っていますか?企業の守りに必要な情報を解説!
1. いざという時の初動対応(インシデントレスポンス)
サイバー攻撃や情報漏えいなどが発生した際、迅速かつ正確な初動対応が求められます。CSIRTは影響範囲の調査、関係者への報告、外部機関との連携などを担い、被害の拡大を防ぐ部隊です。
特に中小企業では、初動の遅れが致命傷になりやすいため、事前に対応フローを明確にしておくことが重要になります。
2. 普段の備えがカギになる(インシデントレディネス)
CSIRTの本領は、むしろ“何も起きていない時”に発揮されることを覚えておきましょう。
緊急時に備えて、対応マニュアルや連絡網の整備、模擬訓練の実施などを通じて「有事でも動ける状態」を作るのがインシデントレディネスです。こうした備えが、いざという時の混乱防止や迅速対応につながります。
3. 脆弱性やセキュリティの抜けを洗い出す
自社システムや運用ルールにどんな“隙”があるかを定期的に点検するのもCSIRTの重要な役割です。
OSやソフトウェアのアップデート忘れ、パスワード管理の甘さ、権限の過不足など、小さな抜けが大きな事故につながることもあります。棚卸しと改善を繰り返す運用が必要です。
4. 社員の意識を変える!セキュリティ教育と啓発
どれだけ対策をしても、ヒューマンエラーが原因のインシデントは防ぎきれません。CSIRTは全社員へのセキュリティ教育や注意喚起も担います。
標的型メールの見分け方、USB機器の取扱いルール、クラウドの使い方など、身近なテーマから継続的な啓発活動を行うことが効果的です。
兼任でもOK!中小企業がCSIRTを立ち上げるステップ5つ
中小企業にとってもサイバー攻撃のリスクは無視できません。しかし、「人もリソースも足りない…」という声も多いのが現実です。
そんな中で注目されているのが、少人数で始められる“兼任型CSIRT”となります。ここでは、中小企業が無理なくCSIRTを立ち上げ、実践的に運用していくためのステップを5つに分けて解説しましょう。
ステップ1:プロジェクトを立ち上げる|まずは小さく始めよう
CSIRTと聞くと大がかりな体制をイメージしがちですが、中小企業では「小さく始める」が鉄則です。
最初は情報システム部門や総務部門などの一部メンバーが兼任するかたちで構いません。有志で構成されたチームが、まず“対応の意識を持つこと”が大きな一歩になります。
ステップ2:今の社内体制やリスクを棚卸し
自社の現状を正しく把握することが、CSIRT立ち上げの土台です。
使っているシステムや外部サービス、社内のIT資産といった情報を洗い出し、どのような脆弱性やリスクが潜んでいるのかを可視化しましょう。無料のリスクチェックツールを使うのもおすすめです。
ステップ3:誰が何をやるか?役割とルールを決める
体制構築でもっとも重要なのが「誰が何を担当するのか」を明確にすることです。対応時にあいまいな状態では、被害を拡大させてしまう恐れがあります。
以下の表のように、最低限押さえておきたいCSIRTの主な役割を定めておくことhが重要です。これにより初動対応から報告までがスムーズになります。
| 役割名 | 主な担当業務 |
| インシデント通報窓口 | 社内からの通報を受け付け、状況を記録。初期判断のための情報を整理する。 |
| 初動対応担当者 | 端末の隔離やログの確認など、即時に対応可能なアクションを実施。 |
| 分析・判断担当者 | 通報された内容を技術的に精査し、外部との連携や広報が必要かを判断する。 |
| 外部連絡窓口 | サーバー会社、クラウドベンダー、JPCERT/CCなどの外部関係者と連携。 |
| 経営・広報対応 | 重大インシデントの場合、経営判断や社内外への説明・報告を担う。 |
中小企業ではこれらすべてを専任で配置するのは現実的ではないため、1人が複数の役割を兼任する体制でも問題ありません。
ポイントは、事前に「誰が何をやるか」を決めておくことです。また、役割ごとの対応フローを簡潔なマニュアルにしておくと、いざというときに全員が迷わず行動できます。
ステップ4:外部との連携体制も想定しておく
CSIRTは社内だけで完結するものではありません。サーバー会社、クラウドサービス事業者、セキュリティベンダー、JPCERT/CCなど、関係しうる外部機関との連携先もリストアップしておきましょう。
緊急連絡先一覧や対応フローを整理しておくことで、初動対応のスピードが段違いに上がります。
ステップ5:始めてからが本番!改善と継続で育てる
一度立ち上げただけで安心してはいけません。インシデント対応の訓練や、対応履歴の記録、報告書の作成などを通じて、CSIRTのレベルは少しずつ向上していきます。
実践を通じて改善を重ねる“育てるチーム”として、定期的に振り返りとブラッシュアップを行いましょう。
支援機関を活用して“ひとり情シス”でも動ける体制に
中小企業では、情報システムの専任担当が1人、または他業務と兼任していることが多く、「CSIRTを立ち上げるのは無理では?」と感じるケースも少なくありません。
そんなときこそ、外部の支援機関や専門家との連携が必要です。ここでは、代表的な支援先を紹介します。
以下では、情シス担当に必要不可欠なコンプライアンス教育について解説しています。こちらも参考にしてみてください。
参考記事:コンプライアンスの教育はどうすればいい?目的・実施方法を学んで経営を安定化!
JPCERT/CCって?国内代表CSIRTの活用方法
JPCERT/CC(Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center)は、日本のCSIRTの代表的存在です。インシデント対応のノウハウや事例を豊富に持ち、無料で公開されているガイドラインや報告テンプレートも活用できます。
以下のようなサポートを受けられることが特徴です。
- インシデント発生時の初動対応支援
- 脆弱性の注意喚起やセキュリティ情報の提供
- 連携ネットワークの構築支援(FIRST加盟機関)
「とにかく何から始めてよいかわからない」という企業は、まずJPCERT/CCの公式サイトを見て、公開リソースを活用することから始めましょう。
CSIRT協議会や地方の支援団体とつながろう
CSIRT協議会(NCA)や、地方の中小企業支援センター、商工会議所、情報セキュリティ支援専門家派遣制度など、地域に根差したサポート体制も整っています。
例えば以下のような項目がサポート内容です。
- 地域CSIRTの設立支援
- 勉強会・相談窓口の提供
- インシデント演習(机上演習など)の開催
これらの団体とつながることで、同業他社の取り組みや失敗談も学ぶことができ、自社に合った体制構築のヒントが得られます。
その他、各Slerなどと協力するのも手段の一つ
セキュリティに強みを持つSIerやMSSP(マネージドセキュリティサービスプロバイダ)と契約して、一部機能を委託するのも現実的な選択肢です。
企業によって違いますが、主に以下が支援内容となります。
- SOCやMDRによる監視業務のアウトソース
- 初動対応の手順書策定支援
- 実践的なセキュリティ教育の提供
社内に専門人材がいなくても、「外部とのハイブリッド体制」でCSIRTの役割をカバーすることが可能です。
「名ばかりCSIRT」にしないための注意点と運用のコツ
CSIRTを立ち上げても、実際には機能せず“形だけの存在”になってしまうことがあります。こうした「名ばかりCSIRT」を防ぐためには、体制面・意識面・運用ルールの3つをしっかり設計することが不可欠です。
トップの理解なしに始めるのはNG
CSIRTの本質は「組織としての危機管理」です。そのためには、経営層の理解と協力が不可欠となります。
経営層からYESを引き出すためのポイントは以下です。
| 経営層からYESを引き出すためのポイント | 内容 |
| 被害事例を提示する | 実際に起きたサイバー攻撃のケースを示し、自社にも起こりうると伝える |
| インシデント対応のコストを定量化 | 業務停止・信用低下・復旧コストなどを金額や工数で提示する |
| 外部からの要請を示す | 取引先や自治体からのセキュリティ強化要請があることを伝える |
| 最小限の投資で最大の防御 | リスクを放置するより、対策コストの方が合理的であることを説明す |
「リスクを放置するよりも、最小限の投資で備えるほうが合理的」という文脈で説明すると、納得を得やすくなります。
担当者が“なんとなく対応”にならない仕組みを作る
CSIRTが名ばかりになる原因のひとつが、「誰が何をどう対応すべきか」が曖昧なまま進むことです。以下のような工夫をしておきましょう。
| 実効性を支える仕組み | 内容 |
| 対応マニュアルを作成 | 初動対応から報告までの手順を明文化 |
| 通報・判断・報告フローの図式化 | フロー図で対応手順を共有し、誰が何をするか明確に |
| シミュレーションの実施 | 月1回程度の机上訓練で対応力を高める |
担当者が“とりあえずやっておく”という感覚で対応してしまうと、初動の遅れや情報共有の不備が発生します。
責任と権限の境界を明確にしよう
CSIRTの役割は多岐にわたり、対応範囲も広いのは事実です。そのため、責任と権限があいまいなままだと混乱を招きます。
| 項目 | 内容 |
| 公表・報告の決定権 | 緊急時に誰がどこまでの情報を外部公開できるか決めておく |
| 情報の取扱い責任 | センシティブな情報の開示・共有範囲の決定者を明確化 |
| 外部連絡の担当 | 警察・JPCERT等への連絡を誰が行うか事前に決めておく |
| 文書化の推奨 | 役割分担表や権限マトリクスで整理しておく |
こうした項目は、あらかじめ「役割分担表」や「権限マトリクス」などにして文書化しておきましょう。
まとめ
CSIRTは、単なるセキュリティチームではなく、企業の信頼と事業継続を守るための重要な仕組みです。中小企業であっても、サイバー攻撃や情報漏洩といったリスクは決して他人事ではありません。
中小企業にとってCSIRTは、リスク対策であり、取引先や顧客からの信頼を高める経営資源でもあります。ぜひ今回の内容を参考に、実効性のあるCSIRT運用を始めてみてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録