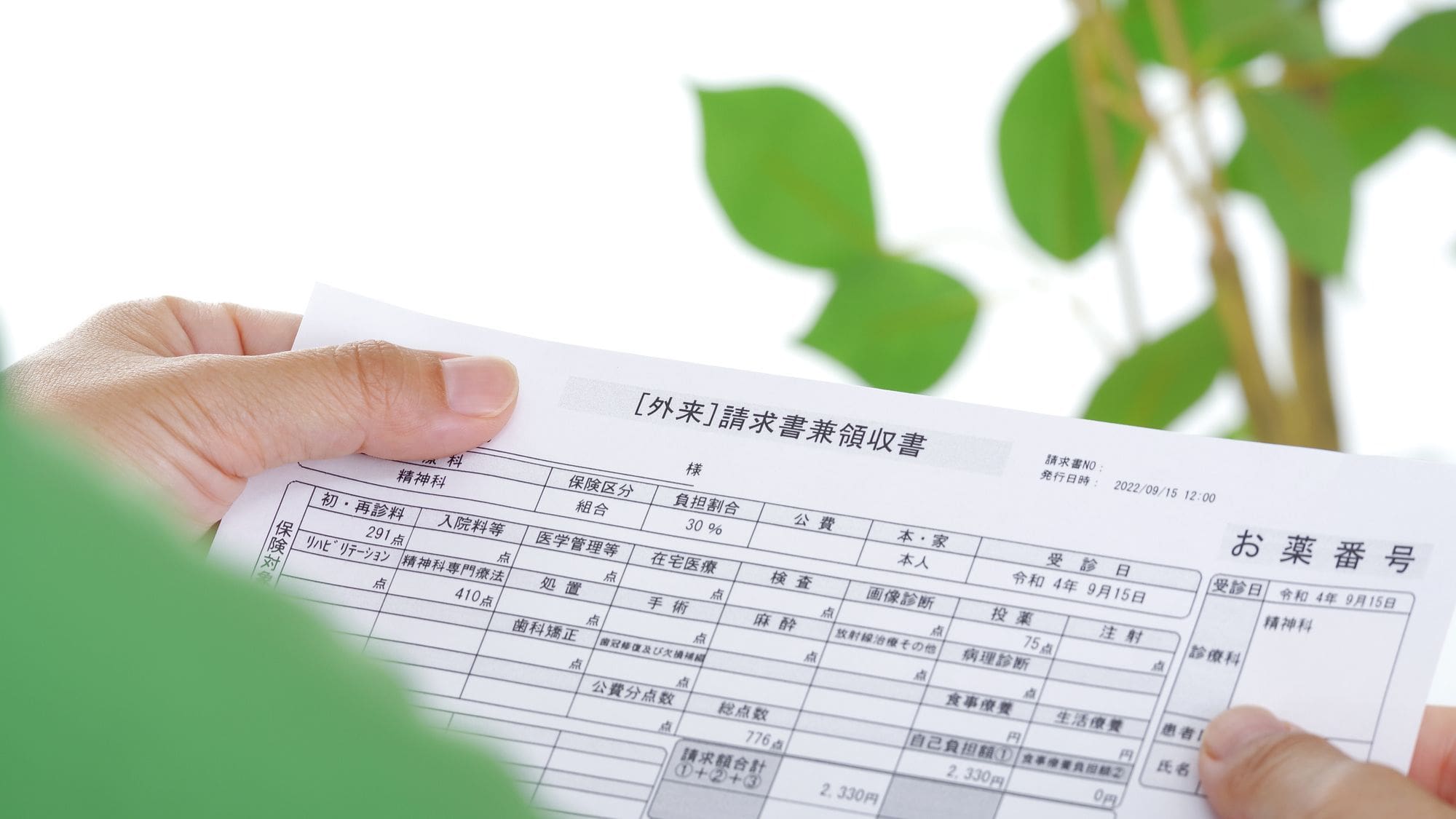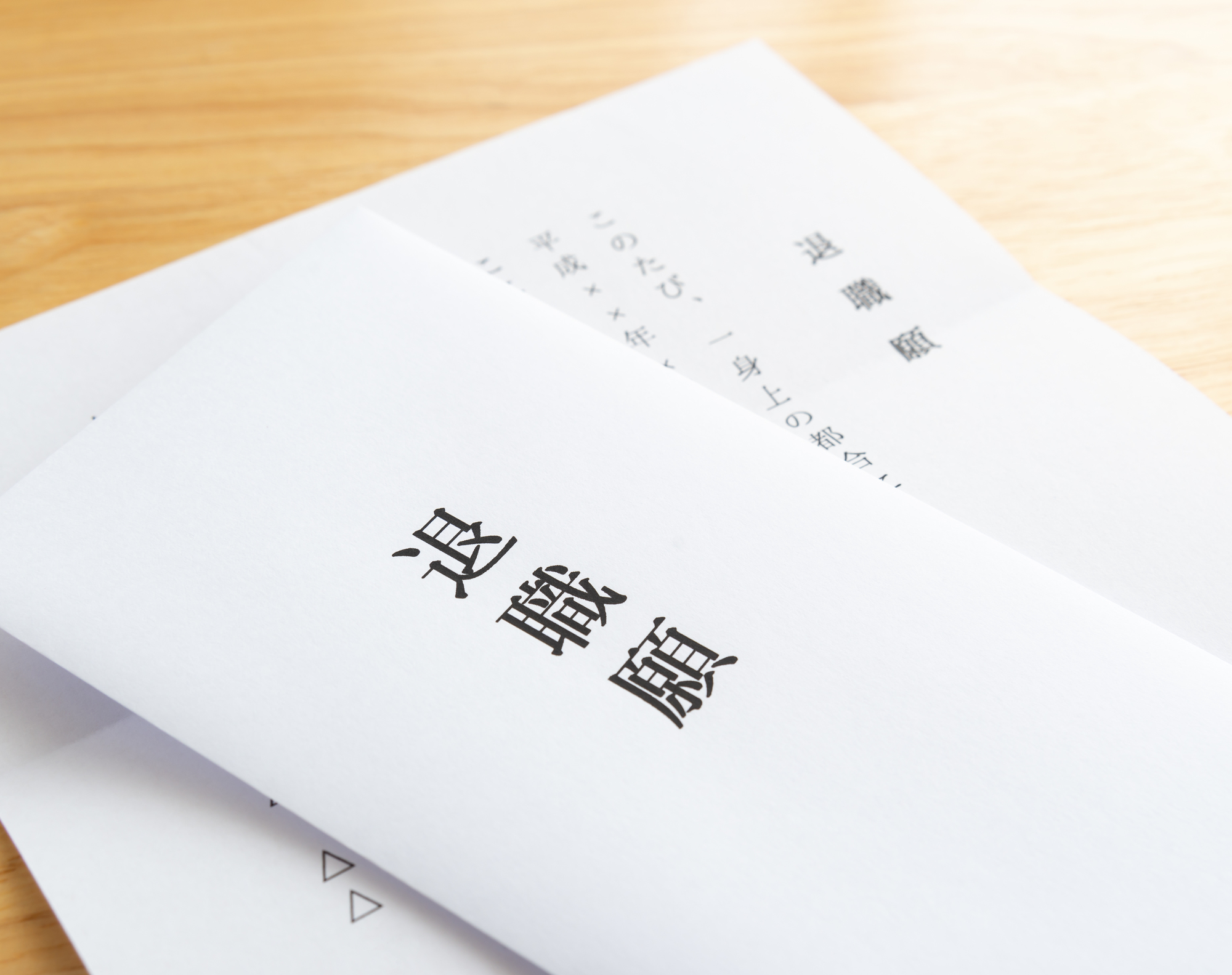アンガーマネジメントで従業員が働きやすい環境を!やり方や役立つ資格

「上司や部下の言動にイライラしてしまう」
「つい感情的に叱責して後悔する」
このような「怒り」に関する悩みは、多くのビジネスパーソンが抱えています。
しかしその問題は、怒りの感情と上手に付き合うためのスキル「アンガーマネジメント」で解決できるかもしれません。
この記事では、アンガーマネジメントの基礎知識から、経営者や管理職が導入することで得られる離職率低下や生産性向上といったメリット、アンガーマネジメントを実践するための具体的な方法などについて詳しく解説します。
「怒り」に関する悩みがある方は、是非この記事を参考にしてください。
目次
アンガーマネジメントとは何か簡単に解説!
アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで開発された、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。
決して、怒りという感情を無理に我慢したり、無くしたりすることを目的とするものではありません。
怒りを感じること自体は、人間にとってごく自然な感情の一つなのです。
重要なのは、怒る必要のある事柄と、そうでない事柄を適切に見極めることです。
そして、怒りを表現する必要がある場面では、他人を傷つけたり自分を不利にしたりしない、建設的な方法で表現するスキルを身につけます。
一方で、怒る必要のない場面では、その感情に振り回されずに穏やかにやり過ごせるようになることを目指します。
アンガーマネジメントは、健全な職場環境を構築し、円滑な人間関係を築くために不可欠なスキルとして、その重要性が高まっているのが現状です。
経営者や管理職がアンガーマネジメントを身に付けておいた方がよい理由
経営者や管理職の感情のコントロールは、個人の問題だけでなく、組織全体に大きな影響を及ぼします。
感情の波は、部下のパフォーマンスや職場の雰囲気に直接伝わるためです。
この項目では、アンガーマネジメントを身につけることで具体的にどのようなメリットがあるのかについて解説していきます。
従業員の離職率低下に繋がる
経営者や管理職が自身の怒りをコントロールできない職場は、従業員にとって大きなストレスの原因となります。
上司の感情的な言動に常に怯えながら仕事をする環境では、従業員は安心して能力を発揮できません。
管理職がアンガーマネジメントを実践し、安定した態度で部下に接することで、職場には安心感が生まれます。
建設的なフィードバックや冷静な問題解決が行われるようになれば、従業員のエンゲージメントは高まり、この会社で働き続けたいという意欲に繋がるでしょう。
結果として、貴重な人材の流出を防ぎ、採用や育成にかかるコストの削減も図れます。
心理的安全性の高い職場になり業務効率が上がる
心理的安全性とは、組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態のことです。
この心理的安全性が低い職場では、従業員は「こんなことを言ったら怒られるかもしれない」「失敗を責められるのではないか」と萎縮してしまいます。
その結果、業務上の重要な報告が遅れたり、新しいアイデアや改善提案が出にくくなったりと、組織の成長が阻害される事態を招きかねません。
アンガーマネジメントを身につけた管理職は、問題が発生した際に感情的に叱責するのではなく、原因を冷静に分析し、建設的な対話を促すことができます。
これにより、部下は失敗を恐れずに挑戦し、自由に意見を述べられるようになり、組織全体の業務効率と生産性の向上に大きく寄与するのです。
参考記事:職場での心理的安全性の作り方は?安心して働ける環境を実現する施策
ハラスメントのリスクを減らせる
| 令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行されました。中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。 |
出典)厚生労働省「労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」
上記の通り、2022年4月からは中小企業においても、パワーハラスメント防止措置が完全に義務化されました。
企業には、ハラスメントのない職場環境を整備する責任があります。
パワーハラスメントの代表的な類型である「精神的な攻撃」は、まさにコントロールされていない怒りの感情が、不適切な言動として現れたものです。
「指導のつもりだった」という弁明が通用しないケースも多く、無自覚のうちにハラスメントの加害者になってしまうリスクは誰にでもあります。
アンガーマネジメントは、怒りの衝動が湧き上がった際に一度立ち止まり、自分の言動を客観的に見つめ直すためのトレーニングです。
カッとなった勢いで相手を傷つける言葉を発してしまう前に、「この表現は適切か」「相手を追い詰めていないか」と冷静に判断する癖がつきます。
このスキルは、パワーハラスメントだけでなく、あらゆるハラスメントの発生リスクを大幅に低減させ、企業を法的なリスクから守るための有効な防衛策となります。
参考記事:【2025年】厚生労働省が定めるハラスメントの定義を知って、企業の安定した経営を守ろう!
自身の健康にも良い影響を与える
人間は、強い怒りを感じると交感神経が優位になり、心拍数の増加や血圧の上昇、筋肉の緊張といった反応が起こります。
これらの反応は、人体にとって決して良いものではありません。
一時的なものであれば問題ありませんが、日常的に怒りやイライラを感じている状態が続くと、身体には大きな負担がかかり続けます。
慢性的な怒りは、高血圧や心疾患、脳卒中、さらには免疫機能の低下といった深刻な健康問題のリスクを高めます。
しかし、アンガーマネジメントを実践することで、こうしたストレス反応を適切に管理し、心身をリラックスさせる術を身につけることができるのです。
アンガーマネジメントは意味ない?中小企業に必要な理由
「アンガーマネジメントは大企業が取り組むもの」
「研修を導入するほどの余裕はない」
こういった考えを持っている中小企業の経営者も少なくありません。
しかし実際には、人材や資金といったリソースが限られている中小企業だからこそ、アンガーマネジメントの導入には大きなメリットがあります。
アンガーマネジメントを導入するメリット
中小企業が、従業員に対してアンガーマネジメントの研修等を導入することで、以下のような大きな恩恵を受けられる可能性があります。
貴重な人材の定着
一人ひとりの従業員の役割が大きい中小企業では、一人の離職が事業に与えるダメージは計り知れません。
アンガーマネジメントによって働きやすい環境を整備することは、人材の定着に直結します。
生産性の最大化
経営者や管理職と、従業員との距離が近い中小企業では、上層部の感情が職場の雰囲気に直接影響します。
円滑なコミュニケーションは、少数精鋭のチームワークを強化し、組織全体の生産性を飛躍的に向上させるでしょう。
経営層の負担軽減
経営から実務まで多くの役割を担う中小企業の経営者や管理職にとって、精神的な安定は不可欠です。
感情のコントロールスキルは、日々のプレッシャーを乗りこなし、健全な経営判断を続けるための支えとなります。
採用競争力の強化
「働きやすい職場」であることは、企業の魅力的なアピールポイントです。
特に近年は、給与や待遇だけでなく、職場の人間関係や環境を重視する求職者が増えています。
アンガーマネジメントへの取り組みは、採用活動において他社との差別化を図る強力な武器になり得ます。
アンガーマネジメントを導入した企業の成功事例
実際にアンガーマネジメント研修を実施して、成果が出たという事例は数多く存在します。
たとえば、システム開発などを手掛けるNSSLCサービス株式会社(現:日鉄ソリューションズサービスアンドテクノロジー株式会社)は、社員間の価値観の違いから生じる人間関係のすれ違いや、チーム内の対立に課題を抱えていました。
そこで、リーダーとしてのマネジメント能力を高めてチーム力を強化することを目的に、2019年からアンガーマネジメント研修を導入します。
研修では、怒りのメカニズムの学習に加え、グループワークで互いの価値観を深く知る機会を設けたことで、社員が自身の怒りの傾向を自覚できるようになりました。
その結果、従業員たちが「怒りとの正しい付き合い方」を知り、社員同士の衝突が減ったり、ハラスメントの防止に役立ったりといった成果を出すことに成功したのです。
このように、企業がアンガーマネジメント研修を導入するメリットは、大変大きいと言えます。
アンガーマネジメントのやり方とは?効果的な方法を知ろう!
アンガーマネジメントは、特別な研修を受けなくても、日常生活の中で意識的に実践できるテクニックがあります。
この項目では、怒りの感情が湧き上がったときに役立つ、代表的で効果的な方法を5つ紹介します。
何かに怒りを感じたら6秒だけ耐える
怒りの感情のピークは、長くても6秒間であると言われています。
この最初の6秒間は、脳の扁桃体が活発に働き、理性を司る前頭葉の働きが追いついていない状態です。
そのため、衝動的に強い言葉を発したり、乱暴な行動をとってしまったりしがちになります。
後で「なぜあんなことを言ってしまったのだろう」と後悔する言動の多くは、この6秒の間に行われているのです。
そこで、カッとなったら、まず意識的に6秒間だけ行動を停止させてみましょう。
心の中でゆっくりと「1、2、3、4、5、6」と数えるだけでも構いません。
あるいは、深く息を吸ってゆっくりと吐き出す深呼吸をするのも効果的です。
このわずかな時間を作るだけで、理性が働き始め、衝動的な反応をぐっと抑えることができるようになります。
一時的にその場から離れる
「6秒ルール」を試しても怒りが収まらない、あるいは非常に強い怒りを感じた場合には、その場を物理的に離れる「タイムアウト」という方法が有効です。
怒りを引き起こしている対象や環境から距離を置くことで、強制的にクールダウンする時間を作ります。
たとえば、会議中に激しい怒りを感じたら、「少し頭を冷やしてきます」と一言断って席を立つ、トイレに行く、飲み物を買いに行くといった行動がタイムアウトに該当します。
怒りの対象から意識をそらすことで、感情の渦に飲み込まれるのを防ぎ、冷静さを取り戻すきっかけをつかむことができるのです。
自分の価値観が本当に正しいのか再確認する
人が怒りを感じる背景には、自分自身が持つ「~するべきだ」「~であるべきではない」という価値観や信念が存在します。
たとえば、「部下は上司の指示にすぐ従うべきだ」「時間は厳守するべきだ」といったものです。
この「べき」が裏切られたり、脅かされたりした時に、人は怒りという感情を抱きやすいのです。
しかし、自分の「べき」は、必ずしも他人にとっての「べき」ではありません。
そこで、怒りを感じた際には、「自分のこの『べき』は、本当に絶対的なルールなのだろうか?」「相手には相手の事情や価値観があるのではないか?」「もう少し許容範囲を広げることはできないか?」と自問自答してみてください。
自分の価値観を客観視し、その境界線を再確認するプロセスは、不要な怒りを手放すのに役立ちます。
「全ての人が自分と同じ価値観を持っているわけではない」と認識することが、寛容さを生み、人間関係をより円滑にします。
自分が何に対して怒ったのかの記録を残す
「アンガーログ」と呼ばれる、怒りを記録する習慣も非常に効果的な手法です。
ノートやスマートフォンのメモ機能などを使い、自分が怒りを感じた出来事について記録していきます。
具体的には、以下のような項目を書き出すとよいでしょう。
- 【日時】いつ怒ったか (例:7月26日 15:00頃)
- 【場所】どこで怒ったか (例:会議室)
- 【出来事】何があって怒ったか (例:Aさんの報告が要領を得なかった)
- 【怒りの強さ】10段階でどのくらいか (例:7)
- 【自分が取った行動】実際にどう行動したか (例:語気を強めて指摘してしまった)
こういった記録を続けていくと、自分がどのような状況で、どのような言葉に、どの程度の怒りを感じやすいのかという「怒りのパターン」が客観的に見えてきます。
自分の傾向を把握できれば、怒りを感じやすい場面を事前に避けたり、怒りが湧き上がってきても「またこのパターンか」と冷静に対処したりすることが可能になるはずです。
アンガーマネジメントに関する資格を取得する
セルフコントロールのためだけでなく、より深く体系的にアンガーマネジメントを学びたい、あるいは他者へ指導できるようになりたいと考える場合には、資格の取得が有効な選択肢となります。
資格取得を目指す過程で、怒りのメカニズムや様々な対処法、さらには指導法までを網羅的に学ぶことができるはずです。
知識が深まることで、自分自身の感情コントロールがより容易になるだけでなく、社内で研修講師を務めたり、部下の指導に活かしたりと、キャリアの幅を広げることにも繋がります。
アンガーマネジメントのスキルは、どのような職種においても高く評価されるポータブルスキルです。
自身の市場価値を高めるという観点からも、挑戦してみる価値は十分にあると言えます。
アンガーマネジメントが身に付く資格
アンガーマネジメントを体系的に学び、仕事やキャリアに活かしたいと考えるなら、資格取得を目指してみましょう。
この項目では、アンガーマネジメントに関する代表的な3つの資格を取り上げ、その特徴や費用、難易度を比較していきます。
| 資格名 | 主催団体 | 費用(税込) | 難易度の目安 |
| アンガーマネジメントファシリテーター | 一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会 | ■受講料:143,000円 ■認定料:33,000円 ■入会金:11,000円 | ★★★★☆ |
| アンガーコントロールスペシャリスト | 一般社団法人 日本能力開発推進協会(JADP) | ■受験料:5,600円 | ★★☆☆☆ |
| アンガーコントロール士 | 日本インストラクター技術協会(JIA) | ■受験料:10,000円 | ★★☆☆☆ |
アンガーマネジメントファシリテーター
アンガーマネジメントファシリテーターは、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会が認定する、アンガーマネジメント関連では広く知られている資格です。
この資格の最大の特徴は、取得後に協会認定のファシリテーターとして、入門講座などを自ら開催できる点にあります。
企業研修の講師やセミナーの開催など、プロフェッショナルとしての活動を目指す方に最適と言えます。
費用は高めですが、その分、質の高い知識と指導スキルを体系的に学ぶことができ、信頼性の高い資格としてキャリアに活かすことが可能です。
アンガーコントロールスペシャリスト
アンガーコントロールスペシャリストは、一般社団法人日本能力開発推進協会(JADP)が認定する資格です。
この資格を取得するには、まず協会が指定する認定教育機関の通信講座を受講し、カリキュラム修了後に在宅で検定試験を受ける形になります。
通信講座で学習する内容は、主に以下の通りです。
- 怒りとは何か?
- アンガーコントロールの基本
- アンガーコントロールテクニック
- 上手な怒りの伝え方
内容としてはそれほど難しくなく、プロの講師を目指すというよりは、自身のスキルアップや業務への応用を主目的とする場合に有力な選択肢となる資格です。
アンガーコントロール士
アンガーコントロール士は、日本インストラクター技術協会(JIA)が認定する資格です。
こちらも通信講座で学習し、在宅で受験する形式が基本となります。
試験では、アンガーコントロールの基本的な知識に加え、アンガーコントロールの歴史、アンガーコントロールの利点などについて広く問われます。
なお、受験資格は特に設けられていないため、誰でも挑戦することが可能です。
受験料も比較的安価で、難易度も高くない上、資格取得後は自宅やカルチャースクールなどで講師として活動する道も開けます。
まとめ
以上、アンガーマネジメントの基本的な知識から、経営者や管理職が身につけるべき理由、企業が導入するメリット、そして個人で実践できる具体的な方法や役立つ資格について解説しました。
アンガーマネジメントは、怒りを無くすことではなく、怒りと賢く付き合うためのスキルです。
このスキルは、従業員の離職率低下や心理的安全性の確保、ハラスメントリスクの低減に繋がり、最終的には企業の生産性向上にも貢献します。
特に、一人ひとりの影響力が大きい中小企業において、その効果は絶大です。
従業員が安心して長く働ける環境づくりの一環として、アンガーマネジメント研修の導入を検討する価値は非常に高いので、自社に必要だと判断した場合はぜひ研修実施を検討してみてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録