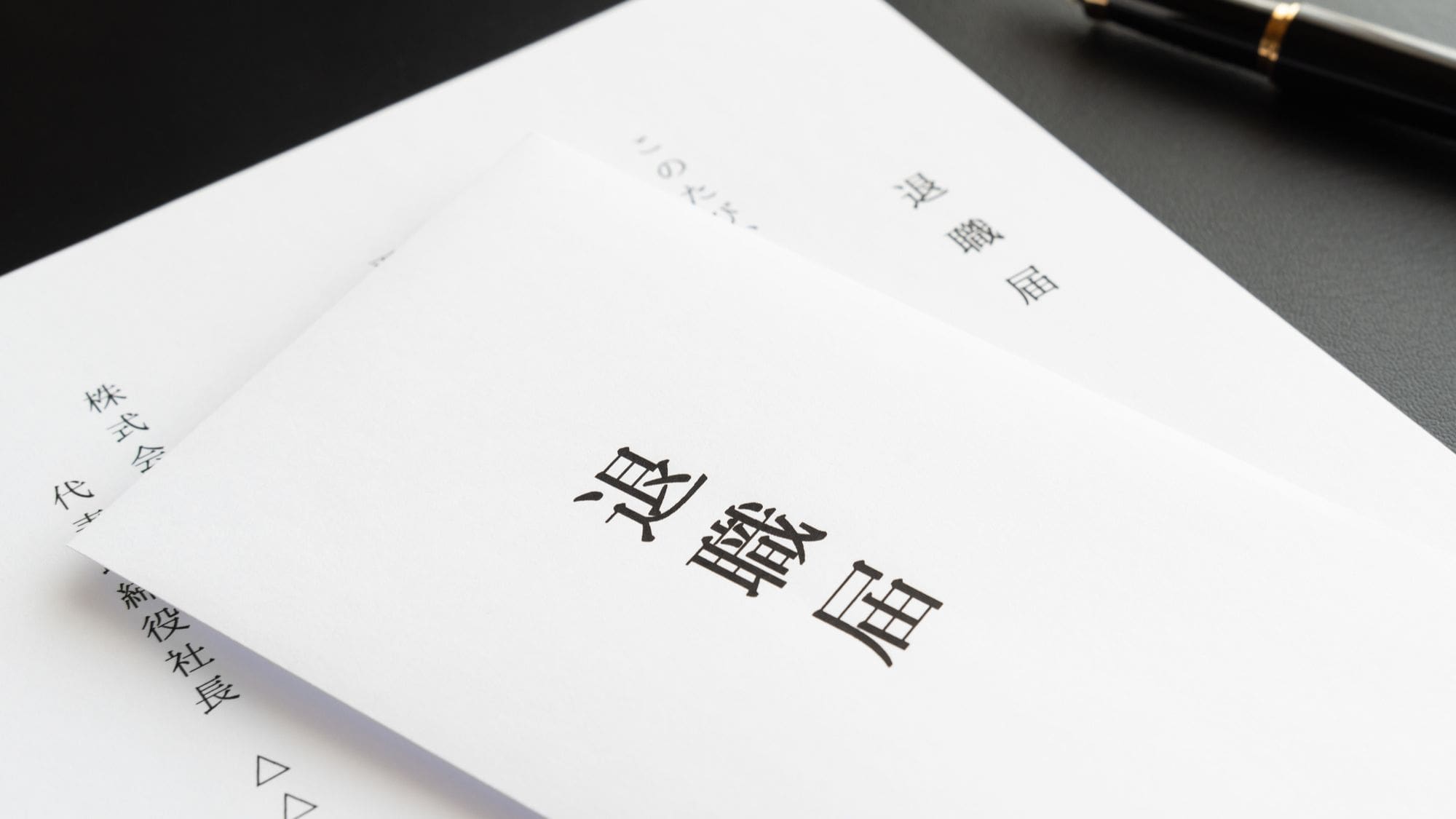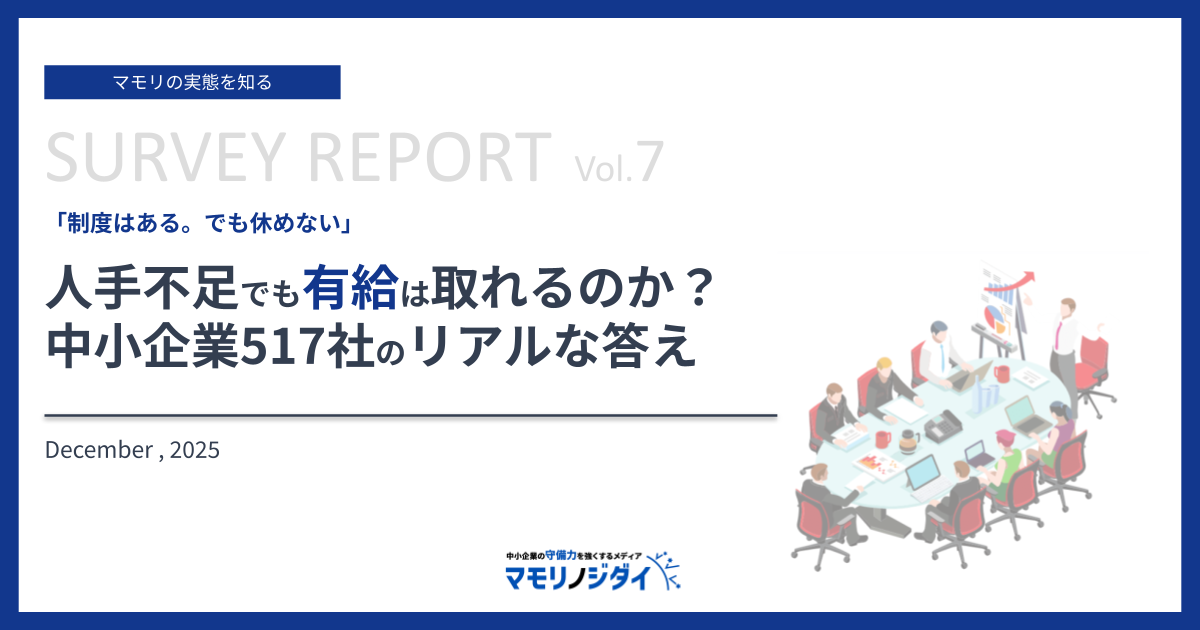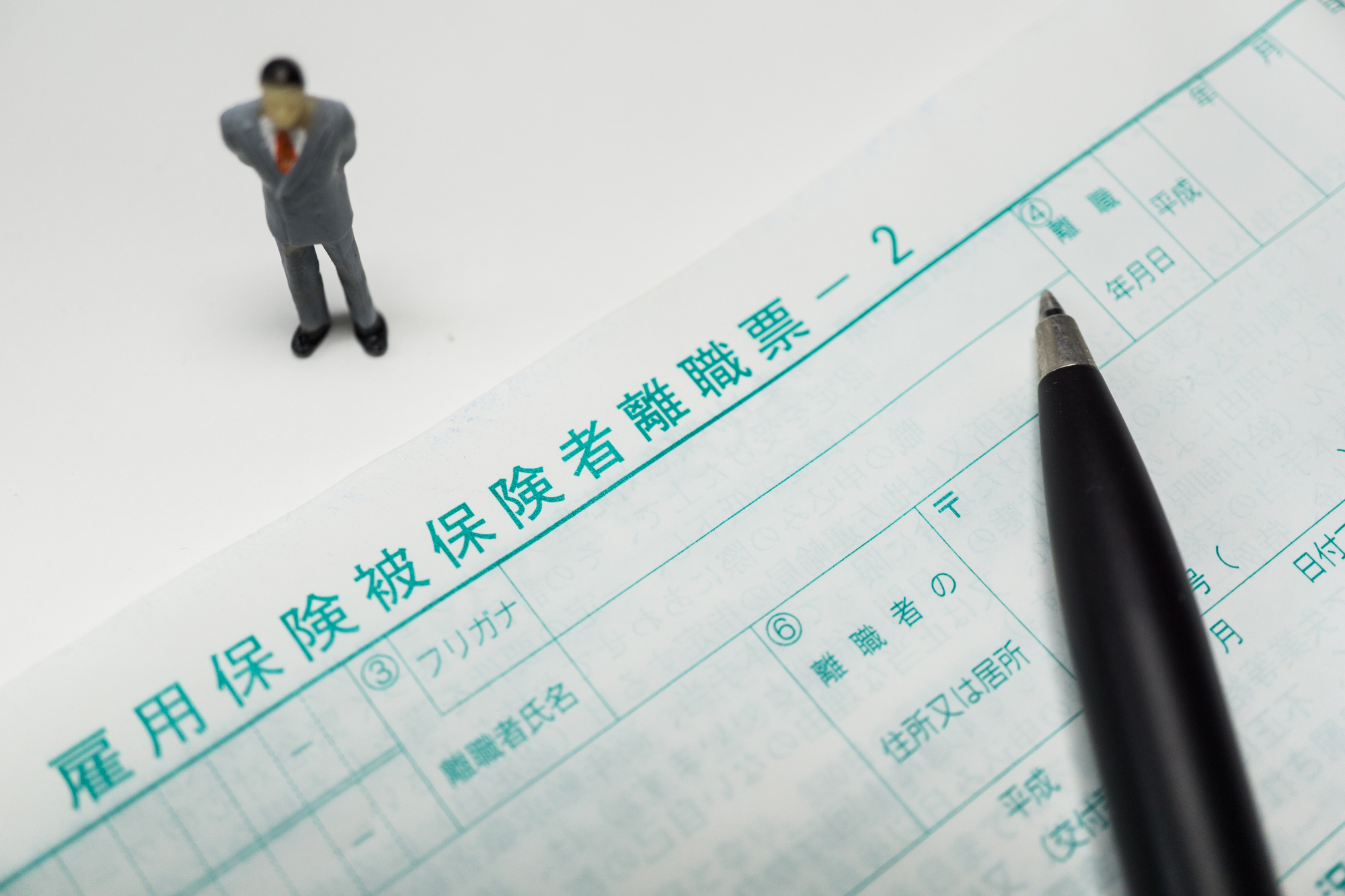【中小企業向け】産業医の選び方と活用法は?義務・役割・面談内容まで

「うちは従業員も少ないし、産業医なんて必要ないのでは?」と思っていませんか?
実は、従業員が50人を超えた時点で、産業医の選任は法律上の“義務”です。しかも、形だけの名義貸しや、機能していない産業医との契約には、企業にとって重大なリスクが潜んでいます。
この記事では、「そもそも産業医とは何か?」「どのように選べばよいのか?」「自社にはどんな産業医が合っているのか?」といった中小企業が抱きがちな疑問や不安を、わかりやすく整理しました。
また、実際の活用例や、産業医との失敗事例も紹介しながら、産業医制度を自社にとって“役立つ仕組み”にするための実践的な知識とポイントをお届けします。
産業医の設置はメンタルのケアなどを通して「離職率改善」にも寄与する施策です。以下の資料では中小企業の経営者、人事担当の方に向けて「人が辞めない組織の作り方」を解説していますので、無料でダウンロードしてみてください。
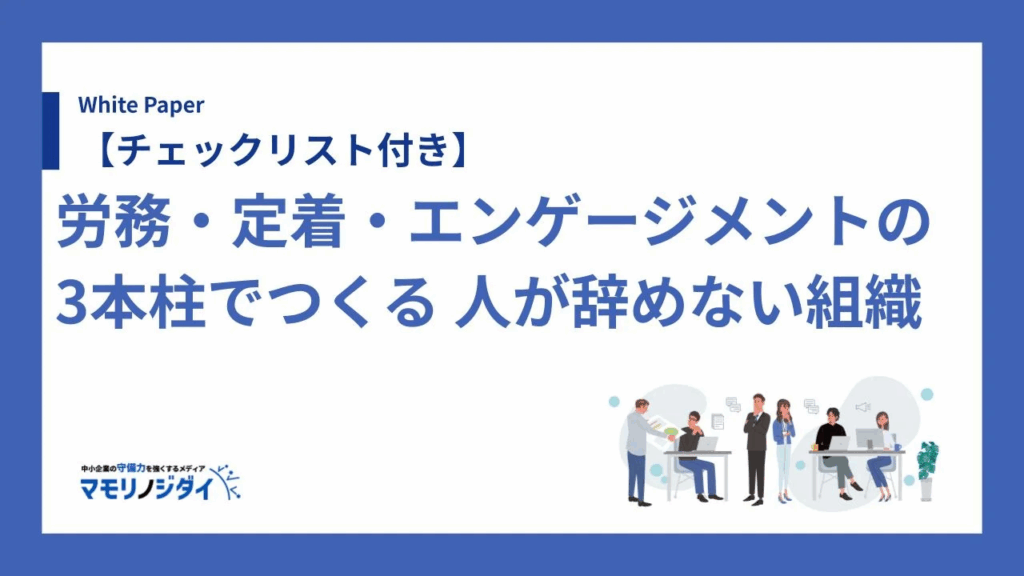
>>【チェックリスト付き】労務・定着・エンゲージメントの 3本柱でつくる 人が辞めない組織のダウンロードはこちら
目次
産業医って必要なの?「義務」と「違反リスク」をわかりやすく整理
実は従業員が50人以上の事業場では、規模にかかわらず産業医の選任が法律で義務づけられています。
産業医の設置は、労働安全衛生法第13条に基づく義務です。違反した場合、50万円以下の罰金を科されるリスクもあるため、見逃すことはできません。
そもそも産業医とは何か? そして、なぜ設置が義務となるのか? 中小企業が最低限押さえておくべきポイントを整理しました。
参考)e-GOV「労働安全衛生法」
参考記事:【2025年】厚生労働省が定めるハラスメントの定義を知って、企業の安定した経営を守ろう!
医師と何が違う?「産業医」の定義と役割を理解しよう
産業医とは、労働者の健康管理を専門に担う医師を指します。通常の医師が「病気の診断と治療」を行うのに対し、産業医は「職場における健康リスクの予防と対策」が主な役割です。
具体的には以下のような業務を行います。
- 定期的な職場巡視による労働環境の改善提案
- 健康診断後のフォローアップや面談対応
- メンタルヘルス不調者への面接指導
- 衛生委員会での助言・指導
つまり産業医は、企業の安全衛生体制の中核的存在とも言える存在です。中小企業でも、従業員の健康を守るための「パートナー」として積極的に活用しましょう。
産業医の設置は「50人以上」の中小企業で義務化!
労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者がいる事業場には、産業医の選任が義務づけられています(※本社・支社など拠点単位でカウントされます)。
選任しなかった場合や、選任報告を怠った場合は、労働基準監督署から是正指導や罰則を受けるおそれがあります。
また、単なる“名義貸し”で機能していない産業医体制も危険です。実質的には「未選任」とみなされる可能性があり、企業の信頼を損ねかねません。
参考)厚生労働省「産業医について」p.1
産業医のタイプには専属産業医と嘱託産業医がある
一口に「産業医」といっても、大きく分けて「専属産業医(常勤)」と「嘱託産業医(非常勤)」に分かれます。
中小企業で求められるのは主に「嘱託産業医」です。しかし違いを正確に理解しておくことで、選任時のミスマッチやトラブルを防ぐことができます。
以下の表に、それぞれの特徴をまとめました。
| 項目 | 専属産業医(常勤) | 嘱託産業医(非常勤) |
| 適用対象 | 常時1,000人以上の労働者がいる事業場など | 常時50人以上〜999人以下の事業場 |
| 雇用形態 | 企業が直接雇用し、常勤で勤務 | 外部の医師と契約し、月1回などの訪問で対応 |
| 勤務日数・時間 | 原則として毎日勤務 | 月1回〜数回程度の訪問(法令により最低頻度あり) |
| 主な役割 | 常時企業内で健康管理業務を実施 | 職場巡視、面談、健診後の措置など必要に応じて実施 |
| 費用感 | 高額(年収ベースで雇用) | 比較的安価(月数万円〜) |
ほとんどの中小企業では、嘱託産業医の選任が現実的です。月1回程度の訪問契約で法令に対応しつつ、必要な助言・面談・報告業務などをお願いできます。
ただし、形だけの名義貸しでは法令違反とみなされる恐れがあるため、実務にしっかり対応してくれる産業医を選ぶことが重要です。
【こんなに頼れる!】産業医の活用シーンと企業が得られるメリット
産業医は「選任して終わり」ではありません。むしろ、企業がうまく活用すれば職場の安全衛生レベルが向上し、従業員の健康リスクや離職率を下げることができる心強い存在です。
ここでは、実際に中小企業でも活用されている具体的なシーンと、それによって得られるメリットをご紹介します。
活用例①《職場巡視》自社では気づけない労災リスクの発見と改善提案
産業医は、月1回以上の職場巡視(※嘱託産業医の場合)が義務です。この際、現場を実際に見ながら「転倒しやすい動線」「照明不足」「過度な騒音」など、労災リスクにつながる要因を専門的な視点で指摘し、改善提案をしてくれます。
こうした巡視によって、自社の中では“当たり前”になっていた危険箇所に気づけるのは、大きなメリットです。結果として、安全配慮義務の履行や労災の未然防止につながります。
活用例②《健康診断の事後措置》「受けっぱなし」を防ぎ、高リスク者を早期フォロー
健康診断を実施しても、その結果を放置しては意味がありません。法令上、産業医は「異常の所見があった従業員」への就業上の措置に関して、事業者に意見を述べることが義務です。
例えば、「血圧が高く、長時間労働を制限すべき」「再検査を早急に受けるべき」といった具体的な医師の意見が従業員フォローに直結します。これにより、重大な健康トラブルを未然に防ぎ、働き続けられる環境づくりが可能です。
活用例③《メンタルヘルス面談》休職・離職の未然防止とスムーズな職場復帰支援
近年増えているのがメンタル不調による休職や退職。産業医は、面談によって早期の異変察知や、復職支援の計画立案を行う役割も担っています。
特に中小企業では、管理職が個別に対応するには限界があるため、第三者かつ医療の専門家としてサポートしてくれる存在は非常に重要です。
従業員の信頼も得やすく、結果として職場全体の心理的安全性の向上や、離職防止にもつながります。
活用例④《衛生委員会》専門家の視点で議論を活性化し、実効性のある施策へ
従業員50人以上の事業場では、毎月1回の衛生委員会の開催も義務です。産業医はこの委員会に出席し、職場改善に向けた議論に専門的な意見を提供します。
例えば、「空調による体調不良が起きていないか」「食中毒対策や感染症対策は十分か」など、実効性のある施策に導くための助言を期待できることがメリットです。
単なる“形式的な会議”になりがちな衛生委員会も、産業医の関与により、社員にとって有益な場へと変えることができます。
中小企業のための失敗しない産業医選びのポイント
「とにかく産業医を探さなきゃ」と焦って選任してしまうと、「連絡がつかない」「何もしてくれない」といった後悔につながることも少なくありません。
中小企業にとって産業医との付き合いは、“価格だけで決めない”ことが鉄則です。ここでは、契約スタイルや費用感といった選定時の判断軸を整理しましょう。
参考記事:労働条件とは?労働条件明示の義務と記載すべき内容を解説
紹介・派遣・直接契約など最適なスタイルは?
産業医との契約スタイルは、大きく分けて以下の3パターンがあります。
| 契約スタイル | 特徴 | 向いている企業 |
| 紹介会社経由 | 産業医のマッチングを支援。契約先は企業と医師本人 | 初めての選任で不安な企業 |
| 派遣会社経由 | 契約先は派遣会社。業務委託型で柔軟に変更や代替が可能 | 定期訪問が必要ながらも柔軟性が欲しい企業 |
| 直接契約 | 自社で医師にアプローチして契約 | 信頼できる医師が見つかっている企業 |
紹介会社や派遣会社を利用することで、法令遵守の手続きや契約書の雛形もサポートしてくれるため、初めての選任には安心です。
一方、直接契約の場合は、費用を抑えやすい反面、相手とのやり取りや契約管理の責任がすべて企業側にある点に注意しましょう。
産業医の料金相場を把握しておこう
嘱託産業医(非常勤)の費用は、契約内容や訪問頻度により大きく異なります。以下は一般的な相場感です。
ただしもちろん、地域や医師の経験、業務範囲(面談の有無、職場改善提案など)により変動があります。実際は候補者にヒアリングをしましょう。
| 項目 | 相場の目安 |
| 月1回訪問・2時間程度の対応 | 3万円〜6万円/月 |
| 月2回訪問+面談など込み | 5万円〜10万円/月 |
| 衛生委員会・報告書提出あり | 上記に加え+1〜2万円程度/月 |
| 年間契約一括払い(割引あり) | 年額30万円〜100万円程度 |
「名義貸しで安ければいい」と考えると、いざという時に全く機能しない産業医を選んでしまう危険性があります。「対応内容」「信頼性」「緊急時の連絡体制」などを含めて、費用に見合った実効性のある契約を結ぶことが重要です。
「連絡がつかない」にならないための契約のコツ
産業医を選任して最も多いトラブルの一つが、「いざというときに連絡がつかない」というケースです。
名義上は契約していても、緊急時や健康相談が必要なタイミングで応答がなければ、企業としての安全配慮義務を果たせず、労務リスクが高まってしまいます。
このような事態を防ぐためには、契約前・契約時の確認事項を明確にしておくことが大切です。以下のポイントを押さえておきましょう。
| 契約前に確認すべきポイント | 契約書に盛り込むべき文言例 |
| 連絡手段と連絡可能時間の明示(メール/携帯/チャットツールなど) | 「緊急対応が必要な場合には、〇時間以内に初回応答を行うこと」 |
| 対応できる業務範囲の明確化(職場巡視、面談、衛生委員会、緊急時対応など) | 「訪問以外の対応(電話・メール・書面等)も業務の一部とする」 |
| 代替医師や不在時の対応方法があるか | 「連絡がつかない場合、●日以内に再連絡がなければ契約見直しの対象とする」 |
| 月あたりの対応時間や稼働イメージの確認 | (上記の文言とあわせて、「稼働時間や業務内容は別紙業務内容表に準ずる」といった明記も有効) |
このように、口頭確認だけで終わらせず、契約書にも明文化しておくことが、トラブル防止の最大のコツです。「うちは小規模だから…」と遠慮せず、必要な運用レベルを最初に共有し、書面に落とし込むようにしましょう。
自社に合う産業医を見つける具体的な探し方
「産業医を選任しなければならないけど、どこから探せばいいのかわからない」という声は中小企業の現場で非常によく聞かれます。
ここでは、初めての企業でも実行しやすい5つの探し方を紹介しましょう。
① 地域の医師会に相談する
地域の医師会(例:東京都医師会、大阪府医師会など)は、産業医のあっせん業務を行っているケースがあります。信頼性が高く、地域事情にも詳しい医師が紹介されやすいため、長期的な関係構築にも有効です。
ただし、紹介までに時間がかかる場合があるため、余裕をもって相談することがポイントになります。
② 産業医紹介サービスを利用する
民間の紹介会社やオンラインサービスを利用すれば、最短即日で候補者を複数提示してもらうことも可能です。面談や条件交渉まで代行してくれるところも多く、スピード重視の企業や初めて選任する企業におすすめになります。
ただし、費用が別途発生する場合があるため、料金体系は事前にしっかり確認しましょう。
③ 健康診断の委託先(健診機関)に相談する
すでに健康診断を委託している医療機関がある場合は、そちらに産業医紹介の可否を相談するのも有効です。医療連携が取りやすく、健康診断→フォローアップ面談までスムーズな体制が築きやすいといえます。
産業医との契約をワンストップで進められるケースもあるため、既存の健診機関にまず一声かけてみるとよいでしょう。
④ 知人や他社の経営者から紹介してもらう
信頼できる経営者仲間や顧問社労士・税理士がいれば、既に付き合いのある産業医を紹介してもらうのも有効です。実際の対応や評判も聞けるため、“ハズレを引きにくい”探し方として活用できます。
ただし、紹介者と相性が良くても、自社と必ずしも合うとは限らないため、事前に希望条件はしっかり伝えましょう。
⑤ 地域産業保健センターを利用する
厚生労働省が各地域に設置している「地域産業保健センター」では、一定の条件下で無料の支援を受けられる制度があります。
特に、常時50人未満の小規模事業場では、保健指導、面接指導、健康相談などが無料で提供されることもあり、制度を有効活用することでコストを抑えた健康管理が可能です。
近隣のセンター情報は、厚労省の専用ページから簡単に検索できます。
産業医がいない中小企業が受ける痛手とは?
産業医の選任は、単なる“お役所対応”ではありません。制度として形骸化していたり、そもそも未選任だったりすると、企業には深刻なリスクが及びます。
主な「痛手」は以下の3つです。
| リスク内容 | 詳細説明 |
| 法令違反による罰則 | 労働安全衛生法違反として、50万円以下の罰金や是正勧告の対象になります。 |
| 労務トラブル対応の遅れ | メンタル不調・長時間労働・職場環境の問題など、従業員の健康問題が深刻化しやすくなります。 |
| 社会的信用の低下・採用難 | 健康管理体制の不備は、取引先や求職者に「ブラック企業では?」という悪印象を与えることも。 |
特に中小企業は、一人の離職や一件の労災で業務が停滞することも少なくありません。「産業医がいない」という状態は、コスト削減どころか逆に“経営リスク”を高める要因にもなり得るのです。
出典)e-GOV「労働安全衛生法」
参考記事:中小企業もハラスメントの相談窓口設置が義務化!相談対応時のポイント
よくある産業医の失敗事例と回避策
産業医を「とりあえず選任した」という形だけの対応では、実際のトラブル発生時に企業が無防備になってしまうリスクがあります。
ここでは、中小企業が実際に経験しやすい3つの失敗パターンと、それを未然に防ぐための具体策を紹介しましょう。
訪問も面談もしてくれない「名義貸し産業医」だった
「選任届のためだけに名前を貸している」、いわゆる“名義貸し産業医”は中小企業で特に問題になりやすい落とし穴です。
初回の顔合わせだけ済ませて、以降は訪問も面談も一切なし。健康診断の結果も見ていなければ、メンタル対応の相談も拒否される、などの状況には気を付けましょう。
そんな状態でも「契約しているから大丈夫」と思っていると、労働基準監督署からの監査で「実質的に未選任」と判断されることもあります。
さらに問題なのは、実際に従業員に健康問題が起きた際、企業が“安全配慮義務違反”として責任を問われるリスクが高まることです。つまり、名義貸しでは法的にも実務的にも守られないのです。
そのため、以下のような対応を事前に講じることが有効です。
- 契約書に「職場巡視の頻度(例:月1回)」「産業医面談の対応範囲」「健診結果フォローの実施有無」などを明記
- 報告書や面談記録の提出を義務付け、「実態ある活動」が客観的に証明できるようにする
- 産業医と定期的な対面機会(衛生委員会や報告ミーティング)を設ける
こうした仕組みを整えることで、名義貸しを避け、実際に職場の健康管理に貢献してくれる産業医との関係を構築できるようになります。
いざという時に「連絡がつかない」「対応が遅い」
「メンタル不調で面談を依頼したが、産業医と連絡が取れないまま時間だけが過ぎてしまった」などの“連絡不通”の問題は、実際の現場で最も切実なトラブルの一つです。
特に中小企業では、産業医の契約が月1回の訪問のみなど、業務ボリュームが小さいために後回しにされやすい構造的な弱点があります。
その結果、従業員対応が遅れ、症状が悪化してしまう、という事態にもつながりかねません。
以下のようなポイントを事前に取り決めておくことが、トラブル回避の鍵になります。
- 緊急対応の連絡手段(電話・チャット・メール)と、応答時間の目安を契約に明記
- 「訪問時以外の対応も業務に含む」旨を契約文に含める
- 産業医が対応不能な場合の代替手段(代理医師の有無など)も事前に確認
連絡体制の整備は、“いざという時に頼れるかどうか”を決定づける重要な基盤です。単に契約するだけではなく、日頃の連絡性やフットワークの軽さを見極めたうえでの選任が求められます。
産業医との連携がうまくいかず、社内で孤立してしまう
契約後に起こりがちなもう一つの課題が、「産業医が企業の中で浮いてしまう」ケースです。
総務や人事担当者が他の業務に追われ、産業医との情報共有や橋渡しが行われないまま、存在が埋もれてしまうという状況が多く見られます。
産業医も「誰に連絡すればよいか分からない」「衛生委員会に呼ばれていない」となれば、関係が悪化しがちです。せっかく専門的な知見を持っていても、それが企業内で活かされないまま終わってしまいます。
このような事態を防ぐには、次のような工夫が必要です。
- 初回契約時に、企業内の連携窓口(人事・総務など)を明確にし、月1回以上の情報共有を設定
- 衛生委員会や面談など、産業医が他部署と関わる機会を積極的に設ける
- 管理職にも産業医との関係構築の意義を共有し、相談しやすい雰囲気づくりを行う
こうした社内連携の仕組みが整えば、産業医も“単なる外部委託”ではなく、従業員の安心を支える信頼のパートナーとして機能するようになります。
まとめ
産業医の選任は、単なる法令遵守にとどまらず、従業員の健康と企業の持続的な成長を守るための“経営施策”です。特に中小企業では、限られた人材・リソースの中で働く従業員の健康管理が、業績や職場の安定性に直結します。
「まだ大丈夫」と思っていたその油断が、いざというときに大きな代償となるかもしれません。自社の健康管理体制を守る第一歩として、今こそ、信頼できる産業医との連携体制づくりに取り組むタイミングです。
必要に応じて、医師会や紹介サービス、地域産業保健センターなど、頼れる外部リソースを活用しながら、リスクのない職場環境を整えていきましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録