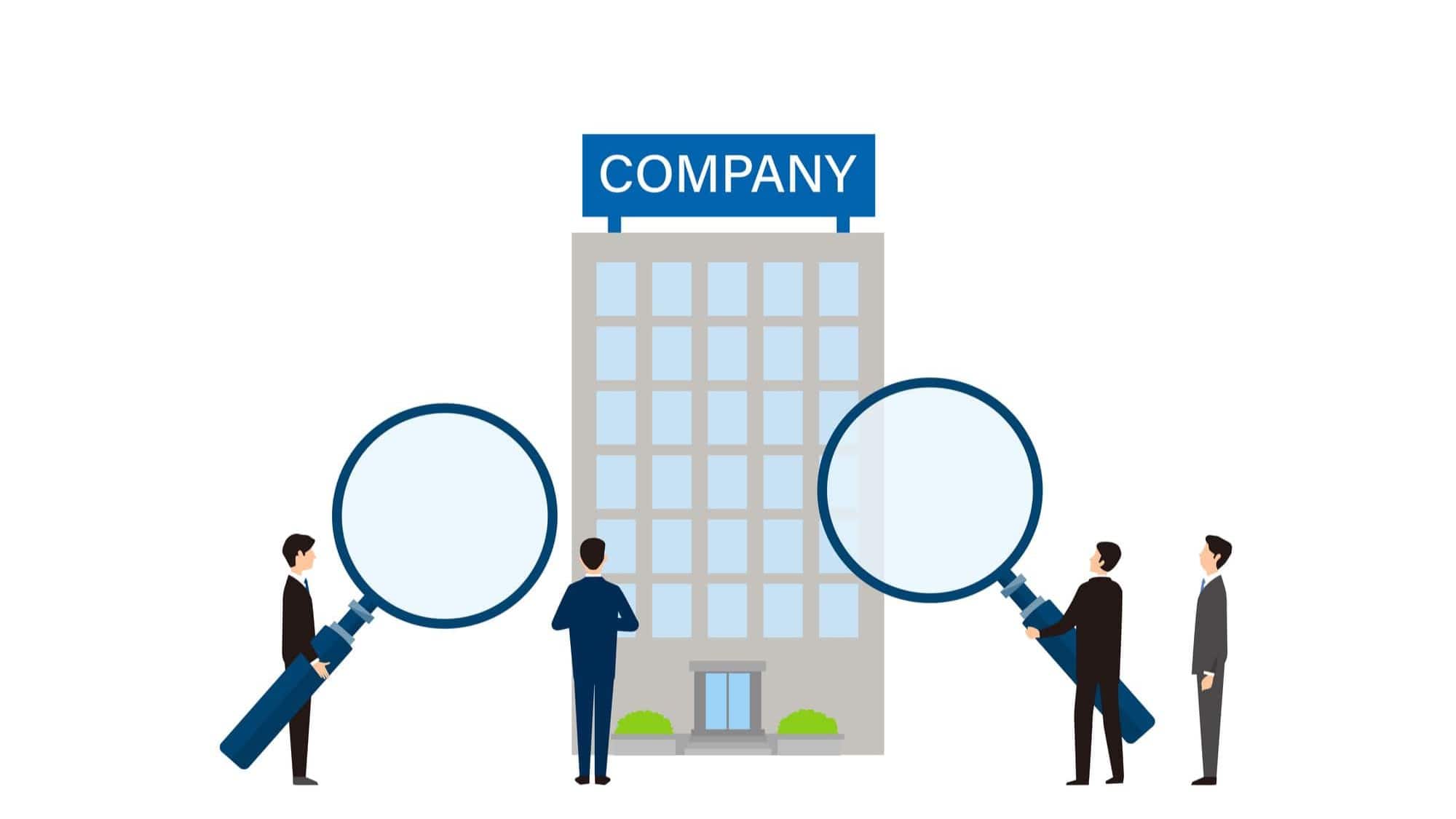KPIとは何かを簡単にわかりやすく解説!KPIが必要な理由も紹介

「KPIとは具体的にどういう意味?」
「目標達成のために重要らしいけど、どう活用すればいい?」
ビジネスの現場で頻繁に耳にする「KPI」という言葉ですが、上記のような疑問を持っている方も多いはずです。
KPIは、単なるビジネス用語ではなく、組織やチームが着実に目標を達成するための強力な羅針盤となる考え方です。
この記事では、KPIとは何かという基本的な定義から、なぜビジネスにKPIが必要なのかという理由、具体的な職種別の設定例まで、わかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
参考記事:KPIとは?具体例・目標設定方法・KGIとの違いを簡単に解説
目次
ビジネスにおけるKPIがどういったものかを簡単にわかりやすく解説
KPIとは、「Key Performance Indicator」の頭文字を取った言葉で、日本語では「重要業績評価指標」と訳されます。
もっと簡単に言うと、KPIとは「最終的な目標を達成するための中間目標」のことです。
たとえば、ある飲食店の最終目標(KGI)が「年間の売上を1億円にする」ことだとします。
しかし、この目標だけでは、日々の業務で何をすればよいのかが具体的にわかりません。
そこで、壮大な最終目標までの過程を分解し、達成までの道のりを示す具体的な指標を設定します。
これがKPIです。
飲食店の場合ならば、売上は「顧客数 × 顧客単価」で成り立っています。
そこで、売上1億円を達成するために、以下のようなKPIを設定することができます。
- KPI①:新規顧客を毎月100人獲得する
- KPI②:リピート率を40%にする
- KPI③:平均顧客単価を3,500円にする
このようにKPIを設定することで、従業員は「今日は新規のお客様を増やすためにチラシを配ろう」「リピートしてもらうために、来店クーポンをお渡ししよう」といった、日々の具体的なアクションを意識できるようになるのです。
毎月これらのKPIの達成度をチェックすれば、最終目標である売上1億円に対して、自分たちが今どの地点にいるのか、計画通りに進んでいるのかを正確に把握できるでしょう。
KPIとKGIには深い関連がある
KPIを理解する上で、切っても切り離せない関係にあるのが「KGI」です。
KGIとは「Key Goal Indicator」の略で、日本語では「重要目標達成指標」と訳されます。
簡単に言えば、前項でも説明したように「最終目標」のことです。
KGIが「組織やプロジェクトが最終的に達成すべき目標」であるのに対し、KPIはそのKGIを達成するための中間指標という位置づけになります。
つまり、「KGIを達成するために、何をすればよいのか」を具体的に示したものがKPIであり、両者は明確な因果関係で結ばれている必要があります。
この関係性をツリーのように分解して考えることを「KPIツリー」と呼びます。
KGIを頂点として、その達成に必要な要素を分解していくことで、日々の具体的な行動まで落とし込むことができるのです。
設定したKPIをすべて達成すれば、自動的にKGIも達成されている、という状態を作ることが理想的なKPIとKGIの関係だと言えます。
KPIを設定すべき理由とは?
KPIを設定することには、単に数字を追う以上の重要な意味があります。
ここでは、ビジネスの成功確率を高めるためにKPIが不可欠な理由を4つの側面から解説します。
定量的なデータに基づいて進捗状況を把握するため
KPIを設定する最大の理由は、目標達成までの進捗状況を、客観的かつ定量的なデータに基づいて正確に把握できるようになるためです。
たとえば、「今月は営業活動を頑張る」という曖昧な目標では、月末になったときに「どれくらい頑張れたのか」「目標達成に近づいているのか」を正しく評価することができません。
「頑張ったつもり」という主観的な感覚に頼ることになり、具体的な改善策も見えてこないはずです。
しかし、「今月は商談のアポを50件獲得する」というKPIを設定すれば、日々の進捗が明確な数値でわかります。
月末を待たずとも、「月の半ばで20件しか達成できていないから、ペースを上げる必要がある」といった判断が可能です。
KPIは、ビジネスにおいて、感覚ではなくデータという信頼できる指標を与えてくれるのです。
目的を明確にして組織内のメンバーで意識を共有するため
組織やチームで大きな目標を目指すとき、メンバー全員が同じ方向を向いて力を合わせることが不可欠です。
KPIは、そのための共通言語として非常に重要な役割を果たします。
もし最終目標(KGI)が「顧客満足度の向上」といった抽象的なものであった場合、メンバーそれぞれの「顧客満足度」の解釈が異なり、別々の行動を取ってしまうかもしれません。
Aさんは電話対応の丁寧さを重視し、Bさんは製品の品質向上に注力する、といった具合です。
そこで、「顧客アンケートの満足度スコア(5段階)を平均4.0以上にする」「問い合わせへの平均返信時間を3時間以内にする」といったKPIを設定します。
これにより、チーム全員が「今、自分たちが最優先で達成すべきことは何か」を具体的に理解し、意識を統一できるようになります。
進捗の遅れによる課題を早期に発見するため
ビジネスは、計画通りに物事が進まないことの方がむしろ多いと言えます。
KPIは、そうした計画からのズレや、目標達成を阻む潜在的な課題を早期に発見するための警告システムとして機能します。
たとえば、「新規顧客からの問い合わせ数を月100件にする」というKPIを立て、毎週進捗を確認する体制を整えておくとします。
月の第1週が終わった時点で問い合わせが10件しかなかった場合、これは明らかに計画が遅れているという危険信号です。
この時点で、「なぜ問い合わせが少ないのか? Web広告の費用が足りないのか? それともWebサイトの導線に問題があるのか?」といった原因分析に素早く着手できます。
このように、月末になってから「目標未達でした」と気づくのに比べ、はるかに早い段階で軌道修正が可能となります。
PDCAサイクルを回しやすくするため
PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)は、業務改善を継続的に行うための基本的なフレームワークです。
KPIは、このPDCAサイクルを効果的に回す上で、中心的な役割を担います。
- Plan(計画):KGIを達成するためのKPIを設定し、具体的なアクションプランを立てます。
- Do(実行):計画に沿ってアクションを実行します。
- Check(評価):設定したKPIの達成度を、期間の終わりや中間地点で測定・評価します。
- Action(改善):KPIが達成できた要因、あるいは未達だった原因を分析し、次の計画(Plan)に活かす改善策を考えます。
このように、KPIという具体的な測定指標があることで、「Check(評価)」の精度が格段に向上します。
評価が客観的かつ明確になるからこそ、次の「Action(改善)」の質も高まり、より良い「Plan(計画)」が立てられるようになるのです。
KPIを活かした目標設定の例
KPIは理論だけでなく、実際の業務に落とし込んでこそ真価を発揮します。
ここでは、代表的な3つの職種(マーケティング、営業、人事)を例に、主に中小企業を対象とした具体的なKPI設定の考え方を見ていきましょう。
マーケティングの場合
マーケティング部門の最終的な目標(KGI)は、「売上目標の達成」や「見込み客(リード)の獲得による売上への貢献」などに設定されることが多いです。
「売上目標の達成」がKGIの場合は、以下のようなKPIが考えられます。
| 最終目標(KGI) | Webサイト経由の月間売上1,000万円 |
| KPIの例 | ■Webサイトの月間ユニークユーザー数:20万人 ■コンバージョン率(購入率):1% ■メールマガジン登録者数:月間500人増 ■広告のクリック単価(CPC):100円以下 ■資料請求数:月間200件 |
Webサイトの売上は「アクセス数 × 購入率 × 顧客単価」で計算されるため、それぞれの要素をKPIとして設定します。
また、すぐには購入に至らない顧客を将来の見込み客として育てるための、メールマガジン登録者数や資料請求数なども重要な中間指標となるでしょう。
営業の場合
営業部門のKGIは、多くの場合「売上目標」や「契約件数」といった、非常に明確な数値になります。
営業活動はプロセスが比較的はっきりしているため、各段階の行動量をKPIとして設定しやすいのが特徴です。
| 最終目標(KGI) | 四半期の売上目標5,000万円 |
| KPIの例 | ■新規アポイントメント獲得数:月間40件 ■商談化率:50% ■受注率(成約率):25% ■平均受注単価:250万円 |
売上目標から逆算し、目標達成に必要な受注率や商談化率、新規アポイントメント件数を算出していきます。
各KPIの進捗を追うことで、営業チームのどこに問題があるのかを特定しやすくなります。
人事の場合
人事部門のKGIは、「優秀な人材の確保」や「従業員エンゲージメントの向上による離職率の低下」などが挙げられます。
営業などと比べて直接的な売上には結びつきにくいですが、組織の基盤を支える重要な役割を担っており、活動を数値で可視化することが可能です。
| 最終目標(KGI) | 年間離職率を5%未満に抑制する |
| KPIの例 | ■従業員満足度調査のスコア:平均80点以上 ■月間平均残業時間:20時間未満 ■有給休暇取得率:70%以上 ■1on1ミーティングの実施回数 |
離職率という最終目標には、労働環境、人間関係、キャリアパスなど様々な要因が影響します。
そのため、従業員の働きがいや満足度を測るための指標をKPIとして設定することが有効です。
これらの数値を定期的に観測することで、組織の状態を健康診断のようにチェックし、問題が大きくなる前に対策を講じることができます。
中小企業もKPIを設定すべき?
「KPI管理は、リソースが豊富な大企業がやるものではないか」
「日々の業務に追われる中小企業に、そんな余裕はない」
このように感じる経営者の方もいるかもしれません。
しかし、実際はその逆です。
限られた人材や資金、時間といったリソースを最大限に有効活用しなければならない中小企業にこそ、KPIの設定は不可欠と言えます。
大企業であれば、多少の無駄な施策があっても経済的な体力でカバーできるかもしれません。
逆に中小企業は、一つの施策の失敗が経営に与える影響が非常に大きいです。
だからこそ、どの活動にリソースを集中させるべきかを、データに基づいて判断する必要があるのです。
KPIは、そのための的確な判断基準を与えてくれます。
特に中小企業は、業務が属人化しやすかったり、経営者の勘や経験に依存した経営になったりすることも少なくないため、定量的なデータに沿って、限られた経営資源を有効活用して業務効率の改善を図るべきです。
とはいえ、いきなり全部門で複雑なKPIツリーを構築する必要はありません。
まずは、会社全体で最も重要なKGIを一つだけ設定し、それを達成するための2〜3個のKPIを設定することから始めてみてください。
たとえば、「今期の売上を20%伸ばす」というKGIに対し、「新規顧客からの問い合わせ件数を月10件増やす」「既存顧客のリピート率を60%にする」という2つのKPIに全社で集中する、といったような形です。
目標がシンプルで明確になることで、少ないリソースでも大きな力を発揮しやすくなります。
参考記事:予実管理の目的を理解して経営を効率化!成功事例から学ぶ中小企業の戦略
まとめ
以上、KPIとはどういったものなのかについてや、KPIを設定すべき理由、具体的な設定例などについて詳しく解説してきました。
KPIは、決して難しい専門用語や、従業員を管理するための堅苦しいツールではありません。
組織やチームが目指す大きなゴール(KGI)に向かって、今自分たちがどこにいて、次に何をすべきかを教えてくれる、非常に便利な指標です。
もし、まだ自社でKPIを設定していないようならば、ぜひこの機会に導入を検討してみてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録